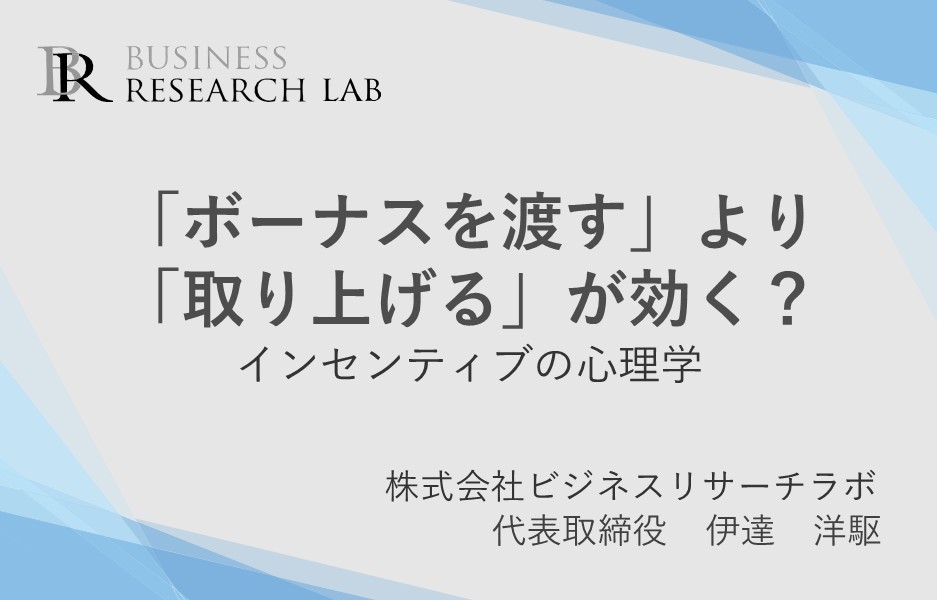2025年11月17日
「ボーナスを渡す」より「取り上げる」が効く?:インセンティブの心理学
従業員のやる気を引き出し、組織全体の活力を高めることは、いつの時代も経営における中心的な課題の一つです。多くの企業では、この課題に応えるため、金銭的な報酬、いわゆるインセンティブ制度を導入しています。目標を達成した者にはボーナスを、高い成果を上げたチームには報奨金を。こうした仕組みは、従業員の努力を促すための分かりやすい仕掛けとして受け入れられています。
しかし、もしそのインセンティブの「渡し方」一つで、人の心の動きや行動が変わるとしたら、どうでしょうか。同じ金額のボーナスであっても、それが「これから得られるもの」として提示されるのと、「一度手にしたものを失うかもしれないもの」として提示されるのとでは、受け取る側の心理的な反応は異なります。人の心は複雑です。
本コラムでは、社会科学の分野で蓄積されてきたいくつかの知見を紐解きながら、インセンティブが人の行動に変化をもたらすメカニズムに迫ります。扱うのは、金銭的な報酬の「見せ方」がもたらす変化だけではありません。お金を介さない「称賛」や「感謝」といった働きかけが持つ力、個人の価値観や考え方に働きかける「研修」という学びの機会が、従業員の行動をどのように変えうるのかについても掘り下げていきます。
罰則を示すだけでチーム生産性が持続的に向上した
金銭的なインセンティブの「見せ方」がもたらす変化から見ていきましょう。同じ金額のボーナスでも、「目標を達成すればもらえる」と伝えるのと、「目標未達だと没収される」と伝えるのとでは、従業員の受け止め方は異なります。この心理的な仕組みが、実際の仕事の成果にどう結びつくのかを探った、ある工場での調査があります[1]。
調査の舞台となったのは、中国にある大手家電メーカーの生産工場です。そこでは日々、DVDプレーヤーの基板を組み立てるなど、手先の器用さが求められる作業が、多くの従業員によって行われていました。調査の対象となったのは、そこで働く165名の従業員です。作業形態は、数名で協力して一つの製品を完成させるチーム作業と、一人で黙々と基板の検査などを行う個人作業の二つに分かれていました。
調査は、約半年間にわたって実施されました。研究チームは、従業員をいくつかのグループに分け、それぞれ異なる条件の下で働いてもらい、その生産性の変化を記録しました。
一つ目のグループには、「週の生産目標を達成すれば、週末にボーナスを支給します」と伝えられました。これは「報酬」としてインセンティブを提示する形です。二つ目のグループには、「週の初めに、あらかじめボーナスを仮払いします。ただし、週の目標を達成できなければ、これを差し引きます」と伝えられました。支給される可能性のある金額は同じですが、こちらは「罰則」の形をとっています。そして、比較のために、特別なインセンティブを設けない、通常通りの勤務条件のグループも置かれました。研究チームは、それぞれのグループの時間あたりの生産量や、製造した製品の不良率などを測定し、条件による違いを分析しました。
その結果、インセンティブ制度を導入されたグループは、何もないグループに比べて、生産性が向上することが分かりました。従業員の意欲を高める上で、金銭的な働きかけがある程度の効果を持つことが改めて確認された形です。
しかし、注目すべきは、二つの伝え方の間に見られた違いでした。チームで作業するグループにおいては、「罰則」として伝えられた方が、「報酬」として伝えられた方よりも、生産性が平均して高かったのです。一方で、一人で作業するグループでは、この二つの伝え方による生産性の差は、はっきりとは現れませんでした。また、生産性を上げるために作業を急いだ結果、製品の質が低下するのではないかという懸念もありましたが、どのグループにおいても不良率に目立った変化は見られませんでした。
なぜ「罰則」の伝え方の方が、チームの生産性を高めたのでしょうか。この背景には、「損失回避」と呼ばれる人の心の働きが関係していると考えられます。人は一般的に、何かを得る喜びよりも、それと同じ価値のものを失う痛みの方を、より強く、そして敏感に感じるという性質を持っています。週の初めに「あなたのもの」として仮に渡されたボーナスは、心理的にはすでに自分の所有物として認識されます。それを失うかもしれない、という状況は、「これからボーナスもらえるかもしれない」という期待感よりも、強い行動への動機づけになったと解釈できるのです。
この仕組みが、個人作業よりもチーム作業において機能した理由も考察されています。チームでは、一人の失敗がチーム全体の損失、つまり全員のボーナス没収に直結します。自分の行動が仲間に直接的な不利益をもたらすかもしれないという意識は、一人ひとりの責任感を強めます。その結果、互いに作業の遅れがないか気を配ったり、困っているメンバーを助けたりといった、協力的な行動が自然と促された可能性があります。
上位限定の称賛が他の人の努力を高める
先ほどは、金銭的な報酬であっても、その提示方法一つで生産性に変化が生じることを見ました。人を動かす要因は、お金だけに限られません。ここでは視点を変え、金銭を伴わない「認められること」の価値を探ります。上司からの感謝の言葉や、ささやかな表彰。こうした働きかけは、従業員の心に火をつけ、仕事への取り組み方を変えるのでしょうか。とりわけ、その称賛が「全員」に向けられたものか、それとも「一部の優れた人」だけに向けられたものかで、周囲の反応は変わるのかを検証した実験があります[2]。
実験の舞台は、ある大学の施設です。大学生を中心とした363名が参加者として集められました。参加者に課されたのは、3時間にわたって、アンケート用紙に書かれた内容をひたすらパソコンに入力していくという単純な作業です。報酬は、作業量にかかわらず一律で25ユーロが支払われることになっていました。参加者は8人ずつ同じ部屋に通され、それぞれが個別のパソコンに向かって作業します。誰がどれだけの量を入力したかは、サーバーの記録によって正確に把握できる仕組みです。
実験の仕掛けは、作業開始から2時間が経過した時点で、予告なく行われました。研究チームは、部屋ごとに異なる介入を実施しました。ある部屋では、何も行いませんでした。これが比較の基準となるグループです。別の部屋では、作業をしていた8名全員に、研究所の所長が手書きで署名した感謝のカードを「突然」手渡しました。さらに別の部屋では、その時点での作業量が多かった上位3名にだけ、同じカードを渡しました。最後の部屋では、作業量が最も多かった、たった1名にだけカードを渡したのです。研究チームの関心は、このカードが配られた後の約1時間で、参加者たちの入力速度がどのように変化するかにありました。
結果、全員にカードを渡したグループでは、入力速度が平均で5.2%上昇しました。感謝の言葉が、たしかに参加者の意欲を高めたことがうかがえます。上位3名にカードを渡したグループでは、入力速度は平均で7.3%の上昇を見せました。興味深いのは、このパフォーマンス向上の大部分が、カードを受け取らなかった下位5名の努力によってもたらされていた点です。カードをもらえなかった人たちの入力速度は、約10%も上がっていました。
最後に、トップ1名だけにカードを渡したグループでも、全体の入力速度は平均5.6%上昇しました。この場合も、カードをもらえなかった7名の貢献が大きく、その入力速度は6.6%上昇していました。一方で、カードを受け取った本人の作業ペースには、ほとんど変化が見られませんでした。
なぜ、称賛されなかった人々が、かえって努力を高めるという現象が起きたのでしょうか。この結果は、「同調性」という人の社会的な心理によって説明することができます。人は集団の中で生活する上で、自分だけが劣っていたり、集団の基準から大きく外れていたりすることを避けたいと感じるものです。上位者だけが公に称賛されるという状況は、「カードをもらえなかった自分は、このグループの中でパフォーマンスが低い存在だ」という信号として機能します。この信号を受け取った人々は、集団の標準的なパフォーマンスレベルに追いつこうと、無意識のうちに作業ペースを上げたと考えられます。
その一方で、カードを受け取った人たちの成績が落ちなかったことや、全員が称賛された場合でも成績が向上した事実は、「互恵性」という観点から解釈できます。互恵性とは、誰かから親切や贈り物を受けたら、何らかの形でお返しをしたいと感じる人間本来の心理です。予期せぬ感謝のカードという「贈り物」に対して、少しでも報いようと、作業を頑張る気持ちが生まれたのでしょう。
研修は態度改善も行動変化は支持層のみ
これまでのところでは、報酬の提示方法や称賛の仕方といった、比較的短期的な外部からの働きかけが、従業員の生産性や努力に結びつく過程を見てきました。しかし、企業が従業員に働きかける方法はそれだけではありません。近年、多くの組織が、多様性を尊重し、職場における無意識の偏見をなくすための研修を導入しています。
こうした研修は、従業員の「意識」を変えるだけでなく、実際の「行動」にまで変化をもたらすことができるのでしょうか。その効き目は、すべての人に等しく現れるものなのでしょうか。この問いに答えるため、あるグローバル企業を舞台に行われた調査があります[3]。
この調査は、世界中に拠点を持つ企業で、63か国に在籍する従業員の中から、募集に自発的に応募した3,016名を対象に行われました。参加者はランダムに3つのグループに分けられ、それぞれ内容の異なるオンライン研修を1時間程度受講しました。
一つ目のグループが受けたのは、「性別バイアス研修」です。職場における性別に関する固定観念や、それがキャリアや評価にどう作用するかといったテーマに特化した内容でした。二つ目のグループが受けたのは、「一般バイアス研修」で、性別に加えて、人種や年齢、性的指向など、より幅広いテーマにおける偏見を扱いました。三つ目のグループは、比較のための対照群として、心理的安全性や傾聴といった、直接的な関連の薄いテーマの研修を受けました。
研究チームは、研修の効果を二つの側面から測定しました。一つは、研修直後の「態度」の変化です。女性の活躍を支援する気持ちや、自分自身が持つ偏見に対する自覚の度合いが、研修の前後でどう変わったかをアンケートで尋ねました。もう一つは、研修後、最大で20週間にわたる実際の「行動」の変化です。具体的には、社内のメンタリング制度で後輩の指導役を選ぶ際に女性を指名する数や、優れた功績を上げた同僚を表彰するプログラムに女性を推薦する数などを、客観的なデータとして追跡しました。
分析の結果、態度の変化については、研修を受けたグループは、受けていないグループに比べて、全体として女性を支援する態度が強まり、自らの偏見を自覚する度合いも高まることが分かりました。態度の変化は、もともと女性支援への意識がそれほど高くなかったアメリカ以外の国の従業員において、より顕著に見られました。改善の余地が大きい人ほど、研修による意識の変化が大きかったことを表しています。
しかし、実際の行動の変化は、より限定的でした。メンタリングで女性を指名したり、表彰に推薦したりといった行動は、研修を受けたグループ全体で見ると、大きな変化は見られませんでした。ところが、データを詳しく分析すると、特定の層に限って行動の変化が起きていることが分かりました。それは、研修を受ける前から、もともと女性支援に肯定的な態度を持っていた従業員たちです。例えば、アメリカ在住の女性従業員などに限ってみると、研修後に女性をメンターとして指名したり、推薦したりする行動が、わずかながらも統計的に意味のある形で増えていました。
この結果から、人の変化に関する一つのモデルが見えてきます。研修のような教育的な介入は、まず知識を提供し、意識を喚起することを通じて「態度」を変えます。しかし、その変化が実際の「行動」に結びつくまでには、もう一段階の壁が存在するようです。もともと意識が高く、行動に移す準備が整っていた人々にとって、研修は背中を押す最後の一押しとして機能しました。
一方で、研修によって初めて意識が変わった人々にとっては、その変化が行動として定着するには、まだ時間や、職場環境からの後押しといった別のきっかけが必要だったのかもしれません。研修の効果は一様ではなく、受講者の元々の態度水準によって、「意識変革」の段階で留まるか、「行動変革」の段階まで進むかが分かれる、という二段階のプロセスが考えられるのです。
脚注
[1] Hossain, T., and List, J. A. (2009). The behavioralist visits the factory: Increasing productivity using simple framing manipulations (NBER Working Paper No. 15623). National Bureau of Economic Research.
[2] Bradler, C., Dur, R., Neckermann, S., and Non, A. (2016). Employee recognition and performance: A field experiment. Management Science, 62(11), 3085-3099.
[3] Chang, E. H., Milkman, K. L., Gromet, D. M., Ruttan, R. W., Massey, C., Duckworth, A. L., and Grant, A. M. (2019). The mixed effects of online diversity training. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(16), 7778-7783.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。