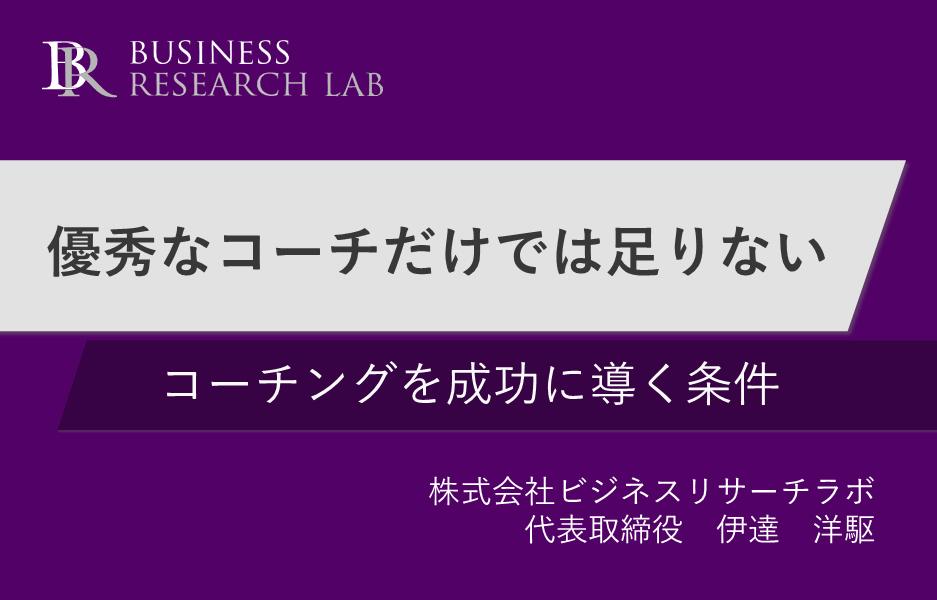2025年11月17日
優秀なコーチだけでは足りない:コーチングを成功に導く条件
人材開発の手法としてコーチングが普及しています。管理職の能力向上からリーダーシップ開発まで、その活用範囲は多岐にわたります。しかし、同じようにコーチングを導入しても、期待した成果が得られる場合もあれば、そうでない場合もあります。この違いは一体どこから生まれるのでしょうか。
コーチングの成否を分ける要因について多くの研究が蓄積されてきました。これらの研究から浮かび上がってくるのは、コーチングの成功は特定のテクニックや手法だけでは決まらないという事実です。むしろ、コーチとクライアントの相性、両者の関係性の質、そしてクライアント自身が持つ特性といった、複数の要因が複雑に絡み合って成果を生み出していることが明らかになっています。
本コラムでは、コーチング成功の鍵となる五つの要因を取り上げます。それぞれの要因について、実証研究の結果を紹介しながら、コーチングが機能するメカニズムを解き明かしていきます。これらの知見は、コーチングを導入する組織にとって、投資対効果を最大化するための指針となるでしょう。
良いマッチングを土台とした関係性
コーチングの設計において、最初に直面する課題のひとつが「誰と誰を組み合わせるか」という問題です。この問いに取り組んだ研究があります。米国の士官学校で実施されたリーダーシップ開発プログラムを対象とした調査では、74組のコーチとクライアントのペアを追跡し、マッチングの基準とコーチングの成果との関係を分析しました[1]。
この研究では、コーチングのプロセスを「インプット–プロセス–アウトプット」という三段階のモデルで捉えています。
インプットの段階では、コーチとクライアントをマッチングする際の三つの基準が検討されました。第一の基準は「共通性」です。これは、性別、人種、学歴、職歴、趣味といった個人的・職業的な特徴がどれだけ似ているかを表します。第二の基準は「適合性」で、性格、行動特性、マネジメントスタイル、学習スタイルなどの行動的な好みが組み合わせやすいかどうかを意味します。第三の基準は「信頼性」で、クライアントが抱える課題に対して、コーチが必要な能力や経験、専門知識を持っているかという点です。
研究では、これらの基準に基づいて系統的にマッチングされたグループと、ランダムに組み合わせられたグループを比較しました。プロセスの段階では、両者の関係性の質を三つの要素で測定しています。「ラポール」は相互の理解と親近感、「信頼」は互いに対する信用と安心感、「コミットメント」は両者がコーチングに真摯に取り組む姿勢を指します。アウトプットの段階では、コーチング経験への満足度、リーダーシップ行動の改善、プログラム全体への評価が測定されました。
結果、系統的にマッチングされたペアとランダムに組まれたペアの間で、最終的な成果に統計的に有意な差は見られませんでした。しかし、関係性の質は成果を強く予測することが分かりました。良好なラポール、信頼、コミットメントが築かれているペアほど、高い成果を得ていたのです。
関係性は「媒介」の機能を果たしていました。「適合性」と「信頼性」というマッチング基準は、直接的に成果を生むのではなく、両者の関係性の質を高め、その高まった関係性を通じて成果に結びついていました。これは、良いマッチングが「良い関係を築くための土台」として機能することを表しています。
この研究から読み取れるメカニズムは次のようなものです。行動スタイルや学習スタイルの相性(適合性)が良いペアは、お互いを理解しやすく、コミュニケーションが円滑になります。コーチがクライアントの課題に対して十分な専門性を持っている場合(信頼性)、クライアントはコーチに対して信頼を寄せやすくなります。これらの初期条件が整うことで、ラポール、信頼、コミットメントが育まれやすい環境が生まれ、結果として高い成果につながっていくのです。
コーチの指導と受け手の信念の相性
コーチングの成果は、コーチとクライアントの心理的な特性がいかに組み合わさるかによっても左右されます。この点を探求した研究では、コーチの指導スタイルとクライアントの能力に対する信念の相互作用に焦点を当てました[2]。
研究では、コーチの指導スタイルを「調整焦点理論」という心理学の枠組みで分析しています。この理論では、人の動機づけを二つのタイプに分類します。「促進焦点」は、成功や成長、達成を追求するスタイルで、「どうすればもっと良くなるか」という視点で行動します。「予防焦点」は、失敗の回避、義務の遂行、安全の確保を重視するスタイルで、「どうすれば間違いをおかさないか」という慎重な視点を持ちます。コーチの指導も、この二つの焦点のどちらかに偏ることがあります。
一方、クライアントの特性は「潜在能力観」という概念で捉えられています。これは、能力についてどのような信念を持っているかを示すものです。「実体論」は、能力は生まれつきのもので固定的だと考える信念で、「増大論」は、能力は努力や学習によって伸ばすことができると考える信念です。
この研究は二つの段階で実施されました。第一段階は実験室実験で、大学生118名を対象に統制された環境下で検証しました。参加者には事前に「知能は固定的である」または「知能は発達する」という内容の記事を読ませ、一時的に実体論的または増大論的な信念を植え付けました。その後、コーチ役が問題解決ツールの使い方を教える際に、促進焦点(「どうすればもっと良くなるか」)または予防焦点(「どうすれば間違いを犯さないか」)という異なる視点で指導しました。成果は、参加者が作成した問題解決ツールの質で測定されました。
第二段階は、グローバル企業の生産工場で働く従業員249名を対象としたフィールド調査でした。従業員の能力に対する信念を質問紙で測定し、9ヶ月後に直属の上司の日常的な指導スタイルを評価してもらいました。成果は従業員の自己評価によるパフォーマンスで測定されました。
その結果、全体として、予防焦点の指導よりも促進焦点の指導の方が高いパフォーマンスにつながる傾向がありました。しかし、重要な発見は、コーチの指導スタイルとクライアントの能力観の「適合」が成果を左右することでした。
能力は固定的だと考える実体論者は、予防焦点のコーチ(失敗しないよう慎重に指導する)の下で、増大論者よりも高いパフォーマンスを示しました。これは、「間違いを避けたい」という動機とコーチの指導スタイルが適合したためと考えられます。一方、能力は努力で伸びると考える増大論者は、促進焦点のコーチ(成長を促す指導)の下で高いパフォーマンスを発揮しました。「もっと良くなりたい」という動機とコーチのスタイルが適合した結果です。
顕著だったのは、増大論者が予防焦点のコーチングを受けた場合のパフォーマンス低下でした。成長意欲を持つクライアントに対して慎重すぎる指導を行うと、動機づけが阻害され、期待とは逆の結果を招く可能性があることが示されました。
この研究のメカニズムは、「調整適合」という概念で説明できます。人は自分の動機的傾向と一致する状況や環境に置かれたときに、より高いパフォーマンスを発揮するという心理学的原理です。実体論者は失敗への不安を感じやすく、具体的な手順や基準を明確に示してくれる予防焦点の指導に安心感を覚えます。増大論者は挑戦への意欲が高く、改善点や成長の可能性に焦点を当てる促進焦点の指導にやりがいを感じるのです。
クライアント視点の良い協働関係
コーチングの成果に関連する要因として、「共通因子」という考え方が注目を集めています。これは心理療法の分野で発展した概念で、特定の技法やモデルを超えて、すべての有効な介入に共通して存在する要素のことを指します。この共通因子をコーチングに応用した研究では、156組のエグゼクティブコーチとクライアントのペアを対象に、どのような要素が成果を予測するのかを包括的に検証しました[3]。
研究では四つの共通因子が検討されました。中心的な因子は「ワーキングアライアンス」です。これはコーチとクライアントの協働関係の質を表し、目標の共有、タスクへの合意、そして感情的な絆という三つの側面で構成されます。第二の因子は「クライアントの自己効力感」で、目標達成に必要な行動をうまく遂行できるという自信を意味します。第三の因子は「パーソナリティのマッチング」で、性格検査を用いてコーチとクライアントの性格特性の類似性や相違性を測定しました。第四の因子は「コーチのテクニックの多様性」で、クライアントがコーチから多様なアプローチや介入を受けたと認識している度合いです。
成果は、クライアントが評価した「コーチング経験全体への満足度」「付加価値の認識」「仕事のパフォーマンスへの影響」「目標達成への貢献」の四項目で測定されました。これらのデータを分析することで、各共通因子と成果との関係性、そして因子間の相互作用が明らかになりました。
最も強力な予測因子は、クライアントが評価したワーキングアライアンスでした。コーチとの協働関係が良好だと感じているクライアントほど、コーチングの成果も高く評価していました。この関係性は強く、他のどの因子よりも成果を予測していました。
コーチ自身による関係性の評価は、クライアントが認識する成果とはほとんど関連がありませんでした。コーチングの成果を決めるのは、コーチ側の主観的な評価ではなく、クライアント側の体験であることを表しています。
クライアントの自己効力感とコーチのテクニックの多様性も、成果と有意な正の関係を示しました。元々自信を持っているクライアントや、コーチが多様な関わり方をしてくれると感じているクライアントほど、高い成果を得ていました。
一方で、パーソナリティのマッチングは成果に有意な影響を与えませんでした。性格の類似性や相違性は、コーチングの効果を左右する要因ではないことが分かりました。
重要なことに、ワーキングアライアンスは他の因子を「媒介」する効果を持っていました。自己効力感が成果に与える影響は、ワーキングアライアンスによって完全に媒介されていました。自信のあるクライアントがコーチと良好な関係を築きやすく、その結果として高い成果を得るというプロセスを意味します。テクニックの多様性の効果も、ワーキングアライアンスによって部分的に媒介されていました。
コーチングにおいて、クライアントがコーチとの関係を「目標を共有し、適切なタスクに取り組み、信頼に基づいた絆を持つ協働関係」として体験できるかどうかが、成果を決める条件です。自己効力感の高いクライアントは、このような関係を築きやすく、多様なテクニックを用いるコーチも、クライアントがそれを関係性の充実として受け取れるときに効果を発揮します。
協働関係は、どんな状況でも重要
先ほど紹介したワーキングアライアンス(協働関係)の重要性について、さらに確固たる証拠を提供したのが、23本の論文を統合したメタ分析です。この研究では、3,563のコーチング事例を分析し、ワーキングアライアンスとクライアントの成果との関係性を包括的に検証しました[4]。
メタ分析という手法は、複数の研究結果を統計的に統合することで、個々の研究の限界を超えた、より一般化可能で信頼性の高い結論を導き出すためのアプローチです。本研究では、コーチングの成果を三つのカテゴリーに分類して分析しました。「情意的成果」は満足度、自己効力感、モチベーションなど感情や態度に関する変化、「認知的成果」は自己内省や気づきなど知識や思考に関する変化、「結果の成果」は目標達成など具体的な行動の結果として現れる変化を指します。
分析の結果、ワーキングアライアンスとコーチングの成果には、統計的に有意で中程度の強さを持つ正の関係があることが確認されました。この関係は、コーチとクライアントの協働関係が良好であるほど、コーチングが成功しやすいことを示しています。
成果の種類別に見ると、ワーキングアライアンスは特に「情意的成果」と「認知的成果」と強い関係がありました。良好な関係性が、クライアントの満足感や自信、そして自分自身への気づきといった内面的な変化を促す上で中心的な機能を果たしていることを意味します。「結果の成果」(目標達成)とも中程度の正の関係が見られました。
さらに、ワーキングアライアンスは「意図せざるネガティブな影響」と負の関係を示しました。良好な関係性は、コーチングがクライアントに害をもたらすリスクを軽減する「安全網」としても機能します。質の高い協働関係は、成果を高めるだけでなく、副作用を防ぐ機能も持っているのです。
この研究では、ワーキングアライアンスの重要性が、様々な条件下で一貫して確認されました。クライアントの種類(学生から企業幹部まで)、コーチの専門性(経験豊富なプロから初心者まで)、コーチングのセッション回数といった要因による差は見られませんでした。ワーキングアライアンスの意義が、特定の状況に限定されないものであることを意味しています。
このメカニズムは、コーチングという営みの構造に関わっています。コーチングは対人関係を基盤とした営みです。クライアントは、コーチとの関係の中で自己開示し、新たな視点を獲得し、行動変容への意欲を高めていきます。このプロセスが機能するためには、基本的な信頼関係と協働の枠組みが不可欠です。
情意的成果との強い関係は、クライアントがコーチングに対して肯定的な感情を持ち、自信を深めるためには、コーチとの関係が安全で支持的であることが前提となることを表しています。認知的成果との関係は、自身への洞察や新たな気づきが、対話的な関係の中で生まれることを反映しています。結果の成果についても、目標達成という変化は、コーチとクライアントが共同で取り組む過程で実現されるものです。
ネガティブな影響の軽減については、良好な関係性がクライアントの心理的安全性を保障し、過度なプレッシャーや不適切な介入から守る機能を果たしていると考えられます。コーチングには、クライアントの価値観や行動パターンに挑戦する側面もありますが、それが機能するためには、信頼と尊敬の土台が必要です。
受ける側の学習意欲と動機の組み合わせ
これまでのところでは、主にコーチとクライアントの関係性に焦点を当ててきましたが、コーチングの成果はクライアント自身が持つ個人的な特性にも左右されます。この点を探求した研究では、イスラエルの企業で働く管理職を対象に、クライアント側の特性がコーチングの効果をどのように予測するかを検証しました[5]。
研究では、エグゼクティブコーチングプログラムに参加する72名の管理職と、同じ組織に所属するがコーチングを受けない29名の同僚を比較する準実験計画法が用いられました。プログラムの開始前と終了後にデータを収集し、クライアントの特性と成果との関係を分析しています。
検討された特性は四つあります。「学習目標志向」は、能力を向上させ、新しいことを学ぶこと自体を目標とする傾向です。「研修前の動機づけ」は、コーチングプログラムに参加する前の段階での学習に対する意欲を表します。「フィードバック受容性」は、他者からのフィードバックを個人の成長機会として前向きに受け入れる姿勢を意味します。「発達的自己効力感」は、自分は学習し、成長できるという能力に対する自信です。
成果は、自己認識の向上、キャリア満足度、職務への情緒的コミットメント、自己報告による職務パフォーマンスなど、多面的に測定されました。これらのデータを用いて、各特性が単独で、あるいは相互に作用しながら成果にどのような影響を与えるかが分析されました。
結果は、クライアントの特性の複雑な相互作用がコーチングの成果を決定することを明らかにしました。興味深いのは、「学習目標志向」と「研修前の動機づけ」の間に見られた交互作用です。
事前の動機が高い場合、学習目標志向が高い人ほど、職務パフォーマンスの向上が大きくなりました。学ぶこと自体を楽しみ、もともと高いモチベーションを持っている人は、コーチングから最大限の利益を得ることができました。このタイプの人は、コーチングを通じて新たな知識やスキルを獲得することに積極的で、それを実際の仕事に応用する意欲も高いことが推測されます。
しかし、事前の動機が低い場合、予想に反して学習目標志向が高い人ほどパフォーマンスの向上度が低くなるという負の関係が見られました。これは、学ぶ意欲はあってもプログラムへのモチベーションが低いと、期待とのギャップからかえって成果が出にくくなる可能性を示唆しています。おそらく、学習への関心は高いものの、特定のプログラムに対して懐疑的な態度を持っている人は、コーチングの内容と自分の学習ニーズとの間に不一致を感じ、積極的に取り組めないのかもしれません。
「フィードバック受容性」についても交互作用が確認されました。フィードバックを前向きに受け入れる姿勢が高い人ほど、職務への情緒的コミットメントが向上することが分かりました。他者からの指摘を成長の糧として受け止められる人は、コーチングを通じて組織への愛着も深める傾向があります。
「発達的自己効力感」は、より直接的な影響を見せました。自分は成長できると信じている人ほど、コーチング後に職務パフォーマンスの向上が見られました。自信が実際の行動変容と成果に直結することが確認されたのです。
これらの結果から浮かび上がるのは、コーチングが機能するための個人的な「レディネス(準備状態)」の重要性です。学習目標志向と事前動機の相互作用が示すように、学ぶ意欲だけでは不十分で、特定のプログラムに対する動機も併せ持つことが必要です。両方が高いレベルでそろったとき、相乗効果が生まれ、高い成果につながります。
フィードバック受容性の効果は、コーチングが他者からの観察とフィードバックに依存した営みであることを反映しています。自分の行動や思考パターンについて客観的な視点を受け入れられる人は、コーチングプロセスをより建設的に活用できるのです。
発達的自己効力感の直接効果は、変化への取り組みにおける自信の重要性を意味しています。「自分は変われる」という基本的な信念がなければ、いくら良いコーチングを受けても、それを行動に移すことは困難です。
この研究は、コーチングの成功が、良いプログラムや優秀なコーチを提供するだけでは保証されないことを示しています。クライアント自身が持つ特性、なぜそれぞれの人がコーチングから利益を得やすいのか、といった「コーチング適性」の理解が、効果的な人材開発にとって大事であることが実証されました。
脚注
[1] Boyce, L. A., Jackson, R. J., and Neal, L. J. (2010). Building successful leadership coaching relationships: Examining impact of matching criteria in a leadership coaching program. Journal of Management Development, 29(10), 914-931.
[2] Sue-Chan, C., Wood, R. E., and Latham, G. P. (2012). Effect of a coach’s regulatory focus and an individual’s implicit person theory on individual performance. Journal of Management, 38(3), 809-835.
[3] de Haan, E., Duckworth, A., Birch, D., and Jones, C. (2013). Executive coaching outcome research: The contribution of common factors such as relationship, personality match, and self-efficacy. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 65(1), 40-57.
[4] Grasmann, C., Scholmerich, F., and Schermuly, C. C. (2020). The relationship between working alliance and client outcomes in coaching: A meta-analysis. Human Relations, 73(1), 35-56.
[5] Bozer, G., Sarros, J. C., and Santora, J. C. (2013). The role of coachee characteristics in executive coaching for effective sustainability. Journal of Management Development, 32(3), 277-294.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。