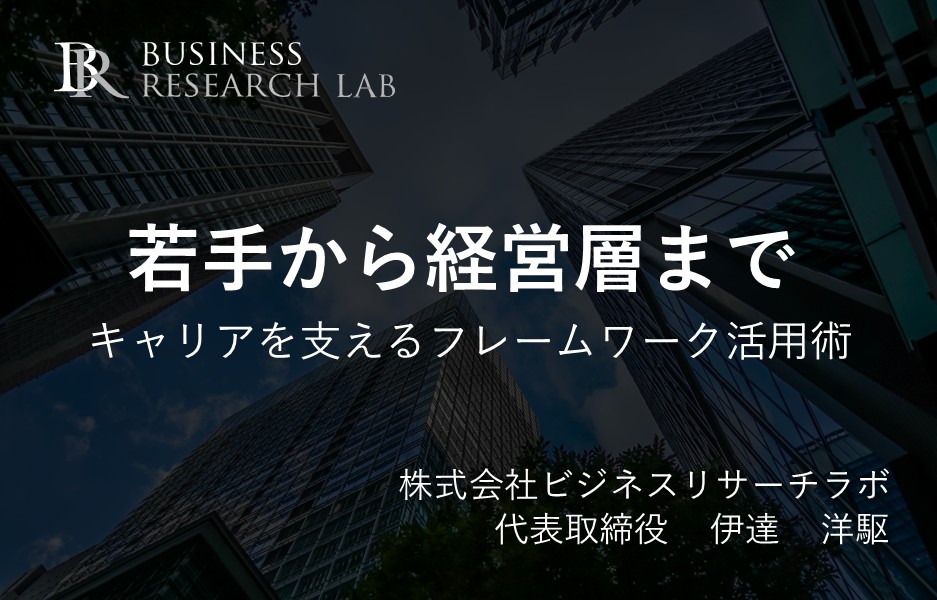2025年11月17日
若手から経営層まで:キャリアを支えるフレームワーク活用術
ビジネスパーソンとしてのキャリアは、長い道のりです。組織の一員として一歩を踏み出した時期、チームの中核として専門性を発揮する時期、より大きな責任を担い、組織全体を導く時期。それぞれの段階で直面する課題の性質は変化し、求められる能力も異なります。若手時代に有効だった成功体験が、管理職になった途端に通用しなくなる。あるいは、プレイヤーとして積み上げた自信が、チームを率いる立場になった途端に揺らぎ始める。多くの人が、キャリアの節目でこうした壁に直面し、自身の思考や行動の変革を迫られます。
経験は間違いなく貴重な資産です。しかし、過去の経験則だけを頼りに複雑な問題に対処することは困難です。なぜ、良かれと思って取った行動が裏目に出てしまうのか。なぜ、かつて機能したはずのマネジメントが、今のチームには響かないのか。こうした問いに答えるためには、経験という個人的な知見に加えて、物事の構造やメカニズムを捉えるための知的な枠組みが必要となります。
この度、私が上梓した『人事・HRフレームワーク大全』は、特定の課題に対する万能薬を提供するものではありません。キャリアの様々な段階で直面するであろう、人と組織をめぐる問題を深く理解するための「思考のOS」を皆さんにインストールすることを目指した一冊です。756ページという物理的な厚みは、83の多様なフレームワークを通じて、皆さんが自身のキャリアステージ、すなわち「現在地」に応じて、思考を深め、行動の精度を高めるための知見を提供します。
本コラムの目的は、この書籍の活用法を、キャリアステージという時間軸に沿って示すことにあります。若手・中堅社員、管理職、経営層。それぞれの立場で直面する典型的な課題を挙げながら、本書がいかにして皆さんの思考を支え、日々の実践を助けるパートナーとなり得るのか、その可能性を探っていきます。
若手・中堅社員編
キャリアの初期から中期にかけて、私たちは組織の「実行者」として、与えられた役割を全うし、専門性を磨くことに注力します。しかし、多くの人がこの段階で共通の壁に突き当たります。それは、組織という大きな仕組みの中で、自身の存在価値や進むべき方向性を見失ってしまうという壁です。
多くの若手・中堅社員が直面するのは、上司や先輩との「見えない関係性」に関する悩みでしょう。「どうすれば、もっと円滑にコミュニケーションが取れるのだろう」「自分の頑張りが、正当に評価されていない気がする」。こうした感情は、上司や先輩との関係性が、業務指示や報告といった公式なやり取りだけで成り立っているわけではないことに起因します。
この目に見えない関係性を可視化する道具の一つが、本書に収録された「LMX(リーダー・メンバー交換理論)」です。この理論は、上司と部下の関係性の質を、「愛着」「忠誠」「貢献」「専門的敬意」という四つの次元で捉えます。この視点を持つことで、「業務上の貢献はできているが、一人の人間としての信頼関係、すなわち愛着を育むような対話が不足しているのかもしれない」といったように、関係性を分析し、次の一手を考えることが可能になります。
また、「フォロワーシップ」のフレームワークは、部下の役割を単なる指示の受け手としてではなく、リーダーに対して主体的・批判的に貢献するパートナーとして捉え直します。これらの知識は、上司との関係をただ待つのではなく、自ら能動的に築いていくための行動指針を与えてくれます。
次に訪れる壁は、キャリアパスへの漠然とした不安です。「この仕事のままで、自分は成長できるのだろうか」「自分の本当にやりたいこと、強みは何だろう」。会社が用意したキャリアパスを歩むだけでは、この種の不安はなかなか解消されません。ここで思考の指針となるのが、「キャリア・アンカー」や「計画的偶発性理論」です。
キャリア・アンカーは、皆さんが職業人生において大切にしたい価値観、例えば専門性の追求なのか、安定した生活なのか、純粋な挑戦なのか、といった自身の軸を見つけ出すための内省を促します。一方、計画的偶発性理論は、キャリアが当初の計画通りに進むとは限らず、偶然の出会いや予期せぬ出来事を好機として捉え、積極的に行動することの重要性を教えてくれます。
これらの視点を得た上で、「ジョブ・クラフティング」のフレームワークを活用すれば、日々の業務をただこなすのではなく、自らの手で再設計していくことが可能になります。与えられた仕事の中に「自分の強みを活かせる工夫はできないか(タスク・クラフティング)」「新しい学びを得られる人とのつながりを作れないか(関係性クラフティング)」と考えることは、受け身の「実行者」から、自らのキャリアを創造する「主体者」へと転換するための、実践的な一歩となるでしょう。
日々の業務に追われる中で、「この仕事が、一体何の役に立っているのだろう」という感覚に襲われることもあります。これは、組織という大きなシステムの中で、自分の役割が断片的に感じられてしまうことが原因の一つです。この課題に対して、「職務特性理論」は、仕事そのものが持つ五つの特性(スキル多様性、タスク完結性、タスク重要性など)が、いかに人のやる気に影響するかを解き明かします。また、「心理的エンパワーメント」は、人が仕事の「意味」や、自らの行動が周囲に与える「影響力」を実感できた時に、内側から力が湧き出ることを示しています。
これらのフレームワークは、自分の仕事と組織、社会とのつながりを再発見させてくれます。本書の各項目末にある「現場で使うためのストレッチ」で、あえてミドルレベルやトップレベルの視点から自分の業務を捉え直してみてください。これまで点にしか見えなかった自分の仕事が、組織全体の文脈の中で、いかに重要な役割を果たしているかが見えてくるはずです。
管理職編
管理職への昇進は、キャリアにおける転換点です。しかし、プレイヤーとして優秀だった人が、必ずしも優れたマネージャーになれるわけではありません。かつての成功体験が、新たな役割を果たす上での足かせとなることも少なくありません。
管理職が直面する最初の壁は、部下の育成とモチベーション管理の難しさです。「最近の若手は打たれ弱い」「自分が若い頃は、もっと主体的に動いたものだ」。こうした嘆きは、リーダーが自身の経験則という、一つの物差しで多様な部下を測ろうとすることから生まれます。
この壁を乗り越えるために、本書は多様な動機づけの理論を提供します。「自己決定理論」は、人の意欲の源泉が「自律性・有能感・関係性」という欲求にあることを示します。部下の行動を細かく管理する(自律性を奪う)のではなく、彼ら彼女らが能力を発揮できる(有能感を育む)環境をどう設計するか。その視点の転換が求められます。
「目標設定理論」や「期待理論」を組み合わせれば、なぜ「具体的で少し困難な目標」が人を成長させるのか、そして「努力が成果に、成果が報酬に結びつく」という期待の連鎖をどう設計すれば良いのか、その道筋が見えてきます。個人面談の場でこれらの理論を意識すれば、皆さんの問いかけは「なぜできないんだ」という詰問から、「どうすれば◯◯さんの力が最も発揮できるだろうか」という支援的な対話へと変わるでしょう。
続いて、機能不全に陥るチームの問題があります。「個々の能力は高いのに、チームとして成果が出ない」「部門間の連携が悪く、いつも対立している」。こうした問題は、人間関係という見えないインフラが整備されていないことに起因します。
「コンフリクトマネジメント」は、対立を単なる問題ではなく、より良い解決策を生むための好機と捉え直す視点を与えてくれます。「組織市民行動」は、職務記述書には書かれていない「自発的な助け合い」をいかに組織の文化として育むか、そのヒントを提供します。「共有メンタルモデル」というフレームワークは、チームが同じ目標、同じ手順、同じ役割分担の「地図」を頭の中に描けているか、その重要性を教えてくれます。優れたチームとは、仲が良いだけでなく、協働のための暗黙のルールが共有された集団です。これらのフレームワークは、皆さんがチームを育むための知識となります。
多くの管理職が、自身のプレイヤーとしての業務と、マネージャーとしての業務の板挟みに苦しんでいます。「自分がやった方が早い」という考えは、部下の成長機会を奪い、自身の疲弊を招きます。
「スキルモデル」は、管理職に求められる能力を「テクニカル(専門知識)」「ヒューマン(対人関係)」「コンセプチュアル(概念化)」の三つに分類します。プレイヤーからマネージャーへの転身とは、テクニカルスキルへの依存から脱却し、コンセプチュアルスキル、すなわち、より大局的な視点から物事を構想する能力へと軸足を移すプロセスに他なりません。
そして、「リーダーシップ代替要因」の考え方は、このジレンマからの出口を示唆します。明確なルールや浸透した文化、自律性の高いメンバーがいれば、リーダーが常に介入しなくてもチームは機能します。目指すべきは、個人として全てを背負うことではなく、皆さんが不在でもチームが自律的に動き、成果を出し続けられる「仕組み」を設計することです。
経営層・人事責任者編
経営層や人事責任者の役割は、個別のチームを動かすことにとどまりません。組織という仕組みを設計し、変化の激しい環境を乗り越え、未来へと導くことです。そのためには、組織という複雑なシステムを動かす、よりマクロな力学を理解する必要があります。
多くの組織変革が掛け声倒れに終わるのは、組織文化という「見えない岩盤」の存在を見過ごしているからです。「企業理念を刷新しても、現場の行動は何も変わらない」「過去の成功体験が、新しい挑戦の足かせになっている」。
本書の「組織文化の構造」に関するフレームワークは、文化を表層の「人工物」、中間の「価値観」、そして深層の「基本的仮定」の三層で捉えます。変革の鍵は、人々が無意識に共有している「当たり前」という名の「基本的仮定」に働きかけることにあります。「両利きの経営」は、既存事業を磨く「深化」と、新規事業を試す「探索」をいかに両立させるかという、現代企業が直面するジレンマに光を当てます。「組織的忘却」は、新しいことを学ぶためには、時に古い知識や成功体験を意図的に「忘れる」ことが不可欠であるという、逆説的だが重要な視点を教えてくれます。
また、「採用はうまくいっているのに、若手が育たず辞めていく」「新しい評価制度を導入したが、現場の納得感が得られない」。これらの問題は、人事施策がそれぞれ孤立し、システムとして機能していないことに起因します。
「高業績作業システム(HPWS)」は、採用、育成、評価、報酬といった人事施策群が、一貫した思想のもとに設計され、相互に連携することで、組織全体のパフォーマンスが最大化されることを示します。「ASAフレームワーク」は、組織が意図せず同質化していく力学を解明し、多様性を確保するための戦略的な採用・配置の重要性を説きます。「P-Eフィット(個人と環境の適合性)」の視点は、採用から配置、育成に至るまで、個人と組織の「相性」をいかに最適化していくか、その指針を与えてくれます。
変化が常態となった現代において、過去の延長線上に未来を描くことはできません。組織自体が、学び、進化し続ける能力を持つことが、持続的な成長の条件となります。
「組織学習」に関するフレームワークは、既存のやり方を改善する「シングルループ学習」から、その前提を問い直す「ダブルループ学習」、さらには「学び方を学ぶ」という「トリプルループ学習」へと、組織の学習レベルを進化させる道筋を示します。「競合価値モデル」や「組織戦略類型」といったフレームワークは、激変する外部環境を診断し、自社のポジショニングを再定義するための思考の地図となります。これらは、未来という不確実な状況を乗りこなすための基盤となるでしょう。
思考の枠組みを手に、自らの道を歩む
キャリアの道のりは、常に平坦ではありません。しかし、各ステージで直面する壁や困難は、皆さんを打ちのめすためではなく、より強く、賢慮に満ちたビジネスパーソンへと成長させるための試練とも言えます。『人事・HRフレームワーク大全』は、その試練のただ中で、皆さんが道を見失わないための知恵と勇気を与えてくれるでしょう。
皆さんの現在の立場から、本書を手に取ってみてください。若手であるならば、数年後の自分の姿をより鮮明に。管理職であるならば、預かるチームと組織の全体像をより立体的に。経営者であるならば、自社が立つべき未来を、より確かなものとして構想できるはずです。
この一冊は、完成された地図ではありません。皆さんの手によって使い込まれ、皆さん自身の経験という軌跡が書き込まれることで、初めて真価を発揮するものです。思考の枠組みを手に、皆さん自身の、そして皆さんの組織の、新たな一歩を始めていただければと思います。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。