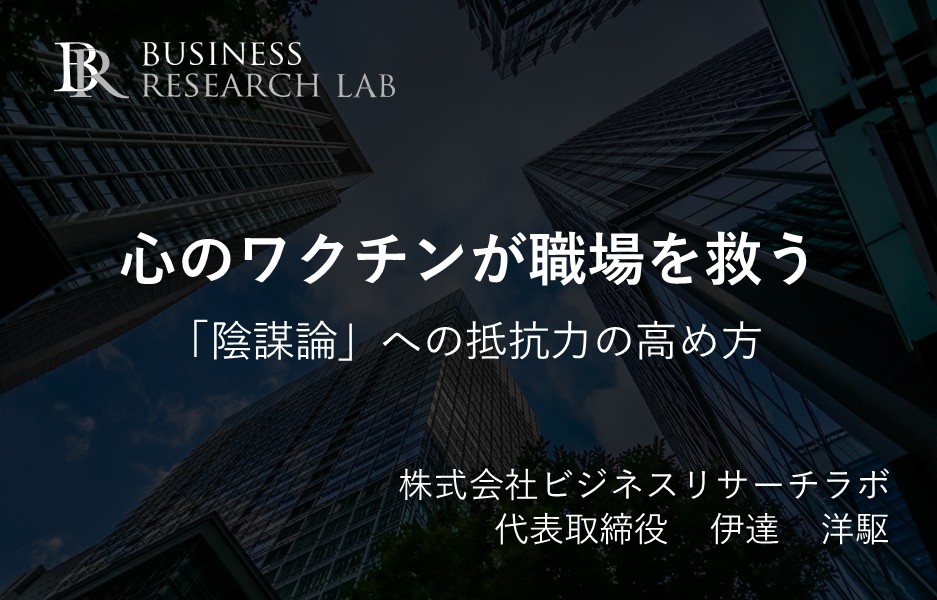2025年11月14日
心のワクチンが職場を救う:「陰謀論」への抵抗力の高め方
私たちの働く環境である職場は、一日の多くの時間を過ごす基盤です。そこでは、同僚との協力、目標達成への邁進、自己実現といった、前向きな活動が繰り広げられています。しかし、その一方で、水面下では目に見えない澱のようなものが溜まっていくことがあります。「あのプロジェクトの失敗は、実は一部の部署が仕組んだことではないか」「今回の人事異動には、経営陣の隠された意図があるに違いない」「会社は業績が良いと発表しているが、本当は経営が傾いているのを隠しているのではないか」。こうした疑念や憶測は、廊下でのささやき声や、ランチタイムの会話の中に、ふとした瞬間に顔をのぞかせます。
これらは噂話やゴシップとして片付けられてしまうことが多いかもしれません。しかし、こうした根拠の不確かな疑念が、特定の意図を持つ存在を想定し、体系的な物語として語られ始めるとき、それは「職場の陰謀論」という様相を呈してきます。社会で語られる壮大な陰謀論とは異なり、職場の陰謀論は、私たちの身近な上司や経営陣、あるいは特定の部署に向けられます。そして、それは組織の活力を蝕んでいくことがあります。従業員同士の信頼関係を損ない、会社への忠誠心を削ぎ、働く人々の心に不安と不満の種をまき散らします。
陰謀論的な見方を、一部の特殊な人々が持つものだと考える向きもあります。しかし、科学的な探求は、そうした考え方への傾倒が、人間の普通の心理メカニズムと結びついていることを解き明かしつつあります。人は誰でも、特定の環境や心理状態に置かれれば、物事の背後に隠された意図を探ろうとする思考に陥る可能性があります。
本コラムでは、職場という閉鎖的でありながらも複雑な人間関係が渦巻く環境で、なぜ陰謀論的な見方が生まれ、育ってしまうのか、そのメカニズムを科学的な知見の窓から覗き込んでいきます。どのようなリーダーの振る舞いが疑念のきっかけとなるのか。私たちの心の中にあるどのような感覚が、そうした見方への扉を開けてしまうのか。一度広まり始めた見方に対して、人の心はどのように反応し、また、冷静に物事を捉える力を保つことは可能なのか。これらの問いを解きほぐしていくことで、職場の陰謀論という現象を理解できればと思います。
破壊的な上司は職場の陰謀信念と離職意図を高める
組織の中で働く私たちにとって、直属の上司との関係は、日々の業務の満足度や精神的な安定に影響を及ぼします。優れたリーダーは、部下の能力を引き出し、チームに一体感をもたらしますが、その逆もまた然りです。上司の不適切な言動は、部下の心に暗い影を落とし、組織全体への不信感を醸成する起点となりえます。どのようなリーダーの振る舞いが、部下をして「この会社の上層部は、何かよからぬことを企んでいるのではないか」という疑念、すなわち「組織内陰謀信念」を抱かせるに至るのでしょうか。この問いに光を当てるため、ある調査が行われました[1]。
この調査は、米国の様々な職種で働く成人を対象に、オンラインプラットフォームを通じて実施されました。回答者は、現在の職場に少なくとも三ヶ月以上在籍しているという条件を満たした約二百名で、平均年齢は三十代前半でした。彼らには、自身の直属の上司の日常的な振る舞いについて、多角的な視点から評価を求めました。
上司のスタイルは、大きく四つの類型に分けて測定されました。一つ目は、部下を個人的な目的のために利用したり、自己中心的で横暴な態度をとったりする「独裁的リーダーシップ」。二つ目は、部下への関与を放棄し、必要な指導や意思決定を怠る「放任主義リーダーシップ」。これら二つは、組織に悪影響をもたらす破壊的なスタイルと位置づけられます。対照的に、三つ目は、将来のビジョンを掲げて部下を鼓舞し、魅力で人々を惹きつける「カリスマ的リーダーシップ」。四つ目が、意思決定のプロセスに部下を参加させ、意見を尊重する「参加型リーダーシップ」です。これらは建設的なスタイルと見なされました。
分析の結果、上司の振る舞いと部下の陰謀信念との間に結びつきがあることが浮かび上がりました。独裁的、あるいは放任主義的な上司の下で働く従業員ほど、自社の経営陣に対して強い陰謀信念を抱いていることが分かったのです。部下を意のままに操ろうとする上司や、逆に部下を守る責任を放棄する上司の存在が、組織上層部全体への猜疑心へとつながっていました。
一方で、部下を意思決定に参加させる参加型リーダーシップは、陰謀信念を抑制する方向に働いていました。日々の業務において自分の意見が尊重され、プロセスに関与できているという感覚が、組織への信頼を育んでいたと考えられます。
人々を惹きつけるとされるカリスマ的リーダーシップは、組織内陰謀信念のレベルと直接的な関連が見られませんでした。これは、リーダーがどれだけ魅力的で雄弁であっても、それだけでは部下が抱く組織への根本的な疑念を払拭するには不十分であることを物語っています。ビジョンを語る言葉の力だけではなく、日々の実務における誠実な関わりが、信頼の礎となるようです。
なぜ独裁的・放任的なリーダーシップが、部下の陰謀信念をかき立てるのでしょうか。そのメカニズムを解き明かす鍵は、「ジョブ・インセキュリティ」、つまり職を失うことへの不安にありました。分析を進めると、これらの破壊的な上司の下で働く従業員は、自身の雇用の安定性に強い不安を感じていることが明らかになりました。この「職が危うい」という不安感が、組織内陰謀信念を増幅させる引き金となっていました。
横暴な上司や無責任な上司は、まず部下の心に「自分の立場は安泰ではない」という不安定な気持ちを生み出します。個人的な不安や脅威にさらされた部下は、その原因を理解しようとします。その過程で、「自分の不安は、経営陣が何かを隠し、自分たち従業員をないがしろにしているせいだ」という、陰謀論的な解釈にたどり着きやすくなるのです。
統制感が高まると陰謀論への傾倒は弱まる
先ほどは、破壊的な上司の存在が部下の心に「職の不安定さ」という不安を生み、それが組織への陰謀信念につながるプロセスを見てきました。ここから分かるのは、人が陰謀論的な考え方に傾く背景には、自身の置かれた状況が不安定で、先行きが見えないという感覚があるということです。この感覚の核心にあるのが、「物事を自分でコントロールできている」という感覚、すなわち「統制感」です。
統制感は、私たちが世界を理解し、精神的な安定を保つ上で欠かせない心理的な基盤です。ここでは、統制感が失われることが、いかに陰謀論への扉を開き、逆に統制感を取り戻すことが、その扉を閉じる鍵となりうるのかを、二つの異なる角度から検証した実験的研究を通じて探っていきます[2]。
一つ目の研究は、人の心の中にある統制感を意図的に操作することで、陰謀論への信じやすさがどう変わるかを調べたものです。これまでの研究の多くは、「統制感を失わせる」と陰謀論を信じやすくなる、という一方向からの検証がほとんどでした。しかし、この研究者たちは一歩進んで、「逆に、統制感を高めたら、陰謀論を信じにくくなるのではないか」という、いわばポジティブな側面からのアプローチを試みました。
実験は、オランダの大学生を対象に行われました。参加者はランダムに三つのグループに分けられ、それぞれ異なる課題に取り組むよう指示されました。
最初のグループ(高統制群)の学生たちには、「これまでの人生で、あなたが完全に物事をコントロールできたと感じた出来事」を一つ思い出し、その時の状況や気持ちを文章に書いてもらいました。これは、参加者の心の中に統制感を呼び覚ますための操作です。二つ目のグループ(低統制群)には、対照的に「あなたが全く物事をコントロールできなかったと感じた出来事」について記述してもらいました。これは、統制感を脅かすための操作です。三つ目のグループ(中立群)には、これらの操作とは無関係に、「昨日の夕食に何を食べたか」を書いてもらいました。
課題を終えた後、参加者全員に、ある架空のシナリオを読んでもらいました。それは、彼ら彼女らが住むアムステルダム市で進められている新しい地下鉄建設計画に関するものでした。そのシナリオには、「市議会は公式の予算よりもはるかに多くの費用がかかっていることを隠蔽している」「建設プロジェクトの遅延は、特定の企業に利益をもたらすために意図的に引き起こされている」といった、陰謀論的な疑念を抱かせるような記述が含まれていました。そして、この計画の背後に陰謀があると思うか、その信念の強さを複数の質問で測定しました。
結果、最も強く陰謀論を信じたのは、コントロールできなかった無力な経験を思い出させられた低統制群の学生たちでした。そして、最も陰謀論を信じなかったのは、自分で物事をコントロールできた成功体験を思い出した高統制群でした。興味深いのは、昨日の夕食について書いた中立群の学生たちの結果です。彼ら彼女らの陰謀信念の強さは、低統制群と大差がなく、高統制群よりも明らかに高い水準にありました。
このことは、日常生活における私たちの心の状態は、どちらかといえば統制感がやや欠如した状態にあり、そこからさらに統制感を失うことの悪影響もさることながら、意識的に「自分にはできる」という感覚を高めること自体に、陰謀論への抵抗力をつける働きがあることを示唆しています。
このような実験室での結果は、現実社会の大きな混乱の中でも当てはまるのでしょうか。二つ目の研究は、この問いに答えるために、歴史的な出来事を舞台に行われました。その舞台とは、1999年の終わり、世界中がコンピューターの「2000年問題(Y2Kバグ)」に対する不安に包まれていた時期です。これは、コンピューターが2000年を1900年と誤認識することで、社会インフラに大混乱が生じるのではないかと危惧された問題でした。個人の力ではどうすることもできない、巨大で不確実な脅威であり、人々の統制感を揺るがす出来事でした。
この調査は、2000年問題への不安がピークに達していた時期に、アメリカの成人1200人以上を対象としてオンラインで実施されました。調査ではまず、2000年問題に対してどれほどの脅威を感じ、自分の生活にどのような危険が及ぶと考えているかが尋ねられました。これは、実社会における統制感の喪失度合いを測るための指標です。同時に、この2000年問題とは全く無関係ないくつかの有名な陰謀論を、どの程度信じているかが問われました。例えば、「政府はUFOの存在を隠蔽している」「ケネディ大統領の暗殺には政府機関が関与している」「黒人コミュニティに意図的に薬物が流入させられている」といった、多岐にわたる陰謀論です。
分析の結果、両者の間には関連が見出されました。2000年問題という、目の前にある巨大な脅威に対して強い不安を感じている人ほど、それとは全く接点のない、様々な陰謀論を広く信じているという傾向が確認されたのです。この結果が物語るのは、一つの大きな、自分の力ではコントロール不能な問題に直面したときに感じる無力感が、その人の世界観全体に波及するということです。目の前の不安を説明できないとき、人は世の中の他の不可解な出来事に対しても、「そこには自分の知らない、誰かの悪意ある意図が隠されているに違いない」という見方をしやすくなります。
接種理論は陰謀論への抵抗力を高める
これまでのところで、職場の陰謀論がどのようなリーダーシップの下で生まれ、個人のどのような心理状態によって育まれていくのかを見てきました。破壊的な上司がもたらす不安、自分の置かれた状況をコントロールできないという無力感。これらが、人々を陰謀論的な思考へと傾かせる素地となります。
では、一度こうした素地ができてしまった心は、特定の主張に対して無防備なままなのでしょうか。あるいは、根拠の不確かな情報や説得力の高い主張に触れた際に、冷静に判断するための心の準備、いわば思考の免疫のようなものをあらかじめつけておくことはできないのでしょうか。この問いに、一つの視点を提供するのが「接種理論」です。
接種理論は、もともと医学の予防接種のアナロジーから生まれたコミュニケーション学の考え方です。本物のウイルスに感染する前に、弱毒化されたウイルス(ワクチン)を体内にいれることで、体が抗体の作り方を学び、いざ本物のウイルスが侵入してきたときに撃退できるようになる。
これと同じように、人の信念や態度も、いきなり強力な反論にさらされると簡単に覆されてしまうかもしれませんが、あらかじめその反論の「弱いバージョン」に触れさせておくことで、心の中で反論に対する「抗体」、すなわち反論への反論を準備することができ、結果として元の信念がより強固になる、というものです。
この理論を、現代社会で関心を集める陰謀論に応用し、その有効性を検証した実験があります[3]。この実験の研究者たちは、陰謀論という、時に感情に強く訴えかけ、論理だけでは割り切れない主張に対しても、この「心のワクチン」は機能するのかどうかを確かめようとしました。さらに、もしワクチンが有効だとして、そのワクチンの効果を無力化するような「ワクチンへのワクチン」、すなわち「メタ接種」という現象も起こりうるのか、という点にまで踏み込んで検証しています。
実験は、アメリカの大学でコミュニケーションの授業を履修する学生約三百名を対象に行われました。彼ら彼女らに「攻撃」メッセージとして見せられたのは、アメリカ同時多発テロ(9/11)がアメリカ政府による自作自演であったと主張する、有名な陰謀論映画の一部でした。この説得力の高い映像を視聴する前に、学生たちはランダムにいくつかのグループに分けられ、異なる「処置」を受けました。
まず、「接種グループ」の学生たちです。彼ら彼女らには、これから見る映画がどのような主張をしてくるかを先取りして伝え、その主張に含まれる論理的な欠陥や事実の誤りをあらかじめ指摘する短い文章を読んでもらいました。これが「心のワクチン」にあたります。このワクチンには二種類が用意されました。一つは、陰謀論側の主張に対して具体的なデータや証拠を提示して反論する「事実ベースの接種」。もう一つは、陰謀論側の推論過程そのものに「矛盾がある」「早まった一般化をしている」といった、論理的な瑕疵を指摘する「論理ベースの接種」です。
次が、「メタ接種グループ」です。彼ら彼女らは、接種グループが読んだような「専門家による反論」そのものに対して、警戒を促すような文章を読みました。例えば、「世の中には様々な意見があり、誰かの解説を鵜呑みにするのは危険です。最終的にはあなた自身の頭で判断することが大切です」といった内容です。これは、接種というワクチン自体の信頼性を揺るがし、その効果を弱めることを狙ったものです。
最後に、これらの処置を一切受けない「統制グループ」がいました。事前の情報なしに、いきなり陰謀論映画を視聴することになります。
すべてのグループがそれぞれの処置を終えた後、全員に陰謀論映画を約四十分間見せ、その直後に、映画の主張をどの程度受け入れたか、そして「アメリカ政府が9/11に関与した」という陰謀信念をどの程度信じるようになったかを、複数の質問によって測定しました。
結果は、接種理論の有効性を裏付けるものでした。事前のワクチンを接種されたグループは、ワクチンなしでいきなり映画を見た統制グループに比べて、映画の主張や陰謀信念を受け入れる度合いが低いことが確認されました。あらかじめ弱い形で反論に触れておくことで、心の中に抵抗力が生まれ、強力な主張に直面しても、簡単には説得されなくなることが示されました。
特に、二種類のワクチンのうち、「事実ベースの接種」の方が、「論理ベースの接種」よりも、抵抗力を高める働きが強い様子が見られました。これは、抽象的な論理の欠陥を指摘されるよりも、具体的な事実やデータを伴う反論に触れることの方が、人々の心に残りやすく、反論の「抗体」を形成する上でより役立つ可能性を示唆しています。
もう一つの発見は、「メタ接種」の効果です。接種の効果を弱めることを狙ったメッセージを読んだメタ接種グループは、ワクチンを打った接種グループよりも陰謀論を信じやすくなり、その信念の強さは、接種グループと統制グループのちょうど中間あたりに位置しました。これは、心のワクチンが確かに有効である一方で、そのワクチン効果を意図的に弱めようとする対抗的なメッセージもまた、ある程度の効果を持つことを物語っています。
脚注
[1] van Prooijen, J. W., and de Vries, R. E. (2016). Organizational conspiracy beliefs: Implications for leadership styles and employee outcomes. Journal of Business and Psychology, 31(4), 479-491.
[2] van Prooijen, J. W., and Acker, M. (2015). The influence of control on belief in conspiracy theories: Conceptual and applied extensions. Applied Cognitive Psychology, 29(5), 753-761.
[3] Banas, J. A., and Miller, G. (2013). Inducing resistance to conspiracy theory propaganda: Testing inoculation and metainoculation strategies. Human Communication Research, 39(2), 184-207.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。