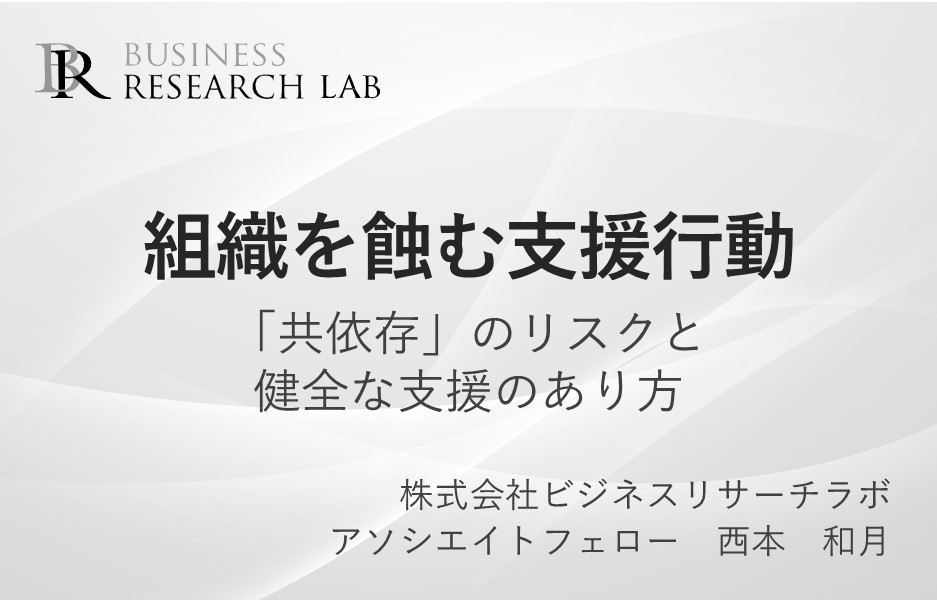2025年11月14日
組織を蝕む支援行動:「共依存」のリスクと健全な支援のあり方
職場では、助け合い、献身、協力といった価値観が奨励されます。困っている同僚を支援し、チームの成果を優先する姿勢は、組織にとって重要なものです。また個人にとっても、誰かのために良い行いをし、そのことによって感謝されたり評価されたりすることは、自己肯定感を高めてくれます。「誰かのため」に行動することは、組織にも個人にも良い影響を与えるものです。
しかし、その「誰かのため」の行動であるはずの支援行動も行きすぎると、知らず知らずのうちに職場に共依存というリスクを招きかねません。共依存とは、他者への過剰な援助や自己犠牲を通じて自らの存在価値を確立しようとする心理的な傾向を指します。
一見、職場の円滑な人間関係を支えているように見える支援行動が、実は本人にも組織にも深刻なダメージを与えている可能性があります。本稿では、心理学と組織研究の知見に基づき、職場における共依存の特徴、その影響、そして予防のヒントについて解説します。
共依存とは何か
共依存とは、もともとはアルコール依存症患者の家族に見られた行動パターンに由来する概念です。アルコール依存症患者を支えている家族は一見支援者ですが、実は支えることで得られる満足感や評価を求めている。つまり支える側も依存状態になっている可能性があるのです。
しかし現在では、この概念の対象は依存症の関係者だけに限りません。自分の欲求や感情は犠牲にして、他者を過度にケアし、コントロールしようとする不健全な関わり方全般を指す言葉として使われています。
共依存の状態にある人には5つの特徴があります[1]。
- 他者を助けることに強迫的:他者の感情、行動、欲求、社会的経験の結果に自分が責任を持たなければならないと感じる。
- 自分の本当の考えや感情を表現することが困難:他者に受け入れられないかもしれないという恐れから、自分の意見や感情を抑圧する習慣がある。
- 完璧主義者:自己肯定感が低く、自分は本質的に欠陥があると信じている。そのため、ミスをすること、特にそのミスが公にさらされることを強く恐れている。
- コントロールしなくてはいけないと信じている:先が読めない状況に恐れを感じているため、人間関係を自分の思い通りにコントロールするために並外れた努力をする。
- 不誠実:他者への依存を否認し、承認欲求を「親切さ」や「いい人らしさ」と偽装する。自分自身に対しても嘘をついている。
共依存から生じる支援行動(以降、共依存行動)は、純粋に相手に好意をもち、その相手を助けたいという動機から生じるものではありません。共依存行動は、他者の幸せや助けになることを一番の目的として行う行動ではなく、自分の価値を高めたり、自己肯定感を高めたりといった、自分の利益を動機とする行動です。
共依存の傾向の強い人が人間関係において抱いている感情は、支援的な温かいものだけではないことを示している研究があります[2]。パートナーがいる大学生を対象として共依存の傾向が強い人の特徴を調べた研究では、共依存の傾向が強い人は親密な人間関係や、お互いを思いやることを強く望んでいると同時に、親密さを恐れていることが指摘されました。そしてパートナーの感情に共感するものの、パートナーを支えたり思いやったりする可能性は高くなく、それどころか、高い競争心を抱いていることが示されました。
こうした共依存行動は、職場ではどのようにあらわれるのでしょうか。研究からは、以下の例が挙げられます。
- 上司や同僚のニーズや感情に敏感で、期待に応えようと過剰な努力をする。
- 困っている同僚や部下の問題に過剰に介入する。
- 自分の限界を超えて援助を続けたりする。
こうした共依存行動は、最終的には共依存の状態にある人が燃え尽き症候群やうつ病に陥るリスクを高める可能性があります。しかしそれだけでなく、個々人の共依存行動が広がると、組織全体が機能不全に陥る危険性も指摘されています。
利他的行動のポジティブな効果
共依存行動をよく理解するために、まず、共依存ではない、純粋に他者のためにする行動のポジティブな効果を見ていきます。見返りを求めずに、他者の役に立とうとする行動を利他的行動と呼びます。利他的行動は、何かをしてもらった側だけでなく、利他的な行動を行った本人にも良い影響を与えることが多くの研究で示されています。
アメリカの高齢者の夫婦を対象にし、他者への支援行動が、ストレスと死亡率の関連を弱くすることを明らかにした研究があります[3]。この研究では、過去1年間に他者を助けた経験がない人では、ストレスフルな出来事に遭遇することによって、調査期間中の死亡率が高くなっていました。
人助けをしない人は、病気や経済的な困難などのストレスフルな出来事に遭遇すると、死亡リスクが30%上昇することを示唆されました。しかし、他者を助けた経験がある人では、ストレスと死亡率との間に関連はみられませんでした。
この結果が意味することは、支援行動は、ストレスが死亡率に与える影響の緩衝剤として機能するということです。他者を助けることは、自分が社会や人間関係の中で役に立っているという実感をもたらします。自分という存在の意味や重要性を感じることは、精神的健康の維持において重要なものであり、心の負担をやわらげる働きがあります。つまり、人助けをした結果として心理状態が向上することが期待でき、その結果として、ストレスによる死亡率の上昇が抑えられる可能性が示されたのです。
人助けが心理状態を向上させることを調べた他の研究では、他者のためにお金を使うことも幸福度を上げることが示されています[4]。普段の生活において、生活のための支出と自分のための買い物を合わせた個人的支出は幸福度とは無関係でしたが、他者への贈り物と慈善団体への寄付を合わせた向社会的支出では、支出が多いほど幸福であるという結果になりました。
この研究では、参加者にお金を渡し、その使い方が幸福感にどのような影響を与えるのかを調べる実験も行っています。実験参加者は、朝にお金が入った封筒を渡され、夕方までにそのお金を使用するように指示されました。お金を使う対象によって2群に分けられ、個人的支出条件に割り当てられた参加者は、自分のためにお金を使うよう指示され、向社会的支出条件に割り当てられた参加者は、誰かへのプレゼントや寄付にお金を使うよう指示されました。
その結果、向社会的支出条件の参加者は、個人的支出条件の参加者よりも、高い幸福感を報告したのです。これらの結果は、他者のためにお金を使うことは、自分のためにお金を使うことよりも幸福を促進することを示しています。自分が得られるはずだったものを犠牲にして、「誰かのために」する行動は、私たちの幸福にしてくれるものだと言えます。
利他的な支援行動と共依存の違い
共依存行動も、「他者のために何かをする」という点では利他的な支援行動と同じなのに、結果が異なってしまうのはなぜでしょうか。その理由は、利他的な支援行動と共依存行動では、「相手のために、健全な距離で支援する(利他的な支援行動)」と「自分のために人を助けてしまう(共依存)」という違いにあります。共依存行動は最終的には自分のための行動なので、自分の評価が上がるなどの見返りが得られないことは、ストレスにつながってしまいます。
共依存の状態にある人は、自分の業務を放置してでも他者を助けるという自分の行為を、素晴らしいサービス行動だと捉えます。相手からの信頼を獲得し、自分の価値を多くの人に認めてもらえる手段であると考えるのです[5]。つまり自分のために相手を助けているのです。
しかし、共依存の状態にある人が自分を犠牲にしてまで助けた相手は、この過剰な介入を押し付けがましいものだと感じ、自分の業務を侵害するものだと捉えるかもしれません。このような場合に共依存の状態にある人は、なぜ自分の犠牲が相手に評価されなかったのか分からず、相手の反応にショックを受けてしまいます。
さらに、共依存の状態にある人は、本来であれば自分が責任を負うはずのものではなかった他者の成果に対して責任を感じることになります。そのため、仕事が成功に結びつかなかったときに、過剰な罪悪感にさいなまれることになってしまうのです。
時間が経つにつれて、共依存行動が強迫的になると、過剰な援助は、援助を必要としない他の人々にまで広がることがあります。共依存の状態にある人の多くは、本来であれば自分には責任がなかったはずの仕事を引き受けてしまうため、常に不安やストレスを感じ、過重労働に悩まされることになります。
仕事を抱え過ぎて、もともと自分に割り当てられていた仕事で成果を出せなかったり、同僚から自分と同じような支援を返してもらえなかったりと、自分が求めた結果が得られないことが共依存の状態にある人には繰り返し起こるようになります。これによって、共依存の状態にある人の自己肯定感や自己効力感は低下し、ストレスの多い仕事や状況に耐えられなくなってしまうのです。
共依存行動は純粋に利他的な支援行動ではなく、自分に自信が持てないために、他者に過剰に干渉し、コントロールしようとしている状態です。求めている結果や利益があるので、それが得られない場合にはネガティブな状態に陥ってしまうのです。
共依存の組織レベルの問題
共依存はもともと、家族や恋人などの、個人の関係において注目されていました。しかし、個人だけの問題ではなく、共依存の状態にある人の存在が組織の機能不全を促進し、最終的には組織の崩壊を導く危険性が指摘されています[6]。
共依存が組織の崩壊を招くメカニズムとして、個人の共依存行動が組織文化としての共依存をもたらし、それが組織を閉鎖的なものにし、最終的には組織の崩壊につながると考えられています。
共依存状態にある人の特徴に、自己を抑圧するというものがあります。自分の意見や感情を押し殺し、他者が受け入れてくれそうなことを表現するのです。自分を抑圧するという行動は、個人の問題にとどまらず、組織に広がり、組織を抑圧的・閉鎖的なものに変化させてしまう危険性があるものなのです。共依存が組織の崩壊につながるメカニズムを段階的に説明すると以下のようになります。
1. 個人の共依存的行動の発生
まずある個人が、共依存の特徴である自己抑圧的な行動をとります。自分の本音やニーズを押し殺し、上司や組織に過剰に適応する「いい人」の行動をとるのです。この共依存行動をとる個人には2種類のタイプが考えられます。1つ目のタイプは、以前の組織で共依存行動を身に着け、今の組織でも同じように行動してしまう人です。
2つ目のタイプは、異論や自由な意見を出しづらい権威主義的な組織の中で、共依存に陥ってしまう人です。自分は無力だと感じ、自分の言いたいことを制限したり、慎重なコミュニケーションをとることが安全だと思える場合に、相手を喜ばせたり、融通を利かせたりといった援助する役割に引き込まれてしまうのです。
この自己抑圧的な行動は、組織から身を守り、組織で生き残るための戦略です。共依存の状態にある人は、本心として考えたり感じたりしていることではなく、その時々で「受け入れられそう」あるいは「安全そう」と思われることを伝えるようになります。
2. 組織文化としての共依存の蔓延
自分を抑圧する行動が組織全体に広がると、組織文化自体が次第に、本音を言わない、問題を隠す、成果至上主義を絶対視する、上司に迎合するといった歪みを抱えるようになります。個人の抑圧が、集団の文化も抑圧的なものに変質させてしまうのです。
3. 情報共有の停滞と外部からのフィードバック機能の低下
組織に共依存が蔓延し、抑圧的な文化があるために積極的なコミュニケーションが行われなくなることは、情報共有を妨げることにつながります。従業員全体で、上司が喜んで耳を傾けるような発言や、組織に許容される発言だけをするようになると、現場からの問題提起や、顧客や市場からのネガティブな声が組織の中枢に届きにくくなります。
本来、組織は外部からのフィードバックによって改善していくべきですが、それが機能しなくなってしまいます。組織の成功、さらには存続にとって重要な情報でさえも、見落とされる可能性が高くなります。
4. 組織の閉鎖化
組織内での情報の共有が行われなくなり、外部からのフィードバックが乏しい状態がさらに進むと、組織もさらに悪化していきます。顧客ニーズの変化に鈍感になったり、技術革新や社会動向に乗り遅れたりといった、外部世界とのつながりが絶たれていく現象が起こります。組織は内部だけで自己完結する、閉じたものになってしまいます。
外部からのフィードバックや社会の変化を取り入れられなくなった閉じたシステムは、自分たちの組織が外部環境から影響を受けることを無視して自己中心的になります。目標達成を可能にするさまざまな手段を無視して誤った手続きを繰り返したり、組織の存続に影響を及ぼすような、外部の偶発的な出来事を考慮しなくなったりしてしまいます。表面的には平穏に見える場合もありますが、内部では確実に組織のエネルギーの枯渇が進みます。
5. 機能不全の進行と組織の崩壊
閉鎖的な組織は、新しいエネルギーを取り込めないため、新しい挑戦ができない、問題が放置される、社員のモチベーションが下がる、人材が離れていくなどの現象が起きるようになります。そして、ついには組織の機能不全、そして崩壊へと進んでいきます。
共依存は個人の問題にとどまらず、集団を抑圧的なものに変化させることによって、外部からの影響が排除された閉じた組織を作りだす原因になってしまいます。組織を健全な状態に保つためにも、共依存の問題に組織として取り組む必要があります。
組織における共依存の発生要因と対策
本来であれば支援行動はポジティブなものであるはずですが、組織の風土が適切ではない場合に、共依存という有害な支援行動を生み出してしまう可能性があります。健全な利他的な支援行動ではなく、共依存を生み出してしまう組織の要因とその対策を見てみましょう[7][8][9]。
強い権威の存在の影響を考慮する
組織の問題について発言する地位がなかったり、意見を聞いてもらえる場がなかったりすると、メンバーは自分が無力だと感じます。自分に自信がないため、相手が喜ぶことをしたり、媚びへつらったりし、自分の感情やニーズを犠牲にして、上司や組織のニーズを優先するようになります。
こうした自己抑圧的な行動を引き起こす強い権威をもつ存在が、組織の内部に発生してしまうことを防ぐ必要があります。そこで、組織として行うと良い、共依存への対策を紹介します。
- 組織に許容される発言や安全だと思われる発言ではなく、本心で考えていることや感じていることを従業員が口に出せるように、組織は職場の心理的安全性[10]を高める。
- 組織は成果だけでなく、努力や挑戦といったプロセスも評価し、従業員の自己肯定感を高める。
- 対人関係や組織の中で、効果的に対処するための能力を身に着けられるような機会を提供する。ソーシャルスキルや感情調整などを身に着けるための研修を実施する。
トップダウン型の意思決定が行われ、上に逆らわず、上を立てることが求められる組織では、権威に媚びることは期待されるだけでなく、報われることでもあるため、共依存が助長されてしまいます。他者からの承認に依存するのではなく、自分自身の考えや選択を表明し、それに基づく行動から得られる自己肯定感を育める環境を整える必要があります。
ワーカホリズムへの対策
仕事への非合理的で過剰なコミットメントであるワーカホリズムは、従業員の仕事以外の人生の側面を貧しくしていきます。ワーカホリズムは単純に多忙であることや、やりがいや楽しさゆえの働き過ぎとは異なり、働くことに強迫的に駆り立てられている、仕事にとらわれてしまっている心理状態です。ワーカホリズムによって犠牲にされるものには、身体の健康や人間関係だけでなく、感情や精神的な健康も含まれます。
ワーカホリズムは短期的に見れば、業務量の多さやレスポンスの速さにつながります。また長時間働くことが、熱心さや頑張りの証として解釈されることもあるため、ワーカホリズムが賞賛される風潮は根強くあります。
ワーカホリズムという強迫的行動が賞賛される組織では、自分が苦痛を感じることをしている場合に大きな拍手喝采を受けるということになります。そうすると、従業員は「もっとやらなければいけない」「すべてをやらなければいけない」と自分を追い込むことになります。
すべてを背負い込まずに、自分の仕事と他者の仕事を明確に区別したり、他者の気分や評価に左右されずに自分の気持ちを尊重するといった、境界線を引くことが大切です。そこで、従業員の状況にいち早く気づいて対応しやすい、上司が行える共依存対策を紹介します。
- 上司は部下に対して、自分が使える時間や労力に境界線を引くことを奨励し、限界に対する意識を持つように指導する。
- 何でも引き受けてしまうことを防止するために、1日の計画を立てる際に、自分の予定に組み込む周囲からのニーズの内容と数を厳選するよう指導する。
- 仕事が殺到しているときには、その瞬間の自分の感情や視点から離れてしまいやすくなる。上司は、部下が自分の感情や、その感情を引き起こした自分の視点について落ち着いて考えるための時間を確保する。
- 部下が仕事を委譲したり、都合の良いタイミングで仕事を行うことができるように、職業人としての自分像を達成可能なものか問い直し、改善する機会になる面談を実施する。
職場での助け合いや貢献は、本来、組織を支える大切な姿勢です。しかし、その支援行動が知らぬ間に共依存という形で個人と組織の健全性を蝕む危険があることを、私たちは見過ごすわけにはいきません。
相手のためを思いつつも、自分の感情を尊重し、自分の限界を適切に把握して、健全な距離を保つ。そのような支援のあり方こそが、持続可能で健全な職場づくりの土台となります。支援行動を見直すことは、組織と自分を守ることでもあります。支援とは何か、貢献とは何か、そして自分や周囲の人の行動の背後にある動機とは何かを、立ち止まって考えることが求められます。
脚注
[1] McMillan, J. J., & Northern, N. A. (1995). Organizational codependency: The creation and maintenance of closed systems. Management Communication Quarterly, 9(1), 6-45.
[2] Springer, C. A., Britt, T. W., & Schlenker, B. R. (1998). Codependency: Clarifying the construct. Journal of Mental Health Counseling, 20(2), 141.
[3] Poulin, M. J., Brown, S. L., Dillard, A. J., & Smith, D. M. (2013). Giving to others and the association between stress and mortality. American journal of public health, 103(9), 1649-1655.
[4] Dunn, E. W., Aknin, L. B., & Norton, M. I. (2008). Spending money on others promotes happiness. Science, 319(5870), 1687–1688.
[5] Clark, D. J. (2020). Escaping the Drama Triangle: Strategies for Successful Research Administration from the Psychology of Codependence. The Journal of Research Administration, 51(2), 84–102.
[6] 脚注1(McMillan & Northern, 1995)と同じ
[7] 脚注1(McMillan & Northern, 1995)と同じ
[8] 脚注2(Springer et al, 1998)と同じ
[9] 脚注5(Clark, 2020)と同じ
[10] 心理的安全性については、当社の別のコラムでまとめております。適宜参照ください;
執筆者
 西本 和月 株式会社ビジネスリサーチラボ アソシエイトフェロー
西本 和月 株式会社ビジネスリサーチラボ アソシエイトフェロー
早稲田大学第一文学部卒業、日本大学大学院文学研究科博士前期課程修了、日本大学大学院文学研究科博士後期課程修了。修士(心理学)、博士(心理学)。暗い場所や狭い空間などのネガティブに評価されがちな環境の価値を探ることに関心があり、環境の性質と、利用者が感じるプライバシーと環境刺激の調整のしやすさとの関係を検討している。環境評価における個人差の影響に関する研究も行っている。