2025年11月14日
真面目な人が過ちを犯す理由:「道徳的アイデンティティ」の科学(セミナーレポート)
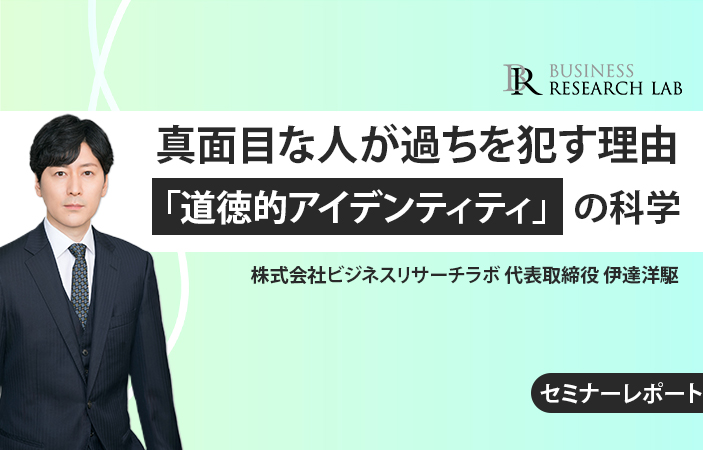
ビジネスリサーチラボは、2025年9月にセミナー「真面目な人が過ちを犯す理由:『道徳的アイデンティティ』の科学」を開催しました。
企業の持続的な成長に、倫理的な組織風土が不可欠であることは論を待ちません。しかし、コンプライアンス研修を重ね、行動規範を徹底しても、なぜ現場での不祥事や倫理的な問題は後を絶たないのでしょうか。ルールによる統制だけで、人の行動を導くことは難しいのかもしれません。
そこで重要になるのが、従業員一人ひとりの心の内側にある「自分は道徳的でありたい」という自己認識、すなわち「道徳的アイデンティティ」です。
この内なる道徳観は、善行を促す力を持つ一方で、時として私たちの直感に反する形で、不正行為の引き金にもなり得ることが近年の研究で明らかになってきました。善かれと思っての行動が、なぜ意図せず組織を傷つける結果を招くのか。その背景には、人の道徳性が持つ、複雑で多面的なメカニズムが存在します。
本セミナーでは、この「道徳的アイデンティティ」に関する最新の科学的知見を基に、人と組織の倫理について考察しました。
なぜ真面目な従業員が過ちをおかすのか、リーダーの倫理観はどのように部下へ伝わるのか。その心の働きを理解することは、形骸化しない倫理教育の設計や、心理的安全性の高い職場づくり、そして実効性のあるリーダーシップ開発において、新たな視点とヒントをもたらすはずです。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
はじめに
真面目で誠実、周囲からの信頼も厚い。そんな人物が、なぜ時に私たちの想像を裏切るような過ちを犯してしまうのでしょうか。人事の皆さんも、従業員の倫理観の育成やコンプライアンス遵守には日々心を配られていることと思います。実は、人が自らを「道徳的だ」と強く信じる心、すなわち「道徳的アイデンティティ」は、気高い善行の源泉にも、そして不正の引き金にもなりうる、両刃の剣です。
本講演では、この複雑で奥深い道徳的アイデンティティという心の仕組みを、科学的な知見から多角的に解き明かし、組織における倫理観を育むための視点を提供します。
道徳的アイデンティティの力
道徳的アイデンティティとは、思いやり、公正さ、正直さといった道徳的な価値観を、自分という人間の中心的なアイデンティティとして捉えている度合いを指します。この内なる道徳観が強い人は、一般的に誠実で、他者への配慮に富んだ人物と見なされ、自らの良心に恥じない行動を自然と選択する傾向があります。この力は、様々な場面でポジティブな影響を及ぼします。
人間の心には、家族や同胞といった「身内」を優先し、自分とは異なる集団を後回しにする作用が備わっています。しかし、道徳的アイデンティティが強固な人々は、この内と外を分ける心の壁を乗り越えることができます。ある調査では、道徳的アイデンティティが強い人ほど、見知らぬ外国人や異なる宗教を信じる人々に対しても、助けるべき道徳的な義務を感じる度合いが高いことが示されました[1]。
さらに、2001年のアメリカ同時多発テロ事件後という、社会全体が特定の集団への緊張感を抱えていた時期に行われた実験では、敵対視されがちなアフガニスタン難民への人道支援に対しても肯定的な評価を下し、実際に寄付も多く行っていました。最も困難な問い、すなわち軍事的な報復によって生じるかもしれない民間人の犠牲を何人まで許容できるか、という質問に対しても、許容できる犠牲者数を少なく見積もり、むしろ加害者を「許す」という行為に高い道徳的価値を見出すなど、その倫理観は一貫していました。
この内なる道徳観は、ストレスの多い職場の最前線でも緩衝材としての役割を果たします。コールセンターの従業員を対象とした多国籍調査では、顧客から理不尽な要求や暴言といった不公正な扱いを受ける頻度が高いほど、仕返しとして意図的に対応を遅らせるなどの報復行動に走りやすいことが明らかになりました[2]。しかし、直属の上司が部下の話を公正に聞き、尊重する姿勢を示すことで、この負の連鎖は大幅に抑制されました。
特に注目すべきは、従業員本人の道徳的アイデンティティが強い場合です。たとえ顧客と上司の両方から不公正な扱いを受けるという最悪の状況に置かれたとしても、報復行動にはほとんど手を染めませんでした。個人の内なる道徳観が、外部からの否定的な刺激に対する強力な「倫理的ブレーキ」として、文化の違いを超えて機能していたということです。
さらに、この道徳観は、人が自身の尊厳を脅かされるような窮地に立たされた時の砦ともなります。アイデンティティ理論では、人は「こうありたい自分」という理想像と現実の自分との間にズレが生じると、その不快感を解消しようと行動すると考えられています。ある実験で、学生たちに模擬試験を受けさせたところ、成績が悪く、「有能な学生」という自己像を維持できなくなった学生ほど、カンニングという不正行為に手を出しやすい傾向が見られました[3]。
しかし、事前に測定された道徳的アイデンティティが強い学生に限っては、たとえ試験の成績が悪くても、カンニングを思いとどまりました。これは、「有能な自分」という一つのアイデンティティが脅かされた時、「道徳的な自分」というもう一つの大切なアイデンティティを固く守ろうとすることで、自己全体の尊厳を維持しようとする心の働きによるものです。能力という自信が揺らいだ時、道徳性が不正への最後の防波堤として機能するという強さが示されたのです。
二つの道徳観と、その動かし方
道徳的アイデンティティは、人の行動に深く関わっていますが、その性質は一様ではありません。詳細な研究により、このアイデンティティは大きく二つの異なる側面から構成されていることが明らかになりました。
一つは、道徳的な価値観を自己の核として心から受け入れている「内面化」です。これは、誰が見ていなくても、自らの信念として善行を尊ぶ、いわば「本物」の道徳心です。もう一つは、道徳的な人間であることを行動や言動を通して他者に示し、良い評価を得たいという欲求である「顕示化」です。こちらは「見せかけ」の道徳心とも言え、この二つの動機は、時に全く異なる、あるいは正反対の結果を生み出します。
初めに、自身の信念として深く根差した「内面化」の側面は、実際の善行と強く、そして一貫して結びついています。ある研究では、言葉の連想を利用した心理テスト(IAT)で、「私」という言葉と「思いやり」などの道徳的な言葉を、人々が無意識レベルでどれだけ強く結びつけているかを測定しました[4]。その結果、この内面化の度合いが高い人ほど、無意識下での結びつきが強いことが示され、この特性が建前ではない、心の深層に根差したものであることが裏付けられました。
そして、この内なる道徳観は、実際の行動として確かに表れます。大学の卒業生を対象とした調査では、内面化の得点が高い人ほど、過去にボランティア活動を経験していることが分かりました。さらに、高校で実施されたフードドライブ(食料品の寄付活動)を秘密裏に観察した研究では、内面化の得点が高い生徒ほど、実際に寄付を行う確率も、寄付する食料品の量も多いことが確認されています。
一方で、他者から道徳的に見られたいという「顕示化」の欲求が強い場合、その影響は状況によって異なります。コールセンター従業員を対象とした研究では、顧客から不公正な扱いを受けた際の反応に、この違いが現れました[5]。道徳観が「内面化」されている従業員は、報復行為が自らの信念に反するため、強い「ブレーキ」として機能しました。
しかし、「顕示化」の欲求が強い従業員は、不公正な扱いを受けると、自らを「不正を許さない正義の執行者」と位置づけ、不当な顧客を罰することが自らの道徳性の高さを証明する行為であると解釈しました。その結果、彼らはかえって積極的に報復行動を行ったのです。この「見せかけ」の道徳心は、攻撃的な行動を正当化し、加速させる危険な「アクセル」へと変貌してしまいました。
これらの異なる動機を持つ人々を、どのように善い方向へ導けばよいのでしょうか。他者からの称賛は、特に外面を気にする人々に効果的です。ある実験では、ボランティア活動への貢献がウェブサイトで公に称賛される状況を設定しました[6]。すると、もともと内なる信念が弱い人ほど、「良い人に見られたい」という顕示化の欲求が強い場合に、ボランティアへの参加率が顕著に上昇しました。他者の視線という外部からの刺激が、行動のエネルギーとなったのです。
とはいえ、人の内面にある道徳観がどちらのタイプかを見分けるのは困難です。本人ですら無意識な場合も多く、上司や同僚が正確に判断することはほぼ不可能です。そこで、「見分けようとする」のではなく、「どちらのタイプにも響く、あるいは悪影響が少ないアプローチから始める」という発想に転換することが現実的です。
具体的には、「まず個人的に行動の背景にある価値観を褒め、その後、本人の許可を得てから公に共有する」という二段階のアプローチが有効です。まず一対一の場で、行動の裏にある誠実さや思いやりといった価値観を承認し、感謝を伝えます。これは内面化タイプに深く響き、顕示化タイプにとってもポジティブなフィードバックとなります。
その上で、本人の意思を確認し、「あなたの行動はチームの素晴らしい学びになります」と伝え、チームミーティングなどで共有することを提案します。顕示化タイプは他者から評価される機会を喜び、内面化タイプは望まないかもしれませんが、その意思を尊重する姿勢が誠実さとして伝わります。この方法は、相手を不快にさせるリスクを最小限に抑えながら、効果的に承認を伝えることができる手法と言えるでしょう。
リーダーの道徳性はいかに伝わるか
リーダーの倫理観は、組織の空気を決定づける要素です。公正で誠実なリーダーのもとでは、部下も安心して業務に邁進できます。しかし、そのリーダーの道徳性は、具体的にどのようにして部下に伝わり、影響を与えていくのでしょうか。
このプロセスを解明した研究は、リーダーが持つべき二つの異なる倫理的特性を明らかにしました[7]。一つは、これまで見てきた自己認識としての「道徳的アイデンティティ」。もう一つは、日々の出来事の中に倫理的な側面を敏感に察知するアンテナの感度、すなわち「道徳的注意性」です。これらの伝わり方には違いがあることが示されています。
中国の企業で働くリーダーとその部下を対象に、時間差を設けて行われた調査によると、リーダーの道徳的アイデンティティ、すなわち「自分は道徳的な人間だ」という内なる信念は、それだけでは部下に直接届きません。その信念が、部下の意見に真摯に耳を傾けたり、評価や報酬の決定において公正な判断を下したりといった、目に見える具体的な「倫理的行動」として表現されて初めて、部下はその姿を手本とし、自らの道徳観を形成していきます。リーダーの道徳的な人柄が部下の心に影響を与えるには、「行動」という、誰もが理解できるものへの翻訳が不可欠です。
一方で、リーダーの「道徳的注意性」、すなわち「何に気を配り、何を大切にしているか」という姿勢は、より直接的に部下に伝播することが分かりました。リーダーが日頃から「この判断は、短期的な利益は生むが、顧客の信頼を損なわないか」「この業務プロセスは、一部の従業員に不公平な負担を強いていないか」といった点に注意を払う姿勢は、会議での発言や日々の会話の端々から、あたかも伝染するかのように部下の注意のアンテナを同じ方向へと向かわせます。リーダーが示す価値観が、組織の非公式な規範として浸透していくプロセスと言えるでしょう。
これらの研究知見から、管理職は二つの側面からアプローチすることが重要になります。一つは、「道徳的アイデンティティを行動で示す」ことです。心の中で思っているだけでなく、部下の評価や業務の割り振りで公平な判断を下し、その理由を明確に説明する、部下と交わした小さな約束も必ず守る、チームの失敗が起きた際には部下のせいにせず自らの責任として受け止める、といった一貫した行動を通して、誠実さを体現する必要があります。
もう一つは、「道徳的注意性を日常的に伝播させる」ことです。特別な行動でなくとも、日々のコミュニケーションがその舞台となります。「このやり方は長期的な信頼を損なわないか」といった倫理的な問いかけを意識的に行ったり、部下が正直にミスを報告した際に、結果を責めるのではなくその誠実な姿勢を具体的に褒めたりすることで、リーダーが何を大切にしているかという「空気感」が醸成されます。部下がコンプライアンス上の懸念を示した際に、それを面倒がらずに真摯に耳を傾ける姿勢も、チーム全体の倫理観を高める上で効果的です。
「個人への称賛」から「物語の共有」へ
他者の卓越した善行に触れたとき、私たちの心には胸が温かくなるような、畏敬の念を伴うポジティブな感情が生まれることがあります。例えば、銃乱射事件の被害者コミュニティが犯人家族を赦し、支援まで申し出たという実話に触れた時のような感動です。この特別な感情は「モラル・エレベーション」と呼ばれ、人を利他的な行動へと駆り立てる力を持っています。ある実験では、この感動を強く経験する人ほど、その後の慈善団体への寄付額が実際に増加することが示されました[8]。
興味深いことに、このモラル・エレベーションを特に強く感じるのは、道徳的アイデンティティの「内面化」が進んでいる、つまり内なる道徳観が強い人々です。彼ら彼女らにとって、他者の善行は自らの価値観と共鳴し、「自分も誰かのために何かをしたい」という純粋な動機を内側から引き出します。
この心の仕組みを考慮すると、組織が取るべき賢明なアプローチは、特定の個人をヒーローとして称賛することから、「善行の物語(ストーリー)を共有する」ことへとシフトすることです。
「物語の共有」というアプローチは、多くの利点を持ちます。まず、内なる道徳観が強い人々を最も自然な形で動かします。彼ら彼女らにとっては、個人への過剰な称賛よりも、善行の事実そのものが心を最も揺さぶり、自発的な行動のきっかけとなります。また、外面を気にする人々にとっても、どのような行動が組織で評価されるのかというモデルケースとなり、望ましい行動の基準を穏やかに示すことができます。
何よりこのアプローチは、社員が「内面化タイプ」か「顕示化タイプ」かを見極める必要がなくなるというメリットがあります。物語は、聞く人それぞれの価値観のフィルターを通して、異なる形で心に響き、組織全体にポジティブな波紋を広げていきます。
具体的なアクションとしては、組織内で善行が自然と発見され、共有される仕組みづくりが重要です。例えば、チームミーティングの冒頭数分を使い、「この一週間で目にした、誰かの素敵な行動とその理由」を目撃者が発表する時間を設けます。発表者が本人ではなく目撃者であることで、感動の伝播、すなわちモラル・エレベーションの連鎖が期待できます。
また、経営層や管理職が自ら「ストーリーテラー」となることも効果的です。「先日、ある社員がお客様のためにこんな行動をとってくれました。私はその話を聞いて、私たちが大切にすべき価値観がここにあると、胸が熱くなりました」というように、リーダー自身の感動を伝えることが、部下の心を動かします。
こうした取り組みは、特定の個人を表彰するのではなく、「この組織では誠実な行動や他者への貢献が自然と尊ばれる」という文化を育み、社員一人ひとりの内なる道徳心を刺激することとなるでしょう。
道徳性の罠に注意
これまで道徳的アイデンティティが持つポジティブな側面を見てきましたが、この内なる道徳観は、時として人を危険な「罠」に陥れることがあります。高い道徳心を持つことが、かえって不正行為の引き金になってしまうという、にわかには信じがたい心のメカニズムが存在します。この逆説を理解することは、組織の倫理リスクを管理する上で重要です。
その一つが、強いインセンティブ、特に成果報酬との危険な関係です。ある交渉実験では、参加者に採用担当者の役を演じてもらい、できるだけ低い給与で応募者と合意できれば報酬がもらえる、という状況が設定されました[9]。その際、交渉を有利に進めるための「この求人は短期間で打ち切られる」という内部情報が与えられます。
その結果、驚くべきことに、もともと道徳的アイデンティティが高いと自己評価していた人ほど、成果報酬を提示された場合に、この不利な情報を隠したり嘘をついたりして、相手を欺く傾向が強まりました。
研究者によれば、これは道徳性が高い人にとって、「道徳的であること」と「利益を追求すること」という二つの重要な価値が心の中で激しく衝突するためです。この強い内的な葛藤から逃れるため、一時的に道徳観を脇に追いやり、「これはビジネスの交渉だから」と自己の行動を正当化し、非倫理的な選択肢に飛びついてしまうのです。
もう一つの罠は、その人の「判断基準」との組み合わせによって生じます。道徳的な判断には、ルールや規範を絶対視する「形式主義」と、行為がもたらす結果の良し悪しを重視する「結果主義」という二つのスタイルがあります。
大学生を対象とした調査では、「良い成績を取るという目的のためなら」と考える結果主義の学生ほど、カンニングの経験が多いことが分かりました[10]。そしてこの関係は、「自分は公正で思いやりのある人間だ」と強く信じている、道徳的アイデンティティが高い学生において、より顕著だったのです。
高い道徳意識が、不正を思いとどまらせるブレーキになるのではなく、自らが採用した「結果が良ければ手段は問わない」という判断を、一貫性を保つために忠実に実行させるためのアクセルとして機能してしまったことを意味します。
これらの側面を踏まえると、私たちは「自分は道徳的だ」という自己評価を過信してはなりません。「自分も間違う可能性がある」という謙虚さを持ち、自分の判断を客観的に見つめ直す習慣が重要です。
特に、大きな成果報酬が絡む時や、「会社のため」「チームのため」といった大義名分が掲げられる時には、細心の注意が必要です。強いプレッシャーを感じた時こそ危険信号と捉え、一度冷静になる、あるいは信頼できる第三者に相談する、そして「目的は手段を正当化するのか」と自問自答する癖をつけることが、道徳性の罠から個人と組織を守るために不可欠です。
おわりに
ここまで見てきたように、「道徳的アイデンティティ」は、人を気高い善行に導く力強いエンジンであると同時に、予期せぬ不正を引き起こす危険な罠ともなりうる、複雑な両刃の剣です。真面目な人が過ちを犯す背景には、このような本人の意図とは裏腹の心のメカニズムが潜んでいます。
従業員の倫理観を個人の資質や意識の問題としてのみ捉えるのではなく、誰もが健全な判断を下せるような組織文化を育むことの重要性を、改めて認識していただければ幸いです。倫理的な行動の「物語」を共有し、健全な葛藤についてオープンに語り合える職場環境が、この両刃の剣を正しく導く道筋となるでしょう。
Q&A
Q:「道徳的アイデンティティ」の高さは、どのようにして測定しているのでしょうか。
道徳的アイデンティティとは、「自分は誠実な人間だ」といった、その人自身の内面的な自己認識、つまり自己概念が核となります。他者からの評価や行動観察だけでは、その人の内面にある信念までを知ることは困難です。そのため、測定は例えばアンケートを用いて行われます。
Q:高い道徳心を持つ人ほど、成功報酬が絡むと不正をしやすいというのは、道徳心が低い人の方が欺かないということですか。
必ずしも「道徳心が低い人の方が欺かない」というわけではありません。この研究が示唆しているのは、普段から倫理観を強く意識している人ほど、大きな成功報酬を前にすると、「道徳的でありたい自分」と「利益を得たい自分」との間で葛藤を経験する、という点です。そして、この強い葛藤を乗り越えて自らの信念を曲げる際には、「これほどの思いをしてまでやるのだから」という心理的な正当化が働き、かえって行動がエスカレーションしてしまいます。結果として、不正に手を染めてしまう可能性がある、という逆説的な現象を指摘しています。
Q:道徳的アイデンティティが高い社員は、顧客からの理不尽な要求にも耐えやすいとのことですが、それは精神的に燃え尽きてしまう「バーンアウト」のリスクを抱えやすいということではないでしょうか。
重要なご指摘であり、まさにおっしゃる通りです。誠実で責任感の強い社員ほど、理不尽な要求に対しても「期待に応えなければ」と一人で抱え込み、過剰なストレスを溜めてしまうことが考えられます。組織が道徳性の高さを単なる「便利なストレス耐性」として利用するようなことがあってはなりません。
むしろ彼らを守る仕組みを構築すべきでしょう。例えば、上司との定期的な面談で安心して本音を吐き出せる環境を作ったり、理不尽な要求は個人の問題ではなく組織全体で対応するという姿勢を示したりすることが、貴重な人材のバーンアウトを防ぐ上で不可欠です。
Q:あまりに崇高すぎる善行の話は、かえって「自分には真似できない」と従業員を無力にさせることはないでしょうか。
その通りで、どのような物語を共有するかという「内容の選択」が重要になります。超人的な英雄の物語は、感銘は与えるかもしれませんが、共感を呼びにくく、「あれは特別な人の話だ」と距離を置かれてしまい逆効果になることもあります。
重要なのは、人々が「自分ごと」として捉えられる「共感可能性」です。日常業務の中でのささやかな勇気や、地道な誠実さが報われた話など、誰もが実践し得る身近な物語が、「自分も明日から試してみよう」という前向きで具体的な行動を促す上で有効です。
Q:会社の公式方針に、従業員が自分の道徳観から賛同できない場合はどうすればよいのでしょうか。
多くの組織が直面する難しい問題かもしれません。大前提として、「全従業員が会社の方針に全面的に同意することを期待すべきではない」という健全な姿勢が重要です。その上で、意見が異なる従業員の存在を認め、その価値観に敬意を払うこと。そして、なぜその方針を採るのか、意思決定のプロセスや背景にある理由を丁寧に説明する責任が組織にはあります。
方針に賛同しないことを理由に不利益な扱いをすることは、信頼を損なう「道徳の濫用」であり、避けなければならない事態です。多様な価値観を尊重し、対話を続けることが組織の健全性を保ちます。
脚注
[1] Reed II, A., and Aquino, K. (2003). Moral identity and the expanding circle of moral regard toward out-groups. Journal of Personality and Social Psychology, 84(6), 1270-1286.
[2] Skarlicki, D. P., van Jaarsveld, D. D., Shao, R., Song, Y. H., and Wang, M. (2016). Extending the multifoci perspective: The role of supervisor justice and moral identity in the relationship between customer justice and customer-directed sabotage. Journal of Applied Psychology, 101(1), 108-121.
[3] Stets, J. E., and Carter, M. J. (2011). The moral self: Applying identity theory. Social Psychology Quarterly, 74(2), 192-215.
[4] Aquino, K., and Reed, A. II. (2002). The self-importance of moral identity. *Journal of Personality and Social Psychology, 83(6), 1423-1440.
[5] Skarlicki, D. P., van Jaarsveld, D. D., and Walker, D. D. (2008). Getting even for customer mistreatment: The role of moral identity in the relationship between customer interpersonal injustice and employee sabotage. Journal of Applied Psychology, 93(6), 1335-1347.
[6] Winterich, K. P., Aquino, K., Mittal, V., and Swartz, R. (2013). When moral identity symbolization motivates prosocial behavior: The role of recognition and moral identity internalization. Journal of Applied Psychology, 98(5), 759-770.
[7] Zhu, W., Trevino, L. K., and Zheng, X. (2016). Ethical leaders and their followers: The transmission of moral identity and moral attentiveness. Business Ethics Quarterly, 26(1), 95-115.
[8] Aquino, K., McFerran, B., and Laven, M. (2011). Moral identity and the experience of moral elevation in response to acts of uncommon goodness. Journal of Personality and Social Psychology, 100(4), 703-718.
[9] Aquino, K., Freeman, D., Reed II, A., Lim, V. K. G., and Felps, W. (2009). Testing a social-cognitive model of moral behavior: The interactive influence of situations and moral identity centrality. Journal of Personality and Social Psychology, 97(1), 123-141.
[10] Reynolds, S. J., and Ceranic, T. L. (2007). The effects of moral judgment and moral identity on moral behavior: An empirical examination of the moral individual. Journal of Applied Psychology, 92(6), 1610-1624.
登壇者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。






