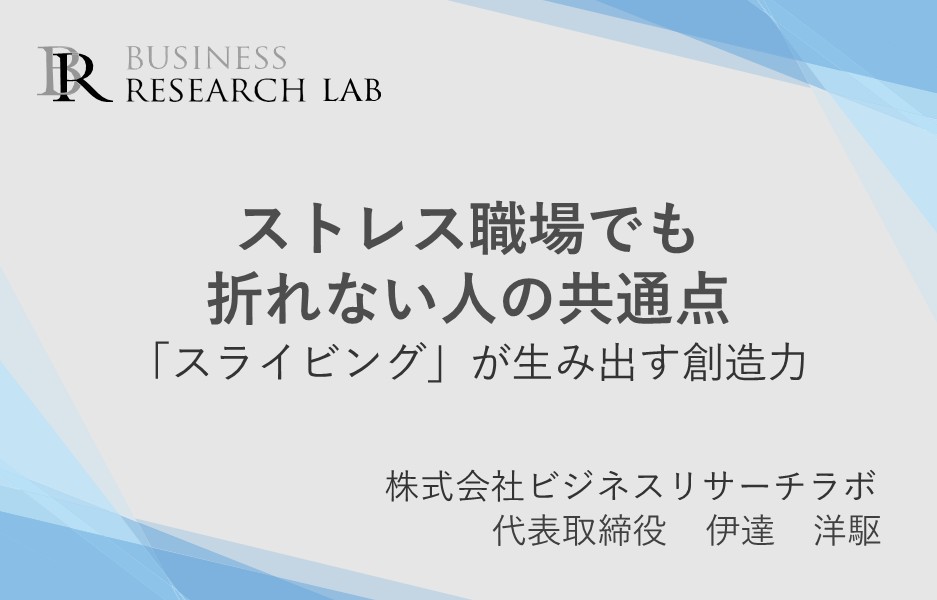2025年11月13日
ストレス職場でも折れない人の共通点:「スライビング」が生み出す創造力
私たちは仕事を通じて、多くの時間を費やし、日々の生活の糧を得ています。その中で、「高い成果を出し続けたい」という願いと、「心身ともに健やかでありたい」という願いは、多くの働く人が共通して抱くものかと思います。とはいえ、この二つを両立させることは、決して簡単なことではありません。一方を求めればもう一方が犠牲になり、高い業績の裏側で心がすり減っていく、あるいは、心身の安寧を保つために仕事への情熱を抑えなければならない。そんなジレンマを感じたことがある人は少なくないはずです。
では、燃え尽きることなく、むしろ成長しながら、持続的に高いパフォーマンスを発揮するという、理想的に見える状態は本当に実現不可能なのでしょうか。この問いに、一つの光を当てる考え方があります。それが「スライビング(Thriving)」という概念です。
スライビングとは、仕事において「活力」に満ちあふれている状態と、「学習」し続けている状態が、同時に満たされている心理的なあり方を指します。生き生きとしたエネルギーに満ち、同時に、新しい知識やスキルを身につけ、成長している実感がある。この二つの歯車が噛み合ったとき、人はまるでエンジンとナビゲーションを両方搭載した車のように、力強く進み続けることができるのかもしれません。
本コラムでは、スライビングという概念が、働く人々のパフォーマンスや心身の健康、創造性にどのような関わりを持つのかを、いくつかの科学的な知見を紐解きながら、多角的に探求していきます。
スライビングが高成果と低燃え尽きを同時に実現
働く人々が高い成果を上げ続けることと、心身の健康を維持することは、しばしば対立するものとして捉えられます。両者を車の両輪のように機能させることはできないのでしょうか。この問いを探求する中で見出されたのが、「スライビング」という心理状態です。これは、ただ仕事が楽しい、満足しているといった静的な幸福感とは一線を画し、より動的で成長を志向するあり方を捉えようとするものです。
スライビングは、「活力」と「学習」という二つの要素が同時に高いレベルにある状態として定義されます。ここで言う「活力」とは、仕事に対して生き生きとしたエネルギーを感じ、情熱を持って取り組める状態を指します。一方の「学習」とは、新しい知識やスキルを習得し、自分自身が成長・向上しているという実感を持つ状態です。
この二つの要素は、どちらか一方だけでは不十分だと考えられています。例えば、活力だけが高くても、学びによる成長がなければ、いずれそのエネルギーは空転し、燃え尽きにつながりかねません。逆に、学習意欲はあっても、それを実行に移すための活力がなければ、行動は伴わず、やがて情熱も冷めてしまうでしょう。活力という現在のエネルギーと、学習という未来への投資が組み合わさることで、人は持続的に発展していくことができます。
この考え方の妥当性を確かめるため、ある大規模な調査が行われました[1]。この調査は、七年という長い歳月をかけて、事務職から現場作業員まで、多様な職種に従事する1200人以上の人々を対象に実施されました。調査では、個々人のスライビングの度合いを測定するとともに、上司による業績評価、本人が感じる燃え尽きの度合い、仕事への満足度、組織への愛着、欠勤状況、さらには医療費といった、多岐にわたる指標が収集されました。
分析の結果、スライビングを経験していると評価された従業員群は、そうでない従業員群と比較して、上司が評価した総合的なパフォーマンスが高いという結果になりました。これは、スライビングが本人の主観的な感覚だけでなく、他者から客観的に評価される成果とも結びついていることを物語っています。
心身の健康面では、より顕著な違いが見られました。スライビングしている人々は、そうでない人々と比べて、仕事が原因で心身が消耗しきる「燃え尽き」の状態にあると自己報告する割合が低かったのです。スライビングが精神的な疲弊を防ぐ要因として機能している可能性を示唆しています。組織に対する愛着や忠誠心を示す組織コミットメント、現在の仕事に対する満足度も、それぞれ高い値を示しました。
病気などによる欠勤日数や、会社が負担する医療コストも低いという結果も得られており、スライビングが個人の健康状態や、ひいては組織の経済的な負担にも良好な関わりを持つことがうかがえます。
疲弊する関係は業績を下げるがスライビングが防ぐ
職場は、一人で黙々と作業に打ち込むだけの場所ではありません。上司、同僚、部下、あるいは他部署の担当者など、多くの人々との関わり合いの中で仕事は進んでいきます。そうした人間関係は、時に私たちに刺激や活力を与えてくれる一方で、知らず知らずのうちに私たちの心を疲弊させ、エネルギーを奪っていくこともあります。先ほどは、個人の内面的な状態であるスライビングが、業績や健康に良い働きをすることを見てきました。では、こうした職場における他者とのネガティブな関係性に対して、スライビングはどのように作用するのでしょうか。
この疑問に答えるため、二つの異なる職場を舞台にした調査が実施されました[2]。研究者たちが光を当てたのは、活力を与えてくれる関係の裏側に存在する、人を精神的に疲れさせる関係です。人を疲れさせる関係性が個人の業績を実際に低下させるのか、そして、スライビングという個人の内なる力が、そのマイナスの作用に対する盾となりうるのかを検証することが、この調査の目的でした。
一つ目の調査は、ある米国企業のIT部門で働く161人を対象に行われました。参加者には、職場の同僚全員の名簿が提示され、一人ひとりについて「その人と関わると、自分のエネルギーが消耗すると感じるか」を評価してもらいました。この評価に基づき、各個人が消耗する関係を何人持っているかが算出されました。この関係の数と、調査期間を挟んだ前後、合計一年以上にわたる期間の人事評価や上司による業績評価との関連が分析されました。分析の結果、人を疲れさせる関係の数が多い従業員ほど、その後の業績評価が低くなるという関連が確認されました。
二つ目の調査は、より規模を広げ、大手コンサルティング企業に勤める439人を対象として行われました。こちらでは、まず各参加者に、仕事で頻繁に関わる人物を最大50人まで挙げてもらい、それらの人々との関係が自身を疲れさせるものかどうかを評価してもらいました。その2週間後、今度は参加者自身のスライビングの度合いを、専用の質問票を用いて測定しました。そして、調査から5か月が経過したのち、会社が公式に記録している人事評価のデータと、これらの測定結果との関連性が分析されました。
ここでも、一つ目の調査と同様に、人を疲れさせる関係の数が多い人ほど、業績が「期待未達」と評価される確率が高まるという結果が得られました。しかし、分析を進めると、個人のスライビングの度合いが、このネガティブな連鎖を断ち切る上で、ある種の緩衝材のような働きをしていることが見えてきました。
スライビングの度合いが高い人々の間では、たとえ人を疲れさせる関係の数が増えたとしても、業績が「期待未達」に陥る確率の上昇度合いが、スライビングの度合いが低い人々と比べて緩やかでした。スライビングしている人は、ネガティブな人間関係から受けるダメージに対して、ある程度の抵抗力を持っていることがうかがえます。
これらの結果は何を物語っているのでしょうか。人を疲れさせる人間関係は、私たちの認知的な資源、例えば集中力や注意力を散漫にし、仕事へのモチベーションを削ぎ、精神的なエネルギーを枯渇させることで、実際の業務遂行能力を低下させていると考えられます。しかし、スライビングという状態にある人は、このダメージを軽減するための「心理的な資源」を、自らの内に蓄えているのかもしれません。
メタ分析でスライビングが創造性を独自に高める要と判明
これまでに、スライビングという心理状態が、個人の業績を高め、燃え尽きを防ぐ働きを持つこと、そして、職場のネガティブな人間関係がもたらす悪影響を和らげる緩衝材としての側面を持つことを見てきました。しかし、ここで一つの疑問が浮かびます。スライビングという概念は、これまでによく知られてきた他のポジティブな心理状態、例えば、仕事に対する熱意や没頭を意味する「ワーク・エンゲージメント」や、日々の「ポジティブな感情」と、一体何が違うのでしょうか。
この問いに答えるため、ある研究者たちは「メタ分析」という手法を用いました[3]。メタ分析とは、特定のテーマに関して過去に行われた数多くの研究結果を、世界中から集め、それらを統計的に統合することで、より信頼性が高く、全体像を捉えた結論を導き出す手法です。今回取り上げる研究は、スライビングに関する73件の研究、総計21,739人分のデータを統合した大規模なものです。
このメタ分析の目的は、大きく分けて二つあります。一つは、どのような要因がスライビングを高め(先行要因)、スライビングがどのような結果をもたらすのか(結果変数)について、これまでの研究で得られた知見を整理し、その関連性の強さを定量的に示すこと。もう一つは、スライビングが、先ほど挙げたワーク・エンゲージメントやポジティブ感情といった類似の概念と比べたときに、それらだけでは説明できない、独自の価値を持っているのかどうかを明らかにすることでした。
分析の結果、スライビングを育む要因が明らかになりました。上司からの支援や、組織全体が従業員を大切にしているという感覚、職場の同僚からの助け、そして礼儀正しさが尊重される文化などが、人々がスライビングする上で追い風となることが、多くの研究に共通して見られる強い関連性として確認されました。
スライビングがもたらすものに目を向けると、仕事への満足感や組織への愛着、そして燃え尽きの低減といった、心身の健康やポジティブな態度と強く結びついていることが改めて裏付けられました。そして、パフォーマンスに関する分析では興味を引く結果が得られました。スライビングは、日々の決められた業務をきちんとこなす「タスクパフォーマンス」や、自分の職務範囲を超えて他者を助ける「組織市民行動」とも、もちろん正の関連が見られました。
しかし、それら以上に、ひときわ強い結びつきが見られたのが、「創造的なパフォーマンス」だったのです。新しいアイデアを生み出したり、革新的な方法を試みたりする行動とスライビングとの間の関連性は、他のどのパフォーマンス指標よりも強いものでした。
「創造性」との強い結びつきは、スライビングの独自性を解き明かす鍵となります。研究者たちは、ある従業員のワーク・エンゲージメントの高さや、ポジティブな感情の多さの影響を計算上取り除いたとしても、なおスライビングがその人の創造性を予測する力が残るかどうかを検証しました。その結果、スライビングは、仕事への熱意やポジティブな気分だけでは説明しきれない、創造性を高めるための独自の何かを持っていることが示されました。
スライビングの何が、これほどまでに創造性と強く結びつくのでしょうか。そのメカニズムは、スライビングを構成する二つの要素、「活力」と「学習」に立ち返ることで理解できます。「活力」という精神的なエネルギーは、従業員が現状に安住せず、新しいことに挑戦するためのガソリンとなります。失敗を恐れずに未知の領域に踏み込み、試行錯誤を繰り返すためには、心理的なエネルギーが不可欠です。一方、「学習」という要素は、創造性の源泉となる知的な好奇心や探求心を刺激します。既存の知識や常識にとらわれず、新しい視点や情報を積極的に取り入れ、それらを自在に組み合わせることで、独創的なアイデアは生まれます。
スライビング尺度で活力と学習が成果と燃え尽き低減を示した
これまでのところで展開してきたスライビングに関する議論はすべて、この目には見えない心理的な状態を、何らかの方法で客観的に測定できる、という大前提の上に成り立っています。では、個人の内面で起きている「活力」と「学習」の実感は、どのようにして信頼できる「尺度」として捉えられ、科学的な分析の俎上に載せられるようになったのでしょうか。スライビングという概念の根幹を支える、その測定方法が開発され、尺度の信頼性や妥当性が検証されていくプロセスを追うことを通じて、この概念の基盤を理解していきたいと思います。
ある研究チームが着手したのは、この「スライビングを測る」という課題でした[4]。その目的は、第一に、信頼性と妥当性の高い測定尺度を開発すること。第二に、その尺度が、スライビングの理論的な定義通り、「活力」と「学習」という二つの異なる、しかし関連しあう側面をきちんと捉えられているかを確認すること。そして第三に、開発した尺度を用いて、スライビングが実際に従業員のパフォーマンスや健康といった有益な結果と結びつくのかを実証することでした。この目的を達成するため、三段階にわたる一連の研究プログラムを計画・実行しました。
第一段階は、尺度そのものを開発し、その質を検証するプロセスです。研究者たちは、まず多くの働く人々にインタビューを行い、「仕事で生き生きと成長していると感じるのはどんな時か」を尋ね、スライビングの状態を表す様々な言葉や表現を集めました。それらの言葉を基に、質問項目の候補を多数作成し、内容を吟味して絞り込む作業を繰り返しました。
最終的に、大学生や若手の社会人など、複数の異なる集団を対象に調査を行い、統計的な分析を用いました。その結果、「活力」に関する質問項目と、「学習」に関する質問項目からなる質問セットが、スライビングという概念の構造を的確に表現することが突き止められました。
この新しく開発されたスライビング尺度が、既存の類似した概念(例えば、ポジティブな感情や、もともとの学習意欲の高さなど)を測定する尺度と、どの程度関連し、どの程度異なるのかも検証されました。その結果、スライビング尺度は、これらの類似概念とは適度な関連性を持ちつつも、それらとは区別される、独自の心理状態を測定していることが裏付けられ、尺度の妥当性が高められました。
第二段階では、この尺度を用いて、スライビングが実際にどのような結果と結びつくのかが検証されました。米国の大学で働く施設部門の職員、様々な業種の6つの会社で働く従業員、管理職向けの研修プログラムに参加するマネジャーなど、多様な人々を対象に調査が実施されました。
分析の結果、スライビングのスコアが高い人ほど、燃え尽きの度合いが低く、自らのキャリアを主体的に切り拓こうとする姿勢が強く、上司から与えられる業績評価も高いことが明らかになりました。自己申告による健康状態は良好で、仕事からくる精神的なストレスも少ないという結果が得られました。これらの関連性は、伝統的によく用いられる指標である「仕事への満足度」や「組織への愛着」の影響を統計的に取り除いた後でも、依然として有意に残っていました。
第三段階では、スライビングの性質を深く探るため、その変動性が検証されました。社会人大学院生を対象に、学期が進行している最中と、学期が終了して1か月が経過した後の、二つの異なる時点でスライビングの度合いを測定しました。もしスライビングが個人の生まれ持った性格のような固定的なものであれば、二つの時点でのスコアはほぼ同じになるはずです。
しかし、結果はそうではありませんでした。多くの参加者で、二つの時点のスコアは異なっており、仕事の状況や環境の変化に応じて、スライビングの度合いはダイナミックに変動することが分かりました。
脚注
[1] Spreitzer, G. M., and Porath, C. L. (2012). Creating sustainable performance. Harvard Business Review, 90(1-2), 92-99.
[2] Gerbasi, A., Porath, C. L., Parker, A., Spreitzer, G., and Cross, R. (2015). Destructive de-energizing relationships: How thriving buffers their effect on performance. Journal of Applied Psychology, 100(5), 1459-1477.
[3] Kleine, A.-K., Rudolph, C. W., and Zacher, H. (2019). Thriving at work: A meta-analysis. Journal of Organizational Behavior, 40(9-10), 973-999.
[4] Porath, C. L., Spreitzer, G. M., Gibson, C., and Garnett, F. G. (2012). Thriving at work: Toward its measurement, construct validation, and theoretical refinement. Journal of Organizational Behavior, 33(2), 250-275.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。