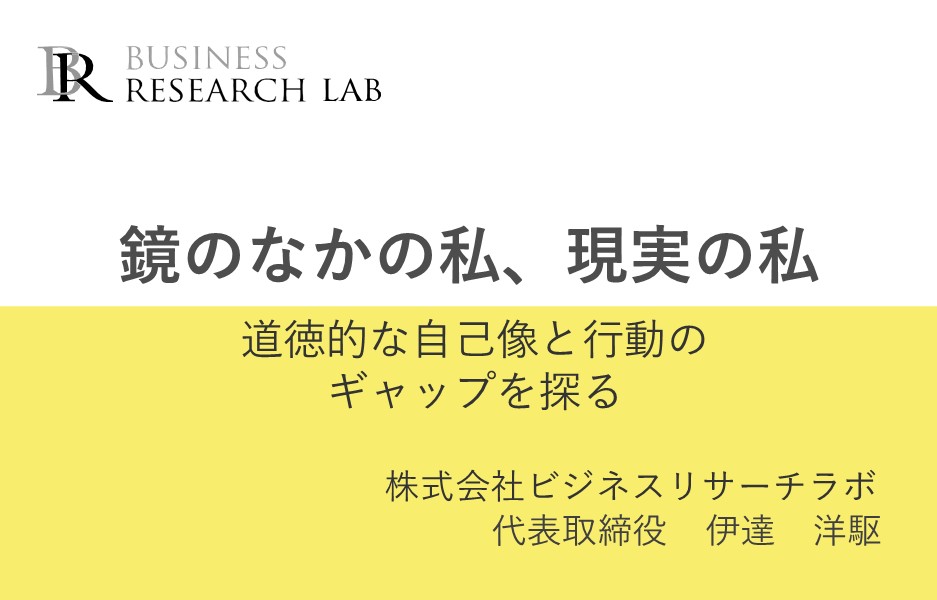2025年11月13日
鏡のなかの私、現実の私:道徳的な自己像と行動のギャップを探る
私たちは、自分自身のことをどのように見ているでしょうか。鏡に映る自分の姿を見て、少なくとも「ひどい人間ではない」と思いたい、できれば「良識的で、道徳的な人間だ」と信じたいかもしれません。正直、公正、思いやり。こうした価値観を、自分という人間の中心に据えていると感じている人は少なくないでしょう。企業の不正や不祥事が報じられると眉をひそめ、道端で困っている人がいれば、「助けてあげたい」という気持ちが芽生える。それが、ごく自然な人間の心の働きだと思う人もいるでしょう。
一方で、現実はどうでしょうか。私たちは、自らが信じる道徳的な理想像の通りに、常に振る舞えるわけではありません。少しだけ都合の良いように事実を曲げて話してしまった経験。見て見ぬふりをしてしまった小さな不正。自分に甘く、他人に厳しくなってしまった瞬間。完璧な人間などいないと言ってしまえばそれまでですが、この「ありたい自分」と「実際の自分の行動」との間には、時に無視できないほどの溝が存在します。
本コラムでは、この誰もが経験しうる「自認する道徳性と実際の行動とのギャップ」という、人間の心に潜むメカニズムについて探求していきます。誰かを善人や悪人と断罪することが目的ではありません。そうではなく、なぜ私たちの心と行動は時として食い違うのか、その背後にある心の働きを検討することを目指します。
道徳的だと自認していても、行動への影響は限定的
「自分は道徳的な人間だ」という自己認識は、私たちの行動にどれほどの道筋をつけてくれるのでしょうか。多くの人は、自分自身の価値観や信念が、日々の選択や行動の指針になっていると信じています。「道徳的価値観が、自分という存在の中核をなしている」という感覚は、「道徳的アイデンティティ」と呼ばれます。道徳的アイデンティティが強固な人ほど、道徳にかなった行動をとりやすいと直感的には考えられます。しかし、この直感は、果たしてどの程度事実なのでしょうか。
この問いに答えるため、過去に行われた膨大な数の研究結果を一つに統合し、大きな視点から分析した調査があります[1]。この種の分析は「メタ分析」と呼ばれ、より信頼性の高い結論を導き出すために行われます。この分析では、2015年までに行われた80件の研究、合計で約35,000人もの人々から得られたデータが用いられました。研究者たちは、「道徳的アイデンティティ」と、実際の「道徳的な行動」との間の関連性の強さを算出することを目指しました。
ここにおける「道徳的な行動」は、幅広く捉えられています。例えば、嘘をつかない、人を傷つけないといった「反社会的な行動の回避」、困っている人を助ける、寄付をするといった「向社会的な行動」、あるいは職場で定められた倫理規範を守るといった「倫理的な行動」などが含まれます。
一方で、「道徳的アイデンティティ」の測り方も様々です。アンケートの質問に自分で答える方法もあれば、言葉の連想などを用いて無意識のレベルでの道徳観を測ろうとする方法もあります。分析では、こうした行動の種類や測定方法の違い、さらには調査が行われた国の文化的な背景(個人を重んじる文化か、集団の和を重んじる文化か)なども考慮に入れられました。
数多くの研究を統合した結果、全体として、道徳的アイデンティティと道徳的な行動の間には、統計的に意味のある関連性が認められました。しかし、その関連性の強さは、「中程度に近い小規模なもの」と評価される水準でした。ある人の道徳的アイデンティティの高さを知ったとしても、その人が次にとる行動を正確に予測するのは難しい、ということを物語っています。
細かく見ていくと、行動の種類、すなわち不正を避けること、人助けをすること、倫理規範を守ることの間で、道徳的アイデンティティとの関連の強さに大きな差はありませんでした。一方で、行動をどのように測定したかによって、違いが見られました。例えば、実験室のような管理された環境で、一回限りの行動を観察した場合よりも、参加者自身に過去の日常的な行動を振り返って報告してもらったり、友人や家族といった第三者にその人の普段の行動を評価してもらったりした場合の方が、道徳的アイデンティティとの関連がやや強く出るという結果でした。
このことは、道徳的アイデンティティが、特定の状況下での一回きりの選択よりも、その人の普段の生活における行動のあり方と、より緩やかに結びついている可能性を示唆しています。
アイデンティティの測定方法によっても違いがありました。自分自身で意識的に回答するタイプの尺度で測った場合の方が、無意識レベルの道徳観を測る潜在的な尺度を用いた場合よりも、行動との結びつきが強くなるという結果が得られました。
文化的な背景も、この関係性に変化をもたらしていました。アメリカや西ヨーロッパのような個人主義的な文化圏では、集団の調和を重んじるアジアなどの集団主義的な文化圏に比べて、個人の道徳的アイデンティティと行動との結びつきが強いという結果が出ています。集団主義的な文化の中では、個人の内なる価値観に従うことよりも、その場の空気や周囲の人々との関係性を保つことが、行動を決める上でより大きな動機となるためかもしれません。
これらの結果を総合すると、道徳的アイデンティティ、要するに「自分は道徳的でありたい」という思いは、決して無力ではありません。確かに私たちの行動を善い方向へと促す力の一端を担っています。しかし、その力は限定的であり、私たちが考えるほど絶対的なものではない、という現実が浮かび上がってきます。自己認識と行動の間には、無視できない「隙間」が存在するのです。
道徳的な人は嘘の後、善行で心のバランスをとる
先ほどは、「自分は道徳的だ」という自己認識が、必ずしも実際の行動と固く結びついているわけではないことを見ました。私たちは、自分自身が信じる道徳律から、時に逸脱してしまう存在です。例えば些細な嘘をついてしまった時、私たちの心の中では一体何が起きているのでしょうか。「正直でありたい」という自分自身の理想像と、「嘘をついてしまった」という現実の行動との間に生じた不協和を、私たちはどのようにして解消しようとするのでしょう。
この問いを探る上で、人の心に備わった自己調整機能に関する考え方が手がかりとなります。それは、私たちが「こうありたい自分」という基準を持っており、実際の自分の行動がその基準からずれていると知覚すると、不快感を覚え、そのズレを修正しようと行動するというモデルです。この心の制御システムは、特に道徳性が自己のアイデンティティの中核をなしている人ほど、敏感に作動していると考えられます。
この考えに基づき、ある研究者たちは、人が道徳に反する行動をとった後の振る舞いについて、二つの異なるパターンを予測しました[2]。一つは、一度犯した過ちに引きずられるように、同じような不正を繰り返してしまう「整合パターン」。もう一つは、犯してしまった過ちを埋め合わせるかのように、別の良い行いをして心のバランスを取り戻そうとする「補償パターン」です。道徳的アイデンティティが高い人ほど、後者の「補償パターン」を選択しやすいのではないか、と仮説を立てました。
この仮説を検証するために、いくつかの実験が行われました。最初の実験では、参加者に最近一週間に行った「道徳的な行い」と「不道徳な行い」を自由に思い出してもらい、その数や思い出すのにかかった時間を記録しました。ここでの狙いは、不道徳な行為を犯した後の心の動きを、記憶の想起という形で捉えることです。
結果、道徳的アイデンティティが高い人々は、不道徳な行いを思い出すことを特別避けたりはしませんでした。その代わり、道徳的な行いを思い出すことにより多くの時間を費やし、より多くの事例を挙げようと努力しました。これは、自分の道徳的な側面を改めて確認することで、かすんでしまった自己像を修復しようとする、心の補償作用の表れと解釈できます。
次の実験では、より直接的に行動を観察しました。参加者は、金銭的な利益がかかったゲームに2回連続で参加します。各ゲームで、参加者は相手に対して「真実の情報」を送るか、「嘘の情報」を送るかを選択できます。嘘をつけば自分に利益がもたらされる状況です。ここで調べられたのは、1回目のゲームでの選択が、2回目のゲームでの選択にどう関わるかでした。
全体として見ると、一度嘘をついた人は、次のゲームでも嘘をつきやすいという「整合パターン」が見られました。しかし、道徳的アイデンティティが高い参加者に限って見ると、この流れが弱まることが確認されました。一度は嘘をついてしまっても、次は真実を伝えようとする、すなわち逸脱した行動を修正しようとする動きが見られたのです。
三つ目の実験は、補償行動の性質をさらに明らかにしました。参加者はお金を分配するゲームに参加し、相手に対して分配額について「本当のことを言う」「黙っている(隠蔽する)」「嘘を言う」のいずれかを選択します。その直後に、ゲームで得た報酬の中から、任意の額を慈善団体に寄付する機会が与えられました。
結果、道徳的アイデンティティが高い人は、分配ゲームで「嘘をついた」後、慈善団体への寄付額が有意に増加しました。嘘という不正行為を、寄付という全く異なる種類の善行によって「帳尻を合わせよう」とする補償行動です。対照的に、道徳的アイデンティティが低い人々は、嘘をついた後よりも、本当のことを言った後の方が寄付額が多いという、整合的な行動パターンを示しました。
これら一連の実験が描き出すのは、道徳性が自己の中心にある人ほど、自分の行動を内的にモニタリングしており、理想の自分から逸脱した際には、別の善行によって心の均衡を保とうとする、自己調整の姿です。一方で、道徳性が自己の周辺に位置する人は、一度逸脱の道に足を踏み入れると、その流れに身を任せてしまいやすいのかもしれません。
善行への称賛は、外面を気にする人ほど効果的である
人がボランティア活動に勤しんだり、見返りを求めずに寄付をしたりする時、その心の中を動かしている力は何でしょうか。心からの共感や、社会を良くしたいという純粋な思いが原動力であることは間違いないでしょう。しかし、それと同時に、「道徳的な人間だと思われたい」「良い行いをしている自分を誰かに見てほしい」という気持ちが、行動を後押しすることもあるかもしれません。この「内なる価値観」と「他者からの評価」という二つの動機は、私たちの道徳的アイデンティティと、どのように絡み合っているのでしょうか。
この問いを探るために、心理学では道徳的アイデンティティを二つの異なる側面から捉える考え方があります。一つは「内面化」と呼ばれる側面です。これは、思いやりや公正さといった道徳的な価値観を、自分自身の核となる信念として取り込んでいる度合いを指します。この内面化のレベルが高い人は、自分自身の価値観に忠実であろうとします。もう一つは「顕示化」という側面です。これは、自分が道徳的な人間であることを、行動やシンボルを通して他者に示したい、という欲求の強さを指します。この顕示化のレベルが高い人は、他者から「道徳的な人だ」と認識されることを求めます。
ある研究者たちは、この二つの側面が、特に「他者からの認知」という状況要因と組み合わさることで、人の善行への動機を複雑に形作るのではないかと考えました[3]。具体的には、「顕示化」の欲求が強い人は、自分の善い行いが誰かに見られたり、褒められたりする状況で、より一層、善行に励むのではないかと予測したのです。この関係は、もともと道徳性を深く「内面化」している人よりも、そうでない人において、よりはっきりと現れるだろうと仮説を立てました。
この仮説を確かめるため、二つの実証研究が行われました。最初の研究では、オンラインで募集した参加者に、まずアンケートに答えてもらい、各自の道徳的アイデンティティの「内面化」と「顕示化」の度合いを測定しました。その後、全く別の課題として、15分間の無償の調査ボランティアに参加してくれるかどうかを尋ねました。
この時、参加者はランダムに二つのグループに分けられました。一方のグループには、「ご協力いただいた方のお名前は、後日ウェブサイトに掲載し、その貢献を称えます」と伝えられました。これが、善行が他者から「認知される」条件です。もう一方のグループには、そのような説明はありませんでした。
自分の善行が誰にも知られない「非認知」の条件では、結果はシンプルでした。「顕示化」の欲求の強さとは無関係に、「内面化」の度合いが高い人ほど、ボランティアに進んで参加しました。自身の内なる価値観が一貫して行動に結びついていたのです。
しかし、善行がウェブサイトで公表される「認知」の条件では、様相は一変しました。この条件の下で、もともと「内面化」の度合いが低い人々に限って、「顕示化」の欲求が強いほど、ボランティアへの参加率が上昇したのです。一方で、すでに「内面化」の度合いが高い人々にとっては、他者から認知されるかどうかは行動にほとんど関係しませんでした。
この結果をより確かなものにするため、別の参加者グループを対象に、二つ目の研究が行われました。今度は、フードバンクへの寄付を目的としたパズル課題に取り組んでもらいました。パズルを1問解くごとに、一定額が研究者から寄付されるという仕組みです。ここでも、参加者の善行(パズルを解いた数)が公に称賛される「認知」条件と、そうでない「非認知」条件が設定されました。そして、全く同じパターンの結果が再現されました。「認知」される状況で、かつ「内面化」の度合いが低い人ほど、「顕示化」の欲求の強さに比例して、より多くのパズルを解き、寄付に貢献しました。
これらの研究が描き出すのは、私たちの善行を支える動機の二面性です。道徳性を深く内面化している人は、誰が見ていようといまいが、自己の信念に基づいて行動する、いわば「内燃機関」のような安定した動機を持っています。一方で、「良い人に見られたい」という顕示化の欲求は、他者の視線という「外部からの点火」があって初めて、行動のエネルギーへと変換されます。
上司の道徳性は行動を介し、注意は直接部下に伝わる
職場という環境において、リーダーの存在は組織の空気を左右します。特に倫理的な側面では、リーダーの振る舞いが部下の行動や考え方に影響を及ぼすことは、多くの人が経験的に知っているでしょう。しかし、その「伝わり方」のメカニズムは、実はそれほど単純ではありません。リーダーの「道徳的な人柄」そのものが部下に伝わるのでしょうか。それとも、日々の「倫理的な行動」を通してのみ伝わるのでしょうか。リーダーのどのような特性が、部下のどのような側面に働きかけるのでしょうか。
この複雑なプロセスを解明しようとした研究は、リーダーが持つ二つの異なる倫理的特性に着目しました[4]。一つは、これまでも見てきた「道徳的アイデンティティ」、すなわち道徳的な価値観がその人の自己認識の中心を占める度合いです。もう一つは「道徳的注意性」という、やや聞き慣れない概念です。
これは、日々の出来事や意思決定の中に含まれる道徳的・倫理的な側面を、どれだけ敏感に頻繁に知覚するか、という特性を指します。例えば、ある業務プロセスの中に、顧客に対する不誠実さや、同僚への不公平さが潜んでいないか、といったことに気づきやすいかどうか、という心の働きです。
研究者たちは、中国の企業で働く89人のリーダーと、その下で働く460人の部下を対象に、時間差を設けた調査を行いました。初めに、リーダーたちに自分自身の「道徳的アイデンティティ」と「道徳的注意性」について回答してもらいました。その3週間後、今度は部下たちに、同じリーダーの普段の振る舞いがどれだけ倫理的かを評価してもらいました。これは「倫理的リーダーシップ」と呼ばれ、部下の意見に耳を傾ける、約束を守る、公正な判断を下す、といった行動で測定されます。さらに、部下たち自身の「道徳的アイデンティティ」と「道徳的注意性」についても回答を求めました。
この設計により、リーダーの「内なる特性」が、リーダーの「見える行動」を介して、部下の「内なる特性」にどう伝わっていくか、その経路を分析することが可能になります。
分析の結果、いくつかの重要な発見がありました。まず、予想通り、リーダーの道徳的アイデンティティと道徳的注意性は、どちらも部下から見た「倫理的リーダーシップ」の評価を高めていました。内面で道徳を重んじ、物事の倫理的な側面に気づきやすいリーダーほど、部下からは「倫理的な上司」として認識されていたのです。
この部下が認識する「倫理的リーダーシップ」は、部下自身の道徳的アイデンティティと道徳的注意性の両方を高めることにつながっていました。倫理的なリーダーの言動に日々接することで、部下もまた、道徳を自分自身の価値観として取り入れたり、物事の倫理的な側面に注意を払うようになったりすることが示されました。
この研究の興味深い発見は、特性ごとの「伝わり方」の違いにありました。リーダーの「道徳的アイデンティティ」が部下の「道徳的アイデンティティ」に届く経路をたどると、それは必ずリーダーの「倫理的リーダーシップ」という具体的な行動を経由していました。直接伝わる経路は見られなかったのです。一方で、リーダーの「道徳的注意性」は、同じように行動を介して部下に伝わるだけでなく、リーダーから部下の「道徳的注意性」へと直接伝わる経路も確認されました。
この非対称な結果は何を物語っているのでしょうか。リーダーが心の中で「自分は道徳的な人間だ」と強く思っているだけでは、その思いは部下には直接届きません。その内なるアイデンティティが、部下への配慮や公正な意思決定といった、目に見える「行動」として表現されて初めて、部下はそれを手本とし、自身の道徳観を形成していきます。アイデンティティの伝播には、「行動」という翻訳機が必要です。
それに対して、リーダーの「道徳的注意性」、要するに「何に気を配っているか」という注意のアンテナの向きは、より直接的に伝播します。リーダーが普段から「この決定は倫理的に正しいか」「社会に対して誠実か」といった点に注意を払う姿勢は、会議での発言や日々の会話の端々から部下に伝わります。その注意の向け方は、あたかも伝染するかのように、部下の注意のアンテナをも同じ方向へと向かわせるのかもしれません。
脚注
[1] Hertz, S. G., and Krettenauer, T. (2016). Does moral identity effectively predict moral behavior? A meta-analysis. Review of General Psychology, 20(2), 129-140.
[2] Mulder, L. B., and Aquino, K. (2013). The role of moral identity in the aftermath of dishonesty. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 121(2), 219-230.
[3] Winterich, K. P., Aquino, K., Mittal, V., and Swartz, R. (2013). When moral identity symbolization motivates prosocial behavior: The role of recognition and moral identity internalization. Journal of Applied Psychology, 98(5), 759-770.
[4] Zhu, W., Trevino, L. K., and Zheng, X. (2016). Ethical leaders and their followers: The transmission of moral identity and moral attentiveness. Business Ethics Quarterly, 26(1), 95-115.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。