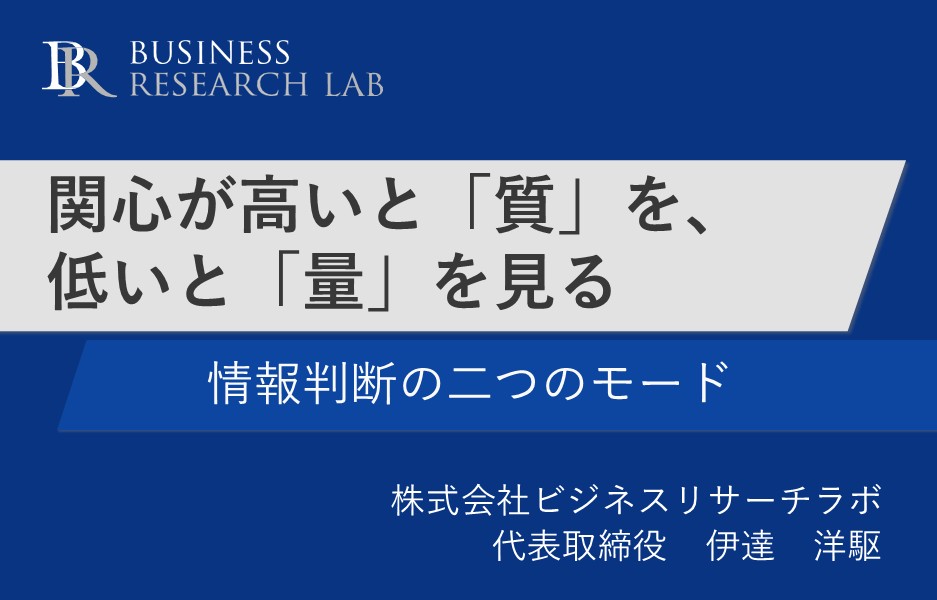2025年11月12日
関心が高いと「質」を、低いと「量」を見る:情報判断の二つのモード
私たちは日々、情報の海の中を生きています。朝起きてスマートフォンでニュースを確認し、職場では無数のメールや資料に目を通し、家に帰ればSNSや動画サイトから様々なコンテンツが流れ込んでくる。かつては一部の専門家や権力者しか手にできなかったような情報にも、多くの人がアクセスできる時代になりました。これは計り知れない恩恵である一方、新たな困難も生み出しています。あまりに膨大な情報の中から、自分にとって本当に価値のあるものをいかにして見つけ出すかという問題です。
私たちは、意識しているかどうかにかかわらず、絶えず情報を選別し、その価値を判断しています。しかし、その判断は一体どのような基準で行われているのでしょうか。ある情報に心を動かされ、行動に移すこともあれば、別の情報には全く関心を示さず、読み飛ばしてしまうこともある。その違いはどこから来るのでしょう。私たちは、情報の正しさや論理的な整合性だけで価値を決めているわけではありません。そこには、もっと複雑な心の働きが隠されています。
本コラムでは、私たちが行っている情報価値の判断プロセスを、いくつかの研究を手がかりに解き明かしていきます。自分自身の関心の度合い、情報の伝えられ方、発信者の人物像、自分自身の知識レベル。これらの要素が、私たちの判断にどのように結びついているのかを見ていくことで、情報との付き合い方を捉え直すきっかけを提供できればと思います。
関心が高いと質を、低いと量を重視する
情報を受け取るとき、私たちの心の状態は一定ではありません。その情報が自分にとってどれだけ切実な問題かによって、情報の受け止め方は変わります。例えば、自分の住む町に新しい商業施設が建設されるという話と、遠い外国の都市に建設されるという話とでは、関心の度合いは異なるでしょう。このような関心の高さ、すなわち「関与」の度合いが、私たちが情報のどこに価値を見出すかを左右することが、ある研究で確かめられています[1]。
この研究は、「説得においては、話の内容の『質』と、根拠の『量』のどちらが人を動かすのか」という問いに、一つの答えを与えようとしたものです。研究者たちは、大学生を対象に、架空の制度改革に関するメッセージを読んでもらう実験を行いました。その制度とは、大学卒業のためには包括的な試験に合格することを義務付けるというものです。
実験に参加した学生たちは、いくつかのグループに分けられました。学生たちの関与度を操作するために、あるグループには「この試験制度は、あなたが在学している大学で来年から導入される予定」と伝えました。これは自分たちの卒業に直接関わるため、関与が高い条件と言えます。一方、別のグループには「この制度は、遠く離れた別の大学で導入が検討されている」と伝えました。これは自分たちには直接関係のない話なので、関与が低い条件です。
メッセージの内容である「論拠」の質と量を操作しました。論拠の質については、説得力のある論理的な理由(「卒業生の初任給が平均的に上昇する」など)で構成された「強い論拠」のメッセージと、あまり説得力がなく、こじつけのような理由(「試験制度は国の伝統に沿っている」など)で構成された「弱い論拠」のメッセージの二種類を用意しました。論拠の量については、理由が3つだけ提示される「少ない論拠」の条件と、9つの理由が提示される「多い論拠」の条件を設定しました。
参加者は「関与(高/低)」「論拠の質(強/弱)」「論拠の量(多/少)」のいずれかの組み合わせのメッセージを読むことになり、その後、この試験制度にどれくらい賛成するかを尋ねられました。
結果は、関与の度合いによって、学生たちの判断基準が異なることを示しました。
関与が高いグループ、自分の大学に新制度が導入されると聞かされた学生たちです。その態度は、論拠の「質」によって左右されました。強い論拠を読んだ学生たちは制度に強く賛成しましたが、弱い論拠を読んだ学生たちは制度に反対の立場をとりました。論拠の数が3つであろうと9つであろうと、その数は彼らの判断にほとんど関係ありませんでした。
一方、関与が低いグループ、自分には関係ない話だと聞かされた学生たちは、逆の反応を見せました。その態度は、論拠の「量」によって左右されたのです。論拠の数が9つ提示されたメッセージを読んだ学生は、3つの論拠のメッセージを読んだ学生よりも、制度に賛成するようになりました。その際、論拠の内容が強いか弱いかは、判断に大きな違いをもたらしませんでした。
この結果から、どのような心のメカニズムが考えられるでしょうか。関与が高いとき、私たちは情報を注意深く、批判的に吟味する傾向にあります。内容をじっくりと処理し、その論理的な妥当性や正しさを評価しようとします。これを「中心ルート処理」と呼びます。この処理プロセスでは、情報の「質」が判断の決め手となります。
それに対して関与が低いとき、私たちは情報を深く処理しようとはしません。内容を精査するのは骨が折れる作業だからです。代わりに、「たくさんの理由が挙げられているのだから、きっと良い提案なのだろう」というような、表層的で直感的な手がかりに頼って判断を下します。これを「周辺ルート処理」と呼びます。このプロセスでは、論拠の「量」のような分かりやすい手がかりが、判断のショートカットとして機能します。
良い情報は誰が言ったかより内容で評価される
先ほどは、情報に対する関心の度合いが、私たちが「質」と「量」のどちらを判断基準にするかを分けることを見ました。では、私たちが情報の「質」を吟味しようとするとき、その評価は具体的にどのように行われるのでしょうか。特に、発信者の顔が見えず、無数の情報が飛び交うオンラインコミュニティのような環境では、「誰が言ったか」という発信者の信頼性と、「何が書かれているか」という内容そのものの良さ、この二つが評価の天秤にかけられます。
この問いに答えるため、ある研究では、二つの異なるオンラインコミュニティを対象とした調査が行われました[2]。一つは、バックパッカー向けの旅行フォーラムです。ここでは、経験豊富な旅行者が「ベストアンサー」として選ばれるなど、発信者の評価がある程度可視化されており、高性能な検索機能も備わっています。もう一つは、計算流体力学という専門分野の技術者たちが集うフォーラムです。こちらは、すべての投稿が時系列で保存されるだけで、検索機能も限定的でした。
このように性質の異なる二つのコミュニティを比較することで、どのような場で、どのような情報が採用されやすいのかを多角的に検証しようとしました。
調査の方法は、各コミュニティの利用者に、自分が問題解決のために参考にした投稿を一つ思い浮かべてもらい、その投稿に関するオンラインアンケートに回答してもらうというものでした。アンケートでは、その投稿の「議論の質」(内容が論理的で、説得力があったかなど)と、「情報源の信頼性」(発信者が専門的で、信頼できる人物だと感じたかなど)を評価してもらい、それらが最終的にどの程度その情報を「採用」したか(実際に役立てたか)にどう結びついているのかを分析しました。
分析の結果、両方のコミュニティにおいて、情報の採用に最も強く結びついていたのは「議論の質」でした。発信者が誰であるかということ以上に、投稿された内容そのものが論理的で、証拠に裏付けられ、包括的であることが、その情報が価値あるものとして受け入れられるための要因だったのです。「情報源の信頼性」も、情報の採用を後押しする要因ではありましたが、その度合いは内容の質には及びませんでした。
この研究では、さらに踏み込んだ分析も行われています。情報を受け取る側の状況が、内容重視と発信者重視のバランスをどう変えるかを調べたのです。例えば、自分が元々持っていた知識や考えとは異なる「反証的な情報」に接したとき、人はどう反応するでしょうか。この調査では、そのような情報に触れた人ほど、「情報源の信頼性」に頼る度合いが減り、「議論の質」をより注意深く吟味するようになることがわかりました。自分の常識が揺さぶられたとき、人は「誰が言ったか」という権威にすがるのではなく、「本当にそうなのか」と内容そのものを検証しようとします。
旅行フォーラムのように優れた検索機能があるコミュニティで、特定の目的を持って情報を探す「フォーカス検索」を行う利用者も、発信者の信頼性よりも内容の質を評価の基準とする度合いが強まりました。検索によって関連情報が絞り込まれると、利用者は少ない候補の中から最適な答えを見つけようと、コンテンツの中身を比較検討するためだと考えられます。
これらの結果が物語るのは、オンラインの知識共有空間において、その価値の根幹をなすのは、発信者の評判や権威といった要素以上に、一つひとつのコンテンツが持つ質の高さであるということです。もちろん、発信者の信頼性も無意味ではありません。それは、情報を評価する際の一つの参考にはなります。しかし、最終的に人々がその情報を「採用」するかどうかを決定づけるのは、内容そのものが持つ説得力や有用性です。
批判より解決策を伴う提案が評価される
情報を受け取る際の関与度や、オンラインでの評価基準について見てきました。情報の内容が評価されることは分かりましたが、その「内容」の中でも、どのような伝え方がより高く評価されるのでしょうか。職場での場面を想像してみてください。会議の席で「この計画には問題点がある」と指摘する声は、組織の過ちを防ぐために必要です。しかし、そのような発言が常に歓迎されるとは限りません。時には、発言者が否定的な人物だと見なされたり、場の空気を悪くしたと評価されたりすることもあります。どのような「声」が、建設的な情報として価値を認められるのでしょうか。
この問いを解明するため、ある研究では、従業員が組織に対して改善提案などを行う「ボイス行動」が、周囲からどのように評価されるのかを調べました[3]。研究者たちは、参加者に架空の製薬会社のチーム会議を録画した映像を見せ、その中で発言する人物のパフォーマンスを評価してもらうという実験を行いました。
この実験では、発言が評価される要因を「メッセージ(発言内容)」「ソース(発言者)」「コンテクスト(状況)」の三つの側面に分け、それらを様々に組み合わせて検証しました。
メッセージ要因としては、「解決策を提示しているか、していないか」や、「表現が肯定的か、否定的か(例:「この新薬には可能性があります」と「このままでは失敗します」)」といった違いが設けられました。
ソース要因としては、発言者が「その分野の専門知識を持っているか」や、「普段から信頼できる人物か」といった情報が操作されました。
コンテクスト要因としては、「プロジェクトの早い段階で発言したか、遅い段階で発言したか」というタイミングや、「組織が普段から発言を奨励する文化か、沈黙を良しとする文化か」といった状況設定が用意されました。
複数の実験を通じて、これらの要因が発言者の評価にどう結びつくかを分析した結果、一つの要因が他を圧倒して強い結びつきを持つことがわかりました。それは、「解決策を提示しているか」どうかです。
問題点を指摘するだけでなく、解決策を伴う提案を行った発言者は、そうでない発言者と比較して、周囲からの評価が高まりました。聞き手はその発言者に対してより強い「好意」を抱き、その発言を「建設的だ」と認識し、そして最終的な「パフォーマンス評価」も格段に高くなったのです。
発言者の「信頼性」の高さや、提案の「タイミングが早い」ことも、評価を高める要因として確認されました。日頃から信頼されている人物が、問題が大きくなる前の早い段階で行う提案は、価値あるものと見なされやすいようです。
一方で、少し意外な結果も見られました。発言者がその分野の「専門家」であるかどうかは、評価に限定的な影響しか与えませんでした。興味深いことの一つは、発言の「フレーミング」、表現が肯定的か否定的かという点は、評価にほとんど全く関係がなかったことです。「希望のある未来」を語るポジティブな言い方も、「危機的な状況」を訴えるネガティブな言い方も、それ自体が評価を左右することはなかったのです。
なぜ、解決策の提示がこれほどまでに評価を高めるのでしょうか。その背景にある心理的なメカニズムとして、二つの点が考えられます。
第一に、聞き手は解決策を伴う提案を「建設的で、組織の改善に本当につながるものだ」と認識しやすいからです。単なる批判は現状を否定するだけですが、解決策は未来への道筋を示すため、より価値が高いと判断されます。第二に、聞き手は、解決策まで考えて提案する発言者の動機を、「組織全体のことを考えた利他的なものだ」と解釈しやすくなります。個人の不満や批判ではなく、集団の利益を考えての行動だと見なされることが、発言者自身の評価も高めるのです。
専門家は助言の中身を、素人は発信者を信じる
これまでの議論で、情報の価値判断が、私たちの関心度、情報の文脈、伝え方によって変わることを見てきました。関心が高ければ質を、低ければ量を評価し、基本的には内容を吟味し、特に解決策を伴う提案を高く評価する。この一連の判断プロセスにおいて、最後に探求すべきは、受け手自身が持つ「専門知識」がどのようなフィルターとして機能するのかという点です。同じ助言を聞いたとしても、その分野の専門家と素人とでは、判断の拠り所は同じなのでしょうか。
この問いに光を当てるため、ある研究では、組織内で日常的に交わされる電子メールでの助言が、どのように採用されるのかというプロセスが調査されました[4]。この研究のユニークな点は、これまでに議論されてきた複数の理論を統合し、より現実に近いモデルを構築しようとしたことです。具体的には、助言の「内容の質」と「発信者の信頼性」が、受け手にとっての「有用性の認識」を介して、最終的な「助言の採用」につながるという枠組みを検証しました。
調査の対象となったのは、大手コンサルティング会社の従業員たちです。研究者たちは、従業員たちにインタビューを行い、実際に受け取った助言メールを参考にしながら、どのような基準で助言を採用するかを質的に探りました。その後、より大規模な質問紙調査を実施し、従業員が最近受け取った助言メールについて、その内容や発信者をどう評価し、どの程度採用したかを回答してもらいました。現実の業務で使われたメールを題材にすることで、実験室の中だけではわからない、生きた判断プロセスに迫ろうとしたのです。
分析の結果、基本的なモデルが支持されました。助言の「内容の質」が高いほど、また「発信者の信頼性」が高いほど、受け手はその助言を「有用だ」と認識し、その結果として助言を「採用」する度合いが高まることが確認されました。内容が優れていて、信頼できる人からの助言は、役立つと思われやすく、実際に使われやすいということです。
研究者たちは、受け手の「専門知識」のレベルによって、このプロセスがどのように変化するのかを分析しました。その結果、専門知識のレベルに応じて、人々が頼る判断基準が異なることが明らかになりました。
その分野に関する専門知識が高い受け手は、助言の「有用性」を判断する際に、主に「内容の質」を吟味していました。自身の知識体系を基に、助言の論理的な一貫性、データの正確さ、結論の妥当性を評価する能力を持っています。そのため、発信者が誰であるかよりも、書かれている内容そのものが優れているかどうかを判断の拠り所としました。
一方で、専門知識が低い受け手は、異なる判断基準を用いていました。助言の有用性を判断する際に、「発信者の信頼性」に依存していたのです。内容の良し悪しを自分自身で評価するための知識が不足しているため、「あの専門家が言うのだから」「信頼できる先輩が言うのだから」といった、発信者の権威や評判を代替的な手がかりとして利用します。これは、複雑な情報を評価するための認知的な負担を軽減する、一種のショートカットと言えるでしょう。
この結果は、冒頭で見た「中心ルート」と「周辺ルート」の考え方とも通じ合っています。専門家は、内容を深く吟味する「中心ルート」で情報を処理する能力と動機を持っています。対照的に、素人は内容の評価が困難なため、発信者の信頼性という分かりやすい「周辺的な手がかり」に頼らざるを得ません。
私たちは、自分自身の知識レベルというフィルターを通して世界を見ており、そのフィルターが、情報のどこに光を当て、どこを影にするかを決めています。専門家にとっては内容の論理性が輝いて見え、素人にとっては発信者の権威が灯台の光のように見えるのかもしれません。
脚注
[1] Petty, R. E., and Cacioppo, J. T. (1984). The effects of involvement on responses to argument quantity and quality: Central and peripheral routes to persuasion. Journal of Personality and Social Psychology, 46(1), 69-81.
[2] Zhang, W., and Watts, S. A. (2008). Capitalizing on content: Information adoption in two online communities. Journal of the Association for Information Systems, 9(2), 73-94.
[3] Whiting, S. W., Maynes, T. D., Podsakoff, N. P., and Podsakoff, P. M. (2012). Effects of message, source, and context on evaluations of employee voice behavior. Journal of Applied Psychology, 97(1), 159-182.
[4] Sussman, S. W., and Siegal, W. S. (2003). Informational influence in organizations: An integrated approach to knowledge adoption. Information Systems Research, 14(1), 47-65.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。