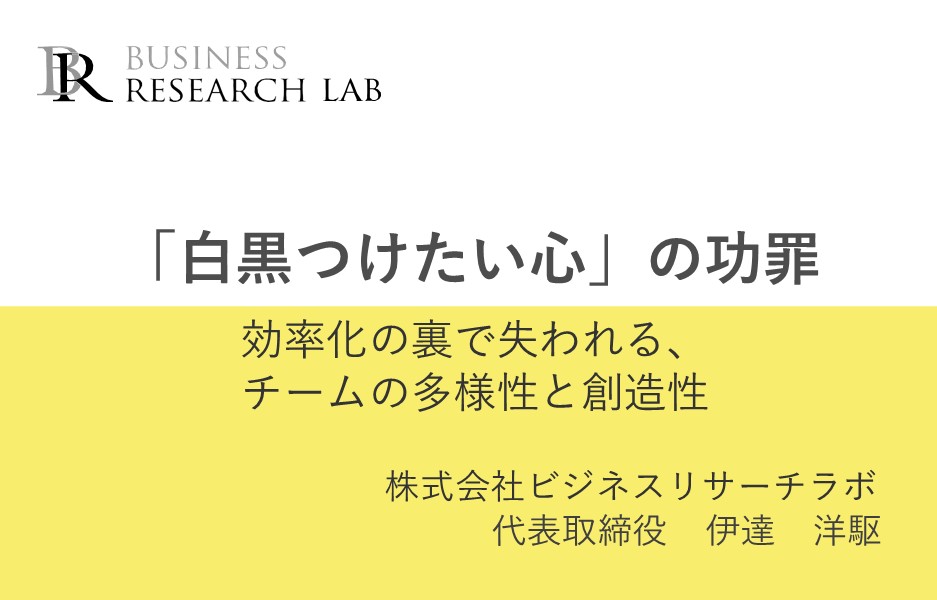2025年11月10日
「白黒つけたい心」の功罪:効率化の裏で失われる、チームの多様性と創造性
「早く結論を出して、スッキリしたい」。会議が長引いたり、議論がまとまらなかったりするとき、誰もが一度はこんな気持ちを抱いたことがあるのではないでしょうか。私たちは、物事が白黒はっきりしない、宙ぶらりんな状態をどこか不快に感じ、早く明確な答えや着地点を見つけたいと願う心を持っています。この「あいまいな状態を避け、確かな答えを求める心の働き」は、心理学の世界で「認知的完結欲求」と呼ばれています。
この欲求は、決して特別なものではありません。締め切りが迫っているとき、疲れているとき、あるいは周りが騒がしいときなど、私たちの日常の様々な場面で自然と高まります。また、もともと「物事を早く決着させたい」という気質を持つ人もいます。一見すると、この欲求は物事を効率的に進める上で便利なものに思えるかもしれません。しかし、この「早くスッキリしたい」という一見無害な気持ちが、集団の中に身を置いたとき、私たちの振る舞いやチーム全体の力学に波紋を広げることがあります。
例えば、会議でいつの間にか一人の声が大きい人だけが話していて、他の人は黙ってそれに従っている光景。あるいは、斬新なアイデアが出にくく、ありきたりな結論に落ち着いてしまうチーム。これらの現象の背後に、実はこの認知的完結欲求が隠れているとしたらどうでしょう。本コラムでは、この目に見えない心の働きが、集団内での発言の偏り、創造性の発揮、さらには少数意見の扱いにどのように関わっているのかを探求していきます。
認知的完結欲求が高まると集団で発言が集中し一人が主導権を握る
会議やグループでの話し合いにおいて、なぜか特定の一人が議論をリードし、他のメンバーは聞き役に回ってしまう、という場面は珍しくありません。このような発言の偏りは、単にその人の性格が積極的だから、という理由だけで片付けられるものでしょうか。実は、集団全体の「早く結論が欲しい」という心理状態が、このようなコミュニケーション構造を生み出す素地となっている可能性が考えられます。この点を探るため、二つの実験が行われました[1]。
最初の実験では、大学生たちに質問票を受けてもらい、「あいまいな状況が苦手で、早く明確な答えを得たい」という気持ちがもともと強い人々と、そうでない人々を事前に選び出しました。そして、欲求が強い人々だけで構成されたグループと、欲求が弱い人々だけで構成されたグループを、それぞれ複数作りました。各グループは四人一組です。彼ら彼女らに与えられた課題は、ある架空の企業の賞金を、功績のあった四人の候補者にどう分配するかを話し合って決める、というものでした。
研究者たちは、その話し合いの様子を観察し、誰がどれだけ発言の機会を得て、維持したかを記録しました。その結果、早く答えを得たいという欲求が強いメンバーで構成されたグループでは、欲求が弱いグループに比べて、発言の機会が一部のメンバーに集中していることが分かりました。ある一人が長く話し続け、他のメンバーはそれを聞いている、という構図が顕著だったのです。
さらに、観察者は各メンバーの話し方を「権威主義的か」「自己中心的か」といった観点から評価しました。すると、欲求が強いグループにおいて、発言を支配していたのは、このような独裁的と評価されるスタイルで話す人物でした。その人物は、他のメンバーからも、また本人自身も、グループの決定に最も大きな影響を及ぼしたと認識されていました。
欲求が弱いグループでは、このような話し方のスタイルと発言の支配度合いとの間に関連は見られませんでした。このことから、集団全体が「早く決めたい」という空気に包まれていると、ぐいぐいと議論を引っ張っていく独裁的なスタイルの人物が自然と主導権を握りやすくなる様子がうかがえます。
二つ目の実験では、人々の元々の気質ではなく、状況によって認知的完結欲求が高められた場合に何が起こるかが調べられました。こちらでも大学生が四人一組のグループに分かれ、同じように賞金分配の課題に取り組みました。ただし、今回は討議が三十分ほど進んだところで、半数のグループにだけ「急な都合で、この部屋をすぐに空けなければならなくなりました」と伝え、意図的に時間的な切迫感を創出しました。これにより、そのグループのメンバーは「早く議論を終えなければ」という気持ち、すなわち認知的完結欲求が高い状態に置かれます。
時間的な切迫感が与えられた後のコミュニケーションを分析したところ、やはり発言の偏りが見られました。切迫感のないグループに比べて、切迫感のあるグループでは、発言する人と聞く人の差が大きくなっていました。一人のメンバーがたくさん話し、他のメンバーはその人に話しかけられることが多い、というコミュニケーションの中心人物が生まれていたのです。
発言量が多い人物は、同時に他のメンバーからの発言の受け手にもなっており、文字通り対話のハブとして機能していました。この中心人物は、他のメンバーからも観察者からも、グループ内で最も影響力のある人物だと評価されていました。
認知的完結欲求が高まると同調圧力が増し創造性が低下する
新しいアイデアや斬新な解決策が求められる場面で、なぜか議論が盛り上がらず、ありきたりな結論に落ち着いてしまうことがあります。チームの創造性が十分に発揮されない背景にも、「早く確かな答えが欲しい」という認知的完結欲求が関わっているかもしれません。この欲求は、不確実性を嫌い、既存の知識や枠組みに固執する動きを強めるため、自由な発想の妨げになる可能性があります。この関係性を明らかにするため、三つの連続した実験が実施されました[2]。
最初の実験は、状況的な圧力が創造的なコミュニケーションをどのように変化させるかを探るものでした。男子大学生たちが四人一組のグループを作り、架空の社員表彰金を四人の候補者に配分するという交渉課題に取り組みました。
実験の途中で、一部のグループにだけ「部屋を急いで空ける必要がある」と伝え、時間的なプレッシャーをかけました。これは、認知的完結欲求を人為的に高めるための操作です。研究者たちは、討議中の発言内容を分析し、特に「たとえ話をする」「冗談を言う」「空想的な話を展開する」といった、直接的な問題解決から少し離れた創造的な発言がどれくらいの割合で出現するかを計測しました。
その結果、時間的なプレッシャーがかけられたグループでは、その直後から創造的な発言の割合が大幅に減少しました。一方で、時間的な制約なく議論を続けたグループでは、そのような変化は見られませんでした。このことは、結論を急がなければならないという状況に置かれると、人々は効率を優先し、一見すると本筋から逸れるような遊び心のある発言や、新しい視点につながるかもしれない発言を控えるようになることを物語っています。
二つ目の実験では、個人の元々の気質としての認知的完結欲求が、創造的な振る舞いにどう結びつくかが検証されました。今度は女子学生たちが参加し、事前に一人ひとりの認知的完結欲求の強さが測定されました。彼女たちは四人組、あるいは八人組のグループで、協力して問題を解決する課題に取り組みました。ここでも、討議中の創造的な発言の頻度が分析されました。
分析の結果、グループの人数にかかわらず、認知的完結欲求が強い人ほど、創造的な発言をする割合が低いことが分かりました。この結果は、時間的切迫のような外的な要因がなくても、個人の内的な特性として「早く答えが欲しい」という気持ちが強いと、自発的に創造的な貢献を差し控えるようになることを示しています。
三つ目の実験は、認知的完結欲求が創造性を低下させる、その背後にあるメカニズムを解き明かすことを目的としました。ここでは、より直接的に創造的な成果物が評価されました。参加した女子学生たちは、四人一組で広告会社のチームという設定で、ある製品の新しいスローガンを考えるという課題に挑戦しました。初めに個人でアイデアを出し、その後グループで討議して最終的な案を四つに絞り込みます。
この実験では、討議中に新しいアイデアがどれだけ生まれたか(発想の流暢性)と、グループ内でどれだけ同調圧力が感じられたか(例えば、異論を唱えにくい雰囲気や、手続きに素直に従う様子など)が、観察者によって評価されました。分析の結果、グループメンバーの認知的完結欲求の平均値が高いほど、討議中に新しいアイデアが生まれにくく、同時に同調圧力も強いことが分かりました。
さらに詳細な分析によって、この三者の関係性が明らかになりました。認知的完結欲求の高さは、直接的にアイデアの生まれにくさに結びついているだけでなく、「同調圧力の強さ」を介して間接的にも作用していたのです。認知的完結欲求が高いメンバーが集まると、まず「みんなと同じでいなければならない」という同調圧力が生まれ、結果的に自由なアイデア出しが妨げられる、という二段階のプロセスが存在することが突き止められました。
完結欲求高まる締切下で少数派が拒否され多数派が賞賛される
集団で意思決定を行う際、全員の意見が一致することは稀です。多くの場合、多数派と少数派が生まれます。私たちは、自分と異なる意見を持つ少数派の人を、どのように評価するのでしょうか。また、自分と同じ意見の多数派の人には、どのような感情を抱くのでしょうか。この評価は常に一定ではなく、集団が置かれた状況、特に「合意を形成しなければならない」という圧力の強さによって変動します。この力学を検証するために、四つの実験が計画されました[3]。
最初の実験の舞台は、イスラエルのスカウトグループのキャンプでした。少年少女たちが集まり、ある問題について討議を行いました。その討議の中には、意図的に多数派の意見に同調する「同調者」と、あえて異なる意見を主張し続ける「逸脱者」の役割を演じる協力者が仕込まれていました。この実験では、討議のタイミングが操作されました。あるグループは決定の期限よりずっと前に、別のグループは期限が目前に迫った時点で行われました。
討議の後、メンバーは逸脱者と同調者をそれぞれどのくらい好ましく思うかを評価しました。結果、逸脱者への評価は、決定の期限が間近に迫っているときに最も低くなりました。期限に余裕があるときは、そこまで厳しい評価にはなりませんでした。時間的な余裕がなくなり、「早くみんなで合意しなければ」という気持ちが強まると、その合意を乱す存在である少数派に対して、人々が不寛容になることを示しています。一方で、同調者への評価は、期限の近さによって変化は見られませんでした。
二つ目の実験では、時間的な切迫感の代わりに「騒音」が用いられました。大学生たちが四人一組のグループで討議を行う際、半数のグループの部屋では、すぐそばでプリンターが大きな音を立てて動き続けました。このような不快な環境は、人々の情報処理能力に負荷をかけ、「こんな状況は早く終わらせたい」「だから早く合意してしまいたい」という気持ちをかき立てます。これもまた、認知的完結欲求を高めるための一つの仕掛けです。
ここでも、討議には同調者役と逸脱者役が参加しました。結果は騒音の有無で異なりました。プリンターの騒音がある環境下では、逸脱者に対する評価は、静かな環境に比べて低くなりました。合意形成を妨げる少数意見が、ストレスの多い状況ではより一層、邪魔なものとして認識されたのです。
三つ目の実験では、意思決定のルールがこの評価にどう関わるかが調べられました。前の実験と同様に騒音のある条件とない条件が設定されましたが、今回はさらに、意思決定のルールが「全員一致でなければならない」か「多数決で決めてよい」かがグループごとに異なっていました。
その結果、逸脱者への強い拒否反応は、「騒音があり、かつ全員一致がルール」という、最も合意形成のハードルが高い条件でのみ顕著に現れました。多数決で決定できるルールの場合、たとえ騒音があっても、逸脱者への拒否反応は和らいだのです。多数決ならば、反対意見を持つ人が一人いても決定は下せます。そのため、少数派を無理に排除したり、意見を変えさせたりする必要性が低下し、結果として彼ら彼女らへの否定的な感情も弱まったと考えられます。
最後の実験では、同調者の役割が少し変更されました。同調者は、単に多数派の意見を述べるだけでなく、議論をまとめたり、他の人の発言を促したりする「意見リーダー」の役割を担いました。この設定で、再び騒音のある条件とない条件で討議が行われました。
結果としては、騒音のあるストレスフルな状況では、逸脱者はやはり強い否定的な評価を受けました。しかし、興味深いことに、意見リーダー役の同調者は、静かな条件のときよりも、騒音下でより高く評価されたのです。これは、合意形成への欲求が高まる困難な状況において、その合意形成を助け、集団をまとめてくれるリーダーの存在が、より価値のあるものとして受け止められることを物語っています。
完結欲求が高まると早期合意と逸脱排斥を伴う集団中心化が進む
これまで、早く答えが欲しいという「認知的完結欲求」が、集団内でのリーダーの台頭、創造性の低下、少数意見への不寛容といった個別の現象につながることを見てきました。しかし、これらの現象はバラバラに起きているのではなく、実は一つの大きな現象の異なる側面であると捉えることができます。それは「集団中心化」と呼ばれ、認知的完結欲求の高まりを起点として、集団が内向きになり、均質化していく一連のプロセスを指します[4]。
この理論の根幹にある考え方はシンプルです。「確かな、揺るぎない知識が欲しい」という認知的完結欲求を持つ人々にとって、その知識を提供してくれる最も手近で強力な源泉は、自分が所属する「集団」です。集団のメンバーが共有する意見や価値観は、一人ひとりの主観的な見方を超えた、「共有された現実」として機能します。
したがって、確かなものを求める気持ちが強い人ほど、この共有現実を生み出し、維持してくれる集団のまとまりを強く求めるようになります。この動機が、集団中心化という一連の行動を引き起こすのです。こうしたプロセスは、共有現実を「創り出す」段階と、それを「維持する」段階に分けて考えることができます。
共有現実を「創り出す」段階では、まず、意見を一つにまとめようとする圧力が働きます。認知的完結欲求が高い人は、意見の不一致というあいまいな状態に耐えられないため、他者を説得したり、あるいは自分の意見を曲げたりしてでも、早く合意に達しようとします。
この迅速な合意形成を助けるのが、専制的なリーダーシップの容認です。リーダーのいない四人組の交渉実験では、認知的完結欲求が高いメンバーで構成されたグループで、発言を独占する人物が登場し、事実上のリーダーとして議論を方向づけたことが思い出されます。集団は、早く答えを出してくれる強力なリーダーの存在を許容し、むしろ歓迎します。
同時に、自分たちが所属する集団への愛着が強まり、外部の集団を拒絶する動きも見られます。大学対抗の実験で、時間的なプレッシャーをかけられた学生たちが、自分たちの大学の仲間への一体感を強め、ライバル大学の学生からの助言を退けたという研究がありました。自分たちの集団こそが正しい知識の源泉であると信じ、外部からの異質な情報を遮断することで、共有現実の純粋性を保とうとするのです。
一度、共有現実が「創り出される」と、今度はそれを「維持する」ためのメカニズムが働きます。その最も分かりやすい例が、逸脱者の排斥です。キャンプ地の決定をめぐる討議で、締切直前という認知的完結欲求が高い状況下で、あえて少数意見を述べたメンバーが厳しい評価を受けたように、集団の和を乱し、共有された現実に疑問を投げかける存在は、脅威として排除の対象となります。
また、一度確立された規範や慣習は、なかなか変わらなくなります。世代交代を繰り返しながら架空の文化を伝達させていく実験では、騒音下で認知的完結欲求が高まった状態のグループ系列は、最初に与えられた規範をほとんど変えることなく、後の世代まで忠実に維持し続けました。新しい情報を取り入れて規範を更新するよりも、既存の知識を「凍結」させることを選ぶのです。
脚注
[1] Pierro, A., Mannetti, L., De Grada, E., Livi, S., and Kruglanski, A. W. (2003). Autocracy bias in informal groups under need for closure. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(3), 405-417.
[2] Chirumbolo, A., Livi, S., Mannetti, L., Pierro, A., and Kruglanski, A. W. (2004). Effects of need for closure on creativity in small group interactions. European Journal of Personality, 18(4), 265-278.
[3] Kruglanski, A. W., and Webster, D. M. (1991). Group members’ reactions to opinion deviates and conformists at varying degrees of proximity to decision deadline and of environmental noise. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 212-225.
[4] Kruglanski, A. W., Pierro, A., Mannetti, L., and De Grada, E. (2006). Groups as epistemic providers: Need for closure and the unfolding of group-centrism. Psychological Review, 113(1), 84-100.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。