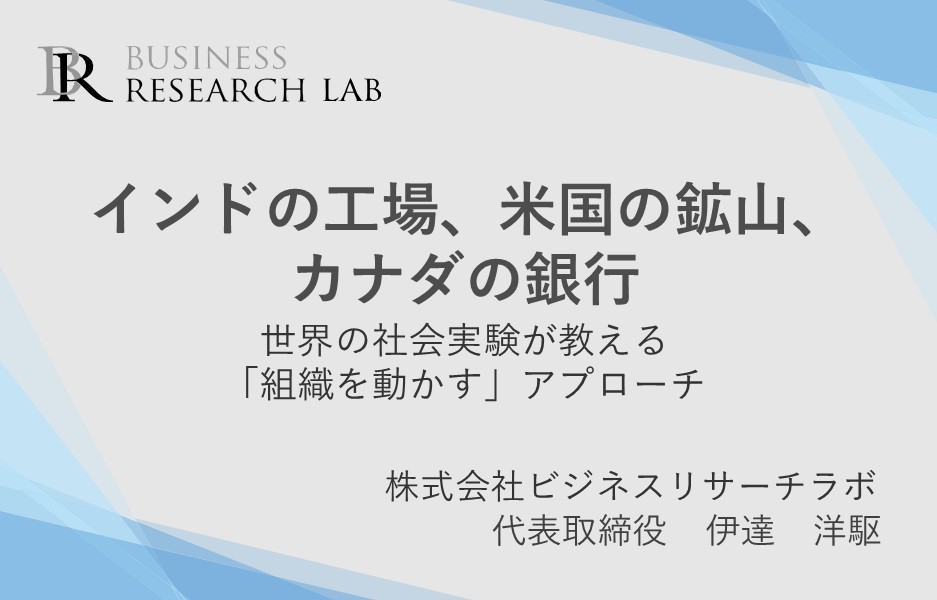2025年11月7日
インドの工場、米国の鉱山、カナダの銀行:世界の社会実験が教える「組織を動かす」アプローチ
組織の成果を高めるために、優れたマネジメントやリーダーシップが求められることは、多くの人が経験的に理解しているでしょう。しかし、その「優れた」とは一体何を指すのでしょうか。管理手法を新しくすること、挑戦的な目標を掲げること、あるいは部下一人ひとりに寄り添うこと。様々なアプローチが考えられますが、それらが実際に組織の中でどのように機能し、どのような変化を生み出すのか、そのプロセスまで深く知る機会は少ないかもしれません。日々の業務に追われる中で、管理や指導のあり方に悩み、その正解が見えずに立ち止まってしまう管理職の方も少なくないはずです。
本コラムでは、そうした漠然としたイメージや悩みを一度脇に置き、科学的な視点からマネジメントとリーダーシップが組織にもたらす変化を紐解いていきます。紹介するのは、現実の職場で、実際の従業員を対象に行われた複数の社会実験の結果です。コンサルタントが工場の管理体制を見直したとき、現場では何が起きたのか。鉱山の作業チームに「目標」と「対話」を導入した結果、仕事の量と質はどう変わったのか。銀行の支店長がリーダーシップ訓練を受けた後、部下の心や支店の売上にはどのような連鎖が生まれたのか。一見すると誰もが納得するようなリーダーシップ理論が、現場では思うように機能しなかったのは何故か。
これらの具体的な事例を一つひとつ見ていくことで、マネジメントやリーダーシップが、測定可能な変化をもたらす一連の技術であることが見えてきます。
管理手法の近代化で織物工場の生産性が向上
企業によって生産性に差が生まれるのは、管理手法の違いに一因があるのではないか。この古くからの問いに、ある実験が答えようとしました[1]。舞台はインド西部、マハラシュトラ州にある複数の綿織物工場です。ここでは、近代的な管理手法を導入することが、本当に企業の生産性を高めるのかを確かめるための、無作為化フィールド実験という手法が用いられました。
実験の対象となったのは、中規模以上の織物企業17社が所有する28の工場です。これらの工場の中から20工場が「実験工場」として選ばれ、くじ引きのような形で無作為に二つのグループに分けられました。一つは、国際的なコンサルティング会社から、近代的な管理手法の導入支援を無料で受けられる「処置群」の14工場。もう一つは、管理状況の診断は受けるものの、具体的な導入支援は受けない「統制群」の6工場です。このようにグループを分けることで、管理手法の導入そのものがもたらした変化を、他の要因と切り分けて測定しようとしました。
実験は三つの段階で進められました。最初の1か月は「診断フェーズ」です。この期間、コンサルタントはすべての実験工場を訪れ、品質管理、在庫管理、設備の保全、人事評価、受注管理といった38項目にわたる管理の実践状況を点検しました。これによって、各工場の現状を把握するための基礎的なデータが構築されます。
次の4か月間は「実装フェーズ」と呼ばれ、ここから二つのグループの処遇が分かれます。処置群の工場では、コンサルタントが現場に常駐し、診断フェーズで見つかった課題を解決するための近代的な管理手法を、一つひとつ導入していきました。例えば、品質管理であれば、欠陥の原因を特定し再発を防ぐ仕組みづくりを、在庫管理であれば、必要な分だけを保有するための基準策定などを支援しました。一方、統制群の工場では、この期間、特別な介入は行われません。
そして最後の「測定フェーズ」では、実験開始前から終了後まで、100週間以上にわたって、すべての工場から生産に関する週次のデータが収集され続けました。生産量や品質、在庫量といった客観的な数値の変化を追跡することで、管理手法導入の成果を評価します。
分析の結果、処置群の工場では変化が見られました。まず、実験の核である管理手法の採用率が、平均で25.6%から63.4%へと、37.8ポイントも上昇しました。これは、コンサルタントの支援によって、近代的な管理手法が現場に根付いたことを示しています。
管理の改善は、工場のオペレーションに変化をもたらしました。品質欠陥指数という、製品の欠陥度合いを示す数値は、約32%低下しました。また、工場の倉庫に眠っていた糸の在庫は16.4%減少しました。これは、無駄な在庫を減らし、適切な在庫量を保つという管理手法が機能した結果です。生産量も5.4%増加しましたが、これは設備の稼働率が上がり、計画的な保全が行われるようになったためと考えられます。
興味深いことに、この変化は生産現場だけにとどまりませんでした。管理が改善され、品質や在庫に関する情報が正確かつ迅速に把握できるようになると、組織の構造にも変化が現れました。これまで本社の経営者が握っていた権限の一部が、工場の責任者である工場長へと委譲される、いわゆる「分権化」が進んだのです。現場の情報が可視化されたことで、経営者が安心して現場に判断を任せられるようになったためと解釈できます。
目標設定で産出量増、チームビルディングで品質向上
組織全体の管理体制を近代化することが、生産性全体を底上げする力を持つことは、先の織物工場の例で確認できました。それでは、視点をより現場に近いレベルに移し、日常的に行われる働きかけに目を向けてみましょう。「目標を設定すること」や「チームで対話を重ねること」。これらは多くの職場で実践されている手法ですが、それぞれが仕事の成果にどのような変化をもたらすのでしょうか。米国西部にある、銀や鉛、亜鉛を採掘する地下の硬岩鉱山で行われたある実験が、この問いに光を当てています[2]。
この実験では、「目標設定」と「チームビルディング」という二つの手法が、鉱山での生産性にどう作用するのかが検証されました。鉱山での作業は、単に量を掘ればよいというものではなく、掘り出した鉱石に含まれる金属の含有率、つまり「品位」も大切です。そこで、生産性を「量(採掘トン数)」と「質(品位)」の両面から測定することになりました。
実験の舞台となったのは、292名の従業員が働く鉱山の、地下にある20の採掘現場(ストープ)です。ここで働く53名の坑夫たちが実験の参加者となりました。これらの採掘現場は、四つのグループに分けられました。一つは「目標設定」と「チームビルディング」の両方を実施するグループ。二つ目は「チームビルディング」のみを実施するグループ。三つ目は「目標設定」のみを実施するグループ。四つ目は、どちらも実施しない対照グループです。ただし、今回は会社の経営層の判断で、まず12の現場にチームビルディングが導入され、その2週間後に、10の現場に対して無作為に目標設定が割り当てられるという、準実験的なデザインが採用されました。
では、それぞれの介入はどのように行われたのでしょうか。「チームビルディング」では、外部のコンサルタントが各作業チーム(クルー)と、1回45分のミーティングを10週間にわたって計6回実施しました。
ミーティングでは、まず坑夫たちが日々の仕事で感じている課題、例えば作業の進め方、安全性、設備の問題、賃金制度への不満などを自由に挙げるところから始まります。次に、それらの問題の原因を皆で分析し、解決策を立案します。シフト間の情報共有を密にするための会議を設けたり、作業場を整理整頓したりといった、すぐに実行できる改善策はその場で決められました。5回目のミーティングには管理職も参加し、坑夫たちの声を受けて、資材置き場を増設したり、設備の改善を行ったりといった、より大きな決定もなされました。
一方、「目標設定」のグループでは、シフトの責任者であるシフト長が1時間の研修を受けました。その後、シフト長は坑夫たちと共に、過去18か月間の自分たちの現場の採掘実績が描かれたグラフを見ながら、今後3か月間の目標を話し合って決めます。目標は「達成は困難だが、現実的に不可能な数字ではない」水準に設定され、採掘量(トン数)と品位の両方について合意が形成されました。介入期間中は毎週、目標達成度を示す個別のグラフが各坑夫に配られ、自分たちの進捗を定期的に確認できる仕組みが作られました。
実験期間は、介入前の2か月間を基準とし、介入後の3か月間の変化を追跡しました。生産性の「量」は、坑夫一人・一シフトあたりの採掘トン数で、「質」は採掘された鉱石の銀と鉛の品位で測定されました。
分析の結果、二つの手法はそれぞれ異なる側面に作用することが分かりました。まず生産量、つまり採掘トン数については、「目標設定」を行ったグループで顕著な向上が見られました。目標を設定されなかったグループに比べて、平均で採掘量が増加したのです。チームビルディングの効果は明確ではありませんでした。
次に生産の質、つまり銀の品位については、反対に「チームビルディング」を実施したグループで改善する動きが見られました。チームビルディングを導入したグループでは品位がわずかに上昇したのに対し、導入しなかったグループはほぼ横ばいでした。目標設定の効果や、二つを組み合わせた場合の効果は、品位に関してははっきりと確認できませんでした。
この鉱山での実験は、同じ「生産性向上」という目的であっても、用いる手法によって作用する側面が異なることを教えてくれます。「目標設定」は、個人の努力を方向づけ、定量的なアウトプットを押し上げる力があります。一方で、「チームビルディング」は、対話を通じて複雑な課題への解決策を生み出し、仕事の質的な側面を改善することに結びつくのです。
変革型訓練で部下の献身と支店売上が向上
目標設定が量に、チームでの対話が質に、それぞれ異なる形で結びつくことが分かりました。これらの手法を実践するのは、現場のリーダーです。では、リーダー自身のあり方や行動スタイルを変えるための訓練は、組織にどのような変化の波紋を広げるのでしょうか。ある銀行で行われた試みが、その過程を教えてくれます。ここで焦点が当てられたのは、「変革型リーダーシップ」という考え方です。
変革型リーダーシップとは、単に部下に指示を与え、達成度に応じて報酬を与えるといった交換的な関係にとどまらず、部下の価値観や信念に働きかけ、期待以上の成果を引き出すようなリーダーのあり方を指します。
変革型リーダーシップは、主に三つの要素から成るとされています。一つ目は「カリスマ/理想化された影響」で、リーダーがビジョンを示し、部下からの尊敬や信頼を集めることです。二つ目は「知的刺激」で、現状を当たり前とせず、新しい視点から問題を捉え直すように部下を促すことです。三つ目は「個別的配慮」で、部下一人ひとりの成長やニーズに関心を持ち、個別にサポートすることです。
これまでの研究で、こうしたリーダーシップと部下の意欲や組織の成果との間に関連があることは分かっていました。しかし、リーダーシップ研修を実施することで、管理職が本当に行動を変え、それが部下の態度や、さらには客観的な業績の改善にまでつながるのかは、はっきりと分かっていませんでした。そこで、カナダの大手銀行の協力を得て、この連鎖を実験的に検証する試みが行われたのです[3]。
実験の対象となったのは、この銀行のある地域に属する20の支店と、その責任者である20名の支店長です。支店長たちは、支店の規模が偏らないように考慮された上で、無作為に二つのグループに分けられました。一方は、変革型リーダーシップを身につけるための研修に参加する「訓練群」の9名。もう一方は、研修に参加しない「統制群」の11名です。
研修プログラムは約5か月にわたって行われました。まず最初に、1日間の集中的なグループ研修が実施されます。そこでは、変革型リーダーシップの三つの要素について学ぶだけでなく、参加者自身がこれまでに経験した「最高のリーダー」と「最低のリーダー」の特徴をグループで話し合い、理論と自らの体験を結びつけました。また、具体的な行動目標を設定し、ロールプレイングを通じて新しいリーダーとしての振る舞いを練習する機会も設けられました。
この1日研修の後、訓練群の支店長たちは、1か月に1回の個別セッションを計4回受けました。このセッションでは、研修で学んだことを実践できているか、部下からはどのように見られているかをデータでフィードバックされ、それに基づいて次の1か月の行動計画を立て、修正を重ねていきました。特に、部下に新たな視点や思考を促す「知的刺激」の行動を増やすことが優先されました。
この研修の効果を測定するために、研修の前後で、いくつかの指標が測定されました。部下たちには、自分たちの支店長が変革型リーダーシップ(知的刺激、個別的配慮、カリスマ)をどの程度発揮していると感じるか、そして、自分がこの銀行組織に対してどれくらいの愛着や貢献意欲(組織コミットメント)を持っているかを尋ねるアンケートに答えてもらいました。加えて、銀行の内部記録から、各支店の個人向けローンとクレジットカードの販売件数という、客観的な財務データも収集されました。
分析の結果、訓練群の支店では、統制群に比べて明確な変化が確認されました。まず、部下たちが認識するリーダーの行動が変わりました。特に「知的刺激」の項目で、訓練を受けた支店長の評価が、受けていない支店長に比べて有意に高まっていました。研修で優先的に扱われた行動が、実際に部下にも伝わるレベルで変化したのです。
続いて、部下たちの心境にも変化が見られました。訓練群の支店に勤務する部下は、統制群の部下に比べて、組織に対するコミットメントが有意に高まっていました。上司の行動が変わったことが、部下の組織への献身的な気持ちを引き出したと考えられます。
最も注目すべきは、これらの変化が、支店の実際の業績にまで結びついていた点です。研修後の期間において、訓練群の支店は、統制群の支店よりも、人員一人あたりの個人ローン販売件数とクレジットカード販売件数が、統計的に見て高い水準にありました。
高期待リーダー訓練の効果は小さく不安定
リーダーの行動変容が、部下の心をとらえ、最終的には組織の成果にまでつながる道筋が見えました。しかし、リーダーシップに関する理論が、いつでもどこでも同じように機能するとは限りません。「部下への期待が高いほど、部下のパフォーマンスも向上する」という、ピグマリオン効果として知られる理論があります。教師が生徒に期待をかけると生徒の成績が上がる、という現象で有名になったこの理論は、一見すると非常に強力で、マネジメントの現場でも応用できそうに思えます。では、管理職に「部下に高い期待を伝える振る舞い」を訓練で身につけさせることは、本当に部下の成果を高めるのでしょうか。
この問いに答えるため、ある研究者グループは、7つものフィールド実験を積み重ねました[4]。実験の目的は、ピグマリオン効果を応用した「ピグマリオン・リーダーシップ・スタイル(PLS)」を、ワークショップ形式の訓練を通じて管理職に植え付け、その実効性を検証することにありました。
このリーダーシップ・スタイルは、「部下に高い期待を明確に示す」「部下が挑戦しやすい支援的な雰囲気をつくる」「部下が成功した際には、その原因を本人の能力や努力にあると伝える」といった行動から構成されます。これらの行動を通じて、部下の自己効力感(自分ならできるという感覚)を高め、それが動機づけ、努力、そして成果へとつながる、というメカニズムが想定されていました。
ワークショップの内容は、実験を重ねる中で改良されていきました。当初は1日だった研修期間は、最終的に3日間の集中研修と、数週間後のフォローアップ研修を組み合わせる形にまで発展しました。内容は、ピグマリオン理論の講義、具体的な行動スキルを身につけるためのロールプレイ、そして学んだことを自分の職場でどう実践するかの計画策定などが中心でした。
ワークショップの効果を確かめるため、研究者たちは様々な現場で実験を行いました。陸軍の訓練部隊、イギリスの青少年キャンプ、国防軍の整備工場、公立小学校、二つの異なる銀行、そして総合病院。対象となったのは、部隊の教官、キャンプのカウンセラー、工場の部門長、校長、支店長、病院の課長といった、多様な立場のリーダーたちです。それぞれの実験で、訓練を受けたリーダーのグループと、受けていないグループとで、リーダー自身の行動や部下の意識、そして組織の成果に違いが生まれるかが比較されました。
しかし、7回にわたる検証の結果、得られた結論は、当初の期待とは異なるものでした。個々の実験結果を見ていくと、その効果は限定的で、不安定だったのです。
例えば、陸軍部隊での実験では、訓練を受けた教官自身のリーダーシップ評価は高まりましたが、部隊全体の成績には変化が見られませんでした。青少年キャンプでは、男性カウンセラーのリーダーシップ評価やチームの協働は改善しましたが、その効果は限定的でした。国防軍の整備工場や二つの銀行、総合病院で行われた実験では、リーダー自身の自己効力感がわずかに向上するケースはあったものの、部下の意識や職場の雰囲気、そして肝心の業績といった客観的な指標には、ほとんど変化が見られませんでした。公立小学校の実験でも、校長自身の態度は変わりましたが、その変化が教師たちにまで及ぶことはありませんでした。
7つの実験結果を統計的に統合するメタ分析という手法で全体を評価しても、その効果量の平均は、有意ではあるものの「小さい」と分類される水準にとどまりました。
なぜ、魅力的に思える理論が、現場ではうまく機能しなかったのでしょうか。研究者たちは、短期的なワークショップと限られたフォローアップだけでは、長年かけて形成されたリーダーの行動様式や、組織に根付いた文化を変えるには不十分だったのではないかと考察しています。ピグマリオン効果という現象自体は、実験室のような管理された環境では確かに存在します。しかし、それを現実の複雑な職場環境で、訓練によって意図的に引き起こし、持続させることの難しさが、この一連の研究によって浮き彫りになったのです。
脚注
[1] Bloom, N., Eifert, B., Mahajan, A., McKenzie, D., and Roberts, J. (2011). Does management matter? Evidence from India (NBER Working Paper No. 16658). National Bureau of Economic Research.
[2] Buller, P. F., and Bell, C. H., Jr. (1986). Effects of team building and goal setting on productivity: A field experiment. Academy of Management Journal, 29(2), 305-328.
[3] Barling, J., Weber, T., and Kelloway, E. K. (1996). Effects of transformational leadership training on attitudinal and financial outcomes: A field experiment. Journal of Applied Psychology, 81(6), 827-832.
[4] Eden, D., Geller, D., Gewirtz, A., Gordon-Terner, R., Inbar, I., Liberman, M., Pass, Y., and Salomon-Segev, I. (2000). Implanting Pygmalion leadership style through workshop training: Seven field experiments. The Leadership Quarterly, 11(2), 171-210.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。