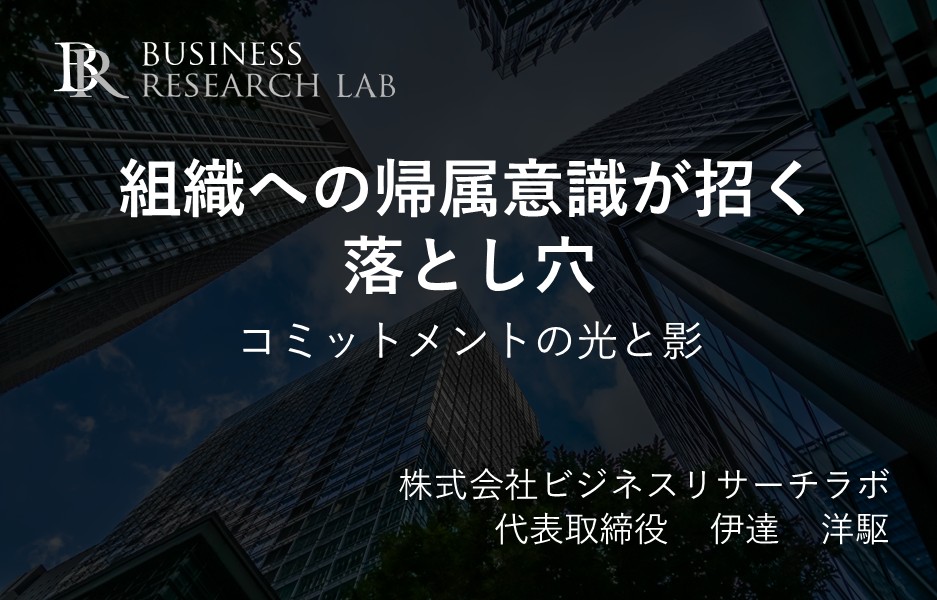2025年11月7日
組織への帰属意識が招く落とし穴:コミットメントの光と影
従業員の「会社への愛着」を育むこと、すなわち組織コミットメントを高めることは、重要なテーマの一つとされています。従業員が自らの所属する組織に強い一体感を持ち、その理念や目標に共感し、成功を我がことのように願う気持ち。それは日々の仕事への活力となり、生産性を高め、創造性を刺激して、優秀な人材の離職を防ぐ力になると期待されています。
実際に、高いコミットメントがもたらすポジティブな側面は数多くの研究で報告されており、企業が研修や社内イベント、福利厚生の充実といった様々な試みを通じて従業員のコミットメントを高めようと努力するのも、当然のことと言えるでしょう。
しかし、その強く、純粋であるはずの「愛着」は、時として思わぬ形で組織や個人に牙をむくことがあります。「会社のためだから」という献身的な思いが、いつしか視野を狭め、社会全体のルールや普遍的な倫理観から逸脱した行動を正当化する危険な口実になってしまう。あるいは、組織を愛するあまり、その内部に潜む不正や不都合な真実から目を背け、声を上げるべき場面で沈黙を選んでしまう。そして、献身的に働くことそのものが、かえって自分自身の心や体を容赦なくすり減らし、やがては「燃え尽き」という深刻な結末を招いてしまう。
このように、一般的に美徳とされ、奨励される組織へのコミットメントには、あまり光が当てられることのない「影」の側面、すなわち副作用が存在します。本コラムでは、組織への強い思いが、なぜ、そしてどのようにして、個人の倫理観を揺るがし、不正行為の温床となり、働く人を疲弊させてしまうのか。そのメカニズムを多角的に探求していきます。
強い情緒的コミットメントが地位追求を介し不正行動を招く
組織への強い愛着、すなわち「情緒的コミットメント」は、従業員の献身的な働きぶりや、部門を超えた協力的な姿勢の源泉となる、組織にとっての貴重な資産と見なされています。しかし、その忠誠心が、個人の「組織内で認められたい」「より高い地位に就きたい」という野心的な欲求と結びついたとき、その性質は予期せぬ、そして望ましくない方向へと変化することがあります。
この点について探った研究は、組織への情緒的な絆が、かえって組織に不利益をもたらす可能性に着目しました[1]。その理論的な背景には、「モラル・ライセンシング」という心理的なメカニズムがあります。これは、人が過去に道徳的に「善い」とされる行いをすると、心の中に道徳的な「貯金」ができたかのように感じ、その後の少しくらいの逸脱行為であれば「自分は善行を積んだのだから、これくらいは許されるだろう」と自身を正当化しやすくなる、という心の働きを指します。
この考え方に基づくと、組織に強くコミットしている従業員は、「自分は日々、組織に忠誠を尽くしている」という善行によって、一種の道徳的な特権意識を持ち、その後の不正行為の心理的なハードルが下がってしまうのではないか、という仮説が立てられました。
この仮説を検証するために、パキスタンにある複数のサービス業の企業で働く従業員とその同僚、合計300組以上を対象とした大規模な調査が行われました。分析の結果、明らかになったのは、組織への愛着が強い従業員ほど、組織のためになる不正行動や同僚への非協力的な行動は少ない、という私たちの直感と一致する関係でした。組織を愛する気持ちが、基本的には逸脱行動を抑制する健全な方向に働くことが、改めて確認されたのです。
しかし、分析はここで終わりませんでした。研究の核心は、この関係に「地位追求動機」がどう影響するかを検証した点にあります。分析を進めると、組織への愛着が強い従業員は、同時に、組織内でより高い地位を得ようとする動機も強い傾向にあることが分かりました。そして、この「地位を求める気持ち」が強い人ほど、結果的に、組織の利益を口実にした不正行為や、自らのキャリアの障害になりうる他者への攻撃的な行動が増加していたのです。
この一連の結果が物語るのは、組織への愛着が「直接的に」不正を引き起こすわけではない、という複雑なプロセスです。むしろ、「組織への愛着」が「地位への渇望」を強め、その渇望を満たすための手段として「不正行為」が選択されてしまう、という危険な連鎖構造が見えてきます。
従業員の心の中では、「私はこれほど組織に貢献しているのだから、目標達成のためには多少のルール違反も許されるはずだ」「このプロジェクトを成功させることが会社への最大の貢献であり、そのためには競合他社を出し抜く情報操作もやむを得ない」「出世のためには、ライバルを蹴落とすことも必要悪だ」といった、巧妙な自己正当化が行われているのかもしれません。
組織への忠誠心という本来ポジティブな感情が、地位追求という個人的な動機と結びつくことで、倫理的な逸脱を許容する「免罪符」のようなものとして機能してしまう可能性が、データによって示唆されました。
コミットメントは道徳観が弱いと組織擁護の不正行動を促す
先ほどは、地位への欲求という個人的な動機が、組織への愛着を不正へとつなげる「触媒」になりうることを確認しました。視点を個人の心の内側、とりわけその人が持つ「道徳的な物差し」へと移します。組織への強い愛着は、そもそも道徳観がしっかりしていない人物の中で、どのように作用するのでしょうか。「会社のために」という大義名分が、倫理の境界線をいかにして曖昧にさせてしまうのか、そのメカニズムを見ていきます。
この問題を解明しようとした研究では、「非倫理的向組織行動(Unethical Pro-Organizational Behavior)」という概念が中心に据えられました[2]。これは文字通り、組織やそのメンバーのためになることを意図して行われるものの、社会の一般的な価値観や規範、法に反する行動を指します。例えば、顧客を欺いてでも自社の製品を売る、競合他社の評判を落とす虚偽の情報を流す、あるいは検査データを改ざんして納期を守るといった、一見すると組織への貢献に見える行為がこれにあたります。これらの行為は、行為者本人に直接的な利益がなくても、「組織のため」という動機によって駆動される点が特徴です。
この研究の目的は二つありました。一つは、組織への情緒的な愛着が、この「非倫理的向組織行動」を本当に促進するのかを確かめること。もう一つは、もしそうした関係があるのなら、個人の「モラル・アイデンティティ」が、その危険な関係を食い止める「ブレーキ」になりうるのかを検証することでした。
「モラル・アイデンティティ」とは、「自分は思いやりがあり、公正で、正直で、親切な人間でありたい」といった、道徳的な価値観を自らのアイデンティティのどの程度中心に据えているかを意味します。モラル・アイデンティティが強い人は、自分の行動が道徳的であるかどうかを意識し、それに反する行動を取ることに強い心理的抵抗を感じ、自己評価を維持しようとします。
調査は、アメリカ南東部にある大手レストランチェーンの5つの店舗で働く従業員130名以上を対象に、アンケート形式で行われました。従業員たちは、自らの組織への愛着の強さ、自分自身をどの程度「道徳的な人間」だと考えているか(モラル・アイデンティティ)、そして「会社の評判を守るためなら、問題のある情報を隠蔽してもよいと思うか」「会社の利益になるなら、顧客に対して事実を少し誇張して伝えてもよいか」といった、非倫理的向組織行動への許容度について、具体的なシナリオに基づいて回答しました。
分析から得られた結果は、示唆に富むものです。先行研究の予測通り、組織への情緒的な愛着が強い従業員ほど、「会社のためなら」と非倫理的な行動に走りやすいという関係が確認されました。組織を思う気持ちが、社会規範からの逸脱を後押ししてしまうという、懸念されていた側面がデータで裏付けられた形です。その一方で、こちらも予想通り、モラル・アイデンティティが高い人ほど、非倫理的な行動には一貫して否定的な姿勢をとっていました。
この研究の核心は、これら二つの要因がどのように相互作用するかを分析した点にあります。組織への愛着が非倫理的行動を後押しする力は、すべての人に等しく働くわけではないことが判明しました。その力は、モラル・アイデンティティが「低い」従業員においてのみ、顕著に強く現れていたのです。言い換えれば、自分の中に確固たる道徳的な基準を持たない人ほど、組織への忠誠心を、不正を正当化するための都合の良いロジックとして用いやすいということです。
対照的に、モラル・アイデンティティが「高い」従業員の場合、たとえ組織への愛着が非常に強くても、それが非倫理的な行動につながることはありませんでした。そうした人々の中では、組織への愛着と非倫理的行動との間には統計的な関連が見られなかったのです。
この結果が描き出すのは、個人の心の中で繰り広げられる、一種の綱引きの構図です。組織への愛着は、「組織の目標達成を最優先せよ」という引力を持ちます。もし個人の心の中に、それに抗うだけのしっかりとした道徳的な軸、要するに強いモラル・アイデンティティがなければ、その引力のまま、「目標のためなら手段は問わない」という危険な領域へと足を踏み入れてしまいかねません。
しかし、強いモラル・アイデンティティは、その引力に対抗する「倫理的なブレーキ」として機能します。「私はこの組織を愛しているし、その成功を心から願っている。しかし、それ以上に、私は道徳的で公正な人間でありたい」という内なる声が、安易な逸脱を食い止め、倫理の砦を守ります。
過度なコミットメントが疲労・不正を引き起こす
「会社のために」と身を粉にして働くその献身的な姿勢は、多くの場面で賞賛の対象となります。しかし、組織への強い愛着が、時として自らを燃やし尽くす炎にもなりうることは、あまり語られません。コミットメントという「良きこと」も、度を超せば、働く人自身の心と体に代償を強いるだけでなく、巡り巡って組織にとっても望ましくない結果を招くことがあります。ここでは、行き過ぎたコミットメントがもたらす、心身への負担や倫理的なリスクについて、これまでの研究知見を整理しながら見ていきます[3]。
組織コミットメントの概念を整理した研究では、それが単一のものではないことが示されています。従業員の心の中には、組織が好きだという「情緒的コミットメント」の他に、この会社を辞めたら経済的に損をするという計算に基づく「存続的コミットメント」、そして自分にはこの組織に留まる義務があるという「規範的コミットメント」という、少なくとも三つの側面が共存しています。この中でも、核となるのは、組織への純粋な愛着を意味する情緒的コミットメントです。
この情緒的コミットメントが過剰になった場合に生じうる、四つの代表的な問題点が指摘されています。
一つ目は、「ワーク・ライフ・バランスの崩壊と心身の疲労」です。組織への愛着が人一倍強い従業員は、正規の勤務時間外であっても、仕事のことが頭から離れません。休日や深夜にも会社のメールをチェックし、無意識に仕事の段取りを考えてしまう。このように、仕事と私生活を心理的に切り離す「心理的ディタッチメント」が困難になると、心身が十分に休息・回復する機会が失われます。その結果、慢性的な疲労、睡眠障害、不安感などが蓄積し、最終的には感情が枯渇し、達成感が得られなくなる「バーンアウト」と呼ばれる状態に陥りやすくなります。この状態は、個人の幸福を損なうだけでなく、生産性の著しい低下や長期休職につながる、組織にとっても大きな損失です。
二つ目は、「対人関係における情緒的な傷つきやすさ」です。組織への思い入れが強い分、投資している心理的なエネルギーも大きくなります。そのため、職場で同僚から些細な無礼を受けたり、自分の貢献が上司から正当に評価されなかったりすると、他の人よりも深く傷つき、強い怒りや罪悪感、無力感を抱きやすくなります。こうしたネガティブな感情は精神的なエネルギーを消耗させ、仕事への集中力を奪い、時には同僚への不信感や攻撃的な態度といった「対人関係逸脱行動」につながることもあります。組織への愛が、かえって人間関係の摩擦を生むという皮肉な結果を招くのです。
三つ目は、「倫理観の麻痺と不正行為のリスク」です。これまでのところでも見てきたように、組織と自分自身を過度に同一視するようになると、いつしか「組織の利益は、すなわち自分の利益である」という考えに支配されます。その結果、組織を守るため、あるいは組織の目標を達成するためとあれば、非倫理的な手段を用いることへの心理的な抵抗が弱まってしまいます。この現象は「倫理的衰退」とも呼ばれ、倫理的な側面が意思決定の視野から消え去り、経済合理性や目標達成といった側面だけが強調される状態を指します。過剰なコミットメントは、倫理的衰退を加速させる危険な燃料となりえます。
四つ目は、「変化や革新への抵抗」です。現状の組織に対する愛着と肯定感が強すぎると、既存のやり方や文化、人間関係に固執し、外部からの批判的な意見や新しいアイデアを受け入れにくくなります。特に、同質性の高いメンバーが集まり、異論を唱えにくい雰囲気になると、「集団浅慮」と呼ばれる、極端で非合理的な意思決定がなされる危険性が高まります。過度にコミットした従業員は、無意識のうちに現状維持の「番人」となり、組織が環境変化に対応して自己変革を遂げていく上での足かせとなりかねません。
これらの問題が生じる背景には、いくつかの心理的なメカニズムがあります。例えば、「資源保存理論」という考え方では、人は自らの時間やエネルギーといった資源を投入し、それに見合う報酬(承認や達成感など)が得られることでバランスを保ちますが、過剰なコミットメントを持つ人は資源を一方的に注ぎ込み続け、やがて枯渇してしまうと説明されます。また、「社会的アイデンティティ理論」では、組織への帰属意識が自己概念の中核を占めるようになると、客観的な判断力を失い、組織を守ることが自己を守ることと同義になってしまうとされています。
脚注
[1] Qazi, S., Naseer, S., and Syed, F. (2019). Can emotional bonding be a liability? Status striving as an intervening mechanism in affective commitment and negative work behaviors relationship. European Review of Applied Psychology, 69(4), 100473.
[2] Matherne, C. F., III, and Litchfield, S. R. (2012). Investigating the relationship between affective commitment and unethical pro-organizational behaviors: The role of moral identity. Journal of Leadership, Accountability and Ethics, 9(5), 35-46.
[3] Johnson, C. W., III. (2024). Too much of a good thing? Exploring affective commitment’s negative impact. The Scholarship Without Borders Journal, 2(2), 4.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。