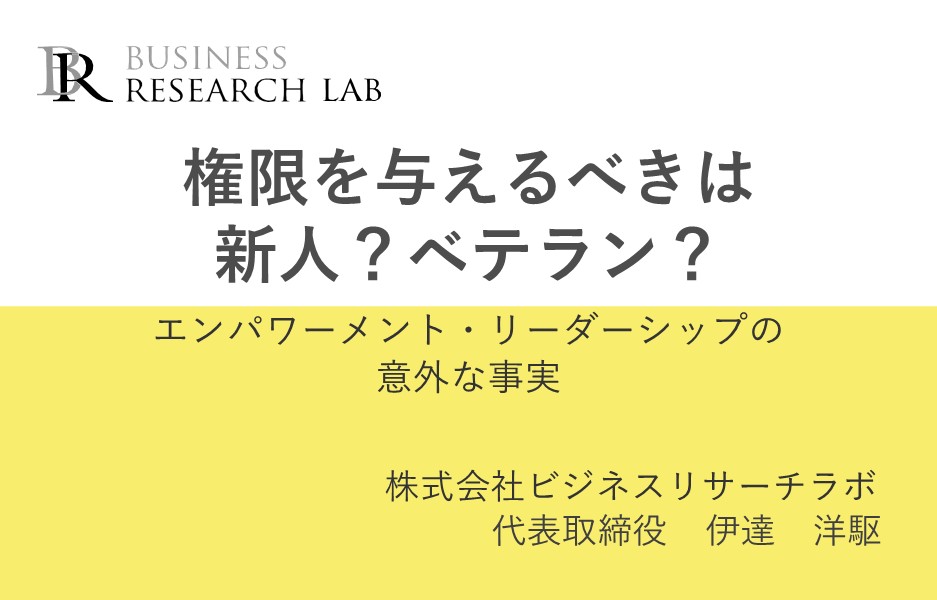2025年11月6日
権限を与えるべきは新人?ベテラン?:エンパワーメント・リーダーシップの意外な事実
従来の上意下達型マネジメントから脱却し、従業員に裁量権を委ねるエンパワーメント・リーダーシップが脚光を浴びています。このリーダーシップスタイルは、部下に権限を与え、自律的な判断と行動を促すものですが、果たして本当に業績向上につながるのでしょうか。
実は、エンパワーメント・リーダーシップの効果は一律ではありません。どのような人に、いつ、どのような形で権限を付与するかによって、その成果は異なります。経験の浅い営業担当者には大きな売上向上をもたらす一方で、ベテランには逆効果になることもあります。チーム発達の初期段階では指示型リーダーシップが優位でも、時間が経つにつれてエンパワーメント型が逆転勝利を収めることもあります。
本コラムでは、エンパワーメント・リーダーシップの効果について、四つの異なる視点から解説します。営業個人のレベルから、チーム内の時間的変化、多層的な組織構造、共有型リーダーシップまで、幅広い角度から検証された知見を通じて、このリーダーシップスタイルが持つ可能性と限界を明らかにしていきます。
権限付与は経験浅い営業の売上を高める
エンパワーメント・リーダーシップの効果を理解するには、個人レベルでの検証から始める必要があります。アメリカの大手製薬企業で実施された調査は、営業現場における権限付与の効果を明らかにしました[1]。
この研究では、女性医療部門の営業担当254名を対象に、リーダーの権限付与行動が営業成果にどのような変化をもたらすかを追跡しました。権限付与行動は四つの側面から捉えられました。仕事の意味づけを強化すること、意思決定への参加を促進すること、高い業績への自信を表明すること、官僚的な制約を取り除くことです。調査には営業担当者231名が回答しました。
研究者たちは営業担当者の自己報告だけでなく、864名の顧客満足データと会社の実績記録(売上クオータ達成率)を収集し、客観的な評価を実現しました。研究の結果、権限付与リーダーシップは営業担当者のセルフエフィカシー(自己効力感)とアダプタビリティ(適応的販売行動)の両方を高めることが判明しました。
業績向上のメカニズムはさらに複雑です。セルフエフィカシーが高まった営業担当者は、アダプタビリティを向上させ、最終的に売上パフォーマンスを向上させました。一方、アダプタビリティの向上は顧客満足度を押し上げ、その顧客満足度が売上パフォーマンスを向上させるという連鎖反応が確認されました。
権限付与の効果は、営業担当者の経験や知識のレベルによって異なりました。研究者たちが「エンパワーメント準備性」と呼んだこの要素との交互作用を分析した結果、権限付与リーダーシップの効果は経験の浅い営業担当者で最も強く現れることが明らかになりました。
準備性の低い営業担当者では、権限付与がセルフエフィカシーとアダプタビリティの両方を大幅に向上させました。ところが、経験豊富で知識レベルの高い営業担当者では、権限付与の効果がほぼゼロか、場合によっては負の効果すら観察されました。
この発見は従来の常識を部分的に覆すものです。多くの管理職は、熟練した部下ほど権限を与えるべきだと考えるかもしれません。しかし実際には、経験の浅い営業担当者こそが権限付与から恩恵を受けることが実証されたのです。
研究結果を踏まえると、権限付与リーダーシップは経験の浅い営業担当者にとって能力開発の手段として機能することがわかります。権限を与えられることで、自信を獲得し、顧客との相互作用から学習し、状況に応じて販売手法を調整する能力が向上するのです。一方、ベテラン営業担当者は既に高いスキルと自信を持っているため、追加的な権限付与から得られる利益は限定的であり、場合によっては既存の効率的な行動パターンを混乱させる可能性もあります。
指示型は序盤優位、権限付与型が終盤で業績逆転
チームにおけるリーダーシップの効果は、時間の経過とともに変化します。この動的な側面を調査した研究では、指示型リーダーシップと権限付与型リーダーシップの効果が時間とともにどのように推移するかを明らかにしました[2]。
研究はアメリカの大規模大学で実施され、上級学部生300名を60の5人チームに編成して行われました。各チームは3時間にわたるネットワーク型ビジネスシミュレーション「リーダーシップ開発シミュレーター」に取り組み、10ラウンドの意思決定を通じて得点を競いました。このシミュレーションは複雑な経営判断を模擬したもので、チームメンバー間の協力と学習が成果を左右する設計となっていました。
実験の核心は、各チームのリーダーに事前に異なる行動スクリプトを提供し、指示型と権限付与型のリーダーシップをランダムに割り当てたことです。指示型リーダーは職位権限を背景に指示と期待を部下に伝える一方、権限付与型リーダーは権限委譲と参加的意思決定を促進しました。このような実験統制により、他の要因を排除してリーダーシップスタイルの効果を測定することが可能になりました。
研究者たちはチーム発達理論に基づき、10ラウンドを二つの期間に分割しました。第1ラウンドから第5ラウンドまでを「形成・編成期」、第6ラウンドから第10ラウンドまでを「チーム編成期」と定義し、各期間でのパフォーマンスを比較しました。
結果は研究者の予想を裏付けるものでした。形成・編成期では、指示型リーダーシップを受けたチームの平均得点が権限付与型チームを有意に上回りました。この初期優位は、明確な指示と役割分担が不慣れなタスクに対する効率的な取り組みを可能にしたためです。メンバーは何をすべきかを迷うことなく、与えられた指示に従って行動できました。
しかし、時間が経過するにつれて状況は変化しました。チーム編成期に入ると、権限付与型リーダーシップを受けたチームの得点向上率が指示型チームを上回るようになりました。統計分析では、時間とリーダーシップスタイルの交互作用が有意であり、権限付与型チームの得点勾配がより急峻であることが確認されました。
この逆転現象の背景には、四つのメカニズムが働いていました。第一に、チーム学習の促進です。権限付与型リーダーシップは、メンバーが試行錯誤を通じて学習することを奨励し、その結果として継続的な改善が実現されました。
第二に、行動的協調の発達です。権限を与えられたチームメンバーは、互いの行動を調整し、効率的な協働パターンを構築しました。
第三に、心理的エンパワーメントの醸成です。メンバーが意思決定に参加し、自らの判断で行動できることで、仕事に対する主体性と責任感が向上しました。この心理的変化も業績向上に寄与したことが統計的に確認されました。
第四に、チームメンタルモデルの共有です。権限付与型環境では、メンバー間でタスクへの理解と戦略が共有され、一体となった行動が可能になりました。これらの媒介変数を統計モデルに投入すると、時間とリーダーシップの交互作用効果が大幅に減少し、これらのメカニズムが逆転現象を説明することが裏付けられました。
一方、指示型リーダーシップは初期の効率性をもたらしましたが、学習と協調の発達を阻害する副作用がありました。継続的な指示への依存は、メンバーの自主的な学習意欲を削ぎ、創造的な問題解決を制限しました。その結果、初期の優位性は時間とともに失われ、最終的に権限付与型チームに追い抜かれることになったのです。
多層的リーダーシップが権限付与を通じ成果を高めた
現実の職場では、個人とチームという複数のレベルでリーダーシップが同時に作用しています。この複雑な現象を解明するため、アメリカの大手ホームセンターで実施された調査は、多層的なリーダーシップの効果を検証しました[3]。
研究は31店舗から62チーム、445名のメンバー、62名の内部リーダー、31名のマネジャーが参加する大規模なものでした。調査対象となったのは、フレイト(配送・在庫管理)とレシービング(受入・検品)という二種類の業務チームです。これらの業務は相互依存性のレベルが異なり、フレイトチームでは高度な連携が求められる一方、レシービングチームでは比較的独立した作業が中心でした。
個人レベルとチームレベルの両方でリーダーシップと心理的エンパワーメントを同時に測定し、その相互作用が検討されました。個人レベルでは、リーダーと部下の関係の質を表すLMXに基づく測定が行われました。一方、チームレベルでは、リーダーシップ風土(チーム全体への権限付与行動の共有認識)が評価されました。
心理的エンパワーメントについても、個人の主体性と有能感を測る個人版と、チーム全体の集合的な効力感を捉えるチーム版の両方が測定されました。パフォーマンスは、個人については直属リーダーによる評価、チームについては外部マネジャーによる評価を用いることで、評価の客観性を確保しました。
研究結果は、多層的リーダーシップのメカニズムを明らかにしました。まず、同一レベル内での媒介効果が確認されました。個人レベルでは、LMXが個人の心理的エンパワーメントを高め、それが個人パフォーマンスの向上につながりました。チームレベルでは、リーダーシップ風土がチームの心理的エンパワーメントを促進し、チームパフォーマンスを向上させました。
しかし、より面白いのは異なるレベル間の効果でした。チームレベルのリーダーシップ風土は、個人レベルのLMXとチーム心理的エンパワーメントを通じて、個人の心理的エンパワーメントに間接的な正の効果を及ぼしました。これは、チーム全体に権限付与的な雰囲気があることで、個々のメンバーも自分自身がエンパワーされていると感じやすくなることを意味します。
さらに、リーダーシップ風土とLMXの交互作用も認められました。チーム全体に権限付与的な雰囲気が強いほど、個人とリーダーとの良好な関係が個人の心理的エンパワーメントに与える効果が増大しました。この結果は、個人的な関係とチーム環境が相乗効果を生むことを示しています。
一方で、高相互依存性のチームでは意外な現象も観察されました。チームの心理的エンパワーメントが高い状況では、個人の心理的エンパワーメントと個人パフォーマンスの関係が弱まる負の交互作用が確認されました。チーム全体が強くエンパワーされている状況では、個人のエンパワーメント感覚の重要性が相対的に低下することを示唆しています。
業務の相互依存性は、これらの効果の調整要因でした。フレイトチームのような高相互依存業務では、モデル全体の効果が一貫して強く確認されました。メンバー間の密接な協力が必要な業務では、リーダーシップの多層的効果がより顕著に現れるのです。反対に、レシービングチームのような低相互依存業務では、一部の関係が不成立となり、個人レベルの効果が主要となりました。
共有型リーダーシップが変革チーム成果を高め指名型を凌駕
従来のリーダーシップ研究は、指名された一人のリーダーが組織を牽引するという前提に立っていました。しかし、組織がフラット化し、自律的なチームワークが求められる現代では、メンバー間で影響力を分散させる共有型リーダーシップという概念が登場しています。このアプローチの効果を検証した研究は、変革管理チームにおける結果を明らかにしました。
研究はアメリカの大手自動車メーカーで実施され、71の変革管理チーム(平均7.2名)が対象となりました[4]。これらのチームは、生産プロセスの改善や組織変革を担当する専門チームで、高度な創造性と問題解決能力が求められていました。研究者たちは6か月間にわたってこれらのチームを追跡し、リーダーシップの源泉がチーム有効性にどのような効果をもたらすかを分析しました。
研究の独創性は、リーダーシップを縦型(指名リーダーによる)と横型(メンバー間の共有)という二つの源泉に分け、それぞれを五つの行動タイプで評価したことです。アヴァーシブ(威圧的)、ディレクティブ(指示的)、トランザクショナル(取引的)、トランスフォーメーショナル(変革的)、エンパワリング(権限付与的)という五つのタイプにより、リーダーシップ行動を包括的に捉えました。
その結果、縦型リーダーシップも横型リーダーシップも、ともにチーム有効性と有意な関連を示しましたが、説明力の比較では横型リーダーシップが優位でした。横型リーダーシップを統計モデルに投入すると決定係数が有意に増加する一方、その後に縦型リーダーシップを追加しても決定係数の有意な増加は見られませんでした。
行動タイプ別の分析では、詳細な知見が得られました。アヴァーシブとディレクティブな行動は、予想通りチーム有効性と負の関連を示しました。威圧的な態度や一方的な指示は、変革チームの創造性と自律性を阻害することが確認されました。特にチーム自己評価では、この負の効果が顕著に現れました。
一方、トランスフォーメーショナルな行動は、マネジャー評価、内部顧客評価、チーム自己評価のすべてで正の関連を示しました。ビジョンの提示、知的刺激、個別配慮といった変革的行動は、チームの成果向上に寄与することが実証されました。エンパワリング行動も、チーム自己評価で正の関連を示し、権限付与がメンバーの満足感と主体性を高めることが確認されました。
トランザクショナルな行動は有意な効果を示しませんでした。報酬と処罰による管理は、創造的な変革活動には適さないことが示唆されます。
研究では、高業績チームの特徴についても分析が行われました。成果の高いチームほど、リーダーシップの総量自体が多く、かつ横型リーダーシップの比率が高いという傾向が観察されました。優秀なチームでは多くのメンバーがリーダーシップを発揮し、相互に影響し合っていることを意味します。
脚注
[1] Ahearne, M., Mathieu, J. E., and Rapp, A. (2005). To empower or not to empower your sales force? An empirical examination of the influence of leadership empowerment behavior on customer satisfaction and performance. Journal of Applied Psychology, 90(5), 945-955.
[2] Lorinkova, N. M., Pearsall, M. J., and Sims, H. P. Jr. (2013). Examining the differential longitudinal performance of directive versus empowering leadership in teams. Academy of Management Journal, 56(2), 573-596.
[3] Chen, G., Kirkman, B. L., Kanfer, R., Allen, D., and Rosen, B. (2007). A multilevel study of leadership, empowerment, and performance in teams. Journal of Applied Psychology, 92 (2), 331-346.
[4] Pearce, C. L., and Sims, H. P., Jr. (2002). Vertical versus shared leadership as predictors of the effectiveness of change management teams: An examination of aversive, directive, transactional, transformational, and empowering leader behaviors. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 6(2), 172-197.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。