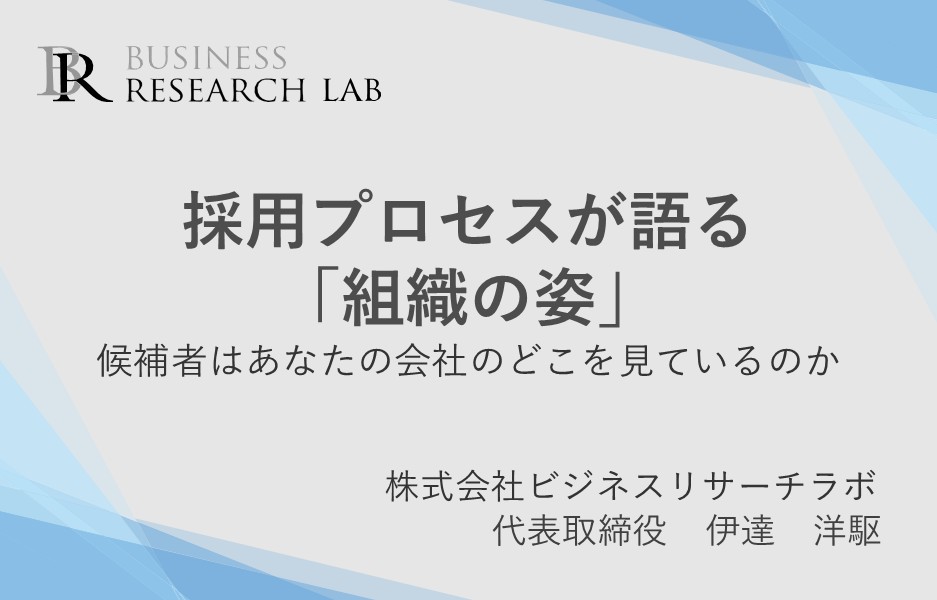2025年11月6日
採用プロセスが語る「組織の姿」:候補者はあなたの会社のどこを見ているのか
企業の人材採用において、書類選考から内定出しまでの一連のプロセスは、選考作業以上の意味を持っています。候補者にとって採用プロセスは、その企業で働くことになった場合の日常を垣間見る機会であり、組織文化や働きやすさを推測する手がかりとなるからです。
近年の労働市場では、優秀な人材の獲得競争が激化しており、企業側が候補者を選ぶだけでなく、候補者も企業を選ぶ時代となっています。このような状況で、採用プロセスにおける企業の対応は、候補者の心理や行動に想像以上に大きな効果をもたらすことが、数多くの研究から明らかになってきました。
面接官の第一印象に基づく態度の変化、採用担当者からの連絡タイミングや対応の質、そして企業が発信する情報の内容や伝え方。これらすべてが、候補者の企業に対する評価や最終的な就職先選択に関わっています。本コラムでは、採用現場で行われた調査研究の結果を通じて、採用プロセスの初期段階における対応や情報提供が、いかにして候補者の意思決定を左右するのかを探っていきます。
候補者の心理メカニズムを理解することで、なぜ優秀な人材が他社に流れてしまうのか、どのような採用体験が候補者の心に響くのかといった疑問への答えが見えてくるでしょう。採用の成功は、良い人材を見極めることだけでなく、その人材に「この会社で働きたい」と思ってもらえるかどうかにかかっています。
第一印象が面接官の支持的応対とラポールを高める
人と人との出会いにおいて第一印象が後の関係性を左右することは、日常生活でも実感として理解されていますが、採用面接という場面でも同様の現象が起こることが実証されています。アメリカの大手企業で実施された調査では、面接官が候補者に対して抱く最初の印象が、その後の面接中の行動や態度にどのような変化をもたらすのかが分析されました[1]。
この調査は、企業の本社で実際に行われた79件の採用面接を対象とし、3名の経験豊富な面接官の行動を録音により記録したものです。面接官たちは多様な職種の候補者と平均約30分の自由形式面接を行いました。研究の核心は、面接が始まる前に面接官が応募書類や職能テストの結果を見て形成した第一印象と、実際の面接中における面接官の行動パターンとの関係を明らかにすることでした。
面接前の第一印象は、応募書類の内容と職能テストの得点を9段階で評価することで測定されました。一方、面接中の行動については、支持的な質問の数、励ましの言葉、友好的な態度、笑いの回数といったポジティブな対応から、会社や職務の説明に費やす時間、情報提供の量、資格を確認する質問の頻度まで、多岐にわたる要素が記録されました。3名の訓練を受けた学生が音声を聞き取り、様々な行動指標を数値化しました。
分析の結果、応募書類に基づいて好ましい第一印象を持った面接官は、面接中に異なる行動パターンを示すことが判明しました。好印象を抱いた候補者に対しては、支持的な質問を多く投げかけ、友好的なスタイルで接し、声調もポジティブになる傾向が統計的に有意に確認されたのです。
好印象を持った候補者に対して、面接官は「会社・仕事のセリング」活動を活発に行いました。面接官は好感を持った候補者により多くの職務情報を提供し、会社の魅力を積極的に伝えようとする行動を取りました。この現象は、面接官が無意識のうちに「この候補者に来てもらいたい」という気持ちになり、採用側から候補者への働きかけを強化することを意味しています。
一方で、面接時間そのものについては予想と異なる結果が得られました。好印象を持った候補者に対して面接官が余分な時間を割くという証拠は見つかりませんでした。面接官は好感を持った候補者に対してより長時間をかけて評価するのではなく、限られた時間の中での対応の質や内容を変化させることを示唆しています。
質問戦略についても興味深いパターンが観察されました。好印象を持った候補者に対しては、質問の総数やクローズドエンドの質問数が減少する傾向が見られました。面接官が既に良い評価を下しており、追加的な情報収集よりも関係構築や情報提供に重点を置くようになることを表しています。
候補者自身の行動にも変化が現れました。面接官から好印象を持たれた候補者は、コミュニケーションスタイルがより積極的になり、面接官との間により良いラポール(信頼関係)を築く傾向が見られました。「双方向の自己成就予言」とでも呼べる現象が起きていることを表しています。候補者は面接官の好意的な態度を敏感に察知し、それに応えるようにより良いパフォーマンスを発揮するのです。
迅速丁寧な採用対応が就職選択を左右する
採用活動が候補者の最終的な就職選択にどの程度の力を持つのかという問いに対して、1980年代後半までの研究は概して悲観的な答えを提示していました。多くの量的調査やメタ分析は「採用活動は候補者の就職選択にほとんど関係ない」という結論を導き出していたのです。しかし、この結論に疑問を持った研究者たちが、従来とは異なるアプローチで採用活動の本当の力を探ろうと試みました。
この研究は、アイビーリーグ系大学の卒業予定者41名を対象として、1月末から5月初旬にかけて継続的に追跡調査を行ったものです[2]。対象者は学部から大学院まで、文理・工学・ビジネス・労務系の4学部から多様性を確保して選出されました。従来の研究が面接直後の一時点での質問紙調査に依存していたのに対し、この研究は求職活動の全期間を通じて候補者の生の声を聞き取ることに重点を置きました。
調査方法として採用されたのは半構造化インタビューで、各参加者に対して就職活動期間中に2回、各20分から60分という時間をかけて聞き取りが行われました。最初のインタビューはキャンパス面接が盛んに行われる1月末から2月にかけて、2回目は内定が出そろい始める3月末から5月初旬に実施されました。
この聞き取り調査から浮かび上がってきたのは、従来の研究では見落とされていた採用活動の複雑で多面的な力でした。候補者たちの語りからは、採用プロセスが単なる選考手続きではなく、企業の姿を垣間見る機会として受け止められていることが明らかになりました。
候補者が企業に対して抱く初期印象の形成において、採用関係者の存在が大きな位置を占めていることが判明しました。全ての候補者が仕事内容や企業特性を初期評価の根拠に挙げたのは当然でしたが、41名中12名がリクルーターの行動を、9名が社内の知人を好印象の根拠として挙げていました。これは採用担当者や社員が企業の「顔」として機能していることを意味しています。
より興味深いのは、初期の好印象が採用プロセスの展開によって失われていく様子でした。23名の候補者が、リクルーターの対応や面接体験を理由に企業への評価を下げており、過度な売り込みや失礼な態度が悪印象を生み出していることが明らかになりました。候補者たちは企業の採用担当者の一挙手一投足を通じて、その企業の組織文化や職場環境を推測しており、ネガティブなシグナルに対して敏感に反応していました。
中でも深刻な問題として浮上したのは、フォローアップの遅延でした。41名中39名という多数の候補者が「極端に遅いフォロー」を経験しており、この遅延が候補者の企業評価に与える打撃は予想を上回るものでした。成績上位で複数の内定を獲得できる候補者ほど、遅いレスポンスを「組織の無能さ」の証拠として解釈し、興味を失う傾向が顕著でした。一方、内定獲得数が少ない候補者は、遅延を「自分が二軍扱いされている」サインと受け取り、自己評価を下げてしまうという異なるパターンの悪影響が確認されました。
この遅延の問題は、企業訪問の招待辞退という行動として現れました。28名が訪問招待を辞退しており、その理由として最も多く挙げられたのが「日程が遅すぎる」(20名)でした。遅延は候補者に他社の選択肢を検討する時間を与えることになり、優秀な人材の流出を招く要因となっていました。
リクルーターが果たす機能についても発見がありました。「優秀なリクルーターや問題のあるリクルーターが内定受諾意向に影響するか」という質問に対して、多くが「強く・ある程度影響する」と答えました。候補者がリクルーターに求めていたのは個人的な魅力ではなく、「その人物がどれだけ組織文化を代表していると見なせるか」という代表性でした。業務部門出身者や将来の同僚となる人物は、強力な組織シグナルとして機能していることが明らかになりました。
候補者の属性による反応の違いも重要です。女性候補者はリクルーターの行動や社内の女性管理職の有無に敏感で、性差別的な示唆があると企業を即座に除外する傾向が見られました。一方、実務経験を持つ候補者はキャンパスリクルーターを重視せず、職務内容で判断する傾向が強いことも確認されました。
この研究が明らかにした含意は、採用プロセスが「見えない組織特性」を示唆する代理情報源として機能しているという点です。候補者は限られた情報の中で企業の姿を推測せざるを得ず、採用担当者の対応や手続きの進め方を通じて組織の能力や文化を判断しています。特に情報が不足している段階や、実際に働くことになる部門の担当者との接触時に、この代理情報としての効果が最大化されることが示されました。
仕事内容と組織環境は応募意図を促すが就職選択には響きにくい
採用分野では長年にわたって数多くの個別研究が蓄積されてきましたが、それらの結果を包括的に統合し、全体像を把握する試みは限られていました。そこで、1950年代以降に発表された膨大な研究を定量的に統合し、候補者の意思決定プロセスを解明しようとするメタ分析が実施されました[3]。
この統合研究では、まず文献の網羅的な探索が行われました。主要データベースでの検索、既存のレビュー論文の参考文献追跡、主要学会での発表論文の調査、そして専門研究者への直接照会という4段階のプロセスを経て、計298件の関連研究が同定されました。この中から統計情報が十分に報告されている71研究が最終的な分析対象として選出されました。
分析の枠組みとして、候補者の反応を4つの段階に分類することが採用されました。「魅力度評価」「応募継続意図」「受諾意図」「実際の就職選択」という段階的な意思決定プロセスを想定し、それぞれに対してどのような要因がどの程度の強さで関連しているかが検証されました。
分析結果は、採用活動の効果が意思決定の段階によって異なることを示しました。応募継続意図の段階では「仕事内容」が最も強い効果を示しました。同様に「組織イメージ」も強い関連を示し、これらの要因が候補者の興味を引きつける段階では有効であることが確認されました。リクルーターの友好性も大きな効果を持っており、人間関係的な要素が初期段階では重要な意味を持つことが明らかになりました。
組織に対する魅力度評価では「職場環境認知」が最大の効果を示し、次いで組織イメージ、P-Oフィット、手続きの公正性に対する知覚が続きました。候補者は単に仕事の内容だけでなく、働く環境の質や自分との適合性を総合的に評価していることが裏付けられました。
受諾意図の段階になると、パターンは継続しつつもより具体的になります。ジョブ・組織特性全体の効果が突出して高く、中でも職場環境、仕事タイプ、能力発揮機会を提供する手続きへの知覚が顕著な効果を示しました。パーソン・ジョブフィットも中程度の効果を持つ一方で、代替機会の認知は統計的に有意な関連を示しませんでした。
実際の就職選択段階での結果は注目に値します。これまでの段階で強い効果を示していた要因の多くが、実際の選択行動に対してはわずかな効果しか持たないことが明らかになったのです。最大でも採用される期待程度の効果しかありませんでした。
候補者のタイプによる違いも重要な発見でした。実際の候補者は「仕事特性」や「公正知覚」を意思決定でより重視し、受諾意図に対して「組織特性」の効果も大きくなることが確認されました。実験室で想定的な状況を考える参加者と、実際に就職先を決めなければならない候補者との間には、心理的な違いがあることを示唆しています。
この大規模な分析が明らかにしたのは、候補者の意思決定プロセスが単純な一本道ではなく、複数の経路が並行して存在する複雑なシステムであるということです。初期段階では人間関係的要素や印象的要素が強い力を持つものの、最終的な選択段階では実質的な仕事内容や組織特性がより決定的な要因となる構造が浮き彫りになりました。
脚注
[1] Dougherty, T. W., Turban, D. B., and Callender, J. C. (1994). Confirming first impressions in the employment interview: A field study of interviewer behavior. Journal of Applied Psychology, 79(5), 659-665.
[2] Rynes, S. L., Bretz, R. D., Jr., and Gerhart, B. (1991). The importance of recruitment in job choice: A different way of looking. Personnel Psychology, 44(3), 487-521.
[3] Chapman, D. S., Uggerslev, K. L., Carroll, S. A., Piasentin, K. A., and Jones, D. A. (2005). Applicant attraction to organizations and job choice: A meta-analytic review of the correlates of recruiting outcomes. Journal of Applied Psychology, 90(5), 928-944.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。