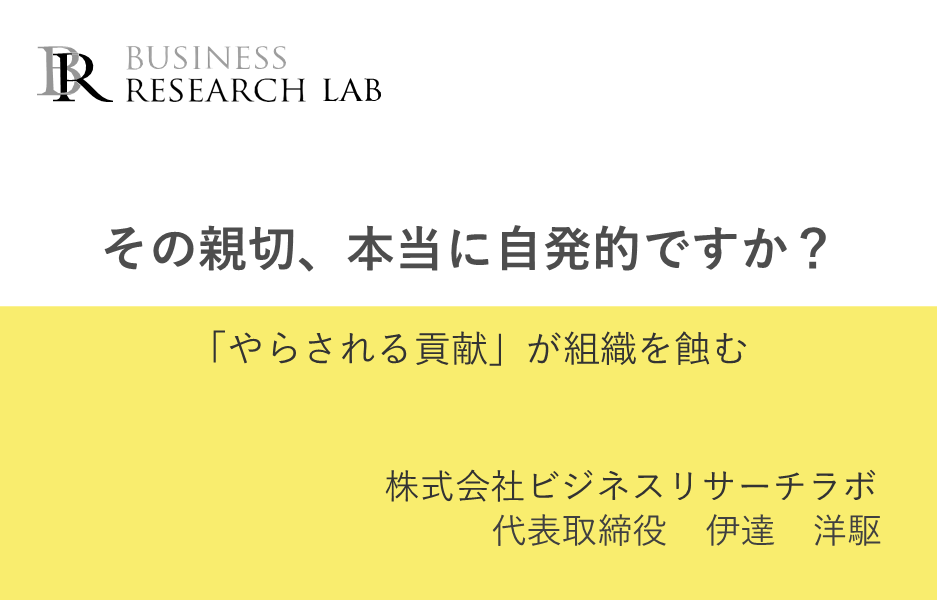2025年11月5日
その親切、本当に自発的ですか?:「やらされる貢献」が組織を蝕む
職場で「いい人」として認められたい、組織に貢献したいと思う気持ちは、働く人が抱く自然な感情です。残業時間に同僚の仕事を手伝ったり、会社のイベントに自主的に参加したり、困っている新人を教えたり。こうした「本来の仕事以上のこと」をする行動は、組織市民行動と呼ばれ、職場における模範的な行動として評価されてきました。
しかし、最近の研究では、この「善意の行動」が必ずしも従業員の自発的な意思から生まれているわけではないことが明らかになってきました。上司からの暗黙の期待、職場の雰囲気による圧力、同僚との競争意識。これらが原因で、本来は任意であるはずの「親切な行動」が、実際には「やらざるを得ない行動」に変わってしまうケースが報告されているのです。
本コラムでは、組織市民行動が強制された時に何が起こるのかを、複数の研究をもとに検討していきます。善意から始まった行動が、どのようにして従業員のストレスや離職意図を高め、組織全体にとってもマイナスの結果をもたらすのか。そのメカニズムを解説していきます。職場で「いい人」でいることの代償について、新たな視点から考えてみませんか。
組織市民行動の「強制」は、負の影響を生む
職場で求められる行動には、明確に定められた職務と、それを超えた自主的な行動の二種類があります。後者は組織市民行動と呼ばれ、同僚を助ける利他的行動、真面目に仕事に取り組む誠実性、不満を言わずに耐える寛容さ、他者への気遣いを表す礼儀正しさ、会社行事への参加といった市民的美徳などが含まれます。これらの行動は必ずしも報酬の対象ではありませんが、組織の効率性や生産性向上に寄与するとされてきました。
しかし、ある研究者によって提唱された新しい概念が、この前提に疑問を投げかけました[1]。それが「強制的市民行動」という考え方です。この概念は、従業員が本来やりたくない任務を上司や同僚の圧力により、無報酬で実施せざるを得ない状況を指しています。管理職が従業員の善意を悪用し、本来任意であるはずの行動を強制することで生まれる現象です。
この研究が生まれた背景には、従来の組織市民行動研究が持つ問題がありました。それまでの研究は、組織市民行動が自発的かつ善意に基づいて行われるものであり、組織の効率や職場環境に肯定的な作用をもたらすという二つの前提に立っていました。しかし、現実の職場では、職務の定義が曖昧な状況が多く、自発的な組織市民行動と強制的な組織市民行動の境界が不明確になることがあります。
問題は、管理職がこの曖昧さを意図的に利用することです。非公式な行動を職務の一部に組み入れ、従業員に対して心理的な圧力をかけるのです。「チームのために」「会社の将来のために」といった大義名分のもとで、実際には強制的な行動を求められる従業員が増えている可能性があります。
研究では、この強制的市民行動が従業員にもたらす悪影響について、5つの仮説が提示されました。第一に、強制的市民行動は職場において広く存在し、多くの従業員が個人的に経験していること。第二に、強制的市民行動は従来の自発的な組織市民行動や通常の職務内行動とは異なる独自の行動として位置づけられること。第三に、強制的市民行動は従業員の仕事ストレス、組織内政治の知覚、離職意図、不注意や怠慢行動、バーンアウトを増加させること。第四に、強制的市民行動は仕事満足度、革新的行動、自発的な組織市民行動、正式な職務内評価を低下させること。第五に、強制的市民行動は、職務への参加や自主性といった他の変数を考慮しても、仕事の結果に対して独自の説明力を持つことです。
これらの仮説は、従来の組織市民行動に対する理解を見直す必要性を示しています。善意から始まった行動が、外部からの圧力によって強制されると、その性質は変わってしまいます。侮辱的管理や強制的説得といった既存理論とも関連付けられ、管理職や同僚が強い心理的圧力を用いて従業員に非自発的な行動を強いる状況の深刻さが浮き彫りになりました。
この研究の意義は、組織市民行動の本来の定義に潜む問題を明らかにしたことにあります。職務の範囲を明確にし、自発的行動と職務内行動の境界を明確化することの必要性、従業員が業務過多を感じた際に自由に発言できる環境の整備、組織内における公平性とコミュニケーションの向上といった課題が、より鮮明に見えてきました。
組織市民行動、強制されればストレスや離職意図増
理論的な提案だけでなく、実際のデータによって強制的市民行動の影響を検証した研究が発表されました。この研究は、イスラエルの学校教員206名とその上司である校長13名を対象に実施され、強制的組織市民行動の実態とその悪影響を明らかにしました[2]。
調査では、従業員が感じる強制的市民行動を測定するために尺度が開発されました。「私は自分の意志に反して、公式の義務を超えて他の教師を支援することを強要されている」といった質問項目を用いて、教員たちの実際の体験を数値化しました。同時に、仕事のストレス、バーンアウト、組織政治、怠慢行動、離職意図、革新性、職務満足度、グループレベルでの組織市民行動、個人レベルでの組織市民行動、正式な職務遂行能力なども測定されました。
調査結果としては、調査対象者の75%以上が、強制的市民行動に該当するようなプレッシャーを職場で経験していると報告しました。職場における強制的市民行動が例外的な現象ではなく、多くの従業員が日常的に直面している問題であることを物語っています。
統計分析により、強制的市民行動が従来の自発的な組織市民行動や正式な職務行動とは区別される独立した概念であることが確認されました。これらの行動が別々の次元で捉えられることが実証されたのです。
強制的市民行動は従業員の心理状態と行動に負の作用を与えていました。強制的市民行動を多く経験する教員ほど、仕事のストレスが高く、バーンアウトの程度が深刻で、組織内政治を強く感じ、離職意図が高く、怠慢行動を取りがちであることが明らかになりました。
一方で、強制的市民行動は従業員の前向きな行動や態度を阻害することも分かりました。革新的な取り組みへの意欲、職務に対する満足感、チーム全体での協力的行動、正式な職務の遂行能力すべてが、強制的市民行動の増加に伴って低下していました。
これらの関係性は、従業員の教育レベル、職務の自主性、意思決定への参加度合いといった他の要因を取り除いた後でも有意に残りました。このことは、強制的市民行動が単独で従業員の行動や態度に悪影響を与えていることを意味します。
研究の考察部分では、この結果が持つ理論的意義について論じられています。従来の組織市民行動研究が前提としてきた「組織市民行動は常に良いもの」という理解に対して、この研究は修正を迫っています。組織市民行動が上司や組織によって悪用・強制されることで、従業員の精神的健康や仕事への満足感が損なわれるリスクがあることが、実証的なデータによって裏付けられました。
この発見は、職場における「善意の行動」の複雑さを浮き彫りにしています。表面的には同じように見える「同僚を助ける行動」や「会社行事への参加」でも、それが自発的に行われるか強制的に行われるかによって、従業員への影響は正反対になってしまうのです。組織は、従業員の善意を利用するのではなく、健全で持続可能な協力関係を築くことの大切さを、この研究は教えてくれています。
組織市民行動の圧力は、行動を促すが弊害も
組織市民行動に関する研究は、さらに複雑な側面を明らかにしました。ある研究では、「市民的行動の圧力(Citizenship Pressure)」という新しい概念が導入され、この圧力が従業員の行動に与える二面性が調査されました[3]。245人のフルタイム従業員を対象とした3週間間隔の2回調査により、組織市民行動への圧力が持つ複雑な影響が見えてきました。
この研究が着目したのは、多くの組織が従業員を「良い兵士」として扱い、組織市民行動を非公式に推奨している現実でした。組織は公式には報酬を与えないものの、従業員が職務を超えた貢献をすることを暗黙のうちに期待しています。この期待が強くなると、本来は任意であるはずの組織市民行動が「行わざるを得ないもの」として従業員に認識されるようになります。
研究では、この市民的行動の圧力が従業員に与える複数の影響を調査しました。圧力と実際の組織市民行動との関係について調べると、予想通り圧力が高い従業員ほど実際に組織市民行動を多く行っていることが分かりました。組織の期待は従業員の行動を変化させているのです。
しかし、この関係には個人の特性や状況による違いがありました。特に興味深いのは、誠実性の低い従業員ほど圧力による行動変化が大きいことでした。通常、誠実性の高い人は自発的に責任感のある行動を取りますが、誠実性の低い人は外部からの圧力がなければそうした行動を取らない傾向があります。結果、組織からの圧力は、本来であれば組織市民行動を行わない人たちの行動を変化させる作用を持っていることが明らかになりました。
家庭の責任についても同様の結果が得られました。独身者や子どもの少ない従業員は、圧力が高まるにつれて組織市民行動を増加させました。家庭での責任が少ない人ほど、職場での期待に応えようとする行動が顕著に現れるのです。
一方で、この研究が重要視したのは、市民的行動の圧力が従業員に与える負の影響でした。圧力を感じる従業員は、仕事と家庭生活の間で葛藤を経験していることが分かりました。本来の職務に加えて組織市民行動も期待されることで、時間的・精神的な負担が増加し、家庭での時間や責任とのバランスを取ることが困難になるのでしょう。
同様に、仕事と余暇時間との葛藤も深刻化していました。組織市民行動への圧力は、従業員の私的な時間を侵食し、個人的な興味や趣味、休息に充てる時間を奪っています。長期的に見ると、これは従業員の精神的健康や生活の質に深刻な影響を与える可能性があります。
職場でのストレスレベルも、市民的行動の圧力と関連を示しました。本来の業務に加えて期待される追加的な行動は、従業員の心理的負担を増加させています。このストレスは、最終的には従業員の離職意図につながることも確認されました。圧力を感じる従業員ほど、現在の職場を離れたいと考えるのです。
この研究の貢献は、組織市民行動への圧力が短期的には組織にとって有益な結果(従業員の協力的行動の増加)をもたらす一方で、長期的には従業員のストレスや離職という形で組織にコストを課すことを明らかにしたことです。
研究者たちは、この二面性を「組織市民行動のパラドックス」と呼んでいます。組織にとって短期的に有益な行動が、長期的には組織自体にとっても損失となる可能性があります。従業員の自発性を尊重しながら、適度な協力関係を築くことの難しさが、この研究によって浮き彫りになりました。
組織市民行動は必ずしも善意からでなく、負の影響も
組織市民行動に対する従来の理解を見直す必要性を指摘した研究が発表されています。この研究は、実証的な調査ではなく理論的な考察を中心としていますが、組織市民行動研究の分野において転換点となり得るものです。研究者たちは、長年にわたって前提とされてきた三つの仮定に疑問を投げかけ、組織市民行動の「暗い側面」について検討を加えました[4]。
第一の仮定は、「組織市民行動は利他的または組織を助ける動機から行われる」というものです。しかし、現実の職場では、従業員が自己利益のために組織市民行動を行うケースが存在することが指摘されました。上司からの評価を向上させるための印象操作、昇進や昇給を狙った戦略的行動、同僚との競争で優位に立つための手段として組織市民行動が利用されています。
従業員が過去の失敗や違反行為を埋め合わせるために組織市民行動を行ったり、同僚の評価を相対的に下げる意図で過剰な援助行動を取ったりすることもあります。表面的には「親切な行動」に見えても、その背後には利己的な計算や競争意識が隠れている場合があるのです。
第二の仮定である「組織市民行動は組織の効率的な機能に寄与する」についても、研究者たちは複数の問題点を指摘しました。組織市民行動が本来の職務遂行の代わりに行われる場合、組織全体の成果が損なわれる可能性があります。従業員が自分の正式な責任を果たす代わりに、より目立ちやすい援助行動に時間を割くことで、組織の基本的な機能が阻害される危険性があります。
職場での過剰な援助行動は、時として非効率性を生み出します。適切な訓練を受けていない従業員が他者を「助ける」ことで、かえって作業の質が低下したり、時間がかかったりすることがあります。組織が従業員の善意に依存することは、人員配置や管理体制の構築を怠ることにつながるかもしれません。
第三の仮定「組織市民行動が多い職場は従業員にとって魅力的である」に対しても、研究者たちは慎重な検討を加えました。組織市民行動が普及すると、従業員の職務の境界が曖昧になり、何が期待されているのかが分からなくなる「役割の曖昧性」が増加します。これは従業員にとってストレス要因となります。
「エスカレートする市民行動」という現象も想定されます。職場で組織市民行動が評価されるようになると、従業員同士が競争的により多くの市民行動を行うようになります。最初は自発的だった行動が、次第に「やらなければならないもの」に変化し、従業員の負担が継続的に増加していきます。
この競争は、職場と家庭生活の葛藤を深刻化させます。組織市民行動に多くの時間とエネルギーを割くことで、従業員は家族との時間や個人的な活動の時間を犠牲にせざるを得なくなります。長期的には、これがバーンアウトや精神的健康の悪化につながるかもしれません。
援助を受ける側の従業員にとっても、過度な援助は必ずしも歓迎されるものではありません。他者からの頻繁な援助は、自分の能力への不信感や劣等感を生み出すことがあります。職場での不公平感の原因となったり、援助される側の自立性や成長機会を奪ったりする可能性もあります。
これらの検討を通じて、研究者たちは組織市民行動研究の今後の方向性について提言を行いました。組織市民行動の動機をより幅広く検討し、利己的な動機も含めて理解すること。組織市民行動が組織成果に与える実際の影響を詳細に検証すること。組織市民行動が従業員個人に与える負の影響を体系的に調査することなどが提案されました。
脚注
[1] Vigoda-Gadot, E. (2006). Compulsory citizenship behavior: Theorizing some dark sides of the good soldier syndrome in organizations. Journal for the Theory of Social Behaviour, 36(1), 77-93.
[2] Vigoda-Gadot, E. (2007). Redrawing the boundaries of OCB? An empirical examination of compulsory extra-role behavior in the workplace. Journal of Business and Psychology, 21(3), 377-405.
[3] Bolino, M. C., Turnley, W. H., Gilstrap, J. B., and Suazo, M. M. (2010). Citizenship under pressure: What’s a “good soldier” to do? Journal of Organizational Behavior, 31(6), 835-855.
[4] Bolino, M. C., Turnley, W. H., and Niehoff, B. P. (2004). The other side of the story: Reexamining prevailing assumptions about organizational citizenship behavior. Human Resource Management Review, 14(2), 229-246.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。