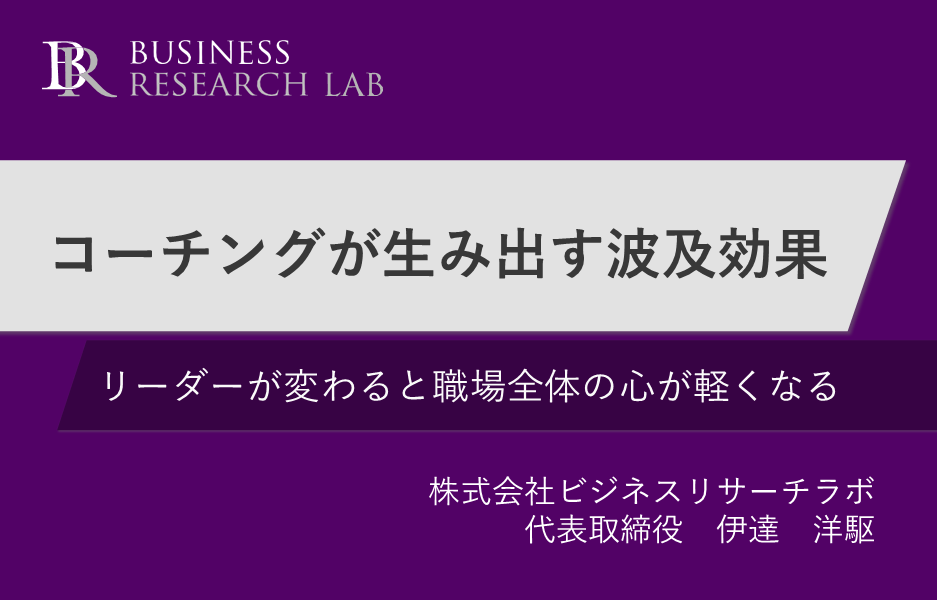2025年11月5日
コーチングが生み出す波及効果:リーダーが変わると職場全体の心が軽くなる
従業員の心理的健康とウェルビーイングへの関心が高まっています。プレッシャーの高い仕事環境や複雑な人間関係、絶え間ない変化への対応など、働く人々が直面する課題は多岐にわたります。こうした中で、一つのアプローチとして「コーチング」が世界中の組織で導入されるようになりました。
コーチングとは、対話を通じて相手の自己実現や目標達成を支援するプロセスです。潜在的な能力の開発や成長に焦点を当てます。近年の研究により、コーチングがスキル向上や業績改善だけでなく、受ける人の心理状態や精神的な健康に対しても変化をもたらすことが検証されるようになってきました。
本コラムでは、コーチングが個人の心理面に与える好ましい変化について探っていきます。自己効力感や幸福感の向上、職場におけるストレス軽減、さらには組織内での波及的な心理的改善、そして異なるコーチング形態がもたらす独特な心理的恩恵について検討します。
コーチングは協働関係を通じ、自己効力感や幸福感を高める
組織におけるビジネスコーチングの効果について、科学的な検証が積極的に行われています。あるシステマティック・レビューでは、過去10年間に発表された52件の実証研究を検討し、コーチングがもたらす心理的な変化とそのメカニズムを明らかにしました[1]。
この包括的な検討において一貫して確認されたのは、コーチングが個人の「自己効力感」に対して及ぼすポジティブな効果です。自己効力感とは、ある課題や困難な状況に対して「自分は対処できる」という自信のことを指します。研究結果によると、コーチングを受けた人々は、仕事上の課題や目標に対して、以前よりも「やればできる」という感覚を強く持つようになることが判明しました。
このような変化が生まれる背景には、コーチングが持つアプローチが関係しています。コーチングでは答えを教えるのではなく、質問を通じて相手自身に気づきを促します。この過程で、コーチングを受ける人は自分の中にある解決策や能力を発見し、それを実際に活用する経験を積み重ねていきます。このような成功体験の蓄積が、自己効力感の向上につながっていると考えられています。
ウェルビーイングの改善についても、多くの研究で肯定的な結果が報告されています。コーチングを受けた参加者は、仕事に対する満足度が高まり、日常生活における充実感も増加する様子が観察されました。この現象は、コーチングが業務スキルの向上だけでなく、個人の価値観や人生の目的について深く考える機会を提供することと関連していると解釈されています。
レジリエンス、すなわち困難やストレスに直面した際の精神的な回復力についても、向上が認められました。コーチングを通じて自分自身の強みや対処法を明確にした人々は、逆境に遭遇した時により柔軟で建設的な対応ができるようになりました。この変化は、自分自身への理解が深まり、内的なリソースにアクセスしやすくなったためと考えられます。
ただし、ストレスや抑うつ症状の軽減については、研究によって結果にばらつきが見られました。一部の研究では改善が報告された一方で、他の研究では統計的に有意な変化が見られませんでした。この不一致は、ストレスの要因が多様であり、コーチングだけですべてを解決することの限界を示すものかもしれません。
コーチングの効果を支える基本的な要素として、「ワーキングアライアンス」と呼ばれる協働関係の質が挙げられています。これは、コーチとクライアントの間に築かれる信頼関係、相互の尊重、そして共通の目標に向かって協力する姿勢を指します。心理療法の分野から導入されたこの概念は、コーチングの成果を予測する上で重要な指標であることが、複数の研究によって裏付けられています。
良好な協働関係が形成されると、クライアントは自分の弱さや不安をオープンに話すことができ、コーチからのフィードバックを建設的に受け入れやすくなります。このような安全で支持的な環境の中で、自己探求と成長のプロセスが促進されます。逆に、関係性が良好でない場合、どれほど優秀なコーチングスキルが用いられても、期待される心理的な変化は生まれにくいことが明らかになっています。
コーチングは職場の不安やストレスを軽減する
職場におけるストレス問題は、現代社会の深刻な課題となっています。仕事に関連する心理的負担は、労働日数の損失をもたらし、個人だけでなく組織全体の生産性にも打撃を与えています。このような問題に対して、新たな選択肢として期待されるようになりました。コーチングは、パフォーマンス向上や成長支援というポジティブな文脈で提供されるため、従業員にとって心理的な抵抗が少ないという利点があります。
英国の大手金融機関で実施された研究では、この仮説を検証するため、実際の職場環境でコーチングがストレス軽減に与える効果を調査しました[2]。この研究では、31名の従業員を対象として、コーチングを受けるグループと受けないグループに分けて比較検討が行われました。心理的ストレスの測定には「抑うつ・不安・ストレス尺度」が使用され、研究の開始前と終了後の両方でデータが収集されました。コーチングは組織内の訓練を受けた社内コーチによって提供され、主に電話を通じて実施されました。各参加者は平均して4回程度のセッションを受けることになりました。
研究の結果、不安とストレスのレベルにおいて、コーチングを受けたグループの方が、受けなかったグループよりも改善を示すことが確認されました。数値の変化を見ると、コーチングを受けた従業員たちの不安やストレスのスコアは、より低いレベルまで減少していました。コーチングが職場での心理的負担を和らげる上で有益な手法となりうることを示唆しています。
一方で、コーチングを受けたグループよりも、むしろ受けなかったグループの方で抑うつスコアの減少幅が大きいことがわかりました。この結果については、研究期間中の他の要因が作用した可能性や、抑うつという症状がコーチングよりも別のアプローチを必要とする可能性などが考察されています。
グループ間の差が統計的有意性の基準に達しなかったという限界も明らかになりました。しかし、この結果について研究者らは、参加者数が31名と比較的少なかったことや、職場ストレスという複雑な現象を測定することの困難さが関係している可能性を指摘しています。
コーチングがストレス軽減に寄与する仕組みについて、研究者らは複数の経路を提案しています。コーチングの対話プロセスを通じて、従業員は自分が抱えているストレスの原因を特定できるようになります。問題が曖昧なままでは対処も困難ですが、具体化されることで対応策を見つけやすくなるのです。
コーチングでは解決策を外部から与えられるのではなく、自分自身で発見するプロセスが重視されます。このアプローチによって、従業員は自分の状況をコントロールできるという感覚を取り戻し、無力感から脱却することができます。自己決定感の回復は、ストレス軽減において意味を持ちます。
定期的なコーチングセッションは、従業員にとって自分の状況を客観視し、感情を整理する時間となります。日常の忙しさの中では見失いがちな自分の価値観や優先順位を再確認することで、仕事に対する新たな視点や意味づけが生まれることがあります。
リーダーへのコーチングは、周囲の人の心の健康にも波及する
組織におけるコーチングの効果を考える際、これまでの研究は主に、コーチングを受けた本人にどのような変化が生じるかに焦点を当ててきました。しかし、組織は単なる個人の集合体ではなく、互いに複雑に影響し合う人間関係のネットワークから成り立っています。オーストラリアの研究者らは、この点に着目し、リーダーシップ・コーチングの効果が、コーチングを受けたリーダー本人を超えて、組織内の他の従業員の心理的健康にまで「波及」するのかどうかを検証する研究を実施しました[3]。
この研究で採用されたアプローチは、従来のコーチング研究とは異なるものでした。組織を「複雑適応系」として捉え、「社会ネットワーク分析」という手法を用いて、人間関係の構造とその変化を数値化し、視覚化しました。これによって、一人のリーダーの変化が組織内にどのような「さざ波」を起こすのかを追跡することが可能になりました。
研究は、ある学術機関の225名の従業員を対象として実施されました。そのうち20名のリーダーが、プロのコーチから8回にわたる個人コーチングセッションを受けました。データ収集は、コーチング実施前のベースライン期間、コーチングの実施期間、そして実施後の期間の3つの時点で行われ、全従業員の心理的ウェルビーイングと、組織内での人間関係の質と頻度が測定されました。
コーチングを受けたリーダー自身については、先行研究と一致する結果が得られました。目標達成度、変革型リーダーシップの他者評価、そして心理的ウェルビーイングのすべてにおいて、統計的に有意な向上が観察されました。これらの結果は、コーチングがリーダー個人に直接的なポジティブな効果をもたらすという、これまでの知見を再確認するものでした。
この研究で興味深い発見は、リーダーと周囲の人々との相互作用に関する認識のずれでした。コーチングを受けたリーダーたちは、自分と他者とのコミュニケーションの質が「向上した」と感じていました。ところが、そのリーダーたちと実際に相互作用している周囲の従業員たちは、逆にそのコミュニケーションの質が「低下した」と認識していました。
この一見矛盾した結果について、研究者らは「遅延効果」という概念で説明を試みています。コーチングを通じて新たな行動パターンやコミュニケーションスタイルを学んだリーダーたちが、それを実践し始めた際、当初はぎこちなさが生じたり、周囲の人々が戸惑いを感じたりする可能性があるというのです。新しいリーダーシップスタイルが周囲に受け入れられ、馴染むまでには一定の時間が必要であり、その過程で一時的な摩擦が生じることは、変化のプロセスにおいて避けられない現象かもしれません。
そして、この研究では「コーチングの波及効果」も明らかになりました。分析の結果、コーチングを受けたリーダーとの組織ネットワーク上での距離が近い従業員ほど、要するに、より頻繁に、より密接に関わっている従業員ほど、心理的ウェルビーイングの向上が大きいという関係性が見出されたのです。この関係は、先ほど述べたコミュニケーションの質に関する一時的な認識の悪化とは独立して成立していました。
この波及効果が生じるメカニズムについて、研究者らはいくつかの仮説を提示しています。コーチングを受けたリーダーが、より支援的で励ましに満ちた行動を取るようになることで、部下や同僚の心理的安全性が高まる可能性があります。心理的安全性とは、自分の意見や失敗を率直に表現しても、罰せられたり恥をかかされたりしないという安心感のことです。
リーダーがコーチングを通じて自己認識を深め、感情的な安定性を増すことで、周囲の人々にとってより予測可能で信頼できる存在になることも考えられます。不安定で予測困難なリーダーの下で働くことは、部下にとってストレス源となりますが、一貫性があり信頼できるリーダーの存在は、チーム全体の心理的な安定をもたらします。
コーチングを受けたリーダーが、目標設定や意思決定のプロセスにおいて、より透明で参加型のアプローチを取るようになることで、チームメンバーの自律性や有能感が高まる可能性もあります。自分の仕事に対してコントロール感を持ち、自分の意見が尊重されていると感じることは、個人のウェルビーイングにとって重要です。
誰がコーチかによって満たされる心の欲求が違う
人間のモチベーションや幸福感を理解する上で、心理学の分野では「自己決定理論」という理論があります。この理論によれば、人は3つの基本的な心理的欲求を持っており、これらが満たされることで、より意欲的で幸福な状態になることができるとされています。ある研究者らは、この理論的枠組みを用いて、異なる形態のコーチングが、それぞれどのような心理的欲求の充足に貢献するのかを検証する研究を実施しました[4]。
自己決定理論で提唱されている3つの基本的欲求とは、まず「自律性の欲求」です。これは、自分の行動や決定を自分自身でコントロールしたいという欲求を指します。人は誰かに強制されるのではなく、自分の意志で選択し、行動したいと感じるものです。次に「有能感の欲求」があります。自分が有能であり、課題を効果的に処理できるという感覚を持ちたいという欲求です。最後に「関係性の欲求」があり、これは他者との温かく安定した関係を築きたいという欲求を表しています。
この研究では、ノルウェーの大手ハイテク企業の127名の管理職を対象として、2つの異なるコーチング形態の効果が比較されました。一つは「外部エグゼクティブ・コーチング」で、これは組織のトップ層19名が、外部の専門的なコーチから個人およびグループコーチングを受けるというものでした。もう一つは「コーチング・ベースのリーダーシップ」で、これはミドルマネージャー108名が、直属の上司(コーチング研修を受けたエグゼクティブ)から日常的にコーチングを受けるというものでした。
研究は1年間にわたって実施され、コーチング介入の前後で、職場における基本的な心理的欲求の満足度が測定されました。その結果、両方のコーチング形態が心理的欲求の充足に対してポジティブな効果を持つことが確認されましたが、その効果の現れ方には違いがありました。
外部の専門コーチによるエグゼクティブ・コーチングを受けたグループでは、欲求満足度全体の向上に加えて、特に「自律性」と「関係性」の欲求が大きく満たされることが明らかになりました。自律性の向上については、利害関係のない第三者であるコーチとの対話を通じて、エグゼクティブたちが自分自身の価値観や信念を深く探求し、外部からの期待や圧力に左右されない、より自分らしい意思決定ができるようになったことが関係していると考えられます。
関係性の向上は、やや予想外の結果でした。個人コーチングという一対一の関係だけでなく、コーチング研修やグループセッションを通じて、普段は競争関係にある他のエグゼクティブたちとの間に、新たな信頼関係や協力関係が生まれた可能性があります。組織の上層部では孤独感を感じることが多いとされますが、同じような課題を抱える仲間との絆が深まることで、関係性の欲求が満たされたのかもしれません。
一方、上司からコーチング・ベースのリーダーシップを受けたミドルマネージャーグループでは、「自律性」と「有能感」の欲求が主に満たされることが分かりました。上司がコーチング的なアプローチを取ることで、部下であるミドルマネージャーたちにより多くの権限委譲が行われ、自分で判断し決定する機会が増えたことが自律性の向上につながったと推察されます。
有能感の向上については、上司からの支援的なフィードバックや能力開発の機会が提供されることで、ミドルマネージャーたちが自分の能力に対する自信を深めたことが関係していると考えられます。コーチング的な対話を通じて、自分の強みや成果を改めて認識する機会が得られたことも、有能感の向上に寄与したでしょう。
両方のコーチング形態を比較すると、外部の専門コーチによるコーチングの方が、全体的により大きな欲求満足度の向上をもたらすことが示されました。これは、専門的な訓練を受けたコーチが持つ高度なスキルや、利害関係のない第三者としての立場が、より深い自己探求と変化を促進するためかもしれません。
しかし、上司によるコーチング・ベースのリーダーシップも確実に欲求充足に貢献しており、日常業務の中で継続的に提供できるという利点があります。外部コーチングは集中的で強力な効果を持つ一方で、頻度や期間に限界があります。これに対し、上司によるコーチングは、継続性と持続性という面で独自の価値を提供することができます。
脚注
[1] Grover, S., and Furnham, A. (2016). Coaching as a developmental intervention in organisations: A systematic review of its effectiveness and the mechanisms underlying it. PLoS ONE, 11(7), e0159137.
[2] Gyllensten, K., and Palmer, S. (2005). Can coaching reduce workplace stress? A quasi-experimental study. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 3(2), 75-85.
[3] O’Connor, S., and Cavanagh, M. (2013). The coaching ripple effect: The effects of developmental coaching on wellbeing across organisational networks. Psychology of Well-Being: Theory, Research and Practice, 3(1), 2.
[4] Moen, F., and Federici, R. A. (2012). The effect of external executive coaching and coaching-based leadership on need satisfaction. Organization Development Journal, 30(3), 63-74.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。