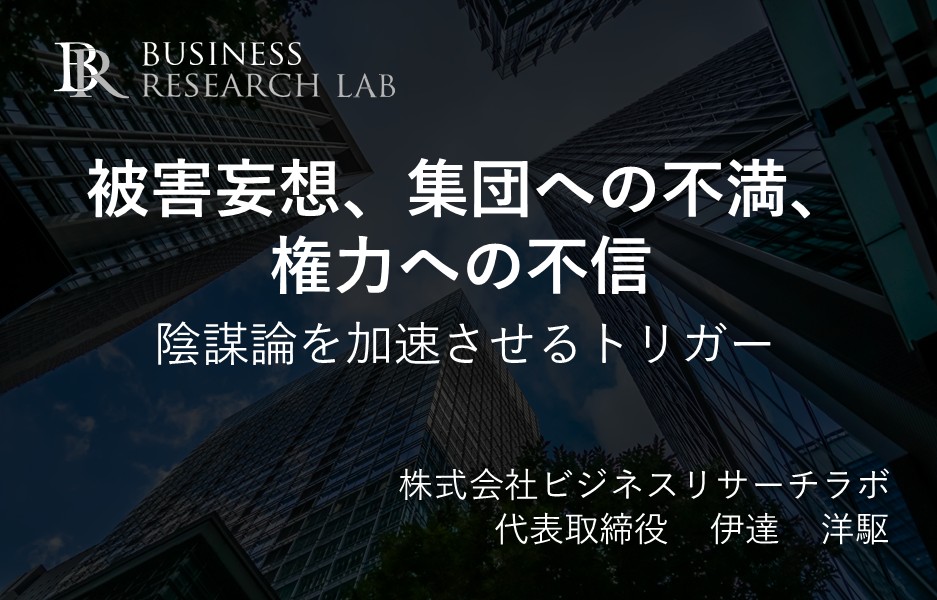2025年11月4日
被害妄想、集団への不満、権力への不信:陰謀論を加速させるトリガー
陰謀論という言葉を耳にする機会が増えました。かつては一部で共有される特殊な見方と見なされがちでしたが、今や社会の様々な場面で、その考え方に触れる機会は少なくありません。ある特定の出来事や社会の動きに対して、「裏で強力な集団が糸を引いているのではないか」という解釈は、なぜ人の心を捉えるのでしょうか。
陰謀論に関心を持つのは、何か特別な性質を持った人々なのでしょうか。あるいは、私たちの誰もが、特定の状況下に置かれれば、そうした考え方に納得感を見出す可能性があるのでしょうか。本コラムでは、陰謀論を個人の資質の問題として切り離すのではなく、それが人の心の中で育まれていく「過程」そのものに光を当てていきます。
これから探求するのは、ごくありふれた、しかしながら時に強い苦痛を伴う経験が、私たちの世界の見え方をどのように変えうるのかということです。例えば、職場で受ける心ない仕打ち、自分が属する集団への複雑な思い、あるいは信頼すべき上司との関係性。こうした日常の中に潜むネガティブな経験や心理が、どのようにして「見えざる敵」や「隠された意図」を見出す解釈へとつながっていくのか。本コラムでは、複数の研究を手がかりに、その繊細で複雑な心のメカニズムを検討していきます。
職場でのいじめ経験は陰謀論への傾向を高める
私たちの日常において、多くの時間を過ごす職場という環境は、自己実現や協力の場であると同時に、時として深刻な苦痛をもたらす場所にもなり得ます。特に、他者からの反復的な攻撃に晒される「いじめ」という経験は、人の心に深い影響をあたえます。その経験は、単に悲しみや怒りを引き起こすだけでなく、世界そのものに対する見方、つまり世界観を変化させることがあります。ここでは、職場でのいじめという個人的な被害経験が、社会的な現象である陰謀論への信じやすさと、どのように結びついていくのかを見ていきます。
この問いを検証するために、英国で働く数百人の成人を対象としたオンライン調査が行われました[1]。参加者はまず、過去半年間に職場でいじめを経験したかどうかについて回答しました。ここでのいじめとは、業務に必要な情報を意図的に隠されたり、根も葉もない噂を流されたり、あるいは同僚から無視されたりといった、業務関連の妨害行為や対人関係における排斥行為を指します。次に、一般的な陰謀論に対する信念の度合いを測る質問に答えました。「多くの『偶発的な出来事』は、実は特定の集団による計画の結果である」といった項目に対し、どの程度同意するかを評価するものです。
分析の結果、職場でいじめを経験した人ほど、一般的な陰謀論を信じる度合いが高いという関連が見出されました。しかし、この二つの間に相関があるというだけでは、いじめが「原因」で陰謀論を信じやすくなると結論づけることはできません。両者の背後には、何か共通の心理的な要因が隠れているのかもしれません。
そこで、この調査ではさらに三つの心理的な状態が測定されました。一つ目は「被害妄想」です。これは、他者が自分に対して悪意を持っており、危害を加えようとしているのではないかと疑う心の状態を指します。二つ目は「不安感」、三つ目は「脅威への過剰な警戒心」です。いじめの経験がこれらの心理状態を高め、その結果として陰謀論への信じやすさにつながるのではないか、という仮説が立てられました。
複数の要因の関係性を分析したところ、一つの道筋が浮かび上がりました。いじめの経験は、確かに被害妄想、不安、脅威への警戒心のすべてを高めていました。しかし、いじめ経験と陰謀論信念との関係を説明する、つまり両者をつなぐ媒介の働きをしていたのは「被害妄想」だけでした。いじめを受けたことで高まった不安感や脅威への警戒心は、直接的には陰謀論への信じやすさには結びついていませんでした。
このことから、職場で他者からの悪意に継続的に晒されるという経験が、世界を「自分を害しようとする他者が存在する」というレンズを通して見るようにさせ、そのように物事を捉える見方が、より大きなスケールである社会的な陰謀論という物語を受け入れやすくさせている、という心理的なプロセスが考えられます。
この調査結果は、いじめと陰謀論の関連性を示唆するものですが、「いじめが陰謀論を引き起こす」と断定するには、さらなる検証が必要です。そこで、次に紹介するのは、この関係を実験的な手法で確かめようとした研究です。
実験では、英国の成人約二百名が参加し、無作為に二つのグループに分けられました。一方のグループ(いじめ条件)には、職場で上司や同僚から情報を隠されたり、嘲笑されたり、悪い噂を立てられたりするといった、典型的な職場いじめの場面が詳細に記述されたシナリオを読んでもらいました。そして、自分がその状況に置かれていると想像するように求められました。もう一方のグループ(支援条件)には、対照的に、同僚から温かい支援や協力を受ける、ポジティブな職場のシナリオを想像してもらいました。
この想像課題の後、参加者は、一般的な陰謀論に対する信念の度合いと、その瞬間に感じている被害妄想的な感情(専門的には「状態被害妄想」と呼ばれます)を測定する質問に回答しました。結果は、研究者たちの予測を裏付けるものでした。いじめられる職場のシナリオを想像したグループは、支援的な職場を想像したグループに比べて、陰謀論を信じる度合いが有意に高かったのです。この結果は、いじめという状況に身を置く(たとえ想像上であっても)ことが、陰謀論的な思考を促進する一つの要因となり得ることを示しています。
いじめのシナリオを想像することは、その人の被害妄想的な感情を高めることも確認されました。しかし、先の調査研究とは異なり、この実験では、高まった被害妄想が陰謀論への信じやすさを媒介するという経路は統計的に明確ではありませんでした。むしろ、いじめの状況を想像すること自体が、被害妄想を介さずに、直接的に陰謀論への信念を高めるという経路が見られました。
集団ナルシシズムは陰謀論を促進し、安定した集団肯定は抑制する
個人の苦しい経験が、世界を疑いの目で見るきっかけとなり得ることを見てきました。視点を広げ、私たち一人ひとりが属する「集団」への思いが、陰謀論とどのように関わっているのかを探っていきます。人は社会的な生き物であり、家族、地域、国家、あるいは特定の思想や趣味を共有するグループなど、様々な集団に帰属意識を持ちます。この「自分たちの集団」を肯定的に思う気持ちは、健全な自尊心や連帯感の源泉となりますが、その肯定の仕方が、陰謀論への信じやすさを左右することが分かってきています。
「自分たちの集団は素晴らしい」という感情には、大きく分けて二つの異なる質が存在します。一つは「集団ナルシシズム」と呼ばれるものです。これは、自集団の偉大さを信じているものの、その評価が外部の他者から十分に認められていない、という不満や被害者意識を抱えている状態を指します。このタイプの集団肯定感は、他者からの承認に依存しており、非常に脆く、防衛的な性質を持っています。
もう一つは、「非ナルシシズム的な内集団肯定」と呼ばれるものです。こちらは、外部からの評価に左右されることなく、自分たちの集団の価値や歴史、文化に対して、内的に安定した誇りや愛着を感じている状態です。脅威に対して過剰に反応する必要がなく、穏やかで安全な肯定感と言えるでしょう。
この二種類の「集団へのポジティブな感情」が、陰謀論、特に「自分たちの集団(内集団)を害そうとする、他の集団(外集団)による陰謀」という信念と、どのように関連するのでしょうか。この問いに答えるため、ポーランドとアメリカで複数の研究が行われました[2]。
最初の研究は、ポーランドの大学生を対象に行われました。ポーランドの歴史において象徴的な出来事である共産主義体制の崩壊に関して、「ポーランドの功績が国際社会で不当に低く評価されている」という趣旨の文章を参加者に読んでもらいました。その後、自国に対する集団ナルシシズムの度合いと、安定した集団への自尊感情(非ナルシシズム的肯定)の度合い、そして「反ポーランド的な国際的陰謀が存在する」という信念の強さを測定しました。
結果は対照的でした。集団ナルシシズムのスコアが高い学生ほど、反ポーランド陰謀論を強く信じていました。一方で、安定した集団への自尊感情が高い学生ほど、その陰謀論を信じる度合いは低かったのです。この二つの集団肯定感は、陰謀論に対して正反対の方向に作用していました。自分たちの偉大さが認められていないという不満を抱える心理状態は、外部に敵を見出し、陰謀の存在を信じることで現状を理解しようとする動きにつながりやすいようです。対照的に、穏やかで安定した誇りは、そうした特定の解釈に傾倒することから人々を遠ざけるのかもしれません。
二つ目の研究は、同じくポーランドで、より具体的な出来事である「スモレンスク航空機事故」を題材に行われました。この事故では、当時の大統領を含む政府要人が多数亡くなっており、ロシアの関与を疑う陰謀論が国内で広まりました。この研究では、集団ナルシシズムと安定した集団肯定感に加えて、ロシアという国に対してどの程度の脅威を感じているか、という「対集団的脅威知覚」も測定されました。
分析の結果、ここでも集団ナルシシズムは対ロシア陰謀論への信念を高め、安定した集団肯定感はそれを抑制するという、一つ目の研究と同様のパターンが確認されました。この関係を解き明かす鍵として「脅威知覚」の存在が浮かび上がりました。集団ナルシシズムが高い人々は、ロシアに対してより強い脅威を感じており、その高まった脅威感が、陰謀論への信念へとつながっていたのです。
「自分たちは正当に評価されていない」というナルシシスティックな不満は、外集団を脅威と見なすフィルターとなり、そのフィルターを通して世界を見ることで、陰謀という物語が現実味を帯びてくる、というメカニズムが考えられます。
これまでの研究はポーランドという特定の文化的・歴史的背景を持つ国で行われたものでした。そこで三つ目の研究では、このメカニズムがより普遍的なものであるかを確認するため、アメリカの成人を対象としたオンライン実験が行われました。この実験の巧妙な点は、陰謀の主体を操作したことです。参加者は、陰謀を企てているのが「自国であるアメリカ政府(内集団)」なのか、それとも「どこかの外国政府(外集団)」なのか、ランダムに割り振られた設定の下で、一般的な陰謀論への信念を評価しました。
結果は、この現象の核心に迫るものでした。安定した集団肯定感は、陰謀の主体が自国政府であろうと外国政府であろうと、一貫して陰謀論への信じやすさを弱める働きがありました。これは、内的に安定した誇りが、全般的な物事の見方に対して、バランスの取れた視点を保つ助けとなることを示唆しています。
対照的に、集団ナルシシズムの働きは、陰謀の対象によって異なりました。集団ナルシシズムが高い人々は、陰謀の主体が「外国政府(外集団)」である場合にのみ、陰謀論をより強く信じるようになりました。陰謀の主体が「自国政府(内集団)」である場合には、集団ナルシシズムと陰謀論信念との間に明確な関連は見られませんでした。
これら三つの研究を総合すると、重要な結論が導き出されます。それは、「自分の集団を誇りに思うこと」自体が陰謀論につながるわけではなく、その「誇りの質」が分水嶺になるということです。他者からの承認を求め、自分たちの価値が脅かされているという感覚に根差した、脆く防衛的なプライド(集団ナルシシズム)は、外部に原因を求めることで自分たちの状況を理解しようとし、その過程で陰謀論という解釈と結びつきやすくなります。
利己的な権力行使は陰謀信念と悪意ある創造性を高める
個人の被害経験、そして集団への帰属意識のあり方が、陰謀論的な世界観と結びつく過程を見てきました。最後に、組織という枠組みの中で、特に「権力」という垂直的な関係性が、人々の心に陰謀論を芽生えさせるメカニズムを掘り下げていきます。職場において、上司や経営陣といったリーダーの振る舞いは、従業員のモチベーションや満足度だけでなく、組織に対する信頼感を左右します。リーダーがその権力をどのように捉え、行使するかは、従業員の目には組織全体の姿勢として映ります。
リーダーが権力をどう捉えるかには、主に二つのタイプがあると考えられています。一つは、権力を「他者への責任(Power as Responsibility)」と見なすタイプです。このタイプのリーダーは、自身の権力を、部下や組織全体のために貢献する責任を果たすための手段と捉えます。そのため、意思決定においては公正さや配慮を重んじ、部下の意見に耳を傾けようとします。
もう一つは、権力を「自己利益追求の機会(Power as Opportunity)」と見なすタイプです。こちらのリーダーは、権力を個人的な目標達成や利益を得るための好機と捉え、利己的な動機で行使する傾向があります。部下は、日々のリーダーの言動や意思決定のスタイルから、そのリーダーがどちらのタイプに近いかを敏感に察知します。
リーダーの権力観が、従業員の間に「組織内陰謀信念」を生み出すのではないか、という仮説が立てられました。組織内陰謀信念とは、「経営陣や上司たちが、従業員に害を及ぼすために、裏で秘密裏に共謀している」という信念のことです。
この陰謀信念は、従業員の行動にも変化をもたらす可能性があります。その一つが「悪意ある創造性(Malevolent Creativity)」です。これは、組織や同僚に損害を与えることを目的とした、巧妙で破壊的なアイデアや行動を指します。例えば、意図的に重要な情報を遅らせる巧妙な方法や、会社の備品を気づかれずに私物化する独創的な手口などがこれにあたります。
この一連の連鎖、すなわち「リーダーの権力観 → 組織内陰謀信念 → 悪意ある創造性」という流れを検証するため、複数の研究が行われました[3]。
最初の研究は、英国の様々な企業で働く従業員を対象とした縦断調査です。この調査では、3週間の間隔をあけて3回、オンラインでアンケートが実施されました。1回目の調査では、従業員が自分たちの直属の上司の権力観をどのように認識しているか(責任志向か、機会志向か)を測定しました。3週間後の2回目の調査では、組織内陰謀信念の度合いを尋ねました。さらに3週間後の3回目の調査で、悪意ある創造性について回答してもらいました。
分析の結果、予測された通りの連鎖が明らかになりました。従業員が上司を「権力は責任」と捉える責任志向のリーダーだと認識している職場では、3週間後の組織内陰謀信念は低く抑えられていました。逆に、上司を「権力は機会」と捉える機会志向のリーダーだと認識している職場では、組織内陰謀信念は有意に高まっていました。そして、組織内陰謀信念が高い従業員ほど、さらに3週間後には、悪意ある創造性が高まるという結果が得られたのです。
次に実験が行われました。実験では、参加者に架空の企業で働くシナリオを読んでもらいました。シナリオの中で、参加者は上司のビルから、業務評価に関するネガティブなフィードバックを受けます。フィードバックの内容自体は全参加者で同じですが、その伝え方、つまり上司の動機づけが三つのパターンに操作されました。
「責任志向」条件では、上司は組織全体の成長という責任感からフィードバックをしている、という設定でした。「機会志向」条件では、上司は自分の立場を良く見せるという利己的な動機からフィードバックをしている、という設定です。三つ目の対照条件では、特に動機づけに関する言及はありませんでした。このシナリオを読んだ後、参加者は組織に対する陰謀信念や、悪意ある創造性を測定されました。
結果は、縦断調査の結果を裏付けるものでした。機会志向の上司のシナリオを読んだ参加者は、他の条件の参加者に比べて、組織内陰謀信念を高めました。逆に、責任志向の上司のシナリオは、陰謀信念を抑制しました。そして、高まった陰謀信念が、悪意ある創造性を高めるという媒介のプロセスが確認されました。
この連鎖の核心部分である「組織内陰謀信念が、本当に悪意ある創造性を引き起こすのか」という点を直接的に確かめるための実験も行われました。この実験では、参加者を二つのグループに分け、一方のグループには、ある企業のデータ流出事件について「経営陣が利益のために意図的に仕組んだ陰謀である」と描写した記事を読んでもらいました。もう一方のグループには、その陰謀を否定する内容の記事を読んでもらいました。その後、悪意ある創造性を測定したところ、陰謀論の記事を読んだグループは、そうでないグループに比べて、明らかに悪意ある創造性が高まることが確認されました。
脚注
[1] Jolley, D., and Lantian, A. (2022). Bullying and conspiracy theories: Experiences of workplace bullying and the tendency to engage in conspiracy theorising. Social Psychology, 53(4), 198-208.
[2] Cichocka, A., Marchlewska, M., Golec-de-Zavala, A., and Olechowski, M. (2016). “They will not control us”: In-group positivity and belief in intergroup conspiracies. British Journal of Psychology, 107(3), 556-576.
[3] Fousiani, K., Xu, S., and van Prooijen, J. W. (2025). Leaders’ power construal influences malevolent creativity: The mediating role of organizational conspiracy beliefs. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 98(1), e70005.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。