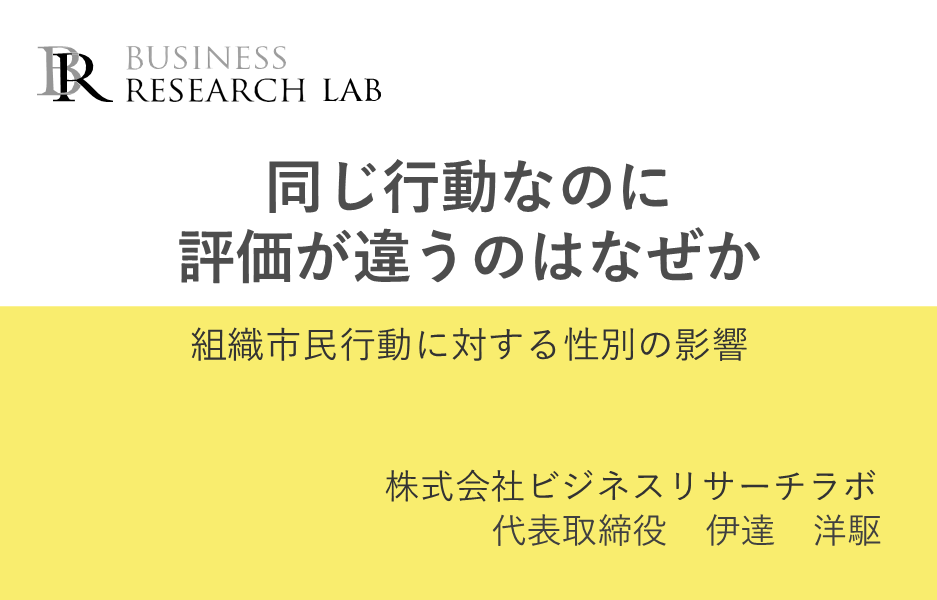2025年11月4日
同じ行動なのに評価が違うのはなぜか:組織市民行動に対する性別の影響
職場で同僚を手伝ったり、会議で積極的に発言したり、周囲の仕事の完成を手伝ったりする。こうした「やらなくてもよいが、やれば組織のためになる」行動は、組織市民行動と呼ばれています。一見すると、このような行動を取る人は性別に関係なく同じように評価されるように思えます。しかし、実際の職場では必ずしもそうではありません。
同じ親切な行動をしても、それが女性によるものか男性によるものかで、周囲の反応や評価が変わることがあります。女性が同僚を助けると「当たり前のこと」として受け取られる一方で、男性が同じことをすると「素晴らしい行動」として評価される。このような現象は、私たちの職場でも日常的に起こっているかもしれません。
組織市民行動をめぐる性別の問題は、評価の違いにとどまりません。女性と男性では、そもそも期待される行動の種類が異なり、それが個人のストレスや役割葛藤にもつながっています。看護師のような職業では協調性が求められ、エンジニアのような職業では自己主張が重視される傾向もあります。
これらの背景には、社会が男女に対して抱く固定的な役割期待があります。女性は思いやりがあって協力的であるべきで、男性は自立的で競争的であるべきだという無意識の前提が、職場での行動評価にも大きく響いているのです。
本コラムでは、組織市民行動と性別にまつわる研究結果を見ていきながら、現代の職場で起こっている見えにくい性別格差の実態を明らかにします。同じ行動でも性別によって評価が変わる理由、職業や個人の特性による違い、そして組織市民行動が個人に与える負担についても考察していきます。
組織市民行動の利他、女性は当然視され男性は高評価
職場で同僚を手伝ったり、新人の指導をしたりする利他的な行動について、ある実験が行われました[1]。架空の従業員について書かれた評価資料を読んで、その人の業績評価や昇進、給与上昇の推薦を行うという実験です。資料には、その従業員が利他的な行動を取ったか、取らなかったか、あるいはその情報がないかのいずれかが記載されていました。実験参加者は、同じ行動について書かれた資料でも、従業員の名前から性別を判断して評価を行いました。
この実験は大学生とMBA学生を対象に行われ、どちらのグループでも一貫した結果が得られました。男性従業員が利他的な行動を取った場合、業績評価や報酬推薦が高くなりました。評価者は、男性が同僚を助けたり新人を指導したりすることを高く評価し、昇進や給与アップに値すると判断したのです。
ところが、女性従業員が同じ利他的行動を取った場合、評価はほとんど改善しませんでした。同僚を助ける、職場の紛争を解決する、新入社員を支援するといった行動は、女性にとっては「やって当然のこと」として受け取られ、評価の向上にはつながりませんでした。
印象的だったのは、利他的行動を取らなかった場合の評価です。女性が利他的行動を取らなかった場合、業績評価や報酬推薦が低下しました。これは、女性には利他的であることが期待されており、その期待に応えない場合には厳しい評価を受けるということを意味しています。一方、男性が利他的行動を取らなかった場合、評価が下がることはありませんでした。男性には最初から利他的行動が期待されていないため、それを行わなくても問題視されません。
この実験では、利他的行動に関する情報が全くない場合の評価も調べられました。その結果、女性は利他的行動を取った場合と同程度の評価を受け、男性は利他的行動を取らなかった場合と同程度の評価を受けました。これは、評価者が女性に対しては利他的行動を期待し、男性に対してはそうした期待を持たないことを表しています。
研究では、利他的な組織市民行動が女性にとっては義務的とみなされる一方、男性にとっては任意的とみなされることが確認されました。同僚を助ける、職場の紛争解決に関わる、新入社員を支援するといった行動は、女性にとっては「やるべきこと」として認識され、男性にとっては「やらなくてもよいこと」として認識されていました。
興味深いことに、主導性を示すような行動、例えば管理者に問題を報告したり追加の労働を引き受けたりすることは、逆に男性にとって義務的だと認識される傾向がありました。これは、社会が男女に対して抱く役割期待の違いを反映しています。女性には協調性や思いやりが期待され、男性には自己主張や積極性が期待されているということです。
この結果は、職場における性別バイアスの存在を浮き彫りにしています。表面的には同じ評価基準を適用しているように見えても、実際には女性と男性に対して異なる行動期待を持ち、それに基づいて評価を行っている可能性があります。女性は利他的であることが当然視されるため、そうした行動を取っても特別な評価を受けず、逆に取らない場合には厳しく評価される。男性は利他的行動が期待されていないため、それを行うと高く評価され、行わなくても問題視されない。このような評価の非対称性は、職場での昇進や処遇に長期的な差をもたらす可能性があります。
組織市民行動は性別や性別役割、職業で違いあり
組織市民行動が性別によってどのように異なるかを理解するためには、行動の種類を詳しく分類して考える必要があります。ある研究では、組織市民行動を「利他主義」と「市民的美徳」という二つの側面に分けて、看護師とエンジニアという対照的な職業の人々を対象に調査が行われました[2]。
利他主義とは、同僚を直接的に助ける行動を指します。困っている人に手を差し伸べたり、新人の面倒を見たり、他者の仕事を代わりに引き受けたりする行動です。一方、市民的美徳とは、組織における意思決定や施策に積極的に参加し、意見を表明する行動を指します。会議で建設的な提案をしたり、組織の問題について発言したり、会社の方針について議論したりする行動です。
この研究では、女性的特性(協調性、共感性、配慮深さ)と男性的特性(自己主張性、競争性、独立性)を測定し、これらの特性が組織市民行動にどのように関連するかも調べられました。また、看護師という伝統的に女性が多い職業と、エンジニアという伝統的に男性が多い職業を比較することで、職業タイプの効果も検討されました。
調査の結果、性別と組織市民行動の関係は複雑であることが判明しました。単純に「女性は利他的行動を多く行う」「男性は積極的行動を多く行う」というわけではありませんでした。実際には、女性は男性よりも市民的美徳の行動をとることが少ないという結果が得られました。これは、女性が組織の意思決定に参加することが相対的に少ないことを示唆しています。
一方、利他的行動については、性別だけでは明確な差は見られませんでした。しかし、個人の持つ性別的特性を考慮すると、興味深いパターンが現れました。女性的特性が強い人は、性別に関係なく利他的行動を多く行いました。協調性や共感性が高い人は、同僚を助けたり支援したりする行動を頻繁に取る傾向がありました。逆に、男性的特性が強い人は、市民的美徳の行動を多くとりました。自己主張性や競争性が高い人は、組織の会議や意思決定に積極的に参加する傾向がありました。
職業による違いも顕著でした。看護師は利他的行動を多く行い、市民的美徳の行動は少ない傾向がありました。看護という職業の性質上、患者や同僚への直接的な援助が重視される一方で、組織の施策や意思決定への参加はそれほど期待されていないのかもしれません。対照的に、エンジニアは市民的美徳の行動を多く行い、利他的行動は相対的に少ない傾向がありました。エンジニアという職業では、技術的な専門知識を活かして組織の問題解決や改善に貢献することが重視される一方で、個人的な援助はそれほど強調されないのかもしれません。
注目したいのは、男性看護師の行動パターンです。男性看護師は女性看護師よりも市民的美徳の行動を多く報告しました。男性が女性の多い職場で働く際に、自分の存在価値を示すために積極的な発言や提案を行う可能性を示唆しています。一方、エンジニアにおいては男女の差は見られませんでした。
これらの結果は、組織市民行動が単純に性別だけで決まるものではないことを示しています。個人の性格特性、所属する職業の文化、そして職場における性別構成などが複合的に作用して、行動パターンが形成されています。女性だからといって必ずしも利他的であるわけではなく、男性だからといって必ずしも積極的であるわけでもありません。
しかし同時に、職業や組織の文化が性別役割期待を強化している可能性も考えられます。看護師という職業では協調性や思いやりが重視され、エンジニアという職業では技術的専門性や積極性が重視される。こうした職業文化が、その職業に就く人々の行動パターンを形作っているのかもしれません。
組織市民行動の自発性は、特に女性の役割過重や役割葛藤に繋がる
組織市民行動は一般的に組織にとって有益なものとして捉えられていますが、それを実行する個人にとっては必ずしもプラスの結果ばかりをもたらすわけではありません。自発的に追加の仕事を引き受けたり、期待を上回る努力をしたりする「個人的なイニシアティブ」と呼ばれる行動について、その負の側面を調べた研究があります[3]。
この研究では、アメリカの大学卒業生98組の夫婦やパートナーを対象に、個人的なイニシアティブが個人に与える負担について調査されています。個人的なイニシアティブには、休日出勤、早出や残業、自宅での仕事、職務要求を超えた追加作業などが含まれます。これらの行動は多くの組織で「良い従業員」の証として評価されますが、実行する個人にはどのような影響をもたらすのでしょうか。
調査では、個人的なイニシアティブが三つの負の結果と関連していることが明らかになりました。第一に、役割過重です。追加の仕事を引き受けることで、本来の職務に加えて負担が重なり、時間的にも精神的にも過重な状態になります。第二に、仕事のストレスです。期待以上の成果を出そうとするプレッシャーや、多くの責任を背負うことによる心理的負担が増加します。第三に、仕事と家庭の役割葛藤です。職場での追加的な責任が家庭での責任と衝突し、どちらも十分に果たせないジレンマに陥ります。
仕事と家庭の役割葛藤においては性差が見られました。個人的なイニシアティブと家庭との役割葛藤の関係は、女性の方が男性よりも強く現れました。同じように追加の仕事を引き受けても、女性の方が家庭での責任との両立により大きな困難を感じるのです。
この性差の背景には、社会的な役割期待の違いがあるでしょう。女性が家庭における主要な責任者として期待されており、育児、家事、介護などの責任は、依然として女性により多く負担されている現状があります。そのため、職場で追加的な努力をする女性は、家庭での責任と仕事での責任の間でより深刻な葛藤を経験することになります。
男性の場合、家庭での責任が相対的に少ないか、あるいはパートナーが主要な責任を担っているため、職場での追加的な努力が家庭生活に与える負担は女性ほど深刻ではない傾向があります。このため、同じような個人的なイニシアティブを取っても、その代償として支払う個人的なコストには性差が生まれます。
この研究の結果は、組織市民行動の推奨には慎重さが必要であることを示しています。確かに、従業員が自発的に追加的な努力をすることは組織にとって有益です。しかし、そうした行動が個人の幸福や家庭生活を犠牲にして行われている可能性があります。特に女性の場合、職場での「良い従業員」であろうとする努力が、家庭での責任とのバランスを取ることを困難にしているかもしれません。
組織市民行動、学生では役割葛藤と満足度・ストレスに影響
組織市民行動の研究は主にフルタイムの正規雇用者を対象として行われてきましたが、近年では様々な雇用形態で働く人々への関心も高まっています。パートタイムや一時雇用で働く大学生を対象とした研究では、これまでとは異なる結果が得られています[4]。
この研究では、英国および欧州の大学生122名を対象に、アルバイトやパートタイムの仕事における組織市民行動とその結果について調査が行われました。学生という立場は、仕事と学業という二つの主要な責任を同時に抱えているという点で、一般的な労働者とは異なります。彼ら彼女らにとって仕事は生活の中心ではなく、学業と並行して行う活動の一つです。
調査では、学生が職場でとる組織市民行動が、仕事満足度、仕事のストレス、幸福感、離職意図に加えて、仕事と大学の役割間葛藤、仕事と余暇の役割間葛藤にどのような関係を持つかが検討されました。学生特有の状況として、仕事、学業、余暇という三つの領域のバランスを取ることの困難さが調査の焦点となりました。
結果、組織市民行動と役割間葛藤の間に明確な関係が見つかりました。組織市民行動を多くとる学生ほど、仕事と大学の間、仕事と余暇の間で葛藤を経験しやすいことが判明しました。これは、職場で期待以上の努力をすることが、学業や個人的な時間を圧迫し、複数の責任の間での調整を困難にすることを表しています。
職場で組織市民行動を行うことで、勉強時間が削られたり、課題やテストの準備が不十分になったりする可能性があります。同時に、友人との交流や趣味、休息といった余暇時間も犠牲になるかもしれません。このような多重の役割葛藤は、学生特有の問題として浮き彫りになりました。
一方で、組織市民行動は仕事満足度とは正の関係を示しました。職場で積極的に貢献する学生は、その仕事により満足感を感じる傾向がありました。自分の努力が認められたり、職場での人間関係が良好になったりすることが理由として考えられます。また、組織市民行動は仕事のストレスとも正の関係を示しました。追加的な責任や努力は、やりがいをもたらす一方で、ストレスの源にもなることが確認されました。
フルタイム従業員を対象とした従来の研究でしばしば見られる関係の一部が、この学生サンプルでは確認されませんでした。例えば、組織市民行動と幸福感や離職意図との関係は有意ではありませんでした。学生にとって仕事が生活の中心ではないため、職場での行動が全体的な幸福感や仕事を続けるかどうかの判断にそれほど大きく響かないのかもしれません。
脚注
[1] Heilman, M. E., and Chen, J. J. (2005). Same behavior, different consequences: Reactions to men’s and women’s altruistic citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 90(3), 431-441.
[2] Kidder, D. L. (2002). The influence of gender on the performance of organizational citizenship behaviors. Journal of Management, 28(5), 629-648.
[3] Bolino, M. C., and Turnley, W. H. (2005). The personal costs of citizenship behavior: The relationship between individual initiative and role overload, job stress, and work-family conflict. Journal of Applied Psychology, 90(4), 740-748.
[4] Johansson, E., and Hart, R. (2023). The outcomes of organizational citizenship behaviors in part-time and temporary working university students. Behavioral Sciences, 13(8), 697.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。