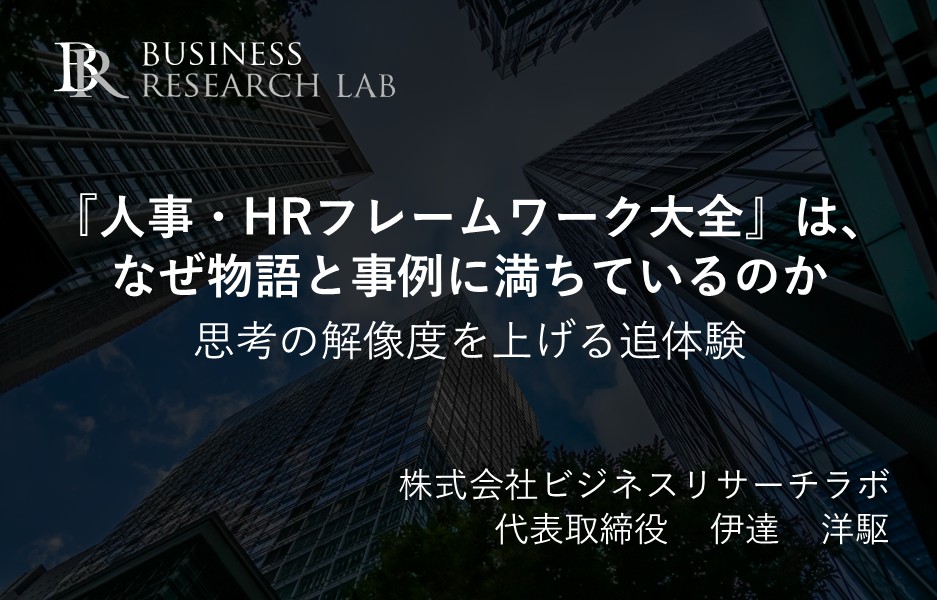2025年11月4日
『人事・HRフレームワーク大全』は、なぜ物語と事例に満ちているのか:思考の解像度を上げる追体験
ビジネス書を手に取るとき、私たちは多かれ少なかれ、現場で直面する課題を解決したいという思いを抱えています。しかし、読書を通じて得た知識を、実際の業務で十分に活かせているかと問われれば、自信を持って頷ける人は決して多くないのではないでしょうか。読んだ直後は納得し、意欲も高まるものの、いざ現場に戻ると日々の業務に追われ、学んだはずの知識は記憶の片隅へと追いやられてしまう。こうした「知っている」ことと「できる」ことの間にある溝は、多くのビジネスパーソンが経験する共通の悩みかもしれません。
この溝が生まれる理由は単純ではありません。一つには、私たちの多くが、新しい知識に触れた瞬間の「理解した感覚」を、実践できる能力と錯覚してしまうことにあります。理論の体系が美しいほど、あるいは解説が明快であるほど、私たちはその知識を完全に自分のものにできたと感じます。しかし、知識の理解と、それを現実の複雑な状況の中で応用する技能との間には隔たりが存在します。
もう一つの理由は、日々の業務の多忙さです。新しいアプローチを試すには、心理的なエネルギーだけでなく、時間的な余裕も必要です。しかし、目の前のタスクに追われる中で、失敗のリスクを冒してまで新しい方法を試すことは容易ではありません。結果、せっかく得た知識も試されることなく、次第にその輪郭を失っていきます。
知識は、それ単体では力になりにくいものです。具体的な文脈や物語と結びつき、誰かの経験を追体験する中で初めて、それは「使える知恵」へと変わります。この度上梓した『人事・HRフレームワーク大全』が、理論の解説に留まらず、数多くの事例や物語に満ちているのは、この「知と実践の溝」を埋めることを意図したからです。
本書は、人と組織の問題を解き明かすための理論書であると同時に、読者が自身の課題を解決するプロセスを擬似的に体験するための、思考の「シミュレーター」として設計されています。本コラムでは、本書がその役割を果たすために、いかに物語と事例の力を重視したか、その設計思想を解説していきます。
思考のプロセスを追体験する
本書の心臓部とも言える83のフレームワーク解説には、その一つひとつに「理解のための例題」というセクションが設けられています。これはただの具体例の提示ではありません。課題を抱えた登場人物が、フレームワークという思考の道具を手にすることで、その視野がどう広がり、行動がどう変わり、結果として何を得るのか。その一連のプロセスを読者が追体験し、思考の流れを学ぶための「ミクロな物語」です。
例えば、多くのリーダーが経験するであろう、部下との関係性の問題を考えてみましょう。あるマネージャーが、特定の部下との間に見えない壁を感じているとします。業務の指示は伝わるものの、どうも信頼関係が築けていない。部下はどこか受け身で、期待以上の働きを見せてくれない。この漠然とした悩みを、どうすれば解決の糸口が見える具体的な課題へと転換できるでしょうか。
ここで本書の「LMX理論」のページを開くと、ある地方テレビ局の報道部長が登場します。彼は経験の浅い若手記者との関係構築に悩み、当初は指示中心のコミュニケーションで相手を萎縮させていました。この状況は、先ほどのマネージャーが抱える悩みと重なります。物語の中で、この報道部長はLMX理論の視点を得ます。上司と部下の関係性の質は、「愛着」「忠誠」「貢献」「専門的敬意」という四つの次元で決まるという考え方です。彼は、自分と若手記者の関係をこの四つの次元で捉え直します。単に「関係がうまくいかない」のではなく、「互いの専門性への敬意が不足しているのではないか」「困難な状況で味方であるという忠誠心を示せていただろうか」と、問いの解像度が上がります。
この新たな視点を得た報道部長の行動は変わります。若手記者の取材現場での小さな気づきや努力を具体的に褒め(貢献・専門的敬意)、非公式な場での雑談を通じて相手の報道への情熱や関心事を理解しようと努めます(愛着)。難しい取材で壁にぶつかった際には、最後まで味方であると伝え、精神的に支える(忠誠)。その結果、若手記者は部長を信頼し、主体的に取材提案を行うようになり、やがてスクープ記事を生み出すまでに成長します。
もう一つ、別の例を見てみましょう。「心理的エンパワーメント」の項目では、教育系ベンチャー企業のカスタマーサポート担当者が登場します。彼は当初、自分の役割を「問い合わせに対応する作業」としか認識していませんでした。しかし、ユーザーの学習進捗データを分析する機会を得て、自分たちの対応が顧客の学習継続率に影響していることを知ります。これは、彼の仕事に対する認識を「意味」と「影響力」の次元で変える出来事でした。自分の行動が組織や顧客に良い変化をもたらしているという実感は、動機づけとなります。彼は、自身の専門性が高まっていることも感じ(能力)、やがて新しい支援方法を自ら考案し、実践するようになります(自己決定)。
これらの一連の物語は、読者に対してフレームワークの活用法を示すだけでなく、思考のシミュレーションを促します。読者はこの報道部長やカスタマーサポート担当者に自分を重ね、「自分のチームではどうだろうか。部下のAさんとの間では『専門的敬意』は示せているか。Bさんとの間では、困った時に支えるという『忠誠』が足りないのかもしれない」「メンバーは自分の仕事の『意味』や『影響力』を実感できているだろうか」と、自身の状況に当てはめて考えることができます。例題は、理論を具体的な行動計画に落とし込むための思考の練習問題なのです。
このように、各項目に埋め込まれたミクロな物語は、読者が自身の職場やチームを登場人物に置き換え、思考実験を行うための舞台装置として機能します。理論を知識として記憶するのではなく、課題解決のプロセスを追体験することで、フレームワークは借り物の知識から、いつでも引き出せる自分自身の思考スキルへと変わっていきます。
複雑な現実を解きほぐす
現場で発生する問題は、一つの理論だけで割り切れるほど単純ではありません。若手の定着率が低いという課題の裏には、上司のマネジメントスタイルの問題、個人のキャリアパスが見えないという問題、チーム内の協力関係が希薄であるという問題が、複雑に絡み合っているかもしれません。単一の処方箋では、症状を一時的に和らげることはできても、根本的な治癒には至りません。
本書の巻末に収録した「応用編」の四つのケーススタディは、こうした複合的な課題に対して、複数のフレームワークをいかに組み合わせ、根本原因に迫っていくかを示すための「マクロな物語」です。
応用編のケース3「新たなマネジメントでチームが一皮むける」を例に見てみましょう。この物語の舞台は、営業成績の伸び悩みと人材定着率の低下に苦しむITソリューション企業です。この問題の構造を分析すると、三つの異なる層に原因が潜んでいることがわかります。一つは、プレイヤーとしては優秀でも、部下育成のスキルが不足している「管理職」の層。一つは、自分の強みを活かせず、キャリア成長を実感できない「一般社員」の層。最後が、個人主義が強く、互いに助け合う文化が失われている「チーム」の層です。
この複雑な状況に対し、物語の中の人事部長は三つの異なるフレームワークを処方箋として組み合わせます。管理職に対しては「スキルモデル」を用いて、専門知識(テクニカルスキル)だけでなく、部下との関係構築能力(ヒューマンスキル)や戦略的思考力(コンセプチュアルスキル)の重要性を認識させ、バランスの取れたリーダーへと成長を促します。売上目標を管理するだけでなく、部下のキャリアに寄り添い、チーム全体の方向性を描く能力が求められていることを、研修と360度評価を通じて可視化します。
一般社員に対しては「ジョブ・クラフティング」のワークショップを開催し、トップダウンで与えられた業務をこなすだけでなく、自らの強みや関心を活かして主体的に仕事の形を再設計する機会を提供します。例えば、データ分析が得意な社員が、営業戦略の立案支援という新たな役割を自ら提案し、上司との対話を通じて実現していく過程が描かれています。これは、社員が仕事の受け手から、主体的な創造者へと変わるプロセスです。
チーム全体に対しては「組織市民行動」という考え方を評価制度に組み込み、個人の売上だけでなく、同僚への支援や知識共有といったチームへの貢献行動が正当に認められる文化を醸成します。これによって、個人間の競争から、チーム全体の成功を目指す協力関係へと、組織の価値観がシフトしていきます。
この物語が示すのは、三つの施策が独立して機能するのではなく、相互に作用し、組織全体を良い方向へと動かしていく連鎖反応です。管理職が部下の話に耳を傾けるようになり(スキルモデル)、部下は自分の強みを活かした仕事を提案できるようになり(ジョブ・クラフティング)、チーム内では自然な助け合いが生まれる(組織市民行動)。この三位一体の変革によって、チームは「一皮むける」ような成長を遂げます。
応用編のマクロな物語は、読者が個別の知識を、課題の構造に応じて組み合わせる「相互に関連し合う知識体系」として捉えるためのガイドです。自社が抱える複雑な問題の構造を分析し、どの層に、どの道具を、どのような順番で適用すれば良いのか。その戦略的な思考プロセスを、物語を通じて学ぶことができます。
本書の余白は皆さんの「ケーススタディ集」に
ここまで、本書に収録された他者の物語について解説してきました。しかし、これらの事例はあくまで出発点に過ぎません。最も重要なのは、読者である皆さん自身が、自らの現場を舞台にした問題解決の物語を紡ぎ出すことです。
そのために、私は一つの実践的なアクションを提案したいと思います。それは、本書を読むだけの対象から、皆さん自身の「実践の書」へと能動的に育てていくという使い方です。
現場で課題に直面したとき、目次や索引を頼りに、関連しそうなフレームワークや事例を探してみてください。そして、本書の余白やノートに、皆さん自身の状況を書き出してみるのです。「この物語の登場人物は、私のチームでは誰だろうか」「このフレームワークを通すと、私たちの問題はどう見えるだろうか」「明日から試せる小さな行動は何だろうか」。
実際に試した結果や、そこから得られた学び、うまくいかなかったことも、本書の関連ページに書き込んでいってください。そうすることで、この一冊は市販の書籍から、皆さんの経験と知恵が詰まった、世界に一つだけの「オリジナルケーススタディ集」へと成長していきます。例えば、「LMX理論」のページの余白には、皆さんのチームメンバー一人ひとりとの関係性の分析が書き込まれ、「組織変革」のページの片隅には、皆さんが主導した小さな改革の成功と失敗の記録が刻まれるかもしれません。
このプロセスが、最も効果的な学習法でしょう。知識をインプットし、現場でアウトプットし、その結果をフィードバックとして再び知識体系に統合する。こうしたサイクルを繰り返す中で、本書は皆さんの思考を整理し、次の一手を共に考える、信頼できるパートナーへと変わっていくはずです。
物語の力を明日の一歩へ
本コラムでは、『人事・HRフレームワーク大全』が単純な理論の解説書ではなく、読者が実践への一歩を踏み出すための「物語の力」をいかに重視しているかを解説してきました。各項目に散りばめられたミクロな物語は思考のプロセスを追体験させ、応用編のマクロな物語は複雑な現実を解きほぐす統合的思考をシミュレートさせます。
フレームワークとは、無味乾燥な理論ではありません。それは、組織という舞台で繰り広げられる、人の意欲や葛藤、協力といった人間的な営みを、より深く、より正確に理解するための血の通った視点です。事例や物語は、その視点に命を吹き込み、私たちの共感と理解を促す力を持っています。
この本を手に取ってくださった皆さんには、ぜひ、その物語の力を信じていただきたいと思います。まずは本書の中の小さな物語を一つ、皆さんの現場という舞台で試してみてください。報道部長が若手記者との関係を変えたように。あるいは、営業チームが三位一体の改革で再生したように。そこから、皆さん自身の物語が始まるはずです。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。