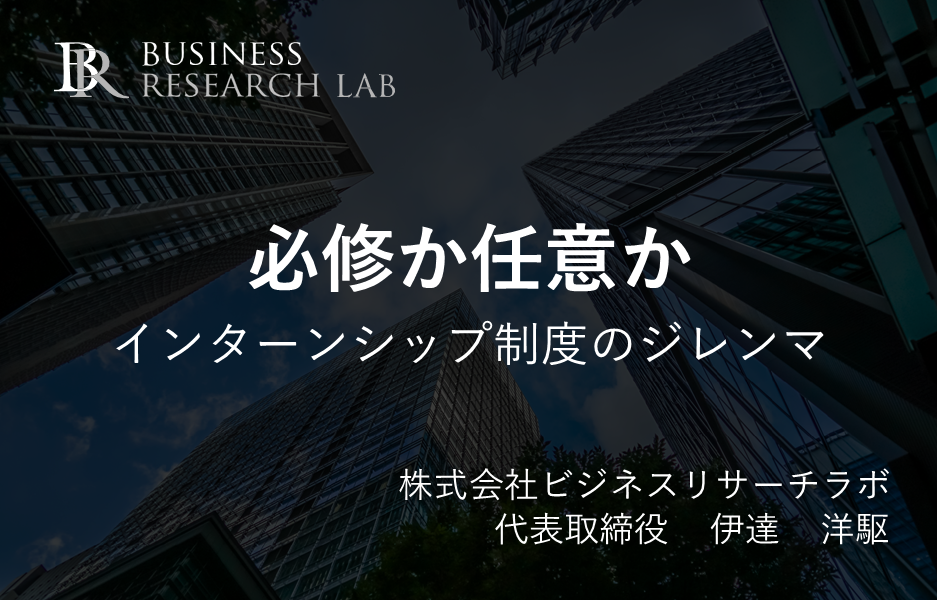2025年10月31日
必修か任意か:インターンシップ制度のジレンマ
大学生活の中で、インターンシップへの参加を考える学生も増えているでしょう。就職活動が本格化する前に、職場で働く経験を積むことで、自分の将来について考える機会となります。日本でも多くの企業がインターンシップを実施しています。
その一方で、インターンシップは本当に学生にとって価値のあるものなのか、どのような形で実施すれば効果が高いのかについては、まだ十分に理解されていない部分があります。学生はインターンシップをどのように捉えているのでしょうか。必修にすることで効果は高まるのでしょうか。それとも、学生の自主性に任せた方が良いのでしょうか。
本コラムでは、海外の大学で行われた研究をもとに、学生とインターンシップの関係について掘り下げていきます。学生自身がインターンシップをどう評価し、何を求めているのか。そして、大学や企業がどのようにプログラムを設計すれば、より効果的な学習体験を提供できるのか。これらの問いについて考えながら、インターンシップの価値について考察していきます。
インターンシップを授業よりも価値が高いと感じる
学生はインターンシップをどのように評価しているのでしょうか。アメリカの研究では、インターンシップを体験した学生114名に対して調査が行われました[1]。この調査は、アメリカ南西部にある大規模な公立大学で実施されました。
調査では、学生たちにインターンシップの価値を1から5のスケールで評価してもらいました。その結果、学生たちはインターンシップを価値の高い経験として評価し、平均で4.1という高いスコアをつけました。
学生たちは通常の授業とインターンシップを比較した際、インターンシップが授業よりも価値が高いと感じていることが分かりました。難易度や作業量については授業と同程度でしたが、学習への意欲、興味の度合い、将来のキャリアに対する価値、実用性の面では、インターンシップが上回っていました。
このような評価の背後には、どのような要因があるのでしょうか。研究者たちは、学生の個人的な特徴、プログラムの設計、そして学生のキャリア志向という3つの観点から分析を行いました。
学生の個人的な特徴について見てみると、年齢が高く学年が上がるほど、インターンシップを高く評価する傾向が見られました。また、学業成績が優秀な学生ほどインターンシップを高く評価していました。
プログラムの設計面では、給与が支払われることや大学の単位として認定されることも評価に影響しましたが、それ以上に重要だったのは、インターンシップが体系的に組織化されていることでした。学生がただ職場に配置されるのではなく、学習目標があり、大学の授業内容と関連付けられているプログラムほど、学生の評価が高かったのです。
最も強い関連性を示したのは、学生のキャリア志向でした。インターンシップが自分の将来の職業志望に近く、業務内容に強い興味を持ち、就職活動に直接役立つと感じる学生ほど、その体験を高く評価していました。
学生はインターンシップを人脈作りの機会と捉える
学生自身はインターンシップという言葉を聞いたとき、何を思い浮かべるのでしょうか。アメリカの3つの異なるタイプの大学で行われた調査では、57名の学生にインターンシップという言葉から連想される内容を自由に述べてもらいました[2]。この手法は「自由リスト法」と呼ばれるもので、人々が特定の概念をどのように理解しているかを探る際に用いられます。
調査に参加した中には、インターンシップを経験したことがある学生と、まだ経験していない学生の両方が含まれていました。学生たちが最も頻繁に挙げた言葉は、「学習」「経験」「キャリアの進展」「人脈やつながり」「有給・無給」「探索や冒険」「一時的」「機会」でした。
この中でも「経験」「学習」「有給」「人脈」という4つの言葉が、学生にとって大切な要素として浮かび上がりました。
「経験」について学生たちは、就職市場で競争力を得るために必要なものだと考えていました。履歴書に書ける実務経験を積むことが、就職活動を成功させる鍵になると認識していたのです。
「学習」については、教室での座学とは異なる体験的な学習の機会として捉えていました。職場で働くことで、自分自身や将来について理解できると考えていました。
「有給・無給」の問題については、学生たちの複雑な感情が表れました。有給のインターンシップは、その仕事の価値や真剣さを表すものとして肯定的に受け止められていました。一方、無給のインターンシップについては、経済的な負担を意識しながらも、避けることのできない現実として受け入れている学生が見られました。
「人脈」については、学生たちがインターンシップを単純な仕事体験ではなく、将来につながる関係性を築く機会として捉えていることが明らかになりました。個人的なつながりや家族の人脈を通じてインターンシップの機会を見つけており、大学教員が持つ人脈も重要な役割を果たしていました。
インターンシップを実際に経験した学生と、まだ経験していない学生の間には、語る内容に違いがありました。経験者はタスクや実務について詳細に語ったのに対し、未経験者は抽象的で一般的なイメージを述べました。未経験者は無給のインターンシップに対してより否定的な印象を持っていることも分かりました。
必修のインターンシップは就職効果がない
学生がインターンシップを高く評価し、多面的な価値を見出していることを見てきました。それでは、大学がインターンシップを必修科目として全学生に課すことで、その効果はより高まるのでしょうか。ドイツで行われた調査研究が、この問いにアプローチしています。
この研究では、ドイツの高等教育機関を卒業した2594名の学生を対象に、必修インターンシップを経験したグループとそうでないグループの卒業後の状況を比較しました[3]。調査は卒業後1年目と5年目の2回にわたって実施され、初職までの求職期間、5年間の雇用経歴の安定性、時給の3つの指標で効果を測定しました。
研究者たちは、必修インターンシップには理論的に3つのメリットがあると考えていました。第一に、その分野に特有の実務スキルを習得することで生産性が向上し、給与の増加につながる可能性があります。第二に、職場でのマナーや社会的な行動様式など、大学では学べない文化的な知識を身につけることができます。第三に、雇用主や従業員との接触を通じて、就職に有利な人脈を形成できる可能性があります。
研究者たちは、家庭の教育背景による格差にも注目しました。高学歴家庭出身の学生は、家庭環境を通じて既に文化資本や社会的つながりを持っている可能性が高い一方、低学歴家庭出身の学生にとって、インターンシップはそうした不利を補う機会になるかもしれないと仮定したのです。
しかし、分析の結果、予想に反する発見がありました。必修インターンシップを経験した学生は、確かに一見すると初職までの求職期間が短い傾向が見られました。しかし、学生の能力や家庭背景などの要因を調整すると、この違いは消失してしまいました。必修インターンシップ自体が就職活動を有利にしているのではなく、そもそも能力や環境に恵まれた学生が良い結果を得ていたのです。
雇用経歴の安定性や時給についても、調整後は有意な改善効果は認められませんでした。低学歴家庭出身の学生に対しても、必修インターンシップは求職期間の短縮や雇用安定性の向上、賃金の増加に統計的に意味のある効果をもたらしませんでした。高学歴家庭出身の学生についても同様で、必修インターンシップから特別な恩恵を受けているという証拠は見つかりませんでした。
なぜこのような結果になったのでしょうか。研究者たちは、いくつかの可能性を挙げています。強制されたインターンシップは学生の内発的な意欲を削ぐ可能性があります。自分から進んで参加するのと、義務として参加するのでは、学習への取り組み方や成果が異なる可能性があります。
必修にすると能力や意欲にかかわらず全ての学生が参加することになるため、全体の効果が薄れてしまう可能性があります。任意参加の場合、もともと能力や意欲の高い学生が参加するため、良い成果が生まれていたのかもしれません。
必修インターンシップは企業側から見ると「特別な努力の証」としてのシグナル価値が低い可能性があります。自主的にインターンシップに応募した学生と比べて、単位取得のために参加している学生を、企業が同じように評価するとは限りません。
義務的なインターンシップは卒業生の失業を減らす
ドイツの研究が必修インターンシップの効果に疑問を投げかけていることを見ました。しかし、ポルトガルで行われた調査は、これとは異なる結果を示しています[4]。経済状況や教育制度の違いが、インターンシップの効果にどのような違いをもたらすのでしょうか。
ポルトガルの研究は、深刻な若年失業問題を背景に実施されました。2013年時点で、ポルトガルの若年失業率は30%を超えており、大学卒業者であっても就職が困難な状況が続いていました。このような状況の中で、高等教育機関は学生の就職支援策として、カリキュラム内インターンシップの導入を進めていました。
研究者たちは、2008年から2009年にかけてボローニャ改革に基づいて新設または改訂された190の学部課程を分析対象としました。これらの課程の中には、新たにインターンシップを導入したものもあれば、従来通りインターンシップを含まないものもありました。失業率の測定には、ポルトガル雇用職業訓練機構に登録された公式データを使用し、インターンシップ導入前の2007年と導入後の2013年のデータを比較しました。
分析の結果、インターンシップを経験した卒業生は、そうでない卒業生よりも失業率が低いことが判明しました。この傾向は、卒業後12か月以上の長期失業率において顕著に現れました。短期的な失業だけでなく、長期間にわたって雇用状況の改善効果が持続していたということです。
研究者たちは、高等教育機関のタイプによる違いも調べました。ポルトガルには伝統的な大学と、より実践的な教育を行うポリテクニックという2つのタイプの高等教育機関があります。分析の結果、どちらのタイプの機関でもインターンシップは失業率低下に効果的でしたが、長期的には大学の方がポリテクニックよりも効果が大きいことが分かりました。
さらに、学生が自主的に選択できる任意のインターンシップと、全学生が必ず参加しなければならない義務的なインターンシップを比較したところ、義務的なインターンシップの方が失業率改善の効果が高いことが明らかになりました。この結果は、先ほど紹介したドイツの研究とは対照的なものです。
研究者たちは、この違いが生まれる理由として、義務的なインターンシップでは大学と企業の間により深い関係が築かれることを挙げています。全学生が参加する制度の下では、企業側も学生を受け入れるための体制をより整備し、学生の能力に対してより高い信頼を置きます。
インターンシップの構造についても分析が行われました。長期間の一度だけのインターンシップ(thick型)と、短期間のインターンシップを複数回実施する形式(thin型)を比較したところ、thin型の方が卒業後の失業率を下げることが分かりました。複数の異なる職場で経験を積むことで、より多様なスキルを習得し、幅広い雇用機会につながる可能性が高まると考えられます。
ドイツとポルトガルの結果の違いは、経済状況や労働市場の構造、教育制度の違いによるものと考えられます。深刻な失業問題に直面しているポルトガルでは、インターンシップが労働市場への橋渡しの役割を強く果たしているのでしょう。一方、比較的安定した労働市場を持つドイツでは、インターンシップの追加的な効果が見えにくい可能性があります。
ポルトガルの研究は、適切に設計された義務的なインターンシップが、深刻な雇用問題の解決に寄与する可能性を示しています。しかし、これが全ての国や状況に当てはまるとは限りません。重要なのは、それぞれの国や地域の経済状況、労働市場の特性、教育制度に応じて、最適なインターンシップのあり方を模索することです。
脚注
[1] Hergert, M. (2009). Student perceptions of the value of internships in business education. American Journal of Business Education, 2(8), 9-14.
[2] Hora, M. T., Parrott, E., and Her, P. (2020). How do students conceptualise the college internship experience? Towards a student-centred approach to designing and implementing internships. Journal of Education and Work, 33(1), 48-66.
[3] Klein, M., and Weiss, F. (2011). Is forcing them worth the effort? Benefits of mandatory internships for graduates from diverse family backgrounds at labour market entry. Studies in Higher Education, 36(8), 969-987.
[4] Silva, P., Lopes, B., Costa, M., Melo, A. I., Dias, G. P., Brito, E., and Seabra, D. (2016). The million-dollar question: Can internships boost employment? Studies in Higher Education, 43(1), 2-21.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。