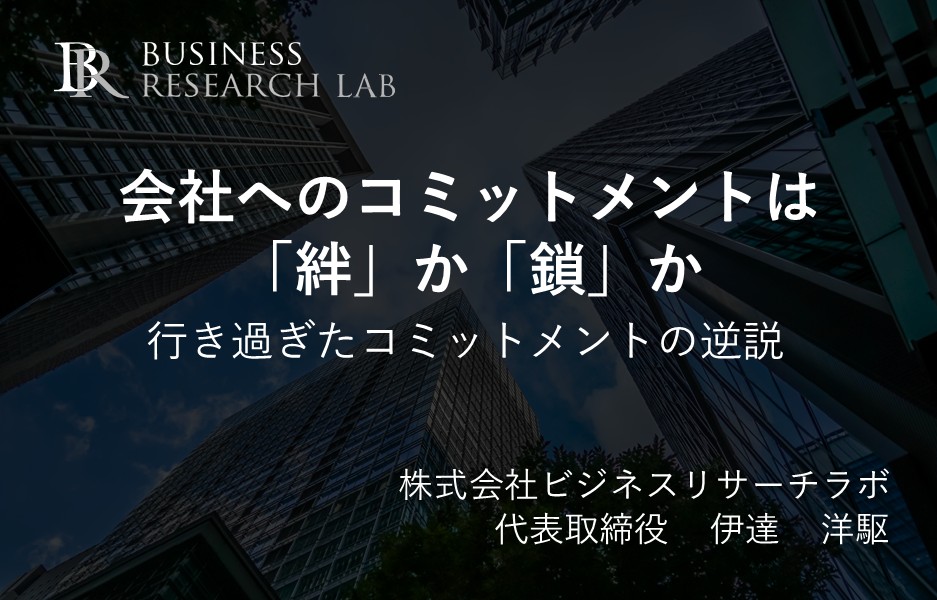2025年10月31日
会社へのコミットメントは「絆」か「鎖」か:行き過ぎたコミットメントの逆説
会社へのコミットメントが高い。この言葉を聞いたとき、多くの人が思い浮かべるのは、仕事に情熱を注ぎ、組織の目標達成のために献身的に働く、模範的な従業員の姿ではないでしょうか。企業もまた、従業員のコミットメントを高めることが生産性の向上や離職率の低下につながると考え、様々な取り組みを行ってきました。コミットメントは、組織と個人の双方にとって「善」である。私たちは長い間、そう信じてきたように思います。
しかし、そのコミットメントが、私たちの私生活や心身の健康、さらには組織の健全性そのものに対して、予期せぬ形で作用することがあるとしたらどうでしょう。「高ければ高いほど良い」という単純な物差しでは測れない、複雑で多面的な顔を持っているとしたら。
本コラムでは、「コミットメント」という一見するとポジティブな概念の光と影を、複数の学術的な調査研究を手がかりに探求していきます。会社への強い思いが、かえって共働き家庭の不和を招く現実。上司の支援という要素が加わることで、コミットメントが従業員を組織に「つなぎとめる絆」から「辞めにくくする鎖」へと姿を変える瞬間。働く場所が一つではない派遣労働者にとって、コミットメントの「対象」が心身の健康を左右する分岐点となること。そして、組織への愛着が、時に不正への「沈黙」を、時にそれを正そうとする「告発」を促す、二律背反のメカニズム。
これから紹介する議論は、コミットメントという視点を通して、現代社会における働き方を見つめ直すものです。これまで当たり前だと思っていた価値観が、少しだけ違って見えるようになるかもしれません。
コミットメントが行き過ぎると共働きで家庭衝突が増える
組織への強い一体感や愛着は、仕事へのやりがいを高め、個人の成長を促す力となります。その充実感が家庭生活にも良い雰囲気をもたらすことは、想像に難くありません。しかし、その献身がある一線を超えたとき、別の側面が見え始めます。会社に尽くす気持ちが、皮肉にも家庭内の不和の火種となることがあるのです。
この関係性を明らかにするため、韓国の公務員を対象に行われた調査があります[1]。韓国では、仕事と家庭の両立を支援する制度が整えられてきたにもかかわらず、多くの働く人々が依然としてその恩恵を十分に感じられていないという背景がありました。研究者たちは、その一因として、組織を第一に考える文化が個人の生活領域を圧迫しているのではないかと考えました。そこで、組織へのコミットメントと、「仕事の要求が家庭生活を妨げる」と感じる度合い(仕事から家庭へのコンフリクト)との間に、どのような関係があるのかを検証することにしました。
この調査では、物事を「資源」という観点から捉えるアプローチが用いられました。人々の持つ時間、エネルギー、注意力などは有限な資源です。組織へのコミットメントが高いと、仕事を通じてスキルが向上したり、自尊心が高まったりといった、個人の資源を増やす側面があります。しかし同時に、仕事に多くの時間とエネルギーを注ぎ込むことは、家庭で使えるはずだった資源を消費することにもつながります。この調査の根底には、コミットメントがもたらす資源の「獲得」と「喪失」のバランスが、ある時点で逆転するのではないか、という問いがありました。
調査の対象となったのは、1000人を超える既婚の韓国人公務員です。回答者たちは、自身がどれほど組織に愛着や一体感を感じているか(情緒的コミットメント)、そして仕事が原因で家庭生活に支障が出ていると感じるか、といった質問に答えました。研究者たちは集められたデータを分析しました。
その結果、明らかになったのは、単純な比例関係ではありませんでした。コミットメントが低い状態から中程度の水準に高まっていく間は、家庭との衝突はむしろ減少していくパターンが見られました。仕事への満足感や誇りが、家庭にも良い雰囲気をもたらしているのかもしれません。ところが、コミットメントがある転換点を超えてさらに高まると、事態は一変します。今度は、コミットメントが高まれば高まるほど、家庭との衝突が増加していくという、「逆U字型」の曲線が描かれたのです。
この関係は、世帯の形態によっても異なっていました。特に、夫婦が共に働く「共働き世帯」において、この逆U字の関係ははっきりと現れました。一方で、夫婦のどちらか一方のみが収入を得ている「片働き世帯」では、コミットメントの高さと家庭との衝突の間に、はっきりとした関連は見出されませんでした。
この結果が物語るのは何でしょうか。適度なコミットメントは、仕事のパフォーマンスを高めるだけでなく、個人の幸福感を通じて私生活にも潤いをもたらすかもしれません。しかし、その献身が「過剰」なレベルに達すると、仕事が家庭生活を侵食し始めます。限られた時間とエネルギーという資源が仕事に過剰に投資されることで、家庭で求められる配慮や協力といったタスクをこなすための資源が枯渇してしまうのです。
仕事家庭葛藤は上司支援次第でコミットメントが増減する
仕事と家庭の間で生じる葛藤は、個人のコミットメントの度合いだけで決まるものではありません。その人が置かれている職場環境、中でも日々顔を合わせる直属の上司の存在は、この葛藤のありようを左右する可能性があります。上司からの理解や支援は、板挟み状態で苦しむ従業員の心を軽くする緩衝材となるのでしょうか。それとも、別の化学反応を引き起こすのでしょうか。
この問いを探るため、アフリカ大陸のケニア、その首都ナイロビの銀行で働く人々を対象とした調査が行われました[2]。文化や労働慣行が日本とは異なる環境で、仕事と家庭の葛藤が組織へのコミットメントにどのように結びつくのかを多角的に分析したものです。
この調査のユニークな点は、まず仕事と家庭の葛藤を二つの方向から捉えたことです。一つは、仕事の要求が家庭生活に支障をきたす「仕事から家庭への葛藤」。もう一つは、逆に家庭の事情が仕事に影響を及ぼす「家庭から仕事への葛藤」です。さらに、組織へのコミットメントも一括りにはせず、「この組織の一員でいたい」という情緒的な愛着(情緒的コミットメント)、「辞めると損だから留まる」という計算的な打算(継続的コミットメント)、そして「組織に尽くすべきだ」という道徳的な義務感(規範的コミットメント)という、三つの異なる種類に分けて測定しました。
研究者たちは、これらの葛藤と三種類のコミットメントの関係に、「上司からの支援をどの程度感じているか」という要素と「性別」が、どのように関わってくるのかを明らかにしようとしました。分析の枠組みとしては、人は複数の役割を同時にこなす難しさに直面するという考え方(役割理論)や、誰かから恩恵を受けたらお返しをしたくなるという心理(社会的交換理論)が参考にされました。
ナイロビ市内の商業銀行に勤務する約300人の従業員が調査に協力しました。アンケートを通じて、仕事と家庭の葛藤の度合い、上司の支援に対する認識、そして三種類のコミットメントのレベルなどが尋ねられました。
分析から得られた結果は、単純な予想を裏切るものでした。当初、仕事と家庭の葛藤はコミットメントを下げるだろうと予測されていましたが、実際には、「仕事から家庭への葛藤」が高い人ほど、三種類すべてのコミットメントが高いという、一見すると逆説的な結果が出たのです。
複雑なのは、上司の支援がこの関係に及ぼす作用です。例えば、「仕事から家庭への葛藤」が高い状況で、上司からの支援を強く感じている従業員は、「この会社を辞めると失うものが大きい」と考える継続的コミットメントが一段と強まることがわかりました。しかしその一方で、同じ状況でも「組織と情緒的に一体化したい」という情緒的コミットメントは、むしろ抑制されるというパターンが見られました。上司の支援は、従業員のコミットメントの「質」を変化させるスイッチのような働きをしていたのです。
性別による違いも確認されました。ケニアの文化的背景もあってか、「家庭から仕事への葛藤」は女性の方が高く、その葛藤がコミットメントに結びつく形も男女で異なっていました。
これらの結果から何を読み取れるでしょうか。まず、「葛藤が高いのになぜコミットメントも高いのか」という点です。研究者たちは、調査対象となったケニアの銀行業界の文化にその答えを求めます。そこでは、長時間労働や仕事優先の姿勢が忠誠の証とみなされ、仕事のために私生活を犠牲にすること自体が、組織への献身として内面化されている可能性があります。
そして、上司の支援の働きです。支援は、必ずしも情緒的な絆を深める万能薬ではありません。厳しい労働環境の中で上司が支援の手を差し伸べたとき、従業員は「この上司や会社に応えたい」と感じるよりも先に、「これだけの支援があるのだから、辛くても辞めるわけにはいかない」という計算的な判断に傾くことがあります。上司の支援は、葛藤に苦しむ従業員を情緒的に救うのではなく、むしろ組織に「留まらせる」ための要因として機能する場合があることを、この調査は示唆しています。
コミットメントの対象次第で派遣労働者の健康影響が逆転する
これまで見てきたコミットメントの話は、主に一つの企業に所属する正社員を前提としていました。しかし、現代の働き方は多様化しています。特に、派遣労働者のように、籍を置く「派遣元」と、実際に業務を行う「派遣先」という二つの組織に関わる人々にとって、コミットメントの問題はより複雑な様相を呈します。自分の忠誠心は、一体どちらの組織に向けられるべきなのか。そして、そのコミットメントの「対象」の違いは、働く人の心身にどのような違いをもたらすのでしょうか。
この問いに光を当てたのが、ドイツの派遣労働者を対象に、14ヶ月という長期間にわたって行われた追跡調査です[3]。この調査の核は、コミットメントを「両刃の剣」として捉える視点にあります。組織への愛着は、安定した状況では心の支えという「資源」になりますが、環境が変化する際には、逆に心を傷つける「脆弱性」にもなりうる、という考え方です。
研究者たちは、ドイツの事務系の派遣労働者を対象に、就業開始から約2ヶ月後、5ヶ月後、そして14ヶ月後の三つの時点で、継続的にアンケート調査を行いました。調査では、派遣元と派遣先のそれぞれに対するコミットメントの強さ、調査期間中に派遣先が変わったかどうか、そして、頭痛や不眠、気分の落ち込みといった心身の不調の度合いが測定されました。この縦断的な設計によって、時間の経過と共に、派遣先の変更という出来事が、コミットメントの対象によって個人の健康状態にどう作用するのかを追跡することができました。
分析から浮かび上がってきたのは、対照的な二つのパターンでした。初めに、「派遣先」の企業に対して強いコミットメントを抱いていた人々です。この人たちは、同じ派遣先で働き続けている間は、心身の不調が少なく、健康状態は良好でした。派遣先での人間関係や仕事内容に馴染み、そこを「自分の居場所」と感じることが、日々のストレスを和らげるクッションになっていたのでしょう。しかし、契約期間の終了などで派遣先が変わると、状況は一変しました。派遣先へのコミットメントが高かった人ほど、異動後に心身の不調が悪化するという結果になりました。
一方で、「派遣元」の会社に対して強いコミットメントを抱いていた人々は、全く逆の反応を示しました。この人たちの場合、調査期間中に派遣先が変わっても、健康状態への悪影響は見られませんでした。それどころか、派遣先が変わった後の方が、むしろ心身の不調が少し和らぐというパターンさえ観察されたのです。
この正反対の結果は、一体どうして生まれたのでしょうか。そのメカニズムを解き明かす鍵は、コミットメントの「対象」にあります。派遣先へのコミットメントは、その場所やそこにいる人々への具体的な愛着です。そのため、異動という出来事は、築き上げてきた人間関係や慣れ親しんだ環境を失う「喪失体験」として認識され、大きなストレスを引き起こします。愛着が強いほど、失ったときの痛みも大きいのです。
それに対して、派遣元へのコミットメントは、より抽象的で、包括的なものです。「自分はあくまで派遣元の社員であり、様々な派遣先で経験を積むのが仕事だ」という職業的なアイデンティティを支えます。この認識は、派遣先が変わることを「予期せぬ喪失」ではなく、「計画された通常業務の一環」として捉えることを可能にします。そのため、異動という変化に対する心の準備ができており、環境変化がもたらすストレスを和らげる緩衝材として機能したと考えられます。
コミットメントが中程度で内部告発最多
コミットメントが個人の私生活や健康に作用する様相を見てきましたが、その矛先は組織内部の行動にも向けられます。組織の不正や非倫理的な行為を知ったとき、従業員はどのような行動をとるのでしょうか。組織への強い愛着は、不正を正そうとする勇気を奮い立たせるのか、それとも「組織への裏切りはできない」という忠誠心から沈黙を促すのか。
この問題に関して、古くから二つの相反する見方が存在してきました。一つは「改革者(リフォーマー)仮説」です。これは、組織への愛着があるからこそ「この組織をより良くしたい」と願い、勇気を出して不正を告発するという考え方です。もう一つは「組織人(オーガニゼーション・マン)仮説」で、こちらは組織へのコミットメントが高すぎる従業員は、組織と自分を同一視するあまり、組織の欠点を外部に露呈させるような内部告発という行為には踏み切れない、とする考え方です。
どちらの仮説が現実をより良く説明するのか。この点を検証するために、アメリカの会計士を対象とした調査が行われました[4]。この調査の巧みな点は、コミットメントと内部告発の関係を、単純な「高いか低いか」の二元論ではなく、コミットメントのレベルを「低い・中程度・高い」という連続的なものとして捉え、その非線形な関係性を探ったところにあります。
調査に参加した全米の会計士たちは、架空のシナリオを提示されました。それは、自身が勤める組織で財務上の不正を発見した、という状況です。その上で、「直属の上司」「内部の監査部門」「企業の監査委員会」といった組織内部の窓口から、「政府の規制機関」や「マスメディア」といった組織外部の機関に至るまで、様々な告発先に「報告しようと思うか」その意図を尋ねられました。同時に、回答者自身の現在の組織に対するコミットメントの度合いも測定され、両者の関係が統計的に分析されました。
分析結果は、告発の相手が組織の「内部」か「外部」かによって、くっきりと分かれました。
初めに、上司や内部監査部門といった「組織内部」への告発意図についてです。ここで見られたのは、「改革者仮説」と「組織人仮説」の両方を部分的に裏付けるような、「逆U字型」の関係でした。組織へのコミットメントが非常に低い人々と、非常に高い人々の双方で、内部告発への意図は低いのです。そして、告発意図が最も高まったのは、コミットメントが「中程度」の人々でした。
一方、政府やマスコミといった「組織外部」の機関への告発意図は、異なる様相を示しました。こちらについては、組織へのコミットメントのレベルとは何の関係も見られず、全体として低い水準に留まっていました。
この結果は、組織へのコミットメントが持つ力学を浮き彫りにします。コミットメントが低すぎる人々は、そもそも組織への関心が薄く、不正があっても「自分には関係ない」と行動を起こさないのかもしれません。逆に、コミットメントが高すぎる人々は、組織への強い忠誠心が、組織の負の側面から目を背けさせ、問題を内々で処理しようとするか、あるいは完全に沈黙させてしまう可能性があります。
その中間に位置する、適度なコミットメントを持つ人々が、組織の自浄作用を担う鍵となるのかもしれません。彼ら彼女らは、組織を「自分たちのもの」として愛着を感じつつも、組織と完全に一体化するのではなく、一歩引いて客観的に物事を見る視点を失っていません。その健全な距離感が、「組織を良くするためには、この不正は正さなければならない」という建設的な行動へとつながるのです。
盲目的な忠誠心ではなく、是々非々で判断できる批判的な精神を伴った献身が、組織の長期的な健全性を支える。この調査は、マネジメントが目指すべき従業員像について、示唆を与えてくれます。
脚注
[1] Lee, H., and Lee, S.-Y. (2021). Is more commitment always better? A study on the side effects of excessive organizational commitment on work-family conflict. Review of Public Personnel Administration, 41(1), 25-56.
[2] Mukanzi, C. M., and Senaji, T. A. (2017). Work-family conflict and employee commitment: The moderating effect of perceived managerial support. SAGE Open, 7(3), 1-12.
[3] Galais, N., and Moser, K. (2009). Organizational commitment and the well-being of temporary agency workers: A longitudinal study. Human Relations, 62(4), 589-620.
[4] Somers, M. J., and Casal, J. C. (1994). Organizational commitment and whistle-blowing: A test of the reformer and the organization man hypotheses. Group & Organization Management, 19(3), 270-284.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。