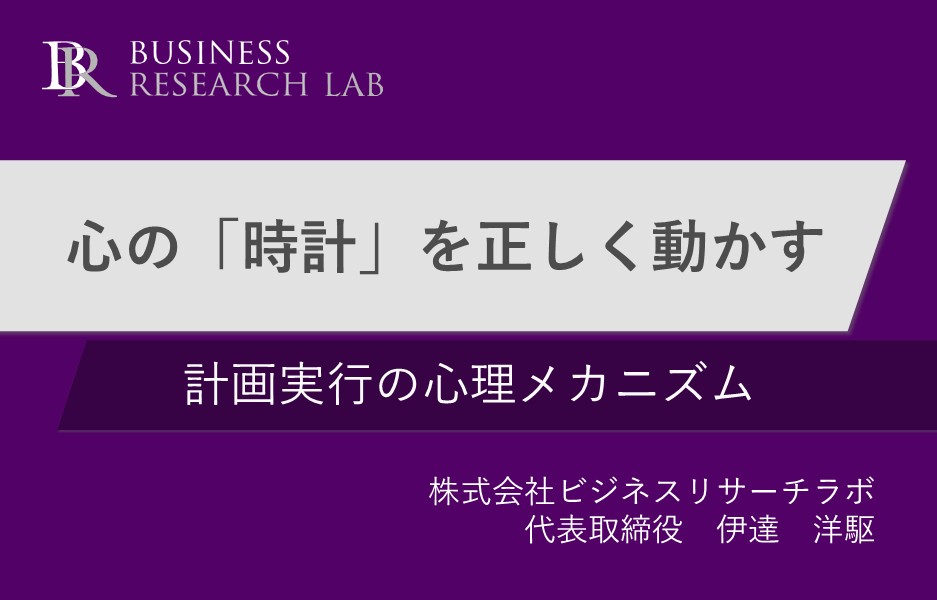2025年10月31日
心の「時計」を正しく動かす:計画実行の心理メカニズム
「今度こそ、計画通りに終わらせる」。そう固く誓ってスケジュール帳に書き込んだはずのタスクが、気づけば締め切り直前になっても手つかずのまま。あるいは、余裕を持って組んだはずの計画が、日を追うごとに崩れていき、最後は慌ただしく帳尻を合わせる羽目になる。このような経験は、多くの人にとって決して他人事ではないでしょう。私たちはしばしば、自らの能力を過信し、完璧な計画を立てた気になっては、その計画が脆くも崩れ去るという現実を目の当たりにします。
この「計画倒れ」という現象を、個人の意志の弱さや能力不足のせいだと片付けてしまうのは簡単です。しかし、この問題の根源は、私たちの誰もが持つ心の「クセ」にたどることもできます。人間が物事を認識し、判断する過程には、特定の状況下で非合理的な結論を導きやすい、体系的な思考の偏りが存在することが知られています。時間を見積もるという行為も、その例外ではありません。
本コラムでは、計画倒れという悩みの背後にある、人間の心の働きを解き明かしていきます。なぜ私たちは未来を楽観視してしまうのか。過去の経験は、見積もりにどう関わっているのか。個人の性格や物事の進め方は、計画の成否にどう結びつくのか。これらの問いへの答えを探ることを通じて、計画倒れという現象を新たな視点から捉え直すことができるはずです。
タスクを細分化すると時間見積もりが実際に近づく
大きな仕事や馴染みのないプロジェクトを前にしたとき、「一体どれくらいの時間がかかるのだろう」と見当もつかず、途方に暮れた経験はないでしょうか。全体像がぼんやりとしか見えないタスクに対して、私たちは正確な所要時間を見積もることが苦手です。こうした状況で、タスクの「見方」を少し変えるだけで、見積もりの精度が変わる可能性を示唆する一連の心理学実験があります[1]。
この探求の中心にある問いはシンプルです。一つの大きなタスクとして丸ごと時間を見積もる方法と、それをいくつかの小さなサブタスクに分解し、それぞれの見積もりを合計する方法とでは、どちらがより現実に近い数値を導き出すのでしょうか。
最初の実験は、比較的短い時間で完了する事務的な作業を用いて行われました。参加者である大学生たちは、いくつかのグループに分けられました。あるグループには、複数の作業をひとまとめにした「タスクセット」として、全体の所要時間を見積もってもらいます。一方、別のグループには、同じ作業を一つひとつ個別に見積もってもらい、後からその合計時間を算出しました。
その結果、タスクを個別に細かく見積もった場合の方が、ひとまとめに見積もるよりも合計時間が長くなることがわかりました。興味深いことに、この実験で扱われたような短いタスクでは、分割して見積もった時間は、実際にかかった時間よりも長くなる「過大評価」の様相を呈しました。
この結果だけを見ると、タスクを分割するとかえって見積もりが不正確になるように思えるかもしれません。しかし、研究はより長い時間を要するタスクで、この現象を掘り下げました。次に行われた実験では、完了までに20分から40分程度かかる、より複雑な課題が用いられました。手続きは最初の実験と同じです。参加者は、課題全体を一括で見積もるか、あるいはいくつかのステップに分割して個別に見積もるかのどちらかを行いました。
ここでも、タスクを分割した方が合計の見積もり時間は長くなりました。しかし、この実験では異なる結果が得られました。課題全体を一括で見積もったグループは、実際にかかった時間よりも短い時間を見積もるという、典型的な「計画錯誤」に陥っていたのです。それに対して、タスクを分割して見積もりを合計したグループでは、この過小評価が抑制され、実際の所要時間とほとんど差がないか、わずかに長い程度の現実的な見積もりを立てることができていました。
これらの結果から、タスクを分割するという行為が、課題の所要時間によって異なる働きをすることが見えてきます。短いタスクでは過大評価を招くことがある一方で、見通しを立てるのが難しい中長時間のタスクにおいては、根拠のない楽観論に陥るのを防ぎ、より安全で現実的な計画を立てる上で助けとなります。
なぜタスクを分割すると見積もりが長くなるのでしょうか。一つの可能性として、私たちが時間を見積もる際に「5分」「10分」といったキリの良い数字を使いがちな「丸め」という習慣が考えられます。例えば、実際には2分で終わる作業も「まあ5分くらいかな」と切り上げてしまう。こうした小さな切り上げが、タスクを分割することで積み重なり、合計時間を押し上げるのかもしれません。
この可能性を検証するため、さらに別の実験が行われました。そこでは、数字で時間を記入させる代わりに、1時間を表す一本の直線が引かれた紙が用いられました。参加者は、タスクにかかると思う時間の長さを、この直線の上に印をつけることで視覚的に表現します。この方法であれば、「5分」や「10分」といった特定の数字に引きずられることなく、より直感的に時間を見積もることができます。結果、この「丸め」が起きにくい状況でも、やはりタスクを分割してから見積もった方が、合計の見積もり時間は長くなりました。
このことは、タスク分割の効果が、数字の丸めという表面的な習慣だけでは説明できない心の働きに由来することを示唆しています。大きな仕事の塊を目の前にすると、私たちはその内部に含まれる細々とした準備、段取り、確認作業、あるいは小休憩といった、目に見えにくい「付随時間」を忘れやすいのでしょう。しかし、タスクを意識的に分解するプロセスを経ることで、これまで見過ごしていた一つひとつのステップが可視化されます。忘れ去られていた時間が拾い上げられ、見積もり全体がより現実に即したものへと変化していくのかもしれません。
実測値提示で記憶が矯正され、予測誤差が半減する
「この作業は前にもやったことがある。だから今度はもっと手際よく、短時間で終えられるはずだ」。私たちは過去の経験を頼りに未来の計画を立てます。しかし、そのとき私たちが思い浮かべている「前回かかった時間」の記憶は、果たしてどれほど正確なものなのでしょうか。計画がうまくいかない原因は、未来に対する楽観的な見通しだけにあるのではなく、参照している過去の記憶そのものの「歪み」に根差しているのではないか。この問いから出発した一連の研究は、時間見積もりの精度を考える上で、新たな光を投げかけます[2]。
この仮説を検証するために、ある実験が行われました。参加した大学生たちには、500枚の紙を10枚ずつの束に数える、という単純な作業に取り組んでもらいました。作業が終了した後、参加者は二つのグループに分けられます。
一方の「記憶想起グループ」には、「今の作業に、だいたい何分くらいかかったと思いますか?」と尋ね、自身の記憶を頼りに所要時間を思い出してもらいました。もう一方の「フィードバックグループ」には、研究者がストップウォッチで正確に計測した「〇分〇秒かかりました」という客観的な実測値が伝えられました。その後、両方のグループの全員に、「もしこの作業をもう一度やるとしたら、次はどのくらいの時間がかかると思いますか?」と予測させ、実際に二度目の作業を行ってもらいました。
その結果、自分の記憶を頼りに所要時間を思い出したグループは、実際にかかった時間よりも短く記憶していることがわかりました。この歪んだ記憶が、そのまま次の予測に反映されていました。過去を短めに記憶していた人々は、未来もまた楽観的に短く予測してしまったのです。一方で、正確な実測値を伝えられたフィードバックグループでは、この過小評価の傾向が解消され、予測と実際の時間のズレは、記憶想起グループに比べて減少しました。
この実験は、私たちの記憶がいかに曖昧で、都合よく短縮されるか、そしてその不正確な記憶が、未来の計画を誤った方向へと導く原因となりうることを示しています。逆に言えば、正確な過去のデータは、未来の予測を現実的な路線に引き戻すための「錨(いかり)」のような働きをします。
では、この「錨」は、いつ下ろすのが最も良いのでしょうか。フィードバックのタイミングが与える影響を調べるため、次の実験が設計されました。参加者は、二つの異なるテーマで短いエッセイを執筆します。一度目の執筆が終わった後、そして二度目の執筆を始める直前の、様々なタイミングで、記憶を思い出させる、あるいは実測値を提示するといった介入が行われました。
この実験で最も予測の精度が高くなったのは、「二度目の作業を予測する直前」に、一度目の正確な実測値を伝えられたグループでした。一度目の作業直後に実測値を伝えられて記憶が一度は正確になっても、一週間という時間が経過した後、いざ二度目の予測を立てる段になって自力で思い出そうとすると、その記憶は再び歪んでしまい、せっかくのフィードバックの効果が薄れてしまうこともわかりました。正確な情報も、時間が経てば忘れ去られたり、曖昧になったりします。このことから、過去のデータという「錨」は、計画という船出のまさにその瞬間に参照できる状態にあることが肝心だと言えます。
これまでの実験は、自分自身の過去の経験に関するものでした。しかし、初めて取り組むタスクなど、自分の中に参照できるデータがない場合はどうでしょうか。それを探るため、研究者たちは実験室を飛び出し、ガソリンスタンドやファストフード店、理髪店といった実社会の様々な場所で調査を行いました。そこでサービスを待つ人々に対し、「この用事が終わるまで、どのくらいの時間がかかると思いますか」と尋ねました。ただし、参加者の一部には、質問の前に「ちなみに、この場所での平均的な所要時間は〇分です」という、他の人々の平均的な実績データを伝えました。
結果的に、自分自身の過去の経験とは関係のない、「他者の平均値」を知らされただけでも、人々の予測誤差は、何も知らされなかったグループに比べて約半分にまで減少しました。この事実は、客観的な基準値が存在するだけで、私たちは自分の能力を過信したり、状況を楽観視したりする個人的なバイアスから一歩距離を置き、より冷静な見積もりを立てられるようになることを示唆しています。
勤勉志向は時間予測誤差を縮め、享楽志向は拡大させる
私たちの周りを見渡してみると、時間の使い方は人それぞれであることがわかります。いつも計画的で、立てたスケジュールを着実に実行していく人がいる一方で、締め切りが迫らないとなかなか行動に移せず、常に時間に追われている人もいます。こうした個人のスタイルの違いは、習慣の問題なのでしょうか、それとも、その人の性格的な特性と結びついているのでしょうか。そして、それは時間見積もりの精度にどのように関わってくるのでしょうか。
計画倒れの度合いに見られる個人差の背景には、時間に対するその人の基本的な姿勢が隠れているのではないか。この着想から、ある研究では、個人のパーソナリティと時間見積もりの誤差との関連性が探られました[3]。
この研究では、大学生を対象に、時間に関する考え方や行動パターンを測定するための質問紙調査が実施されました。調査項目は、「時間を計画的に、構造立てて使う傾向」や、「過去・現在・未来という時間軸の、どれを重視して生きているか」といった内容を含みます。集められた回答を分析したところ、人々の時間に対する姿勢は、二つの異なるタイプに分類できることが見出されました。
一つは、未来を見据え、目標達成のために物事を効率的に、粘り強く進めようとするタイプです。この研究では、この特性を「勤勉・計画志向」と名付けました。もう一つは、先のことを計画するよりも「今、この瞬間」を大切にし、物事を柔軟に、あるいはやや行き当たりばったりに進めることを好むタイプです。こちらは「刹那・享楽志向」と名付けられました。もちろん、誰もがこのどちらかに完璧に当てはまるわけではなく、誰もが両方の側面を併せ持っていますが、どちらの傾向がより強いかという点で個人差が見られます。
これらの特性が実際の時間見積もりとどう関わるかを調べるため、実験が行われました。参加者には、二種類の課題が与えられます。一つは、多くの人が好ましいと感じるであろう「短い物語を読み、登場人物のカップルの将来がどうなるかを自由に記述する」という創造的な課題。もう一つは、退屈で骨が折れるであろう「膨大な数字の羅列の中から、特定の数字をすべて探し出して印をつける」という単調な課題です。参加者は、学期の終わりまでの数週間の間に、これらの課題をいつ終えることができるか、具体的な完了予定日時を予測して提出しました。そして、実際に課題が提出された日時と比較することで、予測と現実のズレが計測されました。
全体的な結果としては、やはり多くの人が、予測した日時よりも実際に完了した日時の方が遅くなるという、計画錯誤のパターンが確認されました。その中でも、個人差がとりわけはっきりと表れたのは、「好ましくない」と感じられる退屈な課題においてでした。
「勤勉・計画志向」の傾向が強い人ほど、予測の正確さが高いことがわかりました。彼ら彼女らはタスクを実際に早く完了させる能力が高く、同時に、予測と実際のズレも小さいという結果でした。一方で、「刹那・享楽志向」の傾向が強い人々は、対照的なパターンを示しました。「早くこの面倒な作業を終わらせてしまいたい」という願望が先行するのか、完了予測は早めに設定される傾向にありました。しかし、実際の行動は遅れやすく、なかなか課題に取りかからないため、予測と現実の間に大きなギャップが生まれてしまいました。
この結果は、時間見積もりの誤差というものが、計算ミスや見通しの甘さといった技術的な問題だけでなく、その人の価値観や物事への取り組み方といった、パーソナリティの次元と結びついていることを物語っています。勤勉・計画志向の人は、計画を立て、それに沿って行動すること自体に価値を見出し、予測と現実を一致させようと努めます。対照的に、刹那・享楽志向の人は、目の前の快・不快に判断が左右されやすく、願望(早く楽になりたい)と実際の行動(面倒なことは避けたい)とが食い違い、その矛盾が計画倒れという形で表面化するのかもしれません。
実行意図が中断を抑え、完了時間と誤差を短縮する
「今日こそあのレポートを仕上げよう」。そう心に決めたはずなのに、いざ机に向かうと、急ぎでもないメールの返信を始めたり、ふと気になったニュースを追いかけてしまったり。私たちの周りには、計画の実行を妨げる無数の「誘惑」や「中断」が潜んでいます。せっかく立てた計画も、行動に移せなければ絵に描いた餅に終わってしまいます。計画と実行の間にある溝を、どうすれば乗り越えることができるのでしょうか。
計画倒れを克服するためのアプローチとして、これまでは「楽観的すぎる見積もりを、より現実的に戒める」という方向性が主流でした。しかし、発想を転換し、見積もりそのものを変えるのではなく、行動の効率性を高めることによって、結果的に見積もりと現実のギャップを埋めることはできないか。この新しい視点から、「実行意図(implementation intentions)」という心理的な手法の検証が行われました。
「実行意図」とは、単に「~をしよう」と目標を立てる(これを「目標意図」と呼びます)だけでなく、その目標を「いつ、どこで、どのようにして実行するのか」を、あらかじめ具体的かつ詳細に計画しておくことを指します。例えば、「レポートを書く」という目標意図に、「明日の朝9時に、図書館の静かな席で、まずは最初の30分で構成を練る」という実行意図を付け加える、といった具合です。
この実行意図が時間見積もりと実際の遂行にどのような影響を及ぼすかを調べるため、ある実験が計画されました[4]。参加した大学生たちには、「自由時間の過ごし方に関するレポート」を、指定された週の間に完成させて提出するという課題が与えられました。
参加者は二つのグループに分けられます。一方の「実行意図グループ」には、レポートを書く具体的な曜日、時刻、場所を決めさせ、その場面を心の中で鮮明に思い描くよう指示しました。もう一方の「統制グループ」には、「期限内にレポートを提出してください」と、目標意図を伝えるだけでした。そして、参加者全員に、作業の開始から完了までにかかる日数を予測してもらい、実際にいつ作業を終えたか、また作業中に何回中断したかを記録してもらいました。
結果は、従来の想定とは異なるものでした。驚いたことに、実行意図を設定したグループは、統制グループに比べて「より早く終えられるだろう」と、予測自体が楽観的になったのです。しかし、ここからがこの研究の核心部分です。彼ら彼女らの実際の行動は、その楽観的な予測をさらに上回るほど迅速でした。結果、予測と実際のズレ(誤差)は、統制グループと比較して小さくなりました。
なぜ、このようなことが起きたのでしょうか。その謎を解く鍵は、参加者が記録していた「中断回数」にありました。分析の結果、実行意図を設定したグループは、作業中の中断回数が統制グループの半分以下に抑えられていたことが判明したのです。
この結果から、実行意図のメカニズムが見えてきます。「いつ、どこで」という具体的な行動計画をあらかじめ立てておくと、その状況が訪れたときに、私たちの脳は半ば自動的に「さあ、やるべき時間だ」というスイッチを入れてくれます。これによって、他の魅力的な誘惑に対する抵抗力が高まり、行動への移行がスムーズになるのでしょう。意志の力に頼って「頑張るぞ」と気合を入れるのとは異なります。あらかじめ行動の「引き金」を環境に仕込んでおくことで、意志力の消耗を最小限に抑えながら、計画された行動へと自らを導く仕組みと言えます。
脚注
[1] Forsyth, D. K., and Burt, C. D. B. (2008). Allocating time to future tasks: The effect of task segmentation on planning fallacy bias. Memory & Cognition, 36(4), 791-798.
[2] Roy, M. M., Mitten, S. T., and Christenfeld, N. J. S. (2008). Correcting memory improves accuracy of predicted task duration. Journal of Experimental Psychology: Applied, 14(3), 266-275.
[3] Pezzo, M. V., Litman, J. A., and Pezzo, S. P. (2006). On the distinction between yuppies and hippies: Individual differences in prediction biases for planning future tasks. Personality and Individual Differences, 41(8), 1359-1371.
[4] Koole, S. L., and van ’t Spijker, N. (2000). Overcoming the planning fallacy through willpower: Effects of implementation intentions on actual and predicted task-completion times. European Journal of Social Psychology, 30, 873-888.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。