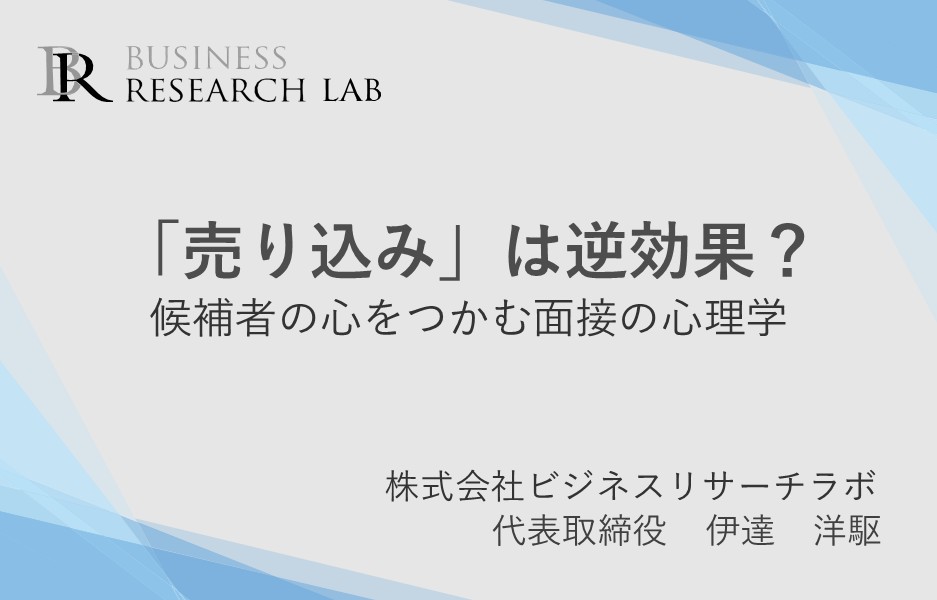2025年10月30日
「売り込み」は逆効果?:候補者の心をつかむ面接の心理学
採用面接は、場合によっては、企業と候補者が初めて直接的かつ本格的に対話する機会です。候補者にとって、面接官の言動は企業全体を判断する手がかりとなり、その後の就職意欲や企業への印象を左右します。面接スペースでの短時間のやり取りが、候補者の心の中でどのような心理的プロセスを通じて企業イメージを形成していくのでしょうか。
近年の研究では、面接官の振る舞いが候補者の企業評価に及ぼすメカニズムが明らかになってきています。候補者は面接官の態度から、その企業の組織文化や価値観を推測し、自分がそこで働くことの魅力度を判断しているのです。
本コラムでは、面接官のコミュニケーション行動が候補者の企業認識に波及する心理的過程について、複数の実証研究の知見を通じて解説します。面接における選抜評価と企業アピールのバランス、面接官の印象管理行動の種類と効果、対人的な温かさが生み出す推論プロセス、そして面接の標準化と個別化がもたらすシグナルの違いまで、幅広い観点から検討していきます。
選抜重視の面接は企業魅力度を高め、過剰売り込みは下げる
アメリカの大学キャンパスで行われる企業の採用面接を調査した研究があります。この研究では、面接官の行動が候補者の企業に対する魅力度や内定への期待感にどのような関わりを持つかを、2,331件の面接を対象に分析しました[1]。最終的に233件の面接について、候補者と面接官の両方からアンケート回答を得て、詳細な検証を行いました。
研究では面接官の行動を五つの側面に分けて測定しました。候補者への関心の度合い、提供する情報の豊富さ、面接の構造化レベル、威圧的な態度、そして企業の売り込み行動です。これらの要素が候補者の「内定をもらえそうだ」という期待感と「この企業は魅力的だ」という評価にどう結びつくかを調べました。
その結果、面接官の行動は候補者の期待感の19パーセント、企業魅力度の17パーセントを説明することができました。中でも特に重要な三つの要素が明らかになりました。第一に、候補者に対して関心を示すことです。面接官が候補者の発言に熱心に耳を傾け、質問を深掘りし、個人的な興味を表現することで、候補者は自分が評価されていると感じるようになります。
第二に、情報提供の充実です。企業の事業内容、職務の詳細、キャリアパス、職場環境について具体的で有用な情報を提供することで、候補者は企業を判断するための材料を得ることができます。第三に、適度な企業アピールです。企業の強みや魅力を伝えることは確かに効果がありますが、これは後述する注意点があります。
一方で、予想外の発見もありました。面接時間の配分に関する分析では、選抜評価に時間を多く割く面接ほど、候補者の期待感と企業魅力度が高まることが分かりました。候補者は面接官が自分をしっかりと理解しようとする姿勢を肯定的なシグナルとして受け取っていました。
これとは対照的に、企業のマーケティングに時間を多く費やす面接では、候補者の魅力度評価が低下することが確認されました。過度な売り込みは候補者に懐疑的な印象を抱かせます。候補者は「なぜこんなにアピールする必要があるのか」と疑問を感じ、企業の信頼性に疑念を持つようになります。
面接の構造化については、質問リストの使用や評価基準の明示といった要素は、面接官の行動の質を底上げする土台として機能しましたが、直接的に企業魅力度を高める効果は見られませんでした。構造化は公正性や組織の誠実さを示すシグナルとして間接的に作用するものの、候補者が感じる魅力は面接官の対人行動により強く依存することが明らかになりました。
面接官の個人的属性(性別、年齢、学歴、人種)は候補者の評価にほとんど関わりを持ちませんでした。候補者が重視するのは「どんな人か」ではなく「どう振る舞うか」だったのです。この結果は、多様な背景を持つ面接官を配置する場合でも、行動基準を統一すれば一貫した候補者体験を提供できることを示しています。
組織売り込みは威信を、候補者称賛は自信を高める
スイスの大学で実施された入学選考面接を活用した研究では、面接官の印象管理行動が候補者に与える効果を、詳細に分析しています。この研究は153件の面接を全てビデオ録画し、面接官の発言を分類することで、どのような印象操作がどのような心理的反応を生み出すかを明らかにしました[2]。
研究者たちは面接官の印象管理行動を二つの主要なカテゴリーに分けました。一つ目は組織強化行動で、これは企業や大学の優秀さ、実績、将来性などを積極的にアピールする行為です。「私たちの組織は業界でトップクラスの成果を上げています」「卒業生は多くの有名企業で活躍しています」といった発言がこれに該当します。
二つ目は候補者強化行動で、面接中に候補者の能力や経験を称賛し、ポジティブなフィードバックを提供する行為です。「素晴らしい経験をお持ちですね」「その考え方は非常に的確です」といった候補者を持ち上げる発言がこれに当たります。
ビデオ分析の結果、これら二つの印象管理行動は異なる効果を持つことが判明しました。組織強化行動は主に候補者の組織に対する威信認知を高めました。面接官が組織の優位性を語ることで、候補者は「この組織は社会的地位が高く、尊敬される存在だ」と感じるようになります。この威信認知の向上は、候補者の組織に対する全般的な評価を押し上げる効果を持ちました。
一方、候補者強化行動は候補者の情緒的反応に強く作用しました。面接官からの称賛や肯定的なフィードバックを受けた候補者は、面接中により多くのポジティブ感情を経験しました。喜び、誇り、安心感といった前向きな気持ちが高まったのです。さらに、候補者強化行動は面接自己効力感の向上にもつながりました。候補者は「自分は面接でうまく答えられている」「自分の能力が認められている」という自信を深めることができました。
研究では、面接官が実際に行った印象管理行動と、候補者がそれをどの程度認知したかを別々に測定しました。その結果、面接官の組織強化行動は候補者による同様の認知と中程度の相関を示し、候補者強化行動についてはより強い相関が見られました。候補者への直接的な称賛の方が、組織アピールよりも候補者に気づかれやすいことを意味しています。
媒介分析によって、これらの印象管理行動が候補者の反応に至る経路も明らかになりました。面接官の組織強化行動は、候補者がそれを認知することを通じて組織威信の評価を高め、最終的に組織への肯定的態度につながりました。候補者強化行動は、候補者の認知を経てポジティブ感情と面接自己効力感を向上させるという、より情緒的な経路を辿りました。
組織強化行動は威信認知だけでなく、候補者の情緒的反応にも波及効果を持つことが分かりました。組織の素晴らしさを聞かされた候補者は、その組織と関わることができるという期待からポジティブ感情を感じるようになりました。
友好的な面接官は推論を介し企業魅力を高める
アメリカの大学で実施されたビデオ実験研究では、面接官の友好的な振る舞いが候補者の企業評価に及ぼすメカニズムを解明しています[3]。この研究では同一の俳優が面接官役を演じ、非言語的行動だけを操作することで、友好性の純粋な効果を測定しました。
実験では171名の学生が、二つのバージョンのうちいずれかの面接ビデオを視聴しました。友好的バージョンでは、面接官が立ち上がって握手し、8回の笑顔を見せ、前傾姿勢を取り、候補者と視線を合わせ続けました。声のトーンも高めで、抑揚に富んだ話し方をしました。
非友好的バージョンでは、面接官は立ち上がらずに握手もせず、笑顔はわずか1回に留まり、椅子に後傾して座り、しばしば視線を逸らしました。声は平坦で単調でした。重要なのは、両バージョンで面接の内容、質問、企業に関する情報提供は完全に同一だったことです。給与、勤務地、昇進機会などの客観的情報に一切の違いはありませんでした。
実験の結果、友好的な面接官を見た参加者は、非友好的な面接官を見た参加者と比べて、明らかに高い企業魅力度を報告しました。しかし、この研究の価値は、なぜそのような違いが生まれるかを解明した点にあります。
研究者たちは、参加者に対して面接で明示されなかった企業特性について推論してもらいました。「この会社は従業員を大切にするだろうか」「評判の高い企業だろうか」「経営が安定しているだろうか」といった11の質問に答えてもらったのです。
分析の結果、友好的な面接官を見た参加者は、これらの未知の企業特性についてより肯定的な推論を行うことが判明しました。友好的条件では平均3.88個の特性について肯定的に推論したのに対し、非友好的条件では2.25個に留まりました。
さらに、この肯定的推論が友好性と企業魅力度の関係を部分的に媒介していました。友好的な面接官の行動が候補者の肯定的推論を促し、その推論が企業魅力度の向上につながるということが確認されました。
この結果は、候補者が面接官の行動を組織全体の代理指標として解釈していることを示しています。候補者は限られた情報の中で企業を判断しなければならず、面接官の人柄や態度から組織の性質を推測しているのです。温かく親しみやすい面接官に接した候補者は、「この面接官のような人が働いている組織なら、きっと人を大切にし、働きやすい環境があるに違いない」と考えるようになります。
逆に言えば、冷たく距離のある面接官に接した候補者は、「この組織は人間関係が希薄で、従業員への配慮に欠けるかもしれない」という懸念を抱くことになります。面接官個人の振る舞いが、候補者の心の中で組織全体のイメージに拡張されます。
温かな面接対応は組織の有能さを伝え魅力度を高める
スイスの大学入学選考を対象とした縦断研究では、面接の標準化と個別化という二つの側面が、候補者の組織認識にどのような象徴的メッセージを送るかを検証しています[4]。この研究では129名の候補者を面接前、面接直後、そして数週間後の三時点で追跡調査し、面接体験が組織イメージの形成に与える効果を明らかにしました。
研究者たちは面接の特徴を二つの軸で捉えました。一つは一貫性で、これは面接が構造化され、標準的な手順に従って実施される度合いを指します。すべての候補者に同じ質問をし、決められた時間配分を守り、評価基準を明確に適用することなどが含まれます。
もう一つは個人性で、これは面接官が候補者一人ひとりに対して温かく、親しみやすく接する度合いを表します。個別の経験に興味を示し、共感的に反応し、リラックスした雰囲気を作り出すことなどが該当します。
研究の発見は、これら二つの面接特徴が候補者に異なる象徴的メッセージを伝えることです。候補者は面接体験から、組織の二つの基本的属性について推論を行っていました。一つは組織的コンピテンス、すなわち「信頼できる」「安全な」「効率的な」といった能力面での評価です。もう一つは組織的ベネボレンス、つまり「親しみやすい」「協力的な」「思いやりのある」といった善意面での評価です。
分析の結果、一貫性のある面接は候補者に組織的コンピテンスのシグナルを送ることが分かりました。標準化された手順は組織の信頼性と効率性を印象づけ、候補者に「この組織は物事をきちんと管理し、公正に業務を遂行する能力がある」という確信を与えました。
一方、個人性の高い面接は、組織的コンピテンスと組織的ベネボレンスの両方にポジティブなシグナルを送りました。温かな対応は当然ながら組織の善意を印象づけましたが、同時に「このように配慮の行き届いた対応ができる組織は、きっと有能で信頼できるに違いない」という推論も促したのです。
候補者の組織魅力度を高めるのは主に組織的コンピテンスの認知でした。組織的ベネボレンスも好ましい印象を与えましたが、魅力度への直接的な関わりは限定的でした。候補者は組織の温かさよりも、「信頼できる」「安全である」「効率的である」といった能力面での安心感を求めていたのでしょう。
この研究は、面接における人間的な温かさが、単なる好感度の向上を超えて、組織の能力に対する信頼感を醸成することを示しました。候補者は面接官の配慮深い態度から、「このような細やかな対応ができる組織なら、きっと他の業務でも高い水準を保っているだろう」と推測するのです。
脚注
[1] Turban, D. B., and Dougherty, T. W. (1992). Influences of campus recruiting on applicant attraction to firms. Academy of Management Journal, 35(4), 739-765.
[2] Wilhelmy, A., Kleinmann, M., Melchers, K. G., and Gotz, M. (2017). Selling and smooth-talking: Effects of interviewer impression management from a signaling perspective. Frontiers in Psychology, 8, 740.
[3] Goltz, S. M., and Giannantonio, C. M. (1995). Recruiter friendliness and attraction to the job: The mediating role of inferences about the organization. Journal of Vocational Behavior, 46(1), 109-118.
[4] Wilhelmy, A., Kleinmann, M., Melchers, K. G., and Lievens, F. (2019). What do consistency and personableness in the interview signal to applicants? Investigating indirect effects on organizational attractiveness through symbolic organizational attributes. Journal of Business and Psychology, 34(5), 671-684.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。