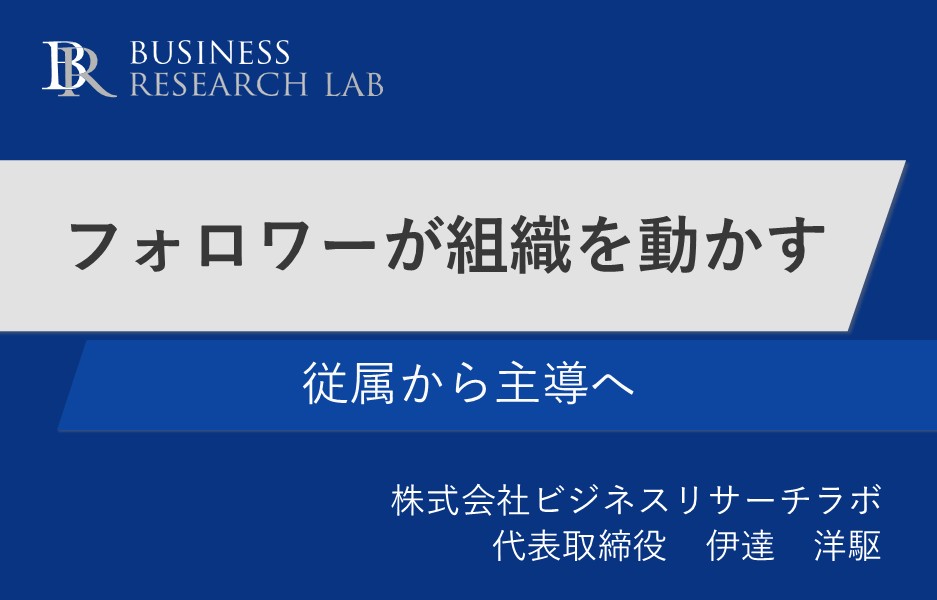2025年10月29日
フォロワーが組織を動かす:従属から主導へ
職場において、私たちはリーダーとフォロワーという関係性の中で働いています。これまで組織研究では、リーダーの能力や行動に目が向けられてきました。しかし近年、フォロワーという立場にある人々の認識や行動こそが、組織の成功を左右することが明らかになってきています。
フォロワーシップとは、リーダーの指示に従うことではありません。それは、組織の目標達成に向けて、フォロワーがどのような姿勢で臨み、どのような行動を選択するかという、主体的で戦略的な営みです。
本コラムでは、フォロワーシップの多面的な性質を探っていきます。フォロワーの行動パターンは予想以上に多様であり、その背景には進化的な適応戦略から現代組織の複雑な人間関係まで、様々な要因が絡み合っています。フォロワーは受身の存在ではなく、リーダーの意欲や判断に積極的に働きかけます。
フォロワーシップは受動から積極まで多様である
職場でフォロワーという立場にある人々は、一様に同じ行動パターンを示すわけではありません。フォロワーの行動には大きく3つのタイプが存在することが明らかになっています。
この調査は、アメリカとカナダの多様な業種で働く31名の従業員を対象として実施されました[1]。教育機関、医療機関、金融業界、IT企業など、様々な職場環境で働く人々に対して、半構造化インタビューという方法が用いられました。研究者たちは、フォロワーとしての自分の立場をどのように捉えているか、成功するために必要な特性や行動は何だと考えるか、そして職場のリーダーや組織の雰囲気がどのような影響を与えているかについて、詳細に聞き取りを行いました。
インタビューの内容を分析した結果、フォロワーシップには3つのパターンが浮かび上がってきました。
第一のタイプは、受動的なフォロワーシップと呼ばれるものです。これらの人々は、「上司の命令に従うこと」や「リーダーの指示に忠実に従うこと」を大切にしていました。彼ら彼女らにとって、フォロワーという立場は責任が軽く、心理的なストレスも少ないものとして受け止められています。決定を下すのはリーダーの仕事であり、自分はその決定に沿って行動すれば良いという考え方が根底にあります。
第二のタイプは、能動的なフォロワーシップです。このタイプの人々は、「リーダーに意見を求められたら意見を述べるが、最終的な決定についてはリーダーに従う」という姿勢を持っています。与えられた枠組みの中では一定の貢献を行おうとしますが、基本的にはリーダーの決定を尊重し、その範囲内で自分なりの価値を発揮しようとします。
第三のタイプは、積極的なフォロワーシップと名付けられました。これらの人々は、「積極的に意見を表明し、時にはリーダーに異議を唱え、自らイニシアチブをとって行動する」ことを重視していました。彼ら彼女らは自分自身を「静かなリーダー」として捉えており、リーダーと協力しながら組織をより良い方向に導いていこうという意識を持っています。
これらのタイプが形成される背景には、個人がフォロワーという立場についてどのような認識を持っているかが関わっています。受動的なフォロワーは、「服従」や「順応性」といった要素を重視する傾向がありました。能動的なフォロワーは、「チームプレイヤーであること」や「適切なタイミングで意見を述べること」を大切にしていました。一方で積極的なフォロワーは、「自発的にイニシアチブを取ること」や「リーダーの考えを問い直すこと」に価値を置いていました。
職場環境もこれらのタイプの発現に影響を与えています。積極的なフォロワーにとって、権威主義的なリーダーシップや官僚的な組織構造は、自分本来の能力を発揮する上での障害となります。自由な発言や創意工夫が認められる環境でこそ、その真価を発揮できます。反対に、受動的なフォロワーは、組織の権威主義的な側面をそれほど問題として感じておらず、むしろ明確な指示系統がある方が安心して働けると感じています。
フォロワーシップは多様で流動的な自己を生む
フォロワーという立場にある人々の内面世界は、従来考えられていたよりも複雑で動的なものです。研究によって、フォロワーが持つアイデンティティの豊かさと複雑さが明らかになってきました[2]。
この研究は、従来のリーダーシップ研究が見落としてきた視点を提供しています。これまでフォロワーは、単一で一貫したアイデンティティを持つ存在として扱われることが多く、その内面の多様性や変化については十分に検討されてきませんでした。しかし実際には、フォロワーは組織やリーダーとの関係性の中で、複数の異なるアイデンティティを同時に、あるいは状況に応じて使い分けながら生活しています。
研究によって明らかになったのは、フォロワーのアイデンティティが大きく3つのタイプに分類できるということでした。これらのタイプは固定的なものではなく、同一人物であっても時期や状況によって異なるアイデンティティを発現させることがあります。
最初のタイプは、同調的自己と呼ばれるものです。このアイデンティティを持つフォロワーは、組織やリーダーの価値観や要求に積極的に合わせようとします。彼ら彼女らは組織内での成功を追求するため、自分自身を組織の期待に沿うように調整していきます。組織の監視システムや評価制度が強化された環境では、このような自己規律的で従順なアイデンティティが形成されやすくなります。
同調的自己を持つフォロワーにとって、組織内での評価は自分のアイデンティティとつながっています。上司からの承認や同僚からの評価は自尊心の源泉となります。そのため、組織の要求に応えることで承認欲求を満たそうとする行動パターンが強化されていきます。
ただし、過度な同調には負の側面も存在します。自分本来の価値観や判断を抑制し続けることで、精神的なストレスが蓄積する可能性が指摘されています。
第二のタイプは、抵抗的自己です。このアイデンティティを持つフォロワーは、組織やリーダーに対して批判的な姿勢を保ち、時には反対意見を表明します。彼ら彼女らは自分の信念や価値観を曲げることなく、組織の慣行やリーダーの決定に疑問を投げかけることを厭いません。
抵抗的自己の表現方法は多様です。内部告発のような行動もあれば、皮肉やユーモアを使った間接的な表現、あるいは無関心を装うことで組織の権威に対する距離を表すこともあります。これらの行動は、フォロワーが自分のアイデンティティを守るための戦略的な選択として理解できます。
しかし、抵抗的な行動にはリスクが伴います。組織によっては、このような行動が本人を不利な立場に追いやる可能性があります。そのため、多くのフォロワーは表立った抵抗を避け、より微妙で間接的な方法で自分の立場を表現する傾向があります。
第三のタイプは、演劇的自己と名付けられました。このアイデンティティを持つフォロワーは、職場において意識的に自分を「演じる」ことで、リーダーや組織からの評価をコントロールしようとします。彼ら彼女らは状況に応じて最適なイメージを演出し、自分にとって有利な結果を得ようとします。
現代の職場では、パフォーマンス評価やモニタリングシステムが高度化しており、このような演劇的自己の重要性が増しています。フォロワーは評価基準を意識し、それに合わせて自分の行動や態度を調整します。
自己演出は、フォロワーが組織内での地位を維持し、報酬や昇進の機会を確保するための合理的な戦略として機能します。しかし同時に、本来の自分と演じている自分との間にギャップが生じ、心理的な負担となる場合もあります。
これらの結果が示しているのは、フォロワーシップが単純な従属関係ではなく、個人のアイデンティティ形成と関わる複雑なプロセスだということです。フォロワーは受動的な存在ではなく、組織との関係性の中で主体的にアイデンティティを構築し、戦略的に行動する存在です。
フォロワーシップは適応戦略の一種である
フォロワーという立場を選択する背景には、進化の過程で培われた深い適応的意味があるという研究もあります[3]。フォロワーシップは消極的な選択ではなく、生存と繁栄のための高度に洗練された戦略であることが指摘されています。
ある研究は、フォロワーシップを「協調的な集団行動を実現するための適応的解決策」として位置づけています。研究者たちは、なぜ人間がリーダーではなくフォロワーという立場を選ぶのか、そしてその選択がどのような進化的利益をもたらすのかを検討しました。
フォロワーシップの進化的起源を理解するためには、人類の祖先が直面していた環境的課題を考える必要があります。私たちの先祖は、生存のために協力的な集団行動を必要としていました。一人では獲得できない大型の獲物を狩ったり、外敵から身を守ったり、厳しい自然環境を乗り越えたりするには、集団での協調が必要でした。
このような状況において、全員がリーダーになろうとすれば混乱が生じ、効率的な協力は不可能になります。一方で、適切な場面で適切な人物にリーダーシップを委ね、他のメンバーがフォロワーとして協力する体制が確立されれば、集団全体の生存確率が向上します。
研究では、人がフォロワーになる理由として、いくつかの進化的に合理的な要因が検討されています。第一に、集団で行動することで個人の安全性が向上し、資源へのアクセスも容易になります。第二に、リーダーとしての責任やコストが過大である場合、フォロワーとして集団に貢献する方が効率的な選択となります。第三に、フォロワーとしての経験を通じて、将来リーダーになるための知識やスキルを蓄積することができます。
フォロワーシップの進化的発展は、段階的に進行してきました。最初期の段階では、基本的な集団行動を可能にするためのフォロワーシップが出現しました。続いて、霊長類に見られるような支配的リーダーの体制が確立されました。その後、狩猟採集社会において、フォロワーがリーダーの支配を抑制する仕組みが発達しました。さらに、信頼性や専門性に基づく威信のあるリーダーを選ぶようになりました。最終的に、現代のような複雑な協力関係を管理するための公式なリーダーシップ制度が構築されました。
フォロワーになりやすい個人的特性についても、進化的な観点から説明が可能です。リーダーシップに必要な身体的、心理的、社会的資源が不足している個人にとって、フォロワーという立場は合理的な選択となります。また、リーダーシップのコストやリスクが個人にとって過大である場合も、フォロワーとしての貢献を選ぶことが適応的です。
フォロワーシップはリーダーに積極的影響を与える
従来の組織研究では、リーダーがフォロワーに与える影響が特に注目されてきました。しかし、ある研究では、フォロワーがリーダーに対して及ぼす影響の仕組みが検討されています[4]。
具体的には、一個人が他者から受ける社会的影響の程度は、三つの要素によって決定されるとされています。それは、影響源の強さ、影響源との即時性、そして影響源の人数です。これらの要素をフォロワーシップの文脈に当てはめることで、フォロワーがどのような条件でリーダーに強い影響を与えるかが明確になります。
フォロワーの強さは、その人が持つ地位、権限、専門知識、信頼性、そしてリーダーとの個人的関係の質によって決まります。高い地位にあるフォロワーや、特定分野の専門家として認められているフォロワーは、リーダーの判断に影響を与える可能性を持っています。信頼関係が築かれているフォロワーの意見は、リーダーにとって重みを持ちます。
フォロワーが一時的に強い影響力を発揮する場面もあります。例えば、積極的に説得を行ったり、リーダーの決定に異議を唱えたりする行動により、その瞬間のフォロワーの影響力は増大します。反対に、継続的に支援的な行動を取り続けることで、長期的に個人的な影響力を蓄積していくことも可能です。
即時性という要素は、さらに三つの側面に分けて理解できます。一つに、心理的距離があります。これは権威の差や社会的立場の違いを指しており、この距離が小さいほどフォロワーの影響力は強くなります。もう一つに物理的距離があり、空間的に近い位置にいるフォロワーほど、リーダーにとって身近な存在として認識され、その意見に耳を傾けやすくなります。さらに交流頻度があり、日常的に頻繁にやり取りするフォロワーの声は、リーダーの意思決定により大きな影響を与えます。
集団レベルでの特性も、フォロワーの影響力を左右します。一般に、フォロワーの人数が多く、その集団内で意見の一致が見られるほど、リーダーに対する社会的影響力は強くなります。ただし、集団が大きくなりすぎると、個々のフォロワーの影響力は相対的に薄まります。
少数派であっても一貫して意見を表明し続けるフォロワーは、時として多数派の一部よりも強い影響力を発揮することがあります。これは、一貫性を持った少数意見がリーダーの関心を引き、真剣な検討の対象となるためです。
リーダーのフォロワーに対する依存度も、影響力の大きさを決定する要因です。リーダーが情報収集や意思決定において特定のフォロワーに依存している場合、そのフォロワーの影響力は強くなります。承認や社会的つながりといった心理的欲求を満たすためにフォロワーに依存しているリーダーは、そのフォロワーからの影響をより強く受けることになります。
フォロワーシップが上司の意欲を左右する
フォロワーの認識や行動が、上司であるリーダーの心理状態や仕事への意欲にどのような影響を与えるかという問題は、組織運営にとって重要な課題です。中国の大手インターネット企業で実施された実証研究により、この関係性のメカニズムが明らかになりました[5]。
この研究では、マネージャー42名とその部下306名を対象に、3つの異なる時期に分けて調査が行われました。時間的な間隔を設けることで変数間の関係をより正確に把握しようとしました。
研究の出発点となったのは、フォロワーが自分の立場についてどのような認識を持っているかという問題でした。フォロワーの役割認識は、二つのタイプに分類されました。
第一のタイプは、共同生成志向と呼ばれるものです。この志向を持つフォロワーは、自分がリーダーシップのプロセスに参加すべきだと考えています。彼ら彼女らは、組織の成功のために自分が果たすべき能動的な責任があると認識しており、リーダーとともに問題解決や意思決定に貢献することを自分の使命だと捉えています。
第二のタイプは、受動的志向です。この志向を持つフォロワーは、リーダーの指示に従い、自主的な関与は避けるべきだと考えています。問題解決や重要な意思決定は基本的にリーダーの責任であり、自分はその決定に従って行動することが適切だという信念を持っています。
これらの異なる役割認識は、職場における行動に違いをもたらします。研究では、「声を上げる行動」と「問題を上司に委ねる行動」という二つの行動パターンが測定されました。
声を上げる行動とは、職場の改善や問題解決のために、意見やアイデアを表明する行動を指します。これは建設的な提案、創意工夫の共有、潜在的な問題の指摘などを含みます。一方、問題を上司に委ねる行動とは、自分で解決可能な問題であっても、判断や責任をリーダーに転嫁する行動を指します。
調査の結果、共同生成志向が強いフォロワーほど声を上げる行動を頻繁に取り、問題を上司に委ねる行動は少ないことが確認されました。反対に、受動的志向が強いフォロワーは声を上げることが少なく、問題を上司に委ねる傾向が強いことが明らかになりました。
さらに、研究では、リーダーの三つの心理的・動機的側面が測定されました。フォロワーからの支援をどの程度感じているか、リーダーとしてのモチベーションがどの程度高いか、そしてフォロワーが目標達成にどれほど貢献していると認識しているかです。
分析の結果は、フォロワーの行動とリーダーの心理状態の間に関連性があることを示しました。積極的に声を上げるフォロワーを持つリーダーは、フォロワーからの強い支援を感じ、自分自身のリーダーとしてのモチベーションも高く維持していました。これらのフォロワーを、目標達成に貢献する存在として高く評価していることも判明しました。
一方で、問題を頻繁に上司に委ねるフォロワーを持つリーダーは、フォロワーからの支援を十分に感じることができず、自分自身のモチベーションも低下する傾向が見られました。これらのフォロワーの貢献度に対する評価も相対的に低いものでした。
このような結果が生じる背景には、いくつかの心理的メカニズムが考えられます。まず、意見を述べるフォロワーは、リーダーにとって協力的なパートナーとして認識されます。彼ら彼女らの提案や指摘は、リーダーの判断を支援し、より良い意思決定を可能にします。自主的に問題解決に取り組むフォロワーは、リーダーの負担を軽減し、リーダーがより戦略的な業務に集中できる環境を作り出します。
反対に、問題を上司に委ねるフォロワーは、リーダーにとって負担の源泉となります。本来であれば部下が処理できる問題まで持ち込まれることで、リーダーの業務負荷が増大し、本来の職務に集中することが困難になります。このような状況が続くと、リーダーは孤独感や過重負担感を抱くようになり、モチベーションの低下につながります。
脚注
[1] Carsten, M. K., Uhl-Bien, M., West, B. J., Patera, J. L., and McGregor, R. (2010). Exploring social constructions of followership: A qualitative study. The Leadership Quarterly, 21(3), 543-562.
[2] Collinson, D. (2006). Rethinking followership: A post-structuralist analysis of follower identities. The Leadership Quarterly, 17(2), 179-189.
[3] Bastardoz, N., and Van Vugt, M. (2019). The nature of followership: Evolutionary analysis and review. The Leadership Quarterly, 30(1), 81-95.
[4] Oc, B., and Bashshur, M. R. (2013). Followership, leadership and social influence. The Leadership Quarterly, 24(6), 919-934.
[5] Carsten, M. K., Uhl-Bien, M., and Huang, L. (2018). Leader perceptions and motivation as outcomes of followership role orientation and behavior. Leadership, 14(6), 731-756.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。