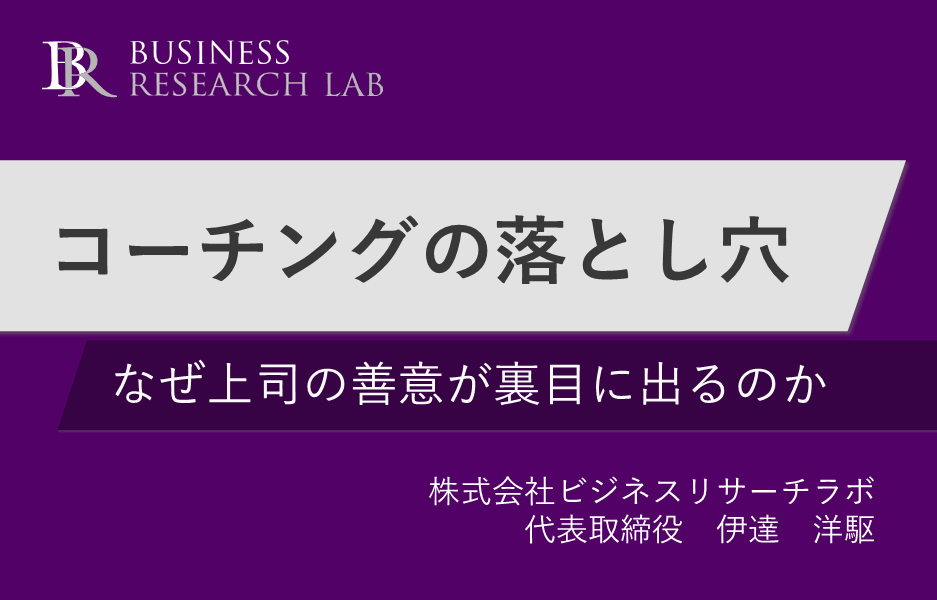2025年10月28日
コーチングの落とし穴:なぜ上司の善意が裏目に出るのか
コーチングが広く浸透して久しいでしょう。上司が部下の成長を促し、潜在能力を引き出すためのコミュニケーションとして、多くの企業で導入され、管理職研修のメニューの一つともなっています。部下一人ひとりの主体性を尊重し、対話を通じて自発的な行動を促す。その響きから、コーチングは有用な処方箋であるかのように語られることもあります。多くの管理職が、良かれと思って部下との面談でコーチングを実践しようと試みていることでしょう。
しかし、現実はどうでしょうか。「コーチングを学んだはずなのに、どうも上手くいかない」「むしろ、部下との関係がぎくしゃくしてしまった」「時間をかけているのに、一向に成果が見えない」。そんな声が、現場のあちこちから聞こえてくるのもまた事実です。良かれと思って費やした時間と労力が、期待した結果に結びつかないばかりか、時として部下のモチベーションを削ぎ、業績を悪化させてしまうという、望まない結末を招くこともあります。
一体、何がそうさせてしまうのでしょうか。コーチングという手法そのものに欠陥があるのでしょうか。それとも、コーチングの実践の仕方に、何か見過ごしている「落とし穴」があるのでしょうか。本コラムでは、コーチングが失敗したり、逆効果になったりする要因を、研究知見に基づいて掘り下げていきます。
下手なコーチングは、やればやるほど部下の業績を下げる
マネージャーが部下の成長を支援する手法として、コーチングは広く推奨されています。その実践にあたり、多くの管理職が抱く素朴な疑問の一つに、「コーチングは、どれくらいの頻度で行うのが良いのか」というものがあるかもしれません。そしてもう一つ、「どれだけ上手にできるか」というスキルの問題も切り離せません。この「量」と「質」という二つの側面は、部下の成果に対してそれぞれどのように関わっているのでしょうか。この問いに、客観的な業績データを用いて向き合った研究があります[1]。
この研究がユニークなのは、製薬会社に所属する136チーム、1,246名もの営業担当者を対象に、一年間という長期間にわたってデータを追跡した点です。コーチングの成果を、部下の自己評価といった主観的なものではなく、実際の「売上目標達成率」という客観的な指標で測定しました。これにより、コーチングという行為が本当にビジネスの現場で通用するのかを検証しようと試みたのです。
研究のデザインとしては、まず、コーチングの「質」、すなわちマネージャーのコーチング・スキルを測定するために、第三者による客観的な評価を取り入れました。具体的には、マネージャーに部下役との模擬コーチングを行わせ、その様子をさらに上の役職にあたるリージョナル・ディレクターが評価するという手法です。これによって、マネージャー自身の「自分はうまくやっている」という思い込みを排除し、スキルのレベルを数値化しました。
次に、コーチングの「量」、すなわち頻度については、マネージャーと営業担当者が現場に同行した回数を、会社の公式な活動記録から抽出しました。これもまた、自己申告に頼らないデータです。これらの「質」と「量」のデータが、最終的な成果である「売上目標達成率」とどう結びつくのかを分析しました。
分析の結果、マネージャーのコーチング・スキル、つまり「質」は、それ単体で部下の売上目標達成率を高める直接的な力を持っていることが分かりました。上手なコーチングは、それだけで部下のパフォーマンスを引き出すことができる、という直感的な仮説が裏付けられた形です。
ところが、コーチングの頻度、つまり「量」については、異なる様相を呈しました。コーチングの頻度だけを取り出して見ると、部下の業績との間に明確な関連は見られませんでした。頻繁にコーチングをすることが、必ずしも業績向上につながるわけではない、ということが示されました。
そして、この研究の興味深い発見は、「質」と「量」が互いにどう作用し合うのかを分析した時に明らかになりました。マネージャーのスキルレベルによって、コーチングの頻度がもたらす結果が異なっていたのです。
コーチング・スキルが高いマネージャーのグループでは、コーチングの頻度は部下の業績にほとんど何の作用もしていませんでした。スキルの高いマネージャーは、必ずしも頻繁にコーチングをする必要がないのかもしれません。
一方で、コーチング・スキルが低いマネージャーのグループでは、コーチングの頻度が高まれば高まるほど、部下の売上目標達成率は逆に「低下」していくという、負の関連が見られました。これは、下手なコーチングは、やればやるほど部下の足を引っ張り、業績を悪化させる毒になりうる、という可能性を物語っています。
この研究は、もう一つの側面からもコーチングのメカニズムを照らし出しています。それは、チーム全体の「役割の明確さ」という概念です。調査の結果、スキルの高いマネージャーが率いるチームは、チームメンバーが「自分のチームでは役割と責任が明確である」と認識している度合いが高いことが分かりました。
そして、この役割の明確さが、個々の部下の目標達成を後押ししていました。スキルの高いマネージャーは、一人ひとりへの直接的な働きかけだけでなく、チーム全体がスムーズに機能するような環境、すなわち「誰が何をすべきか」がはっきりしている状態を作り出すことで、間接的に個人のパフォーマンスを引き出していたと考えられます。
この研究結果から私たちが学ぶべきことは、コーチングの価値を一面的に捉えることの危うさです。コーチングは、ただやれば良いというものではないようです。「質の高い」コーチングである場合に限って、その価値が発揮されます。
スキルの低いマネージャーによる頻繁な介入は、なぜ逆の結果を招いてしまうのでしょうか。それは、的確でないフィードバックが部下を混乱させたり、部下の貴重な営業時間を奪ってしまったり、あるいはマイクロマネジメントのように感じられてモチベーションを削いでしまったりと、様々な不利益を生み出す「プロセス損失」を引き起こしているからかもしれません。
上司のコーチングは、部下に伝わらなければ成果につながらない
先ほどは、コーチングの「質」、スキルが伴わないまま頻度だけを重ねることが、かえって部下の業績を損なう危険性を確認しました。では、その「質」とは一体何でしょうか。上司がどれほど優れたスキルを持ち、洗練された問いかけをしたとしても、その意図が部下に正しく伝わっていなければ、それは空振りに終わってしまうのではないでしょうか。
コーチングが本質的に上司と部下の相互作用である以上、送り手である上司の自己評価だけでなく、受け手である部下がそれをどう認識しているかが、決定的な意味を持つはずです。この「認識のズレ」という問題に、上司と部下の両者からデータを収集するという手法で光を当てた研究があります[2]。
この研究の舞台となったのは、米国の物流業界に属する6つの組織、18の配送センターです。研究チームは、そこで働く438名の従業員と、その直属の上司である67名のペアを対象に調査を行いました。この研究の特徴は、コーチングという現象を、上司か部下のどちらか一方の視点からではなく、ペアで捉え、両者の認識を比較した点にあります。
調査にあたり、研究チームは、コーチングで実践される行動を測定するための尺度を開発しました。これには、8つの具体的な行動が含まれています。そして、同じこの8つの行動について、上司には「自分自身が、これらの行動をどのくらい実践しているか」を自己評価してもらい、同時に、その部下には「自分の上司が、これらの行動をどのくらい実践してくれているか」を評価してもらいました。
さらに、コーチングの成果として、二つの指標が用いられました。一つは、従業員自身が回答する「仕事への満足度」。もう一つは、上司が評価する部下の「職務パフォーマンス」です。このように、複数の情報源からデータを集めることで、より客観的で信頼性の高い分析を可能にしています。
分析の結果、浮かび上がってきたのは、上司と部下の間に横たわる、コーチング行動に関する「認識のギャップ」でした。上司たちは、総じて自分たちのことを、高いレベルでコーチングを実践している、と自己評価していました。
ところが、その部下たちの評価は異なりました。部下たちは、自分たちが上司から受けているコーチングのレベルを、「低い」から「中程度」であるとしか認識していなかったのです。上司が「自分はこれだけやっている」と信じている行動が、部下にはそのようには映っていないという、コミュニケーションの断絶がありました。特にそのギャップが大きかったのは、「部下の視野を広げるよう働きかけている」という項目で、上司側の強い意図とは裏腹に、部下側にはその働きかけが十分に届いていない実態が明らかになりました。
この「認識のギャップ」の存在を念頭に置いた上で、コーチングの成果を見ていくと、この研究の核心が見えてきます。従業員が「上司からコーチングを受けている」と認識している度合いは、その従業員自身の「仕事への満足度」と、統計的に見て非常に強いプラスの関連があることが分かりました。これは、部下が「自分は上司に気にかけてもらっている、支援してもらっている」と感じることが、仕事へのやりがいや喜びにつながることを意味しています。
同様に、部下がコーチングを受けているという認識は、上司が評価したその部下の「職務パフォーマンス」とも、プラスの関連を持っていました。コーチングを受けていると部下が感じるほど、実際に上司からのパフォーマンス評価も高くなる傾向にありました。
これらの結果を総合すると、コーチングが成果を生み出す上での鍵は、上司が「何をしたか」という行動の量や種類以上に、部下がそれを「どのように受け止め、認識したか」という主観的な解釈にある、という結論が導き出されます。
「自分はコーチングをやっているつもりだ」という上司の自己満足では総じて意味をなしにくいと言えます。むしろ、その「つもり」が部下に伝わっていないという現実は、多くの職場が抱える課題でしょう。
コーチングは、コーチが目標設定を主導すると逆効果に
ここまでの議論で、スキルの低いコーチングの危険性や、上司と部下の間に生じる「認識のギャップ」という問題を見てきました。これらは、コーチングがうまくいかない要因を説明する上で説得力のある視点です。
しかし、さらにその本質に迫るためには、コーチングの具体的なプロセス、その心臓部とも言える「目標設定」の場面に光を当てる必要があります。コーチングとは、クライアント(部下)が自らの目標を達成するための支援プロセスです。では、その目標は、一体誰が、どのようにして決めるべきなのでしょうか。この問いに、実際のコーチングセッションをビデオに収め、その一挙手一投足を分析するという手法で答えようとした研究があります[3]。
この研究は、これまで多くの研究が頼ってきた、質問紙による主観的な「認識」の測定から一歩踏み出しています。コーチやクライアントがセッションの後に「私たちの関係は良好でしたか」と尋ねられて答える「認識」と、セッション中に行われている客観的な「行動」は、必ずしも同じではないのではないか。そんな問題意識から、この研究はスタートしました。
研究チームは、31組のコーチとクライアントのペアで行われたキャリアコーチングのセッションをビデオで撮影しました。そして、専門的な訓練を受けた分析者が、その映像を繰り返し再生しながら、コーチとクライアントの発言や行動を逐一コード化していきました。
分析の焦点となったのは、「ワーキングアライアンス(協働関係)」と呼ばれる、コーチングの成否を左右するとされる関係性の質です。この関係性は、大きく二つの要素で構成されると考えられています。一つは「目標とタスクに関する合意」、すなわち、何をゴールとし、そのために何を行うかについて両者が納得していること。もう一つは「絆」、すなわち、互いへの信頼や尊敬といった感情的な結びつきです。
ビデオの分析では、これらの合意形成や絆を深めるための行動が、セッション中に「どちらによって主導されたか(コーチ主導か、クライアント主導か)」を記録していきました。そして、この客観的な「行動」のデータと、セッション後に質問紙で測定した主観的な「認識」のデータ、さらにはコーチングの成果であるクライアントの「目標達成度」のデータを突き合わせ、その関連性を探りました。
分析から得られた発見は、そもそも「認識」と「行動」が一致しないという事実でした。コーチやクライアントが質問紙で「私たちの協働関係は素晴らしい」と高く評価していても、セッション映像を見ると、目標の合意形成に向けた行動や絆を深める行動がほとんど行われていない、というケースが見られました。その逆もまた然りです。私たちが「良い関係だ」と感じる感覚がいかに曖昧で、コミュニケーションの実態とは乖離している可能性があるかを物語っています。
そして、この研究は、コーチングの成果、すなわちクライアントの目標達成に何が結びついていたかを明らかにしました。成果に最も強く、そしてプラスに結びついていたのは、「クライアントが主導して、目標やタスクに関する合意を形成する行動」でした。クライアント自身が「私はこうなりたい」「そのために、これを試してみたい」と主体的に発言し、コーチがその考えを受け入れ、合意に至るというパターンのやり取りが多ければ多いほど、最終的な目標達成度は高かったのです。
これとは対照的に、「コーチが主導して、目標やタスクに関する合意を形成する行動」は、コーチングの成果と「負の相関」関係にありました。コーチが良かれと思って「あなたの目標はこれにすべきです」「これをやってみてはどうですか」と提案し、議論をリードすればするほど、クライアントの目標達成度は逆に「低下」していました。コーチによる目標設定の主導は、手助けになるどころか、クライアントのパフォーマンスを妨げる結果を招いていました。
なお、一般的には良いことだと考えられがちな、共感を示したり称賛したりといった「絆」を深めるための行動についてはどうだったのでしょうか。分析の結果、これらの感情的なやり取りは、それがコーチ主導であれクライアント主導であれ、コーチングの成果である目標達成度とは直接の関連が見られませんでした。
この研究によれば、コーチングの成功の鍵は、情緒的な絆を深めること以上に、「クライアント自身が目標設定の主体となること」にあると考えられます。クライアントが自らの課題を「自分ごと」として捉え、その達成に向けた道のりを自らの言葉で定義していく。そのプロセスをコーチが尊重し、側面から支援することこそが、成果を生み出します。
脚注
[1] Dahling, J. J., Taylor, S. R., Chau, S. L., and Dwight, S. A. (2016). Does coaching matter? A multilevel model linking managerial coaching skill and frequency to sales goal attainment. Personnel Psychology, 69(4), 863-894.
[2] Ellinger, A. D., Ellinger, A. E., and Keller, S. B. (2003). Supervisory coaching behavior, employee satisfaction, and warehouse employee performance: A dyadic perspective in the distribution industry. Human Resource Development Quarterly, 14(4), 435-458.
[3] Gessnitzer, S., and Kauffeld, S. (2015). The working alliance in coaching: Why behavior is the key to success. The Journal of Applied Behavioral Science, 51(2), 177-197.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。