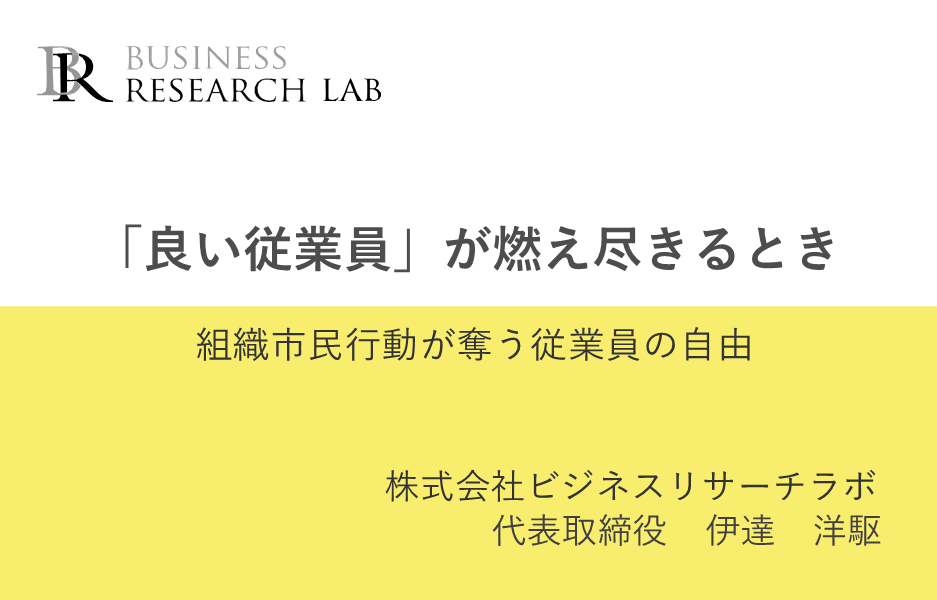2025年10月28日
「良い従業員」が燃え尽きるとき:組織市民行動が奪う従業員の自由
職場において「良い従業員」とはどのような人でしょうか。決められた仕事をこなすだけでなく、困っている同僚を手助けしたり、会社のために自分の時間を割いて貢献したりする人を思い浮かべるでしょう。このような自発的な貢献行動は「組織市民行動」と呼ばれます。
組織市民行動とは、正式な職務記述書には書かれていないものの、組織全体の成功に貢献する行動のことです。例えば、新入社員に仕事を教える、会議の準備を手伝う、職場の清掃を行う、建設的な提案をするといった行動が含まれます。これまでこうした行動は、組織の生産性向上や従業員の満足度向上につながる望ましいものとして捉えられてきました。
しかし近年、この「善意の行動」が従業員にとって予期しない負担や問題をもたらす可能性が明らかになってきています。本来は自由意志に基づく行動であったはずの組織市民行動が、いつの間にか義務的なものとなり、従業員の自律性を奪ったり、仕事と家庭生活の両立を困難にしたり、評価の公平性に疑問を投げかけたりする事態が生じているのです。
組織市民行動のジョブ・クリープ化、自由奪い反発も
職場での善意ある行動が、時として従業員を苦しめる結果につながることがあります。この現象を理解するために、「ジョブ・クリープ」という概念から考えてみましょう。
ジョブ・クリープとは、本来の職務範囲を超えた行動が徐々に期待され、やがて義務的になる現象を指します。これは明確な契約や話し合いを伴わないまま、従業員の担うべき仕事の範囲が静かに拡大していく過程です。最初は自分の意志で行っていた親切な行動が、気がつくと「やって当たり前」のこととして周囲から期待されるようになり、最終的には断ることが難しい義務へと変化してしまうのです。
このジョブ・クリープを取り上げた調査では、組織市民行動が従業員にとって「義務の超過履行」として認識される過程が検討されています[1]。研究者たちは、心理的リアクタンス理論という枠組みを用いて、この問題のメカニズムを解明しようと試みました。
心理的リアクタンス理論とは、人が自らの自由が脅かされたと感じた際に、その自由を取り戻そうとして心理的な抵抗や反発を示すという理論です。選択の自由を奪われそうになると、人はその状況に反発しようとするのです。この理論を組織市民行動に当てはめると、興味深い構図が浮かび上がります。
従業員が組織市民行動を始める初期段階では、これらの行動は完全に自発的なものです。新しい同僚に仕事を教えたり、会議室の準備を手伝ったり、残業している同僚をサポートしたりする行動は、本人の善意と自由意志に基づいています。この段階では、従業員は自分の行動に対してコントロール感を持っており、いつでも止めることができるという感覚があります。
しかし時間が経つにつれて、状況は変化していきます。上司や同僚は、その従業員が継続的に組織市民行動を行うことに慣れ、それを当然のこととして期待するようになります。「いつも手伝ってくれる人」「頼りになる人」という評価とともに、無言のプレッシャーが生まれてくるのです。
この段階で、従業員の認識に変化が起こります。本来は自由な選択であったはずの行動が、周囲の期待や評価によって義務的なものとして感じられるようになるのです。断ることが難しくなり、継続しなければならないという圧迫感が生まれます。職務の境界が曖昧になり、どこまでが正式な仕事で、どこからが追加的な貢献なのかが不明確になってしまいます。
この義務化のプロセスにおいて、従業員は自分の選択の自由が制限されたと感じるようになります。ここで心理的リアクタンスが発動します。自由を奪われたと感じた従業員は、その状況に対して心理的な抵抗を示すようになります。
抵抗は様々な形で現れます。心理的ストレスや不満が蓄積されます。本来楽しんで行っていた行動が、負担として感じられるようになります。組織に対する態度も悪化し、組織への愛着や忠誠心が低下する可能性があります。
さらに、この心理的反発は仕事のパフォーマンスにも悪い進展をもたらします。義務化された組織市民行動に対する嫌悪感が、本来の職務遂行にまで波及してしまいます。集中力の低下、創造性の減退、積極性の喪失といった問題が生じる可能性があります。
最終的には、離職意図の増加や実際の離職行動につながることもあります。善意で始めた行動が原因で、優秀な従業員を失ってしまうという皮肉な結果を招くことがあるかもしれません。
この問題の根本には、職務の曖昧さという構造的な要因があります。職務記述書に明記された業務の範囲が曖昧であったり、チームワークが重視される中で個人の責任が不明確であったりするような環境では、組織市民行動と正式な職務との境界が見えにくくなり、ジョブ・クリープが発生しやすくなります。
組織市民行動は、仕事と家庭の葛藤をへて心の消耗に
組織市民行動が従業員に与える負の作用は、職場での義務感や自由の制約だけにとどまりません。これらの行動は、従業員の限られた時間やエネルギーという資源を消費し、仕事と家庭生活の間に葛藤を生み出すことがあります。
この問題を検討した研究では、組織市民行動が従業員の情緒的消耗にどのような経路で影響するかが検証されています[2]。研究では、インドネシアの様々な産業で働く235名の既婚従業員を対象に、オンライン調査が実施されました。この調査の対象者を既婚者に限定したのは、仕事と家庭の両方に責任を持つ人々における葛藤をより明確に捉えるためでした。
研究の理論的基盤となったのは、資源枯渇理論と資源保存理論という二つの考え方です。資源枯渇理論では、人が持つ時間、エネルギー、注意力といった資源は有限であり、一つの領域(例えば仕事)で多くの資源を使用すると、他の領域(家庭)で使える資源が減少するとされます。資源保存理論では、人は自分の持つ資源を保持し、枯渇を避けようとする行動を取るが、資源が枯渇した場合には心理的な負担が生じるとされます。
調査では、組織市民行動を二つのタイプに分けて測定しました。一つは組織に向けられた行動(OCB-O)で、これには会社の評判を守る、組織の方針に従う、建設的な提案をするといった行動が含まれます。もう一つは個人に向けられた行動(OCB-I)で、困っている同僚を助ける、新入社員を指導する、他者の仕事を代わりに引き受けるといった行動が含まれます。
調査結果は、これらの行動の負の側面を浮き彫りにしました。組織に向けられた市民行動は、統計的に有意な正の関係で情緒的消耗と結びついていることが分かりました。会社のために自発的に行う行動が多いほど、従業員は心理的に疲弊していたのです。
さらに、個人に向けられた市民行動の結果は衝撃的です。同僚への支援行動は、情緒的消耗に対して強い正の関係を示しました。この関係の強さは、組織向けの行動よりも大きく、同僚を助ける行動が従業員の心理的負担にいかに大きな作用を与えるかを物語っています。
研究では、これらの関係において仕事と家庭の間の葛藤がどのような役割を果たすかも検証されました。仕事家庭葛藤とは、仕事の要求と家庭の要求が互いに両立しにくい状況のことを指します。例えば、残業が多くて家族との時間が取れない、仕事のストレスで家庭でも疲れてしまう、家庭の事情で仕事に集中できないといった状況です。
分析の結果、仕事家庭葛藤は、組織市民行動と情緒的消耗の間を部分的に媒介していることが明らかになりました。これは、組織市民行動が直接的に心理的疲労を引き起こすだけでなく、仕事と家庭の間の葛藤を通じて間接的にも負の作用をもたらすことを意味します。
このメカニズムを考えてみましょう。従業員が同僚の仕事を手伝ったり、会社のイベントの準備に参加したりする場合、その分だけ自分の正規の業務に充てる時間が減少します。結果として、本来の仕事を終わらせるために残業をしたり、家に持ち帰ったりする必要が生じます。
組織市民行動は精神的なエネルギーも消費します。他者の問題に気を配り、解決策を考え、実際に支援を提供するプロセスは、認知的な負荷を伴います。この負荷は、一日の終わりには蓄積し、家庭に帰ってからも疲労感として残ります。
時間的な制約と精神的な疲労が組み合わさると、家庭での役割を十分に果たすことが困難になります。配偶者や子どもとの時間が減り、家事や育児への参加が制限され、家族からの期待に応えられないという状況が生まれます。これが仕事家庭葛藤につながります。
この葛藤は、さらなる心理的ストレスの源となります。仕事でも家庭でも十分な成果を上げられないという感覚は、罪悪感、不安、焦燥感を生み出します。完璧主義的な傾向を持つ人ほど、この種のストレスを強く感じる傾向があります。
個人向けの組織市民行動が強い負の作用をもたらす理由として、その性質の違いが挙げられます。組織向けの行動は比較的定型化されており、時間的にも予測可能な場合が多いのに対し、個人向けの行動は相手の状況や感情に左右されるため、予期しない時間や労力を要求される場合があります。
同僚からの相談や支援要請は、しばしば緊急性を伴い、断りにくい性質を持ちます。「今忙しいから後で」と言いにくい雰囲気や、相手の困った表情を見ると放っておけないという人間的な感情が、時間管理を困難にします。
個人向けの市民行動は感情労働の側面も持ちます。相手の気持ちに寄り添い、適切な言葉をかけ、問題解決に向けて一緒に考えるプロセスは、論理的な作業以上にエネルギーを消費します。職場の人間関係が複雑な場合や、支援する相手が多数いる場合には、この感情労働の負担は相当なものになります。
研究結果は、これまで美徳とされてきた組織市民行動にも、従業員の心理的健康を脅かす側面があることを示しています。善意でとる行動が、皮肉にも行為者自身を苦しめる結果につながるという現実は、現代の職場環境における問題として認識される必要があります。
この問題の複雑さは、組織市民行動を完全に否定することもできないという点にあります。これらの行動は確かに組織の機能や同僚の福祉に貢献しており、職場の協力関係を維持する上で欠かせない要素でもあります。しかし、その一方で従業員の資源には限界があり、過度な組織市民行動は個人の健康と家庭生活を犠牲にする可能性があるのです。
組織市民行動の評価、仕事の連携度で重要性が変化
組織市民行動が従業員や組織に与える作用を理解する上で、もう一つ見逃せない視点があります。それは、仕事の性質や職場環境によって、組織市民行動の価値や重要性が変化するという点です。
この問題を探究した研究では、「タスクの相互依存性」という概念に焦点が当てられました[3]。タスクの相互依存性とは、チームメンバーが仕事を遂行する上で、互いにどの程度依存し合っているかを表します。高い相互依存性を持つ仕事では、一人の行動が他のメンバーの成果に影響し、チーム全体の成功には密接な連携が必要となります。一方、低い相互依存性の仕事では、各メンバーが比較的独立して作業を進めることができます。
この研究では、タスクの相互依存性が組織市民行動の評価にどのような影響を及ぼすかを検証するため、三つの異なる調査が実施されました。これらの調査を通じて、職場環境の違いが組織市民行動の意味を変える可能性が明らかになりました。
最初の調査は、238名の大学生を対象とした実験室実験でした。この実験では、参加者に異なる作業環境を想定してもらい、その中で組織市民行動をどのように評価するかを測定しました。実験条件は、タスクの相互依存性の高低とチーム全体のパフォーマンスの高低を組み合わせた四つのパターンに設定されました。
実験の結果、チームのパフォーマンスが高く、かつタスクの相互依存性が高い条件において、組織市民行動(特に他者への援助行動)の評価が最も高くなりました。逆に、タスクの相互依存性が低い条件やチームのパフォーマンスが低い条件では、同じ組織市民行動でも評価が低くなりました。
この結果が示すのは、組織市民行動の価値が絶対的なものではなく、状況に依存して変化するということです。高度に連携が求められる環境では、同僚を助ける行動や協力的な姿勢は高く評価されます。しかし、個人作業が中心の環境では、同じ行動でもそれほど価値あるものとは見なされません。
二番目の調査では、148名のMBA学生を対象に、より直接的な評価の重要性が測定されました。この調査では、参加者に上司の立場から従業員を評価する場面を想定してもらい、組織市民行動をパフォーマンス評価の基準としてどの程度重要視するかを調べました。
結果は一番目の実験を支持するものでした。タスクの相互依存性が高い条件では、参加者は組織市民行動(特に援助行動と市民的美徳)を評価基準として重要視しました。相互依存性が低い条件では、その重要性は低下しました。
これらの実験室研究を補完するため、三番目の調査では130名の実務管理者を対象とした現場調査が実施されました。この調査では、実際の職場において管理者がどのように従業員を評価しているかが調べられました。
現場調査の結果も、実験室研究と一致していました。タスクの相互依存性が高い職場で働く管理者ほど、組織市民行動を従業員のパフォーマンス評価において重要視していることが確認されました。これによって、実験室で観察された現象が現実の職場でも生じていることが実証されました。
これらの研究結果から浮かび上がるのは、組織市民行動の評価における不公平性の問題です。同じ行動を取ったとしても、その人が置かれた職場環境によって評価が異なってしまうのです。
この評価の格差は、従業員にとって複数の問題を引き起こします。例えば、努力と報酬の不均衡という問題があります。同じだけの時間とエネルギーを組織市民行動に投入したとしても、職場環境によって得られる評価が異なることは、公平性の観点から疑問視されます。
この不公平感が従業員のモチベーションや行動選択に与える負担もあります。評価されにくい環境にいる従業員は、組織市民行動をとることの意味を見出しにくくなり、協力的でない行動を選択するかもしれません。逆に、評価されやすい環境にいる従業員は、本来の職務よりも組織市民行動を優先してしまう危険性があります。
職場環境の違いが生み出すもう一つの問題は、組織市民行動に対する期待の不明確さです。従業員は、自分の職場でどの程度の組織市民行動が期待されているのかを正確に把握することが困難になります。管理者からの明確な指針がない状況では、従業員は手探りで行動せざるを得ず、過度な行動や不十分な行動につながるかもしれません。
脚注
[1]Van Dyne, L., and Ellis, J. B. (2004). Job creep: A reactance theory perspective on organizational citizenship behavior as over-fulfillment of obligations. In J. A.-M. Coyle-Shapiro, L. M. Shore, M. S. Taylor, and L. E. Tetrick (Eds.), The employment relationship: Examining psychological and contextual perspectives (pp. 181-205). Oxford University Press.
[2] Ekowati, D., Kasman, S., and Sulistiawan, J. (2023). Organizational citizenship behavior and emotional exhaustion: Examining the role of work-family conflict. Journal of Theoretical and Applied Management, 16(1), 196-205.
[3] Bachrach, D. G., Powell, B. C., Bendoly, E., and Richey, R. G. (2006). Organizational citizenship behavior and performance evaluations: Exploring the impact of task interdependence. Journal of Applied Psychology, 91(1), 193-201.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。