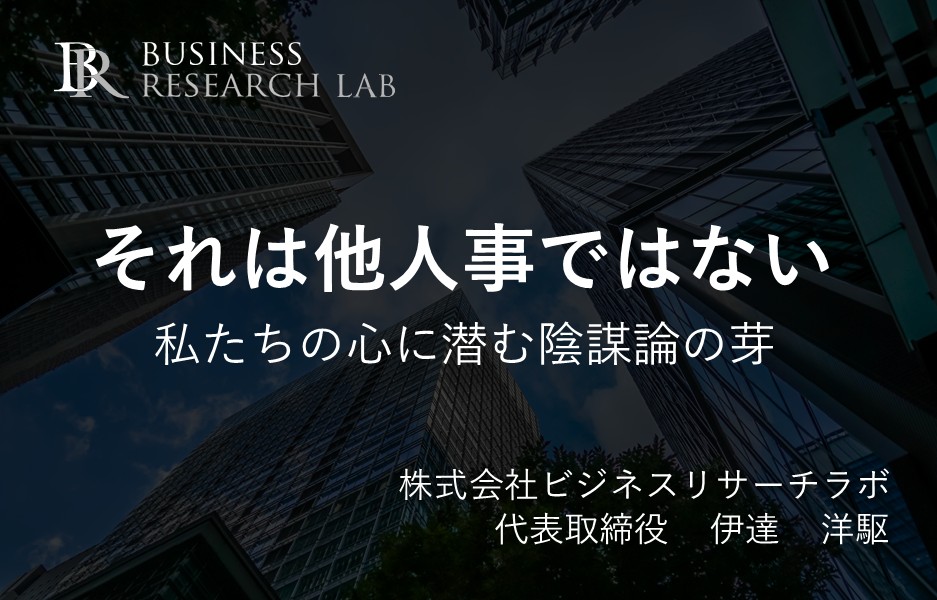2025年10月27日
それは他人事ではない:私たちの心に潜む陰謀論の芽
私たちの周りには、にわかには信じがたいような話があります。「ある歴史的な大事件は、実は裏で糸を引く組織によって仕組まれたものだった」「広く使われているあの製品には、人々を操るための秘密が隠されている」。このような、社会の出来事の背後に悪意ある強力な存在の計略を見る物語を、「陰謀論」と呼びます。かつては一部の人々が囁くだけの存在だったかもしれませんが、今やインターネットを通じて瞬く間に広がり、誰にとっても決して無縁なものではなくなりました。
人はどのような時に、このような物語に惹きつけられ、信じるようになるのでしょうか。この問いに対して、「情報リテラシーの問題だ」とか「一部の人の特殊な考え方だ」と結論づけるのは簡単かもしれません。しかし、現実はもう少し複雑なようです。陰謀論を受け入れる心性は、人間の心に備わっている認知の仕組みや、特定の心理状態と結びついています。それは、決して遠い誰かの話ではなく、私たち自身の心の働き方と地続きの問題でもあります。
本コラムでは、陰謀論を信じる人々の心の内側で何が起きているのかを解き明かしていきます。無関係な出来事の間に意味を見出そうとする人間の基本的な性質から始まり、ストレスが私たちの世界の見方をどう変えるのか、他者の意図を敏感に読み取ろうとする心の働き、職場のような身近な組織で疑念が生まれるプロセスまで、異なる角度から光を当てていきます。
無意味な出来事にパターンを見出す人は陰謀を信じる
私たちの脳は、世界を理解しようとする優れた能力を持っています。夜空に輝く星々を結んで星座の物語を紡ぎ、日々の些細な出来事から未来の兆しを読み解く。このように、一見するとバラバラに見える情報をつなぎ合わせ、そこに意味のある「パターン」を見出す力は、私たちが複雑な環境を生き抜くために不可欠なものでした。
しかし、この力が時に、私たちの解釈と現実の間に少しずれを生じさせることがあります。偶然の連なりを、何か大きな力が働いた結果だと解釈するのです。無意味なものの中にパターンを見出してしまう心の働きが、陰謀論を受け入れる素地となることが分かっています。
この関連性を調べるため、ある調査が行われました[1]。参加者には、ランダムに打たれた点の集合や、テレビの砂嵐のようなノイズ画像、無作為に生成された数列などを見せ、「この中に何か意味のあるパターンが含まれていると感じるか」を尋ねました。その上で、さまざまな陰謀論や超常現象をどの程度信じているかを測定しました。
結果、ランダムな刺激の中にパターンを見出す度合いが高い人ほど、陰謀論や超常現象を強く信じているという関連が見出されました。偶然の出来事の中に何らかの秩序や構造を見つけようとする心の働きが、陰謀論や超常現象といった、目に見えない大きな力を想定する信念の共通基盤となっている可能性を示唆します。
パターンを見つけようとする心理状態を人為的に作り出し、それが陰謀論への信念に結びつくかを確かめる実験が複数行われました。ある実験では、参加者に架空のサッカーの試合結果を見せました。この勝敗の系列は完全にランダムに作られていますが、一方のグループには「この結果の裏には、何らかのパターンが隠されているかもしれません」と伝え、もう一方のグループには「この結果はサイコロを振るのと同じで、完全にランダムです」と伝えました。
その後、両グループの陰謀論への信念を測定したところ、「パターンがあるかもしれない」と伝えられたグループの方が、陰謀論を信じる度合いが高まっていました。ランダムな事象に対してパターンを探すよう促されるだけで、世界の見方が変わり、陰謀論的な解釈を受け入れやすくなります。
別の実験では、より曖昧な状況でのパターン認識が調べられました。参加者は、雪が降るテレビ画面のような、ランダムなノイズが表示された画面を見せられ、その中に隠されている「画像」を見つけ出すよう求められました。実際には、ノイズの中に本物の画像は一枚も隠されていません。
しかし、多くの試行の中で「画像が見えた」と報告した人ほど、陰謀論や超常現象を信じる度合いが高いことが分かりました。この結果は、知性や教育レベル、その時の気分といった要因を考慮に入れても変わりませんでした。はっきりしない情報の中から意味を抽出しようとする心の働きそのものが、陰謀論への信じやすさと結びついているようです。
こうした心の働きは、社会的な出来事の解釈にも及びます。アメリカの成人を対象とした実験では、参加者を二つのグループに分け、一方には国家安全保障局(NSA)による盗聴疑惑を示唆する陰謀論的な記事を、もう一方にはその疑惑を否定する懐疑的な記事を読んでもらいました。
その後、「世の中で起きる出来事に、どの程度パターンを感じるか」を尋ねたところ、陰謀論的な記事を読んだグループは、懐疑的な記事を読んだグループに比べて、世界の出来事全般により強いパターンを感じるようになっていました。そして、この「パターンを感じる度合い」の高まりが、陰謀論への信念を強めることにつながっていたのです。
心理社会的ストレスが強いほど陰謀論を信じやすい
無関係な物事の間にパターンを見出し、そこに意味を求める人間の性質は、常に一定の強さで働くわけではありません。私たちの心が不安定で、先行きが見えないと感じる時、この性質はより強く顔を出すことがあります。
大きな災害に見舞われた時、経済的な苦境に立たされた時、あるいは個人的な人間関係で深く悩んでいる時。このような強い心理社会的ストレスに晒されると、世界はコントロール不能で、理不尽な場所のように感じられます。この不確実性の高い状況を乗り越えようとする中で、人は状況を単純化し、分かりやすい秩序を与えてくれる物語に心の安定を見出すことがあります。その受け皿の一つとして、陰謀論が選ばれることがあるのです。
ストレスと陰謀論を信じることの関連は、これまでもしばしば指摘されてきましたが、その関係をさまざまな角度から数量的に検証した研究は十分ではありませんでした。そこで、この結びつきを明らかにするための調査がアメリカで行われました[2]。分析の結果、ストレスと陰謀論信念の間には、はっきりとした正の関連があることが分かりました。最近ストレスの多い出来事を多く経験した人ほど、また、主観的に「ストレスが溜まっている」と感じている人ほど、陰謀論を信じる度合いが高かったのです。この二つのストレス指標は、それぞれ独立して陰謀論信念と関連していました。
興味深いことに、不安の度合いと陰謀論信念の間の関連は、ストレスのレベルを考慮に入れるとはっきりしなくなりました。このことは、漠然とした不安感そのものよりも、自分の力ではどうにもならない脅威や無秩序な状況に置かれているという「ストレス状態」が、陰謀論を受け入れる一つのきっかけになっている可能性を示唆します。
この結果は、陰謀論が人々にとってどのような機能を持っているのかを理解する上で手がかりを与えてくれます。強いストレスに苛まれている時、私たちの心は複雑な現実をありのままに受け止めるための精神的なエネルギーが消耗しやすくなります。世界はなぜこんなにも理不尽なのか、なぜ自分ばかりがこんな目に遭うのか。こうした問いに対する答えが見つからない時、「すべては、ある特定の邪悪な集団が自分たちの利益のために仕組んだことだ」という陰謀論的な説明は、一種の納得感や心の落ち着きをもたらすことがあります。
それは、混沌としていた世界に「敵」と「味方」、「原因」と「結果」という単純明快な秩序をもたらします。誰を責めればよいのかがはっきりすることで、コントロール不能だった状況に対して、少なくとも認知の上ではコントロールを取り戻したかのような感覚を得られるのです。この「分かりやすさ」と「意味の付与」が、ストレスに直面した心にとって、受け入れやすい説明として映り、陰謀論が真実味を帯びてくる理由なのかもしれません。
意図を過剰に読み取る人ほど陰謀論を信じやすい
ストレスに満ちた不確実な世界で、分かりやすい説明を求める心は、自然と物事の背後にある「原因」を探し始めます。とりわけ、その原因が「誰かの意図」によるものだと考えられれば、複雑な現象も一気に理解しやすくなります。人間は、他者の表情や行動からその人の考えや感情を読み取り、次に来る行動を予測するという、高度な社会的能力を発達させてきました。この「心を読む」能力は、円滑な人間関係を築く上で不可欠です。
しかし、この能力が特に強く働くと、本来意図など持たないものにまで、それを読み取ろうとしてしまいます。例えば、コンピューターが不機嫌であるかのように感じたり、単なる偶然の出来事を誰かの周到な計画の結果だと解釈したりすることです。あらゆる物事の背後に能動的な主体の「意図」を検出しようとする認知的な特性が、陰謀論の核心をなす「悪意ある誰かが裏で糸を引いている」という物語を信じる上で、一つの素地となることが分かっています。
「意図を過剰に読み取る」性質と、陰謀論を信じる度合いとの直接的な関連を検証するため、一連の研究が行われました[3]。最初の研究では、オンラインで集められた参加者に対して、まず認知的な特性を測定しました。その一つが「アントロポモルフィズム(擬人観)」と呼ばれるもので、これは動物や家電製品、自然現象といった人間以外のものに対して、どの程度人間のような意識や感情、意図を感じるかを尋ねるものです。もう一つは、三角形や円などの幾何学図形が動き回る短いアニメーションを見せ、その動きをどのくらい「意図的」で「意識的」なものとして捉えるかを評価させる課題でした。
これらの測定の後、参加者がどの程度、有名な陰謀論を信じているかを尋ねました。その結果、無生物に人間らしさを感じやすい人ほど、また、図形のランダムな動きに意図を読み取りやすい人ほど、陰謀論を強く信じていることが明らかになりました。
しかし、「意図の過剰検出」は、超常現象のような他の非合理的な信念とも関連している可能性があります。そこで、二つ目の研究では、最初の研究の手順を繰り返しつつ、新たに参加者の超常現象への信念も測定しました。分析の結果、意図を過剰に読み取る性質、特にアントロポモルフィズムは、超常現象への信念とは独立して、陰謀論への信念を予測することが分かりました。陰謀論の根底にあるのが、単に目に見えない力を信じる心性というよりは、より限定された、「人間のような(そして多くの場合、悪意に満ちた)意図」を世界の出来事の背後に見出そうとする、特有の心の働きであることを示しています。
これら二つの研究では、もう一つ共通した結果が見られました。それは、教育水準が高い人ほど陰謀論を信じにくいというものです。この関連自体は以前から知られていましたが、今回の研究は、その背景にあるメカニズムの一端を解き明かしました。統計的な分析によると、教育水準の高さは、「意図を過剰に読み取る」という認知的な特性を抑制する方向に働き、その結果として陰謀論を信じにくくさせている、という間接的なプロセスが確認されたのです。
自己意識と反芻が組織内の敵意的解釈を強める
これまで見てきた、パターンや意図を読み取ろうとする人間の心性は、国家や世界といった大きなスケールだけでなく、私たちが日々多くの時間を過ごす職場のような、より身近な組織の中でも働いています。他者の意図を過剰に、そしてネガティブに解釈してしまう心性は、自分が他者からどう見られているのか、どう評価されているのかという「自己意識」が過剰に高まった時に、その鋭さを増します。ここでは、こうした心理的なプロセスが、組織内での不信感や、一種の「社内陰謀論」とも呼べるような敵意的な解釈をどのように生み出していくのかを見ていきましょう。
職場という環境は、上司や同僚からの評価、昇進や異動の可能性、人間関係の力学など、他者の視線を意識せざるを得ない場所に満ちています。会社に入ったばかりの新人や、プロジェクトで重要な役割を任されたばかりの人など、自分の立場が不安定だと感じている人は、「自分は常に試されている」「少しでもミスをすれば、悪く評価されるのではないか」といった不安、すなわち高い自己意識に苛まれがちです。
このような心理状態にある時、他者の何気ない言動—例えば、挨拶が素っ気なかった、会議で自分の意見に反論された、といった出来事—を、「自分に対する個人的な敵意の表れだ」とそのように解釈してしまうことがあります。曖昧な状況を悪意を持って解釈する認知的な解釈のパターンを、「悪意帰属の誤り」と呼びます。
この現象を実証するため、あるビジネススクールで実験が行われました[4]。対象は、入学したばかりの1年生と、すでに1年間の学校生活を経験した2年生です。参加者には、学生間で起こりうる曖昧でネガティブな出来事(例えば、約束していたミーティングに相手が現れなかった、など)が書かれたシナリオを読んでもらい、その原因をどう解釈するかを尋ねました。
その結果、組織における新参者である1年生は、2年生に比べて、相手の行動を「意図的な嫌がらせ」や「悪意によるもの」だと判断する度合いが有意に高いことが分かりました。この敵意的な解釈は、自分が1年生で相手が2年生という、自分の方が立場的に弱いと感じられる状況で、最も強くなりました。これは、自分が他者からどう見られているかという不安や自己意識の高さが、他者の行動を敵意的に解釈するフィルターとして機能することを示しています。
この敵意的な解釈がどのように強固な信念へと変わっていくのかを調べるため、別の実験が行われました。この実験では、「自己意識」に加えて、「反芻思考」、すなわちネガティブな出来事を頭の中で何度も繰り返し考え続けること、というもう一つの心理的なプロセスが調べられました。
参加者は数人のグループで資源管理ゲームを行いますが、その際、一部の参加者は自分の姿がビデオで撮影され続けました(自己意識を高めるための操作)。そして、ゲームの途中の休憩時間で、一部の参加者は「ゲームにおける他者の行動や、その裏にあるかもしれない策略について、詳しく考えて記述してください」と指示されました(反芻思考を促すための操作)。
結果、ビデオで撮影され(高い自己意識)、かつ、他者の策略について繰り返し考えさせられた(高い反芻)参加者たちが、最も強く他者への疑念を抱き、集団全体への信頼感を失い、将来またこのメンバーと協力したいという意欲も最も低くなりました。
この二つの研究が描き出すのは、組織内で不信感が醸成される一つのプロセスです。まず、不安定な立場などによって個人の自己意識が高まると、曖昧な出来事に対して敵意的な解釈、つまり「誰かが自分を害そうとしている」という疑念が芽生えます。そして、その疑念を一人で、あるいは同じような不満を持つ仲間内で繰り返し反芻することで、当初は単なる憶測に過ぎなかったものが、次第に補強され、増幅され、「揺るぎない事実」としての確信に変わっていくのです。
脚注
[1] van Prooijen, J.-W., Douglas, K. M., and De Inocencio, C. (2018). Connecting the dots: Illusory pattern perception predicts belief in conspiracy theories and supernatural phenomena. European Journal of Social Psychology, 48(3), 320-335.
[2] Swami, V., Furnham, A., Smyth, N., Weis, L., Ley, A., and Clow, A. (2016). Putting the stress on conspiracy theories: Examining associations between psychosocial stress, anxiety, and belief in conspiracy theories. Personality and Individual Differences, 99, 72-76.
[3] Douglas, K. M., Sutton, R. M., Callan, M. J., Dawtry, R. J., and Harvey, A. J. (2016). Someone is pulling the strings: Hypersensitive agency detection and belief in conspiracy theories. Thinking and Reasoning, 22(1), 57-77.
[4] Kramer, R. M. (1994). The sinister attribution error: Paranoid cognition and collective distrust in organizations. Motivation and Emotion, 18(2), 199-230.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。