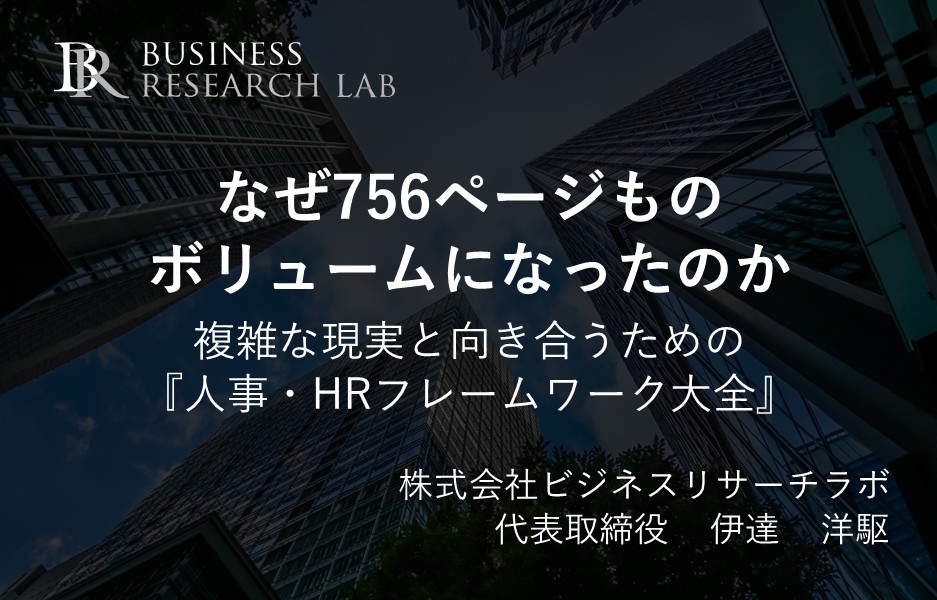2025年10月27日
なぜ756ページものボリュームになったのか:複雑な現実と向き合うための『人事・HRフレームワーク大全』
この度、『人事・HRフレームワーク大全』を上梓しました。書店に足を運ぶと、すぐに読めて要点がまとまった書籍が数多く並んでいます。情報が溢れ、時間に追われる現代において、効率的に知識を得たいという需要は当然のものでしょう。そのような時代に、756ページ、83のフレームワークを収録した一冊の本を世に送り出すことの意味を、お話しなければなりません。その厚みには意図があります。
人と組織をめぐる問題は、単一の特効薬で解決できるほど単純ではありません。「若手社員の定着率が低い」という一つの事象をとっても、その背景には賃金や労働時間といった待遇の問題だけでなく、上司との人間関係、キャリアパスへの不安、仕事そのものへの価値観といった、目に見えにくい無数の要因が複雑に絡み合っています。一つの要因に対処しても、別の要因が問題として浮上する。そのような対処に追われ、疲弊しているリーダーや人事担当者は少なくないはずです。
誰かの成功体験を切り取った断片的な知識では、この複雑な現実の理解は簡単ではなく、その深層にある構造にまでアプローチすることはできないものです。本書の分厚さは、その複雑さから逃げず、誠実に向き合うための必然でした。一つの解決策で全ての課題に対応できないからこそ、83もの多様な「思考の道具」を体系的に整理する必要があったのです。
本コラムは、広範な知識が収められた本書を、皆さんがそれぞれの現場で自在に使いこなすための活用法を示すものです。756ページというボリュームは、皆さんが立ち向かう課題の複雑さを反映したものです。そのページ一枚一枚が、複雑な現実を分析し、乗り越えるための指針となるでしょう。
一つの課題を多角的に掘り下げる
組織が直面する課題の中でも、特に多くの管理職が頭を悩ませるものの一つに「中堅社員のマンネリ化とエンゲージメント低下」が挙げられます。かつては意欲的に業務に取り組んでいた社員が、いつしか現状維持を好み、会議での発言も減っていく。こうした状況に対し、一般的な対策としてインセンティブの追加や新たな研修の実施といった手が打たれることがあります。しかし、多くの場合、その効果は一時的で、根本的な解決には至りません。なぜなら、問題の本当の原因が特定されていないからです。
『人事・HRフレームワーク大全』が提供する価値は、こうした捉えどころのない問題の解像度を上げ、その本質に迫る「深さ」にあります。本書に収められた複数のフレームワークを用いて、一つの課題を多角的に掘り下げてみましょう。
初めに、モチベーションの観点から分析します。「モチベーションと目標設定」の章で紹介する「職務特性理論」は、仕事が持つ特性が人の意欲を左右すると解説します。この視点から見ると、問いは具体的になります。彼ら彼女らの仕事は、単調な作業の繰り返しになっていないか。多様なスキルを活かす機会はあるか。自分の仕事が製品やサービスの完成にどう貢献しているのか、その全体像を把握できているか。その仕事が社会にとってどれほど重要なのかを実感できているか。仕事への意味や手応え、すなわち「心理的エンパワーメント」が失われていれば、意欲が低下するのは当然かもしれません。
続いて、キャリアの観点から考察します。「キャリア開発」の章にある「キャリア・アンカー」は、人が職業人生で譲れない価値観の軸を明らかにします。その中堅社員は、専門性を追求することに喜びを感じるタイプなのか、それとも安定した環境を望むタイプなのか。現在の業務内容は、彼または彼女が本当に大切にしたい価値観と合致しているでしょうか。「計画的偶発性理論」の視点に立てば、マンネリの原因は、予期せぬ挑戦や新しい出会いの機会が組織から失われていることにあるのかもしれません。安定は、時として成長の機会を奪う停滞にもなり得ます。
組織文化の観点も有効です。「組織文化と社会化」の章で解説する「組織的公正」は、結果の公平性だけでなく、意思決定プロセスの透明性がいかに重要かを教えてくれます。日々の評価や業務の割り当て、昇進の決定過程に不透明さや不公平感があれば、従業員の心には組織への不信感が募り、冷笑的な態度、すなわち組織的シニシズムが生まれます。彼ら彼女らの態度の背景には、報われない努力の積み重ねがあるのかもしれません。
さらに、ウェルビーイングの観点を通して、目に見えない消耗の可能性を探ります。「ストレス、健康、ウェルビーイング」の章にある「バーンアウト」や「労力–回復モデル」は、人が気づかぬうちに心身のエネルギーを消耗し、燃え尽きてしまう過程を示します。エンゲージメントの低下は、意欲の問題ではなく、長年の貢献によって心身の資源が枯渇してしまった結果である可能性も考えられます。適切な休息と回復の機会が組織的に保障されていなければ、持続的な貢献は望めません。
このように、複数のフレームワークを組み合わせることで、「中堅社員のマンネリ化」という一つの現象が、個人の動機、キャリア観、組織の公正性、心身の健康状態といった、いくつもの要因が絡み合った立体的な問題として理解できます。本書の厚みとは、一つの課題に対して複数の診断仮説を立て、多角的な分析を可能にし、根本原因へと迫るための「深さ」の証明です。
人事施策のつながりを可視化する
多くの組織では、人事に関する施策が個別に実施されています。採用担当は優秀な人材を採ることに注力し、研修担当は質の高い研修プログラムを企画する。評価制度の担当者は、より公平な評価基準の策定に腐心する。それぞれの担当者が誠実に職務を果たしていても、施策同士の連携が取れていなければ、組織全体としての効果は限定的になってしまいます。採用はうまくいっているのに育成が追いつかない、評価制度は新しくなったのに旧態依然とした組織文化がそれを阻害する、といった問題は決して珍しくありません。
組織とは、各機能が相互に影響しあう一つのシステムです。『人事・HRフレームワーク大全』が83ものフレームワークを網羅しているのは、このシステム全体を俯瞰し、施策間のつながりを設計するための視座を提供することを目指したからです。本書の広範なカバレッジは、人事という機能を分断されたものではなく、一貫した思想のもとに連携するものとして捉える思考法を促します。本書の構成に沿って、その考え方の一端を辿ってみましょう。
組織の「入口」である採用と配置から始まります。ここでは、「PE-フィット(個人と環境の適合性)」という基本的な考え方が重要になります。個人の価値観や能力が、組織の文化や要求とどれだけ適合しているか。この適合性を高めることが、長期的な定着と貢献の土台となります。「高業績作業システム」が示すように、厳選された採用と適切な配置は、組織全体のパフォーマンスを左右する最初の一手です。
次に、組織に迎え入れた人材が円滑に馴染み、成長していくための「定着と育成」のプロセスです。「組織社会化」のフレームワークは、新メンバーが組織の文化や規範を学び、一員となるまでの段階的な過程を示します。この過程で、「自己決定理論」が示す「自律性」「有能感」「関係性」といった欲求を満たすような環境を提供できれば、彼ら彼女らの内発的動機づけは高まり、主体的な成長が促されます。
個人の成長は、チームという文脈の中で発揮されて組織の力になります。「グループ発達」の理論は、チームが形成期から混乱期、統一期を経て、高い成果を出す遂行期へと至る成熟のプロセスを描き出します。この過程でリーダーは、「PM理論」が示すように、目標達成を推し進める側面と、チームの人間関係を維持する側面の両方をバランス良く発揮することが求められます。
これらの日々の活動が、組織の文化として根付いていく段階です。メンバーの貢献が「組織的公正」に則って評価され、役割や職務記述書を超えた自発的な貢献である「組織市民行動」が自然と生まれるような風土が醸成されていく。これは、持続的に成果を生み出す健全な「組織文化」の姿です。
756ページという本書の「広さ」は、これら人事の各機能がいかに連動しているかを体系的に理解し、個別の施策をシステムの一部として捉えて、持続的なインパクトを生むための視座を提供します。一つの施策を導入する際に、それが他の機能にどのような影響を与えるのかを予測し、組織全体として一貫性のある人材マネジメントを設計するための思考の土台となります。
古典から学び、未来の組織を構想する
ビジネスの世界では、新しい経営理論や人事に関する用語が次々と生まれては、消費されていきます。その中で、本書があえて「PM理論」(1960年代)のような古典的フレームワークから、「心理的資本」(2000年代以降)のような比較的新しい概念まで、幅広い時間軸の知を網羅しているのはなぜでしょうか。それは、過去から学び、現在を分析し、未来を構想するという、長期的な時間軸の中で組織を捉える視点が、変化の時代に対応するために有用だと考えるからです。
「PM理論」や「衡平理論」のような古典的フレームワークは、時代背景や技術がどれだけ変わろうとも、その根底で変わることのない人間行動の原理原則を教えてくれます。リーダーシップにおける目標達成と人間関係維持のバランスの重要性や、人が他者との比較の中で公平性を求める心理は、半世紀以上の時を経てもその本質は変わりません。これらは、複雑な現代の組織問題を理解するための、揺るぎない基礎となります。流行りの手法に飛びつく前に、この基礎を自らの中にしっかりと根付かせることが、応用のための土台を築きます。
一方で、「キャリア・アダプタビリティ」や「チーム・バーチャリティ」「心理的ウェルビーイング」といった新しい概念は、VUCA、テレワークの普及、ダイバーシティの推進といった、現代特有の経営環境に対応するために生まれました。長期雇用が前提でなくなり、個人が自律的にキャリアを形成する必要性が高まる中で、変化に適応し続けるための心理的資源とは何か。物理的に離れたメンバーが、いかに一体感を持ち、協働していくか。これらの新しいフレームワークは、基礎理論を土台としながら、現代的な課題に対する処方箋を示してくれます。
本書に収められた83のフレームワークを、その誕生した時代背景と共に捉え直すとき、そこには人と組織に関する知が、社会や働き方の変化に応じていかに進化してきたかという、学術的な発展の歴史が見えてきます。この歴史的な視点を持つことで、私たちは単に個別の知識を学ぶだけでなく、未来の組織が直面するであろう課題を予測し、先手を打つための洞察を得ることができます。例えば、AIの進化がさらに進んだ未来において、人はどのような動機で働き、組織にはどのような公正性が求められるのか。過去の変遷を理解することは、未来を構想するための思考の基盤を与えてくれます。
本書の厚みは単なる量の多さではなく、数十年にわたる学術研究の蓄積です。私たちはこの蓄積を辿ることで、過去から学び、現在を正確に分析し、未来を創造するための長期的な視点を手に入れることができます。
「分厚い本」から「実践の書」へ
ここまで、本書の「深さ」「広さ」「時間軸」という三つの側面から、756ページというボリュームに込められた意図を解説してきました。この本が読者の皆様に提供する最終的な価値は、83の個別の知識そのものではありません。それは、これらの知識を学び、使い、組み合わせるプロセスを通じて、皆さん自身の思考の基盤を構築するきっかけです。
本書は、一度読んで終わりにするためのものではありません。むしろ、そこからが本当の始まりです。日々の業務で具体的な課題に直面した際には、目次や索引から関連する項目を探し出す「辞書」として。チームや部署内で輪読し、フレームワークを「共通言語」として議論すれば、感覚的な対立を乗り越え、建設的な対話を生み出すための土台として機能するでしょう。そして、本書の余白に自分自身の経験から得た気づきや、現場で試した結果を書き込んでいけば、それは皆さんだけの「実践の書」へと成長していきます。
フレームワークを学び、実践し、そして時にはその限界を吟味し、複数の理論を組み合わせる。このプロセスを繰り返すうちに、皆さんの頭の中には、個別の知識が結びついた、体系的な思考が構築されていくはずです。そうなった時、この756ページの一冊は、皆さんのキャリアを支え、皆さんが関わる組織をより良い方向へ導くための指針となるでしょう。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。