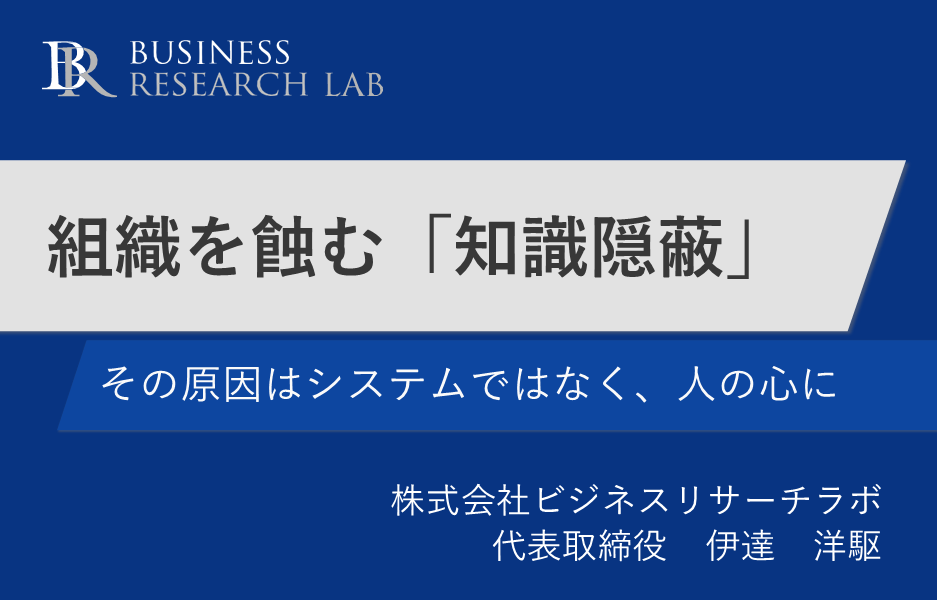2025年10月27日
組織を蝕む「知識隠蔽」:その原因はシステムではなく、人の心に
知識の共有は組織の成長に欠かせない原動力です。しかし、従業員が持つ貴重な知識が必ずしも円滑に共有されないという問題が起きている企業もあります。この現象は「知識隠蔽」と呼ばれ、同僚から求められた知識を意図的に隠したり、提供を拒んだりする行動を指します。
一見、目立たないこの行動ではありますが、組織に深刻な影響を及ぼしかねません。新しいアイデアの創出を妨げ、チーム内の協力関係を損ない、組織全体のパフォーマンスを低下させる原因となるのです。
では、なぜ人々は知識を隠してしまうのでしょうか。そして、どのような条件下でこの行動は生まれやすくなるのでしょうか。本コラムでは、知識隠蔽という現象を分析した複数の研究を通じて、その背景にある心理的メカニズムと組織要因を探ります。「リーダーシップ」「組織文化」「個人の心理的所有感」という異なる視点から知識隠蔽を理解することで、この問題の本質に迫ります。
チームの協力意識が低くても、信頼あるリーダーが知識隠蔽を防ぐ
知識隠蔽という現象を理解するために、注目したいのがチーム内での人間関係とリーダーシップの役割です。ある研究では、チーム内における知識隠蔽がどのような要因によって左右されるかが調査されました[1]。
研究の対象となったのは、知識隠蔽という行動そのものでした。知識隠蔽とは、他者から求められた知識や情報を意図的に隠す行為で、「知らないふりをする」「情報提供を先送りする」「情報提供できない理由を合理的に説明する」という3つの具体的な行動パターンで特徴づけられます。従来、この現象は主に個人間の関係で研究されてきましたが、この研究では「チーム」という集団の中で発生する知識隠蔽に焦点を当てました。
研究者たちは、社会交換理論という枠組みを基盤として、チーム内の知識隠蔽が二つの要因によってどのように左右されるかを探りました。一つ目は「集団レベルの向社会的動機」、二つ目は「リーダーとメンバーの交換関係」です。
向社会的動機とは、他者の利益を考慮し、他者の福祉を促進したいという欲求を意味します。チーム全体がこのような動機を共有している場合、メンバーは自然と知識を共有しようとし、知識隠蔽は減少すると予想されました。一方、リーダーとメンバーの交換関係については、経済的交換と社会的交換という二つの側面から分析されました。
経済的交換とは、短期的で取引的、計算的な関係を指します。「これを提供したら、その見返りに何を得られるか」という損得勘定に基づく関係です。このような関係が強い場合、知識隠蔽が促進されると予測されました。一方、社会的交換は信頼を基盤とした長期的で持続的な関係を意味します。リーダーとメンバーの間に深い信頼関係が築かれている場合、知識隠蔽は抑制されると考えられました。
この研究では、二つの異なる手法で検証が行われました。最初の研究では、大学生115人を29のチームに分け、リーダーとメンバーの関係を人為的に操作した実験が実施されました。参加者たちは、リーダーとの関係が良好な条件と良好でない条件に分けられ、その後の知識隠蔽行動が測定されました。
実験の結果は予想を裏付けるものでした。チームの向社会的動機が高い場合、知識隠蔽は少なくなりました。メンバーが他者の利益を考える気持ちを持っているチームでは、自然と知識が共有されやすい環境が生まれていました。リーダーとメンバーの関係についても、信頼に基づく社会的な交換関係が強いほど知識隠蔽は少なくなりました。
チームの向社会的動機が低い状況での発見は特筆すべきものです。通常であれば、メンバーが自分のことばかり考えているチームでは知識隠蔽が多発すると予想されます。しかし、このような状況でも、リーダーとメンバーの間に強い信頼関係が存在する場合、知識隠蔽は抑制されることが分かりました。
二つ目の研究では、より現実的な環境での検証が行われました。ヨーロッパの保険会社に勤務する309人の従業員(92チーム)を対象としたアンケート調査が実施されました。実際の職場環境では、実験室と異なる複雑な要因が作用するため、結果は実験研究ほど明確ではありませんでした。
現場調査では、チームの向社会的動機単体では知識隠蔽との明確な関係を示しませんでした。これは実験環境と実際の職場環境の違いを反映していると考えられます。実際の職場では、向社会的動機以外にも多様な要因が同時に作用するため、単純な関係性が見えにくくなるのでしょう。
経済的交換関係についても、予想に反して知識隠蔽への明確な影響は確認されませんでした。しかし、社会的交換関係については、やはり知識隠蔽を減少させる傾向が確認されました。特に、チームの向社会的動機が低い場合でも、リーダーとメンバーの間の社会的な信頼関係が知識隠蔽をある程度抑制する傾向が見られました。
この研究が明らかにしたのは、リーダーシップの質が知識隠蔽を防ぐ上で重要な役割を果たすということです。チーム全体の協力意識や利他的な動機が理想的である必要はありません。むしろ、リーダーが個々のメンバーと信頼に基づく関係を築くことができれば、たとえチーム全体の雰囲気が必ずしも協力的でなくても、知識隠蔽を防ぐことが可能であることが示されました。
知識隠蔽は、システムや規則では防げず、文化が鍵
知識隠蔽の問題を解決するために、多くの組織が最初に考えるのは、システムの導入や規則の制定です。しかし、これらのアプローチは果たして有効なのでしょうか。北米の信用組合を対象とした研究は、この疑問に対する答えを提供しています[2]。
この研究は、知識隠蔽という「非生産的な知識行動」に焦点を当て、その原因と結果を包括的に分析したものです。知識隠蔽は「個人が他者から要求された知識を意図的に隠したり提供しない行動」と定義され、知識共有とは本質的に異なる現象として位置づけられました。知識隠蔽には二つの特徴があります。まず、意図的であること、そして求められた知識を隠すことです。
研究者たちは、知識隠蔽の前提要因として四つの要素を検討しました。技術的側面として、ナレッジマネジメントシステムの存在と知識共有ポリシーの有無が調査されました。一般的に、これらの仕組みがあることで従業員の知識隠蔽は減少すると考えられていました。
文化的側面では、組織の知識共有文化が検討されました。オープンで協力的な文化を持つ組織では、知識隠蔽が起こりにくいと予想されました。最後に、構造的要因として職務の不安定性が分析されました。給与が低く、解雇率が高い組織では、従業員が自己保護的に知識を囲い込む行動を取りやすいと考えられました。
知識隠蔽の結果についても二つの側面が検討されました。一つは相互知識隠蔽、つまり他者が知識を隠すと自分も報復的に知識を隠すという悪循環です。もう一つは自主的離職意図で、知識隠蔽が蔓延する職場では従業員の離職意図が高まると予想されました。
調査は北米の信用組合15社の従業員691名を対象に実施されました。ナレッジマネジメントシステム、知識共有ポリシー、知識共有文化、知識隠蔽、相互知識隠蔽、離職意図などが評価され、組織レベルのデータとして給与水準や解雇率も収集されました。
調査結果は、多くの組織が抱いている仮説を覆すものでした。ナレッジマネジメントシステムや知識共有ポリシーの有無は、知識隠蔽に有意な影響を与えませんでした。高度なシステムを導入し、詳細なポリシーを策定しても、従業員の知識隠蔽行動には変化が見られませんでした。
多くの企業が知識共有の促進や知識隠蔽の防止のために、システムや制度の整備に着手します。しかし、この研究結果は、技術的あるいは制度的な仕組みだけでは知識隠蔽を抑止できないことを示しています。
一方で、組織の知識共有文化は知識隠蔽に影響を与えていました。オープンで協力的な文化を持つ組織ほど、知識隠蔽行動は低下していました。従業員の行動が表面的な規則やシステムではなく、職場の雰囲気や価値観により左右されることを示しています。
職務の不安定性についても予想通りの結果が得られました。給与が低く、解雇率が高い組織では、知識隠蔽が増加していました。経済的な不安や雇用の不安定さが、従業員を自己保護的な行動に向かわせているのです。自分の持つ知識が唯一の価値であり、それを手放すことで自分の立場が危うくなると感じる従業員は、知識を囲い込もうとします。
知識隠蔽の悪循環についても結果が得られました。同僚が知識を隠すほど、自身も知識隠蔽で応じる傾向が見られました。知識隠蔽は個人の行動として始まりますが、職場全体に感染するように広がる性質を持っています。一人が知識を隠し始めると、他の人々も「自分だけが損をしたくない」という心理から同様の行動を取るようになります。
知識隠蔽と離職意図の関係も確認されました。知識隠蔽が多い環境ほど、従業員の離職意図が増大していました。知識が自由に共有されない職場は、従業員にとって魅力的ではありません。学習機会が制限され、成長が阻害される環境では、優秀な人材ほど他の選択肢を模索するようになります。
組織が知識隠蔽を防ごうとする場合、システムや規則の整備だけでは不十分です。従業員が安心して知識を共有できる文化的土壌を育成し、雇用の安定性を向上させることが解決策となります。
「自分の仕事」への所有感が知識隠蔽を、会社への所有感が共有を生む
知識隠蔽の心理的メカニズムを理解するために、個人の心理状態に焦点を当てた研究があります。この研究は、知識隠蔽がもたらす組織への損害の大きさを示しながら、その背景にある心理的要因を分析しています[3]。
Fortune 500企業における年間推定315億ドルという損失額は、知識隠蔽がいかに深刻な問題であるかを物語っています。この巨額の損失は、社内コラボレーションの阻害、新しいアイデアの生成や施策実施の妨害、チームや組織のパフォーマンス低下によって生まれています。では、従業員はなぜ自らの知識を隠そうとするのでしょうか。
この研究が明らかにした要因は、心理的所有感という概念です。心理的所有感とは、物理的な所有権とは異なり、個人が特定の対象を自分自身の延長として感じる心理状態を指します。職場においては、従業員が特定の職務、役割、プロセス、あるいは知識そのものに対して強い所有感を抱くことがあります。
この所有感が強いほど、他者と知識を共有することに抵抗感を感じるようになります。「これは私の専門領域だ」「この知識は私が苦労して獲得したものだ」という意識が強くなると、その知識を他者に渡すことで自分の価値や地位が脅かされると感じるようになります。結果的に、同僚から求められても知識を隠蔽する行動を取りやすくなるのです。
心理的所有感と関連する概念として、縄張り意識があります。縄張り意識は、職場内で自分の領域を明確にし、それを保護しようとする行動として現れます。これには目に見える形での領域の主張(名前の入ったドア、個人的な写真の掲示、専用の機器の使用)と、心理的な領域の防衛(他者からの侵入に対する苦情、知識共有への拒否反応)の両方が含まれます。
研究では、縄張り意識が高い従業員ほど知識隠蔽行動を取りやすいことが確認されました。自分の領域を守ろうとする意識が強い人は、知識を自分だけの財産として捉え、それを他者と共有することを領域侵害と感じてしまいます。
心理的所有感には別の側面もあります。組織そのものに対する心理的所有感です。従業員が自分の所属する組織を自分自身の一部として捉えている場合、その行動パターンは変わります。組織への心理的所有感が強い従業員は、組織の成功を自分の成功と同一視し、組織全体の利益のために積極的に知識を共有しようとします。
同じ心理的所有感でも、その対象が個人の職務や知識に向けられるか、組織全体に向けられるかによって、知識共有行動は正反対の方向に向かいます。個人レベルの所有感は知識隠蔽を促進しますが、組織レベルの所有感は知識共有を促進します。
研究では、組織への心理的所有感が個人の縄張り意識による知識隠蔽の傾向を弱める役割を果たすことも明らかになりました。たとえ個人が自分の仕事領域に強い所有感を持っていても、組織全体への愛着や一体感がそれを上回る場合、知識隠蔽よりも知識共有を選択する可能性が高くなります。
知識隠蔽の心理的メカニズムには、所有感の喪失によるネガティブ感情も関与しています。自分が所有していた知識や領域を他者に奪われたり共有したりすることで、制御感が失われ、ストレスやフラストレーションが生じます。このネガティブな感情が、さらなる知識隠蔽や他の非機能的な行動を促進する悪循環を生み出します。
知識が交渉力や組織内での地位向上の道具として機能することも、知識隠蔽を促進する要因の一つです。専門的な知識を独占することで、その個人は組織内での特権的地位や権限を維持できます。この交渉力を手放すことは、自分の価値の低下や立場の悪化につながると認識されるため、知識隠蔽への動機が強まります。
従業員が知識を隠すのは、必ずしも悪意や怠慢によるものではありません。むしろ、人間の心理的ニーズである所有感や制御感、安全欲求と深く関連しています。個人が自分の専門性や知識に価値を感じ、それを自分のアイデンティティの一部として捉えることは自然なことです。
しかし、この自然な心理が組織レベルでは問題を生み出します。個人の心理的ニーズと組織の知識共有ニーズの間には、構造的な矛盾が存在するのです。この矛盾を解決するためには、個人の所有感を組織レベルに拡張し、従業員が組織全体の成功を自分の成功として捉えられるような環境づくりが必要になります。
脚注
[1] Babic, K., Cerne, M., Connelly, C. E., Dysvik, A., and Skerlavaj, M. (2019). Are we in this together? Knowledge hiding in teams, collective prosocial motivation and leader-member exchange. Journal of Knowledge Management, 23(8), 1502-1522.
[2] Serenko, A., and Bontis, N. (2016). Understanding counterproductive knowledge behavior: Antecedents and consequences of intra-organizational knowledge hiding. Journal of Knowledge Management, 20(6), 1199-1224.
[3] Peng, H. (2013). Why and when do people hide knowledge? Journal of Knowledge Management, 17(3), 398-415.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。