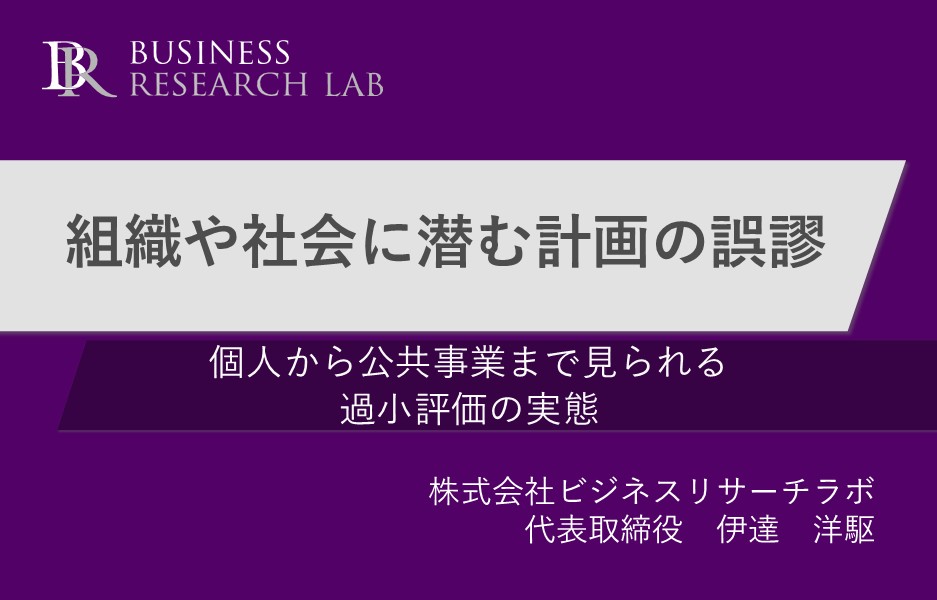2025年10月24日
組織や社会に潜む計画の誤謬:個人から公共事業まで見られる過小評価の実態
歴史に名を刻む壮大な建築物や、国家の威信をかけた巨大なインフラ。私たちは完成した姿に目を奪われますが、建設の裏側で、当初の計画を遥かに超える時間と費用が必要となったという事実があります。例えば、当初10年で終わるはずだったプロジェクトが20年かかったり、予算が2倍、3倍に膨れ上がったりすることは、実は例外的な失敗ではありません。
この現象は、国家的な大事業だけの話ではありません。企業の新規事業開発、オフィスの移転、あるいは個人のキャリアプランや週末の予定に至るまで、私たちの周りには「計画通りに進まない」事例があふれています。なぜ、私たちは未来を楽観的に見積もってしまうのでしょうか。
ただの能力不足や不運が原因ではありません。人間の思考に根ざした、体系的な認知の歪み、すなわち「計画錯誤」と呼ばれる心の働きが存在します。一部の楽観的な人だけが持つ癖ではなく、専門家から一般の生活者まで、誰もが陥る可能性のある思考の罠です。
本コラムでは、この計画錯誤という現象の分け入っていきます。研究知見を手がかりに、なぜ私たちの計画は現実から乖離してしまうのか、そのメカニズムを検討していきます。個人の心理から、組織の力学、さらには社会全体の構造に至るまで、様々な角度から迫ります。
人前で期限を宣言すると楽観が強まる
「目標は口に出して公言した方が、責任感が生まれて達成しやすくなる」という考え方は広く信じられています。確かに、他者の目を意識することで、自分を律する力が働く場面はあるでしょう。しかし、こと「計画の正確さ」という観点から見ると、この公言という行為が、予測を歪ませる原因となりうることを示した研究があります[1]。
ある心理学の実験において、大学生たちを対象に、計画を公にすることが予測にどのような作用を及ぼすかが検証されました。実験の参加者は、いくつかの課題が含まれた宿題を渡され、それを自宅で完了させて電子メールで提出するよう求められます。その際、この宿題が完了するまでにおおよそ何日かかると思うか、その所要日数を予測してもらいました。
ここでの工夫は、予測の伝え方にありました。参加者の一部は、実験者がいる前で、完了予定日を「口頭で」宣言するように求められました。これは、他者に対して公に予測を立てる状況を再現したものです。一方で、もう一方の参加者は、予測した日数を紙に書き、誰にも見られないように封筒に入れて提出しました。こちらは他者の評価を気にすることなく、匿名で予測を立てる状況に当たります。
この実験ではもう一つの条件が加えられました。宿題の予測を立てる直前に、参加者は別の簡単な作業を行うのですが、その半数には「残念ながら時間内に終わりませんでした」と告げられ、失敗を経験させられます。実験者は参加者の目の前で、その作業用紙を無情にもゴミ箱に捨ててみせるという演出まで行われました。残りの半数は、予定通りに作業を完了できたと告げられます。これによって、「直近の失敗経験」が、その後の計画にどう関わるかも調べられるように設計されていました。
宿題の提出までにかかった実際の日数と、参加者が事前に立てた予測日数を比較したところ、二つの群の間で違いが見られました。実験者に対して口頭で完了日を宣言した群は、実際にかかった日数よりも、平均して短い日数を予測していました。要するに、楽観的な計画を立てていたのです。それに対して、匿名で予測を紙に書いた群では、予測と実際にかかった日数の間にあまり差はありませんでした。
この結果は、予測の精度という点から見ると、さらに明確な対照を描き出します。匿名で予測を立てた群では、予測した日数と実際にかかった日数にある程度の相関関係がありました。予測が短い人は実際に早く終え、長いと予測した人は時間もかかるという、ある程度合理的な関係です。ところが、口頭で宣言した群では、この相関が消えていました。早く終わると宣言した人が、必ずしも早く終えるわけではなかったのです。
この結果が物語るのは、人前で計画を宣言する時、私たちの心の中では「正確な予測を立てること」よりも、「他者によく見られたい」という動機が優位に立つという事実です。有能で、仕事が早い人間だと思われたい。その欲求が、計画が外れてしまうかもしれないというリスクを上回ってしまうのでしょう。
直前に失敗を経験したかどうかは、この楽観バイアスの大きさには直接的な変化をもたらしませんでした。失敗を経験した参加者は、罪悪感からか、次の宿題にはより早く取り組む行動を見せましたが、だからといって予測がさらに楽観的になるわけではありませんでした。計画の誤謬を駆動する力は、過去の経験よりも、予測を立てるその瞬間に誰の視線を意識しているか、という社会的な文脈にあることがうかがえます。
内的視点で人は小事に慎重、大計画を過度に楽観する
私たちの意思決定は、一貫しているようでいて、矛盾をはらんでいます。例えば、目の前に「確実に1万円もらえる」選択肢と、「50%の確率で3万円もらえるが、50%の確率で何ももらえない」というギャンブルがあった場合、多くの人は前者を選びます。期待値としては後者の方が高いにもかかわらず、不確実性を避けて確実な利益を手にしようとするのです。このように、比較的小さなリスクに対しては、私たちは慎重に行動する傾向があります。
ところが、これが会社の未来を左右するような大規模なプロジェクト計画になると、事態は一変します。数億円規模の投資、数年がかりの新規事業開発。そうした大きな意思決定の場面では、あれほど慎重だったはずの同じ人物が大胆で楽観的な予測を信じ、承認することがあります。小さなリスクには臆病なのに、巨大なリスクを伴う計画にはなぜか大胆になれる。この一見した矛盾の背後には、人間の認知における特性が隠されています。
この現象を説明する鍵となるのが、「内的視点」と「外的視点」という二つの考え方です[2]。私たちが何か新しい計画を立てるとき、多くの場合「内的視点」に支配されています。これは目の前にある計画そのものの詳細、独自の強み、成功に至るまでの理想的なシナリオに意識を集中させる見方です。自分たちのチームは優秀だ、この技術は画期的だ、競合はこう動くだろうから我々はこのように対応できる、といった具合に、計画のユニークな側面に光を当てます。
一方で、「外的視点」とは、その計画をいったん脇に置き、過去に行われた類似のケースがどのような結果になったかという事実に目を向ける見方です。例えば、新しいソフトウェアを開発する計画を立てているなら、「過去に同規模のソフトウェア開発プロジェクトは、平均してどのくらいの期間と予算で完了し、成功率はどの程度だったか」という客観的なデータを参照するのが外的視点です。
問題は、私たちが「内的視点」を好み、「外的視点」を軽視してしまうことにあります。自分たちの計画は過去のどの事例とも違う「特別なもの」だと考えたいのです。この心理を象徴する逸話があります。ある専門家チームが、新しい学校カリキュラムを開発するプロジェクトの計画を立てていました。チームのメンバーに完成までの期間を尋ねたところ、誰もが「1年半から2年半」の範囲で終わると答えました。皆、計画の詳細を熟知しており、自信に満ちていました。
しかし、そのチームの一人がふと、過去の類似したカリキュラム開発プロジェクトの事例を思い出しました。調べてみると、そうしたプロジェクトが完成に至るまでには、平均して7年から10年もの歳月がかかっており、しかも約4割は計画倒れに終わっていました。この客観的なデータ、つまり「外的視点」からの情報は、チームに衝撃を与えました。しかし、結局のところチームはこの悲観的なデータを無視することを選びました。「我々のプロジェクトは、過去の失敗例とは違う」と。そして、そのプロジェクトが最終的に完了するまでには、8年という長い時間がかかったのです。
なぜ組織では、このような非合理的な楽観主義がまかり通ってしまうのでしょうか。そこには、組織内での生存競争という政治的な力学が働いています。新しいプロジェクトの承認を得るためには、その計画がいかに素晴らしく、迅速かつ低コストで実現可能であるかをアピールしなくてはなりません。慎重で現実的な、地味に見える計画よりも、大胆で楽観的な、魅力的に響く計画の方が、経営層の承認を得やすいものです。その結果、プロジェクトの提案者たちは、意図的であるかどうかにかかわらず、成功の可能性を過大評価し、コストや時間を過小評価した計画を提示するようになります。
このように、個別の問題として切り離して考える「孤立化」という認知の癖と、自分たちの計画を特別視する「内的視点」への固執が組み合わさることで、臆病な個人が、組織の一員としては大胆な楽観主義者へと変貌してしまいます。
所要時間の過小評価は、過去の記憶が短縮されているせい
私たちは、将来の計画を立てる際、多かれ少なかれ過去の経験を頼りにします。「あの仕事は確か一週間くらいかかったから、今度の似たような仕事もそれくらいだろう」というように、過去の事例を検索し、未来の予測に当てはめています。これまで計画錯誤は、こうした過去の失敗経験や、時間がかかった辛い記憶を意図的に無視し、楽観的なシナリオだけを描こうとする心理によって生じると考えられてきました。「過去を忘れる」ことが問題だとされてきたのです。
しかし、この通説に一石を投じる、異なる視点が存在します。それは、私たちは過去を無視しているのではなく、むしろ過去の経験に忠実に依拠している、というものです。ただし、そこには一つ、重大な問題があります。その依拠している「過去の記憶」が、私たちの頭の中で、もとの出来事よりも体系的に短く圧縮されてしまっているというのです。これは「メモリー・バイアス仮説」と呼ばれ、計画錯誤の根源を、未来への希望的観測ではなく、過去を振り返る際の記憶の歪みに求める考え方です。
この仮説の妥当性を検証するため、過去数十年間にわたって行われた、計画時間に関する膨大な数の実証研究を網羅的に分析したレビューが行われました[3]。その結果、まず分析対象となった研究の実に九割近くで、人々がタスクの所要時間を実際よりも短く見積もる「過小評価」が確認されました。日常的な課題から専門的な作業まで、この過小評価は共通して見られる現象でした。
ここで特に興味深い発見は、課題に対する熟練度と、過小評価の大きさの関係です。一般的に考えれば、経験を積んだベテランほど、作業時間の見積もりは正確になるはずです。しかし、データが示した事実はその逆でした。
ある実験では、携帯電話の操作に慣れた熟練者は、初心者が同じ操作を終えるのにかかる時間を予測するよう求められました。すると熟練者は、実際の所要時間よりも短い楽観的な予測を立てたのです。ピアニストやプログラマーを対象とした別の研究でも、習熟度が高い人ほど、自らの作業時間を過小評価する傾向が強まることが分かっています。
この「熟練者ほど見積もりが甘くなる」という一見不可解な現象は、「メモリー・バイアス仮説」を用いると説明がつきます。
ある作業に習熟するということは、その作業の各ステップを意識することなく、自動的に実行できる状態になるということです。そのため、後からその作業を振り返ったとき、記憶の中では個々の苦労や細かな手順が省略され、全体としてスムーズに進んだという印象が残ります。作業にかかった時間の感覚が記憶の中で「圧縮」され、実際よりも短く感じられるようになるのです。そして、未来の計画を立てる際に、この短く圧縮された記憶を基準として用いると、必然的に予測もまた過小評価されてしまいます。
この記憶の歪みが予測に直接作用していることは、別の実験からも裏付けられています。参加者に課題をこなしてもらう際に、「できるだけ早く完成させたら報酬を与えます」と動機づけを行うと、人々はその課題にかかった時間を、実際よりもさらに短く記憶するようになります。それに引きずられるように、将来の同様の課題に対する予測時間も、より一層短くなります。報酬を提示されても、実際の作業時間が劇的に短縮されるわけではありません。変わったのは、現実の行動ではなく、記憶と、その記憶に基づいた予測の方です。
これらの知見が私たちに伝えるのは、計画錯誤が、ただ未来を楽観視する心の問題だけではないということです。それは、私たちが経験を積み重ね、過去を振り返るという、ごく自然な認知活動の過程に組み込まれた、避けがたい記憶の仕組みに根ざしている可能性を示唆しています。したがって、「過去の経験をよく思い出して計画を立てなさい」とアドバイスするだけでは、根本的な解決にはなりません。なぜなら、その思い出されるべき過去の記憶自体が、すでに信頼性を失っているかもしれないからです。
公共事業費は意図的に恒常的に過小に見積もられる
これまで私たちは、計画が現実から乖離していく原因を、他者への見栄や、自分たちの計画を特別視する思い込み、経験によって歪められる記憶といった、人間の心理的なメカニズムに求めてきました。これらはある意味で、悪意のない「誠実な誤り」と呼べるかもしれません。しかし、国家的なプロジェクトで繰り返される、当初予算の超過を、本当に「うっかり」や「思い込み」といった言葉だけで説明し尽くすことができるのでしょうか。ここでは、計画錯誤が、意図的な「嘘」である可能性を、大規模なデータ分析によって検証した研究を紹介します[4]。
この研究が取り組んだのは、公共事業、特に交通インフラにおけるコスト見積もりの信頼性という問題です。研究者たちは、世界20カ国、5大陸にまたがる258件もの巨大プロジェクトのデータを収集しました。対象となったのは、1927年から1998年までの約70年間に完成した鉄道、道路、橋、トンネルです。分析の焦点は一点に絞られました。プロジェクトの着工が決定された時点での見積もりコストと、実際に完成までにかかった最終的なコストとの間に、どれほどの乖離があるかです。
その結果、調査対象となった258件のプロジェクトのうち、実に86%で、実際のコストが見積もりを上回る「コスト超過」が発生していました。この研究における重大な発見は、こうしたコスト超過の傾向が、分析対象となった70年という長い期間にわたって改善されていなかったという事実です。測量技術や建設技術、あるいはプロジェクト管理の手法がどれほど進歩しても、見積もりの甘さは一向に修正されていません。
コスト超過が純粋に技術的な予測の難しさに起因するのであれば、長年の経験の蓄積や技術革新によって、徐々にでも見積もり精度は向上していくはずです。しかし、データはそうした学習の跡を示していません。また、人間の心理的な楽観主義、すなわち「計画錯誤」だけで説明するのも困難です。個人や組織が、70年間も全く同じ種類の失敗から学ばず、同じように楽観的な過ちを繰り返し続けるというのは不自然です。
そこで研究者たちが妥当な説明として提示したのが、「戦略的な虚偽表示」という仮説です。プロジェクトの推進者や関係者が、そのプロジェクトをなんとしても実現させるために、計画段階で意図的にコストを低く見積もって提示するという考え方です。巨額の予算を必要とする公共事業は、費用対効果の面から審査に晒されます。その際、コストを低く、便益を高く見せかけることができれば、他の競合プロジェクトを退けて承認を勝ち取りやすくなります。一度プロジェクトが始動してしまえば、途中でコストが想定より膨らんだとしても、「今更やめるわけにはいかない」という論理が働き、追加の予算が認められやすくなります。
この「政治・経済的な要因」は、データに見られたパターンをうまく説明します。コスト超過が70年間も改善されないのは、それが技術的な失敗ではなく、プロジェクトを勝ち取るための合理的な戦略であり続けているからでしょう。計画錯誤は、ここでは個人の心理的なバイアスという領域を超え、組織や社会の構造に根ざした、意図的な情報操作という側面を帯びてくるのです。
脚注
[1] Pezzo, S. P., Pezzo, M. V., and Stone, E. R. (2006). The social implications of planning: How public predictions bias future plans. Journal of Experimental Social Psychology, 42(3), 221-227.
[2] Kahneman, D., and Lovallo, D. (1993). Timid choices and bold forecasts: A cognitive perspective on risk taking. Management Science, 39(1), 17-31.
[3] Roy, M. M., Christenfeld, N. J. S., and McKenzie, C. R. M. (2005). Underestimating the duration of future events: Memory incorrectly used or memory bias? Psychological Bulletin, 131(5), 738-756.
[4] Flyvbjerg, B., Skamris Holm, M., and Buhl, S. (2002). Underestimating costs in public works projects: Error or lie? Journal of the American Planning Association, 68(3), 279-295.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。