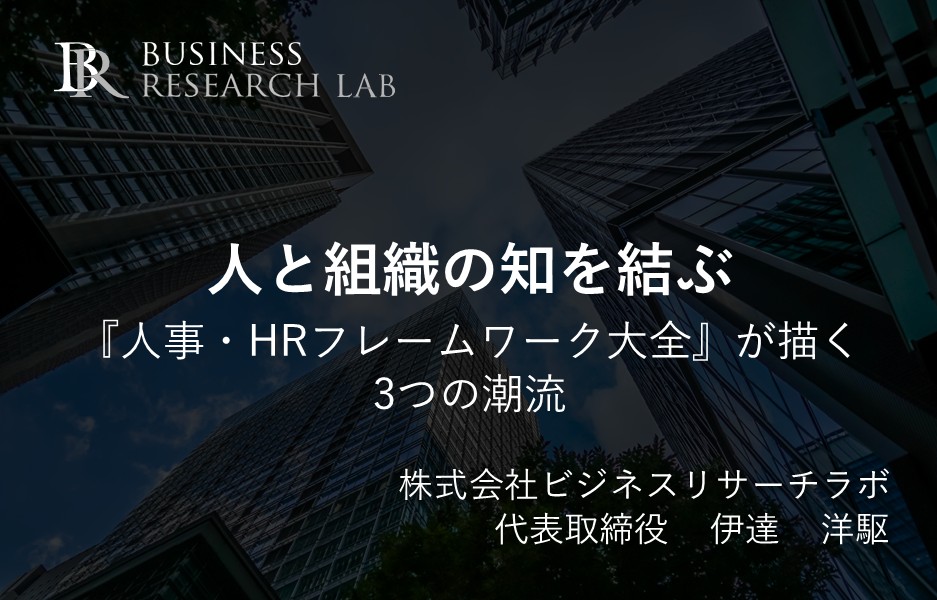2025年10月24日
人と組織の知を結ぶ:『人事・HRフレームワーク大全』が描く3つの潮流
人と組織をめぐる問題は複雑です。一つの課題を解決したかと思えば、別の場所から新たな問題が顔を出す。その連続に、私たちは日々向き合っています。こうした状況において、個別の施策やテクニックといった点の知識だけでは、根本的な解決に至らないケースが増えているのではないでしょうか。必要なのは、目の前の事象に振り回されるのではなく、問題の全体像を俯瞰するための「知の地図」です。
かつて多くの管理職が頼りにしてきた「勘」や「経験」は、今もなお重要な役割を果たします。しかし、市場環境の変動は激しく、働き方や従業員の価値観も多様化する現代において、過去の成功体験が通用しない場面が増えているのも事実です。このような時代に求められるのは、個別の事象に対処するマネジメントではなく、問題の背後にあるメカニズムを理解し、より再現性の高い打ち手を考えるためのアプローチに他なりません。
この度上梓した『人事・HRフレームワーク大全』は、そうした背景のもと生まれました。本書は、複雑に絡み合った人と組織の現実を解き明かすための「思考のナビゲーション」として設計されています。本書に散りばめられた83のフレームワークは、それぞれが独立した道具であると同時に、それらが集まることで、人と組織という広大な領域を解き明かすための地図を描き出します。
本コラムでは、その地図の全貌を紹介することを試みます。個々のフレームワークを紹介するのではなく、それらが織りなす大きな思想の流れをたどりながら、本書がいかなる知的冒険への招待状であるかを解説します。
第一の潮流:個人の内面を科学する
人と組織の問題を考える上で、すべての起点となるのは「個人」の存在です。なぜ人はやる気を出すのか、あるいは失ってしまうのか。どうすれば自律的に能力を発揮し、成長し続けることができるのか。本書に収録されたフレームワーク群が描き出す一つ目の大きな潮流は、こうした個人の内面、すなわち「心」のメカニズムを科学的に探求しようとする試みです。
この潮流の核にあるのが、「欲求」の探求です。かつて、人の動機づけは報酬や罰といった、いわゆる「アメとムチ」による外的要因で説明されることが主流だったかもしれません。しかし、研究が進むにつれて、それだけでは人の持続的なエネルギーを説明できないことが明らかになります。
そこで登場するのが、「自己決定理論」や「基本的欲求理論」といったフレームワークです。これらの理論は、人の内側から湧き出るエネルギーの源泉として、「自律性(自分で選びたい)」「有能感(できるようになりたい)」「関係性(誰かとつながりたい)」という三つの欲求が存在することを示しました。これらの欲求が満たされるとき、人は外的報酬がなくとも自発的に行動し、高い満足感と成果を生み出す「内発的動機づけ」の状態に入ります。この視点は、管理職の役割を、部下を一方的に「管理する者」から、彼らが自律的に能力を発揮できる「環境を設計する者」へと変えることを要請します。
次に重要なテーマが、「目標と期待」です。人は目標によって行動を方向づけ、その達成可能性を信じることで最初の一歩を踏み出します。「目標設定理論」は、なぜ「明確で、少し困難な目標」が人を成長させるのかを明らかにしました。曖昧な精神論ではなく、具体的で測定可能な目標が、行動のエネルギーを集中させるのです。
「期待理論」は、私たちの行動意図が「この努力は成果につながるだろうか(期待)」、「その成果は自分にとって価値ある報酬をもたらすだろうか(道具性)」という二つの認識の連鎖によって形成されるプロセスを解き明かしました。この心理的な連鎖をいかに強固に設計できるか、そして、従業員一人ひとりが「自分ならこの仕事をやり遂げられる」という「自己効力感」をいかに育むかが、組織全体のパフォーマンスを左右します。
この潮流は「認知と感情」という、より繊細な領域へと分け入っていきます。人は合理的な計算だけで動く存在ではありません。「心理的エンパワーメント」というフレームワークは、人が仕事の「意味」を求める存在であることを教えてくれます。自分の仕事が単なる作業ではなく、組織や社会にとって価値あるものであり、自らの行動が周囲に良い影響を与えているという「感覚」が、どれほど強力な動機づけとなるかを示しています。
また、「感情イベント理論」は、職場での日々の小さな出来事、例えば上司からの一言や顧客からの感謝の言葉が、私たちの感情をどう揺さぶり、その感情の積み重ねが、組織への満足度やエンゲージメントといった長期的な態度をいかに形成していくかを明らかにします。この潮流は、人の心を科学の目で捉え、個人の活力を最大限に引き出すための原理原則を提供してくれます。
第二の潮流:組織というシステムを解剖する
個人の意欲や能力がいかに高くとも、それが発揮される舞台である「組織」というシステムに問題があれば、その力は十分に活かされません。本書が示す第二の潮流は、組織を一つの生命体、あるいは複雑なシステムとして捉え、その内部で働く「見えない力学」を可視化しようとするアプローチです。一見、個人の問題に見える現象が、実は組織の構造や文化、権力関係によって生み出されているという事実に光を当てます。
この潮流の核をなすのが、「文化と風土」の探求です。なぜ、経営層が情熱を込めて語る立派な企業理念が、現場では形骸化してしまうのでしょうか。「組織文化の構造」に関するフレームワークは、その答えが文化の深層にあることを示唆します。目に見えるオフィス環境や服装といった「人工物」、公式に語られる「価値観」のさらに奥深くには、人々の行動を無意識のうちに規定する「基本的仮定」が存在します。例えば、「失敗は許されない」という暗黙の前提が組織に根付いている限り、いくら「挑戦を奨励する」という価値観を掲げても、従業員は萎縮してしまいます。
また、「競合価値モデル」は、組織のDNAを「家族的(クラン)」か「官僚的(ヒエラルキー)」かといった四つのタイプに分類し、自社の現在地と目指すべき姿を客観視するための地図を提供します。さらに、「ASAフレームワーク」は、組織が特別な意図なくとも、なぜ次第に似たような考えの人ばかりが集まる「同質的」な集団になっていくのか、そのメカニズムを解き明かし、多様性を確保するための戦略的視点の重要性を教えてくれます。
続いて、組織を動かす現実的な力学である、「権力と意思決定」の探求へと進みます。組織は、組織図に示された公式の役職だけで動いているわけではありません。「パワーと影響力」に関するフレームワークは、専門知識、人望、あるいは重要な情報へのアクセスといった、非公式なパワーの源泉がいかに重要であるかを明らかにします。誰が影響力を持っているのかを理解することなくして、組織を動かすことはできません。
「ゴミ箱モデル」は、組織の意思決定が必ずしも合理的な分析に基づいて行われるわけではない、という現実を描き出します。問題、解決策、参加者、そして会議といった選択機会が、あたかもゴミ箱の中で偶然出会うようにして意思決定がなされるというこのモデルは、計画通りに進まないプロジェクトの背景を理解する上で、示唆に富んでいます。
この潮流は組織の根幹をなす「公正と信頼」というテーマにたどり着きます。「組織的公正」の理論は、人は「何を得たか(分配の公正)」という結果だけでなく、「その結果がどのように決められたか(手続きの公正)」というプロセスを重視することを示しています。たとえ望まない結果であったとしても、その決定過程が透明で公平であると認識できれば、組織への信頼は維持されやすいのです。
さらに、「心理的契約」という概念は、雇用契約書には書かれていない、従業員と組織の間の「暗黙の期待」の重要性を明らかにします。成長機会の提供、キャリアへの配慮、困ったときの支援といった、目に見えない約束が裏切られたとき、従業員の心は静かに組織から離れていきます。この潮流は、組織という複雑なシステムを解剖し、その健全性を保つための診断ツールを提供してくれます。
第三の潮流:変化の時代を乗りこなす
現代は、変化が常態となり、未来の予測が困難な時代です。このような環境において、個人と組織はどのように変化に適応し、持続的に成長していけば良いのでしょうか。本書が描き出す第三の潮流は、この現代的な問いに応えようとするアプローチであり、「キャリア自律」や「学習する組織」といったテーマと結びついています。
この潮流の柱の一つが、「キャリア自律」の探求です。かつてのように、企業が個人のキャリアパスを最後まで用意してくれる時代は終わりつつあります。そこで重要になるのが、自らの職業人生の舵を自分で握るための思考法です。「キャリア・アンカー」というフレームワークは、変化の荒波の中でも自分を見失わないための「錨」の重要性を説きます。自分がキャリアにおいて本当に大切にしたい価値観、例えば専門性の追求なのか、安定した生活なのか、あるいは純粋な挑戦なのかを深く理解することが、様々な意思決定の方針となります。
「計画的偶発性理論」は、キャリアは計画通りに進むものではなく、むしろ偶然の出会いや予期せぬ出来事をチャンスに変える力こそがキャリアを豊かにするという、新しいキャリア観を提示します。そして、「キャリア・アダプタビリティ」は、未来への「関心」、自律的な「統制」、未知への「好奇心」、挑戦への「自信」という四つの心理的資源を育むことで、変化に適応し続ける力を身につける方法を示します。
もう一つの柱は、「組織学習」の探求です。変化の激しい時代においては、組織自体が学び、進化し続けなければなりません。組織の学習レベルを論じたフレームワークは、既存のやり方を改善する「シングルループ学習」と、そのやり方の前提となっている価値観や目標を問い直す「ダブルループ学習」を区別します。多くの組織は前者にとどまりがちですが、真の変革は後者からしか生まれません。
では、イノベーションはどのようにして組織のDNAとなるのでしょうか。「4Iモデル」は、個人の「ひらめき(直観)」が、対話を通じてチームの共通理解として「統合」され、やがて組織の仕組みとして「制度化」されるまでのプロセスを描き出します。さらに、「両利きの経営」は、既存事業を効率化し収益を確保する「深化」の活動と、未来の成長のために新しい事業の種を探す「探索」の活動を、組織がいかに両立させるべきかという、現代企業が直面するジレンマに光を当てます。
「道具箱」から未来は始まる
ここまで、本書『人事・HRフレームワーク大全』に収録された83のフレームワークが織りなす、三つの大きな思想の潮流をたどってきました。一つは「個人」の内面に深く分け入り、その活力の源泉を探る旅。一つは「組織」というシステムを解剖し、その見えない力学を解明する旅。もう一つは、予測困難な「変化」の時代を乗りこなし、未来を創造するための旅です。
本書は、これら「個人」「組織」「変化」という三つの異なる視点から、人と組織の科学を立体的に描き出すことを目指しました。そして、これらの視点を自在に往復し、組み合わせることで、私たちは目の前で起きている問題の本質を多角的に捉えることができるようになります。
本書で紹介した83のフレームワークは、それぞれが特定の課題に有効な知識です。しかし、それらを学び、組み合わせ、使いこなしていくプロセスを通じて、皆さんの内面には、より本質的な変化が起きるはずです。それは、複雑な現実を読み解くための、皆さん自身の「思考OS」です。
思考OSが一度インストールされれば、本書の多様な活用法が見えてきます。日々の業務で課題に直面した際には、必要な項目を参照する「辞書」として。人と組織に関する知の全体像を掴みたいときには、順を追って読み進める「教科書」として。チームのメンバーと共に輪読し、議論すれば、感覚的な対立を乗り越え、建設的な対話を生み出すための「共通言語」として機能するでしょう。
しかし、忘れないでいただきたいのは、この「道具箱」は完成品ではないということです。どれほど優れた道具も、使われなければその価値を発揮しません。本書の価値は、読者の皆さんがそれぞれの現場という舞台で、これらの道具を手に取り、試し、時には失敗しながら、自分だけの使い方を見つけ出していく、そのプロセスの中にあります。
最初からすべてを完璧に使いこなす必要はありません。まずは一つで構いません。今、最も気になっている課題に対して、使えそうな道具を一つ、試してみてください。きっと、問題の背後にある構造が見え、解決への新たな一歩を踏み出す勇気が湧いてくることでしょう。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。