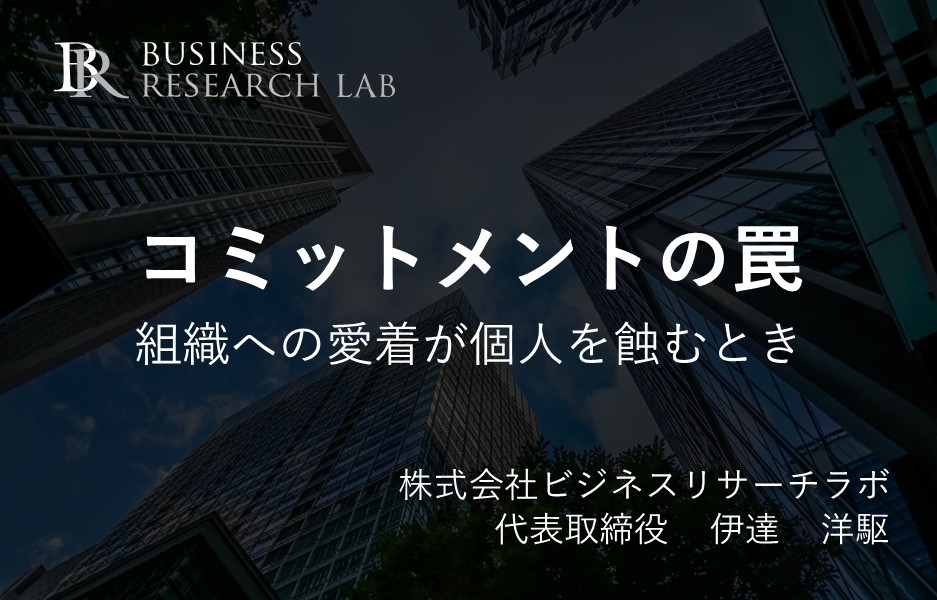2025年10月24日
コミットメントの罠:組織への愛着が個人を蝕むとき
仕事への熱意、所属する組織への忠誠心。これらは、しばしば称賛されるべき美徳として語られます。熱心に仕事に打ち込む姿は責任感の表れと見なされ、会社への愛着が強い従業員は組織の礎であると信じられています。私たちは、こうした「コミットメント」の高い状態を、個人にとっても組織にとっても望ましい姿だと、半ば無意識のうちに考えているのかもしれません。高い目標を掲げ、仲間と一丸となって邁進する。その一体感や達成感は、何物にも代えがたい充実感を与えるでしょう。
しかし、もしその熱意が、その忠誠心が、ある一線を超えてしまったとしたら、一体何が起きるのでしょうか。一つの物事に心を奪われるあまり、他のすべてが色あせて見えるようになったとしたら。組織への帰属意識が強まるあまり、外の世界が見えなくなってしまったとしたら。それは果たして、本当に「望ましい姿」であり続けるのでしょうか。
本コラムでは、これまで光が当てられることの少なかった「コミットメントの弊害」という側面に光を当てます。仕事や組織への「行き過ぎた想い」が、知らず知らずのうちに私たちの心身を蝕み、組織の活力を奪っていく過程を、いくつかの学術的な知見を頼りに解き明かしていきます。これは、単に熱意を否定するものではありません。むしろ、私たちが大切にしているはずのその熱意が、なぜ、そしてどのようにして、個人と組織にとっての重荷へと変貌してしまうのか。その複雑で皮肉なメカニズムを探ります。
過度なコミットメントは健康と組織革新を阻む
仕事への献身や組織への愛着といった概念を考えるとき、私たちはそれを一つの塊として捉えがちです。しかし、この複雑な心理状態を理解するためには、少し解きほぐして見る必要があります[1]。
一つは「ジョブ・インボルブメント」と呼ばれるもので、これは個人にとって「仕事」が自分を定義する上でどれほど中心的な位置を占めているか、という度合いを指します。自身のアイデンティティの核に仕事があり、他の生活領域、例えば家庭や趣味、地域社会での活動などと比べて、仕事に強い心理的な重きを置いている状態です。もう一つは「組織愛着」であり、これは従業員が所属する組織の目標や価値観を自分自身のものとして受け入れ、その一員であり続けたいと願う気持ちの強さを示します。
これら二つの気持ちは、適度な範囲であれば、個人の働きがいや組織の生産性を高める力となり得ます。問題は、この関与と愛着が「過剰」になったときに生じます。これまで善とされてきたものが、その強度を増すことによって、個人と組織の両面に深刻な影を落とし始めるということです。
組織の側面から見てみましょう。過剰なコミットメントは組織の「柔軟性」を損ないます。従業員が既存の方針や過去の成功体験に固執するようになると、組織全体が変化に対して臆病になります。かつて成功したプロジェクトに多大な時間と労力を注ぎ込んできた人々にとって、その方針を転換することは、自らの過去の努力を否定するような痛みを伴います。市場環境が変わり、戦略の見直しが必要な局面においても、「ここまで投資したのだから」という論理がまかり通り、誤った道を進み続けてしまいます。
次に、組織内での「同調圧力」が強まります。組織への忠誠心が高い人々が集まると、組織の決定や主流派の意見に異を唱えることが裏切り行為であるかのような空気が醸成されることがあります。多様な視点や健全な批判精神は封じ込められ、意思決定の質が劣化します。波風を立てることを恐れ、異論を飲み込むようになると、集団全体が思考停止に陥ります。
さらに、行き過ぎた忠誠心が「倫理観の麻痺」を引き起こす危険性もあります。組織の目的を絶対視するあまり、その目的達成のためならば手段を問わないという思考に陥るかもしれません。組織への強い一体感が、かえって社会的な規範からの逸脱を正当化する論理を生み出してしまうのです。
こうした組織では「人的資源の硬直化」も進みます。採用の場面で、自社の価値観に合致する人材ばかりを求めると、組織は均質な集団と化します。価値観の多様性が失われれば、新しい発想や創造性が生まれる機会は減少し、環境の変化に適応していく力も徐々に削がれていくでしょう。
一方で、個人に目を転じると、その代償はより切実なものとなります。分かりやすいのは、「ワーク・ファミリー・コンフリクト」とそれに伴う「社会的孤立」です。過剰に仕事にのめり込む人は、必然的に長時間労働に陥りやすくなります。平日の夜や休日まで仕事のことを考え、手を動かす生活が続けば、家族と食卓を囲む時間や、友人と語らう機会は失われます。人間関係が職場中心に偏り、いざという時に頼れる社会的な支えを失い、孤立を深めていくことになります。
心身の健康へのダメージも考えられます。仕事への過剰なコミットメントは、「ストレス反応」や「バーンアウト」の温床です。
個人の「キャリア柔軟性の低下」という問題もあげられます。一つの組織に深くコミットしすぎると、心理的な「しがらみ」が強くなり、他の選択肢に目を向けることが困難になります。たとえより良い成長の機会が外部にあったとしても、転職や異動を決断できず、自身の長期的なキャリアの可能性を狭めてしまうことにもなりかねません。
高すぎるコミットメントは成果低下と疲弊を生む
先ほどは、過剰なコミットメントが組織と個人の双方に、いかに広範な弊害をもたらしうるかを見てきました。それは、まるでアクセルを踏み込みすぎた車がコントロールを失うかのように、行き過ぎた想いが予期せぬ破綻を招く姿でした。
このことから、一つの素朴な疑問が浮かび上がります。それは、コミットメントと仕事の成果、あるいは心身の健康との関係は、本当に「高ければ高いほど良い」という、どこまでも上昇していく直線的な関係なのだろうか、という問いです。もしかしたら、そこにはある種の「最適な水準」が存在し、それを超えると、効果が薄れたり、逆効果になったりするのではないでしょうか。
この疑問に、ある研究が光を投げかけています。この研究は、カナダの長期介護施設で働く看護師や介護補助員など、日々、高い倫理観と感情的な労力を求められる人々を対象に行われました[2]。研究者たちの関心は、これまで多くの人々が信じてきた「コミットメントが強まるほど、業績は上がり、燃え尽きは減る」という単純な比例関係を疑い、その関係性がもっと複雑な、曲線を描くものではないかを検証することにありました。
具体的には、コミットメントがある一定のレベルまでは良い結果をもたらすものの、それを超えると逆にパフォーマンスが低下する「逆U字」型の関係や、あるレベルを超えると逆に燃え尽きが深刻化する「U字」型の関係が存在するのではないか、という仮説を立てました。
この仮説の背景には、いくつかの理論的な考え方があります。一つは、人は自分が投じた努力に対して、見合った報酬(給与のような金銭的なものだけでなく、承認や達成感、成長の機会といった精神的なものも含みます)が得られないと感じると、心身の資源が枯渇してしまう、という考え方です。過剰なコミットメントを持つ人は、組織や患者のために膨大なエネルギーを注ぎ込みますが、その努力が必ずしも報われるとは限りません。努力と報酬のバランスが崩れたとき、その熱意は空回りし始め、やがては心身の疲弊やパフォーマンスの低下につながるのではないか、と考えられます。
調査では、従業員たちが誰に対して強い愛着を感じているか(組織、上司、同僚、患者という四つの対象)、そしてその愛着の強さが、日々の仕事の成果や燃え尽きの度合いとどのように関連しているかが分析されました。
仕事の成果は、契約で定められた職務をどれだけこなしているかという「役割内パフォーマンス」と、職務内容を超えて組織に貢献する「組織市民行動」で測定されました。燃え尽きの度合いは、感情がすり減ってしまう「情緒的消耗」、仕事に対して皮肉な見方をするようになる「シニシズム」、そして自分の能力に自信を持てるかという「職務効力感」といった側面から捉えられました。
分析の結果、非常に示唆に富む関係性が見えてきました。決められた職務をこなす「役割内パフォーマンス」や、自分の仕事に自信を持つ「職務効力感」については、研究者たちの予測通り、組織や患者へのコミットメントとの間に「逆U字」の関係が確認されました。組織や患者への愛着が平均的なレベルに達するまでは、確かに仕事の成果や自信を高める方向に働くものの、そのレベルを超えて極端に高くなると、逆に成果が頭打ちになり、低下し始めることを意味します。ひたむきな想いも、度を超すとパフォーマンスの足かせになりうる、というわけです。
仕事に対して皮肉な見方をする「シニシズム」に関しても、同様に曲線関係が見出されました。こちらは「U字」型で、組織や患者へのコミットメントが非常に低い場合と、逆に極端に高い場合に、シニシズムが強まるという結果でした。コミットメントが高すぎることが、かえって物事を斜めに見てしまう態度につながるというのは、一見すると矛盾しているように思えるかもしれません。しかし、これは過剰な期待が裏切られたときの反動と解釈できます。組織や患者に深く献身しているからこそ、理想と現実のギャップに直面した際の失望も大きく、それが皮肉な態度として表出してしまうのでしょう。
一方で、職務内容を超えた貢献である「組織市民行動」や、感情のすり減りである「情緒的消耗」については、このようなはっきりとした曲線関係は見られませんでした。
研究者たちは、この曲線関係のメカニズムを、やはり「努力と報酬の不均衡」という観点から説明しています。組織や患者へのコミットメントが極端に高い従業員は、自分の時間や感情といった資源を惜しみなく注ぎ込みます。しかし、組織や患者がその莫大な貢献に対して、常に見合った報酬を返し続けることは困難です。この埋めがたいギャップが、次第に「これだけやっているのに報われない」という潜在的な不満や資源の枯渇感を生み、パフォーマンスの低下やシニシズムの増大という形で現れる、と考えられます。
高いコミットメントが無礼後の怒り・罪悪感を増幅する
これまでの議論で、過剰なコミットメントが平常時においてさえ、個人のパフォーマンスや組織の健全性を損なう可能性があることを見てきました。熱意という内なる炎が、時として自らを焼き尽くす燃料となりうるのです。では、この炎は、外部からの予期せぬ出来事、例えば職場で受けるネガティブな仕打ちに対して、どのように反応するのでしょうか。特に、組織への愛着が人一倍強い従業員は、そうした逆境に対して、より強く、あるいはより脆く反応するのでしょうか。ここでは、コミットメントが持つもう一つの側面、すなわちストレスに対する「脆弱性」に光を当てた研究を紹介します[3]。
この研究が焦点を当てたのは、「インシビリティ」と呼ばれる現象です。これは、はっきりとした敵意や攻撃の意図があるわけではないものの、相手を軽んじたり、無神経に扱ったりする、比較的強度の低い無礼な言動を指します。例えば、挨拶をしても無視される、会議で発言を遮られる、重要な情報から意図的に外される、といった日常的に起こりうる些細な出来事がこれにあたります。一つ一つは小さな棘のようですが、繰り返し経験することで、人の心に深く突き刺さり、大きなストレスとなり得ることが知られています。
研究者たちが解明しようとしたのは、二つの大きな問いでした。第一に、こうした無礼な行為を受けたとき、人はどのような感情を抱き、それが仕事への態度や行動にどう結びついていくのか。第二に、そしてこれが本コラムのテーマと関わる点ですが、組織へのコミットメントが高い従業員は、無礼な行為に対して、より強い感情的な反応を経験するのではないか、という問いです。組織を愛する気持ちが、かえって職場の無礼に対する心の傷つきやすさを増幅させてしまうのではないか、という仮説を検証しようとしました。
この問いに答えるため、研究者たちは二段階にわたる調査を行いました。最初の調査では、米国の働く女性たちを対象に、職場で無礼な行為を経験する頻度と、それによって引き起こされるネガティブな感情全般、そして仕事への意欲や職場からの心理的な離脱との関係が調べられました。さらに、組織へのコミットメントの高さが、無礼な行為とネガティブな感情との結びつきを強めるかどうかについても分析されました。
その結果は、仮説を裏付けるものでした。職場で無礼な行為を経験する頻度が高い人ほど、より多くのネガティブな感情を抱えていることが確認されました。そして、ここが重要な点ですが、この結びつきは、組織へのコミットメントが高い人々の間で、より一層強くなっていました。組織への想いが強い人ほど、些細な無礼によって心が大きく揺さぶられ、ネガティブな感情の渦に巻き込まれやすいという現実が浮かび上がりました。
研究者たちは、この発見をさらに掘り下げるため、二つ目の調査を実施しました。今度は、対象を全米の働く男女とその同僚に広げ、引き起こされる感情を「怒り」と「罪悪感」という二つの感情に分けて分析しました。怒りは他者に向かう攻撃的な感情であり、罪悪感は自らを責める内向きの感情です。この二つの異なる感情が、無礼な行為の後にそれぞれどのように生じ、個人の自尊心や他者から見た仕事の成果にどうつながるのかを追跡したのです。
ここでも、興味深い結果が得られました。無礼な行為が「怒り」と「罪悪感」の両方を引き起こすことが改めて確認されました。そして、組織へのコミットメントの役割に目を向けると、コミットメントが高い人ほど、無礼な行為を経験した後に、より強い「罪悪感」を抱く傾向があることが明らかになりました。一方で、「怒り」の強さに関しては、コミットメントの高さによる違いは見られませんでした。組織を深く愛する人ほど、無礼な扱いを受けたときに「相手が悪い」と怒るよりも、「自分が何か悪かったのではないか」と自らを責めてしまう傾向が強い、ということが示されたということです。
引き起こされた感情がもたらす結末にも違いが見られました。「怒り」は、仕事への意欲の低下や、その職場を辞めたいという気持ちに結びつきやすいのに対し、「罪悪感」は、自尊心の低下や、同僚から評価される客観的な仕事のパフォーマンスの低下に結びついていました。
なぜ、組織へのコミットメントが高い人ほど、無礼に対して罪悪感を抱きやすいのでしょうか。このメカニズムは、「社会的アイデンティティ」という考え方で説明できます。
組織へのコミットメントが高い人は、組織と自分自身を強く同一視しています。「会社の成功は自分の成功」であり、「会社の失敗は自分の失敗」と感じるのです。そのため、自分が所属し、愛着を持っている組織の中で無礼な行為というネガティブな出来事が起きると、それを自分自身の価値が否定されたかのように感じてしまいます。その不快な状況を理解しようとするあまり、「もしかしたら自分に至らない点があったから、あのような扱いを受けたのかもしれない」という自己批判的な思考に陥り、罪悪感を抱きやすくなります。
脚注
[1] O’Driscoll, M. P. (1989). Over-commitment to the job and the organisation: Implications of excessive job involvement and organisational attachment. New Zealand Journal of Industrial Relations, 14, 169-177.
[2] Morin, A. J. S., Vandenberghe, C., Turmel, M.-J., Madore, I., and Maiano, C. (2013). Probing into commitment’s nonlinear relationships to work outcomes. Journal of Managerial Psychology, 28(2), 202-223.
[3] Kabat-Farr, D., Cortina, L. M., and Marchiondo, L. A. (2018). The emotional aftermath of incivility: Anger, guilt, and the role of organizational commitment. International Journal of Stress Management, 25(2), 109-128.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。