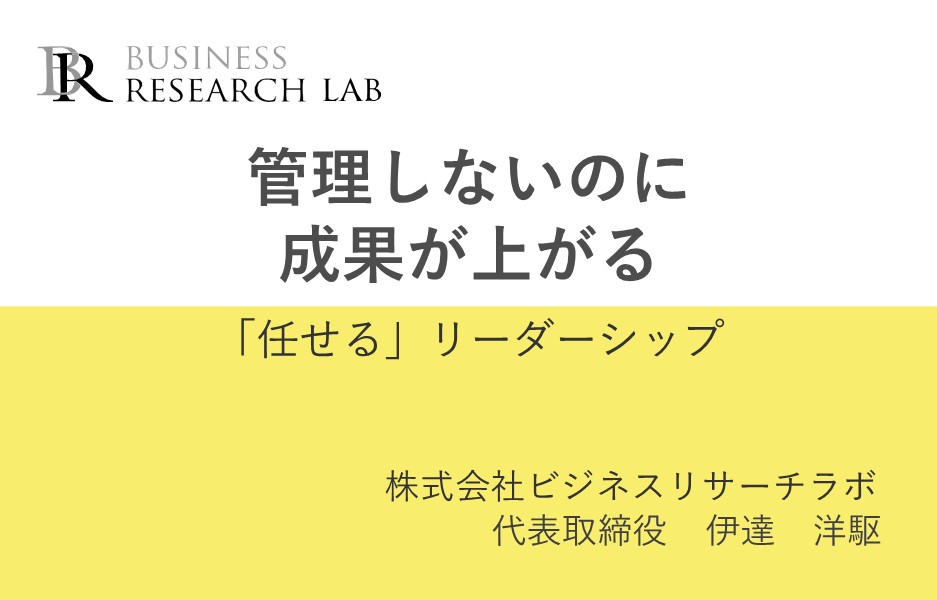2025年10月23日
管理しないのに成果が上がる:「任せる」リーダーシップ
トップダウン型、つまり上司が一方的に指示し、部下がそれに従うだけの画一的なマネジメントは、変化の激しいビジネス環境においてはなかなか通用しません。市場は複雑化し、顧客のニーズは多様化の一途をたどっています。
このような時代において、組織が生き残り、成長し続けるためには、現場の最前線にいる一人ひとりの知恵や工夫、そして迅速な判断が不可欠です。組織構造もフラット化が進み、個々の従業員が価値創造の主役となる時代になった今、管理者に求められる役割は変わりつつあります。それは、部下を細かく管理・統制する「監督者」ではなく、彼ら彼女らの持つ潜在能力を引き出し、開花させる「支援者」としての役割です。
こうした背景から生まれたのが、部下に積極的に権限を委ね、自律的な判断と行動を促す新しいリーダー像、「エンパワーメント・リーダーシップ」です。このリーダーシップは、部下の「やらされ感」を「自ら挑戦したい」という内発的な意欲へと転換させ、個人の創造性やチーム全体への協力的な姿勢を高める力を持っています。
しかし、その重要性が叫ばれる一方で、「具体的にどのような行動が、部下の心にどう響き、成果に結びつくのか」というメカニズムは、これまで経験則で語られることが多く、科学的には十分に解明されていませんでした。近年の精力的な研究によって、リーダーの特定の行動が部下の心理にどのような変化をもたらし、最終的に組織のパフォーマンス向上へとつながっていくのか、その道のりが少しずつ見えてきています。本コラムでは、研究成果を基に、このエンパワーメント・リーダーシップの謎を解き明かしていきます。
リーダーの「6つの行動」が部下の意欲と満足の鍵だった
「部下のやる気を引き出す(エンパワーメントする)」という考え方は多くの企業で語られてきましたが、そのためにリーダーが何をすべきか、明確な指針は長い間ありませんでした。この問いに答えるため、ある研究が、リーダーが実践すべき行動を体系化し、その効果を明らかにしようと試みました[1]。
研究者たちが注目したのは、「この仕事には価値がある」「自分ならできる」といった、部下の仕事に対する前向きな気持ち(心理的エンパワーメント)です。リーダーの行動がこの気持ちを高める鍵だと考え、現場のリーダーたちの行動を分析。その結果、「①権限を委ねる」「②求める成果を明確にする」「③自律的な意思決定を促す」「④仕事に必要な情報を共有する」「⑤能力開発を支援する」「⑥失敗を学びと捉え、挑戦を促す(コーチング)」という6つの行動が浮かび上がりました。とりわけ、部下が安心して実力を発揮できるよう、知識やスキルの土台を整える「情報共有」や「能力開発支援」、そして挑戦を奨励する「コーチング」が重要だとされました。
この6つの行動が本当に有効なのかを確かめるため、ある大手企業の管理職424名に対し、その部下1,309名が評価を行う調査が実施されました。統計的な分析の結果、この6つの行動は、部下のやる気を測る上で信頼性が高いことが確認されました。
さらに、米国企業84名を対象とした第二の調査では、これらのリーダーの行動が、部下の「心理的エンパワーメント」「仕事への満足度」「組織への愛着(組織コミットメント)」にどう影響するかが調べられました。分析の結果、リーダーの6つの行動は、これら部下のポジティブな気持ちや態度と強い関係があることが判明。特に「権限委譲」は仕事の満足度と非常に強く結びついていました。
さらに詳しい分析で、リーダーの行動が「心理的エンパワーメント」という心の状態を「経由して」、仕事の満足度や組織への愛着につながっているという、心のメカニズムが実証されました。この研究は、リーダーが示すべき行動と、それが部下の心に火をつけ、前向きな仕事ぶりにつながる道筋を明確にし、リーダー育成の確かな指針となりました。
「自主性の尊重」と「成長の後押し」が成果を生む
先の研究成果を土台に、エンパワーメント・リーダーシップを測る「ものさし」を、より正確で使いやすいものにするための研究が進められました。知識やアイデアが競争力の源泉となる現代、部下に権限を与えるリーダーシップへの関心は高まる一方でしたが、その概念や測定方法にはまだ曖昧な点が残っていました。
新しい研究では、エンパワーメント・リーダーシップの概念を改めて整理し、信頼性の高い測定尺度を開発することを目指しました[2]。過去の文献を調べ、リーダーの行動は「権限の共有」「やる気の支援」「成長の支援」という3つのプロセスと、それに紐づく8つの行動にまとめられる、と理論的に整理されました。これらの行動が、部下の自律性や内発的な意欲、そして「自ら考え行動する力(セルフリーダーシップ)」を高めると考えられたのです。
尺度開発は3段階にわたる調査で進められました。第一の研究では、317名の部下と86名の上司のデータを分析し、リーダーの様々な行動の中から要素を探りました。その結果、リーダーの行動は大きく分けて「部下の自主性を尊重し、任せる(自律支援)」と「成長を後押しする(能力開発支援)」という2つの柱に集約されることが分かりました。この2つの柱で構成された新しい尺度は、統計的に信頼性が高いものでした。
この「自律支援」と「能力開発支援」の両方が、部下の仕事への満足度と、仕事にかける熱意(ワークエフォート)を共に高めることが確認されました。さらに、リーダーの支援が部下の「セルフリーダーシップ」を高め、それが最終的に上司から評価される「業績」につながる、という好循環の存在も明らかになりました。
第二の研究では、別の企業のデータでこの2つの柱からなる尺度の有効性を再検証。結果は同様に良好で、この尺度が安定して使えるものであることが証明されました。また、この研究ではリーダーの支援が部下の「心理的エンパワーメント」を高め、それが「創造性」の発揮につながるという効果も示されました。
第三の研究では、831名の従業員を対象に、この新しい尺度が、既存の他のリーダーシップ尺度(例えば、リーダーとメンバーの信頼関係に着目する理論など)とどう違うのかが検証されました。分析の結果、エンパワーメント・リーダーシップは、他のリーダーシップ論では説明しきれない、部下の「心理的エンパワーメント」を高める独自の効果を持つ、最も強力な要因であることが実証されました。
この一連の研究は、リーダーが「自主性の尊重」と「成長の後押し」という2軸で部下に関わることが、個人の成長と組織の成果の両方につながることを力強く示しました。
チームを成功に導くリーダーの「5つの行動」
1990年代以降、多くの企業が階層型の組織から、メンバー一人ひとりが自律的に動く「チーム制」へと移行を進めてきました。しかし、そうしたチームを効果的に率いるために、リーダーは何をすべきなのか、その答えは明確ではありませんでした。特に、チームの一員ではないながらも、外からチームを導き、支援するリーダーの行動を体系化し、誰もが測れる形にすることが急務でした。
この課題を解明するため、研究者たちは3つの段階的なアプローチを取りました[3]。初めに、様々な企業のリーダーとチームメンバーに直接インタビューを行い、「うまくいった時」「いかなかった時」のリーダーの具体的な行動例を数多く収集。そこから125の行動パターンを抽出し、内容を分析して8つのカテゴリーに分類しました。
続いて、このインタビューから得られた知見を基にアンケート項目を作成し、複数の企業で量的調査を実施。統計分析の結果、チームを成功に導くリーダーの行動は、5つの要素にまとめられることが分かりました。最終段階として、さらに多くの企業からデータを集めて再検証したところ、この5つの要素からなるモデルが非常に安定しており、信頼性が高いことが確認されました。
その5つの行動とは、①「模範を示す」:リーダー自らが手本となり、高い基準で仕事に取り組む姿勢を見せること。②「コーチング」:答えを教えるのではなく、メンバーが自ら考え、成長できるよう問いかけ、支援すること。③「参加型の意思決定」:リーダーが独断で決めず、チームの意見を積極的に取り入れ、決定に反映させること。④「情報共有」:会社の目標や方針、なぜその決定がなされたのかという背景まで、丁寧に説明し共有すること。⑤「メンバーへの配慮」:一人ひとりの状態や人間関係に気を配り、継続的に対話の機会を持つことです。
この5つの行動は、部下の「自分ならできる」という自信を高め、精神的に支え、必要な情報を提供するという心理的なメカニズムに合致しています。それは、従来の「指示・統制」によって部下を動かすのではなく、リーダーが「統制」の主導権をチーム自身に渡し、メンバーの力を引き出すための具体的な行動リストを示したものと言えるでしょう。
なぜエンパワーメント・リーダーは信頼され、創造性を引き出すのか
これまで個別に見てきたエンパワーメント・リーダーシップの効果を、より大きな視点で統合し、「本当に効果があるのか」「なぜ効果があるのか」を検証する必要がありました。組織の階層が少なくなり、部下の自律性がますます重要になる中で、その効果を科学的に検証し、どんな条件で機能するのか、その仕組みは何かを体系的に解き明かすことが求められていたのです。
この課題に答えるため、過去に行われた膨大な研究成果を集めて統合・分析する「メタ分析」という手法が用いられました[4]。厳しい基準で選ばれた89件の文献(105の独立した調査データ)を分析対象とし、未発表の研究も加えることで、世に出やすい研究だけに偏るリスクを避けました。分析では、個々の研究のバラつきを統計的に調整し、より信頼性の高い結論を導き出しました。
分析の前提として、「権限を委ねる」「やる気を支える」「成長を後押しする」というリーダーの3つの行動が、部下の「心理的エンパワーメント」を高め、成果につながるという仮説を立てました。また、リーダーへの「信頼」や良好な関係性も、その効果を後押しする要因になると考えました。さらに、組織の文化や、部下の在籍期間などが、効果の現れ方にどう影響するかも検証しました。
分析の結果、エンパワーメント・リーダーシップは、個人の「業務成果(タスク・パフォーマンス)」はもちろん、「自発的な協力行動(組織市民行動)」や「創造性」と関係していることが確認されました。特に、決められた業務をこなす力よりも、自ら進んで組織に貢献したり、新しいアイデアを生み出したりする力と、より強い結びつきが見られたのです。この傾向は、個人レベルだけでなくチームレベルでも同様でした。
どのような条件で効果が変わるかの分析では、興味深い結果が得られました。例えば、部下の在籍期間が短いほど、エンパワーメント・リーダーシップの効果は大きいことが分かりました。これは、キャリアの初期段階で自律性を促す関わりが特に重要であることを示唆しています。
また、他の有名なリーダーシップ論と比較しても、エンパワーメント・リーダーシップの独自性が証明されました。他のリーダーシップの効果を差し引いてもなお、エンパワーメント・リーダーシップは「自発的な協力行動」「創造性」「心理的エンパワーメント」に対して、独自にプラスの影響を与えていたのです。ただし、基本的な業務成果への直接的な上乗せ効果は見られませんでした。
最後に、なぜ効果があるのかというメカニズムについては、「心理的エンパワーメント」と「リーダーへの信頼」が、リーダーの行動と部下の成果をつなぐ架け橋になっていることが明らかになりました。特に、自発的な協力行動に対しては、「信頼」のルートが最も強く影響していました。
この包括的な分析が示したのは、エンパワーメント・リーダーシップが、他のリーダーシップと重なる部分を持ちつつも、特にこれからの時代に求められる「創造性」や「自発的な協力」といった側面、そしてそれを支える「内なる意欲」に、他にはない独自の影響力を持つということです。
脚注
[1] Konczak, L. J., Stelly, D. J., and Trusty, M. L. (2000). Defining and measuring empowering leader behaviors: Development of an upward feedback instrument. Educational and Psychological Measurement, 60(2), 301-313.
[2] Amundsen, S., and Martinsen, O. L. (2014). Empowering leadership: Construct clarification, conceptualization, and validation of a new scale. The Leadership Quarterly, 25(3), 487-511.
[3] Arnold, J. A., Arad, S., Rhoades, J. A., and Drasgow, F. (2000). The empowering leadership questionnaire: The construction and validation of a new scale for measuring leader behaviors. Journal of Organizational Behavior, 21(3), 249-269.
[4] Lee, A., Willis, S., and Tian, A. W. (2017). Empowering leadership: A meta-analytic examination of incremental contribution, mediation, and moderation. Journal of Organizational Behavior, 1-20.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。