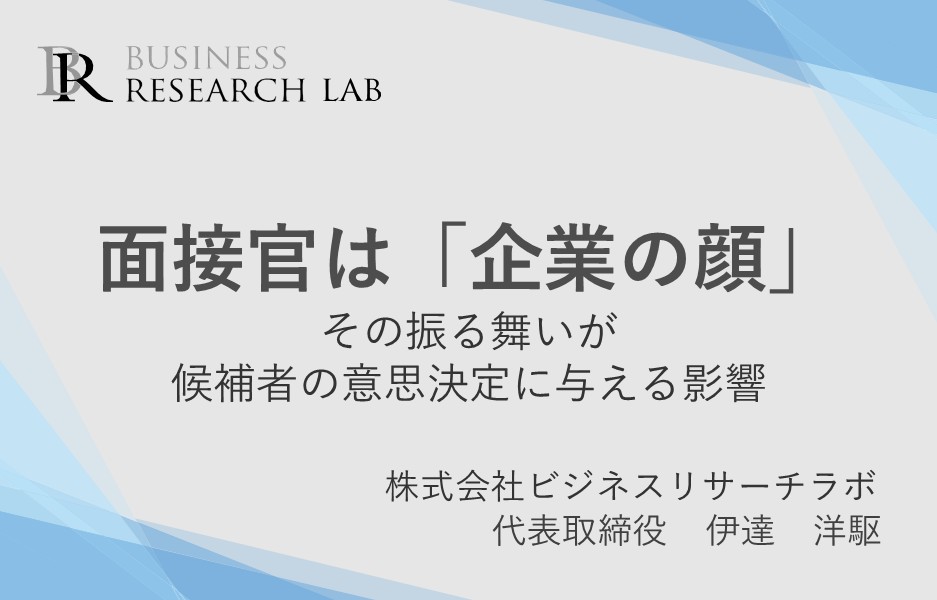2025年10月23日
面接官は「企業の顔」:その振る舞いが候補者の意思決定に与える影響
採用プロセスにおいて、面接は企業と候補者の双方にとって重要な意味を持ちます。企業側は優秀な人材を見極めたいと考え、候補者側は自分に合った職場を見つけたいと願っています。しかし、面接は単なる選抜の場ではありません。候補者が企業に対して抱く印象や入社への意欲は、面接での体験によって左右されるのです。
これまで多くの研究者が、面接における様々な要素が候補者の心理にどのような変化をもたらすかを調査してきました。その結果、例えば、面接官とのコミュニケーションの質、提供される情報の豊富さ、候補者への関心の示し方、面接の公正性などが、候補者の企業に対する魅力度や入社意欲に関わることが明らかになっています。
本コラムでは、こうした研究成果を通じて、面接がいかに候補者の意思決定に影響を及ぼすかを見ていきます。面接の品質が候補者の満足度を左右し、企業の魅力度や入社意図にまで波及していく仕組みを、実証的なデータとともに理解していきましょう。
面接満足度が求人魅力度と入社意図を左右する
採用面接における候補者の体験が、その後の企業評価や入社意欲にどのような変化をもたらすかを調べた研究があります[1]。この研究では、面接全体のコミュニケーション満足度という指標を用いて、面接体験の質が候補者の意思決定に及ぼす影響を分析しました。
調査は、アメリカの州立大学のキャリアセンターで実施された学部生向けの企業面接を対象に行われました。研究者たちは121名の候補者に対して、面接の前後で調査を実施するという縦断的な手法を採用しました。面接前には、その企業に対する魅力度と入社意図を測定し、面接直後には同じ項目に加えて、面接中のコミュニケーション満足度を調べました。
コミュニケーション満足度は、話題の意義深さ、会話の滑らかさ、面接官による候補者理解の程度、提供される情報の有用性など、面接での対話の総合的な品質を評価する指標です。候補者が感じた面接体験の質を数値化しました。
研究の結果、面接前の企業に対する印象と面接中のコミュニケーション体験は、候補者の中で区別されていることが判明しました。面接前に企業に対して抱いていた魅力度は、面接中のコミュニケーション満足度をほとんど予測できませんでした。候補者が面接前の企業情報と実際の面接体験を別々のものとして捉えていることを意味します。
一方で、面接中のコミュニケーション満足度が面接後の企業魅力度に及ぼす効果は顕著でした。面接前の企業魅力度を統計的に制御した上でも、コミュニケーション満足度は面接後の企業魅力度を説明していました。入社意図についても同様の結果が得られました。面接前の入社意図と面接後の企業魅力度を考慮してもなお、コミュニケーション満足度は入社意図を独自に説明しました。
これらの発見は、面接が単なる情報収集の場ではなく、候補者の企業に対する認識を変える力を持っていることを物語っています。面接官との対話の質、相互理解の深さ、情報提供の仕方といった要素が組み合わさって、候補者の心に残る体験を作り出します。そして、その体験が、候補者の意思決定を左右する要因となるのです。
面接後魅力は仕事内容が鍵、評判は期待ギャップで低下も
企業の評判、仕事の内容、面接官の行動という三つの要素が、候補者の企業に対する魅力度をどのように形成するかを探った研究を紹介しましょう。この調査は、アメリカ中西部の州立大学で実施された2,250件の面接のうち、前後の調査データがそろった361件を対象に高度な統計手法を用いて分析されました[2]。
研究では、候補者が面接前後に感じる企業魅力度の変化を追跡しました。測定項目には、支援的な職場環境、企業の特性、報酬や昇進の機会、挑戦的な仕事内容、勤務地といった仕事や組織に関する属性が含まれていました。面接官の行動については、親しみやすさ、専門性の欠如、情報提供やセリングの程度、面接の構造化レベルという四つの側面から評価されました。
分析の結果、仕事や組織の属性が面接後の企業魅力度に及ぼす効果は大きく、強い正の関係が確認されました。候補者が面接を通じて得た仕事内容や職場環境に関する情報が、企業への魅力度を決定する要因であることを示しています。中でも、支援的な職場環境、挑戦的な仕事、勤務地に関する情報は、候補者の心に強く響くことが明らかになりました。
一方、面接官の行動が企業魅力度に直接的に与える効果は統計的に有意ではありませんでした。しかし、面接官の行動は仕事や組織の属性の認知を通じて間接的に魅力度に影響を及ぼしていました。親しみやすさや情報提供はプラスの効果を、専門性の欠如はマイナスの効果を生み出しました。これは、面接官の振る舞いが候補者の情報処理に色づけを与え、企業評価を左右することを意味しています。
企業評判が面接後の魅力度に負の直接効果を示したのは驚きです。評判の高い企業ほど面接後に魅力度が下がるという、一見矛盾した結果です。研究者たちは、この現象を期待と現実のギャップで説明しています。評判の高い企業に対して候補者が抱く期待は高く、実際の面接体験がその期待を下回った場合、相対的に魅力度が低下してしまうのです。
このメカニズムは、心理学でいうヘドニック適応や対比効果の概念と関連しています。人は高い期待を持っているとき、それを満たすだけでは満足感を得にくく、期待を上回る体験があって初めて魅力を感じます。逆に、期待が高すぎると、客観的には良い体験であっても物足りなさを感じてしまいます。
企業評判は、仕事や組織の属性認知および面接官行動の評価に正の効果を与えていました。これは、評判の良い企業の面接では、候補者が提供される情報をより肯定的に解釈し、面接官の行動もより好意的に受け取る傾向があることを示しています。このような認知バイアスは、ブランド効果として知られる現象の一種です。
面接後の企業魅力度を強く予測したのは、実は面接前の魅力度でした。これは第一印象の持続性を表しており、面接体験による変化はあるものの、初期の印象が根強く残ることを示しています。しかし、面接体験そのものも魅力度の変化に実質的な寄与をしており、適切な面接設計によって候補者の印象を改善する余地があることも同時に示されています。
情報豊富な面接が公正感と入社意向を強め企業の魅力を高める
面接における公正性の知覚が候補者の態度や行動にどのような変化をもたらすかを調べた研究では、個人の特性、面接官の行動、そして組織からの支援感が絡み合いながら、候補者の意思決定プロセスを形成していく様子が描き出されました。
この調査は、ギリシャの国立大学卒業生ネットワークを通じて実施され、直近3か月以内に採用面接を経験した238名の実際の候補者を対象としました[3]。すべての参加者に最新の面接体験を思い起こしながら回答してもらいました。
研究で測定された変数は多岐にわたりました。候補者の個人特性として、自己評価の肯定性を表すコア・セルフ・エバリュエーションと、積極的な行動傾向を示すプロアクティビティが評価されました。面接官の特性については、親しみやすさ、専門性、情報提供の充実度という三つの側面から測定されました。そして、面接の公正性、組織からの支援感、組織や仕事への魅力度、入社に向けた行動意図が結果変数として扱われました。
分析の結果、個人特性が公正性の知覚に及ぼす効果には興味深いパターンが見られました。自己評価の肯定性が高い候補者ほど面接を公正だと感じる傾向が確認された一方で、積極的な行動傾向は公正性の知覚と有意な関係を示しませんでした。自分自身に対して肯定的な評価を持つ人が、他者との相互作用においても良好な体験を得やすいことを示唆しています。
面接官の三つの特性すべてが、候補者の行動意図や魅力度に効果を発揮しました。統制変数を考慮した上で、面接官特性の投入により行動意図の説明力が19%、仕事への魅力度が9%、組織への魅力度が28%向上しました。この中でも、情報提供の充実度が三つのアウトカムすべてに一貫して有意な効果を示したことは、面接における情報交換の重要性を浮き彫りにしています。
親しみやすさは行動意図と組織魅力度に、専門性は組織魅力度に、それぞれ独自の寄与をしていました。これらの結果は、面接官が候補者に対して提供する情報の量と質が、候補者の意思決定において決定的な役割を果たすことを示しています。同時に、面接官の人間的な温かさや専門的な能力も、候補者が組織に対して抱くイメージの形成に寄与していることがわかります。
公正性の知覚と組織からの支援感の間には、中程度から強い正の相関が観察されました。面接で公正な扱いを受けたと感じる候補者ほど、その組織が自分を支援してくれるだろうという期待を抱くことを意味しています。この支援感は、公正性を統制した後でも、行動意図、仕事への魅力度、組織への魅力度のすべてに強い効果を及ぼしていました。
組織からの支援感が候補者の態度に与える影響の大きさは特筆すべきものです。公正性を統制した上で支援感を追加すると、説明力が向上しました。この結果は、面接が単なる評価の場ではなく、組織が候補者をどれだけ大切にし、支援してくれるかを伝える機会であることを表しています。
面接における情報提供の効果が一貫して現れた理由として、現実的職務予告(Realistic Job Preview)の理論が関係していると考えられます。候補者は面接を通じて、仕事の実際の内容や組織の真の姿を知りたいと願っており、そうした期待に応える情報提供が高い評価につながります。
面接官の親しみやすさが組織魅力度に与える効果は、候補者が面接官を企業の代表として捉え、その人柄から組織全体の文化や雰囲気を推測することを表しています。専門性については、面接官の能力の高さが組織のブランド価値や信頼性の認知に結びついていると解釈できます。
候補者への真摯な関心と専門的な面接が期待と魅力度を高める
ホスピタリティ業界における大学キャンパス面接を対象とした研究では、面接官の行動が候補者の内定期待と企業魅力度にどのような変化をもたらすかが調査されました[4]。この業界は深刻な人材不足と高い離職率に直面しており、効果的な採用手法の確立が急務となっている背景があります。
調査は、アメリカ北東部の大規模大学でホテルマネジメント系を専攻する学生152名を対象に実施されました。2001年春学期に受けたキャンパス面接の直後にオンラインまたは紙の調査票で回答しました。
研究者たちは、面接官の行動を分析するため、22項目からなる質問を分析にかけ、六つの行動パターンを抽出しました。これらは、候補者への関心の示し方、威圧的な態度、情報提供の充実度、面接の構造化、専門的な面接運営、セリング行動として分類されました。
候補者の評価は、企業で働くことの魅力度(バレンス)と内定を得られる可能性の期待度(エクスペクタンシー)の二つの側面から測定されました。バレンスは「この会社で働けたら光栄だ」「魅力的だ」「友人に薦める」という三項目、エクスペクタンシーは「二次面接に呼ばれる可能性」「内定を得る可能性」という二項目で構成されます。
分析の結果、面接官の行動パターンが候補者の心理に与える効果はそれなりのものでした。六つの行動因子全体で、内定期待の30%、企業魅力度の49%を説明していました。この説明力は、面接官の振る舞いが候補者の意思決定において重要な位置を占めていることを物語っています。
最も強力な効果を示したのは、候補者への関心の示し方でした。この因子は内定期待に対しても、企業魅力度に対しても関連し、すべての行動パターンの中で最大の影響力を持っていました。面接官が候補者に真摯な関心を向け、個人的な質問をしたり、応答に対して適切なフィードバックを与えたりする行動が、候補者の心に強い印象を残すことが示されました。
専門的な面接運営も企業魅力度に有意な効果を与えていました。面接の進行が組織化されており、時間管理が適切で、質問が体系的に行われることが、候補者に組織の能力の高さを印象づけることを意味しています。プロフェッショナルな面接運営は、候補者に対して「この組織はしっかりしている」「ここで働けば成長できそうだ」という信頼感を与えます。
威圧的な態度や過度な情報提供不足は、予想通り負の効果を示しましたが、その影響は限定的でした。これは、明らかに問題のある行動は候補者に悪印象を与えるものの、ポジティブな行動の方がより強い影響力を持つことを示唆しています。
面接官の属性については、行動要因ほど強い効果は見られませんでしたが、いくつかの興味深いパターンが確認されました。女性の面接官と修士学位を持つ面接官は、企業魅力度に対してわずかながらプラスの効果を示しました。ただし、これらの効果は説明力のわずかな追加にとどまり、行動要因の影響力と比べると副次的なものです。
候補者と面接官の性別の一致や出身校の一致といった類似性要因は、内定期待や企業魅力度のいずれにも統計的に有意な効果を示しませんでした。この結果は、表面的な類似性よりも、面接における実際の相互作用の質の方が候補者の評価を左右することを示しています。
この研究が明らかにしたのは、ホスピタリティ業界という競争の激しい環境においても、面接官の個人的な属性や表面的な類似性より、面接時の行動が候補者の評価を決定するという事実です。候補者に対する真摯な関心と専門的な面接運営が、内定期待と企業魅力度を同時に高める鍵となっています。
脚注
[1] Ralston, S. M., and Brady, R. (1994). The relative influence of interview communication satisfaction on applicants’ recruitment interview decisions. Journal of Business Communication, 31(1), 61-77.
[2] Turban, D. B., Forret, M. L., and Hendrickson, C. L. (1998). Applicant attraction to firms: Influences of organization reputation, job and organizational attributes, and recruiter behaviors. Journal of Vocational Behavior, 52, 24-44.
[3] Nikolaou, I., and Georgiou, K. (2018). Fairness reactions to the employment interview. Journal of Work and Organizational Psychology, 34(2), 103-111.
[4] Wildes, V. J., and Tepeci, M. (2004). Influences of campus recruiting on applicant attraction to hospitality companies. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 2(1), 3951.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。