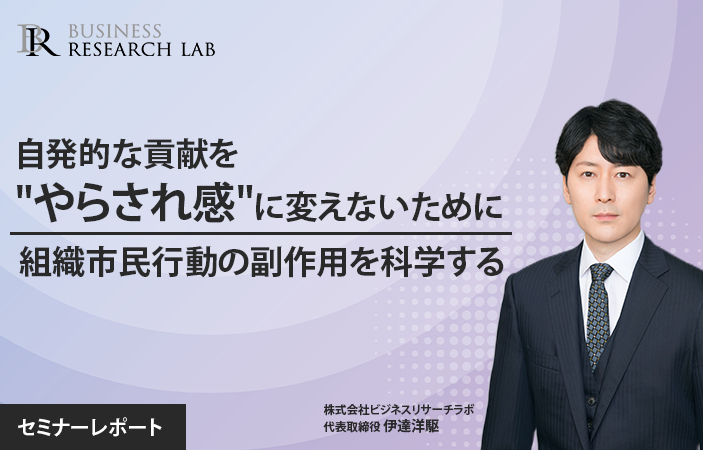2025年10月22日
自発的な貢献を”やらされ感”に変えないために:組織市民行動の副作用を科学する(セミナーレポート)
ビジネスリサーチラボは、2025年9月にセミナー「自発的な貢献を“やらされ感“に変えないために:組織市民行動の副作用を科学する」を開催しました。
皆さんの職場には、こういう人がいませんか。自分の仕事が終わっていても、困っている同僚がいれば迷わず手を差し伸べる人。会議で誰も発言しない中、組織を良くするための建設的な意見を口にする人。あるいは、会社の備品を大切に扱い、共有スペースをきれいに保つよう心がけている人。
これらは、給与や評価のために定められた職務内容には含まれていないかもしれません。しかし、こうした一人ひとりの自発的な行動が、職場の雰囲気を和ませ、チームの連携を深め、組織全体の生産性を高めていることに、多くのリーダーは気づいているはずです。このような「組織のために自発的に行われる貢献的な行動」は「組織市民行動」と呼ばれます。
これまで、この組織市民行動は、組織にとって有益で、奨励されるべき「善意の行動」として一貫して捉えられてきました。従業員の満足度が高い職場で生まれやすく、組織への貢献意欲を高める万能薬のようにも考えられていました。
しかし、近年の研究では、この組織市民行動が持つ、これまで光が当てられてこなかった「影」の側面が明らかになってきました。良かれと思って始めた貢献が、いつの間にか本人のキャリア形成の足かせになったり、過度な負担から燃え尽きの原因になったりするケース。
あるいは、善意の行動が周囲から「やって当たり前」と見なされ、やらなければ評価が下がるという無言の圧力、つまり「やらされ感」に変わり、かえって従業員のストレスを高めてしまうという皮肉な現実も報告されています。
本セミナーでは、組織の潤滑油とも言える「組織市民行動」について、その本質を掘り下げていきました。どのような環境や働きかけが、従業員の自発的な貢献意欲を育むのか。そして、そのポジティブな力を最大限に引き出しつつ、個人への過度な負担や評価の不公平といった「副作用」を防ぐためには、組織に何ができるのか。
組織の力を高めたいと願う皆さんに本レポートを読んでいただければと思います。
※本レポートはセミナーの内容を基に編集・再構成したものです。
はじめに
従業員の自発的な貢献、いわゆる「組織市民行動」は、職場の潤滑油として組織の活力を高める要素です。しかし、その一方で「良かれと思って」の行動が、いつしか「やらされ感」に変わり、従業員を疲弊させる副作用も報告されています。本講演では、この組織市民行動がもたらす光と影の両側面に、科学的な研究知見から光を当てます。自発的な貢献意欲を健全に育み、組織と個人の持続的な成長につなげるためのヒントを探ります。
組織市民行動とは何か
組織市民行動とは、職務として明確に定められているわけではないものの、従業員が自発的に行う、組織全体の機能や効率性を高める行動を指します。例えば、業務で困っている同僚に手を差し伸べる、新人に率先して仕事を教える、会社の備品を大切に扱い無駄遣いをしない、といった行動がこれにあたります。これらは直接的な報酬を期待せずに行われる、いわば「良き組織市民」としての振る舞いです。
組織市民行動は、いくつかの異なる側面から理解することができます。一つの考え方は、行動が向けられる対象によって「利他主義」と「一般的遵守」の二つの次元に分けるものです[1]。
利他主義とは、特定の個人を直接的に助ける行動を指します。例えば、多忙な同僚の仕事を手伝ったり、不在のメンバーの業務を代行したりするような、個人への援助行動が中心です。こうした行動は、従業員の職務満足度といった感情的な要因から生まれやすいとされています。
一方で、一般的遵守とは、特定の誰かではなく、組織全体に向けられる貢献行動です。時間を厳守する、会社のルールや方針を真摯に守る、といった行動が該当し、こちらは組織への忠誠心や規範意識から生じやすいと考えられています。
組織市民行動は、組織や個人にどのような影響をもたらすのでしょうか。数多くの研究成果を統合したメタ分析によれば、組織市民行動は個人と組織の双方に有益な効果をもたらすことが確認されています[2]。
個人レベルでは、組織市民行動を頻繁に行う従業員は、上司から高いパフォーマンス評価を受けやすく、昇給や昇進において有利になる傾向があります。また、組織への愛着が深まることで離職意図が低下し、実際の離職率や欠勤率も低くなるなど、人材の定着に貢献します。
組織レベルで見てもその効果は絶大です。組織市民行動が活発な職場では、生産性の向上、業務効率の改善、コスト削減といった直接的な業績向上に強い効果があることが実証されています。さらに、従業員の自発的な配慮は顧客満足度の向上にもつながり、組織全体の離職率を低下させるなど、社内外にわたってポジティブな影響を及ぼす、組織にとって価値ある資産です。
仕事満足度が組織市民行動を促進する
従業員の自発的な貢献、すなわち組織市民行動を促す要因は何でしょうか。「誠実さ」や「協調性」といった個人の性格を思い浮かべる人もいるかもしれません。しかし、数万人規模のデータを統合した大規模なメタ分析は、その直感に反する事実を明らかにしました[3]。
組織市民行動を最も強く予測するのは、持って生まれた性格特性よりも、従業員が日々の仕事に対して抱く「仕事満足度」だったのです。この結果は、採用時に特定の性格を重視する以上に、従業員が入社後にやりがいや満足感を得られるような職場を整えることの重要性を示唆しています。組織市民行動は、能力よりも「意志」に根差す行動であるため、その人が職場で幸福感を得ているかという感情的な状態が、性格的素質以上に実際の行動に結びつきやすいと考えられます。
仕事満足度の影響力は、従来の生産性指標との比較によって一層鮮明になります。長年の研究で、仕事満足度と生産量や品質といった客観的な生産性指標との間には、実はそれほど強い関係がないことが知られていました。しかし、ある研究が組織市民行動というレンズを通してこの謎を解き明かしました。管理部門職員を対象とした調査で、仕事満足度は生産性よりも、組織市民行動と強い正の相関関係にあることが確認されたのです[4]。
このメカニズムは、二つの理論で説明できます。一つは「社会的交換理論」で、満足している従業員は組織から受けた恩恵への「お返し」として貢献行動を増やすという考え方です。もう一つは「正の感情状態理論」で、満足感から生まれるポジティブな気分が、他者への親切な行動を自然に引き出すというものです。
これらの知見に基づき、従業員の仕事満足度を高め、組織市民行動を自然に引き出すためには、仕事そのものの設計を見直すことが有効です。「職務特性モデル」の考え方を応用し、具体的な施策を検討してみましょう。
・第一に、従業員が持つ多様なスキルや能力を活かせる機会(技能多様性)を創出します。配置転換や部門横断プロジェクトへの参加を促し、単調な作業に陥ることを防ぎます。
・第二に、仕事の全体像が見えるように配慮します(タスク完結性)。細切れの作業ではなく、企画から完成まで一貫して関われるような、まとまりのある単位で仕事を任せることで、達成感と貢献実感が高まります。
・第三に、自分の仕事の重要性を伝えます(タスク重要性)。自分の仕事が組織や社会にどう貢献しているかを、全社会議での事例共有や顧客からの感謝の声を通じて知らせます。
・第四に、裁量権を積極的に委譲します(自律性)。目標は共有しつつ、仕事の進め方やスケジュールは従業員に任せることで、主体性を引き出します。
・第五に、仕事の結果が直接わかる仕組み(フィードバック)を構築します。上司からの評価だけでなく、売上データや顧客満足度指標などを担当者が直接確認できる環境を整えることで、自分の仕事の成果をリアルタイムで実感できるようにします。
これらの施策は、従業員の仕事への満足度を高め、結果として組織全体を活性化させる自発的な貢献行動へとつながっていきます。
上司の公正さが自発的な貢献を育む
従業員の自発的な貢献を育む上で、仕事満足度と並んで重要なのが、リーダー、すなわち上司の存在です。とりわけ、上司が示す「公正さ」は、部下の組織市民行動を引き出す上で重要な役割を果たします。しかし、その影響は直接的なものではありません。
退役軍人省病院の従業員126名を対象とした研究では、リーダーの公正さが「上司への信頼」という心理的なプロセスを介して、組織市民行動を促進するメカニズムが解明されました[5]。この研究で注目されたのは、報酬や評価といった「結果」の公平さ(分配的公正)よりも、それに至るまでの意思決定の「過程」が公平であるか(手続き的公正)の方が、上司への信頼をより強く高めるという点です。
従業員は、たとえ結果が不本意でも、その決定プロセスが透明で、自分の意見が考慮されたと感じられれば、上司を信頼しやすくなるのです。そして、この信頼関係が、社会的交換理論における「恩返し」の感情を生み、見返りを求めない自発的な貢献行動へとつながっていきます。
「上司への信頼」をより包括的に捉える概念が、リーダーと部下の関係の質(LMX:Leader-Member Exchange)です。LMXは、単なる公正さだけでなく、信頼、尊敬、相互の責任感といった、より幅広い関係性を含みます。
9,000人以上を対象とした50の研究を統合したメタ分析によると、LMXの質と組織市民行動の間には、中程度に強い正の関係があることが確認されています[6]。興味深いことに、LMXは組織全体に向けられた行動よりも、困っている同僚を助けるといった、特定の個人に向けられた「個人指向型」の組織市民行動と、より強く関連していました。
これは、LMXがリーダーと部下という個人間の社会的な交換関係であるため、その返礼もまた、身近な同僚への援助といった、より個人的で直接的な形で現れやすいことを示唆しています。公正な手続きを担保しつつも、最終的には一人ひとりの部下との人間的な信頼関係を築くことが、職場全体の協力体制を強化することにつながります。
これらの科学的知見を日々のマネジメントに活かすためには、具体的な行動変容が求められます。
- 意思決定のプロセスを「見える化」することが大事です。チーム方針や業務分担を決める際には、その背景や理由を丁寧に説明し、一方的な通達ではなく、部下が意見を述べる機会を設けることが手続き的公正を高めます。
- 部下の意見に真摯に耳を傾ける姿勢が重要です。個人面談などを通じて、部下が安心して本音を話せる雰囲気を作り、「何か困っていることはないか」と問いかけることで、自分の意見が尊重されているという感覚を育みます。
- チーム全体への働きかけだけでなく、一人ひとりと向き合い、個別の関係(LMX)を築く努力も欠かせません。定期的な面談でキャリアプランや価値観を理解し、日々の業務における小さな貢献を見逃さずに「〇〇さん、ありがとうございます。助かりました」と感謝を伝えることが、信頼関係を深化させます。
- 上司自らが尊敬と責任感を行動で示すことが大切です。部下の専門性に敬意を払い、問題発生時には責任を明確にする姿勢を見せることで、部下との間に「この人のためなら貢献したい」という信頼関係が生まれ、それが組織全体の活力となる自発的な組織市民行動へと結実していきます。
組織市民行動の知られざる副作用
これまで組織市民行動の持つ輝かしい側面を見てきましたが、どんな物事にも光と影があるように、この自発的な貢献行動にも知られざる副作用が存在します。良かれと思って始めた行動が、意図せずして従業員を疲弊させ、かえって組織の活力を削いでしまう危険性があるのです。近年、組織市民行動のダークサイドに注目する研究が数多く登場しています。
その代表的なものが「市民疲労」という概念です。これは、組織市民行動を継続的に行うことで生じる、特有の心理的・身体的な消耗状態を指します。台湾の大学教員273名を対象とした追跡調査では、特に組織からの支援が低いと感じる環境や、行動へのプレッシャーが高い状況で組織市民行動を行うと、この市民疲労が生じやすいことが明らかになりました[7]。
そして、一度市民疲労を経験した従業員は、自らの心理的資源を守ろうとする防衛反応から、その後の組織市民行動の頻度を減らしてしまうという、組織にとって望ましくない結果につながることも示されています。
また、組織市民行動の種類によっても、その副作用は異なります。イギリスの銀行員79名を対象とした研究では、組織市民行動の中でも特に、残業を厭わない、休憩時間を削るといった「誠実性」を示す行動が、従業員の情緒的な消耗や、仕事と家庭生活との間での葛藤を引き起こすことが分かりました[8]。
衝撃的なのは、この負の影響が、職務パフォーマンスの高い、いわゆる「仕事ができる人」ほど強くなるという逆説的な結果です。優秀な従業員は、高い職務成果と模範的な組織市民行動の両方を周囲から期待され、その二重の期待に応えようと限られた資源を注ぎ込むことで、より早く枯渇してしまうのです。
自発的だったはずの行動が、いつの間にか周囲から「やって当たり前」と期待され、断ることが難しい義務へと変わってしまう現象も深刻な問題です。これは「ジョブ・クリープ」と呼ばれ、従業員の選択の自由を脅かします[9]。
心理的リアクタンス理論によれば、人は自由を奪われると強い心理的抵抗を感じ、反発します。この抵抗は、ストレスの増大や組織への態度の悪化、さらには本来の職務パフォーマンスの低下といった形で現れ、最終的には優秀な従業員の離職につながる危険性さえ伴います。善意から始まった行動が、従業員の自律性を奪い、組織への反発心を生むという皮肉な結末を招くのです。
さらに、組織市民行動は、仕事と家庭の間の葛藤を通じて、従業員の心を蝕むこともあります。インドネシアの既婚従業員235名を対象とした調査では、組織市民行動、特に同僚を助けるといった個人向けの支援行動が、従業員の情緒的消耗と強い正の関係にあることが示されました[10]。この関係は、組織市民行動に時間と精神的エネルギーを費やすことで家庭での役割を十分に果たせなくなり、それが「仕事家庭葛藤」という新たなストレス源となることで説明されます。
これらの研究知見は、組織市民行動を単なる美徳として奨励するだけでは不十分であり、その副作用を予防するためのマネジメントがいかに重要であるかを物語っています。
組織としては、特定の優秀な従業員に貢献の負担が偏らないよう配慮し、「やって当たり前」の風潮を作らないことが不可欠です。貢献に対しては感謝や承認を惜しまず、それが従業員のワークライフバランスを犠牲にするものであってはならないというメッセージを発信し続ける必要があるでしょう。
同時に、従業員個人も、自らの善意が自分自身を追い詰めることのないよう、時には「断る勇気」を持ち、自分の限界を認識し、無理をしないセルフケアの視点を持つことが、持続可能な貢献のためには不可欠と言えます。
強制的市民行動の弊害と予防策
組織市民行動の深刻な副作用は、それが自発性を失い、「強制的市民行動」へと変質してしまうことです。これは、従業員が本心ではやりたくないにもかかわらず、上司や同僚からの有形無形の圧力によって、職務外の貢献を無報酬で実施せざるを得ない状況を指します。
イスラエルの教員206名を対象とした研究では、この強制的市民行動が、従業員のストレスやバーンアウトを著しく増加させ、仕事への満足度や革新的な行動意欲を大きく低下させることが実証されました[11]。管理職が「チームのため」という大義名分を盾に、職務範囲の曖昧さを利用して心理的圧力をかけることで、善意の行動は従業員を苦しめる凶器へと変わってしまいます。
別の研究では「市民的行動の圧力」という概念が提唱され、その二面性が明らかになりました[12]。245名の従業員を対象とした調査によると、この圧力を高く感じる従業員ほど、実際に組織市民行動を多く行う傾向がありました。しかしその一方で、圧力は仕事と家庭、あるいは余暇との葛藤を深刻化させ、従業員のストレスレベルを上昇させて、最終的には離職意図を高めることも確認されました。要するに、圧力は短期的には組織に有益な行動を引き出すかもしれませんが、長期的には従業員の心身を蝕み、組織から人材を流出させるという深刻なパラドックスが存在します。
これらの研究結果を踏まえると、組織市民行動を健全に育むためには、行動の「量」を追い求めるのではなく、その源泉となる「動機」に焦点を移すマネジメントが求められます。目指すべきは、従業員が管理され、行動を「引き出される」のではなく、自ら「貢献したい」と自然に思える環境を整えることです。そのためのアプローチとして、いくつかの「スイッチ」を提案できます。
- 第一に、「自己決定権」のスイッチです。「やらされ感」をなくすため、依頼の仕方を「指示」から「相談」に変えます。「この仕事お願いします」ではなく、「今、チームでこういう課題があるんですが、何か手伝ってもらえそうなことはありますか?」と問いかけることで、従業員は貢献の方法を自分で選ぶことができます。また、「難しければ遠慮なく断ってください」と明確に伝えることで、心理的圧力は低下します。
- 第二に、「承認と感謝」のスイッチです。「やって当然」の空気を防ぐため、貢献に対して具体的かつタイムリーに感謝を伝えます。「いつもありがとうございます」という曖昧な言葉ではなく、「さっきの会議で議事録を取ってくれたおかげで、議論に集中できました。ありがとうございます」と伝えることで、従業員は自分の行動の価値を実感できます。
- 第三に、「公平性」のスイッチです。いつも同じ「いい人」に負担が偏る状況は、全体の意欲を削ぎます。上司は誰が貢献しているかを把握し、負担が集中しないよう配慮するとともに、会議の準備といった「見えない仕事」を可視化し、チーム全体で分担する意識を醸成することが重要です。
- 第四に、「意義と影響力」のスイッチです。「手伝ってくれたおかげで、お客様からとても感謝されました」というように、行動の先にあるポジティブな結果をフィードバックすることで、従業員は自分の貢献の意義を実感し、次のモチベーションへとつなげることができます。
こうしたスイッチを意識することが、強制ではない、自発的な貢献文化を育むことでしょう。
おわりに
本講演では、組織市民行動という、従業員の自発的な貢献がもたらす光と影の両側面を、科学的な研究知見に基づいて探ってきました。組織市民行動は、生産性や顧客満足度を高める組織の貴重な資産ですが、その育成方法を誤れば、従業員を疲弊させ、組織の活力を奪う「諸刃の剣」にもなり得ます。大切なのは、行動の量を強制するのではなく、従業員が内発的に「貢献したい」と感じられる環境を整えることです。本講演で紹介した知見が、皆さんの組織で自発的な貢献意欲を持続可能な形で引き出すための一助となれば幸いです。
Q&A
Q:「仕事満足度」と「エンゲージメント」は、同じような意味の言葉でしょうか。「ロイヤリティ」はこれらとは少し違うもののように感じています。これらの言葉の定義や関係性について教えていただけますか。
これらは似ていますが、異なる概念です。「仕事満足度」は、給与や職場環境、人間関係といった働く環境に対する満足度、つまり「心地よさ」を指します。
一方「エンゲージメント」は、仕事や組織へのより能動的な関わりを示す言葉です。これには二種類あり、一つは会社の方針に共感し貢献したいと思う「組織コミットメント」で、これは「ロイヤリティ」に近い概念です。もう一つは、仕事そのものに情熱ややりがいを感じ、夢中になっている状態を示す「ワークエンゲージメント」です。
満足度が環境への評価であるのに対し、エンゲージメントは組織や仕事へのポジティブで主体的な関わりという点で異なります。
Q:お話を聞きながら、結局のところ、組織にいる一人ひとりが、まずは自分に与えられた役割や仕事をきちんと理解し、それを着実に実行していくことが最も重要なのではないかと感じました。この点について、どのようにお考えでしょうか。
それは組織が機能するための大前提です。自分に与えられた役割をきちんと果たすこと(タスクパフォーマンス)は、組織の根幹を成します。
その上で、今回テーマとした「組織市民行動」は、その役割の範囲を超えて、自発的に組織や同僚を助ける「役割外の行動」を指します。どれだけ役割を細かく決めても、必ず予期せぬ業務や「役割の隙間」は生まれます。組織市民行動は、その隙間を埋めて組織の運営を円滑にする「潤滑油」の役割を果たし、結果的に組織全体の成果を高めます。
まずは役割内をこなす土台を固め、その上で役割外の貢献を重ねるという、両輪で考えることが重要です。
Q:組織の中には、積極的に役割外の貢献をする従業員がいる一方で、自分の担当業務以外には関わろうとしない従業員もいます。その結果、貢献している一部の人にばかり負担が集中し、不公平感が溜まって、最終的には組織全体のモチベーション低下につながってしまうのではないかと心配です。
多くの組織が直面する切実な問題です。対処法として、二つの側面からのアプローチが考えられます。
一つ目は、貢献してくれている従業員の行動が「当たり前」にならないよう、周囲が感謝を伝え、評価などで正当に報いる仕組みを整えることです。彼ら彼女らの善意が報われる環境がなければ、意欲は長続きしません。
二つ目は、非協力的に見える従業員をすぐに責めるのではなく、その背景を探ることです。業務過多で手一杯だったり、エンゲージメントが低下していたりする可能性があります。対話を通じて状況を理解し、必要な支援を行うことで、組織全体の協力的な風土を育むことができます。
Q:組織市民行動のような自発的な貢献に対して、金銭的な報酬を与えた場合は、どのような影響があるでしょうか。
金銭的な報酬と自発的な行動の相性は、あまり良くないとされています。
組織市民行動は「人の役に立ちたい」といった内側からの動機によるものです。ここに金銭という外的な報酬を与えると、行動の目的が報酬にすり替わり、「報酬がなければやらない」という状態を招きかねません。これは本来の助け合いの精神を損なうリスクがあります。
ただし、興味深いことに、役割外の貢献を頻繁に行う人ほど、結果的に人事評価が高くなる傾向があるという研究結果があります。要するに、直接的な報酬を設定しなくても、日々の貢献は上司に評価され、昇進や昇給という形で間接的に報われる可能性が高いのです。直接的なインセンティブよりも、貢献が自然に評価される文化を醸成する方が望ましいでしょう。
脚注
[1] Smith, C. A., Organ, D. W., and Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68(4), 653-663.
[2] Podsakoff, N. P., Whiting, S. W., Podsakoff, P. M., and Blume, B. D. (2009). Individual- and organizational-level consequences of organizational citizenship behaviors: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 94(1), 122-141.
[3] Organ, D. W., and Ryan, K. (1995). A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior. Personnel Psychology, 48(4), 775-802.
[4] Bateman, T. S., and Organ, D. W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee “citizenship”. Academy of Management Journal, 26(4), 587-595.
[5] Konovsky, M. A., and Pugh, S. D. (1994). Citizenship behavior and social exchange. Academy of Management Journal, 37(3), 656-669.
[6] Ilies, R., Nahrgang, J. D., and Morgeson, F. P. (2007). Leader-member exchange and citizenship behaviors: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 92(1), 269-277.
[7] Bolino, M. C., Hsiung, H. H., Harvey, J., and LePine, J. A. (2015). “Well, I’m tired of tryin’!” Organizational citizenship behavior and citizenship fatigue. Journal of Applied Psychology, 100(1), 56-74.
[8] Deery, S., Rayton, B., Walsh, J., and Kinnie, N. (2017). The costs of exhibiting organizational citizenship behavior. Human Resource Management, 56(6), 1039-1049.
[9] Van Dyne, L., and Ellis, J. B. (2004). Job creep: A reactance theory perspective on organizational citizenship behavior as over-fulfillment of obligations. In J. A.-M. Coyle-Shapiro, L. M. Shore, M. S. Taylor, and L. E. Tetrick (Eds.), The employment relationship: Examining psychological and contextual perspectives (pp. 181-205). Oxford University Press.
[10] Ekowati, D., Kasman, S., and Sulistiawan, J. (2023). Organizational citizenship behavior and emotional exhaustion: Examining the role of work-family conflict. Journal of Theoretical and Applied Management, 16(1), 196-205.
[11] Vigoda-Gadot, E. (2006). Compulsory citizenship behavior: Theorizing some dark sides of the good soldier syndrome in organizations. Journal for the Theory of Social Behaviour, 36(1), 77-93.
[12] Bolino, M. C., Turnley, W. H., Gilstrap, J. B., and Suazo, M. M. (2010). Citizenship under pressure: What’s a “good soldier” to do? Journal of Organizational Behavior, 31(6), 835-855.
登壇者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。