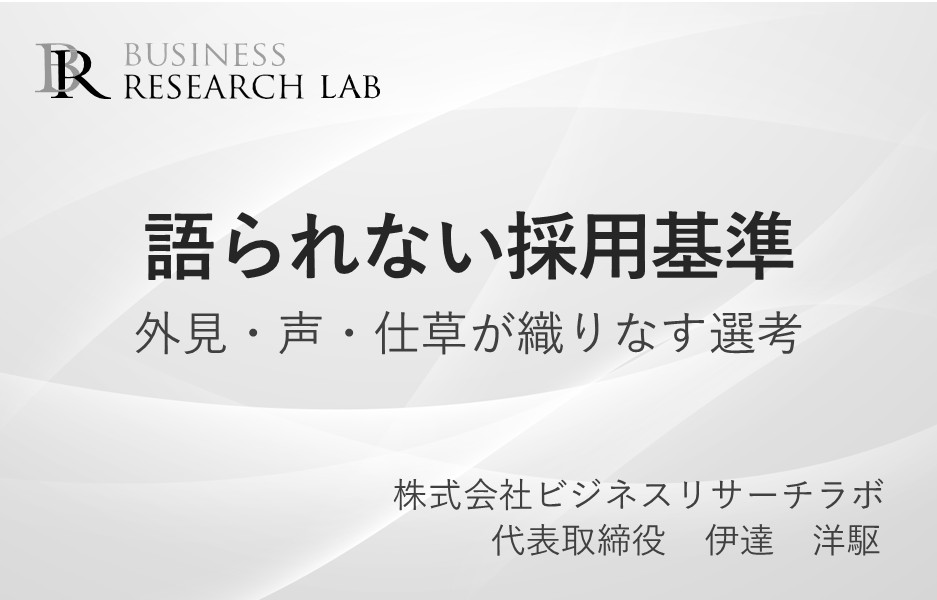2025年10月22日
語られない採用基準:外見・声・仕草が織りなす選考
採用面接の場で、私たちは候補者の能力や経験といった「語られる内容」に集中し、客観的な評価を下していると信じています。しかし、その判断は本当に純粋なものでしょうか。実は、候補者の性別や体型、握手の力強さ、声のトーンといった「語られない情報」が、私たちの評価を無意識のうちに左右しているとしたらどうでしょう。
このような影響は、決して評価者の意図的な偏見から生じるわけではありません。限られた情報から素早く結論を導き出すという、人間の脳に備わった効率的な認知システムに根差しています。外見や身体的特徴は、相手の能力や人柄を推測するための無意識的な手がかりとして機能してしまうのです。この仕組みは、かつて生存に有利な能力でしたが、多様な人材が活躍すべき現代の職場においては、公正な選考を妨げる「認知バイアス」という壁になり得ます。
本コラムでは、採用の現場で働く無意識の力に光を当てていきます。男性優位の職場で生じやすい性別の影響、能力とは無関係に評価を歪める体重への偏見、そして握手や声の質が面接官に与える効果。これらの研究知見は、私たちが自らの判断を疑い、より公正な採用とは何かを考えるためのヒントとなるでしょう。
男性優勢職で情報曖昧だと男性が選ばれやすい
職場における性別による評価の違いは、これまで実際の職場での調査では明確に捉えることが困難でした。現実の職場では、男女の候補者が全く同じ条件で比較されることがなく、本当の業績差と偏見を区別することができなかったからです。
このような限界を克服するため、採用場面を実験室で再現した研究が数多く行われてきました。これらの実験研究を統合的に分析した論文では、1970年から2012年にかけて発表された111の研究、延べ22,348人の参加者のデータが検討されました[1]。各研究では、性別以外の条件を統制し、候補者の履歴書や面接での回答内容を同一にした状態で、評価者がどのような判断を下すかが測定されています。
分析の結果、職場の性別構成によって評価の偏りが異なることが判明しました。男性が多い職場(女性の比率が35%未満)では、男性候補者が系統的に高く評価される現象が確認されました。この偏りの大きさは統計的に小から中程度とされ、実際の採用判断に無視できない影響を与えるレベルです。
一方、女性が多い職場(女性の比率が65%以上)や男女がほぼ同数の職場では、こうした性別による評価差はほとんど見られませんでした。女性優勢の職場では男性候補者がわずかに高く評価される傾向が観察されました。これは「ガラスのエスカレーター」と呼ばれる現象で、女性が多い分野でも男性が昇進において有利になることがあるという指摘と一致しています。
この偏見の背景には、職場に求められる資質に関する無意識の思い込みがあります。男性が多い職種では、その職務に必要な能力が男性的な特質と結びつけて考えられやすいものです。例えば、技術系や管理職では「論理性」「決断力」「リーダーシップ」などが求められると考えられ、これらの資質は文化的に男性と関連付けられています。そのため、同じ履歴書を見ても、男性候補者の方がこれらの能力を持っているように感じられてしまうのです。
評価者の性別も判断に影響しました。男性の評価者は男性優勢職において顕著に男性候補者を優遇する傾向があり、その偏りは中程度の大きさでした。一方、女性の評価者ではこうした偏見はほとんど見られませんでした。これは男性評価者が自分と同じ性別の候補者に無意識に親近感を感じたり、男性的資質をより高く評価したりする可能性を示唆しています。
候補者に関する情報の量や質も、性別による偏見の大きさを左右する要因でした。履歴書などの情報が限定的で、候補者の能力が判断しにくい状況では、性別による偏見が最も強く現れました。情報が曖昧な場合、評価者は無意識のうちに性別のステレオタイプに頼って判断を下してしまいます。
しかし、候補者の高い能力が明確に示される場合、この偏見はほぼ消失しました。客観的な業績データや詳細な推薦状などが提供されると、評価者は性別に関係なく能力を正しく評価できるようになります。十分な情報があれば人は公正な判断を下せることを意味しています。
情報の量についても同様の傾向が見られました。履歴書だけしか提供されない場合は大きな偏見が生じましたが、推薦状や面接記録などが追加されると偏見は減少しました。ただし、情報を2点以上に増やしても追加的な改善効果は限定的でした。
評価者に慎重な判断を促す仕組みも偏見の抑制に有効でした。採用決定について説明責任を求められたり、公平性の大切さを事前に伝えられたりした評価者は、男性優勢職でもほとんど偏見を示しませんでした。これは、人々が意識的に偏見を制御できることを示しています。
実務経験のある評価者は、学生や一般の人々と比べて偏見が小さいことも明らかになりました。おそらく豊富な経験により、外見的特徴よりも職務関連能力に注目する習慣が身についているためと考えられます。
過体重候補者、特に女性は同等能力でも採用評価が低い
身体的特徴が採用判断に与える影響で見過ごせないのが、候補者の体型です。体重による差別は、能力とは関係のない外見的要素が、人生を左右する就職機会に影響を与える典型例です。
この問題を科学的に検証した研究では、従来の実験の限界を克服する方法が用いられました[2]。過去の実験では、痩せた人と太った人という異なる人物を比較していたため、体重以外の要因(表情、声質、話し方など)が結果に混入してしまう問題がありました。
そこで研究者は、同一の男女の俳優に特殊メイク用のプロテーゼを装着させ、標準体型と約20%の過体重状態を再現しました。同じ人物が体型だけを変えて、全く同じ内容の模擬面接を行ったのです。この実験設計により、体重そのものが採用評価に与える効果を測定することが可能になりました。
実験には320名の大学生が参加し、販売員とシステムアナリストという2つの職種について採用判断を行いました。参加者は8つの異なる面接映像を視聴し、「1=絶対採用しない」から「7=必ず採用する」までの7段階で評価しました。
結果、過体重の候補者の平均評価は4.22点で、標準体重の候補者の5.75点を大幅に下回りました。この差は統計的に大きく、実際の採用決定に影響を与えるレベルでした。
この体重による差別は女性候補者でより深刻でした。過体重の女性候補者の評価は3.61点と最も低く、過体重の男性候補者の4.83点をさらに下回りました。女性には「痩身であるべき」という社会的圧力がより強く働くため、体重増加が二重の不利をもたらすのです。
対人接触の多い販売職と技術系のシステムアナリスト職の間で、差別の大きさに有意な違いは見られませんでした。「人前に出る仕事では外見がより重視される」という予想に反し、体重による偏見は職種を問わず一様に存在していました。
この心理的メカニズムを探るため、研究では候補者への人格的評価も測定されました。過体重の候補者は「非生産的」「決断力がない」「怠惰」といったネガティブな人格特性を帰属される傾向が見られました。これは「太っている人は自己管理ができない」という文化的ステレオタイプが働いているためです。
しかし統計分析の結果、この人格的偏見だけでは採用評価の差を完全に説明できないことが判明しました。人格評価を統計的に除去しても、体重知覚自体が採用評価の16%を独自に説明していました。これは、意識的な人格判断を超えた、より根深い情動的反応が存在することを示唆しています。
評価者自身の身体への関心度も差別の強さに影響していました。自分の体型や外見を重視し、それに満足している評価者ほど、過体重の候補者、特に女性を厳しく評価する傾向が見られました。自分の身体基準を他者に投影してしまう心理的プロセスの表れと考えられます。
この研究が明らかにした体重による採用差別は、中程度の肥満という決して極端ではない状態でも顕著に現れることが恐ろしい点です。BMI(体格指数)で20%の増加、例えば身長160cmで体重が51kgから61kgになっただけで、採用機会が減少してしまうのです。
力強い握手は外向性を示し採用評価を高める
面接において最初に交わされる握手は、わずか数秒の接触にもかかわらず、その後の評価全体に持続的な影響を与えることが明らかになっています。これまで主に海外における実務的なアドバイスとして語られてきた「しっかりとした握手の大切さ」が実証されたのです。
この研究では、98名の大学生が実際の企業人事担当者26名との模擬面接に参加しました[3]。面接は30分から45分の本格的なもので、候補者は事前に企業研究を行い、適切な服装で臨むよう指示されました。研究者は面接の内容には一切介入せず、現実の採用面接とほぼ同じ環境を再現しました。
握手の評価は、面接とは独立した訓練を受けた5名の評価者が担当しました。彼ら彼女らは面接前後に候補者と握手を交わし、5つの側面から評価しました。握りの完全性(手全体でしっかり握れているか)、握力の強さ、持続時間、握手の活力度、そして握手中の視線です。各項目を5段階で評定し、その平均を総合的な握手スコアとしました。
同時に、候補者の性格特性もビッグファイブで測定されました。ビッグファイブは外向性、協調性、誠実性、神経症的傾向、開放性という5つの基本的な性格次元からなり、職場での行動や業績と関連することが知られています。
面接官による最終的な採用評価は、「この候補者を採用したい満足度」など5項目の平均で算出されました。これらの項目は実際の採用決定でよく用いられる基準で構成されており、実務的な妥当性を持っています。
統計分析の結果、握手の質と採用評価の間には中程度の正の相関が確認されました。力強く、完全で、適度な時間続き、活力があり、アイコンタクトを伴う握手をした候補者ほど、面接官から高い評価を受けていました。
さらに、握手の質が外向性という性格特性と関連していました。外向的な人ほど質の高い握手を示す傾向があり、そして外向的な人ほど面接で高く評価されていました。これによって、握手が単なる表面的な技術ではなく、その人の性格特性を反映している可能性が示唆されました。
握手が外向性と面接評価を結ぶ媒介要因であることも明らかになりました。外向的な人は質の高い握手を行い、それが面接官に好印象を与えて、高い評価につながるという関係が裏付けられたのです。
性別による違いも興味深いところです。女性は平均的に男性より握力が弱く、握りも不完全になりがちでした。この生理的違いは自然なものですが、最終的な面接評価では男女差は見られませんでした。これは女性が他の側面(視線、持続時間、活力度など)で補っているか、あるいは面接官が性別による握力差を考慮して評価している可能性があります。
なぜ握手がこれほど強力な効果を持つのでしょうか。心理学的には、握手は「即座性(immediacy)」を高める非言語的コミュニケーションとして機能すると説明されます。身体接触は相手との心理的距離を縮め、親近感や信頼感を醸成します。面接という緊張した状況で最初に交わされる握手は、その後の相互作用全体の調子を決める役割を果たすのです。
握手は社会的スキルや自信の表れとして機能します。しっかりとした握手ができる人は、対人関係において積極性や主張性を持っており、これらの特性は多くの職務で求められるものです。面接官は無意識のうちに、握手の質からその人の社会的能力を推測しているのかもしれません。
声と身振りの魅力が面接評価と実績を高める
人と人とのコミュニケーションにおいて、言葉の内容以外の要素が与える印象は想像以上に大きなものです。面接場面でも、候補者の声の質や身振り手振りといった非言語的要素が、評価に決定的な影響を及ぼすことが研究によって明らかになっています。
この研究では、実際の企業で働く管理職を対象に、二段階の調査が実施されました[4]。まず予備調査として、公益事業会社の現職マネジャー60名が行動記述式の面接質問に答える様子がビデオ撮影されました。研究者は録画された映像から音声を抽出し、声の特徴を客観的に測定しました。
声の分析では、ピッチ(音の高さ)の平均値と変動幅、話す速度、発話の間に入るポーズの長さ、そして声の強弱の変化幅という5つの要素が測定されました。これらは10秒間のサンプルを2回ずつ抽出して分析され、測定の信頼性が確保されました。
これらの声の特徴を特定の公式で組み合わせると、実際の職場での業績評価と関連することが判明しました。話す速度が適度に速く、ピッチの変動が豊かで、無音のポーズが少なく、一定した音量と振幅を保つ声の持ち主ほど、上司から高い業績評価を受けていたのです。
本格的な検証は、大手新聞社の若手マネジャー110名を対象に行われました。参加者はリーダーシップに関する構造化された9つの質問からなる面接を受け、その様子が録画されました。この映像を用いて、視覚的要素と聴覚的要素の両方が分析されました。
視覚的要素の測定では、5名の評価者が音声を消した状態で2分間の映像を視聴し、外見的魅力度、微笑の頻度、面接官への視線、手振りの量、そして体の前傾度を評価しました。聴覚的要素については、予備調査と同じ方法で声の5つの特徴が測定され、統合的な音声魅力度スコアが算出されました。これらの非言語的要素が面接評価や実際の業績にどのような影響を与えるかが検証されました。
その結果、視覚的に魅力的な非言語行動を示した候補者は面接で高く評価され、聴覚的に印象的な声を持つ候補者はさらに高い評価を受けました。見た目の印象よりも声の印象の方が面接評価により強く作用していたのです。
これらの非言語的要素は面接評価だけでなく、実際の職場での業績とも関連していました。魅力的な声を持つ人は職場でも高い成果を上げており、視覚的要素も業績と関連する傾向が見られました。
なぜこのような現象が生じるのでしょうか。研究では、非言語的要素が人々の情緒的反応を通じて評価に影響することが確認されました。参加者の学生が映像(視覚のみ)または音声(聴覚のみ)を視聴し、候補者への好感度、信頼感、能力感、支援意図などを評価したところ、魅力的な非言語行動は一貫して好意的な感情を引き起こしていました。
まず、候補者の魅力的な視覚的・聴覚的シグナルが観察者の好感や信頼といった情緒的反応を喚起します。そしてこの情緒的反応が面接評価の形成に寄与するのです。声については、同じプロセスが職場でも機能し、実際の業績評価にまで波及していました。
この発見は、面接の妥当性について新たな視点を提供します。従来、面接は主観的で偏見に満ちた選考方法として批判されることがありました。しかし、この研究は、面接官が候補者の非言語的シグナルから対人影響力や社会的スキルを敏感に読み取っている可能性を示唆しています。
しかし研究者は同時に慎重な姿勢も示しています。非言語的要素の評価に対する影響は中程度であり、構造化された面接質問や能力テストなどの他の選考手法と比べて決定的に優れているわけではありません。
脚注
[1] Koch, A. J., D’Mello, S. D., and Sackett, P. R. (2015). A meta-analysis of gender stereotypes and bias in experimental simulations of employment decision making. Journal of Applied Psychology, 100(1), 128-161.
[2] Pingitore, R., Dugoni, B. L., Tindale, R. S., and Spring, B. (1994). Bias against overweight job applicants in a simulated employment interview. Journal of Applied Psychology, 79(6), 909-917.
[3] Stewart, G. L., Dustin, S. L., Barrick, M. R., and Darnold, T. C. (2008). Exploring the handshake in employment interviews. Journal of Applied Psychology, 93(5), 1139-1146.
[4] DeGroot, T., and Motowidlo, S. J. (1999). Why visual and vocal interview cues can affect interviewers’ judgments and predict job performance. Journal of Applied Psychology, 84(6), 986-993.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。