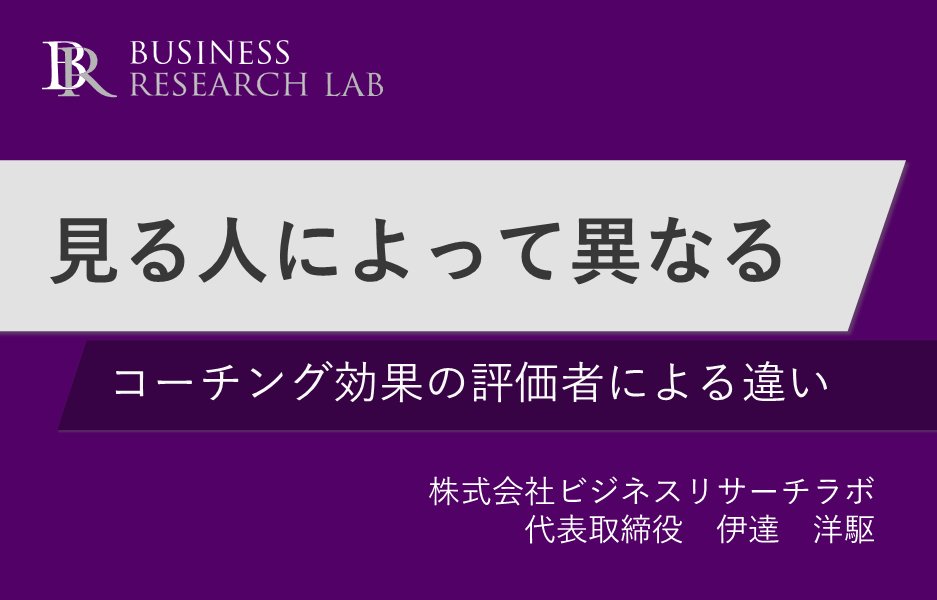2025年10月21日
見る人によって異なる:コーチング効果の評価者による違い
導入する企業が増えているエグゼクティブ・コーチングですが、「その効果は?」という問いへの答えは、私たちが思う以上に複雑で、そして示唆に富んでいます。私たちはつい、「パフォーマンスは上がったか」「本人は満足しているか」という単純な物差しでその価値を測ろうとします。しかし、もし「部下からの評価は向上したのに、本人はコーチングに不満を抱いている」としたらどうでしょうか。あるいは、「会社の業績には変化がないのに、本人は『キャリアで最高の経験だった』と語る」としたら、どう評価すべきでしょうか。
近年の実証研究が明らかにしつつあるのは、まさにこのような一見矛盾した事態が起こり得るということです。コーチングの価値は、短期的な成果や主観的な満足度だけでは捉えきれない、多面的で奥深いところに隠されています。
本コラムでは、複数の研究を紐解きながら、コーチング効果の複雑さと豊かさを探求します。客観的な成果と主観的な実感の間に生じるギャップ、そして評価する人の立場によって全く異なる効果が見えてくる不思議さ。こうした多層的な価値を理解することで、コーチングという手法に、より深く迫ることができるはずです。
コーチングは成果を上げるが、本人の満足度とは関連がない
コーチングの効果を測定する際、直感的で分かりやすい指標は、客観的なパフォーマンスの向上です。しかし、あるグローバル企業で実施された研究が明らかにしたのは、パフォーマンスの改善と本人の満足度との間には、必ずしも密接な関係がないという事実でした[1]。
この研究では、1361名の上級管理職を対象に、多面的フィードバック(360度フィードバック)とエグゼクティブ・コーチングを組み合わせた介入が実施されました。参加者は二つのグループに分けられ、一方は多面的フィードバックのみを受け、もう一方は追加的にエグゼクティブ・コーチとの協働も経験しました。そして1年後、両グループのパフォーマンス評価の変化が比較されました。
多面的フィードバックとは、上司、同僚、部下といった複数の関係者から、その人のパフォーマンスに関する評価を収集する手法です。自分では気づかない強みや改善点を客観的に把握することができます。一方、エグゼクティブ・コーチングでは、外部の専門家であるコーチが1対1で管理職を支援し、フィードバック結果を基にした能力開発や課題解決を促進します。
研究の結果、エグゼクティブ・コーチと協働したグループは、1年後の他者評価において統計的に有意な改善を見せました。上司や部下からの評価が実際に向上したのです。これは、コーチングが行動変容を促し、周囲から見てもわかる形でパフォーマンスが改善されたことを意味します。
他方で、この研究で印象的なのは、コーチングを受けた管理職の主観的な評価、つまり「コーチングがどれだけ効果的だったか」という満足度が、実際のパフォーマンス向上とは関連していなかった点です。「素晴らしいコーチだった」「非常に有益な経験だった」と感じた管理職の行動が、必ずしも他者から見て改善されたわけではありませんでした。逆に、コーチングに対してそれほど高い評価をしていなかった管理職の中にも、客観的な評価が向上したケースが見られました。
コーチングの価値を評価する際、私たちは何を基準にすべきなのでしょうか。本人の満足度は高いが成果が見えない場合と、本人はそれほど満足していないが客観的な成果が上がっている場合、どちらがより価値のあるコーチングと言えるのでしょうか。
コーチングは業績より、本人のキャリア満足度を向上させる
先ほど見た研究とは対照的に、別の研究では、コーチングが客観的な業績よりも、本人の主観的な満足感により強く作用することが明らかになりました。イスラエルで実施されたこの研究は、エグゼクティブ・コーチングの効果を多角的に検証し、その結果、コーチングの価値がキャリア満足度の向上にあることを浮き彫りにしました[2]。
この研究は、197名の管理職を対象とした準実験計画法により実施されました。参加者は、コーチングプログラムを受けるグループと、同じ組織に所属するがコーチングを受けないコントロールグループに分けられました。コーチングプログラムは認知行動論的アプローチに基づき、10回から12回のセッションで構成され、約9ヶ月間にわたって継続されました。
研究者たちは、コーチングの効果を測定するため、複数の指標を用いました。職務パフォーマンス、自己認識、職務への情緒的コミットメント、そしてキャリア満足度です。これらの指標は、コーチングプログラムの開始前と終了後に測定され、その変化がコントロールグループと比較されました。
分析の結果、職務パフォーマンスについては、自己評価と上司評価の両方において、コーチングを受けたグループが対照群を明確に上回るような改善は見られませんでした。一部の指標では両グループともにスコアが向上しましたが、コーチングによる特別な効果は確認されなかったのです。
ところが、キャリア満足度においては、異なる結果が得られました。コーチングを受けたグループでは、プログラム終了後にキャリア満足度が統計的に有意に向上しました。一方、コントロールグループでは、そのような向上は見られませんでした。
キャリア満足度とは、自分の職業的な歩みに対する総合的な満足感を指します。現在の仕事の内容、将来の展望、これまでの達成感、そして職業人としての成長実感などを包含する概念です。この研究が明らかにしたのは、コーチングが、短期的な業績向上よりも、こうした長期的で包括的な満足感の向上により強く寄与するということでした。
なぜコーチングがキャリア満足度を向上させるのでしょうか。コーチングプロセスでは、コーチとクライアントが1対1で対話を重ね、クライアントの価値観、目標、強み、課題について探求します。この過程で、クライアントは自分自身のキャリアを見つめ直し、これまでの経験を意味づけし直し、将来へのビジョンを構築する機会を得ます。
認知行動論的アプローチでは、思考パターンと感情、行動の関係に焦点を当てます。コーチングを通じて、クライアントは自分の思考の癖や制限的な信念に気づき、より建設的で前向きな思考パターンを身につけることができます。これは、困難な状況に直面した際の対処法を改善し、ストレスを軽減し、全体的な職業満足度を高めることにつながります。
コーチングの力は、まず目標達成より良い関係性を築く点にある
コーチングの効果を理解するために、これまでに実施された多数の研究を統合し、全体像を描き出そうという試みが行われました。このメタ分析は、コーチングという介入が何にどの程度の効果を持つのか、そしてその効果は何によって左右されるのかを包括的に明らかにしようとしたものです。
研究者たちは、2000年から2014年までに発表されたリーダーシップ、ビジネス、エグゼクティブ・コーチングに関する実証研究を対象に、大規模な文献検索を実施しました[3]。厳密な基準によってスクリーニングを行った結果、24本の研究に含まれる26の独立したサンプルが、最終的な分析対象として選定されました。
この研究では、コーチングによってもたらされる成果を分類しています。「関係性の成果」と「目標達成の成果」です。関係性の成果とは、コーチとクライアントの間に生まれる協働関係(ワーキングアライアンス)の質を指します。一方、目標達成の成果には、行動変容、態度の変容、認知の変化、他者との関係改善、コーチングへの満足度などが含まれます。
分析の結果、コーチングは、目標達成の成果よりも、関係性の成果に対してより大きな効果を持つことが判明しました。コーチングは、具体的な行動変容や目標達成を促す前に、コーチとクライアントの間に良好で信頼に満ちた関係を築く上で強力な介入であることが実証されたのです。
この関係性は、単なる副産物ではありません。コーチとクライアントの協働関係は、目標達成の成果と有意な正の相関があることも確認されました。良い関係性は、それ自体が目的であるだけでなく、最終的な成果を生み出すための基盤となります。
目標達成に関する成果の中でも、効果の大きさには違いが見られました。「行動変容」や「仕事関連の態度の変容」に対しては有意なプラスの効果が見られましたが、「個人的な態度の変容」や「認知の変化」に対する効果は比較的小さく、「他者との関係改善」については有意な効果が見られませんでした。コーチングが最も直接的に作用するのは、職場での具体的な行動や仕事に対する姿勢であることを示しています。
研究では、コーチングの効果を左右する要因についても分析が行われました。対象者の種類を比較すると、企業で働くエグゼクティブよりも、大学生のサンプルにおいて効果が大きいことが分かりました。エグゼクティブの場合、既に確立された行動パターンや複雑な組織環境があるため、変化が表面化するまでにより長い時間が必要なのかもしれません。
コーチの専門的背景について、コーチが心理学の専門家であるか否かは、成果に大きな違いをもたらしませんでした。心理学系と非心理学系の両方の背景を持つコーチの混合チームが、むしろより効果的である可能性が示唆されました。
セッション回数に関する分析では、「多ければ良い」という単純な関係ではないことが明らかになりました。1回から3回のセッションが、4回から6回のセッションよりも効果が高いという結果が出ており、適切な「スイートスポット」が存在する可能性が示唆されました。
教師へのコーチングは、自己評価は変えるが他者評価は変えない
コーチングの効果を測定する際、誰がその効果を評価するかによって、結果が異なることがあります。この点を示したのが、オーストラリアの高校教師を対象とした研究です[4]。
44名の高校教師を対象としたこの研究では、二つの異なる研究デザインが組み合わされました。一つは、参加者をランダムに「コーチング群」と「待機リスト対照群」に分けたランダム化比較試験で、これによりコーチングが目標達成、メンタルヘルス、ウェルビーイング、レジリエンスに与える効果が比較されました。もう一つは、コーチング群のみを対象とした準実験計画法で、コーチングの前後でリーダーシップ・スタイルがどのように変化したかを、自己評価と他者評価の両方を用いて測定しました。
コーチングプログラムは、プロのコーチによる10回の個人セッションを20週間にわたって実施するという、本格的なものでした。アプローチとしては、認知行動療法と解決志向アプローチを基盤とし、セルフリーダーシップと変革型リーダーシップの理論が取り入れられました。コーチング開始前には、参加者は自身のリーダーシップ・スタイルに関する多面的なフィードバックも受けており、客観的なデータに基づいたコーチングが実施されました。
研究の結果、コーチングが教師に与える効果は多岐にわたることが明らかになりました。目標達成度については、仕事関連の目標と個人的な目標の両方で、コーチング群が対照群を上回る改善を見せました。レジリエンスと職場でのウェルビーイングについても顕著な効果が確認されました。対照群のスコアが期間中に低下したのに対し、コーチング群は高いレベルを維持し、統計的に有意な差が生じました。
ストレスレベルについても、コーチング群は対照群に比べて有意に低くなりました。教師という職業は、生徒との関係、保護者との対応、同僚との協働、管理業務など、多方面にわたってストレスの多い仕事として知られています。コーチングが、こうした職業特有のストレスを軽減する効果を持つことが実証されたのは、教育現場にとって価値のある発見です。
また、リーダーシップ・スタイルの評価において、自己評価と他者評価の間に違いが見られました。コーチング群の自己評価においては、コーチング後にポジティブな変化が確認されました。建設的リーダーシップ・スタイル(達成意欲や人間性を重視するスタイル)のスコアが向上し、防衛的リーダーシップ・スタイル(攻撃的・受動的なスタイル)のスコアが減少しました。
ところが、他者(上司や同僚)による評価では、コーチングの前後で有意な変化は見られませんでした。教師自身は、自分のリーダーシップがより建設的で効果的になったと感じているにもかかわらず、周囲の人々はそのような変化を認識していなかったのです。
この現象は、どのように解釈すべきでしょうか。一つの可能性は、自己認識の変化が実際の行動変容として他者に認識されるまでには、より長い時間が必要であるということです。コーチングによって内面的な変化が起こっても、それが外見的な行動として現れ、他者がそれを認識し、評価を更新するまでには、20週間という期間では不十分だったのかもしれません。
別の可能性として、評価者である同僚や上司が、日常的にその教師の教室での行動を直接観察する機会が限られていることが挙げられます。教師の仕事の多くは、閉じられた教室の中で行われるため、リーダーシップの変化が最も現れやすい場面を、同僚が目にする機会は少ないのです。
既存の印象や期待による認知の偏りも考慮すべき要因です。人は他者に対して一定の印象を形成すると、それを維持しようとする傾向があります。同僚や上司が、ある教師について既に持っている印象を変えるためには、かなり明確で一貫した変化の証拠が必要になるかもしれません。
コーチングの効果は、部下より上司からの評価で高く出る
コーチングの効果を評価する際、誰が評価するかによって結果が異なることは、先に触れましたが、この点を検証した他の研究があります。2014年以降に発表された職場コーチングに関する実証研究を統合したメタ分析では、評価者の立場によってコーチングの効果がどのように変わるかが分析されました[5]。
この研究では、厳格な基準によって選定された11本の論文が分析対象となりました。コーチングの成果の評価者は、「自己評価」「上司による評価」「部下による評価」の三つに分類され、それぞれの評価におけるコーチングの効果量が比較されました。
その結果、「上司による評価」が最も大きな効果を示し、次いで「自己評価」でした。一方、「部下による評価」では、統計的に有意な効果は見られませんでした。この発見は、コーチングの効果が評価者の位置や関係性によって左右されることを示しています。
なぜ上司による評価で最も高い効果が現れるのでしょうか。いくつかの要因が考えられます。
上司は被コーチの仕事ぶりを包括的に観察する立場にあります。会議での発言、プロジェクトの進め方、チームメンバーとの関わり方、意思決定のプロセスなど、様々な場面での行動を継続的に見る機会があります。これによって、コーチングによる変化を多角的に捉えることができるのかもしれません。
上司は被コーチのパフォーマンスを評価する責任を負っているため、その変化に対して敏感に反応する動機があります。部下の成長は自身の管理能力の証明にもなるため、ポジティブな変化を積極的に認識し、評価する可能性があります。
多くの組織では、コーチングプログラムの導入について上司の理解と支持が得られている場合が多く、この期待効果も働いている可能性があります。上司がコーチングの価値を信じている場合、その効果をより敏感に察知し、評価に反映させるかもしれません。
一方、部下による評価で効果が見られなかった理由も考察する必要があります。部下の視点から見ると、上司のコーチングによる変化は必ずしも直接的に実感されないかもしれません。コーチングで扱われる内容の多くは、戦略的思考、意思決定能力、リーダーシップ・スタイルなど、部下の日常業務に直接的な影響を与えるまでに時間がかかるものが多いからです。
部下は上司の行動の一部分、主に自分との直接的な関わりの部分しか観察できません。会議室での戦略的な議論や、経営陣との意思決定プロセスなど、コーチングの効果が最も現れやすい場面を目にする機会は限られています。このため、実際に変化が起こっていても、それを部下が認識することは困難であると考えられます。
部下は上司に対して既存の印象や期待を強く持っており、これが評価に影響を与える可能性もあります。特に、ネガティブな印象を持っている場合、その印象を変えるためには相当大きな変化が必要になりそうです。
脚注
[1] Smither, J. W., London, M., Flautt, R., Vargas, Y., and Kucine, I. (2003). Can working with an executive coach improve multisource feedback ratings over time? A quasi-experimental field study. Personnel Psychology, 56(1), 23-44.
[2] Bozer, G., Sarros, J. C., and Santora, J. C. (2012). Examining the effectiveness of executive coaching on coachees’ performance in the Israeli context. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 10(1), 14-32.
[3] Sonesh, S. C., Coultas, C. W., Lacerenza, C. N., Marlow, S. L., Benishek, L. E., and Salas, E. (2015). The power of coaching: a meta-analytic investigation. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 8(2), 73-95.
[4] Grant, A. M., Green, L. S., and Rynsaardt, J. (2010). Developmental coaching for high school teachers: Executive coaching goes to school. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 62(3), 151-168.
[5] Cannon-Bowers, J. A., Bowers, C. A., Carlson, C. E., Doherty, S. L., Evans, J., and Hall, J. (2023). Workplace coaching: a meta-analysis and recommendations for advancing the science of coaching. Frontiers in Psychology, 14, 1204166.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。