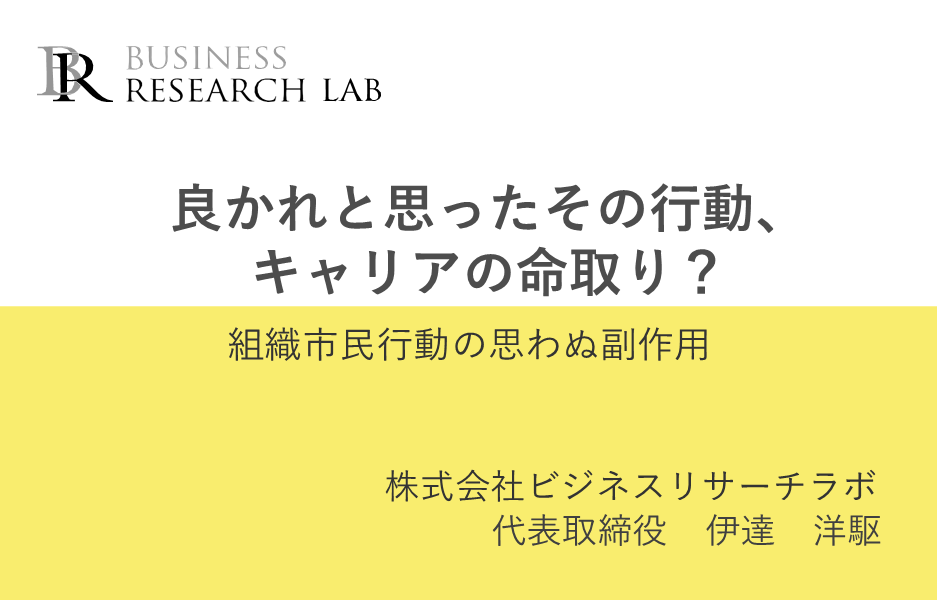2025年10月21日
良かれと思ったその行動、キャリアの命取り?:組織市民行動の思わぬ副作用
組織市民行動という言葉をご存知でしょうか。従業員が自発的に組織のためにとる行動を指します。例えば、困っている同僚を手伝ったり、会議室を整理整頓したり、新人の指導を率先して行ったりすることです。
長い間、こうした行動は組織にとっても個人にとっても良いものだと考えられてきました。チームワークが向上し、職場の雰囲気が良くなり、組織全体の生産性向上につながるからです。こうした自発的な貢献行動は奨励されてきました。
しかし、近年の研究によって、組織市民行動の隠された別の側面が明らかになってきています。組織市民行動は確かに組織にとって有益かもしれませんが、それを実行する個人にとっては思わぬ代償を払うことになる場合があります。本業務に使える時間が削られてしまうことで昇進や昇給の機会を逃したり、精神的に疲弊してしまったり、家庭生活にまで悪い変化が生じたりすることが分かってきました。
本コラムでは、組織市民行動の光の部分だけではなく、影の部分にも目を向けていきます。善意の行動がなぜ個人にとって負担となってしまうのか、どのような状況でそれが起こりやすいのか、そして優秀な人ほど陥りやすい罠について探っていきます。
組織市民行動は成果主義下でキャリアのコストに
組織市民行動が個人のキャリアに予想外の負担をもたらすという問題は、成果主義的な評価制度を採用している職場で顕著に現れることが分かっています。ある研究では、アメリカのプロフェッショナル・サービス企業で働く3,680名の従業員を対象に、この現象が調査されました[1]。
この企業では、従業員の評価が「顧客への請求可能な労働時間」、いわゆるビラブル・アワーによって決まる制度が採用されていました。これは典型的な結果基準型の評価システムで、どれだけ売上に直結する作業を行ったかが重視される仕組みです。研究では、このビラブル・アワーを本来の職務遂行として位置づけ、それ以外の管理業務時間から義務的な作業を除いたものを組織市民行動として定義しました。
調査の結果、組織市民行動に多くの時間を費やした従業員ほど、業績評価における得点が低くなっていることが分かりました。確かに組織市民行動自体も評価の対象にはなっていましたが、その影響力は本来の職務遂行よりも弱いものでした。
組織市民行動に費やされた時間と職務遂行に費やされた時間の間に、負の相関関係がありました。組織市民行動に時間を使えば使うほど、本来の業務に割ける時間が減ってしまうという図式を表しています。
この時間のトレードオフは、従業員の客観的なキャリア成果にも影響を与えていました。組織市民行動への時間投資が多い従業員は、給与の増加率が低く、昇進の速度も遅くなっていることが確認されました。一方で、ビラブル・アワーの多い従業員は、業績評価が高く、昇進についても有利な立場に置かれていました。
こうした結果が生まれる背景には、組織の評価制度の仕組みがあります。結果基準型のシステムでは、測定可能で明確な成果が評価の中心となります。顧客への請求可能な時間や売上といった数値は客観的で比較しやすく、評価者にとって判断の基準として使いやすいものです。
一方、組織市民行動は定性的な側面が強く、その価値を数値化することが困難です。同僚を手伝うことや職場環境の改善に貢献することは価値のある行動ですが、それが直接的に売上や利益につながるかどうかを示すことは簡単ではありません。結果、評価制度上では二次的な扱いを受けることになってしまいます。
この現象は、従業員にとってジレンマを生み出します。組織から期待され、奨励される行動をとることで、かえって自分のキャリアにとって不利益を被ることになるからです。善意でとった行動が、昇進や昇給の機会を遠ざける結果になってしまうという矛盾した状況が生まれています。
組織市民行動は、キャリアに負の影響を与える矛盾も
先ほどの調査結果を踏まえると、組織市民行動が個人のキャリアに与える影響については、より理論的な検討が必要であることが分かります。この分野の理論的研究では、「組織市民行動の潜在的パラドックス」という考え方が提唱され、善意の行動がなぜ個人にとって負担となってしまうのかについて、説明が試みられています[2]。
このパラドックスの核心にあるのは、人間の時間とエネルギーが有限であるという現実です。誰もが一日24時間という限られた時間の中で働いており、その時間をどのように配分するかによって成果が左右されます。組織市民行動に時間を割くということは、本来の職務遂行に使える時間を削ることを意味します。これをゼロサム関係と呼びますが、一方が増えれば他方が減るという図式です。
問題となるのは、職務遂行の方が組織市民行動よりもキャリア評価において重視されるという場合です。昇進や昇給の判断基準として、売上達成や業績目標のクリアといった測定可能な成果が用いられることが多く、組織市民行動のような定性的な貢献は評価されにくい構造になっています。
この理論的枠組みに基づいて、いくつかの仮説が提示されています。基本となるのは、限られた時間の中で組織市民行動により多くの時間を割いた従業員は、職務遂行に集中した従業員よりもキャリア成果が低くなるという仮説です。これは先ほど紹介した実証研究の結果とも一致しています。
しかし、この関係性は組織の状況によって変化することも指摘されています。組織の報酬制度が成果中心の場合、組織市民行動はキャリア成果に負の作用をもたらしますが、行動プロセスを評価する制度の場合は正の作用をもたらす可能性があります。また、従業員の職務が曖昧で裁量の余地が大きい場合は組織市民行動が評価されやすく、明確に定義された職務の場合は評価されにくいという違いもあります。
組織市民行動の可視性も要因として挙げられています。上司の目に付きやすい種類の組織市民行動は評価につながりやすく、見えにくい場所で行われる行動は評価されにくいという現実があります。これは公平性の観点から問題があるだけでなく、従業員に表面的な行動を促してしまう可能性もあります。
組織市民行動の水準についても仮説が提示されています。適度な組織市民行動はポジティブに評価されるものの、過度に高い水準の組織市民行動はかえってキャリア成果に悪影響を及ぼすというものです。これは、バランス感覚を欠いた行動として捉えられる可能性や、本来の職務への悪影響が懸念されるためです。
さらに、組織市民行動の性質による違いについても言及されており、協調的な行動は好意的に受け取られやすい一方で、現状に挑戦するような行動は負の評価を受けやすいとされています。これは、組織の安定性を重視する管理職の心理を反映したものと考えられます。
時間コストの観点からも検討がなされており、短時間で済む組織市民行動は長時間を要する行動よりも評価されやすいことが指摘されています。これは合理的な判断と言えますが、同時に本当に組織にとって価値のある行動が軽視される可能性も含んでいます。
勤務時間の延長によってこのトレードオフを解決できるという仮説もありますが、これは従業員の負担増加という別の問題を生み出します。また、他者からの返報が期待できる場合は組織市民行動の負の側面が軽減されるという仮説もありますが、これも相手次第という不確実性があります。
これらの理論的考察は、組織市民行動をめぐる問題が単純ではないことを物語っています。組織と個人の利害が必ずしも一致しない問題があり、従業員は自分の置かれた状況を慎重に判断して行動する必要があることが浮き彫りになっています。
組織市民行動の「市民疲労」、支援等で変わるが行動減
組織市民行動の負の側面を理解する上で、注目を集めているのが「市民疲労」という概念です。組織市民行動を継続的に行うことによって生じる心理的・身体的な消耗状態を指しており、従来のストレス研究やバーンアウト研究とは異なる視点を提供しています。
台湾の私立大学で働く教員273名を対象とした研究では、この市民疲労の実態とその発生メカニズムが明らかにされています[3]。この研究では、時期を変えて複数回のアンケート調査が実施され、組織市民行動から市民疲労の発生、そしてその後の行動変化までの一連のプロセスが追跡されました。
市民疲労は、一般的な仕事のストレスやバーンアウトとは区別される概念として定義されています。通常のバーンアウトが職務全般に対する消耗感を表すのに対し、市民疲労は組織市民行動に対してのみ生じる消耗感を指しています。そのため、市民疲労を経験している従業員でも、本来の職務遂行能力には必ずしも影響が現れないという特徴があります。
この研究における発見は、組織市民行動が市民疲労を引き起こすかどうかが、職場環境や状況によって左右されるということでした。組織からの支援をどれだけ感じているか、チーム内での関係性がどの程度良好か、組織市民行動を行うプレッシャーがどの程度あるかといった要因が、市民疲労の発生を左右していました。
組織支援の認知が低い環境では、組織市民行動を行うことが市民疲労の増加につながっていました。従業員が組織から十分にサポートされていないと感じている状況で、さらに自発的な貢献を求められることは、大きな負担として受け止められるということです。逆に、組織支援を強く感じている場合は、同じ組織市民行動を行っても市民疲労は生じにくいことが分かりました。
チーム内での関係性についても同様の傾向が見られました。チームメンバー間の信頼関係や相互支援が充実している環境では、組織市民行動が市民疲労を軽減する作用すら示していました。良好な人間関係の中で行われる貢献行動が、義務や負担としてではなく、自然で満足感のある活動として体験されるためと考えられます。
一方、組織市民行動を行うプレッシャーが高い状況では、その行動が市民疲労を増加させる傾向が確認されました。自発性が重視されるはずの組織市民行動が、実際には強制的な要素を帯びている場合、従業員にとってストレス源となってしまうのです。逆に、プレッシャーが低い環境では、組織市民行動が市民疲労を軽減する効果を示していました。
この研究では、市民疲労がその後の組織市民行動に与える変化についても検討されています。市民疲労を経験した従業員は、その後の組織市民行動の頻度を有意に減少させることが明らかになりました。限られた心理的資源を保護しようとする自然な反応と考えられます。
このプロセスは、資源保存理論と呼ばれる理論によって説明されています。人間は自分の持つ心理的・身体的資源を維持しようとする動機を持っており、資源の枯渇を感じると、それ以上の消耗を避けようとする行動を取るというものです。市民疲労を経験した従業員が組織市民行動を控えるようになるのは、この理論的枠組みで理解することができます。
この研究結果は、組織市民行動の持続可能性について示唆を提供しています。短期的に組織市民行動を促すことは可能かもしれませんが、適切な環境整備を行わなければ、長期的には従業員の疲労と行動の減退を招いてしまう可能性があります。
組織支援やチーム内の良好な関係性は、組織市民行動の負の側面を軽減し、持続可能な貢献行動を可能にする要因であることが明らかになりました。逆に、プレッシャーによって組織市民行動を強要しようとすることは、短期的には効果があっても、長期的には逆効果となり得ることも示されています。
組織市民行動の誠実性、仕事ができる人ほど葛藤や消耗増
組織市民行動の負の側面を考える上で、どのような人がよりその影響を受けやすいのかという問題は重要です。イギリスの銀行の顧客コンタクトセンターで行われた研究では、職務能力の高い従業員ほど組織市民行動による負担を強く感じるという、逆説的な結果が明らかになりました[4]。
この研究では、79名の顧客サービス担当者を対象に、2回の調査が1年間の間隔を置いて実施されました。組織市民行動については上司による評価が用いられ、職務パフォーマンスについては企業の客観的な記録が使用されました。その後、従業員自身による情緒的消耗と仕事–家庭間の葛藤の評価が収集され、これらの関係性が分析されました。
組織市民行動は従来、単一の概念として扱われることが多かったのですが、この研究では行動の種類によって異なる影響があることが明らかになりました。利他主義、誠実性、市民的美徳、礼儀、スポーツマンシップという5つの次元に分けて分析した結果、特に「誠実性」の次元が従業員の負担に強く関連していることが分かりました。
誠実性の組織市民行動とは、例えば定時よりも早く出勤する、休憩時間を短縮する、残業を厭わない、期限を必ず守るといった行動を指します。これらの行動は確かに組織にとって価値のあるものですが、同時に従業員の時間とエネルギーを大きく消費する性質を持っています。
研究の結果、誠実性の組織市民行動は情緒的消耗と強い正の関連を示し、仕事–家庭間の葛藤についても同様の関連が確認されました。時間を多く要する組織市民行動が、従業員の心理的負担と生活への悪循環を生み出すことを意味しています。
一方、礼儀の次元については異なる結果が得られました。同僚に対する丁寧な対応や配慮のある行動は、仕事–家庭間の葛藤を軽減する効果がありました。礼儀正しい行動が比較的時間やエネルギーの消費が少なく、むしろ職場の人間関係を良好にすることで、ストレスを軽減するためと考えられます。
職務パフォーマンスの高さが組織市民行動の負の作用を増幅させるという結果も得られました。誠実性の組織市民行動と職務パフォーマンスの交互作用効果を分析したところ、職務パフォーマンスが高い従業員ほど、誠実性の組織市民行動が情緒的消耗と仕事–家庭間の葛藤に強く関連していることが明らかになりました。
この現象は、能力の高い従業員が置かれた状況を考えると理解できます。優秀な従業員は本来の職務でも高い成果を求められ、同時に組織市民行動についても模範的であることを期待されます。限られた時間の中で両方の期待に応えようとすることで、資源の枯渇が起こりやすくなります。
職務パフォーマンスが低い従業員の場合、このような負の影響は顕著に現れませんでした。これは、もともと職務への投入度が低いか、あるいは組織市民行動への期待度が相対的に低いことが関係していると考えられます。皮肉なことに、組織にとって最も価値のある従業員が、組織市民行動による負担を強く感じているという構造が浮き彫りになりました。
この研究は、組織市民行動の推奨にあたって、従業員の能力や置かれた状況を慎重に考慮する必要があることを示しています。優秀な従業員に対してさらなる貢献を期待することは、短期的には組織にとって利益をもたらすかもしれませんが、長期的にはその従業員の消耗と組織からの離脱を招く危険性があるのです。
脚注
[1] Bergeron, D. M., Shipp, A. J., Rosen, B., and Furst, S. A. (2013). Organizational citizenship behavior and career outcomes: The cost of being a good citizen. Journal of Management, 39(4), 958-984.
[2] Bergeron, D. M. (2007). The potential paradox of organizational citizenship behavior: Good citizens at what cost? Academy of Management Review, 32(4), 1078-1095.
[3] Bolino, M. C., Hsiung, H. H., Harvey, J., and LePine, J. A. (2015). “Well, I’m tired of tryin’!” Organizational citizenship behavior and citizenship fatigue. Journal of Applied Psychology, 100(1), 56-74.
[4] Deery, S., Rayton, B., Walsh, J., and Kinnie, N. (2017). The costs of exhibiting organizational citizenship behavior. Human Resource Management, 56(6), 1039-1049.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。