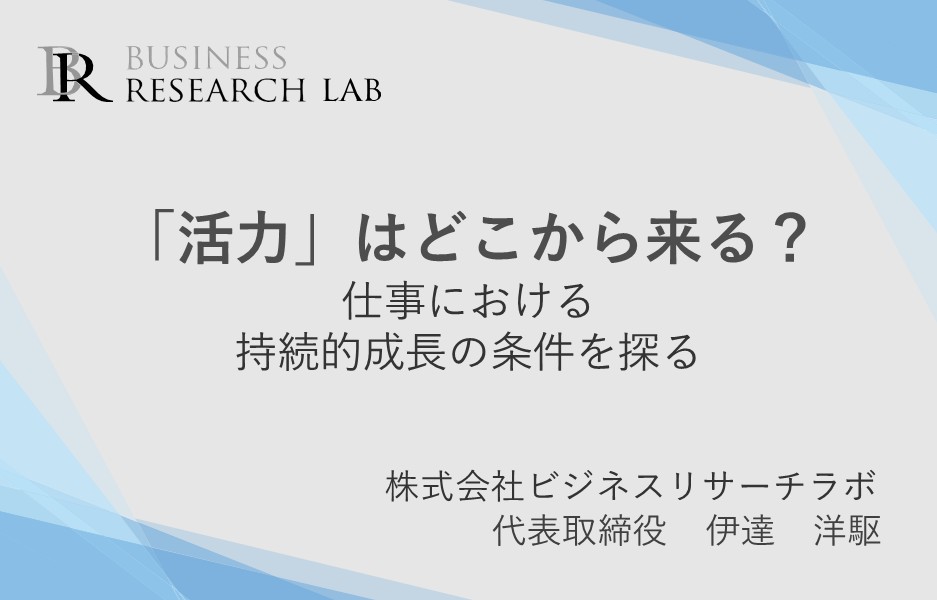2025年10月20日
「活力」はどこから来る?:仕事における持続的成長の条件を探る
仕事の時間が、もしただ義務をこなすだけの退屈なものであったとしたら、人生の豊かさは損なわれてしまうかもしれません。逆に、仕事を通じて自分が生き生きとし、何か新しいことを学び、成長している実感を得られたとしたら、それは素晴らしいことではないでしょうか。
近年、このような「活力」と「学習」を同時に高いレベルで経験している状態が、「スライビング(Thriving)」という概念で呼ばれるようになりました。これは、バーンアウトのような心身の消耗とは対極にある、ポジティブで持続的な心のあり方です。スライビングしている人は、仕事に熱意をもって取り組み、困難な課題にも前向きに挑戦し、高いパフォーマンスを発揮することが分かってきています。
しかし、人がスライビングする条件は、決して一つではありません。ある人にとっては最高の環境が、別の人にとってはそうではないかもしれません。仕事のプレッシャーが、ある側面では私たちの成長を促し、別の側面ではエネルギーを奪うといった、複雑な様相を呈することもあります。私たちはどのような環境で、どのような心のプロセスを経て、この「生き生きと学び続ける状態」に至るのでしょうか。
本コラムでは、スライビングという現象を多角的に解き明かすことを目指します。上司からの支援、個人の内面的な欲求、仕事の特性、職場全体の雰囲気といった、さまざまな要因がどのように絡み合い、私たちの活力と学習の感覚を育んでいくのか。調査研究の結果をたどりながら、そのメカニズムを確認していきます。
家族支援的上司はケア欲求高い部下のスライビングを高める
職場における人間関係は、私たちの働きがいを左右します。中でも、直属の上司との関係は、日々の業務の進めやすさからキャリアの見通しまで、さまざまな面に及ぶものです。近年、上司が部下の仕事と家庭の両立を気遣い、支援する姿勢を見せることが、部下の心身の健康や仕事への満足度を高めることが知られてきました。
こうした上司の支援は、部下が生き生きと学びながら働く「スライビング」という状態にまで結びつくのでしょうか。そのプロセスは、文化や個人の価値観が異なっても同じように見られるのでしょうか。この疑問を探るため、文化的な背景が異なる二つの国、イタリアと中国で調査が行われました[1]。
この調査の目的は、家族を支援する上司の振る舞いが、どのような作用を経て部下のスライビングにつながるのかを明らかにすることでした。研究者たちは、上司の支援が部下の「心理的可用性」を高めるのではないかと考えました。心理的可用性とは、心配事や不安から解放され、目の前の仕事に心身のエネルギーを安心して注ぎ込める状態を指します。この心理的な余裕が生まれることで、仕事での経験やスキルが家庭生活を豊かにする「ワーク・ファミリー・エンリッチメント」という感覚が高まり、最終的に仕事での活力と学習、すなわちスライビングが促進される、という一連の流れを想定しました。
調査は、イタリアの企業10社に勤める従業員156名と、中国の三つの主要都市で働く従業員356名を対象に行われました。どちらの国でも、同じ従業員に対して6ヶ月の時間をおいて2回、アンケート調査を実施しています。1回目の調査では、上司がどれだけ家族支援的な行動(例えば、家庭の事情に配慮してくれる、仕事のスケジュール調整に柔軟に応じてくれるなど)を示しているか、そして部下自身が「他者から気遣われたい、ケアされたい」とどの程度感じているか(ケア欲求)などを尋ねました。6ヶ月後の2回目の調査で、心理的可用性、ワーク・ファミリー・エンリッチメント、スライビングの状態を測定しました。
結果、二つの国で異なる側面と共通する側面が浮かび上がりました。中国のデータでは、研究者たちが想定した通りの連鎖が確認できました。家族支援的な上司の存在が、部下の心理的な余裕(心理的可用性)を生み出し、その余裕が仕事と家庭の好循環(ワーク・ファミリー・エンリッチメント)を促し、その結果としてスライビングが高まるという連鎖が見られたのです。
一方、イタリアのデータでは、家族支援的な上司の振る舞いが、直接的に心理的可用性を高めるという部分は明確ではありませんでした。しかし、両国に共通する、興味深い発見がありました。それは、部下自身の「ケアされたい」という欲求の強さが、プロセス全体を左右するという点です。分析を進めると、ケア欲求が強い従業員ほど、上司からの家族支援がワーク・ファミリー・エンリッチメントを通じてスライビングにつながる、という間接的な結びつきが強まることが分かったのです。
この結果から何が考えられるでしょうか。一つには、上司からの支援という「資源」は、それ自体が自動的に部下の成長や活力に結びつくわけではないということです。その支援が、部下自身の内面的なニーズ、この場合は「気遣われたい」という欲求と合致したときに初めて、その価値が発揮され、心理的な豊かさやスライビングへと転換されていくのかもしれません。どんなに手厚い支援も、受け取る側がそれを求めていなければ、「おせっかい」に感じられたり、あるいはその価値に気づかれなかったりする可能性があります。
また、イタリアと中国での結果の違いは、文化的な背景が仕事に対する価値観や人間関係のあり方にどう関わっているかを考えさせます。例えば、集団の調和を重んじる文化圏では、公私にわたる上司の配慮が自然に受け入れられ、心理的な安心感につながりやすいのかもしれません。対照的に、個人としての自律性を重んじる文化圏では、仕事とプライベートの境界がより明確で、上司の支援が心理的な余裕に直結するとは限らない、という可能性も考えられます。
中国版尺度で、探索がスライビングを高め、役割曖昧が削ぐ
上司の支援が部下のスライビングに結びつくプロセスに文化的な違いが見られる可能性が示されました。このことは、スライビングという概念そのものが、西洋で生まれてきた背景を持つため、異なる文化圏でそのまま通用するとは限らない、という根本的な問いを投げかけます。ある文化で「活力」や「学習」と見なされる心の状態が、別の文化では少し違うニュアンスで捉えられるかもしれません。
この課題に向き合い、中国という特定の文化に焦点を当ててスライビングのあり方を探求した一連の研究があります[2]。この研究は、既存の理論を検証するだけでなく、その前提となる「測定の道具」自体を文化に合わせて作り直すことから始まりました。
この研究の第一の目的は、西洋で開発されたスライビングを測るための質問項目が、中国の働く人々にとっても違和感なく、的確にその心理状態を捉えられるかを検証し、必要であれば修正することでした。研究者たちは、既存の質問項目を中国語に翻訳し、それを組織心理学の専門家や、実際に企業で働く一般の従業員たちに提示しました。そして、「この質問はスライビングという状態をよく表しているか」「活力と学習、どちらの側面を測るものか」「中国の職場文化の中で不自然に聞こえないか」といった点について検討を重ねました。
その結果、元の質問項目の中から、文化的な背景によらず共通して理解でき、かつスライビングの本質を捉えていると判断された、活力に関する4項目と学習に関する3項目、合計7項目からなる中国版のスライビング測定尺度が完成しました。
測定の道具が整ったところで、研究は第二段階へと進みます。この新しい尺度を用いて、中国のさまざまな業種で働く従業員285名を対象にオンライン調査を実施し、何がスライビングを促し、何がそれを妨げるのかを検証しました。特に注目されたのは、個人の内面的な志向と行動、そして職務環境の明確さでした。
具体的には、「新しい知識やスキルを習得すること自体が目標である」という個人の「学習志向目標」、仕事において「新しいやり方を試したり、未知の領域に足を踏み入れたりする」といった「探索行動」、そして「自分の仕事の範囲や責任、期待されている成果がはっきりしない」という「役割曖昧性」の三つが、スライビングにどう関わっているかが分析されました。
その結果、スライビングを育む二つの力と、それを削ぐ一つの力が浮かび上がりました。促進要因として、個人の「学習志向目標」と「探索行動」が、いずれもスライビングと強い結びつきを持っていることが分かりました。自らの成長を願い、新しいことを学ぼうとする意欲が、生き生きと学ぶ状態の源泉となっていました。その意欲を実際の行動に移し、試行錯誤を重ねる探索的な振る舞いが、スライビングを一段と高めていました。さらに分析を進めると、学習志向が探索行動を促し、その探索行動がスライビングにつながるという間接的な経路も確認できました。
他方で、阻害要因として「役割曖昧性」がスライビングを低下させることが明らかになりました。自分が何をすべきか、どこまでが自分の責任で、何を期待されているのかが不明確な状況では、人は活力と学習の両方を失いやすくなります。自分が進むべき方向が霧の中にあるような状態では、安心してエネルギーを注いだり、新しい挑戦から学んだりすることが難しくなるのは、想像に難くありません。
時間圧・学習負荷は学びを増やすが活力とは関連なし
これまでのところで、上司の支援や役割の明確さといった、いわば「ポジティブな」要因がスライビングを育むことを見てきました。では、仕事におけるプレッシャーや負荷といった、一見すると「ネガティブな」要因は、常にスライビングを妨げるだけなのでしょうか。私たちは日々の仕事の中で、締め切りに追われたり、新しいスキルや知識の習得を迫られたりすることがあります。
こうした状況はストレスフルであり、心身を消耗させるように思われます。しかし、本当にそうなのでしょうか。あるいは、これらの負荷が私たちの心に及ぼす作用は、もっと複雑なものなのでしょうか。この問いに、日々の心の動きを詳細に追跡することで迫った研究があります[3]。
この研究が試みたのは、時間的な切迫感(タイムプレッシャー)や、新しいことを学ばなければならないという要求(学習要求)といった、いわゆる「チャレンジ・ストレッサー」が、日々のスライビング、特にその構成要素である「活力」と「学習感」にどのような変化をもたらすかを解き明かすことでした。チャレンジ・ストレッサーとは、困難ではあるものの、乗り越えることで個人の成長や達成感につながる可能性を秘めたストレス要因を指します。
研究者たちは、これらのストレス要因が、スライビングの二つの側面である活力と学習感に対して、必ずしも同じ方向に作用するわけではないのではないか、という仮説を立てました。
この仮説を検証するために調査が行われました。対象となったのは、専門的な知識やスキルを要する仕事に従事する知識労働者124名です。参加者には、連続する5日間、1日に3回、短いアンケートに回答してもらいました。具体的には、昼前に、その日の仕事で感じているタイムプレッシャーや学習要求のレベルを測定します。次に午後には、それらのプレッシャーを、自分にとっての「挑戦の機会」と捉えているか、それとも目標達成を「妨害するもの」と捉えているかを尋ねます。そして一日の仕事の終わりに、その日に感じた「活力」と「学習感」を測定しました。
結果としては、タイムプレッシャーも学習要求も、その日の「学習感」を有意に高めることが分かりました。締め切りが迫っていたり、新しいことを学ぶ必要があったりする日ほど、参加者たちは「自分は今日、何かを学んだ、成長した」と感じていました。この結果は、チャレンジ・ストレッサーが成長の機会となりうるという考えを裏付けるものです。
しかし、もう一方の側面である「活力」については、異なる結果が出ました。タイムプレッシャーや学習要求は、活力に対して統計的に明確な影響を及ぼしていませんでした。負荷が高い日でも、必ずしもエネルギーが奪われるわけではなかったのです。これは、負荷が学習感を高める一方で、活力を削ぐという単純なトレードオフの関係にはないことを意味します。
分析を進めると、ストレッサーが学習感を高めるプロセスは、参加者がそのストレッサーを「挑戦の機会」と肯定的に捉えることによって媒介されていることが分かりました。プレッシャーを乗り越えるべき課題と認識することが、学習の実感につながっていたのです。一方で、学習要求が「妨害するもの」と認識された場合には、活力が低下する経路も見られました。
心理的安全が活力を媒介して創造的関与を高める
これまで、上司の支援、個人の志向、仕事の特性といった要因が、スライビングという状態にどのように関わるかを見てきました。これらの要因は、個人の内面や、個人と仕事との直接的な関係性に焦点を当てたものでした。視点を少し広げ、職場全体の「雰囲気」が私たちの心、特にスライビングの一翼を担う「活力」にどう作用し、それがどのような行動につながっていくのかを探求したいと思います。「この場所では、安心して自分らしくいられる」という感覚が、私たちの内に秘めたエネルギーを解き放つことはあるのでしょうか。この問いに、創造性という観点から光を当てた研究があります[4]。
この研究が解明しようとしたのは、「心理的安全性」が、従業員の「創造的な仕事への関与」に結びつく、そのプロセスです。心理的安全性とは、ある集団の中で、対人関係におけるリスク、例えば「こんな意見を言ったら馬鹿にされるかもしれない」「失敗したら非難されるだろう」といった恐れを感じることなく、安心して発言したり行動したりできると信じられている状態を指します。
研究者たちは、心理的安全性が直接的に創造性を高めるだけでなく、その間に「活力」という心理的な状態が介在するのではないか、というモデルを考えました。安心できる環境がまず人の心を生き生きとさせ、その高まったエネルギーが創造的な取り組みへの原動力になる、という連鎖です。
この仮説を検証するため、大学院に通いながら実際に企業などで働いている社会人学生を対象に、時間を空けて2回の調査が行われました。1回目の調査で、参加者たちが自分の職場で感じている心理的安全性のレベルと、その時点での個人の活力の度合いを測定しました。その2週間後に2回目の調査を行い、参加者が新しいアイデアの提案や問題解決といった「創造的な仕事に、どれだけ時間と労力を注いでいるか」を尋ねました。
結果的に、研究者たちの想定した連鎖が裏付けられました。従業員が職場で心理的安全性を高く感じているほど、その人の活力も高い水準にあることが確認されました。失敗を恐れずに意見を言えるような安心感が、個人の内なるエネルギーを高めていました。この活力が高い人ほど、創造的な仕事への関与も高いことが分かりました。生き生きとしたエネルギーに満ちている状態が、新しいことに挑戦しようという意欲や行動につながっていたのです。
重要な発見は、この「活力」が、心理的安全性と創造的関与との間をつなぐ役を担っていた点です。心理的安全性が高いからといって、それが自動的に創造的な行動に結びつくわけではありません。その間に「活力が湧き上がる」というプロセスを挟むことで、その結びつきが強固なものになっていました。
脚注
[1] Russo, M., Buonocore, F., Carmeli, A., and Guo, L. (2018). When family supportive supervisors meet employees’ need for caring: Implications for work-family enrichment and thriving. Journal of Management, 44(4), 1678-1702.
[2] Jiang, Z., Jiang, Y., and Nielsen, I. (2019). Workplace thriving in China. International Journal of Manpower, 40(5), 979-993.
[3] Prem, R., Ohly, S., Kubicek, B., and Korunka, C. (2017). Thriving on challenge stressors? Exploring time pressure and learning demands as antecedents of thriving at work. Journal of Organizational Behavior, 38(1), 108-123.
[4] Kark, R., and Carmeli, A. (2009). Alive and creating: The mediating role of vitality in the relationship between psychological safety and creative work involvement. Journal of Organizational Behavior, 30(6), 785-804.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。