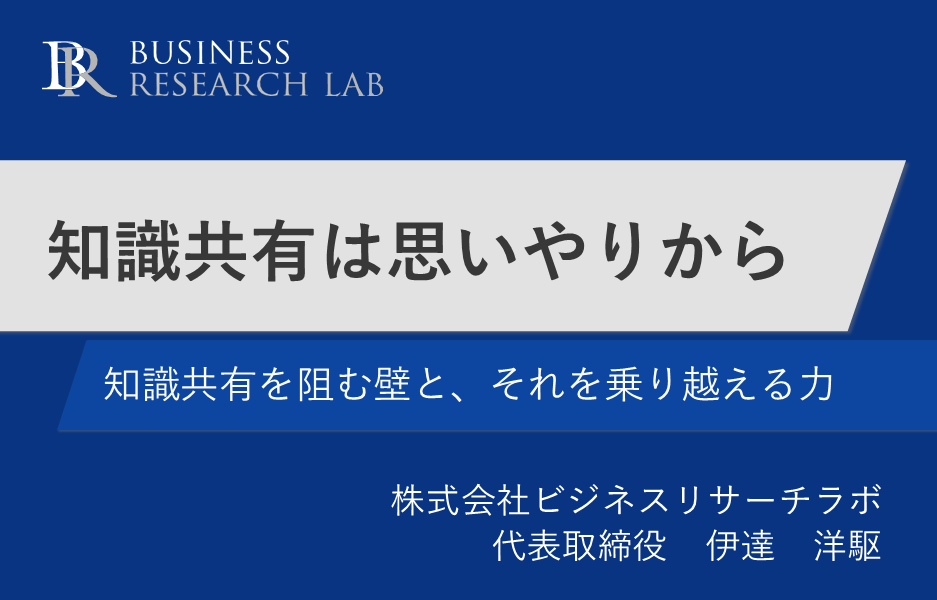2025年10月20日
知識共有は思いやりから:知識共有を阻む壁と、それを乗り越える力
組織マネジメントにおいて、従業員同士の知識共有は競争力向上の鍵とされています。しかし実際の職場では、従業員が意図的に知識を隠す現象が見られます。「知識隠蔽」というこの行動は、組織の学習能力や創造性を損なう要因として近年注目されています。
知識隠蔽とは、同僚や部下が求める情報や専門知識を、意図的に教えなかったり、曖昧な回答でごまかしたりする行動を指します。表面的には協力的に見えても、有用な情報を伝えない、あるいは間違った情報を提供するといった形で現れることもあります。
この現象の背景には、職場における複雑な人間関係や組織構造が関わっています。上司からの不当な扱い、組織内の政治的な駆け引き、過度な業務負荷など、様々な要因が従業員の知識隠蔽行動を誘発する可能性があります。一方で、個人の価値観や倫理観、専門職としての誇り、他者への共感能力などが、こうした負の行動を抑制する要因として機能することも明らかになってきています。
本コラムでは、知識隠蔽を促進する要因と阻害する要因を探究します。職場でのリーダーシップのあり方、従業員の個人的特性、組織文化などが、どのようにして知識の流れを左右するのかを見ていきます。
「目には目を」と考える人ほど、虐待に知識隠蔽で報復
職場における上司と部下の関係性は、知識隠蔽行動に影響を及ぼします。パキスタンの通信業界と銀行業界で働く364名の従業員を対象とした調査では、上司による虐待的な行動が従業員の知識隠蔽を促進し、創造性を低下させることが明らかになりました[1]。
この研究で取り上げられた侮辱的管理とは、上司が部下に対して継続的に敵対的で侮辱的な態度を取ることを指します。公然と批判する、怒鳴りつける、無視する、不公平な扱いをするといった行動が該当します。研究者たちは、このような監督スタイルが従業員にどのような心理的・行動的変化をもたらすかを、異なる時期に複数回の調査を実施して追跡しました。
調査の結果、虐待的な行動を受けた従業員は、上司や同僚に対して知識を隠す行動を取りやすくなることが判明しました。この関係性には個人差があり、「負の互酬性信念」と呼ばれる考え方を強く持つ人ほど、知識隠蔽で報復する傾向が顕著に現れました。
負の互酬性信念とは、「目には目を、歯には歯を」という発想に近く、自分が不当な扱いを受けたら相手にも同じように悪い行動で返すべきだという考え方です。このような信念を持つ従業員は、虐待的な行動を受けた際に、直接的な反抗ではなく、知識を隠すという形で報復行動を取ることが分かりました。
この現象の背景には、転嫁攻撃理論と呼ばれる心理学的メカニズムが働いています。従業員は上司に直接立ち向かうことが難しいため、攻撃の矛先を他の対象に向けるのです。知識隠蔽は、表面的には問題視されにくい一方で、組織全体の知識流通を阻害する巧妙な報復手段として機能します。
研究では、知識隠蔽が従業員の創造性に与える影響についても調べられました。知識を隠す行動を取る従業員は、同僚や部下からの創造性評価が低くなることが確認されました。これは、創造的なアイデアの創出には他者との知識交換が不可欠であり、知識隠蔽がそのプロセスを妨げるためと考えられます。
この研究から浮かび上がってくるのは、職場での虐待的な行動が直接的な被害者だけでなく、組織全体の知識循環システムを破綻させる危険性です。虐待を受けた従業員の報復的な知識隠蔽は、組織の創造性や革新性を損なう結果をもたらすでしょう。
報復を禁じる倫理観が、虐待されても知識隠蔽をさせない
虐待的な行動を受けても、すべての従業員が知識隠蔽で報復するわけではありません。パキスタンのホテル業界で働く224名の従業員を対象とした別の研究では、個人の価値観や倫理観が知識隠蔽行動を抑制する要因となることが明らかになっています[2]。
この調査では、イスラム労働倫理(Islamic Work Ethics)と呼ばれる価値体系に焦点が当てられました。イスラム労働倫理とは、イスラム教の教義に基づく働き方の指針で、誠実さ、協力、知識の共有、社会への貢献などを重視し、報復や欺瞞を禁じる倫理観です。研究者たちは、この倫理観が強い従業員ほど、虐待的な行動を受けても知識隠蔽に走りにくいのではないかと仮説を立てました。
調査は3つの時期に分けて実施され、侮辱的管理の程度、従業員の対人的公正感、イスラム労働倫理の強さ、知識隠蔽行動の頻度などが測定されました。対人的公正感とは、上司や同僚から尊重され、公平に扱われていると感じる程度を指します。
研究結果は仮説を裏付けるものでした。侮辱的管理を受けた従業員であっても、イスラム労働倫理を強く持つ人は知識隠蔽行動を取りにくいことが証明されました。逆に、この倫理観が弱い従業員は、虐待的な扱いを受けると知識を隠す行動に出る可能性が高まりました。
メカニズムの分析では、侮辱的管理が従業員の対人的公正感を損なうことで知識隠蔽を促進することも判明しました。上司から不当な扱いを受けると、従業員は職場での人間関係全般に対して不信感を抱き、その結果として知識を共有することへの意欲を失うのです。しかし、強固な倫理観を持つ従業員は、このような状況下でも知識共有への姿勢を維持することができました。
イスラム労働倫理が知識隠蔽を抑制するメカニズムには、いくつかの要素が関わっています。第一に、この倫理観では知識を独占することは社会に対する裏切りと見なされます。第二に、困っている同僚を助けることは宗教的義務と位置づけられています。第三に、報復的な行動は倫理的に禁じられており、受けた害に対しても寛容な態度を取ることが求められます。
研究では、侮辱的管理を受けた従業員の中でも、イスラム労働倫理が強い人と弱い人の間に違いが観察されました。倫理観の強い従業員は、上司からの不当な扱いに対して感情的には傷つきながらも、同僚や部下との知識共有は継続しました。一方、倫理観の弱い従業員は、虐待的な扱いを受けると職場全体に対して防衛的になり、知識を隠すことで自分を守ろうとする行動を取りました。
専門職としての誇りが、社内政治による知識隠蔽を防ぐ
職場での政治的な駆け引きや権力争いは、知識隠蔽を引き起こす別の要因として機能します。パキスタンの3つの大規模公立大学で働く316名の教員とその上司を対象とした研究では、組織内政治が知識隠蔽を通じて従業員の創造性を損なうプロセスと、専門職コミットメントがそれを食い止める機能について調べられています[3]。
組織内政治とは、個人や派閥が自己利益を追求するために行う非公式な権力闘争を指します。昇進や資源配分において公正さよりもコネや駆け引きが優先される状況、上層部の意思決定プロセスが不透明である状況、評価基準が曖昧で恣意的な判断がまかり通る状況などが典型例です。このような環境では、従業員は自分の立場を守るために知識を武器として使おうとする誘惑に駆られます。
調査対象となった大学教員たちは、研究や教育に関する豊富な専門知識を持つ職業集団です。研究者たちは、彼ら彼女らの専門職コミットメント、すなわち自分の専門分野への愛着や誇り、職業的使命感の強さが、政治的環境下での知識隠蔽行動にどのような影響を与えるかを分析しました。
結果、組織内政治を強く感じている教員ほど知識隠蔽行動を取りやすいことが確認されました。政治的な環境では、知識は競争優位を保つための資源と見なされ、同僚に教えることで自分の地位が脅かされる可能性があると認識されるためです。知識を隠す教員は上司からの創造性評価が低くなることも明らかになりました。
しかし、この関係性には個人差がありました。専門職コミットメントが高い教員は、政治的な環境に置かれても知識隠蔽に走る可能性が低いことが見えてきました。専門職コミットメントとは、自分の専門分野に対する深い愛着、専門家としての倫理観、学問や教育への使命感などを包含する概念です。
専門職コミットメントが知識隠蔽を抑制するメカニズムには、複数の心理的要因が関わっています。専門家としての誇りが、短期的な政治的利益よりも長期的な専門性の発展を優先させます。知識を共有し、学問コミュニティ全体の発展に貢献することが、専門家としての存在意義とつながっています。
専門職倫理が利己的な行動を抑制します。教育者として学生の成長を支援し、研究者として学問の進歩に寄与するという使命感が、個人的な損得勘定を超えた行動原理として機能します。同僚の質問に対して知識を隠すことは、この使命感と矛盾する行為として認識されます。
この研究が示すのは、専門職としてのアイデンティティと誇りが、組織の政治的混乱に対する防波堤として機能するということです。外部環境が不安定になっても、専門家としての核となる価値観が揺らがなければ、建設的な知識共有行動を維持できるのです。
相手の身になる力が、多忙による知識隠蔽を食い止める
日々の業務における時間的プレッシャーは、現代の職場で一般的なストレス要因の一つです。ヨーロッパの保険会社の従業員285名を対象とした調査研究とスロベニアの大学生を用いた実験研究では、時間不足が知識隠蔽を引き起こすメカニズムと、それを緩和する個人特性について検証されています[4]。
時間的プレッシャーとは、与えられた時間では業務を完了できないという主観的な感覚や、迫り来る締め切りによる心理的負担を指します。研究者たちは、資源保存理論という枠組みを用いてこの現象を分析しました。この理論によれば、人は限られた心理的・物理的資源を効率的に配分しようとし、一つの資源(時間)が不足すると、他の資源(知識や注意力)を節約しようとする行動を取ります。
保険会社での調査では、時間的プレッシャーを強く感じている従業員ほど、同僚からの質問に対して知識隠蔽行動を取りやすいことが確認されました。忙しい状況では、丁寧に知識を教える時間と労力を惜しみ、曖昧な答えでごまかしたり、「知らない」と嘘をついたりする頻度が増加したのです。
しかし、すべての従業員が同じように反応したわけではありません。向社会的動機と他者視点取得能力が高い従業員は、時間的プレッシャー下でも知識隠蔽に走りにくいことが明らかになりました。
向社会的動機とは、他者を助けたい、組織全体の利益に貢献したいという内発的な動機を指します。この動機が強い人は、自分が忙しくても同僚の困りごとを軽視せず、可能な限り協力しようとします。彼ら彼女らにとって知識共有は負担ではなく、職場での人間関係を豊かにし、組織の成果向上に寄与する価値ある活動として認識されています。
他者視点取得能力は、相手の立場や気持ちを理解する認知的スキルです。この能力が高い人は、同僚が知識を求めている背景や切迫感を敏感に察知し、たとえ自分が忙しくても相手のニーズに応えようとします。彼ら彼女らは質問してきた同僚の状況を想像し、その人にとって情報がどれほど重要かを理解することができます。
実験研究では、これらの関係性がより明確に確認されました。時間的プレッシャーを人為的に操作した状況で、向社会的動機の高い参加者は低い参加者よりも知識隠蔽行動を取りにくいことが証明されました。向社会的動機が知識隠蔽を抑制する効果は、他者視点取得能力を通じて発揮されることも明らかになりました。
このメカニズムは次のように説明できます。向社会的動機が高い人は、困っている同僚を見ると自然に相手の立場に立って考えようとします。その結果、相手がどれだけその情報を必要としているか、自分の協力がどれだけ価値があるかを具体的に理解できるようになります。この理解が、時間的プレッシャーによる知識の出し惜しみを抑制し、協力的な行動を促進するということです。
一方、向社会的動機が低く他者視点取得能力も乏しい人は、時間的プレッシャー下では自分のことで精一杯になってしまいます。同僚の質問を面倒な割り込みとしか感じられず、適当にあしらって早く自分の業務に戻ろうとします。彼ら彼女らには相手の困り具合や情報の緊急性が見えていないため、知識隠蔽に対する心理的抵抗も生まれません。
この研究が提供する洞察は、職場における知識流通を支える人間的要素の重要性です。技術的なツールや制度的な仕組みだけでは限界があり、個人の他者への共感と理解が知識共有の基盤となることが示されています。時間に追われる現代の職場環境においても、相手の身になって考える能力と他者を助けたいという気持ちが、組織の知識循環を維持するきっかけとなっています。
脚注
[1] Jahanzeb, S., Fatima, T., Bouckenooghe, D., and Bashir, F. (2019). The knowledge hiding link: A moderated mediation model of how abusive supervision affects employee creativity. European Journal of Work and Organizational Psychology, 28(6), 810-819.
[2] Khalid, M., Bashir, S., Khan, A. K., and Abbas, N. (2018). When and how abusive supervision leads to knowledge hiding behaviors: An Islamic work ethics perspective. Leadership & Organization Development Journal, 39(6), 794-806.
[3] Malik, O. F., Shahzad, A., Raziq, M. M., Khan, M. M., Yusaf, S., and Khan, A. (2019). Perceptions of organizational politics, knowledge hiding, and employee creativity: The moderating role of professional commitment. Personality and Individual Differences, 142, 232-237.
[4] Skerlavaj, M., Connelly, C. E., Cerne, M., and Dysvik, A. (2018). Tell me if you can: Time pressure, prosocial motivation, perspective taking, and knowledge hiding. Journal of Knowledge Management, 22(7), 1489-1509.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。