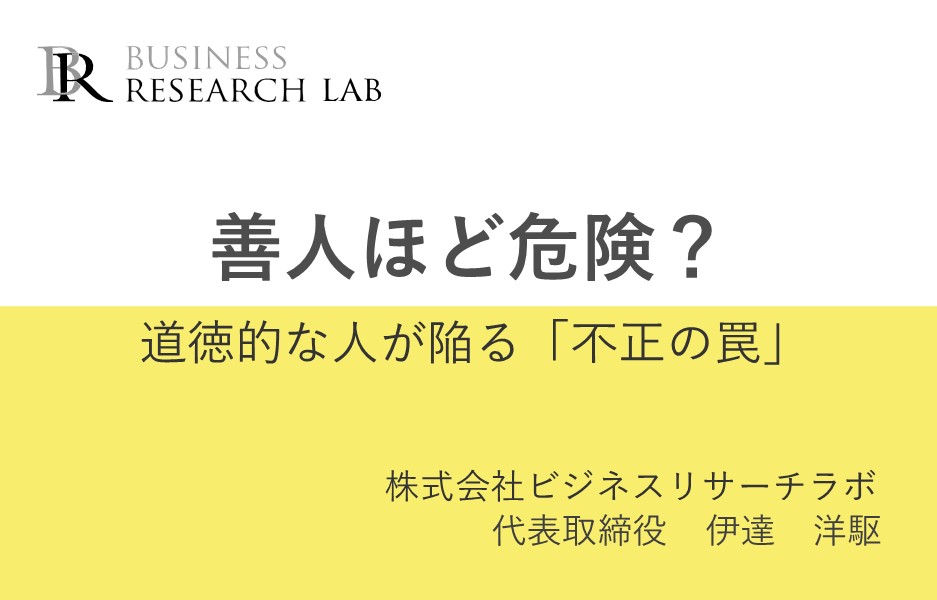2025年10月17日
善人ほど危険?:道徳的な人が陥る「不正の罠」
清廉潔白で、誰よりも道徳を重んじる人。私たちはそうした人物を前にしたとき、安心感を覚えます。不正や裏切りといった行いとは遠い存在だと信じ、組織の規範や倫理を託すにふさわしいと考えるのが自然な感覚でしょう。社会が「良い人」に寄せる期待は大きく、その存在は組織の健全性を示す証しと見なされます。しかし、もしその「高い道徳心」が、かえって不正行為の引き金になってしまうとしたら、どうでしょうか。
にわかには信じがたいこの逆説は、私たちが抱く人間観を揺さぶるかもしれません。人の心は、私たちが思うほど単純でも、一貫したものでもないようです。ある状況では鋼のように固い倫理観が、別の状況では驚くほどたやすく歪んでしまう。善意が、意図せずして悪意に転化してしまう。こうした現象は、決して特殊な個人の問題ではなく、人間の心理に潜むメカニズムによって引き起こされることが少しずつ見えてきました。
本コラムでは、そうした人間の道徳性が持つ複雑で多面的な側面に光を当てていきます。科学的な知見をたどりながら、「道徳的な人」が成果報酬のために嘘をつきやすくなる心理や、強い信念がかえって不正を後押しする仕組みを解き明かしていきます。理想的なリーダーシップが、なぜ組織のための不正を誘発しうるのか。「良い人」であることの危うさとは何か。この問いを通して、個人と組織の倫理を、より深く、現実的に見つめ直すきっかけを提供できればと思います。
道徳的な人ほど、成果報酬に釣られて嘘をつきやすい
人の行動は、その人が置かれた状況によって変わることがあります。普段は穏やかな人が、極度のプレッシャーのもとで攻撃的になったり、倹約家が、特別な日には気前よくお金を使ったりするのは、誰もが経験したり見聞きしたりすることでしょう。「状況の力」は、私たちの道徳的な振る舞いに関しても例外ではありません。「自分は道徳的な人間でありたい」という内なる声は、状況によって強まったり、あるいはかき消されたりします。この心の揺らぎを、いくつかの実験を通して検証した研究があります[1]。
研究の出発点にあるのは、「人は誰でも、心の中に様々な自分を持っている」という考え方です。例えば、「学生としての自分」「友人としての自分」「家族の一員としての自分」など、場面に応じて異なる自己の側面が意識にのぼります。その中の一つに、「道徳的な人間としての自分」という自己認識、すなわち「道徳的アイデンティティ」が存在します。この道徳的アイデンティティを、自分という人間の中心に据えている人もいれば、そうでない人もいます。研究者たちは、この道徳的アイデンティティの中心性の度合いと、その時々の状況が、人の行動にどのように結びつくのかを明らかにしようと試みました。
道徳的な事柄に意識を向けることが、行動にどのような変化をもたらすかを探る実験が行われました。参加した大学生たちは、二つのグループに分けられます。一方のグループには、宗教的な道徳律である十戒を思い出せるだけ書き出してもらい、もう一方のグループには、最近読んだ本について書き出してもらいました。これは、前者のグループの心の中で「道徳」という概念を活性化させるための仕掛けです。その後、全員に架空の企業のマネージャーの立場になってもらい、利益にはならないものの社会的には意義のある活動(企業の社会的責任活動)に、会社の資源をどれくらい投じるかを決めてもらいました。
その結果、十戒について考えたグループは、本について考えたグループに比べて、より多くの資源を社会貢献活動に投じる意思を示しました。道徳的な事柄に触れることで、人々の心の中の「道徳的な自分」が表に出てきて、行動を後押ししたと考えられます。
この実験ではもう一つ、興味深い点が確認されました。もともと「自分は道徳的な人間だ」という自己認識が非常に強い人たちにおいては、十戒を思い出すという行為の効果があまり見られなかったのです。これは、普段から道徳性が自己の中心にあり、常に活性化されているため、追加的な刺激を受けても行動が大きくは変わらなかったからだと解釈できます。道徳的アイデンティティが高い人は、特別なきっかけがなくても、自ずと道徳的な行動を取りやすい素地を持っていると言えるかもしれません。
状況が変わり、自己の利益を追求する場面に直面したとき、この道徳的アイデンティティの高さはどのように作用するのでしょうか。これを検証するために、次のような交渉実験が設計されました。
参加者は二人一組で、求人面接の採用担当者と応募者の役を演じます。採用担当者役の参加者には、この交渉でできるだけ低い給与で応募者と合意できれば、それに応じた報酬がもらえる、というルールが伝えられました。そして、交渉を有利に進めるための「切り札」として、この求人には実は将来性がなく、短期間で打ち切られる予定だという内部情報が与えられます。この不利な情報を正直に応募者に伝えるか、それとも隠して、あるいは嘘をついてでも低い給与で契約を結ぶか。ここに、倫理的な葛藤が生まれます。
この実験で、参加者の一部には、交渉の成果に応じて金銭的なボーナスが支払われる「成果報酬条件」が設定され、他の参加者には、交渉結果にかかわらず一定の確率で謝礼がもらえる「抽選条件」が設定されました。この二つの条件を比較したところ、成果報酬を提示された人の方が、相手に嘘をつこうとする意図が強く、実際に嘘をつく行動も多く観察されました。金銭的なインセンティブが、自己利益の追求を促し、倫理的なためらいを乗り越えさせました。
ここで重要な発見は、この現象が、もともと道徳的アイデンティティが高いと自己評価していた人たちの間で、よりはっきりと現れたという点です。道徳的であろうとする意識が高い人ほど、成果報酬という「エサ」を目の前にしたときに、かえって嘘をつきやすくなったのです。これは一体どういうことなのでしょうか。
研究者たちは、この逆説的な結果を次のように説明しています。道徳的アイデンティティが高い人にとって、「道徳的であること」は自己の根幹をなす重要な価値です。そこに、「自己の利益を最大化せよ」という成果報酬の目標が提示されると、心の中で二つの価値が激しく衝突します。
この強い内的な葛藤は、かえって一時的に道徳的な自己認識を脇に追いやる働きをします。そして、「これはビジネスの交渉なのだから、利益を追求するのは当然だ」といったように、状況を限定的に解釈することで自己の行動を正当化し、嘘をつくという非倫理的な行動へのハードルが下がってしまうのです。道徳性が高いがゆえに葛藤が深まり、その葛藤から逃れるために、かえって非倫理的な選択肢に飛びついてしまう、という心のメカニズムが考えられます。
一方で、道徳性が常に意識される環境にあれば、その強さが維持されることも別の実験で示されています。他者と協力してお金を出し合い、それを増やして分配する、という公共財ゲームにおいて、道徳的な言葉に繰り返し触れていたグループでは、たとえ他の参加者が裏切って自分の利益だけを追求するようになっても、道徳的アイデンティティが高い人は協力的な行動を続けやすいことがわかりました。
強い道徳心は、判断次第で、かえって不正を後押しする
人が置かれた状況、特に自己利益が絡む場面で、高い道徳意識が予期せぬ形で不正につながる可能性を見てきました。今回は、視点を個人の内面、とりわけ「何をもって正しい行動とするか」という判断の「ものさし」に転じてみたいと思います。道徳的でありたいと強く願う気持ちが、その人固有の判断基準と結びついたとき、一体どのような振る舞いとして現れるのでしょうか。ここにもまた、私たちの直感に反するような、複雑な心の働きが隠されています。
この問題を解き明かすため、ある研究では「道徳的判断」と「道徳的アイデンティティ」という二つの異なる心理的な要素が、どのように絡み合いながら実際の行動を生み出すのかが検証されました[2]。ここで言う「道徳的判断」とは、ある行為の善悪を考える際の思考のスタイルのことです。研究では、これを大きく二つのタイプに分けました。
一つは「形式主義」と呼ばれるもので、ルールや規範、義務といった決まり事を絶対的な基準として、それに従うことを正しいと考える立場です。もう一つは「結果主義」で、行為そのものよりも、それがもたらす結果の良し悪しによって善悪を判断する立場です。「皆のためになるなら、多少のルール違反は許される」と考えるのが、この結果主義の一例です。
一方で「道徳的アイデンティティ」は、先ほども触れたように、「自分は道徳的な人間だ」という自己認識の強さを指します。これも二つの側面に分けて捉えられました。一つは「内在化」で、思いやりや公正さといった道徳的な価値を、心から自分自身のものとして受け入れている度合いです。もう一つは「顕示化」で、社会やまわりの人から道徳的な人間として見られたいという欲求の強さを示します。
研究者たちは、これらの要素が組み合わさることで、人の行動がどのように変わるのかについて、一つのモデルを考えました。その鍵となるのが、「社会的合意」という概念です。これは、ある行動が道徳的か非道徳的かについて、社会の意見がどれくらい一致しているかという度合いを指します。例えば、「慈善団体に寄付をする」という行動は、ほとんどの人が善いことだと考えるでしょう。このように社会的合意が高い行動の場合、人はあまり深く考えなくても、「道徳的な自分」でありたいという気持ち(道徳的アイデンティティ)から、自然と行動に移しやすいと予測されます。
問題は、社会的合意が低い、善悪の判断が人によって分かれるようなグレーゾーンの行動です。例えば、学生の「カンニング」がこれにあたります。絶対に許されないと考える人もいれば、成績のためには仕方がないと考える人もいるかもしれません。このような場面では、まずその人の「道徳的判断」のスタイルが、行動の方向性を決めると考えられます。形式主義の人は「ルール違反だからダメだ」と考え、結果主義の人は「単位を取るという良い結果のためなら」と考えるかもしれません。道徳的アイデンティティの高さは、その決定された方向への行動を「増幅させる」エンジンのような働きをするのではないか、と仮説が立てられました。
この仮説を検証するため、大学生を対象とした調査が行われました。参加者たちの道徳的判断のスタイル(形式主義か結果主義か)、道徳的アイデンティティの強さ、そして過去にカンニングをした経験の頻度が尋ねられました。分析の結果、明らかになったのは、結果主義的な判断をする傾向が強い学生ほど、カンニングの経験が多いという関係でした。そして、この関係は、道徳的アイデンティティを内面的に強く持っている学生において、より顕著に見られたのです。
これは重要な点を含んでいます。「良い結果のためなら手段は問わない」という判断基準を持つ学生が、同時に「自分は思いやりがあり、公正な人間だ」と強く信じている場合に、より積極的にカンニングという不正行為に及んでいたということを意味するからです。高い道徳意識が、不正を思いとどまらせるブレーキになるのではなく、むしろアクセルとして機能してしまっています。
この現象の背後にある心理的なメカニズムは、次のように考えられます。高い道徳的アイデンティティを持つ人は、「自分は一貫性のある人間でありたい」「自分の信条に沿って行動したい」という強い動機を持っています。この動機自体には、善悪の色はありません。それは純粋なエネルギーのようなものです。もし、その人が「結果の最大化」を正しいことだと信じる判断基準を採用した場合、そのエネルギーは、その基準に一貫して従うために使われます。
その結果、カンニングという手段が「単位取得」という目標達成のために合理的であると判断されれば、ためらうことなくその行動を実行に移してしまうのです。道徳的であろうとする強い思いが、自らが採用した判断基準を忠実に実行させる力となり、不正行為を後押しするという皮肉な構造があります。
同様のパターンは、社会人を対象とした調査でも確認されました。職場における様々な倫理的なジレンマ場面において、道徳的アイデンティティが高い人は、自らの判断スタイル(形式主義か結果主義か)に、より忠実な行動選択をすることがわかったのです。
理想的な上司は、会社への忠誠心から不正を誘発しうる
これまでの議論で、個人の道徳性が状況や判断基準によって複雑に揺れ動く様を見てきました。私たちが日々多くの時間を過ごす職場において、状況や判断基準に大きな影響を与える存在は、おそらく直属の上司でしょう。中でも、高いビジョンを掲げ、部下を鼓舞し、一人ひとりに成長の機会を与えようとする「理想的なリーダー」は、倫理的で健全な職場環境を築く上で、頼りになる存在に思えます。そのカリスマ性と配慮深さは、部下のやる気を引き出し、組織全体のパフォーマンスを高める力があると信じられています。
しかし、その輝かしいリーダーシップの光の裏に、意図せずして不正を生み出す影が潜んでいるとしたら、私たちはその事実をどう受け止めるべきでしょうか。
この問いに正面から向き合った研究があります。研究者たちが焦点を当てたのは、「変革型リーダーシップ」と呼ばれる、まさに理想像とされるリーダーシップスタイルです[3]。このリーダーシップが、結果として「会社のためになる」と信じて行われる不正行為、すなわち「非倫理的向組織行動」を引き起こしてしまうのではないかという可能性を探りました。ここで言う不正行為とは、個人の私利私欲のためではなく、あくまで自社や自部門の利益を守るため、あるいは目標を達成するために行われる、データの改ざんや顧客への不誠実な説明、競合他社の不利になるような情報の流布といった行動を指します。
研究者たちが描いたのは、次のような心の連鎖反応です。まず、魅力的でビジョンにあふれたリーダーは、部下の心に「この人のため、この会社のために貢献したい」という強い気持ちを育みます。これは、組織の成功をまるで自分自身の成功のように感じ、組織の目標達成に深くコミットするようになる状態です。この組織への強い一体感は、通常であれば高いモチベーションやチームワークといった望ましい結果につながります。
しかし、この一体感が過剰になると、副作用が生じ始めます。組織への忠誠心が高まるあまり、「会社のためならば、多少のルール違反やごまかしも許されるのではないか」という考えが頭をもたげるようになります。組織の目標が至上命題となり、それを達成するためには手段を選ばないという思考に陥りやすくなるのです。その結果、本来であれば倫理的に許されないはずの行動に、手を染めてしまう。このように、理想的なリーダーシップが、組織への同一視を介して、結果的に不正行為への扉を開いてしまうのではないか、というのが研究者たちの立てた仮説でした。
この仮説を検証するため、様々な企業で働く従業員を対象とした調査が、時間を置いて複数回にわたって実施されました。参加者には、自身の上司がどれだけ変革型リーダーシップを発揮しているか、自分がどれだけ会社と一体感を感じているか(組織アイデンティフィケーション)、そして「会社のためなら不正も厭わないか」という意図がどの程度あるかを、それぞれ尋ねました。
分析の結果は、研究者たちの予測した通りの連鎖を裏付けるものでした。上司が変革型リーダーであると部下が感じている職場ほど、部下の組織アイデンティフィケーションのレベルは高まっていました。その高い組織アイデンティフィケーションが、組織のための不正行為への意図を強めることにつながっていたのです。リーダーの持つ人を惹きつける力が、部下の忠誠心を高め、その忠誠心が不正を容認する土壌を作り出していた、という構図が浮かび上がりました。
このプロセスには個人差が介在することもわかりました。もともと、マキャベリズムの一側面である、道徳を軽視してでも目的を達成しようとする傾向が強い人や、他者に対する公正さをあまり重視しない性格の人ほど、高まった組織アイデンティフィケーションが不正行為への意図に結びつきやすいことが示されました。リーダーの魅力的なリーダーシップと、部下本人が元来持っている倫理観の低さが掛け合わさることで、不正行為のリスクが増大するという、危険な組み合わせが存在することが明らかになりました。
このメカニズムは、変革型リーダーが語る「我々の組織」「我々が目指す高次の目標」といった言葉の作用を考えると、より深く理解できます。これらの言葉は、部下の意識を強く「組織の内側」へと向けさせます。組織への強い一体感は、仲間意識や連帯感という美徳を生む一方で、組織の外にいる顧客、取引先、あるいは社会全体といった他者への配慮を忘れさせ、「内側の論理」を絶対視させる危険性をはらんでいるのです。
尊敬されるリーダーが、かえって職場の不正や対立を招く
これまでのところを振り返ると、個人の高い道徳意識や、理想とされるリーダーシップスタイルでさえ、特定の条件下では不正の引き金になりうることが見えてきました。ならば、リーダー自身が明確に「倫理」を掲げ、自ら模範を示し、部下にもそれを求める「倫理的リーダーシップ」が、職場の不正を防ぐための最終的な答えであるように思えます。そのリーダーシップは、組織に公正さをもたらし、従業員間の無用な対立を減らす万能薬となるのでしょうか。この問いを探求した研究は、一筋縄ではいかない、リーダーシップの複雑な現実を映し出しています。
ある研究は、そもそもどのような資質を持つリーダーが「倫理的リーダーシップ」を発揮しやすいのか、そしてそのリーダーシップが、職場の不正行為や人間関係の対立に実際にどのような影響を及ぼすのかを、包括的に明らかにしようとしました[4]。ここで定義される「倫理的リーダーシップ」とは、単にリーダー個人の人柄が誠実であるというだけではありません。それは、リーダーが自らの行動を通じて倫理的な手本を示すと同時に、部下との対話やルール、報酬制度などを通じて、部下にも倫理的な行動を促すという、いわば「倫理をマネジメントする」側面まで含んだ概念です。
この研究では、リーダーが倫理的リーダーシップを発揮する源泉として、リーダー自身の「道徳的アイデンティティ」に目が向けられました。リーダーが自分自身をどれだけ道徳的な人間だと認識しているか(内在化)、そして、それを周囲に示そうとしているか(顕示化)が、実際のリーダーシップ行動につながるのではないかと考えました。その倫理的リーダーシップが、部署全体の不正行為の頻度や、従業員同士の感情的なこじれといった「関係葛藤」を減らす効果を持つだろうと予測されました。
アメリカの様々な業種の職場を対象に、上司と部下の双方からデータを集めて分析した結果、予測の一部は裏付けられました。リーダーが自らの道徳性を他者に見せようとする意識(顕示化)が強いほど、部下からは「倫理的なリーダーである」と認識されやすいことがわかりました。部下が上司を倫理的リーダーだと評価している職場では、実際に部署全体の不正行為や、従業員間の感情的な対立が少ないという関係が見られました。
この研究の価値は、倫理的リーダーシップを、他の似通ったリーダーシップ概念と比較検討した点にあります。特に、先程も触れた変革型リーダーシップの一要素であり、カリスマ的な魅力で部下を惹きつけ、高い理想を掲げる「理想化された影響」と呼ばれるリーダーシップを同時に測定したところ、示唆に富む結果が得られました。なんと、この理想を掲げるタイプのリーダーシップは、部下の不正行為や対立を減らすどころか、統計的にはむしろ「増やしてしまう」という正の関連が見られたのです。
尊敬され、理想の体現者と見なされるリーダーのもとで、なぜかえって不正や対立が増えてしまうのか。これまでの議論を振り返ることで、その背景にあるメカニズムを推測することができます。リーダーが掲げる高邁な理想やビジョンは、時に組織への過剰な一体感や、「目的のためなら手段は問わない」という結果主義的な風潮を組織内にもたらす危険性があります。また、一人のカリスマ的なリーダーへの強い心酔は、そのリーダーを熱心に信奉するグループと、そうでない冷めたグループとの間に見えない溝を生み出し、職場内の対立や不和の原因となるのかもしれません。
このことは、倫理的リーダーシップがなぜ不正を減らす力を持つのかを、より鮮明に浮かび上がらせます。倫理的リーダーシップが有効なのは、リーダーが持つ人としての魅力や、部下への公正な態度といった要素もさることながら、何よりも「倫理的なルールを明確に示し、コミュニケーションをとり、違反には公平かつ厳格に対処する」という、いわば「モラル・マネジャー」としての地道な機能が働いているからだと考えられます。ただ尊敬されているだけ、ただ理想を語るだけでは不十分です。倫理を組織の日常業務に組み込み、仕組みとして運用していく視点が、職場の健全性を支える上で欠かせません。
脚注
[1] Aquino, K., Freeman, D., Reed II, A., Lim, V. K. G., and Felps, W. (2009). Testing a social-cognitive model of moral behavior: The interactive influence of situations and moral identity centrality. Journal of Personality and Social Psychology, 97(1), 123-141.
[2] Reynolds, S. J., and Ceranic, T. L. (2007). The effects of moral judgment and moral identity on moral behavior: An empirical examination of the moral individual. Journal of Applied Psychology, 92(6), 1610-1624.
[3] Effelsberg, D., Solga, M., and Gurt, J. (2014). Transformational leadership and follower’s unethical behavior for the benefit of the company: A two-study investigation. Journal of Business Ethics, 120(1), 81-93.
[4] Mayer, D. M., Aquino, K., Greenbaum, R. L., and Kuenzi, M. (2012). Who displays ethical leadership, and why does it matter? An examination of antecedents and consequences of ethical leadership. Academy of Management Journal, 55(1), 151-171.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。