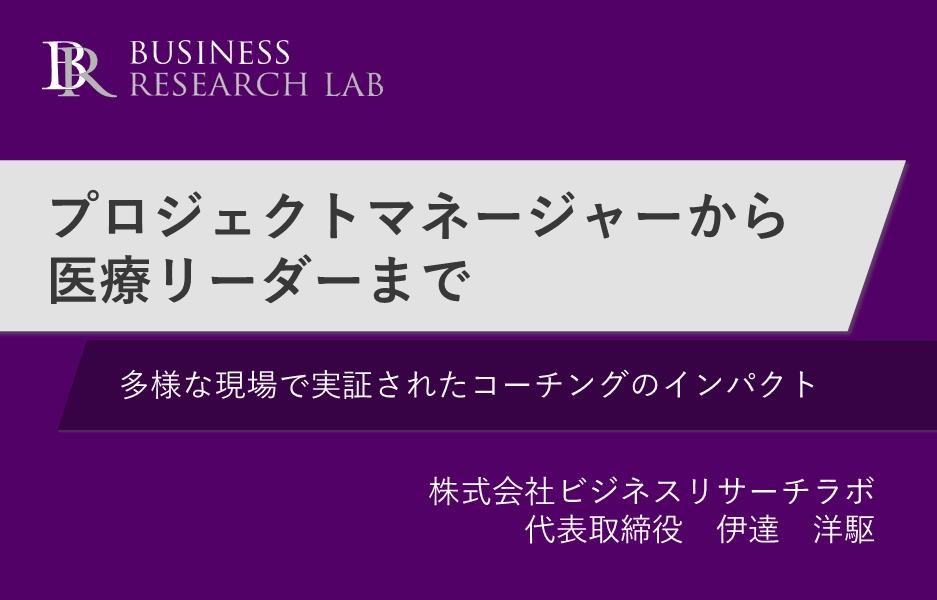2025年10月17日
プロジェクトマネージャーから医療リーダーまで:多様な現場で実証されたコーチングのインパクト
変化の激しいビジネス環境において、組織の持続的な成長の鍵は、従業員一人ひとりが自ら考え、行動する「自律性」をいかに引き出すかにかかっています。画一的な指示命令型のマネジメントでは、複雑化する課題に対応しきれず、個々の潜在能力を十分に活かせない場面も少なくありません。
こうした状況を打破するアプローチの一つとして、今、「コーチング」に注目が集まっています。コーチングとは、対話を通じて相手の内にある答えや可能性を引き出し、自発的な成長を促すコミュニケーションです。例えば、上司が答えを与えるのではなく、問いかけることを通じて、部下自身が課題解決の主役となるプロセスを支援します。
しかし、「コーチングは本当に効果があるのか」という問いに、私たちはどう答えるでしょうか。その有効性は、個人の感覚や体験談に留まらず、客観的な事実として検証されるべきです。本コラムでは、この問いに答えるため、業界も文化も異なる様々な職場で行われた実証研究を紐解き、コーチングがもたらす効果を多角的に探ります。
これらの研究結果を通じて、コーチングが個人の能力開発、チームの関係性、そして組織全体の成果にいかに貢献するのか、その力と多様な価値を明らかにしていきます。組織における人材育成の新たな可能性を探る一助となれば幸いです。
コーチングはリーダーの部下への信頼を高め、部下の離職を防ぐ
リーダーシップ開発において、コーチングがどのような心理的変化をもたらすのか、そしてその変化が組織全体にどう波及していくのかを明らかにした研究があります[1]。この研究では、質的手法と量的手法を組み合わせた混合研究法というアプローチが採用されています。
研究は二段階で進められました。最初の段階では、経験豊富なリーダーシップ・コーチたちを対象としたフォーカスグループ・ディスカッションが実施されました。現場で実際にコーチングに携わっている専門家たちから、「コーチングの成果とは何か」というリアルな声を集めることが目的でした。
この質的分析から、二つの成果指標が浮かび上がりました。一つ目は「リーダーの役割効力感」です。これは、リーダーが自身のリーダーとしての職務をうまく遂行できるという能力に対する自信を指します。二つ目は「リーダーの部下への信頼」で、リーダーが部下の能力や責任感を信頼し、権限委譲や業務の委任ができることを意味します。
次の段階では、これらの指標を用いて実際のフィールドで準実験が行われました。6ヶ月間のコーチング・プログラムに参加するリーダーたちと、同じ組織に所属するがコーチングを受けないリーダーたちが比較対象となりました。コーチングの開始前と終了後に、両グループから心理的データを収集し、さらにそのリーダーたちの部下からも、上司への信頼の変化によって生じると考えられる心理的エンパワーメントや離職意向に関するデータが収集されました。
分析の結果、コーチングを受けたリーダーたちは、受けていない対照群と比較して、役割効力感と部下への信頼の両方が統計的に有意に向上しました。コーチングがリーダー自身の職務に対する自信を高め、部下を信頼する姿勢を育む上でポジティブな効果を持つことが実証されたのです。
この研究で興味深いのは、リーダーの心理的変化が組織全体に波及する効果です。リーダーの部下への信頼が向上すると、その部下たちの離職意向が低下することが明らかになりました。リーダーが部下を信頼するようになると、部下はその組織を辞めたいと思わなくなるという関係性が確認されました。
この現象のメカニズムを探るため、研究者たちはコーチの具体的な行動に着目しました。その結果、コーチの「ファシリテーション行動」が、これらのポジティブな変化を説明する上で重要な働きをしていることが判明しました。ファシリテーション行動とは、クライアントを支援し、時に挑戦的な問いを投げかけ、建設的なフィードバックを提供するという行動を指します。
上司のコーチングは、文化や業種を超えて業績を向上させる
マネージャーが部下に対して行う日常的なコーチングが、実際に部下の業績にどれほどの効果をもたらすのかという問いに、二つの国際的な調査を通じて答えを示した研究があります[2]。この研究の特徴は、文化や産業背景が異なる環境で同様の調査を実施し、コーチング効果の一般性を検証した点にあります。
研究の舞台となったのは、ラテンアメリカのBtoB営業担当者と、カナダのBtoC金融サービス担当者という、全く異なる二つの職場環境でした。前者は、あるアメリカの工業メーカーのラテンアメリカ支社で、石油、ガス、通信などの様々な業界を担当するBtoB営業担当者を対象としました。後者は、カナダの大手地方銀行で営業責任を持つファイナンシャル・アドバイザーなどの第一線の従業員を対象としました。
この研究の理論的基盤として、リーダー・メンバー交換理論が用いられています。この理論によると、リーダーはすべての部下と均一な関係を築くわけではなく、一部の部下とは信頼と尊敬に基づいた質の高い関係を、他の部下とは形式的で契約的な質の低い関係を築くとされています。コーチングは、この質の高い関係を築くための行動と捉えることができます。
研究では、上司によるコーチングの頻度や質を部下による評価として測定し、それと客観的な業績指標との関連性を調査しました。従業員の経験年数や在職期間といった変数の効果を統計的に取り除いた上で、コーチングがパフォーマンスに与える効果が検証されました。
両方のサンプルを用いた分析の結果、一貫して同じパターンが確認されました。従業員の経験や勤続年数などの要因を考慮した後でも、上司によるコーチングは部下のパフォーマンスと統計的に有意な正の相関関係を示したのです。
この研究の価値は、文化的背景も業界も異なる二つの環境で、コーチングの効果が一貫して確認されたことにあります。ラテンアメリカとカナダという地理的な違い、BtoBとBtoCという取引形態の違い、工業メーカーと金融サービスという業界の違いを超えて、上司のコーチング的な関わりが部下の客観的なパフォーマンスを向上させるという効果が実証されました。
コーチングはプロジェクトマネージャーの管理・統率力を高める
プロジェクトマネジメントの分野では、技術的なスキルだけでなく、リーダーシップやストレス対処能力といった個人のコンピテンシーが成功の鍵を握ることが認識されています。これらのソフトスキルをどのように効果的に開発できるかを、エグゼクティブ・コーチングの文脈で検証した実験研究があります[3]。
この研究では、30名のプロジェクトマネージャーと、彼ら彼女らの仕事ぶりをよく知る30名の評価者(上司やチームメンバー)が参加しました。参加したプロジェクトマネージャーはランダムに二つのグループに分けられ、実験群は4ヶ月間にわたって1回90分の個人セッションを8回受けました。対照群はコーチングを受けず、介入の前後で両グループのコンピテンシーがどのように変化したかが比較されました。
評価には、プロジェクトマネジメント協会が開発したコンピテンシー開発フレームワークが用いられました。これは、コミュニケーション、リーダーシップ、マネジメント、認知能力、有効性、プロフェッショナリズムという6つの領域に関する90の行動項目を含んでいます。プロジェクトマネージャー本人による自己評価と、評価者による360度評価の両方が実施され、多角的な視点からコンピテンシーの変化が測定されました。
コーチングセッションは、認定プロフェッショナルコーチによって、GROWモデルを基本としつつ、目標設定や行動計画の策定を支援するプロセスに沿って行われました。このプロセスでは、現状の把握、目標の明確化、選択肢の検討、実行計画の策定という段階を踏んで、参加者の自発的な気づきと行動変容を促しました。
分析の結果、コーチングを受けた実験群では、個人的コンピテンシー全体の平均スコアが統計的に有意に向上しました。自己評価でも他者評価でも向上が見られ、対照群には有意な変化が認められませんでした。コーチングがプロジェクトマネージャーの個人的コンピテンシーを強化する上で効果を持つことが明らかになりました。
しかし、コーチングはすべてのコンピテンシーに均等に作用するわけではありませんでした。最も大きな改善が見られたのは「マネジメント」と「リーダーシップ」の領域です。マネジメント能力については、プロジェクトマネージャーの自己評価において最も大きな伸びを示しました。これには、期待や責任を明確に伝えること、機会を捉えて他者に任せることといった行動が含まれます。
リーダーシップ能力については、他者評価において最も大きな伸びを示しました。チームの学習を促進する行動や、効果的に情報を伝える行動において改善が確認されました。認知能力についても、他者評価でリーダーシップに次いで大きな改善が見られました。
一方で、「プロフェッショナリズム」に関するコンピテンシーには大きな変化は見られませんでした。これは、参加者が実験開始前からこの領域で既に高いスコアを示しており、改善の余地が小さかったためと考察されています。倫理観や責任感といった基本的な職業意識については、初めから十分に高い水準にあったということです。
この研究は、エグゼクティブ・コーチングが、プロジェクトマネージャーの個人的コンピテンシー、とりわけソフトスキルを強化するための有効な手法であることを実証しました。困難な状況下でチームを率い、資源を管理し、ストレスフルな状況に対処するといった、現代のプロジェクトマネージャーに求められる能力に対して、コーチングは大きな効果を発揮します。
医療現場のコーチング効果は、仕事だけでなく私生活にも及ぶ
オーストラリアの公衆衛生システムで働くリーダーたちを対象とした研究では、コーチングの効果が職場を超えて個人の生活全般に及ぶという発見がもたらされました[4]。この研究は、ストレスの多いヘルスケア現場において、リーダーシップ・コーチングがどのような多面的な効果をもたらすのかを探求したものです。
研究の対象となったのは、ニューサウスウェールズ州の医療制度において戦略的な変革プロジェクトを担う31名のリーダーでした。看護、医療、関連分野のシニアリーダーやプログラムマネージャーなど、高い責任を負う立場の専門家たちです。彼らは予算の圧迫や需要の増大といった厳しい環境の中で、変化に柔軟に対応し、多様な関係者と効果的に協働していく高度な能力を求められていました。
研究では、参加者全員がプロフェッショナルなリーダーシップ・コーチによる1時間のセッションを6回、6ヶ月間にわたって受けました。コーチングは、個人の強みを活かし、解決策を見出すことに焦点を当てる解決志向の認知行動論的な枠組みに基づいて実施されました。このアプローチでは、問題の原因を追求するのではなく、望ましい未来の状態を明確にし、それに向けた行動を支援することに重点が置かれました。
プログラムの前後で、目標達成度、解決志向思考、リーダーシップの自己効力感、レジリエンス、ストレス、不安、抑うつ、視点取得能力、曖昧さへの耐性、自己洞察など、多岐にわたる尺度を用いて変化が測定されました。
分析の結果、参加者が自身で設定した仕事上の目標の達成度が、コーチング後に有意に向上しました。目標設定から達成までのプロセス全体において、参加者の能力が向上したことを示しています。思考様式にも変化が見られ、「解決志向思考」「視点取得能力」「曖昧さへの耐性」「自己洞察」がすべて有意に向上しました。
解決志向思考とは、問題ではなく解決策に焦点を当てる考え方を指します。視点取得能力は他者の視点を理解する力、曖昧さへの耐性は不確実な状況に対処する力を意味します。これらの思考スタイルの変化は、複雑で予測困難な医療現場において、リーダーが効果的に機能するために有効な能力の向上を表しています。
メンタルヘルスの面でも改善が見られました。参加者の「ストレス」と「不安」のレベルが、コーチング後に有意に減少しました。同時に、「レジリエンス」と「リーダーシップの自己効力感」も有意に向上しました。レジリエンスは困難から立ち直る力、リーダーシップの自己効力感はリーダーとして効果的に行動できるという自信を指します。
さらに、コーチングで得られた学びや気づきは、職場だけでなく、私生活や家庭にまで転移していました。プログラム終了後の自由記述では、多くの参加者がワークライフバランスの改善、自己や他者との関係性に対する深い洞察の獲得、家族とのより良いコミュニケーションの実現、家庭でのストレス軽減などを報告しました。
この研究が明らかにしたのは、リーダーシップ・コーチングが持つホリスティックな効果です。職場での目標達成やストレス軽減といった効果にとどまらず、思考様式の変化を通じて、個人の人生全体にポジティブなインパクトを与える可能性が実証されました。
脚注
[1] Ladegard, G., and Gjerde, S. (2014). Leadership coaching, leader role-efficacy, and trust in subordinates. A mixed methods study assessing leadership coaching as a leadership development tool. The Leadership Quarterly, 25(4), 631-646.
[2] Pousa, C., and Mathieu, A. (2014). The influence of coaching on employee performance: Results from two international quantitative studies. Performance Improvement Quarterly, 27(3), 75-92.
[3] Ballesteros-Sanchez, L., Ortiz-Marcos, I., and Rodriguez-Rivero, R. (2019). The impact of executive coaching on project managers’ personal competencies. Project Management Journal, 50(3), 306-321.
[4] Grant, A. M., Studholme, I., Verma, R., Kirkwood, L., Paton, B., and O’Connor, S. (2017). The impact of leadership coaching in an Australian healthcare setting. Journal of Health Organization and Management, 31(2), 237-252.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。