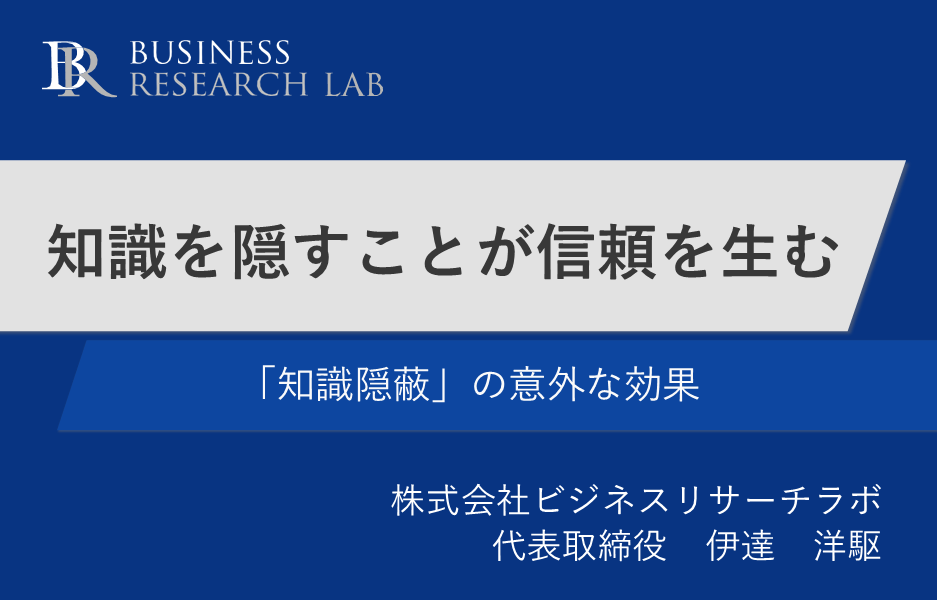2025年10月16日
知識を隠すことが信頼を生む:「知識隠蔽」の意外な効果
同僚が持つ知識やノウハウを教えてもらおうとしても、なかなか素直に教えてくれない場面に遭遇することがあります。「忙しいから後で」と言われたまま結局教えてもらえなかったり、「それは会社の方針で教えられない」と断られたり、時には「知らない」と言われてしまうこともあるでしょう。
このような現象は「知識隠蔽」と呼ばれ、近年の組織研究で注目を集めています。知識隠蔽とは、他者から求められた情報や知識を意図的に隠したり、提供しなかったりする行動を指します。一見すると単純な非協力的行動のように見えますが、その背景には複雑な心理的メカニズムが働いています。
知識隠蔽が職場で起こる理由を理解することは、現代の組織マネジメントにおいて欠かせない視点です。知識経済と呼ばれる現代において、従業員が持つ知識やスキルは組織の競争力の源泉となっています。しかし、その貴重な知識が組織内で共有されなければ、組織全体のパフォーマンスは低下してしまいます。
本コラムでは、知識隠蔽がどのようなメカニズムで生まれるのかを探っていきます。善意による隠蔽から悪意のある囲い込みまで、様々なタイプの知識隠蔽とその原因を明らかにしていきましょう。
正当な理由がある知識隠蔽は、むしろ関係を良くする
知識隠蔽と聞くと、多くの人は職場の人間関係を悪化させる悪い行動だと考えるでしょう。しかし、実際にはすべての知識隠蔽が同じ結果をもたらすわけではありません。隠し方によっては、むしろ相手との関係性が改善されることもあります。
ある研究では、知識を隠す側と隠される側の両方の視点から、知識隠蔽の影響を調査しました[1]。この研究は、知識隠蔽を三つのタイプに分類して分析を行いました。
第一のタイプは「合理化した隠蔽」で、情報を提供できない理由を論理的に説明する方法です。例えば「この情報は機密事項なので、会社の規則により教えることができません」といった説明をするケースです。第二のタイプは「回避的隠蔽」で、誤った情報を教えたり、「後で教える」と言いながら実際には教えない方法です。第三のタイプは「無知を装う」もので、実際は知っているにもかかわらず「知らない」と嘘をつく方法です。
この研究は二段階で実施されました。最初の研究では、194名の従業員を対象に、自分が知識を隠した経験についてオンラインアンケートを実施しました。参加者には、実際に起こった知識隠蔽の状況を詳しく思い出してもらい、その時の行動や相手との関係への影響について回答してもらいました。
次の研究では、210名の従業員を対象に、今度は知識を隠された側の視点から調査を行いました。同じく実際の体験に基づいて、相手の行動をどのように受け取ったか、その後の関係や自分の行動にどのような変化があったかを調べました。
研究結果は予想外のものでした。合理化した隠蔽については、知識を隠された側は関係性が強化されたと感じていたのです。正当な理由を説明されることで、相手を理解し、むしろ信頼感が高まっていました。一方、知識を隠した側は、たとえ正当な理由があっても、多少は関係性が損なわれると考えていました。
対照的に、回避的隠蔽では両者ともに関係性が悪化すると認識していました。誤った情報を教えられたり、曖昧な返答で実際には教えてもらえなかったりすることは、信頼関係を損なう行為として受け取られていました。隠した側も、このような行動が将来的に相手からの報復を招く可能性があることを認識していました。
無知を装うケースでは、興味深い結果が見られました。知識を隠された側は関係性の悪化を感じていましたが、知識を隠した側はそれほど関係性への悪影響を認識していませんでした。しかし、将来的な報復の可能性については、隠した側も認識していました。これは、嘘をついていることへの後ろめたさが、将来への不安として現れたものと解釈できます。
この研究が明らかにしたのは、知識隠蔽の方法によって、その後の人間関係に与える影響が異なるということです。正当な理由を丁寧に説明する合理化した隠蔽は、一時的には情報共有を阻害しますが、長期的には信頼関係の構築に役立つ可能性があります。これは、相手への敬意と透明性を保った対応として受け取られるためです。
一方、回避的隠蔽や無知を装う行為は、関係性を悪化させ、職場の協力的な雰囲気を損なってしまいます。これらの行動は、相手を騙したり軽視したりする行為として認識され、将来的な協力関係の構築を困難にしてしまいます。
知識隠蔽は、必ずしも悪意から行われるわけではない
職場で知識隠蔽が起こる背景を理解するためには、この行動が決して悪意だけから生まれるものではないことを知る必要があります。実際、多くの知識隠蔽は、複雑な職場環境の中で従業員が直面する様々な制約や配慮から生まれています。
知識隠蔽という現象を体系的に研究した先駆的な調査では、金融サービス企業の従業員36名を対象に、5日間にわたって日常の出来事を記録してもらいました[2]。研究者たちは、参加者に毎日の業務の中で知識共有や知識隠蔽に関する出来事があったかどうかを報告してもらい、その具体的な内容を聞き取りました。
この調査で明らかになったのは、従業員の約10パーセントが日常的に何らかの形で知識隠蔽を行っているという事実でした。しかし、これらの行動の多くは、決して悪意や自己利益の追求だけから生まれているわけではありませんでした。
例えば、ある従業員は部下から業務手順について質問を受けた際、その情報が機密性の高い内容だったため、会社の規則に従って教えることを控えました。別のケースでは、同僚から専門的な知識について相談を受けたものの、その知識が非常に複雑で、短時間では正確に伝えることが困難だったため、不完全な説明をしてしまいました。
研究者たちはこうした実際の事例を分析し、知識隠蔽行動を三つのカテゴリーに分類しました。無知を装う行動では、実際には知識を持っているにもかかわらず、知らないふりをします。回避的隠蔽では、質問に対して曖昧な答えをしたり、不正確な情報を提供したりします。合理化した隠蔽では、情報を提供できない理由を論理的に説明します。
続いて実施された194名の社会人を対象とした調査では、これらの三つのタイプの知識隠蔽が異なる行動パターンであることが確認されました。この調査では、知識隠蔽が単なる知識共有の欠如や個人的な知識の蓄積とは区別される独立した現象であることも明らかになりました。
さらに、知識隠蔽を引き起こす要因も分析されています。105名のビジネス系大学生を対象とした調査では、どのような状況で知識隠蔽が起こりやすいかを調べました。
その結果、最も強力な予測因子は対人関係における不信感でした。相手を信頼できないと感じる時、人々はあらゆるタイプの知識隠蔽を行いやすくなることが分かりました。これは、信頼関係が知識共有の基盤となっていることを示しています。
知識の複雑さも隠蔽行動に影響を与えていました。複雑で理解が困難な知識ほど、回避的隠蔽が起こりやすいことが明らかになりました。不正確な情報を伝えてしまうリスクを避けたいという心理から生まれる行動だと考えられます。
業務との関連性についても結果が得られました。業務に直接関連する知識の場合、合理化した隠蔽は減少する一方で、回避的隠蔽は増加する傾向が見られました。業務に関連する知識を共有する圧力がある一方で、その知識が組織内での自分の価値や地位に直結するため、完全に共有することへの躊躇が生まれるためだと解釈できます。
組織全体の知識共有に対する雰囲気も知識隠蔽に関わっていることが分かりました。知識共有が奨励され、それが組織文化として根付いている職場では、回避的隠蔽が有意に減少していました。これは、組織環境が個人の行動選択に与える影響の大きさを物語っています。
「自分の知識」という縄張り意識が、知識隠蔽と問題行動を生む
職場における知識隠蔽の背景には、従業員が自分の専門知識や技能に対して感じる強い所有意識があります。この心理的な「縄張り意識」が、どのように知識隠蔽を引き起こし、職場全体に悪影響を与えるのかを調べた研究があります[3]。
この研究は、アラブ首長国連邦の銀行・保険業界で働く198組の三者関係(チームリーダー、その直属の部下、その上司)を対象に実施されました。この調査では知識隠蔽に関わる異なる立場の人々から別々に情報を収集しました。縄張り意識については本人が自己評価し、知識隠蔽の被害については部下が評価し、業務遂行能力や問題行動については上司が評価するという方法を取りました。
縄張り意識とは、従業員が自分の持つ知識、技能、専門性を自分だけのものだと感じ、それを他者から守ろうとする心理的な態度です。この意識が強い人は、自分の知識や技能を積極的に主張し、それを他の人が使えないように保護しようとします。例えば、「この分析手法は私が開発したものだ」「この顧客対応のノウハウは私の経験から生まれたものだ」といった具合に、知識に対する所有権を主張する行動として現れます。
研究の結果、縄張り意識の強い従業員は知識隠蔽を行いやすいことが確認されました。自分の知識を他者に取られてしまうのではないかという不安や、知識を共有することで自分の優位性が失われることへの恐れが、知識隠蔽行動を引き起こしていると考えられます。
さらに、縄張り意識が業務遂行能力そのものを低下させることが明らかになりました。自分の知識を守ることに意識が向きすぎると、他者との協力や学習機会を逃してしまい、本人の業務パフォーマンスが悪化してしまいます。これは一見すると逆説的に思えますが、現代の職場では個人の力だけでは限界があり、チームワークや知識の相互交換が業務成功の鍵となっていることを反映しています。
縄張り意識が職場での逸脱行動を増加させることも見えてきました。逸脱行動には二つのタイプがあります。一つは組織全体に対する逸脱行動で、会社の規則を無視したり、業務時間中に私的な用事をしたりする行動です。もう一つは対人的な逸脱行動で、同僚に対して失礼な態度を取ったり、意図的に協力を拒否したりする行動です。縄張り意識の強い従業員は、両方のタイプの逸脱行動を起こしやすいことが分かりました。
研究では、知識隠蔽が縄張り意識と様々な問題行動との間を取り持つ媒介的な機能を果たしていることも明らかになりました。これは、縄張り意識が直接的に問題を引き起こすだけでなく、知識隠蔽という行動を通じて、より広範囲にわたる職場の問題を生み出すメカニズムを指しています。
知識を隠された同僚や部下は、不満や怒りを感じます。これらの感情は、職場の雰囲気を悪化させ、チーム全体のモチベーションや生産性に悪影響を与えます。知識隠蔽を行った本人も、罪悪感や孤立感を覚え、職場への帰属意識が低下して、逸脱行動を起こしやすくなるという悪循環が生まれます。
競争心が強いと、良い職場でもノウハウの知識隠蔽は残る
学術界は、一般的に知識の自由な交換と協力を理想とする環境だと考えられています。しかし、実際には昇進、研究資金の獲得、論文の発表などをめぐって激しい競争が繰り広げられており、この矛盾した状況が知識隠蔽にどのような影響を与えるのかを調べた研究があります[4]。
この研究は、クロアチアの公立・私立ビジネススクールで働く210名の教員を対象に実施されました。大学という協力的な環境であっても、個人の競争的な性格特性が知識隠蔽行動にどのような影響を与えるかを調査しました。
研究では、知識を明示的知識と暗黙的知識の二つに分類して分析を行いました。明示的知識とは、文書やマニュアルとして明文化され、比較的容易に他者に伝達できる知識です。例えば、授業で使用する教材の作成方法や、研究データの分析手順などがこれにあたります。一方、暗黙的知識とは、個人の経験や直感に基づく知識で、言葉で説明することが困難な知識です。優秀な学生を見分けるコツや、効果的な論文指導の方法などがこの例です。
調査の結果、教員たちは明示的知識よりも暗黙的知識を隠蔽する傾向が強いことが明らかになりました。これは、暗黙的知識が個人の競争優位の源泉となりやすく、それを共有することで自分の地位や評価が脅かされるリスクを感じるためだと考えられます。明示的知識は比較的標準化されており、共有しても個人の独自性が失われにくいのに対し、暗黙的知識は個人の経験や能力と密接に結びついているため、より慎重に扱われます。
個人の競争的性格についても発見がありました。他者を上回ることに強い喜びを感じる競争的な性格の教員は、明示的知識と暗黙的知識の両方において、より多くの知識隠蔽を行っていました。協力を前提とした学術環境においても、個人の性格特性が知識共有行動に影響することを意味しています。
興味深いのは、職務設計が知識隠蔽に与える影響です。この研究では、タスクの相互依存性と社会的支援という二つの職務環境要因を調べました。タスクの相互依存性とは、自分の業務を遂行するために他者との協力がどの程度必要かを意味します。社会的支援とは、同僚や上司からどの程度のサポートを受けられるかを表します。
分析の結果、これらの職務環境要因は、明示的知識の隠蔽については一定の抑制効果を持つことが分かりました。他者との協力が不可欠な業務環境では、明示的知識を隠蔽することが自分の業務遂行にも支障をきたすため、隠蔽行動が抑制されます。同様に、同僚からの支援が充実している環境では、知識を共有することへの心理的な抵抗が和らぎ、明示的知識の隠蔽が減少します。
しかし、暗黙的知識に関しては、職務環境の改善効果は限定的でした。個人の競争的性格が強い場合、協力的な職務設計があっても、暗黙的知識の隠蔽行動は依然として高い水準で維持されていました。これは、暗黙的知識が個人のアイデンティティや競争優位性と深く結びついているため、環境的な要因だけでは隠蔽行動を抑制することが困難であることを意味しています。
なぜ暗黙的知識の隠蔽がこれほど根強いのかを理解するには、その知識が持つ特別な価値を考える必要があります。暗黙的知識は、長年の経験や試行錯誤を通じて蓄積された個人的な財産のような性質を持っています。それを他者と共有することは、自分の競争上の優位性を手放すことを意味し、特に競争的な性格の人にとっては心理的負担となるのです。
脚注
[1] Connelly, C. E., and Zweig, D. (2015). How perpetrators and targets construe knowledge hiding in organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24(3), 479-489.
[2] Connelly, C. E., Zweig, D., Webster, J., and Trougakos, J. P. (2012). Knowledge hiding in organizations. Journal of Organizational Behavior, 33(1), 64-88.
[3] Singh, S. K. (2019). Territoriality, task performance, and workplace deviance: Empirical evidence on role of knowledge hiding. Journal of Business Research, 97, 10-19.
[4] Hernaus, T., Cerne, M., Connelly, C. E., Poloski Vokic, N., and Skerlavaj, M. (2019). Evasive knowledge hiding in academia: When competitive individuals are asked to collaborate. Journal of Knowledge Management, 23(4), 597-618.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。