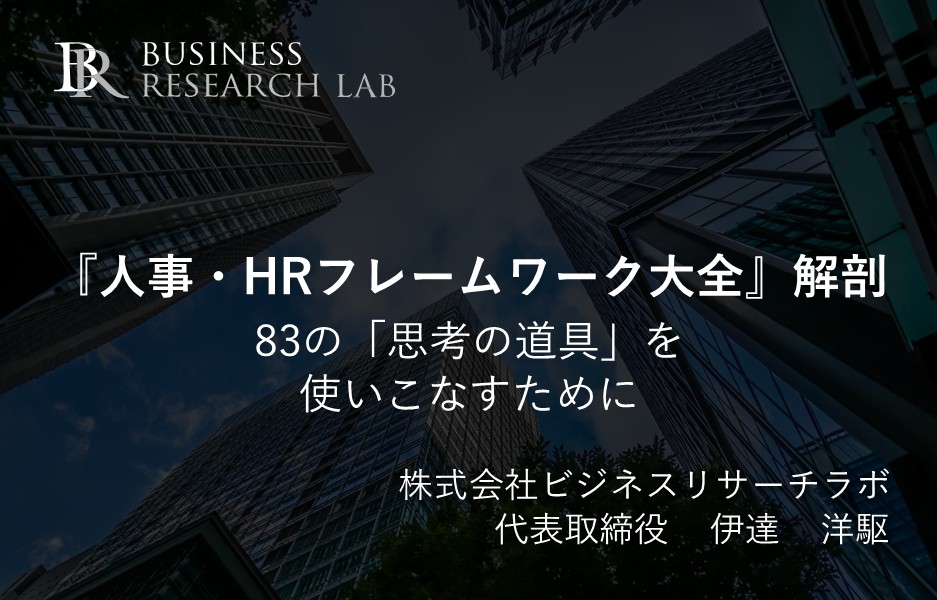2025年10月15日
『人事・HRフレームワーク大全』解剖:83の「思考の道具」を使いこなすために
ビジネス書を手に取る人の多くは、現場で直面する課題を解決したいという思いを抱えています。しかし、読書を通じて得た知識を、実際の業務で十分に活かせているかと問われれば、自信を持って頷ける人は決して多くないでしょう。読んだ直後は納得し、意欲も高まるものの、いざ現場に戻ると日々の業務に追われ、学んだはずの知識は記憶の片隅へと追いやられてしまう。こうした「実践の壁」は、多くのビジネスパーソンが経験する共通の悩みではないでしょうか。
この度、上梓した『人事・HRフレームワーク大全』は、この問題意識から生まれました。本書は、単純に83のフレームワークを紹介する知識の集積ではありません。むしろ、読者が「知る」という段階から「実践する」という段階へ移行できるよう設計された一冊の「思考のナビゲーション」です。一つひとつの理論解説は、読者の思考を段階的に深め、具体的な行動へと導くための水先案内人としての役割を担っています。
本コラムでは、その設計思想を著者である私自らが説明し、本書を読み物で終わらせないためのガイドブックとして、その構造と活用法を解説します。この本は、ただ「読む」ものではなく、対話し、思考し、実践するためのパートナーです。本書に埋め込まれた設計図を理解することで、具体的な使い方が見えてくるはずです。
乱雑な問題の中から、進むべき道を照らし出す
問題解決の精度は、最初の「問い」の質で決まります。しかし、現場で発生する問題の多くは、「最近、チームの雰囲気がどこかぎくしゃくしている」「若手社員が思うように育たない」といった、輪郭のはっきりしない、漠然とした形で私たちの前に現れます。こうした霧の中にいるような状態で、やみくもに解決策を探しても、空回りしてしまいます。
本書が各フレームワークの解説の冒頭に「どのような場面で有効か」という項目を設けているのは、こうした理由に基づきます。この項目は、読者が自身の抱える漠然とした悩みに輪郭を与え、それを客観的に捉えるための「診断ツール」として機能します。リストアップされた場面と自身の状況を照らし合わせることで、読者は自らが直面している問題が、どのような学術的知見と関連しているのかを発見できます。
例えば、「部下の主体性が発揮されていない」という課題を感じている管理職がいるとします。その場合、本書の目次や各章をめくりながらこの項目に目を通すことで、その課題が個人の意欲の問題ではなく、「リーダーシップ代替要因」という自律的な仕組みの問題かもしれないし、「心理的エンパワーメント」という内発的動機づけの欠如が関係しているのかもしれない、あるいは「自己決定理論」が示す欲求が満たされていない可能性もある、といったように、複数の角度から問題を捉え直すきっかけを得ることができます。
これは、すぐに答えを求めるのではなく、まず適切な「問い」を立てるためのステップです。問題の本質がどこにあるのか、その当たりをつけることで、思考の迷路に迷い込むことなく、解決に向けた経路を歩み始めることができるようになります。この最初のセクションは、乱雑に絡み合った課題の糸を解きほぐし、進むべき道を照らし出します。
複雑な現象に「名前」を与え、チームの共通言語を創造する
人と組織に関する問題がこれほどまでに厄介なのは、その多くが目に見えず、形がなく、捉えどころがないからです。私たちは、形のないものについて考え、他者と議論することに大きな困難を伴います。フレームワークが持つ価値の一つは、こうした無形で複雑な現象に構造と「名前」を与えることにあります。
本書の中心部分である「どんなフレームワークか」という解説セクションは、長年の研究によって体系化されてきた学術的な知見を、ビジネスパーソンが現場で使える言葉と論理に「翻訳」する役割を担っています。難解な専門用語を避け、平易な言葉でその理論の核となる部分を解説することで、読者は目の前で起きている現象の背後にあるメカニズムを理解できるようになります。
特に、各フレームワークに添えられた「図解」は、直感的な理解を助けるために重要な役割を果たします。例えば、「競合価値モデル」が示す四つの組織文化タイプを2軸のマトリクスで示した図は、自社の文化を客観的にマッピングし、チーム内で「私たちの組織は今、どのあたりに位置しているだろうか」「今後どちらを目指すべきか」といった対話を生むための「地図」として機能します。文章だけでは捉えきれない理論の全体像や要素間の関係性を視覚的に示すことで、読者の思考は整理され、より深い理解へと進むことができます。
このプロセスを通じてフレームワークがもたらす大事な効果の一つが、組織内に「共通言語」が創造されることです。これまで「やる気がない」という曖昧な言葉で片付けられていた個人の状態が、「自己決定理論における『有能感』が満たされていないのではないか」という具体的な言葉で議論できるようになれば、対話の質は向上します。感覚的な言葉によるすれ違いや感情的な対立が減り、問題の構造に焦点を当てた、建設的な解決策の模索が始まります。フレームワークは、複雑な現象をチームで共有し、共に乗り越えていくための知的なインフラとなるでしょう。
知識を血肉に変え、自分の武器にする
理論を理解するだけでは、現実は変わりません。本書が力を注いだ部分の一つが、学んだ知識を行動へと橋渡しする設計です。その中核を担うのが、「どう使えば良いか」と「理解のための例題」という二つのセクションです。これらは、読者が知識を自らの血肉に変え、現場で使える「武器」として磨き上げるための実践的なトレーニングの場となります。
「どう使えば良いか」の項目は、理論を現場で実践するための「アクションリスト」です。例えば、「変革型リーダーシップ」という概念を学んだとしても、「明日から具体的に何をすれば良いのか」が分からなければ行動には移せません。このセクションでは、「信頼される存在になる」「目標を示し、共感を得る」といったように行動レベルの指針を提示しています。理論という抽象的な概念を、「行動の選択肢」として示すことで、読者が最初の一歩を踏み出すためのハードルを下げることを狙いました。
一方、「理解のための例題」は、読者がフレームワーク活用の流れを「疑似体験」するためのシミュレーションとして設計されています。ビジネスシーンを想定したケーススタディを通じて、理論がどのように現実の問題解決に応用されるのかをイメージすることができます。このセクションを読む際、物語として追うだけでなく、登場人物を自分自身や自社のメンバーに置き換えて思考実験をしてみることをお勧めします。「もし自分のチームで同じ状況が起きたら、自分はどう判断し、どう行動するだろうか」と自問することで、フレームワークの活用法を自分の中に刻み込むことができるでしょう。
この二つのセクションを繰り返し行き来するプロセスは、単純な知識のインプットではありません。それは、抽象的な理論を行動計画へと変換し、その結果を予測するという思考の訓練です。この練習を通じて、読者はフレームワークを借り物の知識ではなく、いつでも引き出せる自分自身の思考スキルとして定着させていくことができます。
万能薬という幻想から抜け出し、思考の成熟度を高める
優れた道具も、その使い方を誤ったり、限界を知らずに用いたりすれば、期待した効果は得られません。それどころか、意図しない問題を引き起こすこともあります。フレームワークという思考の道具も同様です。一つの理論に感銘を受けると、ついそれを様々な問題に適用できる「万能薬」であるかのように考えてしまいますが、それは思考の成熟を妨げる兆候でもあります。
本書が、すべてのフレームワークの解説に「何に注意すべきか」という項目を設けているのは、読者がこうした思考の罠に陥ることを防ぎ、より健全な批判的思考を育むことを意図しているからです。このセクションは、各理論が持つ有効範囲の「限界」や、適用する際に陥りがちな「注意点」を明示しています。
例えば、「PM理論」において目標達成機能(P)と集団維持機能(M)の両方が高いリーダーシップ(PM型)が有効だと学んだとしても、現場の状況は常に理想を許容するわけではありません。本書の注意点では、緊急時や危機管理においてはP機能を優先した迅速な判断が求められる場合もあることに触れています。これは、読者に対して、理論を盲信するのではなく、状況に応じて最適な判断を下すことの重要性を示唆しています。
この項目は、フレームワークという道具を絶対視するのではなく、あくまで一つの「視点」として相対化し、現実の複雑な状況に対して多角的な検討を行う姿勢を養うためのものです。なぜこの理論は万能ではないのか、どのような条件下でその有効性が揺らぐのかを理解することで、読者の思考はしなやかになります。単一の正解に固執するのではなく、状況に応じて複数のフレームワークを使い分ける、あるいは組み合わせて複眼的に物事を捉えるという、より高度な問題解決のレベルへと足を踏み入れるためのガイドとなるでしょう。
視座を変え、思考のジャンプを体験する
多くのビジネスパーソンは、自身の役職や立場という「視座」から物事を捉え、課題解決に取り組みます。それは自然なことですが、時にその視座が思考の範囲を限定し、より本質的な解決策から目を遠ざけてしまうことがあります。本書の各項目の最後に置かれた「現場で使うためのストレッチ」は、ただの応用問題ではありません。これは、読者に意図的に「視座の転換」を促し、思考の壁を打ち破るための思考トレーニングです。
このセクションでは、同じテーマについて「担当レベル」「ミドルレベル」「トップレベル」という三つの異なる立場からの問いを立てています。例えば、担当レベルの読者が、ミドルマネジメントや経営トップの視点から同じ課題を捉え直すと、どう見えるでしょうか。これまで「自分の業務範囲の問題」だと考えていたことが、実は「部門間の連携の問題」であり、さらには「全社的な経営資源の配分の問題」とつながっていることに気づくかもしれません。
この思考プロセスは、問題の構造をより立体的かつ体系的に理解することを可能にします。自分の目線からだけでは見えなかった課題の全体像が明らかになり、大局的な観点から解決策を構想する力が養われます。担当者は管理職の意思決定の背景を、管理職は経営層の戦略的意図を理解するきっかけにもなります。
この思考のジャンプを体験することは、日々の業務においても有益です。目の前のタスクをこなしながらも、それが組織全体の目標の中でどのような意味を持つのかを意識できるようになります。この視座の転換能力は、個人をプレイヤーから、組織全体を動かすことのできるリーダーへと成長させる要素となります。
この本は「対話し、思考する」ためのパートナー
ここまで、本書『人事・HRフレームワーク大全』に込めた設計思想とその構造について解説してきました。お気づきの通り、本書の構成は、読者が一方的に知識を受け取る受動的な学習ではなく、各項目と対話し、自分自身の思考を能動的に深めていくことを促すための仕掛けに満ちています。
「どのような場面で有効か」で自身の課題を特定し、「どんなフレームワークか」で現象に名前を与え、「どう使えば良いか」と「例題」で実践をシミュレーションする。そして、「何に注意すべきか」で理論を批判的に吟味し、「ストレッチ」で視座を高める。この一連の流れは、知識を行動に変え、行動を経験に変え、経験をさらなる知恵へと昇華させていく、問題解決能力を鍛えるためのサイクルです。
この構造を意識して活用することで、本書は皆さんの書棚に眠る「フレームワーク集」から、日々の課題解決を支援し、思考力を鍛え上げるための「思考のジム」へとその姿を変えるでしょう。
人と組織の問題に、唯一絶対の正解はありません。だからこそ、私たちには拠り所となる思考の道具が必要です。この一冊が、皆さんの「知の道具箱」に加わり、皆さん自身が思考の主体者として成長していくための、信頼できるパートナーとなることを願っています。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。