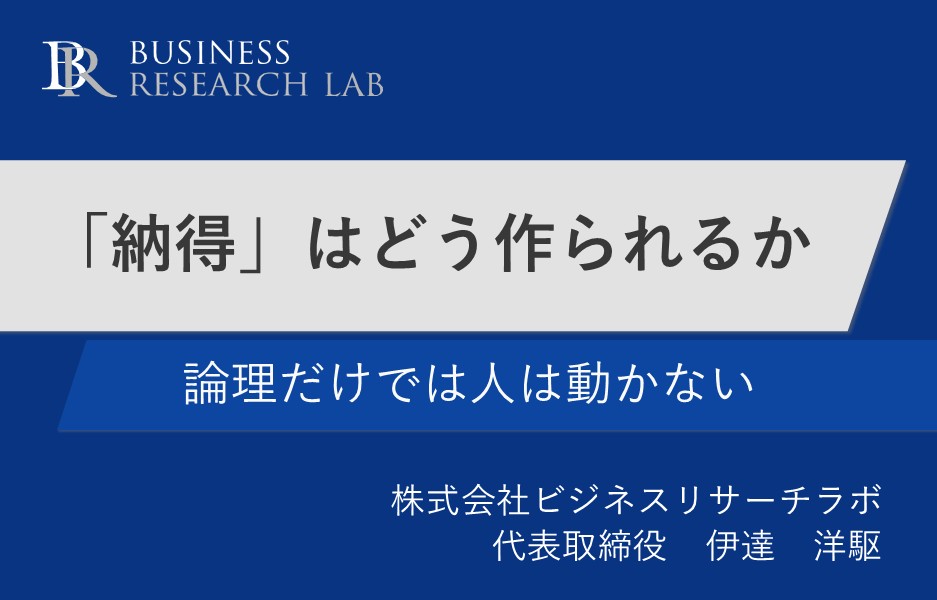2025年10月14日
「納得」はどう作られるか:論理だけでは人は動かない
組織やチームで何か新しいことを始めようとするとき、そこには「合意形成」というプロセスが待ち受けています。全員が最初から同じ方向を向いていることは稀で、異なる意見や価値観がぶつかり合うのは、健全な姿とさえいえます。しかし、そのプロセスが円滑に進まず、議論が空転したり、表面的な賛成しか得られなかったりした結果、せっかくの計画が頓挫してしまったという経験を持つ人も少なくないはずです。
正しい理屈を述べ、合理的なデータを示せば、自ずと納得してくれるものではありません。現実はそう単純ではないのです。人の心を動かし、持続的な協力関係を築くための合意は、論理の正しさだけで成り立っているわけではありません。そこには、さまざまな心理的な力が働いています。提案者の権威、周りの人々の反応、あるいはその場の文化といったものが、知らず知らずのうちに私たちの判断を左右しています。
本コラムでは、合意形成の舞台裏で働く、こうした「人の心の動き」に光を当てていきます。新しいシステムを受け入れる際の説得の仕組み、同僚たちの賛成や反対が持つ意味、文化的な背景がコミュニケーションのあり方をどう変えるのか。いくつかの知見を紐解きながら、合意形成という営みの奥深さを探求していきたいと思います。
論理による納得は、権威への信頼より長続きする
合意形成の出発点は、多くの場合、誰かからの「説得」です。新しい方針やツールの導入が提案されたとき、私たちは何を根拠にそれを受け入れ、あるいは拒むのでしょうか。人の態度がどのように変わり、それがどう維持されていくのかを考える上で、説得には大きく分けて二つの異なる道筋があるという考え方があります。
一つは、提示された情報の論理性をじっくりと吟味し、自らの頭で考えて結論を出す道筋。もう一つは、情報の送り手の肩書きや評判といった、内容以外の周辺的な手がかりに頼って判断する道筋です。この二つの道筋が、私たちの納得の「質」と「持続性」にどのように関わっているのかを見ていきましょう。
この問いを調べるために、ある都市の市役所で行われた調査があります[1]。そこでは、職員の業務効率化を目指して、新しい文書管理システムが導入されることになっていました。調査の設計者たちは、この新しいシステムを職員たちが受け入れる過程を追跡しました。まず、システムの導入に先立ち、全職員を対象とした3日間の操作研修会が開催されました。研修終了直後、参加した職員たちにアンケートへの回答を依頼し、システムに対する考えや感情を尋ねました。
このアンケートでは、二つの重要な要素が測定されました。一つは、研修での説明がどれだけ論理的で分かりやすかったかという「論拠の質」です。もう一つは、説明を行った専門家がどれだけ信頼できそうかという「情報源の信頼性」です。これらの要素が、職員たちのシステムに対する二つの評価、すなわち「このシステムは自分の仕事に役立ちそうだ」という実用的な評価と、「このシステムに対して好ましいと感じるか」という感情的な評価にどう結びつくのかが分析されました。
研修直後の結果は、二つの説得ルートがどちらも機能していることを示しました。システムの利点について論理的で質の高い説明を受けたと感じた職員ほど、「このシステムは仕事の役に立つ」と高く評価する傾向が見られました。これは、内容をしっかり吟味して納得するという、一つ目の道筋が働いた結果と考えられます。
一方で、説明を行った専門家に対する信頼度が高いと感じた職員は、「このシステムは好ましい」というポジティブな感情を抱きやすいだけでなく、「仕事の役にも立ちそうだ」という実用的な評価も高めることが分かりました。専門家への信頼という周辺的な手がかりが、感情と実利の両方の評価を高めていたのです。短期的には、論理と権威の双方が、人々の心を開かせる力を持っていたといえます。
この調査では、どのような職員がどちらの道筋を通りやすいのかも調べられました。その結果、導入されるシステムが自分の日々の業務と関わっている職員ほど、説明の論理性を吟味する姿勢が強いことが分かりました。自分にとって切実な問題であればあるほど、人は安易な手がかりに頼らず、真剣に内容を検討します。同様に、もともとコンピューターに関する専門知識が豊富な職員も、論理性を重視する動きを見せました。これに対し、専門知識があまりない職員は、専門家への信頼度といった周辺的な情報に判断を委ねる様子がうかがえました。
この調査の真骨頂は、ここからです。設計者たちは、最初のアンケートから3ヶ月が経過した時点で、再び職員たちに同じ内容のアンケートに答えてもらいました。時間が経つことで、人々の心にどのような変化が生まれるのかを確認するためです。
3ヶ月後の結果は興味深いものでした。「このシステムは好ましい」という感情的な評価は、全体として研修直後よりも少し下がっていました。最初の熱気が少し冷めた状態です。しかし、評価の変化の仕方は、人によって異なっていました。研修の際に、論理的な説明に基づいて「このシステムは役に立つ」と強く納得していた職員たちの評価は、3ヶ月後もほとんど低下していませんでした。彼ら彼女らの納得は、時間が経っても揺るがなかったのです。対照的に、専門家への信頼といった周辺的な手がかりに頼って好意的な態度を形成していた職員たちの評価は、色褪せやすいことが分かりました。
この時の経過が明らかにしたのは、納得の「質」の違いです。論理に基づいてじっくりと考え抜かれた納得は、深く根を張り、時間が経っても安定しています。それに対して、権威や雰囲気といった手軽な手がかりによる受容は、即効性こそあるものの、その効果は長続きしにくいのかもしれません。新しい物事を組織に根付かせようとする際、専門家のお墨付きや影響力のある人物からの推薦は、最初の抵抗を和らげ、導入のきっかけを作る上では有用でしょう。しかし、それだけで人々の心からの賛同を得て、長期的な行動変容を促すのは難しいのかもしれません。
同僚の反対が少ないほど、支持された提案は通りやすい
どんなに優れた内容の提案であっても、それが必ず採用されるとは限りません。提案の論理的な正しさや実現可能性とは別に、それを最終的に判断する管理者の意思決定には、周囲の状況、特に同僚たちの反応が影を落とすことがあります。近年、多くの企業で導入されているオンラインのアイデア投稿プラットフォームのように、従業員の意見やそれに対する他の人々の評価が「見える化」される環境では、この同僚たちの声が持つ意味は、かつてなく大きくなっています。
この現象を解明するため、北米の複数の企業で実際に運用されているアイデア管理プラットフォームの膨大なデータを分析した調査があります[2]。この調査では、従業員から投稿された5000件を超える個別のアイデアが、その後どのような運命をたどったのかが追跡されました。
分析の対象となったのは、それぞれのアイデアに関する三つの情報です。一つ目は、提案内容そのものの質。これは根拠が明確か、実現の可能性は高いか、組織にどれだけ貢献するかといった複数の観点から、専門の評価者が採点しました。二つ目は、そのアイデアに対して、他の同僚たちから寄せられた「賛成」票の数。三つ目が、同様に寄せられた「反対」票の数です。これらのデータと、最終的にそのアイデアが管理者によって採用され、実行に移されたかどうかという事実とを突き合わせることで、提案が日の目を見るまでのプロセスが明らかにされました。
分析から見えてきたのは、提案内容の質と同僚からの支持との関係です。質の高い、つまり論理的で実現可能性の高いアイデアほど、より多くの同僚から「賛成」票を集めることが分かりました。これは直感的に理解できる結果でしょう。優れたアイデアは、仲間内での評価を得やすいのです。
この同僚からの「賛成」票の数が、管理者の最終的な意思決定にどう関わっているのかが調べられました。結果、「賛成」票の数が多ければ多いほど、管理者がそのアイデアを実行に移す確率は高まっていました。多くの同僚が支持しているという事実が、管理者にとって一種の「社会的なお墨付き」として機能していることを示唆します。管理者は、「これだけ多くの人が賛成しているのなら、このアイデアは受け入れられるだろうし、実行しても大きな問題は起きないだろう」と判断しやすくなるのです。
興味深いことに、提案の質そのものは、管理者の実行決定に直接的な結びつきを持っていませんでした。質は、あくまで同僚の支持を集めるための一つの手段であり、その支持というフィルターを通して、間接的に管理者のもとに届いていた、という構図です。
この調査の重要な発見は、「賛成票が持つ力」が、もう一つの要素、すなわち「反対票」の数によって左右されるという点でした。同僚からの「反対」が全く、あるいはほとんどない状況では、「賛成」票の力は最大限に発揮され、管理者の実行を強く後押ししました。たとえ賛成の数がそれほど多くなくても、反対がなければ、管理者は安心して採用の決断を下せます。
ところが、たとえ少数であっても「反対」票が存在すると、状況は一変します。多くの「賛成」票が集まっていたとしても、反対意見が少しでもあると、その賛成票が持つプラスの効果は弱まってしまうのです。反対意見の存在が、全体の賛成ムードに水を差し、管理者の心にブレーキをかける様子が、データから見て取れました。
この調査結果から浮かび上がってくるのは、合意形成のプロセスにおける「コンセンサスの見た目」がいかに重要かということです。管理者は、提案内容の良し悪しを純粋に評価しているだけではありません。同時に、「このアイデアを実行することで、組織内に不要な波風が立たないだろうか」「反対する人々から後で突き上げを食らうことはないだろうか」といった、実行に伴う社会的なリスクも慎重に評価しているのです。
たくさんの賛成票は、「このアイデアは安全で、多くの人に歓迎されている」という安心のシグナルとして機能します。しかし、たった数票の反対票であっても、管理者に「このアイデアには異論を唱える者がいる。実行すれば面倒なことになるかもしれない」という懸念を抱かせるには十分です。
提案を通したいと考える側からすれば、賛成の声を一つでも多く集める努力は当然です。しかし、この調査の結果は、それと同じくらい、あるいはそれ以上に、反対意見を減らすこと、あるいはそもそも反対意見が出にくいような根回しや丁寧な説明を尽くすことが、最終的な成功の鍵を握っている可能性を示しています。
米国では能力、中国では敬意が提案を通す鍵
職場で現状の問題点を指摘し、改善策を提案する。そうした場面で、その「言い方」に悩んだ経験は誰しもあるのではないでしょうか。問題点を遠慮なくストレートに指摘すべきか、それとも相手の感情に配慮して、言葉を選びながら丁寧に伝えるべきか。この「伝え方」が提案の成否にどう関わるのか、その効果は、提案者が普段から周囲にどのような人物だと思われているかや、その組織が根差している文化的な背景によっても変わってきます。
この複雑な問いを解き明かすため、従業員からの提案が上司に承認されるプロセスについて、三つの要素に着目した一連の調査が行われました[3]。その三つの要素とは、①提案の「直接性」(遠回しな表現を避け、要点をはっきりと伝える度合い)、②提案者の「丁寧さ」(相手への敬意や配慮を示す言動)、③提案者の「信頼性」(仕事の能力や専門知識に対する周囲からの評価)です。これらの要素がどのように絡み合い、最終的な承認に結びつくのかを、文化的価値観が異なるとされる米国と中国という二つの国で比較検討しました。
この研究は、複数の異なる手法を組み合わせた設計になっています。オンライン上の実験で、架空のシナリオを参加者に読ませ、その反応を見ることで、三つの要素が承認に与える基本的な関係性を確認しました。その後、より現実の職場に近い状況でデータを集めるため、二つの現場調査が実施されました。一つは米国の医療施設で、もう一つは中国の太陽電池メーカーです。どちらの調査でも、従業員とその直属の上司に協力を依頼し、一定期間にわたって、従業員が行った提案の内容とその伝え方、上司がその提案をどう評価し、承認したかという情報を集めました。
米国の現場調査の結果から見ていきましょう。米国の職場では、提案は直接的であればあるほど、上司に承認されやすいという関係が見られました。曖昧で遠回しな表現よりも、問題点や改善案をはっきりと、具体的に伝えるコミュニケーションスタイルの方が、メッセージの明確性が高まり、上司からの評価を得やすいという結果が得られました。
しかし、この「直接性の効果」は、誰が言っても同じように発揮されるわけではありません。その効果の大きさは、提案者の「信頼性」によって左右されることが分かったのです。普段から「あの人は仕事ができる」「専門知識が豊富だ」と同僚や上司から評価されている、信頼性の高い従業員が直接的な提案を行ったときに、その承認率は最も高くなりました。上司の側から見れば、「能力のある人物がこれだけはっきり言うのだから、その内容は真剣に聞く価値がある」と判断するのでしょう。
一方で、提案者の「丁寧さ」は、提案が承認されるかどうかには、統計的に意味のある関連を持ちませんでした。米国の文脈においては、対人関係への配慮を示すことよりも、能力に裏打ちされた明確なコミュニケーションが、提案を通す上での鍵となる様子がうかがえます。
続いて、中国の現場調査の結果です。中国の職場でも、直接的な提案の方が承認されやすいという基本的な点は、米国と同じでした。メッセージの明確性が評価されるのは、文化を越えた共通項なのかもしれません。
ところが、その直接性の効果を後押しする要因が、米国とは異なっていました。中国では、提案者の「信頼性」、すなわち仕事の能力評価は、承認率に大きな違いをもたらしませんでした。その代わりに決定的な役割を果たしていたのが、提案者の「丁寧さ」でした。
普段から礼儀正しく、上司や同僚に対して敬意を払う姿勢で接している従業員が、勇気を出して直接的な提案を行った場合、その提案は「組織を思うがゆえの建設的な意見」として、好意的に受け入れられやすかったのです。反対に、普段から丁寧さを欠く、あるいは無礼だと見なされている人物が、たとえ正論であってもストレートな物言いをすると、それは「個人的な不満」や「上司への挑戦」と受け取られかねず、内容を吟味される前に拒絶されてしまう危険性があります。
これら二つの現場調査の結果を並べてみると、合意形成のプロセスが、文化的な価値観といかに結びついているかが浮かび上がってきます。
個人の能力や成果を高く評価し、率直なコミュニケーションを良しとする傾向のある米国のような社会では、提案の説得力は、「誰が言ったか(その人の能力)」と「何を言ったか(メッセージの明確さ)」という二つの要素に集約されます。そこでは、人間関係への配慮は二の次とされることもあります。
それに対して、集団の調和や人間関係の維持を重んじる文化的な背景を持つ中国のような社会では、「どのように言ったか(伝え方の丁寧さ)」が、提案内容そのものの評価に先立つフィルターとして機能します。相手への敬意を欠いた提案は、たとえその内容がどれほど論理的で優れたものであっても、そもそも聞く耳を持ってもらえない可能性があります。
脚注
[1] Bhattacherjee, A., and Sanford, C. (2006). Influence processes for information technology acceptance: An elaboration likelihood model. MIS Quarterly, 30(4), 805-825.
[2] Brykman, K. M., and Raver, J. L. (2023). Persuading managers to enact ideas in organizations: The role of voice message quality, peer endorsement, and peer opposition. Journal of Organizational Behavior, 44(5), 802-817.
[3] Lam, C. F., Lee, C., and Sui, Y. (2019). Say it as it is: Consequences of voice directness, voice politeness, and voicer credibility on voice endorsement. Journal of Applied Psychology, 104(5), 642-658.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『組織内の“見えない問題”を言語化する 人事・HRフレームワーク大全』、『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(ともにすばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。