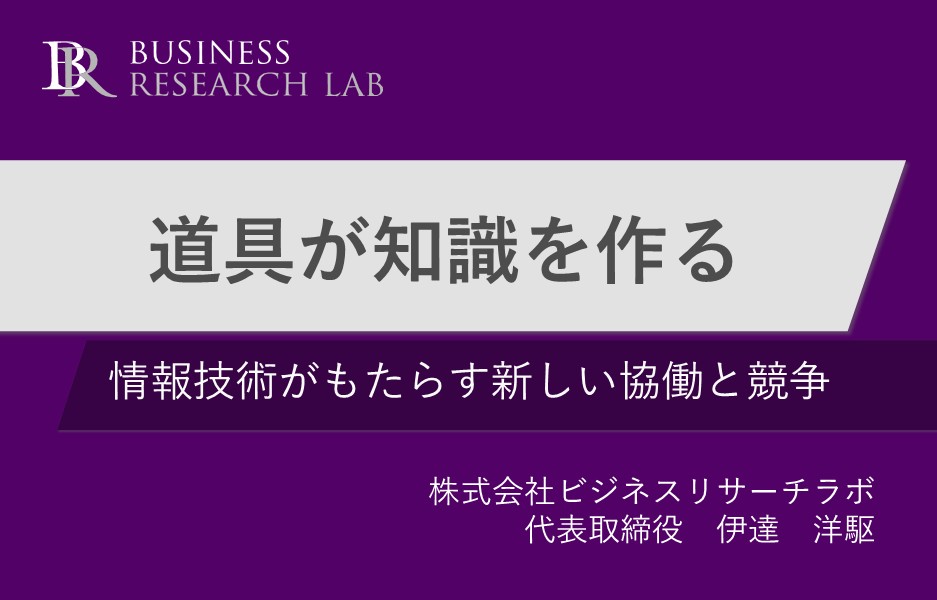2025年10月14日
道具が知識を作る:情報技術がもたらす新しい協働と競争
現代の職場では、ITツールやデジタル技術が業務の中心的な存在となっています。しかし、これらの技術が私たちの働き方や組織運営に与える意味を、どこまで理解できているでしょうか。多くの場合、技術導入は効率化や自動化といった、ある種、表面的な効果に目が向きがちです。
実際には、技術と人間の関わりは想像以上に複雑で奥深いものです。コンピューターソフトやオンラインシステムは、単純な道具を超えて、私たちの思考方法や意思決定プロセス、そして組織全体の文化まで変えてしまいます。技術は組織の中で生きているかのように振る舞い、私たちの行動や判断に予想外の変化をもたらします。
本コラムでは、そうした技術と人間の相互作用について考察していきます。IT技術がどのように組織構造を変化させるのか、技術の柔軟性が私たちの行動パターンにどのような変化をもたらすのか、オンラインにおける評価システムが従来のビジネス関係をどう再編するのか、そして日常的な道具が戦略的思考にどのような変化を生み出すのかを見ていきます。
ITのアフォーダンスが組織構造を柔軟に変化させる
1950年代から1980年代にかけて、組織と技術の関係は経営学のテーマでした。当時の研究者たちは、技術の進歩が組織のあり方をどう変えるかに強い関心を寄せていました。しかし、1980年代以降、学術界の興味は別の分野に移り、技術への関心は薄れていきました。
ところが、この間にIT技術は急速に発達し、組織の日常業務に深く浸透していきました。今日では、コンピューターやインターネットなしに業務を行うことは考えられません。しかし、この劇的な変化に対する理論的な理解は十分に追いついていませんでした。
そこで有益なのが「アフォーダンス」という考え方です。[1]アフォーダンスとは、非常に単純化して言えば、技術が人間に対して提供する「可能性」のことを指します。例えば、椅子は「座る」という可能性を提供し、ドアは「通り抜ける」という可能性を提供します。IT技術も同様に、私たちに様々な可能性を提示しています。
この視点から、IT技術が組織に提供する5つのアフォーダンスが明らかになってきました。
第一のアフォーダンスは「業務プロセスの全体可視化」です。組織内の業務プロセスは部門ごとに分断されており、全体を把握することは困難でした。しかし、統合されたデータベースやビジネスプロセス管理ツールの登場により、業務の流れを一元的に把握できるようになりました。
例えば、大手小売企業では商品の仕入れから販売まで、すべての過程をリアルタイムで追跡できるシステムを構築しています。このシステムにより、どの店舗でどの商品がいつ売れたかを瞬時に把握でき、在庫管理や商品配置の最適化が可能になりました。これは情報システムの導入を超えて、組織全体の意思決定方法を変える変化と言えます。
第二のアフォーダンスは「リアルタイム・柔軟な製品サービス創造」です。従来の製品開発は長期間を要し、一度作った製品を変更することは容易ではありませんでした。しかし、ソフトウェアベースのサービスが普及したことで、既存のサービスを組み合わせて新しい価値を即座に生み出せるようになりました。
この変化の背景には、サービス指向アーキテクチャやオープンソースソフトウェアといった技術的基盤があります。これらの技術によって、異なるシステム間での情報のやり取りが容易になり、新しいサービスの組み合わせが短期間で実現できるようになりました。同時に、多様な専門分野の人々が協力しやすい組織文化も必要です。エンジニア、デザイナー、マーケティング担当者などが境界を越えて協働することで、従来では考えられなかった速度でイノベーションが生まれています。
第三のアフォーダンスは「バーチャルコラボレーション」です。地理的に離れた場所にいる人々が、まるで同じ場所にいるかのように協働できる能力を指します。電子メール、ビデオ会議、共有プラットフォームなどのツールがこれを支えています。
しかし、技術的なツールだけでは真のバーチャルコラボレーションは実現できません。チームメンバーが安心して意見を述べられる心理的安全性や、お互いの状況を理解し合える環境づくりが必要です。うまくいっているバーチャルチームでは、定期的なコミュニケーション、明確な目標設定、そして信頼関係の構築に力を入れています。
第四のアフォーダンスは「大規模コラボレーション」です。これは従来の組織の枠を超えて、多数の人々がインターネット上で情報を共有し、共同で何かを作り上げる能力です。オンライン百科事典や群衆による予測市場などがその例です。
この形態の協働では、参加者の動機づけや品質管理が課題となります。どのようにして多くの人々の参加を促し、同時に成果物の質を保つかという問題です。成功事例では、参加しやすいルール設計、貢献者への適切な評価システム、そして品質チェックの仕組みが整備されています。
第五のアフォーダンスは「シミュレーション・人工的表象」です。コンピューターの力を借りて、現実の状況を模擬し、様々な仮説や戦略を事前に検証できる能力です。企業資源計画システムやビジネスインテリジェンスツールがこの能力を支えています。
従来は経験や直感に頼っていた意思決定が、データに基づいたアプローチに変わりつつあります。ただし、シミュレーション結果を実際の業務に活かすためには、データを読み解く能力と、結果を現実の文脈で解釈する組織的な学習能力が必要です。
これら5つのアフォーダンスは、それぞれが独立して機能するものではありません。組織内で相互に関連し合いながら、従来の組織構造を柔軟で適応的なものに変えていきます。階層的で固定化された組織から、プロセス中心で流動的な組織への変化が生まれています。
このような変化は、組織の境界そのものも曖昧にしていきます。明確に内部と外部が分かれていた組織が、顧客や取引先、さらには競合他社とも協働する新しい形態を生み出しています。技術と組織が互いに作用し合いながら進化する現代において、私たちは組織というものの概念自体を見直す必要に迫られているのです。
技術の柔軟性が組織の行動パターンを変化させる
技術と人間の関係を理解する上で、両者がどのように相互に作用し合うかという問題は複雑です。従来の考え方では、技術は人間が使う道具であり、人間が技術をコントロールするという一方向的な関係が想定されていました。しかし、実際の職場を観察してみると、技術と人間の関係はもっと動的で相互依存的なものであることがわかります[2]。
ある自動車メーカーの安全性評価部門で起きた出来事は、この複雑な関係を理解する上で参考になります。この部門では、自動車の衝突安全性能を評価するために、物理的な衝突実験に頼っていました。しかし、コンピューターシミュレーション技術の発達により、「CrashLab」という新しいシミュレーションシステムが導入されることになりました。
この変化の過程で観察されたのは、技術と人間の間で起こる「絡み合い」という現象です。人間が技術に対して何らかの働きかけを行うと、技術側もそれに応答し、さらにその応答が人間の行動に新たな変化をもたらすという循環が生まれました。
この絡み合いのプロセスは、5つの段階を通じて展開されました。
最初の段階では、エンジニアたちが既存の解析ツールに対して不満を感じていました。従来のツールでは、同じ条件で実験を行っても毎回異なる結果が出てしまい、一貫性のある評価ができなかったのです。この制約を解決するために、CrashLabシステムの開発が決定されました。CrashLabには、自動的に一貫性のあるレポートを作成する機能が組み込まれました。
第二段階では、CrashLabの標準化機能がエンジニアたちに新しい可能性を提示しました。作業を標準化し、評価プロセスを高速化できる可能性です。この可能性を活かすために、組織内に新しい標準化推進チーム「Bestpra」が設立され、標準的な作業手順の策定が始まりました。
第三段階で、管理者層が新たな制約を感じるようになりました。CrashLabによって作業は速くなったものの、まだ十分ではないと感じたのです。そこで、モデル設定を自動化する新機能の追加が決定されました。この機能によって、エンジニアが手動で行っていた複雑な設定作業が簡素化されました。
第四段階では、新機能によってエンジニアたちに予想外の可能性が生まれました。モデル設定にかかる時間が半分に短縮されたことで、浮いた時間をより深い分析作業に充てることができるようになりました。この結果、エンジニア同士が相談し合い、結果について議論する新しい習慣が生まれました。
最終段階では、エンジニアたちがCrashLabに対して新しい制約を感じるようになりました。複数のシミュレーション結果を比較検討したいのに、既存の機能では十分に対応できなかったのです。この要求に応えて、結果を視覚的に比較できる新機能「クロスプロット」が開発され、同時に結果の体系的分析を行う新しい組織グループも設立されました。
この事例から見えてくるのは、技術と人間が互いに影響を与え合いながら、組織全体の行動パターンを変化させていく過程です。人間が技術に対して「制約」を感じれば技術の改良を求め、技術が「可能性」を提示すれば人間の行動様式が変わる。このような相互作用を通じて、組織内の業務プロセスや人間関係が継続的に進化していきます。
この絡み合いのメカニズムには、二つの要素が関わっています。一つは「人間的主体」で、これは人間が目的を設定し、それを実現しようとする能力です。もう一つは「物質的主体」で、これは技術が人間の完全なコントロールを離れて、独自の動作を示す能力です。
例えば、CrashLabが自動的にレポートを生成する機能は、人間が直接操作しなくても動作します。この「技術の自律性」が、人間に新しい可能性や制約を提示し、それに対する人間の反応がさらなる技術改良や組織変化を生み出すのです。
このような視点から組織を見ると、技術導入や変更は一回限りの出来事ではなく、継続的な相互適応のプロセスであることがわかります。技術を導入する際には、それが組織に与える効果だけでなく、その後に続く一連の相互作用も考慮に入れる必要があります。
オンラインレビューがホテルの説明責任を再構成する
オンラインにおける評価システムが企業活動に変化をもたらしています。この変化は情報技術の進歩を超えて、企業と顧客の関係性そのものを再定義する現象として現れています。
旅行業界でこの変化が顕著に現れているのが、オンラインレビューサイトの普及です[3]。もともと、ホテルや宿泊施設の評価は主に専門的な評価機関によって行われていました。ミシュランガイドのような権威ある出版物や業界専門誌が、施設の質を判定する基準となっていたのです。こうした評価システムでは、一般の宿泊客の意見は限定的な役割しか果たしていませんでした。
しかし、インターネットの普及とともに状況は一変しました。一般の利用者が自由に意見を投稿できるプラットフォームが登場し、それらの意見が集約されて施設のランキングが決定されるシステムが確立されました。この変化によって、専門家主導の評価体系から、一般顧客の主観的体験に基づく評価体系への移行が起こりました。
この現象を理解するために、イギリスの地方にある小規模ホテルの事例を見てみましょう。このホテルは、オンラインレビューサイトの活用により変化を遂げました。以前は地域でそれほど知られていない施設でしたが、顧客からの高評価レビューが蓄積されることで、やがて地域で最上位にランクされるホテルとなり、売上も大幅に向上しました。
この変化の背景には、「説明責任」という概念の変化があります。説明責任とは、組織や個人が自らの行動について他者に対して説明し、その評価を受け入れる社会的な関係のことです。従来のホテル業界では、この説明責任は主に業界の専門家や評価機関に対するものでした。
ところが、オンラインレビューシステムの普及により、ホテル経営者は「匿名の一般顧客」に対して説明責任を負う状況が生まれました。この変化は表面的なものではありません。日々の経営判断から従業員教育、サービス提供の細部に至るまで、すべてが一般顧客の評価を意識した形で行われるようになりました。
オンラインレビューの特徴は、その即時性と透明性にあります。宿泊客は滞在中や滞在直後に、体験した内容をレビューとして投稿できます。これらのレビューは他の潜在的な顧客に即座に公開され、施設選択の判断材料として利用されます。しかも、このプロセスは24時間365日継続的に行われるため、ホテル経営者は常にサービス品質の監視と改善に取り組まざるを得ない状況に置かれます。
この事例のホテル経営者は、レビューサイトを定期的にチェックし、投稿された評価内容を従業員の教育やサービス改善の情報源として活用していました。良い評価は従業員のモチベーション向上に役立て、改善点の指摘は業務改善の指針として取り入れていました。
しかし、この新しいシステムには課題も存在します。悪意のあるレビューや事実に基づかない評価が投稿される可能性があり、これらが施設の評判に深刻な損害を与える場合があります。経営者はこうした不正確な情報への対応策を講じる必要があり、レビュー内容の解釈や対応方法が新たな経営課題となっています。
このシステムのもう一つの特徴は、評価算出のアルゴリズムが非公開であることです。どのような基準でランキングが決定されているかが明確でないため、ホテル経営者にとっては不確実性の要因となっています。しかし、レビューの数の多さや投稿の継続性が信頼性を高めているという認識も広がっています。
オンラインレビューシステムは、従来は無名だった地方の小規模施設にとって大きな機会も提供しています。専門的な評価機関からの評価を得ることが困難だった施設でも、優れたサービスを提供すれば顧客からの高評価を獲得し、知名度と売上の向上を実現できるようになったのです。
人工物は戦略活動で知識を抽象化し代替する
現代の組織において戦略を立案する際、私たちは様々な道具や資料を使用します。写真、地図、データ資料、表計算ソフト、グラフなど、これらの物理的な道具は単純な補助的な存在ではありません。実際には、戦略的思考と意思決定の過程において中心的な役割を果たしています。
この現象を深く理解するために、再保険業界で働く引受マネージャーの業務を観察した研究があります[4]。再保険とは、保険会社が引き受けたリスクをさらに別の保険会社に分散させる仕組みです。引受マネージャーは、様々な保険契約を評価し、どの契約を引き受けるかを決定する専門家です。
この業務では、一つの契約を評価するために膨大な情報を処理する必要があります。建物の構造、立地条件、過去の災害データ、財務情報など、多岐にわたる情報を総合的に判断して、リスクの程度と適正な価格を決定しなければなりません。
引受マネージャーたちは、この複雑な判断プロセスを5つの段階に分けて、それぞれに異なる道具を使用していることがわかりました。
第一段階は「物理的実体化」です。ここでは写真が主要な道具として使われます。建物の外観、構造、周辺環境を撮影した写真を検討することで、保険対象となる物件の物理的特性を把握します。写真によって、書面では伝わらない建物の状態や潜在的なリスク要因を視覚的に理解できます。
第二段階は「位置付け」で、地図が中心的な道具となります。インターネット上の地図サービスを活用して、対象物件の正確な立地を確認し、周辺の地理的条件を把握します。河川からの距離、山地の近さ、都市部からのアクセスなど、災害リスクや事故発生の可能性に関わる地理的要因を検討します。
第三段階は「数値化」で、データパックと呼ばれる資料が使用されます。このデータパックには、建物の価値、面積、構造材料、建築年数など、リスク評価に必要な定量的情報が網羅的に記載されています。これらの数値データにより、リスクの規模と範囲を把握できます。
第四段階は「分析」で、表計算ソフトウェアが主要な道具となります。データパックから得られた情報を表計算ソフトに入力し、数式や計算モデルを使ってリスクを金融商品として数値化します。過去の損失データや統計モデルを組み合わせて、損失発生の確率や予想される損失額を計算します。
最終段階は「選択」で、グラフが決定的な道具として機能します。複数の契約案件を視覚的に比較できる形でグラフ化し、リスクと収益性の観点から最適な投資判断を行います。グラフによって、複雑な数値データが直感的に理解できる形に変換され、最終的な意思決定が促進されます。
これら5つの段階を通じて、物理的で具体的な情報が段階的に抽象化されていく過程が観察されました。写真で捉えた現実の建物が、最終的には投資判断のためのグラフ上の点として表現されるのです。この変化は情報の整理にとどまりません。各段階で使用される道具が、前段階で得られた知識を引き継ぎながら、新しい形式で再構成する役割を果たしています。
この現象を理解するために、「抽象化」と「代替」という二つの概念が提起されました。抽象化とは、具体的で詳細な情報が徐々に簡素化され、本質的な要素のみが残されていく過程です。代替とは、ある段階の道具が前段階の知識を別の形式で表現し直す過程です。
写真から地図への移行では、建物の詳細な構造情報は省かれ、位置関係という抽象的な情報が強調されます。地図からデータパックへの移行では、地理的な視覚情報が数値データに置き換えられます。このように、各段階で情報の形式は変化しますが、リスク評価に必要な本質的な知識は保持され、むしろ意思決定に適した形に精製されていきます。
この研究から得られる洞察は、戦略立案や意思決定における物理的道具の重要性です。戦略は抽象的な思考活動ではなく、具体的な道具を使った実践的な活動として理解する必要があります。使用する道具の選択や活用方法が、戦略の質や有効性に直接的な影響を与えます。
PowerPointは戦略立案の知識文化を形成する
現代の組織において、戦略立案の場面でよく使用されるツールの一つがPowerPointです。会議室で映し出されるスライド、配布される資料、メールで共有されるプレゼンテーション。これらはもはや組織活動に欠かせない存在となっています。しかし、PowerPointの役割は情報伝達手段を超えて、組織の戦略的思考そのものを形成しています。
ある大手通信技術企業での観察により、PowerPointが戦略立案プロセスに与える影響が明らかになりました[5]。この企業では、新技術の開発方向や市場戦略の決定において、PowerPointが中心的な役割を果たしていました。
PowerPointの影響を理解するためには、それを単なるソフトウェアツールではなく、組織内での知識生産を支える「仕組み」として捉える必要があります。科学研究の分野では、実験器具や測定装置が研究成果の質に影響を与えることが知られています。同様に、組織の戦略立案においても、使用するツールが思考プロセスや成果に影響を与えるのです。
PowerPointが戦略立案に与える影響は、二つの側面から観察されました。
第一の側面は「協働による意味交渉」です。戦略立案は本質的に不確実性の高い活動です。市場の将来動向、技術の発展可能性、競合他社の行動など、多くの要因が不明確な状況で重要な判断を下さなければなりません。このような状況では、様々な専門分野の知識を持つ人々が協力して、断片的な情報を統合し、一貫した戦略を構築する必要があります。
PowerPointは、この協働プロセスを促進する独特の特性を持っています。スライドはモジュール化されており、個別のスライドを自由に組み合わせたり並び替えたりできます。この特性によって、異なる視点や専門知識を持つメンバーが、それぞれの貢献を提示し、全体の議論に統合することが可能になります。
例えば、新技術開発プロジェクトでは、技術担当者が技術的可能性について、マーケティング担当者が市場機会について、財務担当者が収益性についてそれぞれスライドを作成します。これらのスライドを組み合わせることで、多角的な視点から総合的な戦略が構築されていきます。
スライドの共有と編集も重要です。地理的に分散したチームメンバーが、同じ文書を継続的に更新し、コメントを追加し、修正を加えることで、時間をかけて戦略の内容が精緻化されていきます。この過程では、個人の意見が組織の集合的知識に変換される現象が観察されます。
第二の側面は「地図作成による境界線引きと利害調整」です。戦略立案は単純な分析活動ではなく、組織内の様々な利害を調整し、限られた資源をどこに配分するかを決定する政治的プロセスでもあります。PowerPointは、この政治的交渉の手段として機能します。
戦略文書の「オーナー」となった個人やグループは、どのスライドを含めるか、どの情報を強調するか、どの視点を前面に出すかについて影響力を持ちます。この選択によって、戦略の方向性が事実上決定される場合があります。
例えば、ある技術開発プロジェクトでは、技術チームとマーケティングチームの間で意見の対立が生じました。技術チームは技術的優位性を重視し、マーケティングチームは市場での実現可能性を重視していました。最終的な戦略文書では、技術チームが作成したスライドが中心となり、マーケティングチームの懸念は脇に置かれる形となりました。この結果、プロジェクトの方向性は技術重視のものとなったのです。
PowerPointが「正式な戦略」として承認されることで、その内容は組織的な正当性を獲得します。一度承認された戦略は、今後の意思決定や資源配分の基準となり、組織の行動を方向付けます。この意味で、PowerPointは単なる記録ではなく、組織の将来を規定する「地図」としての役割を果たします。
PowerPointの物理的特性も影響を与えます。スライドという限られた空間には、複雑な情報を簡潔にまとめる必要があります。この制約によって、詳細な議論は省略され、本質的なポイントのみが残される結果となります。一方で、この簡素化により、複雑な戦略的議論が関係者にとって理解しやすい形で共有されるという利点もあります。
視覚的な表現能力もPowerPointの特徴の一つです。グラフ、図表、画像を効果的に組み合わせることで、数値データや抽象的概念を直感的に理解できる形で提示できます。この視覚化によって、異なる専門分野の人々が共通の理解基盤を持ちやすくなります。
しかし、PowerPointの使用には課題も存在します。スライドの制約により、複雑な論理構造や微妙な判断が単純化されすぎる危険性があります。視覚的なインパクトを重視するあまり、表面的で説得力に欠ける議論になる可能性もあります。
脚注
[1] Zammuto, R. F., Griffith, T. L., Majchrzak, A., Dougherty, D. J., and Faraj, S. (2007). Information technology and the changing fabric of organization. Organization Science, 18(5), 749-762.
[2] Leonardi, P. M. (2011). When flexible routines meet flexible technologies: Affordance, constraint, and the imbrication of human and material agencies. MIS Quarterly, 35(1), 147-167.
[3] Scott, S. V., and Orlikowski, W. J. (2012). Reconfiguring relations of accountability: Materialization of social media in the travel sector. Accounting, Organizations and Society, 37(1), 26-40.
[4] Jarzabkowski, P., Spee, A. P., and Smets, M. (2013). Material artifacts: Practices for doing strategy with ‘stuff’. European Management Journal, 31(1), 41-54.
[5] Kaplan, S. (2011). Strategy and PowerPoint: An inquiry into the epistemic culture and machinery of strategy making. Organization Science, 22(2), 320-346.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。