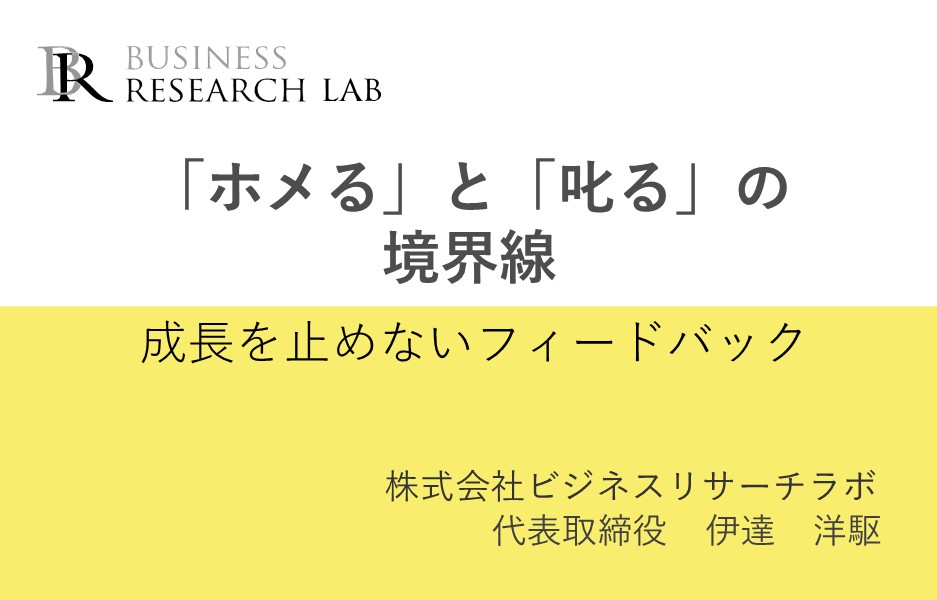2025年10月10日
「ホメる」と「叱る」の境界線:成長を止めないフィードバック
チームを率いる立場にある人ならば、一度は直面するであろう問いがあります。人を育てる上で、ホメるべきか、叱るべきか。あるいは、そのバランスをどう取るべきか。多くのリーダーが、「最近はホメることが推奨されている」という風潮を意識しながらも、「言うべきことは厳しく言わなければ、組織の規律が保てないし、本人のためにもならない」という感覚との間で、揺れ動いているのではないでしょうか。
この葛藤は、多くの管理職が経験則と誠実さから生み出す、真摯な悩みです。私たちはこれまで、この問題を「アメとムチ」という二元論で捉えがちだったかもしれません。しかし、この伝統的な比喩は、フィードバックという複雑なコミュニケーションを、個人の感覚やその場の感情に委ねてしまう危うさを伴っています。ある時は過度に甘くなり、ある時は感情的に厳しくなる。その不安定さが、かえって部下の成長を阻害し、信頼関係を損なう一因になります。
この度、私たちは『科学的に正しいホメ方』という本を上梓しました。その探求の過程で見えてきたのは、「ホメる」ことの重要性だけではありませんでした。科学の光を当てることで、「ホメる」という行為の本質が明らかになるにつれて、対極にあると思われた「叱る」という行為の役割をも、新たな視点から再定義できるという可能性です。
本コラムでは、その核心に触れていきます。「ホメる」と「叱る」を対立するものとしてではなく、一貫した育成方針のもとで統合するためのアプローチです。なぜ質の高い「ホメ」がなければ、厳しいフィードバックは機能しないのか。そして、人の成長を止めないための建設的なフィードバックとは、本来どうあるべきなのか。感覚論から一歩踏み出し、その構造を共に考えていきたいと思います。
「叱る」を機能させるための土台
最初に、重要な事実を共有しなければなりません。それは、多くのリーダーが望む「効果的な叱責」、すなわち相手の行動を修正し成長を促すネガティブ・フィードバックは、それ単体では十分に機能しないということです。むしろ、機能させるためには前提条件があります。それが、ポジティブ・フィードバックの蓄積です。
ある研究では、安定した人間関係を築いているチームでは、肯定的なやりとりと否定的なやりとりの比率が「5対1」であると示されています[1]。これは努力目標ではありません。厳しいフィードバックという「1」の支出に耐えうる関係性を維持するための、必要な「心理的な貯金」の残高と考えるべきでしょう。この貯金がなければ、いざという時の支出に口座は耐えられず、関係性は破綻してしまいます。
この「心理的な貯金」はどのように蓄えられるのでしょうか。それは、日々の何気ないコミュニケーションの中で、相手の貢献や努力のプロセスに光を当て、具体的な感謝や承認の言葉を積み重ねることによって可能になります。「先日の資料、あの部分のデータ分析が非常に丁寧で、提案の説得力につながりました。ありがとうございます」といった、具体的な行動とその価値を伝える言葉の繰り返しが、相手の中に「このリーダーは、自分の仕事を見て、正当に評価してくれる味方だ」という認知を形成していきます。
特に重要なのは、結果だけでなくプロセスを承認することです。成功に至るまでの試行錯誤や、困難な状況で見せた粘り強さを言語化して伝えることで、相手は「結果が出なくても、自分の努力は無駄ではなかった」と感じることができます。この感覚が、信頼関係の強固な礎となります。
信頼の土台がない状態で発せられた厳しい言葉は、相手にどう届くでしょうか。それは成長を促すフィードバックではなく、「人格への攻撃」として受け取られます。その結果、相手は心を閉ざし、反発するか、あるいは過度に萎縮して次の挑戦を恐れるようになります。
興味深いことに、私たちの脳には、自己肯定感を守るために、自分にとって都合の悪い情報を記憶から排除しようとする「記憶無視」という働きがあることも分かっています。「何度言っても直らない」という現場の嘆きは、相手の意欲の問題だけでなく、そもそも厳しい言葉が記憶に定着しにくいという、人間の認知システムに起因する可能性があります。叱責が相手の記憶に残らないのであれば、それは自己満足の叱責であり、行動変容にはつながりません。ネガティブな感情だけが残り、関係性を蝕んでいくだけです。
厳しいフィードバックを相手に届け、行動の修正を真剣に願うのであれば、リーダーがまず全力を注ぐべきは、「叱り方」の技術を磨くこと以前に、日々のポジティブ・フィードバックを通じて、揺るぎない信頼関係というインフラを構築することです。効果的に「叱る」ための道は、まず正しく「ホメる」ことから始まります。
成長を促すフィードバックと、成長を止めるフィードバック
信頼関係という土台が築かれた上で、行動修正を促すための「叱る」という行為、すなわちネガティブ・フィードバックについて考えていきましょう。しかし、その伝え方を誤れば、せっかく築いた信頼を損ない、相手の成長の芽を摘んでしまいかねません。「叱る」という行為の目的は、あくまで「望ましくない行動を修正し、相手の未来の成長を促すこと」にあります。この目的を達成するために、本書で探求した科学的知見は、成長を促すフィードバックと、逆にそれを止めてしまうフィードバックの間に境界線があることを示しています。
第一の境界線は、変えられる「行動」を扱うか、変えられない「人格」を扱うか、という点です。本書では、個人の才能や資質といった固定的なものを対象とする「能力ホメ」が、失敗への恐怖心を生み、挑戦する意欲を削いでしまう危険性を指摘しています。これは、自分の能力は固定的であると考える「固定マインドセット」を強化してしまうためです。ネガティブ・フィードバックにおいても、この構造は同じでしょう。「なぜ◯◯さんはいつも注意力散漫なのか」といった人格への非難は、「自分はそういう人間だから仕方がない」という諦めにつながり、改善への道を閉ざしてしまいます。
一方で、本書が推奨する、具体的な行動や努力の過程に焦点を当てる「プロセスホメ」は、能力は努力で伸ばせると考える「成長マインドセット」を育みます。同様に、ネガティブ・フィードバックも「今回の報告書では、この部分に事実確認の漏れがありました」というように、修正可能な具体的な「行動」に限定して指摘することで、相手はそれを次への学習機会として捉えることができます。成長を促すフィードバックは、相手が変えられるものに焦点を当てます。
第二の境界線は、未来の「目標」を示すか、過去の「失敗」を問いただすか、という点です。そもそもフィードバックとは、「現状」と「目標」とのギャップを相手に認識させ、その差を埋めるための行動変容を支援するコミュニケーションと定義されます。この定義に照らせば、「なぜあんなミスをしたんだ!」という過去を糾弾するだけの問いかけは、フィードバックとして機能していません。それは相手を心理的に追い詰め、自己防衛的な言い訳を引き出すだけで、未来の解決策にはつながらないからです。
成長を促すフィードバックは、未来志向です。「このミスを防ぐために、次回からはこのチェックリストを使ってみてはどうですか」というように、現状の課題を指摘すると同時に、目標達成に向けた具体的な軌道修正案を示すことで、相手の思考は過去への後悔から、未来への行動計画へと切り替わります。
第三の境界線は、「信頼」を育むか、「恐怖」を植え付けるか、という点です。本書では、ポジティブなやりとりを目撃した第三者の協力行動が増す「感謝の目撃効果」などを紹介していますが、これはフィードバックがオープンな場で行われることで組織に良い影響が広がる例です。
しかし、ネガティブ・フィードバックの場合は全く逆の効果を生む可能性があります。公衆の面前での叱責は、相手の尊厳を深く傷つけるだけでなく、それを見ている他のメンバーにも「この組織では、失敗は許されない」という恐怖心を植え付けます。これは、挑戦や自由な発言の土壌となる心理的安全性を破壊する行為です。
本書が示すように、フィードバックの効果は相手との信頼関係の質に左右されます。ネガティブ・フィードバックは、その信頼関係へのダメージを最小限に抑え、建設的な対話を可能にするために、心理的に安全な場で行われなければなりません。
これらの境界線を意識することは、フィードバックを感情の発露ではなく、相手の未来のために行使される技術へと昇華させるでしょう。
皆さんならどう使い分けるか
理論を理解した上で、次に重要なのは、それを現実の複雑な状況でいかに応用するかです。ここでは、リーダーが遭遇するであろう三つの場面を取り上げ、どのようなフィードバックが適切かを考えていきます。
一つ目のケースは、期待の若手が、準備を重ねて臨んだ初めての大きなプレゼンテーションで失敗してしまった場面です。この時、リーダーが考えるべきは、相手の心理状態です。彼はおそらく自信を失い、自己嫌悪に陥っているでしょう。ここで必要なのは叱責ではありません。失敗を責めれば、彼はプレゼンテーション自体に恐怖心を抱き、二度と挑戦できなくなるかもしれません。
まずは、挑戦したという事実を承認し、信頼関係を再確認することです。具体的には、「大変でしたね。でも、あの難しい質問に対して、逃げずに誠実に答えようとした姿勢は素晴らしかったと思います」と、結果ではなくプロセスを評価する言葉をかけます。そして、「今回の経験を次に活かすために、どこを改善すればもっと良くなるか、後で一緒に振り返ってみましょう」と、未来志向の対話を提案する。これが、挑戦の心を折らずに次へとつなげるフィードバックです。
二つ目のケースは、何度も同じ種類のケアレスミスを繰り返す中堅社員の場面です。この状況では、行動修正が求められます。これまで築いてきた「心理的な貯金」があれば、今こそネガティブ・フィードバックを行うべきタイミングです。ただし、その際も原則は守らなければなりません。
例えば、1対1の場で、「◯◯さんの作成する報告書の、この項目での計算ミスが今月で3回目になります。このままではチームの信頼に関わるから、一度原因を一緒に考えたいと思います」と、人格ではなく具体的な行動と、その影響を伝えます。そして、「どういう状況でこのミスが起きやすいか、教えてもらえますか」と、過去を糾弾するのではなく、未来の対策を共に考える姿勢を示すことが重要です。一方的に解決策を押し付けるのではなく、本人が原因を特定し、自ら対策を立てられるよう導くことで、主体的な改善を促すことができます。
三つ目の、そして高度なケースは、個人の成果は非常に高いものの、その言動がチームの和を乱しがちなエース社員の場面です。ここでいきなり協調性の欠如を指摘すれば、反発を招くでしょう。
まずは、「◯◯さんの今期の目標達成はチームにとって本当に大きな力になっています。感謝しています」と、彼の成果を承認し、自分が味方であることを伝えます。その上で、「ただ一つ相談があるのですが」と切り出し、「先日の会議での〇〇という発言が、少し他のメンバーを萎縮させてしまったかもしれません」と、主観的な評価ではなく、観察された具体的な「行動」と、それがもたらした「事実」を伝えます。
そして、「◯◯さんの影響力は大きいからこそ、チーム全体のパフォーマンスを最大化するために、もう少し表現を工夫してもらえると、チームはさらに強くなると思います」と、その存在価値を認めた上で、より高いレベルでの貢献を期待するメッセージとして伝えます。これは叱責ではなく、さらなる成長への「招待」です。
これらのケースから分かるように、「ホメる」と「叱る」は単純な二者択一ではありません。それは、相手の状況、習熟度、自分との信頼関係の蓄積量といった変数を見極め、「相手の未来の成長」という目的に照らし合わせながら、最適な言葉を選択していくプロセスなのです。
「ホメ上手」かつ「叱り上手」になる
現代の組織においてリーダーに求められるのは、かつてのような画一的な「アメとムチ」による管理能力ではありません。それは、チームという複雑な生態系の中で、メンバー一人ひとりの状況と心理を理解し、その成長段階に応じてフィードバックという介入を精密に最適化していく技術です。
質の高い「ホメ」によって信頼の土台を築き、その土台の上で、必要な時には的確に「叱る」、すなわち未来志向で行動の修正を促す。この両輪が回ることで、人と組織は持続的に成長していくことができます。真に「叱り上手」なリーダーは、例外なく、その何倍も「ホメ上手」であるはずです。
私たちが執筆した『科学的に正しいホメ方』は、その出発点として、「ホメる」という行為がいかに深く、そして科学的な知見に裏打ちされたものであるかを探求した一冊です。その本質を理解し、実践することは、自ずと皆さんの「叱る」という行為の質をも変容させていくでしょう。手にとっていただけると嬉しいです。
脚注
[1] 本コラムで引用している研究は『科学的に正しいホメ方』において詳細および文献情報を紹介しています。
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。