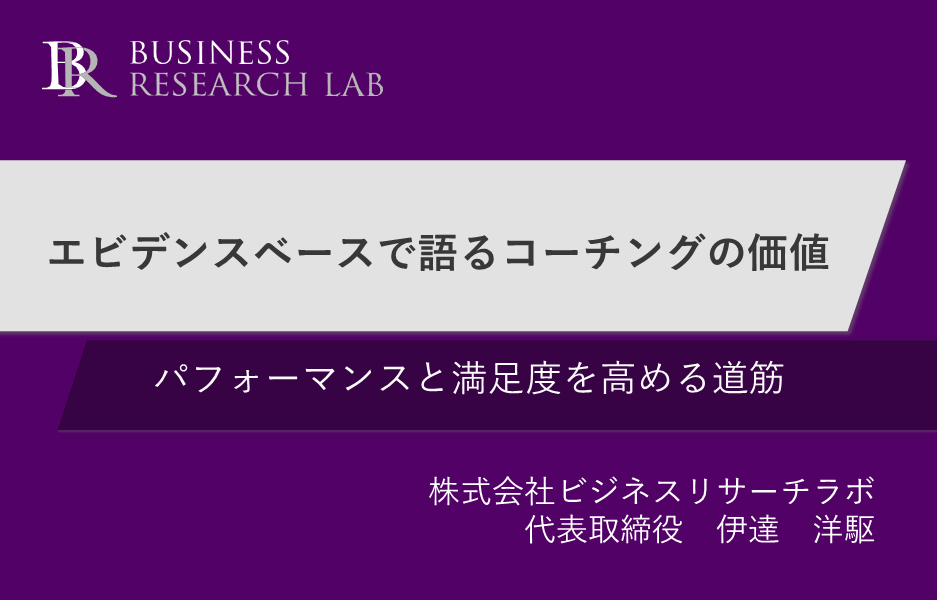2025年10月10日
エビデンスベースで語るコーチングの価値:パフォーマンスと満足度を高める道筋
個人の成長と組織の発展を両立させる育成手法として、コーチングが導入されるようになっています。経営者やマネージャーから若手社員まで、様々な階層でコーチングが活用される一方で、その価値についてはまだ十分に理解されていないのが実情でしょう。
コーチングとは、対話を通じて相手の潜在能力を引き出し、自主的な行動変化を促すアプローチです。しかし、その効果は一体どこまで実証されているのでしょうか。コーチの専門性によって効果に違いはあるのでしょうか。そして、どのような心理的メカニズムを通じて、個人と組織に変化をもたらすのでしょうか。
本コラムでは、コーチングの効果を、5つの異なる視点から紹介します。コーチの専門性による実践の違いから始まり、科学的根拠に基づく効果の実証、さらには自己効力感や心理的資本といった心理学的概念を通じた効果のメカニズムまで、包括的に解き明かしていきます。
コーチングの実践は、心理学の専門分野ごとの差も大きい
コーチングの世界を覗いてみると、実践者の背景や専門性が多様であることに気づきます。心理学者もいれば、ビジネス経験豊富な元経営者もいます。同じ心理学者であっても、カウンセリング、臨床、産業組織といった専門分野は様々です。この多様性は果たしてコーチングの実践にどのような違いを生み出すのでしょうか。
アメリカで実施された研究では、428名のエグゼクティブコーチを対象に、その実践方法の分析が行われました[1]。参加者は心理学者172名と非心理学者256名に分けられ、使用するアセスメントツール、コーチングのアプローチ、クライアントとのコミュニケーション方法、契約期間などについて調査されています。
結果は、「心理学者コーチ対非心理学者コーチ」という単純な図式を覆すものでした。確かに両者の間には統計的に有意な違いが存在しました。心理学者コーチは博士号取得者が多く、経験年数も長く、料金設定も高めでした。実践面では、クライアントの上司や同僚へのインタビュー、多面評価といった客観的なアセスメントを好む傾向がありました。一方、非心理学者コーチはセッション回数を多く設定し、成功の評価においてクライアント本人の自己評価により重きを置いていました。
しかし、興味深い発見は別のところにありました。心理学者という大きな括りの中で、異なる専門分野間の実践方法の違いが、心理学者と非心理学者の違いと同程度に大きかったのです。産業組織心理学者はビジネス関連のトピックを扱うことが多く、臨床心理学者は企業のCEOや起業家をクライアントとすることが多いなど、専門分野によってクライアント層やアプローチに特色が見られました。
この研究が浮き彫りにしたのは、コーチの質を単純に「心理学者か否か」で判断することの限界です。コーチの専門性や実践スタイルは、その人の学歴や資格だけでは予測できないほど複雑で多様です。
コーチングの効果は厳格な基準によっても実証された
コーチングの実践者が多様である一方で、その効果については長年にわたって議論が続いてきました。「本当に効果があるのか」「科学的根拠は十分なのか」といった疑問に対して、厳格な研究手法で答えを出そうとした研究があります[2]。
この研究の特徴は、分析対象をランダム化比較試験のみに限定したことです。ランダム化比較試験とは、参加者を無作為にコーチングを受けるグループと受けないグループに分け、両者を比較することで介入の効果を測定する手法です。
研究者たちは、膨大な文献データベースから1,055件の論文を抽出し、厳格な基準でスクリーニングを行いました。その結果、最終的に11件の研究が分析対象として選ばれました。これまでのコーチング研究の多くが、より緩やかな基準で実施されていたことを考えると、この選別の厳しさがうかがえます。
選ばれた研究で測定されたコーチングの成果は、パフォーマンス、ウェルビーイング、対処能力、仕事への態度、目標志向の自己調整といった多岐にわたる領域に分類されました。これらの成果は統一的な効果量に変換され、異なる尺度で測定された結果を共通の基準で比較できるようになりました。
分析の結果は、コーチングの価値を裏付けるものでした。全ての成果を総合した効果量は0.42となり、これは統計的に有意な中程度のポジティブな効果を意味します。個別の成果カテゴリーでも、態度、対処能力、自己調整、ウェルビーイングのすべてにおいて、コーチングが統計的に有意な正の効果を持つことが確認されました。
ただし、この効果量は先行研究よりも控えめでした。より緩やかな基準で研究を選定した過去のメタ分析では、より大きな効果量が報告されていました。これは、質の低い研究を含めるとコーチングの効果が過大に評価される可能性があることを示唆しています。
研究者たちは、参加者の年齢がコーチングの効果に与える影響についても調査しましたが、30歳未満と30歳以上のグループ間で効果の大きさに有意な差は見られませんでした。これは、コーチングが年齢に関係なく効果を発揮する汎用性の高い手法であることを示しています。
コーチングは自己効力感を高め、組織に利益をもたらす
科学的根拠によってコーチングの効果が実証される中で、具体的にどのような心理的変化が個人に起こるのかを詳しく調べた研究があります。英国の大規模な公共セクター組織で2年間にわたって実施されたこの研究は、ディベロップメンタルコーチングが従業員の自己効力感に与える効果を検証しました[3]。
自己効力感とは、特定の状況において目標を達成するために必要な行動をうまく実行できるという、自分自身の能力に対する信念です。この信念が強い人は、困難な課題にも積極的に挑戦し、挫折してもあきらめずに取り組み続ける傾向があります。
研究では、過去2年間にディベロップメンタルコーチングを受けた61人の従業員と、コーチングを受けていない57人の従業員を比較しました。ディベロップメンタルコーチングとは、仕事のスキルだけでなく、キャリアや人間関係といった幅広いテーマを扱い、全人格的な成長を支援するアプローチです。
データ収集には質的手法と量的手法の両方が用いられました。まず、コーチ、被コーチ、プログラム関係者に対してフォーカスグループインタビューを実施し、コーチング体験の生の声を収集しました。これらの声を分析した結果をもとに、自己効力感を測定する標準的な質問紙を含むアンケートが作成され、両グループの比較が行われました。
結果、コーチングを受けたグループは、受けていない対照グループと比較して、統計的に有意に高い自己効力感スコアを示しました。この結果は、ディベロップメンタルコーチングが従業員の自信や目標達成能力への信念を高める上で、効果を持つことを実証しています。
自己効力感に加えて、コーチングを受けたグループは、キャリアの方向性に対する満足度、仕事に対する満足度、自分の強みと弱みの認識においても、対照グループより高い評価を示しました。
また、コーチングを行うコーチ自身にもポジティブな変化が生じることが示されました。コーチの役割を担うことで、コーチ自身の問題解決能力や対人スキル、そして自己効力感も向上するという、双方向の利益が確認されたのです。
この研究は、コーチングの効果を心理的メカニズムの観点から説明しただけでなく、その組織的価値についても考察を提供しました。自己効力感の向上は、従業員がより積極的に仕事に取り組み、困難を乗り越える心理的基盤となります。これは組織全体の生産性向上に貢献する「無形の利益」と言えるでしょう。
コーチングは心理的資本を高め、仕事の満足度を向上させる
自己効力感に続いて、コーチングが個人の心理的リソースに与える影響を包括的に検証した研究があります。この研究では、「心理的資本」という概念を通じて、コーチングの効果がどのようなメカニズムで生まれるのかを解明しようとしました[4]。
心理的資本とは、人の成長とパフォーマンスを促進するポジティブな心理状態のことで、希望、自己効力感、レジリエンス、楽観主義の4つの要素から構成されます。希望とは目標達成への意志と経路を見出す力、自己効力感は課題を成功裏に遂行できるという自信、レジリエンスは逆境から素早く立ち直る力、楽観主義は物事のポジティブな側面に目を向け成功を期待する態度を指します。
あるマーケティング会社の56名の従業員を対象としたこの研究では、参加者をランダムに実験群と対照群に分け、実験群には4ヶ月間のコーチングプログラムを提供しました。対照群はウェイティングリストに登録され、実験群のプログラム終了後に同じコーチングを受ける設計となっていました。
コーチングプログラムは、心理学のバックグラウンドを持つ外部のプロフェッショナルコーチによって実施されました。月1回、60分のセッションが計4回行われ、目標設定のGROWモデルを基盤としつつ、心理的資本の4要素を高めるための問いかけや活動が組み込まれていました。
データは、プログラム開始前、終了後、さらに実験群については終了から4ヶ月後の計3回収集されました。測定項目には、心理的資本、職務満足度、組織コミットメント、職務パフォーマンスが含まれ、パフォーマンスについては自己評価だけでなく上司や同僚からの多面評価も活用されました。
分析結果は、コーチングの心理的メカニズムを実証するものでした。コーチングを受けた実験群は、対照群と比較してプログラム終了後に心理的資本、職務満足度、組織コミットメントが統計的に有意に向上しました。職務パフォーマンスについては、協調性の側面でのみ有意な向上が見られました。
心理的資本の媒介効果も見えてきました。「コーチング→心理的資本の向上→職務満足度・組織コミットメントの向上」という関係の連鎖が確認されたのです。コーチングは直接的に満足度や組織への愛着を高めるのではなく、まず個人の心理的リソースを強化し、その結果として様々なポジティブな成果が生まれるということが実証されました。
追跡調査では、効果の持続性についても検証されました。プログラム終了から4ヶ月が経過した時点でも、心理的資本と職務満足度は開始前と比べて高いレベルを維持していました。一方で、組織コミットメントについては時間の経過とともに効果が減衰する傾向が見られました。
この研究が明らかにしたのは、コーチングが個人に変化をもたらすプロセスの詳細なメカニズムです。コーチングは単にスキルを教えるのではなく、目標設定のプロセスや内省を促す問いかけ、フィードバックを通じて、従業員が本来持つポジティブな心理的リソースを活性化させます。この「心理的資本」というエンジンが強化されることで、従業員は仕事や組織に対してより前向きな態度を形成し、環境に対して主体的に働きかけるようになります。
コーチングは役割の明確化を起点に、満足度や成果を高める
これまで見てきたコーチングの効果は、主に外部のプロフェッショナルコーチによるものでしたが、実際の職場では直属の上司やマネージャーがコーチの役割を担うケースも少なくありません。韓国の民間企業で実施された研究は、このマネジリアルコーチングがどのような心理的プロセスを経て成果につながるのかを検討しています[5]。
この研究の理論的背景には、パスゴール理論と組織支援理論という2つの枠組みがありました。パスゴール理論では、リーダーの役割を部下が目標を達成するための道筋を明確にし、その過程を支援することと定義します。組織支援理論では、従業員が組織からどの程度大切にされ、貢献を評価されているかという認識が、組織へのコミットメントに影響するとされます。
これらの理論を統合して、研究者は次のような連鎖的な関係性を持つ概念モデルを構築しました。マネジリアルコーチングがまず部下の役割の明確さを高め、それが仕事への満足度向上につながり、満足度の向上が組織コミットメントを高め、最終的に職務パフォーマンスの向上に結びつくという、段階的なプロセスです。
研究には234名の正社員が参加し、直属のマネージャーのコーチング行動、自身の役割の明確さ、仕事への満足度、組織コミットメント、職務パフォーマンスについてアンケート調査が実施されました。
分析結果は、提案された概念モデルを支持するものでした。マネジリアルコーチングは、部下の「役割の明確さ」と「仕事への満足度」に対して統計的に有意な正の直接的な効果を与えていました。これは、マネージャーから適切なコーチングを受けることで、部下は自分の仕事の目的や期待される役割をより明確に理解し、仕事そのものに対する満足感も高まることを意味します。
さらに、コーチングは他の成果に対して媒介変数を通じて間接的にポジティブな影響を与えていました。役割の明確さを通じて仕事への満足度と職務パフォーマンスが向上し、仕事への満足度を通じて組織コミットメントが向上し、組織コミットメントを通じて職務パフォーマンスが向上するという、複層的なポジティブサイクルが確認されました。
この研究で特筆すべきは、「役割の明確さ」が中心的な役割を担っていることが示されたことです。マネージャーがコーチとして機能することで、部下は「自分は何をすべきか、何を期待されているか」を理解します。この認知的な変化が、満足度やパフォーマンスといった様々なポジティブな結果を引き起こす引き金となるのです。
この研究が韓国という東アジアの文化圏で実施されたことにも意義があります。個人主義的な欧米文化で生まれたコーチングという手法が、集団主義的な価値観が強いとされる文化的背景においても効果を発揮することが実証されました。
脚注
[1] Bono, J. E., Purvanova, R. K., Towler, A. J., and Peterson, D. B. (2009). A survey of executive coaching practices. Personnel Psychology, 62(2), 361-404.
[2] Burt, D., and Talati, Z. (2017). The unsolved value of executive coaching: A meta-analysis of outcomes using randomised control trial studies. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 15(2), 17-25.
[3] Leonard-Cross, E. (2010). Developmental coaching: Business benefit – fact or fad? An evaluative study to explore the impact of coaching in the workplace. International Coaching Psychology Review, 5(1), 36-47.
[4] Fontes, A., and Dello Russo, S. (2021). An experimental field study on the effects of coaching: The mediating role of psychological capital. Applied Psychology: An International Review, 70(2), 459-488.
[5] Kim, S. (2014). Assessing the influence of managerial coaching on employee outcomes. Human Resource Development Quarterly, 25(1), 59-85.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。