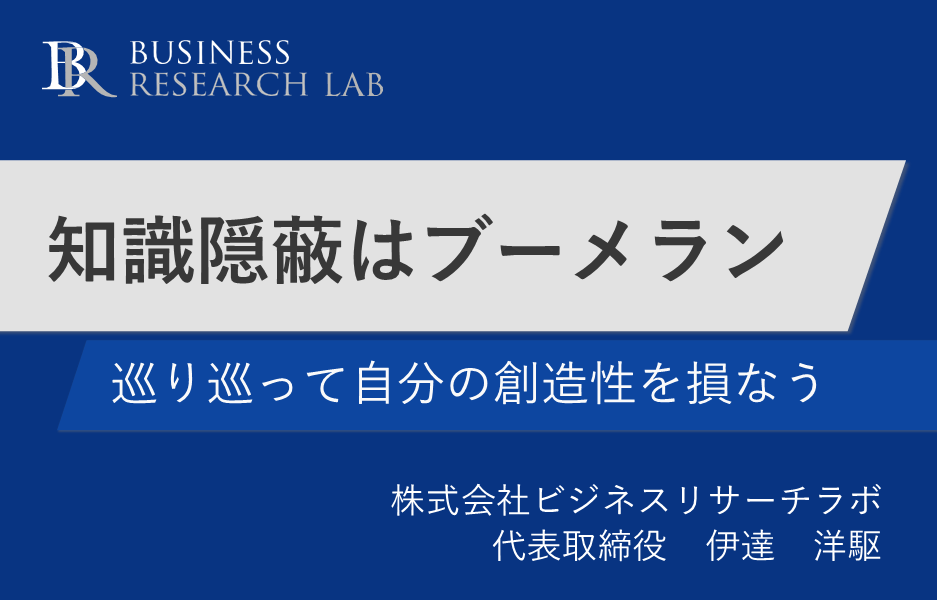2025年10月9日
知識隠蔽はブーメラン:巡り巡って自分の創造性を損なう
職場において、同僚から質問されたときに情報を教えないことがあるかもしれません。忙しいからと言って断ったり、知らないふりをしたり、もっともらしい理由をつけて情報を出さないといった行動です。こうした「知識隠蔽」は、組織にとって悪いものだと考えられています。確かに、チーム全体の生産性や創造性を下げる場合が多いでしょう。
しかし、知識隠蔽の実態は少し複雑です。隠した本人にはどのような心理的な変化が起こるのでしょうか。そして、その結果として生まれる行動は、組織にとって常に悪いことばかりなのでしょうか。近年の研究では、知識隠蔽が引き起こす感情や行動の連鎖に、意外な側面があることが分かってきました。
本コラムでは、知識隠蔽が個人や組織に及ぼす作用について見ていきます。知識隠蔽は決して単純な「悪」ではなく、時には組織にとってプラスの結果をもたらすこともある一方で、隠した本人には予想外の負担をかけることもあります。これらの現象を理解することで、職場でのより良いコミュニケーションのあり方を考えていきましょう。
知識隠蔽が生む罪悪感は貢献に、恥は孤立につながる
職場で同僚から質問されたとき、知っている情報をあえて教えないという行動は、隠した本人にどのような感情をもたらすのでしょうか。この問題について研究者らは興味深い発見をしています[1]。
知識隠蔽には大きく分けて3つのパターンがあります。1つ目は「回避的隠蔽」で、間違った情報や不完全な情報をわざと伝える行動です。2つ目は「無知を装う」もので、本当は知っているのに知らないふりをすることです。3つ目は「合理化した隠蔽」で、情報を教えない理由をもっともらしく説明する行動です。
研究者らは、これらの知識隠蔽行動が、隠した本人に「罪悪感」と「恥」という2つの異なる感情を引き起こすことを発見しました。罪悪感は「自分の行動が悪かった」と感じる気持ちで、恥は「自分という人間がダメだ」と感じる気持ちです。
この研究では、156人のアメリカ人労働者を対象にした実験を行いました。参加者には知識隠蔽をする場面と、しない場面の2つの状況を想像してもらい、そのときの感情を答えてもらいました。結果、知識隠蔽をした場面を想像した人は、しなかった場面を想像した人よりも、罪悪感と恥の両方を強く感じることが分かりました。
続いて、ドイツの職場で働く275人を対象に、実際の職場での行動と感情を2回に分けて調査しました。この調査では、3つの知識隠蔽パターンの中でも、「無知を装う」行動だけが罪悪感と恥の両方を強く引き起こすことが判明しました。一方、「回避的隠蔽」については予想に反して感情との関連が見られず、「合理化した隠蔽」については予想通り感情への大きな作用がありませんでした。
ここで注目すべきは、罪悪感と恥が反対の行動を導くことです。罪悪感を覚えた人は、その埋め合わせをしようとして、組織のために自発的に貢献する行動を増やしました。掃除や後輩の指導など、本来の仕事以外でも会社のためになることを積極的に行うようになったのです。
一方、恥を感じた人は逆の反応を見せました。自分自身への否定的な感情から、職場での自発的な貢献行動を減らしてしまいました。恥は人を内向きにさせ、他者との関わりを避けさせることが確認されました。
同じ知識隠蔽という行動でも、引き起こされる感情によって、その後の組織への貢献度が変わってしまうのです。罪悪感は建設的な方向に人を向かわせる一方で、恥は破壊的な方向に導いてしまいます。
知識隠蔽は、巡り巡って自分の創造性を損なう
職場で情報を隠すという行動は、隠された相手だけでなく、隠した本人にも予想外の代償をもたらします。ある調査により、知識隠蔽は最終的に隠した本人の創造性を低下させることが明らかになりました[2]。
この研究の出発点は、知識隠蔽が「負の循環」を生み出すという仮説でした。同僚から情報を隠すと、その同僚は隠した人を信頼しなくなります。そして、信頼を失った人は職場で孤立し、新しいアイデアを生み出すために必要な情報交換から遠ざかってしまうというものです。
研究チームは、この仮説を検証するために2つの異なるアプローチを取りました。スロベニアの2つの企業で働く240人の従業員と34人の上司を対象にした調査を実施しました。従業員には自分の知識隠蔽行動について、上司には部下の創造性について評価してもらいました。
調査の結果、知識隠蔽を多く行う従業員ほど、上司から創造性が低いと評価されることが分かりました。知識隠蔽が創造性の低下と結びついていることが確認されました。
詳しいメカニズムを解明するため、研究チームは132人の大学生を対象とした実験も行いました。参加者を複数のグループに分け、一部のグループには知識隠蔽を行う状況を、他のグループには知識共有を行う状況を体験してもらいました。
実験の結果、知識隠蔽を行ったグループの参加者は、そうでないグループと比べて創造性テストの成績が低くなりました。知識隠蔽を行った参加者は、他のメンバーからの信頼を失い、自分自身の創造的なパフォーマンスが下がることも確認されました。「知識隠蔽→信頼失墜→創造性低下」という負の循環が実際に存在することが実証されました。
この研究で注目されるのは、職場の雰囲気が知識隠蔽の悪い結果を左右することです。熟達風土、すなわち学習や成長、チームワークを大切にする職場では、知識隠蔽による創造性への悪い作用が和らげられました。一方、遂行風土、すなわち他者との競争や成果の比較を強調する職場では、知識隠蔽の悪い結果がより深刻になりました。
熟達風土の職場では、失敗や知識不足を学習の機会として捉えるため、知識隠蔽による信頼の損失が比較的早く回復しやすいと考えられます。一方、遂行風土の職場では、能力の欠如や失敗が厳しく評価されるため、一度失った信頼を取り戻すことが困難になります。
この研究成果は、知識隠蔽の隠れたコストを明らかにしています。情報を隠すことで短期的には自分の優位性を保てるかもしれませんが、長期的には自分自身の創造性という大切な能力を損なってしまうのです。
リーダーに倣う知識隠蔽は、自身の仕事満足度を下げる
職場での知識隠蔽は、上司の行動によって左右されます。研究者らが行った調査により、上司が知識隠蔽を容認したり推奨したりすると、部下もそれに倣って情報を隠すようになり、自分自身の仕事への満足度や帰属意識が低下することが判明しました[3]。
この研究では、「リーダー示唆型知識隠蔽」という新しい概念が提唱されました。これは、上司が直接的または間接的に知識隠蔽を許容する態度を示すことで、部下にその行動を促してしまう現象を指します。上司が「その情報は教えなくていい」と言ったり、自分自身が情報を出し惜しみしたりする行動を取ると、部下はそれが組織で受け入れられる行動だと学習してしまいます。
研究チームは、この現象を検証するために2つの調査を実施しました。1つ目は1,162人の従業員を対象とした縦断調査で、2回にわたって同じ人たちの行動と態度の変化を追跡しました。2つ目は1,169人の従業員を対象とした横断調査で、より詳細な心理的要因を測定しました。
調査の結果、上司が知識隠蔽を示唆する行動を取ると、部下の知識隠蔽行動が増加することが確認されました。これは、先ほど説明した3つの知識隠蔽パターン、すなわち「回避的隠蔽」「無知を装う」「合理化した隠蔽」のすべてにおいて観察されました。人は周囲の行動、とりわけ権威のある立場の人の行動を模倣する傾向があることが、職場の知識隠蔽においても確認されました。
部下は知識隠蔽を行うようになった結果、本人の職務満足度が低下しました。知識隠蔽を多く行う従業員は、仕事に対する満足感が減り、会社を辞めたいと考える気持ちが強くなりました。自分の仕事に対する自信や主体性も失ってしまうことが明らかになりました。
ただし、知識隠蔽の3つのパターンが職務態度に与える作用は均一ではありませんでした。「回避的隠蔽」と「無知を装う」については、予想通り仕事満足度の低下や離職意向の増加が見られました。しかし、「合理化した隠蔽」については離職意向を減らし、場合によっては仕事満足度を高める作用があることが分かりました。
この隠蔽パターンでは、情報を提供しない理由を論理的に説明するため、隠蔽を行う本人も相手も、その行動を正当なものとして受け入れやすくなります。「今は忙しいので後で」「この情報は機密性が高いため」といった説明は、社会的に受け入れられる理由として認識されるため、罪悪感や恥といった負の感情を引き起こしにくいのです。
一方、「回避的隠蔽」や「無知を装う」は、本人も相手も騙している意識が強いため、道徳的な葛藤を生み出しやすくなります。この葛藤が継続すると、仕事への態度全般に悪い作用を及ぼすと考えられます。
文化的知性が高ければ、知識隠蔽されても創造性は落ちにくい
多様な文化的背景を持つ人々が働く職場では、知識隠蔽が起きても、それに対処できる個人の能力によって結果が変わることが分かってきました。ある調査により、「文化的知性」が高い人は、知識隠蔽による創造性への悪い作用を軽減できることが明らかになりました[4]。
文化的知性とは、異なる文化的背景を持つ人々と効果的に協力できる個人の能力です。これは4つの要素から構成されています。第1は「メタ認知的文化的知性」で、異文化での自分の思考プロセスを客観視し、調整する能力です。第2は「認知的文化的知性」で、他の文化に関する具体的な知識や理解です。第3は「動機付け的文化的知性」で、異文化の人々と積極的に関わろうとする意欲です。第4は「行動的文化的知性」で、状況に応じて自分の言動を調整する実践的な能力です。
研究チームは、文化的知性が知識隠蔽の悪い結果を和らげるかどうかを、2つの研究で検証しました。最初の研究では、文化的に多様な中小企業20社の621名の従業員を対象に調査を行いました。これらの企業では、様々な国籍や文化的背景を持つ人々が協力して働いていました。
調査の結果、知識隠蔽は創造性を下げるという基本的な関係が確認されました。しかし、文化的知性が高い従業員については、この関係が弱くなることが分かりました。文化的知性の高い人は、同僚から情報を隠されても、それによる創造性の低下が比較的小さかったのです。
この現象を詳しく理解するため、研究チームは国際的な学生104人を対象とした実験も行いました。参加者を24のチームに分け、知識隠蔽の程度を人為的に操作した環境でビジネス課題に取り組んでもらいました。そして、個人レベルとチームレベルの両方で創造性を評価しました。
実験の結果、知識隠蔽は個人とチームの創造性を低下させることが再確認されました。しかし、文化的知性が高い参加者については、知識隠蔽による創造性の低下が有意に軽減されることが分かりました。
この現象が起きるメカニズムについて、研究者らは次のように説明しています。知識隠蔽が創造性を下げる理由の1つは、人々が文化的な違いによって相手を「内集団」か「外集団」かに分類し、外集団の人からの情報提供を期待しなくなることです。しかし、文化的知性が高い人は、このような分類に過度に依存せず、多様な背景を持つ人々との協力関係を維持できます。
ただし、この研究では文化的知性が万能の解決策ではないことも示されています。文化的知性は知識隠蔽の悪い結果を軽減できますが、完全に解消することはできません。根本的な解決のためには、組織全体で知識共有を促進する仕組みづくりが依然として必要です。
知識隠蔽があっても、良い風土と仕事の自由があれば革新は生まれる
職場で知識隠蔽が起きてしまった場合でも、それを補って余りある環境を整えることで、従業員の革新的な行動を促進できることが分かりました。具体的には、チームの学習風土と職務設計の工夫によって、知識隠蔽の悪い作用を克服できることが明らかになっています[5]。
この研究では、従業員の「革新的な仕事行動」に焦点が当てられました。これは、新しいアイデアを生み出すだけでなく、そのアイデアを積極的に推進し、実際の職場で実現させるまでの一連の行動を指します。
研究の中心となるのは、「熟達風土」という概念です。これは、チーム内で個人の学習、努力、自己改善が評価され、支援される環境を指します。このような環境では、失敗を学習の機会として捉え、メンバー同士が互いの成長を支援し合います。競争よりも協力が重視され、短期的な成果よりも長期的な能力向上が大切にされます。
研究チームは、スロベニアの中規模企業2社で働く240名の従業員とその上司34名を対象に調査を行いました。革新的な仕事行動については、より客観的な評価を得るために上司による評価を用いました。一方、知識隠蔽、熟達風土、職務特性については従業員自身に評価してもらいました。
調査の結果、予想通り知識隠蔽は革新的な仕事行動を阻害することが確認されました。情報を隠す行動が多い従業員ほど、上司から革新的でないと評価される傾向がありました。これは、知識隠蔽が信頼関係を損ない、新しいアイデアの発展に必要な協力関係を妨げるためと考えられます。
しかし、チームの熟達風土が強い場合、知識隠蔽の悪い作用が軽減されることが分かりました。学習と成長を重視する環境では、知識隠蔽による信頼の損失が比較的早く回復し、革新的な行動への悪い作用が最小限に抑えられます。
さらに、職務設計の要素がこの関係を複雑に調整していました。研究では、「タスク相互依存性」と「意思決定自律性」という2つの職務特性が検討されました。タスク相互依存性は、自分の仕事が他の人の仕事とどの程度密接に関連しているかを示し、意思決定自律性は、仕事の進め方について自分でどの程度決定できるかを表します。
分析の結果、知識隠蔽が多い状況でも、熟達風土が強く、かつタスク相互依存性が低い場合、革新的な仕事行動が維持されることが分かりました。学習重視の環境で、しかも他人への依存度が低い独立性の高い仕事では、知識隠蔽があっても自分なりの方法で革新的なアイデアを実現できるのでしょう。
同様に、知識隠蔽が多い状況でも、熟達風土が強く、意思決定自律性が高い場合も、革新的な仕事行動が促進されることが明らかになりました。自分で仕事の進め方を決められる環境では、知識隠蔽による制約を創意工夫で乗り越え、新しいアプローチを試すことができます。
知識隠蔽を完全に防ぐことは現実的に困難ですが、適切な環境整備により、その悪い作用を相殺することが可能であることが示されました。熟達風土の醸成、タスク設計の工夫、意思決定権限の委譲などを組み合わせることで、知識隠蔽が存在する状況でも革新的な成果を生み出せるのです。
脚注
[1] Burmeister, A., Fasbender, U., and Gerpott, F. H. (2019). Consequences of knowledge hiding: The differential compensatory effects of guilt and shame. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 92(2), 281-304.
[2] Cerne, M., Nerstad, C. G. L., Dysvik, A., & Skerlavaj, M. (2014). What goes around comes around: Knowledge hiding, perceived motivational climate, and creativity. Academy of Management Journal, 57(1), 172-192.
[3] Offergelt, F., Sporrle, M., Moser, K., and Shaw, J. D. (2019). Leader-signaled knowledge hiding: Effects on employees’ job attitudes and empowerment. Journal of Organizational Behavior, 40(7), 819-833.
[4] Bogilovic, S., Cerne, M., and Skerlavaj, M. (2017). Hiding behind a mask? Cultural intelligence, knowledge hiding, and individual and team creativity. European Journal of Work and Organizational Psychology, 26(5), 710-723.
[5] Cerne, M., Hernaus, T., Dysvik, A., and Skerlavaj, M. (2017). The role of multilevel synergistic interplay among team mastery climate, knowledge hiding, and job characteristics in stimulating innovative work behavior. Human Resource Management Journal, 27(2), 281-299.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。