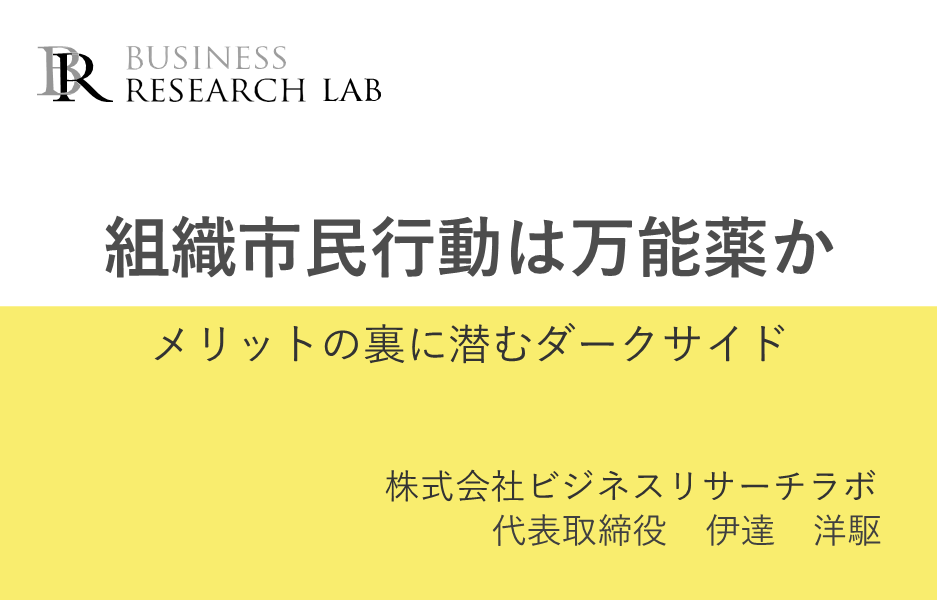2025年10月9日
組織市民行動は万能薬か:メリットの裏に潜むダークサイド
職場で働く人の多くが、こんな同僚に出会ったことがあるでしょう。困っている新人に進んで教える人、休憩時間に共有スペースを掃除する人、会社のイベントを自主的に手伝う人。こうした行動は、正式な職務に含まれていないにもかかわらず、職場をより良い場所にしてくれます。
この種の自発的な行動は「組織市民行動」と呼ばれ、長らく職場における良い振る舞いとして称賛されてきました。確かに、こうした行動は組織の雰囲気を良くし、業務の効率を高めてくれます。しかし近年の研究では、この一見すばらしい行動にも思わぬ落とし穴があることが分かってきました。
善意から始まった行動が、時として当事者や周りの人々に負担をもたらしたり、組織全体の生産性を下げたりすることもあるのです。本コラムでは、組織市民行動がどのような要因によって生まれ、どのような結果をもたらすのかを探っていきます。
組織市民行動は性格より仕事満足度が強く影響
組織市民行動について考える際、多くの人は「親切な性格の人ほど、こうした行動をとりやすいのではないか」と想像するかもしれません。確かに、生まれ持った性格が人の行動を左右することは否定できません。しかし、この直感的な理解は、実際の研究結果とは異なることが明らかになっています。
大規模な調査研究においては、組織市民行動を予測する要因として、性格特性と仕事への態度のどちらがより強い関連性を持つかが検証されました[1]。この研究は、過去55本の論文データを統合して分析するメタ分析という手法を用いており、合計で数万人規模の働く人々のデータを扱っています。
研究者たちは、性格要因として誠実性や協調性といった特性を測定し、態度要因として仕事満足感や組織への愛着度を測定しました。組織市民行動については、同僚を助ける行動や会社のルールを進んで守る行動など、さまざまな自発的行動を上司が評価する方法と、本人が自己評価する方法の両方が用いられました。
分析の結果、仕事満足感が組織市民行動の最も強力な予測要因であることが判明しました。組織への愛着度も同様に強い関連性を示しましたが、性格要因の効果は予想外に限定的でした。誠実性という性格特性は、本人が自分の行動を評価する場合には一定の関連性を示しましたが、上司が評価する場合にはその関連性は弱くなりました。協調性についても、他者を助ける行動に限定して効果が見られるにとどまりました。
この結果が意味するところは大きいでしょう。採用面接などで「協調性のある人材」や「責任感の強い人材」を重視する企業がありますが、実際には性格よりも、入社後の職場環境や仕事への満足度の方が、自発的な協力行動に作用を及ぼすことが分かったのです。
研究者たちは、この結果について次のように解釈しています。組織市民行動は本質的に「意志」に基づく行動であり、「能力」に基づく行動ではありません。そのため、その人がどれだけ職場に満足し、組織に愛着を感じているかという感情的な要素が、性格的な素質よりも行動に直結しやすいのでしょう。
なお、自己評価と他者評価では異なるパターンが見られました。自分で自分の行動を評価する場合には性格要因の効果がやや強く現れましたが、上司が部下の行動を評価する場合には仕事への態度の方がより強い関連性を示しました。これは、実際の職場で目に見える形で現れる協力行動が、その人の内面的な満足度に大きく左右されることを示唆しています。
この発見は、職場での人材育成や組織マネジメントを考える上で重要な視点を提供してくれます。「良い人」を採用するだけでは不十分で、採用後にその人が職場で満足感を得られるような環境づくりが、自発的な協力行動を促進するということです。
職務満足度は、生産性より組織市民行動に強く影響
仕事への満足度が高い従業員は、より良いパフォーマンスを発揮するというのは、一般的に信じられている考え方です。しかし長年の研究において、実際には仕事満足度と従来の意味での生産性(作業量や品質)との関係は、期待されるほど強くないことが繰り返し確認されてきました。この現象は研究者たちを長らく困惑させてきましたが、ある研究が、この謎を解く手がかりを提供しました。
この研究では、アメリカ中西部の大学で働く77名の管理部門職員を対象に、約5週間から7週間の期間をおいて2回の調査が実施されました[2]。対象者には、プログラマー、学生カウンセラー、資金調達担当者、会計士など、多様な職種の人々が含まれていました。
調査では、従業員自身が質問紙に回答し、その一方で上司が部下の組織市民行動を評価しました。職務満足度は、仕事そのもの、給与、昇進機会、同僚、監督者という5つの側面から測定され、組織市民行動は、規則の遵守、他者への支援、協力的態度、時間厳守、職場環境の整備など、幅広い自発的行動が対象となりました。
研究の結果は、従来の常識を覆すものでした。職務満足度全体と組織市民行動との間には、強い正の相関が確認されたのです。従来の職務満足度と生産性の関係よりも強い関連性でした。特に、監督者への満足度と昇進機会への満足度が、組織市民行動と強い関連を示しました。
研究者たちは、この結果について考察を行っています。従来の生産性指標(作業量や品質など)は、多くの場合、従業員の能力や技術、さらには組織のシステムや資源によって制約されています。しかし組織市民行動は、まさに従業員の「やる気」や「意欲」に依存する行動です。そのため、仕事への満足度という感情的な要素が、これらの自発的行動により強く反映されることになります。
研究では、社会交換理論と正の感情状態理論という二つの理論的枠組みから、この現象を説明しています。社会交換理論によれば、職務満足度が高い従業員は、組織から恩恵を受けていると感じ、その「お返し」として組織市民行動を増やします。一方、正の感情状態理論では、満足感が生み出す前向きな感情状態が、他者への親切な行動や協力的な行動を促進すると説明されます。
この研究で重要な発見は、職務満足度のどの側面が組織市民行動に最も強く関連しているかという点です。監督者への満足度が強い関連を示したことは、上司との良好な関係が、部下の自発的な協力行動を引き出す上で重要であることを物語っています。昇進機会への満足度が次に強い関連を示したことも、将来への希望や成長の見込みが、現在の積極的な行動を動機付けることを示唆しています。
組織市民行動は個人・組織の双方に好影響
組織市民行動が職場にどのような成果をもたらすのかという問題は、経営者や人事担当者にとって長年の関心事でした。直感的には良い結果をもたらすと思われてきましたが、その効果の大きさや具体的な現れ方については、科学的な検証が求められていました。あるメタ分析は、この問題に対して包括的な答えを提供し、組織市民行動の価値を明らかにしました[3]。
この研究は、1983年から2007年までの24年間に発表された研究論文から、個人レベルでは168のサンプル(合計51,235名)、組織レベルでは38のサンプル(合計3,611の組織単位)という結果を統合的に分析しました。
個人レベルでの効果を見てみましょう。組織市民行動が個人の職場での評価に与える効果は、予想を上回る強さでした。組織市民行動をよく行う従業員は、上司からのパフォーマンス評価において高い評価を受けていました。これは、職務上の成果と同程度か、それ以上に組織市民行動が評価されていることを意味します。
報酬面での効果も顕著でした。組織市民行動は報酬配分の意思決定に正の相関を示し、特に昇給や昇進の推薦においては強い関連性が確認されました。ただし、実際の給与増額などの具体的な報酬への反映は相対的に弱く、制度上の制約や予算の制限が関わっていることが推測されます。
組織市民行動が従業員の離職行動に与える効果も一つの発見でした。組織市民行動をよく行う従業員は、離職意図が低く、実際の離職率も低いことが確認されました。欠勤率についても負の相関が見られ、組織市民行動が従業員の組織への定着に寄与していることが裏付けられました。
組織レベルでの効果は印象的です。組織市民行動が組織全体のパフォーマンスに与える効果は、正の関連性を示しました。指標別に見ると、生産性の向上、業務効率の改善、コスト削減において特に強い効果が確認されました。一方、収益性への直接的な関連は比較的弱く、組織市民行動の効果が売上や利益として現れるまでには時間がかかることが示唆されています。
顧客満足度への効果も見逃せません。組織市民行動は顧客満足度の向上にも寄与しており、顧客接点を持つ従業員が自発的な配慮や努力を行うことで、サービス品質の向上につながることが確認されました。組織市民行動が社内だけでなく、外部のステークホルダーにも好影響を及ぼすことを示す証拠です。
組織レベルでの離職率についても、組織市民行動が活発な職場では離職率が有意に低いことが明らかになりました。協力的で支援的な職場環境が、従業員の働きやすさを高め、結果として人材の定着につながることを表しています。
研究では、いくつかの調整要因についても分析が行われましたが、例えば、組織市民行動の対象が個人なのか組織なのかによる差異は、ほとんど見られませんでした。同僚個人を助ける行動も、組織全体のためにとる行動も、評価や成果に与える効果に大きな違いはないということです。自発的な協力行動の価値が、その対象に関係なく一様に認識されていることを意味します。
組織市民行動のダークサイド(負の側面)を解明
これまで見てきたように、組織市民行動は職場に多くの恩恵をもたらす行動として研究されてきました。しかし、どんなに良いものでも行き過ぎれば弊害が生じるように、組織市民行動にも思わぬ負の側面があることが、近年の研究で明らかになってきました。ある研究が、こうした「ダークサイド」にメスを入れ、組織市民行動への見方を変える契機となりました[4]。
研究者たちは、組織市民行動の負の側面を三つの観点から検討しました。第一に、組織市民行動が従業員個人に与える負担やコスト、第二に、組織市民行動を行う際の動機の問題、第三に、組織市民行動が個人やチーム、組織全体のパフォーマンスに与える悪影響の可能性です。
個人への負担について見てみましょう。組織市民行動は本来、自発的で任意の行動とされていますが、実際の職場では従業員がこうした行動を「義務」として感じるケースが少なくありません。これは「強制的市民行動」と呼ばれる現象で、上司や同僚からの期待やプレッシャーによって、本来は自由な選択であるはずの行動が、実質的に強制されてしまう状況を指します。
このような状況に置かれた従業員は、通常の職務に加えて追加的な負担を強いられることになります。同僚の仕事を手伝ったり、会社のイベントに参加したり、職場の環境整備に時間を費やしたりすることで、本来の仕事の時間が圧迫されたり、プライベートな時間が犠牲になったりします。研究では、こうした「市民行動への圧力」を感じている従業員ほど、仕事と家庭生活の両立が困難になり、ストレスレベルが上昇し、最終的には離職意図が高まることが確認されています。
さらに問題なのは、組織市民行動が次第に「仕事の一部」として認識されるようになる現象です。これは「職務拡大」と呼ばれ、当初は自発的だった行動が、時間の経過とともに当然の責務として扱われるようになることを指します。この結果、従業員は昇進や報酬の面で適切な評価を受けられないまま、実質的な業務負荷だけが増加することになります。
第二の問題は、組織市民行動を行う動機の複雑さです。すべての組織市民行動が純粋な善意や組織への愛着から生まれるわけではなく、自己利益や印象操作を目的として行われることも珍しくありません。例えば、昇進を狙っている従業員が、評価期間の前後だけ組織市民行動を活発に行い、その後は元の行動パターンに戻るというケースが観察されています。
このような「戦略的」な組織市民行動は、短期的には上司や同僚に好印象を与えるかもしれませんが、長期的には組織にとって真の価値を生み出しません。むしろ、職場の信頼関係を損なったり、他の従業員のモチベーションを下げたりする可能性があります。
組織市民行動と反社会的行動の関連も指摘されています。一部の従業員は、過去に問題行動を起こした罪悪感から組織市民行動を増やしたり、逆に組織市民行動を行った後に「良いことをしたのだから多少の悪いことは許される」という心理状態(道徳的正当化)から、問題行動に走ったりすることがあります。これは、組織市民行動が必ずしも一貫した倫理的行動の現れではないことを示しています。
第三の問題は、組織市民行動が組織の効率性に与える悪影響です。従来の研究では、組織市民行動が組織の生産性を高めるとされてきましたが、すべての状況でそれが当てはまるわけではないことが分かってきました。
例えば、作業の相互依存性が低い職場では、同僚を手伝おうとする行動が逆に作業効率を低下させることがあります。各人が独立して作業を進める方が効率的な状況で、不必要な介入や支援が行われると、かえって全体の生産性が損なわれる可能性があります。
現状に異議を唱えたり改善提案を行ったりする「挑戦的市民行動」についても、適度なレベルでは組織の革新性を高めますが、過度になると組織の安定性や統制を損なう結果になることが示されています。建設的な批判や提案も、頻度や強度が極端になれば、職場の調和を乱したり、意思決定プロセスを混乱させたりする要因となります。
これらの発見は、組織市民行動に対する従来の見方を変えるものです。組織市民行動は常に望ましいものだという前提を見直し、その質や動機、文脈を慎重に考慮する必要があることが明らかになったのです。
脚注
[1] Organ, D. W., and Ryan, K. (1995). A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of organizational citizenship behavior. Personnel Psychology, 48(4), 775-802.
[2] Bateman, T. S., and Organ, D. W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee “citizenship”. Academy of Management Journal, 26(4), 587-595.
[3] Podsakoff, N. P., Whiting, S. W., Podsakoff, P. M., and Blume, B. D. (2009). Individual- and organizational-level consequences of organizational citizenship behaviors: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 94(1), 122-141.
[4] Bolino, M. C., Klotz, A. C., Turnley, W. H., and Harvey, J. (2013). Exploring the dark side of organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior, 34(4), 542-559.
執筆者
 伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役
神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知の両方を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析のサービスを提供している。著書に『60分でわかる!心理的安全性 超入門』(技術評論社)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)、『越境学習入門 組織を強くする「冒険人材」の育て方』(共著;日本能率協会マネジメントセンター)などがある。2022年に「日本の人事部 HRアワード2022」書籍部門 最優秀賞を受賞。東京大学大学院情報学環 特任研究員を兼務。